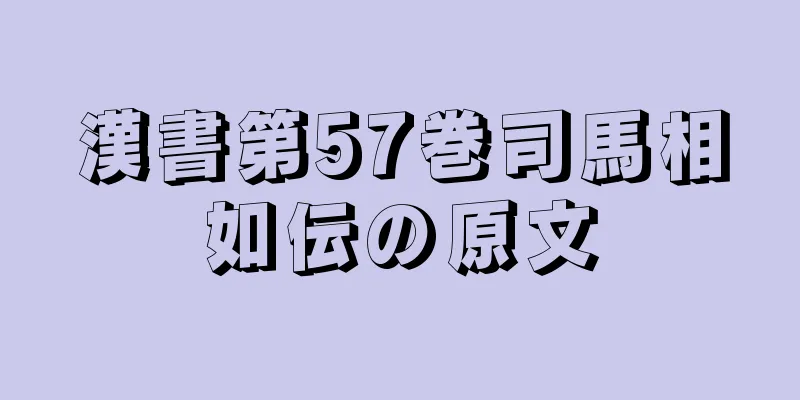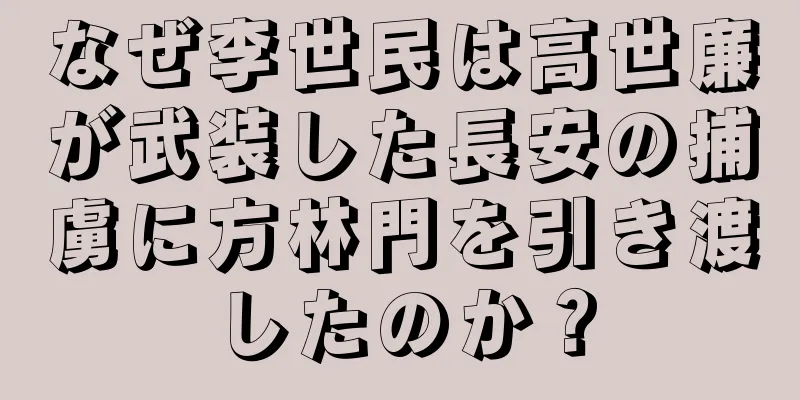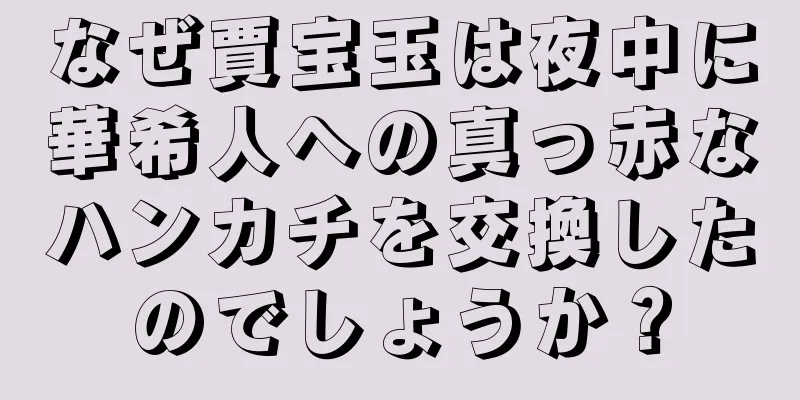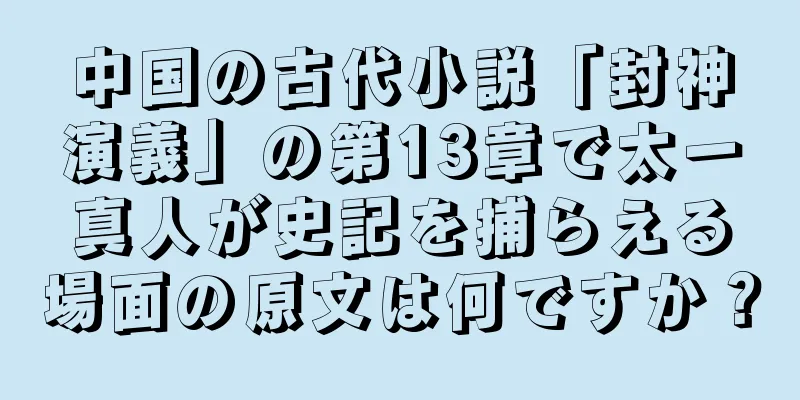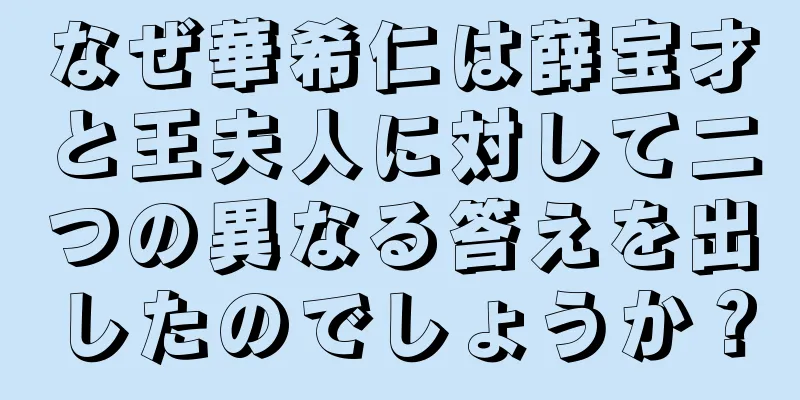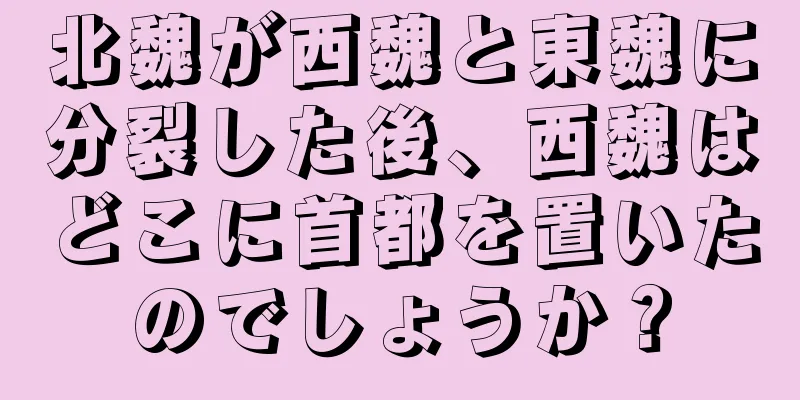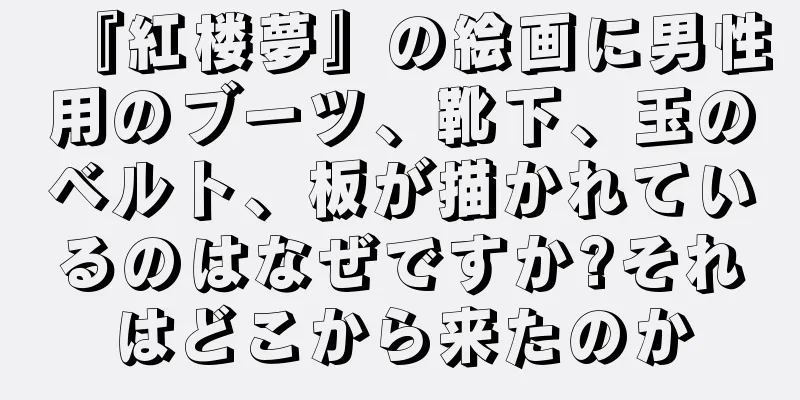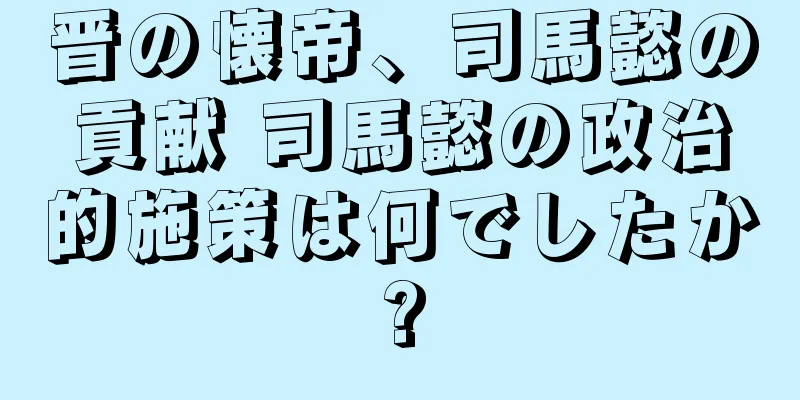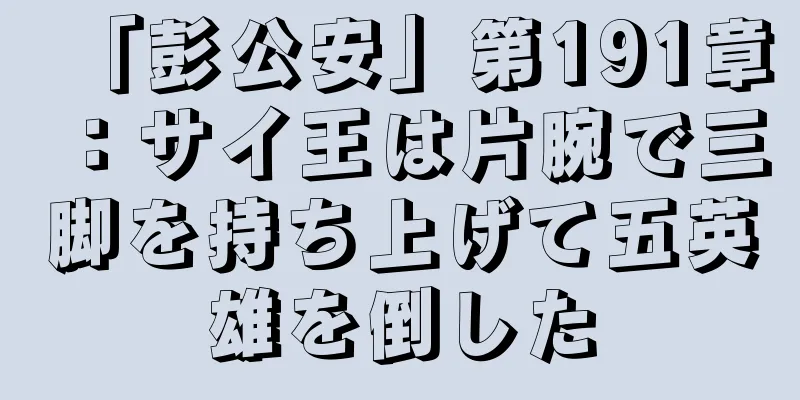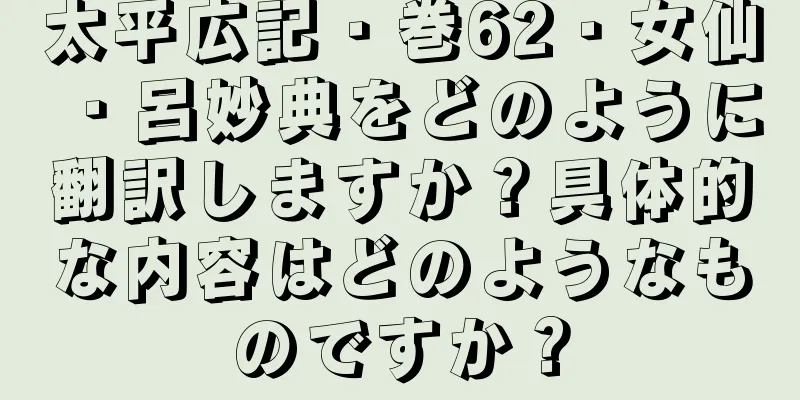「古代軍行進曲」を書いた詩人は誰ですか?どうやって鑑賞すればいいのでしょうか?
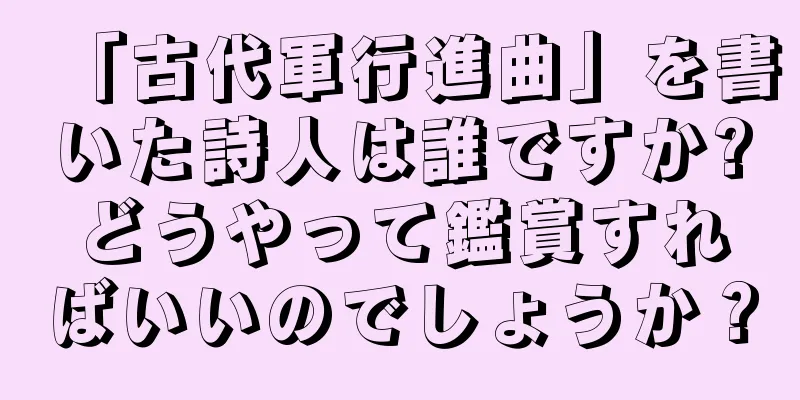
|
【オリジナル】 昼間は狼煙を見るために山に登り、夕暮れには蛟河のほとりで馬に水を飲ませました。 歩行者たちは暗い風と砂の中で格闘しており、姫の琵琶は悲しみに満ちていた。 何千マイルも続く荒野の雲の中には都市はなく、砂漠一面に雨と雪が降ります。 胡のガチョウは毎晩悲しげな鳴き声をあげながら飛び、胡の子どもたちは涙を流します。 玉門門はまだ封鎖されていると聞いて、命をかけて軽馬車を追いかけました。 年々、兵士たちの骨は荒野に埋められ、ランブータンだけが漢の家族のもとに入っていくのが見られる。 【翻訳】 彼は昼間は山に登って警報灯台を観察し、夕暮れには馬を連れて膠川の近くで水を飲ませた。 薄暗い砂嵐が、漢代の王女の琵琶の怨念のような音を爆発的に響かせた。 荒野は霧と雲に覆われ、何千マイルもの間、目に見える城壁はなく、果てしない砂漠は雨と雪に覆われていた。 夜ごとに胡雁が鳴き声をあげて空を飛び、胡兵士たちは涙を流した。 玉門関が退路を塞いでいると聞いて、兵士たちは将軍の後を追って必死に逃げるしかなかった。 戦死者の死体は毎年荒野に埋葬され、その見返りとして受け取れるのは西域のブドウを漢王朝に送ることだけだった。 注記 ビーコン:古代の警報装置の一種。 馬に水を飲む:馬に水を与える。横に:沿って。交河:古代の県の名前。新疆ウイグル自治区トルファンの西に位置する古い都市。 歩行者: 戦争に向かう兵士たち。釣豆:古代の軍隊で使われていた銅製の調理器具。容量は1豆。昼間は料理に、夜は太鼓を叩くのに使われます。 公主の琵琶:漢の武帝の治世中、江都の劉建王の娘である妲君が烏孫の昆墨王に嫁いだ。彼女が旅の途中で退屈するのではないかと心配した漢の武帝は、彼女を楽しませるために琵琶を弾いた。 「聞聞」の二文:漢の武帝はかつて李光利に大院を攻撃し、宜石城に行って良い馬を手に入れるよう命じた。戦いはうまくいかなかったため、光利は手紙を書いて軍隊を撤退させて帰国するよう要求した。武帝は激怒し、玉門関に使者を派遣して「もし兵士で侵入しようとする者がいたら、斬首せよ!」と言った。この二文は国境戦争がまだ続いているため、将軍に従って死ぬまで戦わなければならないという意味である。 Syzygium wilfordii: 現在は「ブドウ」と呼ばれています。 【著者について】 李斉(690-751)は漢民族で、東川(現在の四川省三台)(異論あり)の出身で、唐代の詩人であった。彼は若い頃、河南省登封市に住んでいました。開元13年に進士となり、新郷県の下級官を務めた。詩は主に辺境をテーマにしており、大胆で寛大で悲痛な作風で、特に七字歌が特徴的である。 】 この詩は天宝時代(唐の玄宗皇帝の治世、742-756年)の初期に書かれたものです。詩人は歴史について歌っていたが、その内容は唐の玄宗皇帝の侵略的で強硬な「国境を強める」政策に対する見解を表現していた。 |
<<: 『Yan Ge Xing』の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
>>: 「陸軍への入隊・第2部」の原文は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
推薦する
オズの魔法使い 第70章: 危険な言葉を聞き、世俗的な考えを断ち切り、昔の夢を探し、道中で永遠に絆を結ぶ
『オズの魔法使い』はファンタジー小説というよりは社会小説です。冷玉冰は仙人となる途中で弟子を受け入れ...
チェス盤の真ん中に「楚河」と「漢境」と書いてありますが、これは「楚漢戦争」とどう関係があるのでしょうか?
中国の将棋盤の真ん中には、「楚河」と「漢境」と書かれたスペースがよくあります。これは何を意味するので...
昭武帝慕容勝には何人の兄弟がいましたか?慕容勝の兄弟は誰でしたか?
慕容勝(373年 - 401年)、号は道雲、五夷十六国時代の後燕の皇帝、慕容宝(後燕の恵民帝)の長男...
『太平広記』第49巻の仙人に関する原文は何ですか?
パン・ズンシ、リー・ヘ、チャン・ジフー、ジェン・チェ、チェン・フイシュ、ウェン・ジンジャオパンさん宋...
魏将軍との心からの友情を表現するために、ヤン・ウェイは「丹陽魏将軍に告す」を書いた。
厳維は、雅号を鄭文といい、号は不明で、越州(現在の紹興)の出身である。唐代中期の詩人、作家。 生没年...
唐代の王亜が書いた『秋思』は詩人の深い思いを十分に表現している。
王雅(号は広津)は唐代の官吏であり詩人であった。彼の詩は優美でありながら優雅で、その主題は主に辺境で...
「遅い馬でも走り続ければ10倍速く走れる」とはどういう意味ですか?昔々、「ウサギとカメ」の話がありました!
今日、Interesting History の編集者が「遅い馬でも諦めなければ 10 日間で 10...
『紅楼夢』で黛玉が賈屋敷に入ったとき、なぜ彼女の叔父二人は現れなかったのですか?
黛玉は『紅楼夢』のヒロインであり、金陵十二美女のリーダーであり、賈夫人の孫娘です。この点についてよく...
孟子:李楼第1章第8節原文、翻訳および注釈
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸...
漢の元帝の寵愛を受けた妾、馮元の息子、劉嗣は誰ですか?馮元の子孫は誰ですか?
馮元(紀元前?年 - 紀元前6年)は、上当魯県(現在の山西省六安市)の出身で、左将軍馮風世と、漢の元...
なぜ司馬昭は劉禅を殺さなかったばかりか、彼を安楽県公にしたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「秋の夜長にひとり坐る」を鑑賞するには?著者は誰ですか?
秋の夜に一人で座る王維(唐代)空っぽのホールで二回目の見張りが始まろうとしているとき、一人で座ってい...
唐伯虎の孤高を主張する詩です。最後の一文がとても有名です!
明代の文化史上、唐伯虎は無視できない人物である。彼は才能で有名であったが、彼の人生は極めて不成功であ...
水滸伝で高丘を憎んだ涼山の英雄は誰ですか?
水滸伝の高丘は憎むべき悪役です。次は、Interesting Historyの編集者が説明します。四...
福建料理の代表的な料理の一つである「佛跳壁」を発明したのは誰ですか?なぜ「仏陀跳壁」というタイトルなのですか?
おもしろ歴史編集部が『仏陀跳壁』の由来をまとめて、みなさんに詳しく解説しています。ぜひご覧ください。...