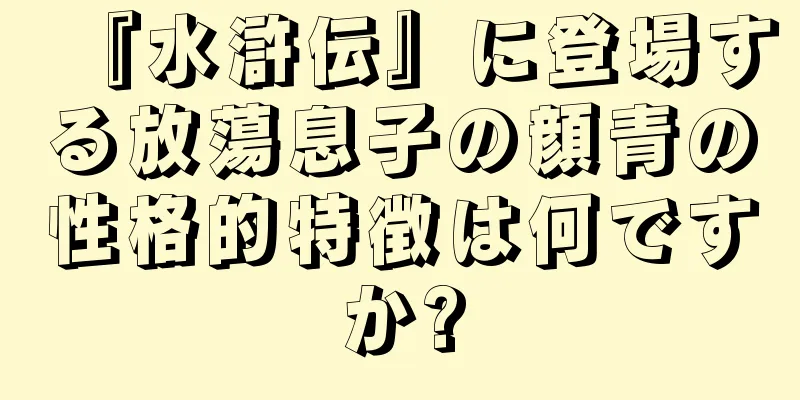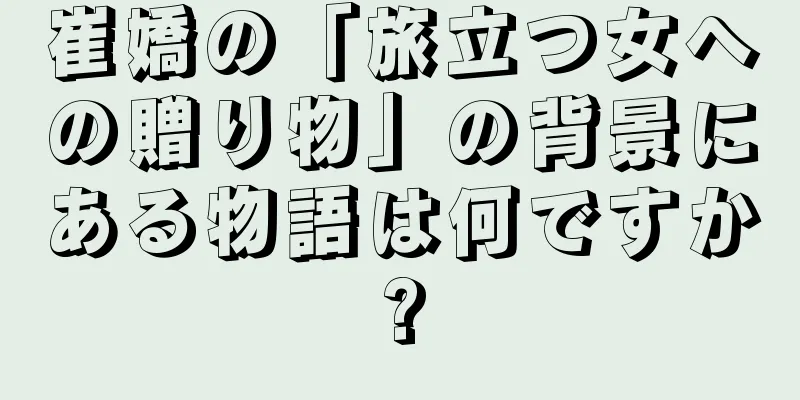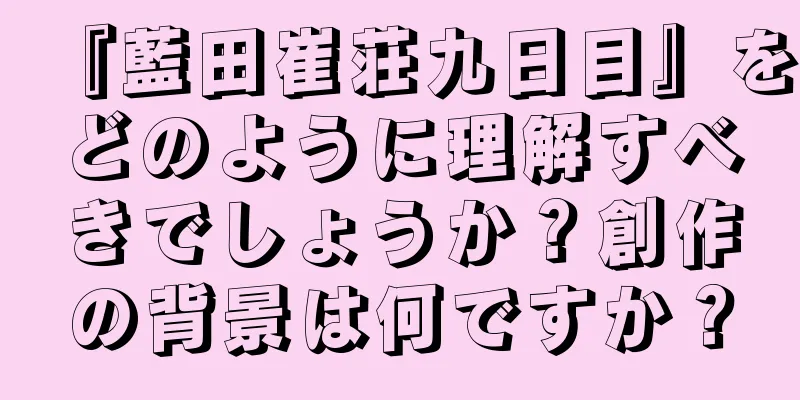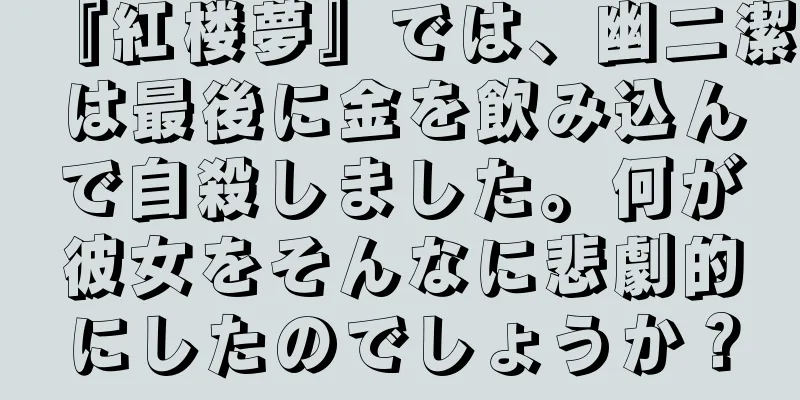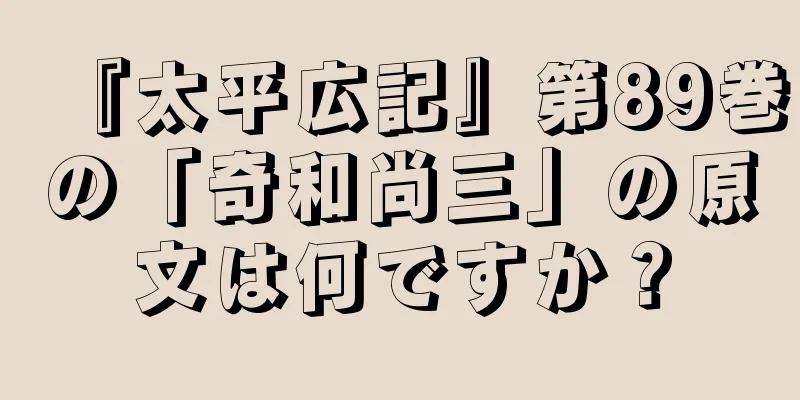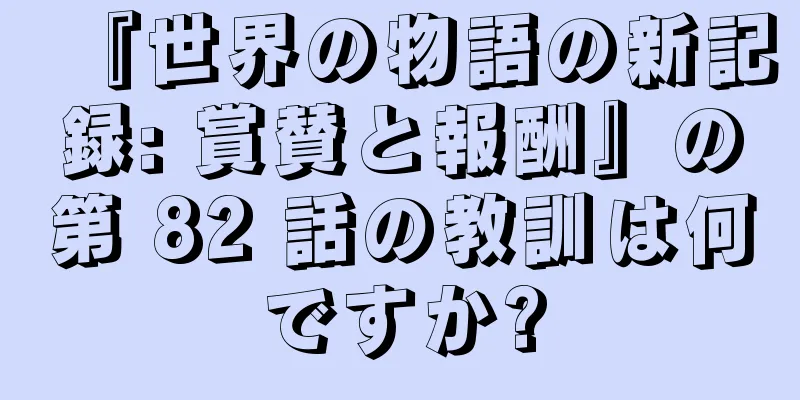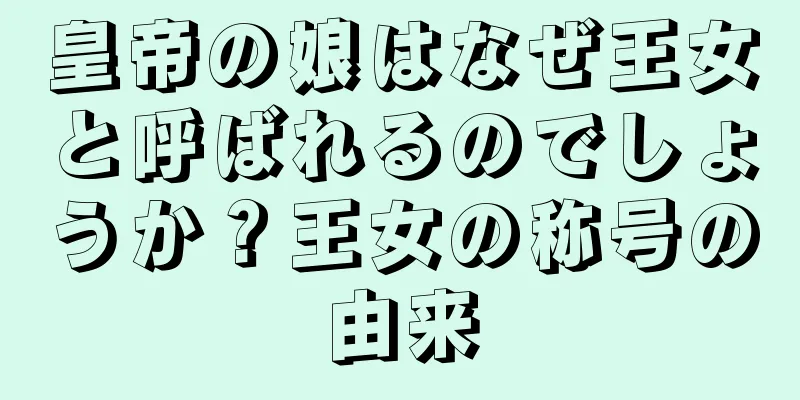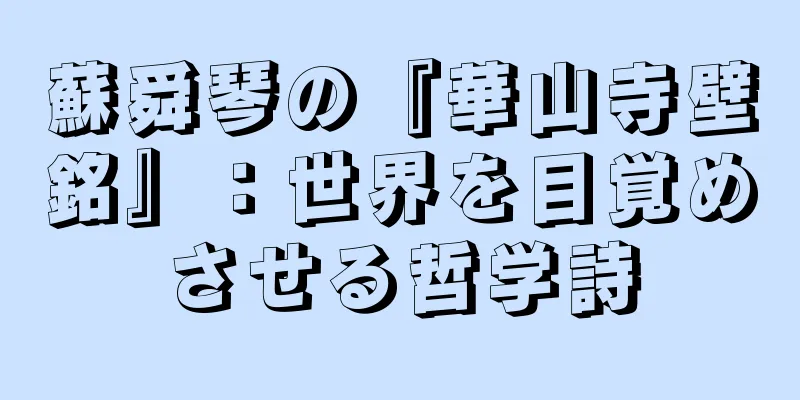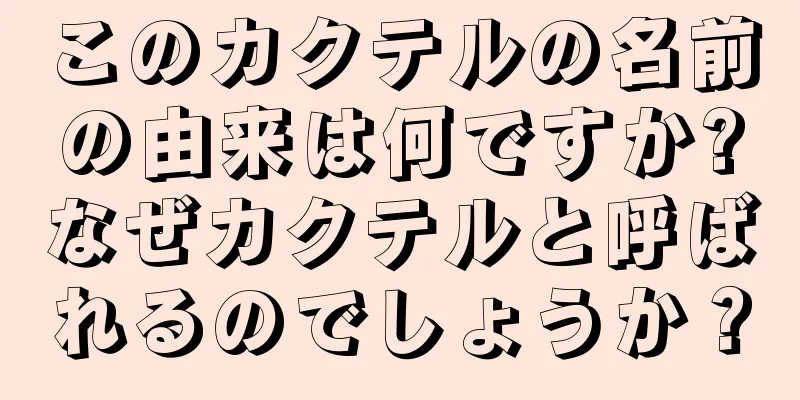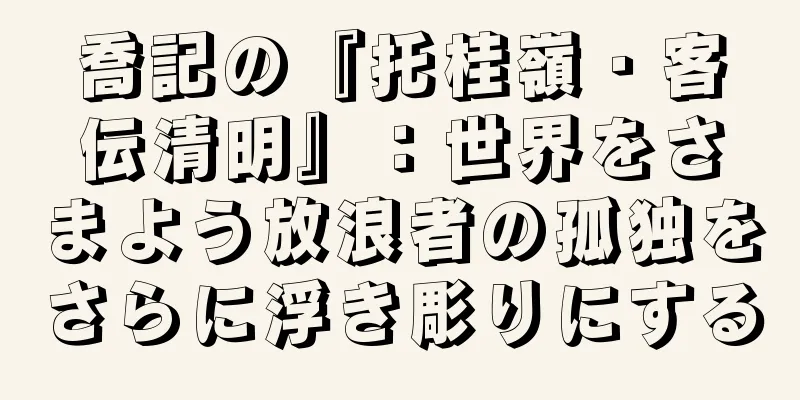李清昭の『生生漫・荀荀密』:六朝の叙情短編小説の真髄
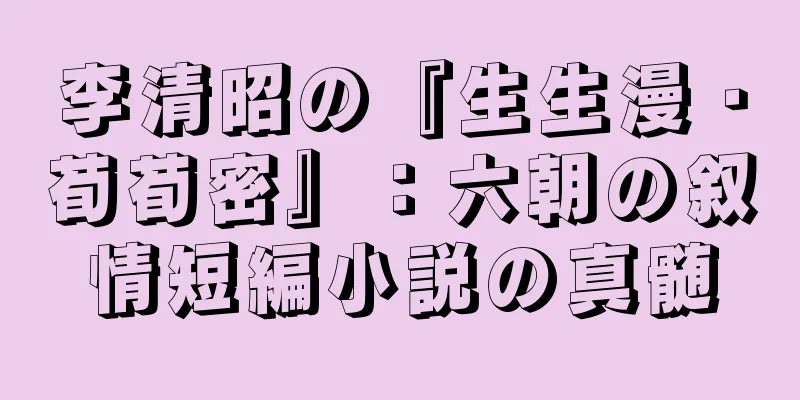
|
李清昭(1084年3月13日 - 1155年)は、易安居士とも呼ばれ、宋代の斉州章丘(現在の山東省章丘の北西)の出身で、済南に住んでいた。宋代の女流詩人であり、優美で優雅な詩風を代表する人物で、「史上最も才能のある女性」として知られています。 『李易安全集』、『易安居士全集』、『易安辞』などがあるが、紛失している。後世の人々は『朔魚集』と『朔魚辞』を編纂した。現在では『李清昭全集』が出版されている。それでは、次の興味深い歴史編集者が李清昭の「生生人・荀荀密密」をお届けします。見てみましょう! ゆっくりゆっくり · 検索 李清昭(宋代) 探して探して、寒くて孤独で、悲しくて惨め。天気が急に暖かくなったり寒くなったりすると、休むのが最も難しくなります。 3杯と2杯の軽いワイン、夜の強い風にどうやって耐えられるのでしょう!ガチョウが通り過ぎていくのが悲しいですが、彼らは古い知り合いです。 地面は黄色い花で覆われ、枯れて傷んでいます。今さら誰が摘めるでしょうか。暗くなるまで一人で窓辺で待つなんてできません。パラソルの木は霧雨で覆われ、日暮れまで降り続きます。このような状況での私の悲しみをどう表現したらいいでしょうか? 靖康事件の後、李青昭の国は滅び、家族は没落し、夫は亡くなり、彼女は人事によって傷つけられた。この時期の彼女の作品は、以前のような新鮮さや楽しさがなくなり、暗く悲しいものとなり、亡き夫の趙明成への思いや、彼女自身の孤独で荒涼とした状況が主に表現されていました。この詩は、この時代を代表する作品の一つです。 この詩の冒頭は珍しく、7つの単語のグループが続けて繰り返されています。彼は作詞だけでなく、詩や音楽においても独特です。しかし、利点はこれだけではありません。これらの 7 つの重複グループは非常に音楽的です。宋辞は歌うためのものなので、調和のとれた音色は非常に重要な要素でした。李青昭は音楽に対する理解が深かったので、この7つの重複した単語群が声に出して読まれたとき、それはまるで玉皿に落ちる真珠のようだった。私には、歯と舌の音が、長く低く、優しく悲しげに、行ったり来たりと繰り返しているのが聞こえただけで、まるでとても悲しい人がささやいているかのようでした。しかし、彼女が口を開く前から聴衆は彼女の悲しみを感じ取ったようで、彼女が話し終えた後も、その悲しい感情は消えませんでした。言い表せない憂鬱が私の心と空気に広がり、長い間漂い、終わりのない後味を残しました。 詩人は機嫌が悪く、暖かい気候から寒い気候への急激な変化もあって、眠ることさえできなかった。深い眠りに落ちれば、しばらくは苦しみから逃れられるかもしれない。しかし、眠りたいと願えば願うほど、眠りにくくなる。そこで詩人は、自然と亡くなった夫のことを思い浮かべた。起きて、服を着て、まずは体を温めるためにワインを飲みましょう。しかし、風邪は孤独によって引き起こされるものであり、お茶を飲むのと同じように、飲酒は一人でいるときに特に孤独感を感じることになります。 薄酒を一杯持って、空が暗く、雲が低く、風が強く冷たいこの季節に、突然一羽のガチョウの悲しげな鳴き声が聞こえた。悲しげな声が空を切り裂き、また詩人の癒えない傷を切り裂いた。頭が白いオシドリはパートナーを失って飛び去った。詩人はため息をついた。「ああ、野生のガチョウよ、あなたたちはとても悲しく、憤慨して泣いている。あなたたちも私のように老いて未亡人になるのか? あなたたちは、私のように、残りの人生を一人で山と丘の雪と向き合うのか?」 彼が荒々しい考えに浸り、目に涙を浮かべていると、突然、その一羽のガチョウが、以前彼にラブレターを届けてくれたガチョウであると感じた。どうしようもなく花は散り、ツバメはまるで見覚えがあるかのように戻ってくる。昔の恋の使者はまだそこにいるが、秋娘と小郎は生死によって引き離され、魂と幽霊は別々の道を歩んでいる。物事は変わり、すべてが終わった。言葉を発する前に涙が流れる。この素晴らしいアイデアには、言い表せないほどの悲しみが詰まっています。 この頃の菊を見ると、花は枯れてしまい、「夕方東の垣根で酒を飲み、袖にほのかな香りを漂わせる」という風情はもうなくなっていた。詩人は考えた。夫が生きていて、一緒に詩を歌い、古い本を整理していた頃は、なんと素晴らしい日々だったことだろう。しかし、今はどうだろう。残されたのは私一人だけで、終わりのない孤独に苦しんでいる。古いものはそのまま残っていますが、人々は全く違います。 「天気は古くなり、服も古くなり、ただ気持ちだけが以前と同じではなくなった。」孤独な雁と枯れた菊を前にして、私はさらに寂しさを感じます。彼女は手で頬を押さえ、目には涙が溢れていた。夕暮れを恐れて、一日を耐える。この暗い空を前にして、人はどうやって夕暮れまで生き延びることができるのか。時間の長さが孤独をさらに恐ろしいものにする。一人でいると、時間の流れがゆっくりになるように感じました。 夕暮れまで長い間待った後、再び雨が降り始めました。一滴一滴、止まない霧雨は悲しみのように細かく、人々をさらに動揺させます。それから私は家の外にある2本のプラタナスの木を眺めました。2本の木は風雨にさらされながらも、互いに支え合い頼り合っていました。それに比べると、私は一人でいる方がずっと寂しいと感じました。 突然の嵐、一羽の雁、枯れた菊や桐の木、詩人の目の前に広がるすべてのものが、悲しみと憤りで詩人を圧倒し、言葉では言い表せないほどで、表現する方法が見つからないほどでした。したがって、詩人はもはやいかなる対比も誇張も比喩も必要とせず、ただこう言うのです。「この感情を『悲しみ』というたった一つの言葉でどう表現すればいいのだろう?」その単純さと率直さによって、詩はより魔法的で、より詩的で、より味わう価値があるように思えます。それに比べれば、李游の「東に流れる湧き水の川のように、どれほどの悲しみを抱くことができるだろうか」という言葉も、比較にならないほど色あせてしまう。湧き水の川は果てしなく流れていますが、それでも描写することは可能です。詩人の憂鬱は言葉では言い表せないので、当然少しはマシです。 この詩に関するこれまでの解説者たちは、主に、最初の 3 つの文で一連の単語が繰り返されていることが特徴であると指摘していました。しかし、この側面だけに注目すると、必然的に表面的なものになってしまいます。歌詞は主人公の一日中の悲しい気分を描いているが、それは「探して探して」で始まり、彼女は起きてからずっと退屈していて、まるで何かを失ったかのように、海を漂う人が救われるために何かをつかむ必要があるかのように、空虚さと孤独を和らげるために何かを見つけることを望んで周囲を見回していることを示しています。次の「寒くて寂しい」という文章は、「探して探して」の結果です。何も見つからなかっただけでなく、孤独で冷たい雰囲気に襲われ、惨めで悲しい気持ちになりました。それから彼は別の文章を書いた。「とても悲しい、とても惨めで、とても悲しい。」たったこの3つの文章で、悲しみと悲嘆の雰囲気が記事全体を包み込み、読者は息を止めて集中することになります。これは、必要に迫られて表現しなければならない感情の爆発、いわゆる「止められない」状態の結果です。 「暖かい時も寒い時も」という一文もこの詩の難しいところの一つです。この詩は秋に書かれたものですが、秋の気候は「寒いようで暖かい」と表現されるべきです。「暖かいようで寒い」と表現できるのは早春の気候だけです。これは季節についてではなく、ある日の朝についてです。秋の早朝は、太陽が昇り始めたばかりなので「急に暖かくなる」と言いますが、朝の冷え込みがまだ強く、秋風が身にしみているので「まだ寒い」と言います。 「時」という字については、古代中国語では「季節」と解釈すべきだと考える人もいるが、劉勇の『永雨楽』には「薫り高い風が悲しみを和らげ、昼の景色は澄み切って穏やか、それは新天の時である」とある。曇りや雨から新天までは比較的短い期間であり、宋代の「時」という字は現代中国語と変わらないことがわかる。 「休むのが一番難しい」という文章は、上の「探して探して」という文章と重なり、朝早くから何をしたらよいか分からなかったことを示しています。 次の行「3 つのカップと 2 つのグラスの軽いワイン、夜来る強い風にどうやって耐えられるだろうか?」は、上記の行「暖かいけれども寒い」と一致しています。古代人は朝起きて毛の時間に酒を飲んでいたため、「毛頭毛酒」とも呼ばれていました。ここでは悲しみを和らげるために飲酒するのは無駄だと言われています。 「雁が渡る」の「雁」は、昔北で見られた南から渡る秋雁のことなので、「悲しいけれど、昔の知り合いだ」ということになります。 『唐宋辞選』には「雁は互いに面識はないが、『旧知』という言葉は郷愁を表現している。趙固の『寒池』には『郷愁は果てしなく、雁は南楼を飛ぶ』とある。詩の意味は似ている。」とある。 詩の最初の部分は、愛を求める人の無駄な探求と、ワインが彼の悲しみを和らげることができず、風に運ばれてきたガチョウの鳴き声が彼の郷愁を増すだけであるということについて語っています。詩の後半では、秋の空から家族の中庭へと移ります。庭園には菊が咲き乱れ、秋真っ盛りです。ここで「地面が黄色い花で覆われている」とは、地面一面に枯れた花びらがあるのではなく、満開の菊のことを指します。 「やつれて痩せ細る」というのは悲しみでやつれて痩せ細るという意味であり、菊が枯れて死んでしまうという意味ではありません。花を観賞する気がないからこそ、菊が地面に山積みになっていても、摘んで鑑賞する気にならない。これが「今、誰が摘むに値するのか」の真の解釈である。しかし、花は摘まなければ自然に枯れてしまいますし、傷んでしまうと摘むのに適さなくなります。この詩は、花を摘む気力がない詩人の憂鬱さを表現しているだけでなく、花が枯れてしまうことに対する残念な気持ちも表しています。この詩の意味は、唐の詩人杜丘娘が歌った「花は摘むべきときにすぐに摘みなさい。摘む花がなくなるまで待ってはいけない」という詩節よりもずっと深いものです。 「窓を守りながら」以降では、一人で座っていることの退屈さや心の苦悩が描写されており、「探して探して」という3つの文章よりもさらに一歩進んでいます。 「守著」という文章を張慧燕の『辞玄』に従って分割すると、「独」で前の文章とつながります。秦冠(別名、匿名)の「ヤマウズラの空」の後半部分は、次のようになっています。「何も言わず、香りのよい杯の前に座り、夕暮れまで私の心は張り裂けそうでした。ちょうどランプに火をつけようとした時、雨が梨の花を打つ中、私はしっかりと扉を閉めました。」この詩は、この詩と似た芸術的概念を持っています。しかし、秦の詩は夕暮れに対する人々の心の準備に焦点を当てているのに対し、李の詩はそれとは反対のアプローチをとっており、まるで空がわざと暗くなることを嫌がっているかのようで、人々を特に悲しくさせている。 「梧桐」に関する2行は、淮海から引用しただけでなく、文廷雲の『耿樂子』後半の「梧桐の木、午前3時の雨、別れの苦しみは分からない、葉一枚一枚、音一枚一枚、夜明けまで空の階段に滴り落ちる」という意味も取り入れており、2つの内容を1つに統合し、より直接的な文章とより深い感情を表現しています。この詩は「悲しみという一言でどう表現できるだろうか」という一文で終わるが、これもまたユニークなアプローチだ。于鑫以来、悲しみは千、数万胡に等しいと言う人もいれば、悲しみは河や海のように広いと言う人もいます(それぞれ李游と秦観の詩を参照)。要するに、彼らは悲しみの量を誇張しているのです。ここで彼は多数を少数に変え、自分の考えが混乱し複雑であり、それをたった一つの言葉「悲しみ」で完全に表現できるとだけ言っている。この詩の美しさは、詩人が「悲しみ」という言葉以外にどんな感情を抱いているかを説明していない点にあります。まるで結論が残っていないかのように、突然終わっています。表面的には、何か言いたくても言えないような感じだが、実は、すでにすべてを、余すところなく、吐き出しているのだ。 この詩は壮大で包括的で、余分な詳細はありません。関連する出来事を一つずつ語っていますが、秋の悲しみというテーマを貫いています。六朝の叙情詩の小賦の真髄を捉え、話し言葉に近いシンプルで新鮮な言葉で新しい曲を作り、悲しい言葉と音楽的な言葉で感情を表現し、慣用句の作曲家の飾らない性質を体現しています。それは本当に独特の個性を持つ叙情詩の傑作です。 |
<<: 『春節李学師宛書状』は北宋時代の李涛によって書かれたもので、酔った老人を描いたものである。
>>: 「辺境の笛を聞く」は唐代の高石によって書かれたもので、強い郷愁が込められている。
推薦する
古代の王子と王女は、なぜ新婚初夜の前に王女と試し結婚をしたのでしょうか?
古代の王子と王女は、新婚初夜前に王女と試しに結婚した理由は何でしょうか。これは多くの読者が気になる疑...
万皇后の伝記 万皇后はどのようにして亡くなったのでしょうか?
万妃は姓を陳といい、陳延章の娘であり、康熙帝の治世55年12月20日に生まれた。乾隆帝が即位する前の...
宋代の刑務所制度はどのようなものだったのでしょうか?それは古代中国社会の監獄制度にどのような影響を与えたのでしょうか?
宋代の監獄は、刑事被告人、未執行の囚人、証人を拘留する施設であると同時に、民事訴訟の当事者の避難所で...
子孫を残すのが難しいことの責任の半分をなぜ賈憐が負わなければならないのか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
宋代の詩人李清昭も酒飲みだったのでしょうか?最も直接的な証拠は何ですか?
李清昭といえば、その名前を知らない人はいないと思います!優雅で上品な流派の代表、史上最高の才女、詩の...
歴史考古学によれば、香を焚くための香炉が古代のどの時代に登場したのでしょうか?
古代中国では、香の使用に長い歴史があります。中国に仏教が伝わると、さまざまな香料が登場し、香の芸術が...
『梁書』の馮道根の伝記にはどのような歴史物語が記録されているのでしょうか?
梁は、中国史上、南北朝時代に南朝の第三王朝として存在した謎の王朝です。蕭延が斉に代わって皇帝になりま...
歴史上の五代十国の混乱と唐王朝との間にはどのような関係があるのでしょうか?
五代十国時代は歴史上、よく知られた混乱の時代です。唐の滅亡を五代十国の歴史の始まりとすれば、この混乱...
古代の「売春宿」とは一体何だったのでしょうか?男性はなぜ売春宿に行くのでしょうか?
今日は、おもしろ歴史編集長が古代の「売春宿」がどのようなものであったかをお話しします。皆様のお役に立...
『紅楼夢』で、元春は黛玉と宝柴に対してどのような態度を取っていますか?違いは何ですか?
賈元春は『紅楼夢』の登場人物。賈家の長女であり、四姉妹のリーダーである。興味のある読者とIntere...
『新説世界文学物語』第90話の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
有名な古代書物『新世界物語』は、主に後漢末期から魏晋までの著名人の言行や逸話を記録しています。では、...
古代の皇帝が自分の子供を他人に託す際に共通する特徴は何でしょうか?相互に抑制し合う状況を形成するのはなぜ難しいのでしょうか?
皇帝が息子を他の大臣に託すのは、孤立した事件ではなく、中国の歴史では非常に一般的な現象です。老皇帝は...
「たとえ服がなくても、私の服をあなたと分け合います」という言葉はどこから来たのでしょうか? 「秦風・五一」裏話!
今日は、Interesting Historyの編集者が「秦鋒・武夷」の裏話をお届けします!興味のあ...
宋王朝の創始皇帝として、趙匡胤の功績は他の皇帝の功績と比較できるでしょうか?
中国には500人以上の皇帝がいました。中には平凡な皇帝もいましたが、歴史に名を残し、人々に称賛された...
胡磊はどんな外見ですか?開発の歴史はどのようなものですか?
胡磊:古代中国の撥弦楽器。胡磊は古くは「胡琴」「二仙」とも呼ばれ、馬上で演奏されました。『文県通鑑』...