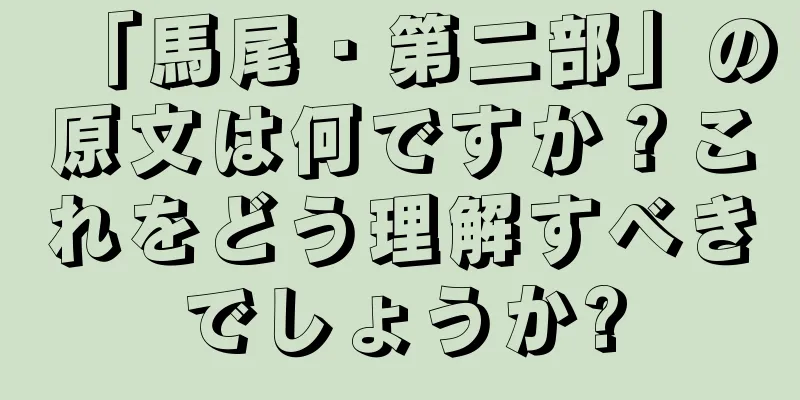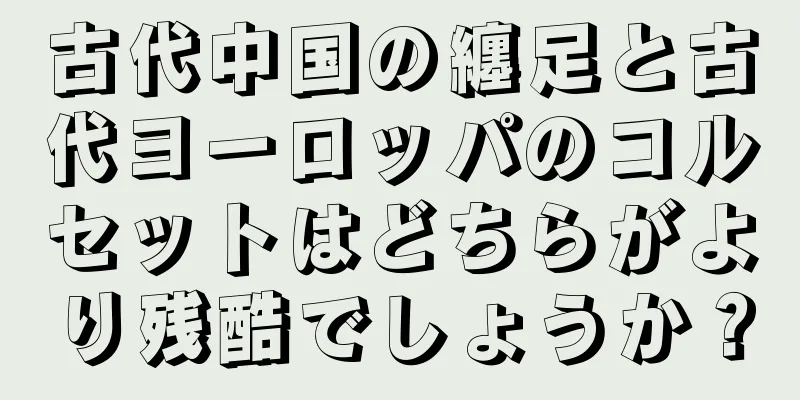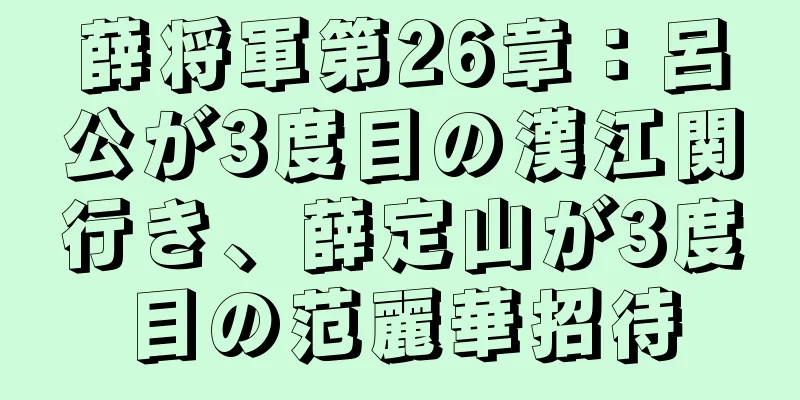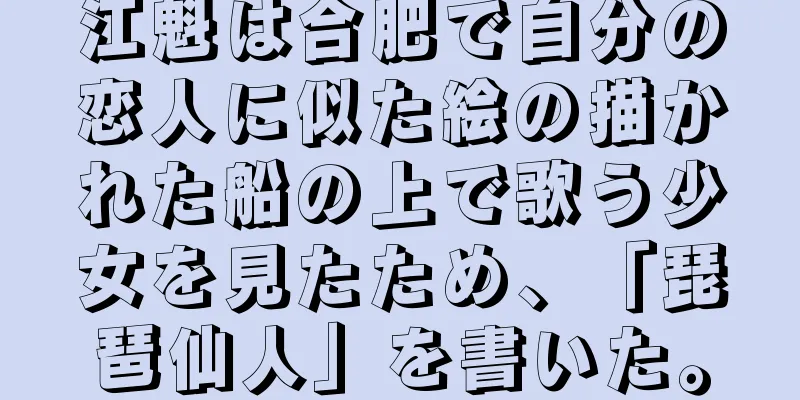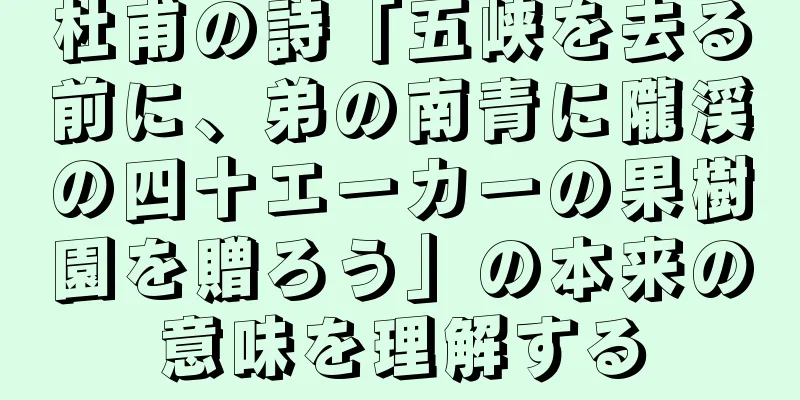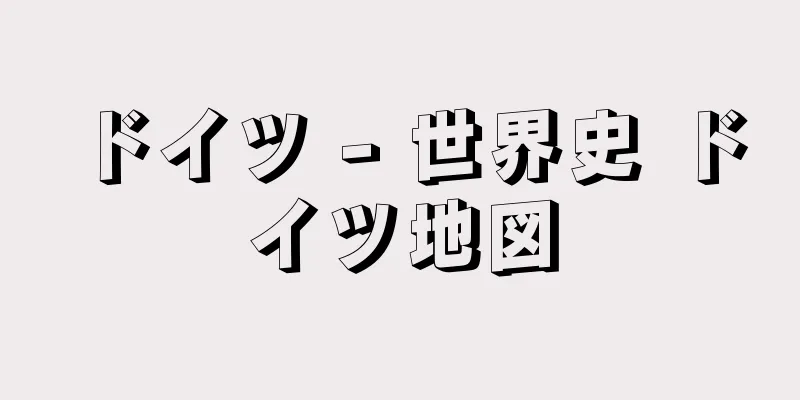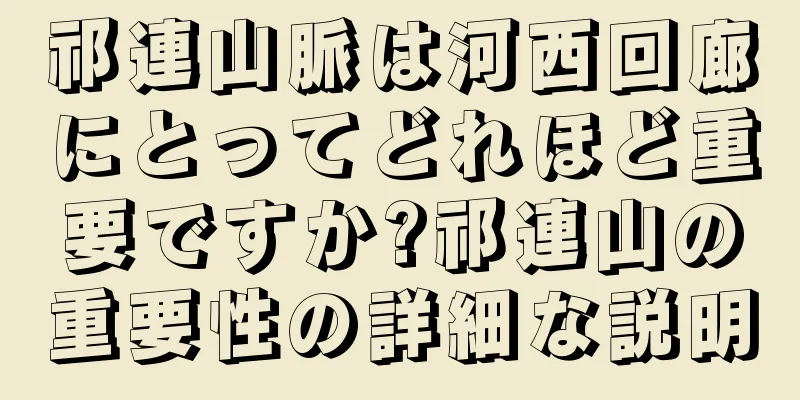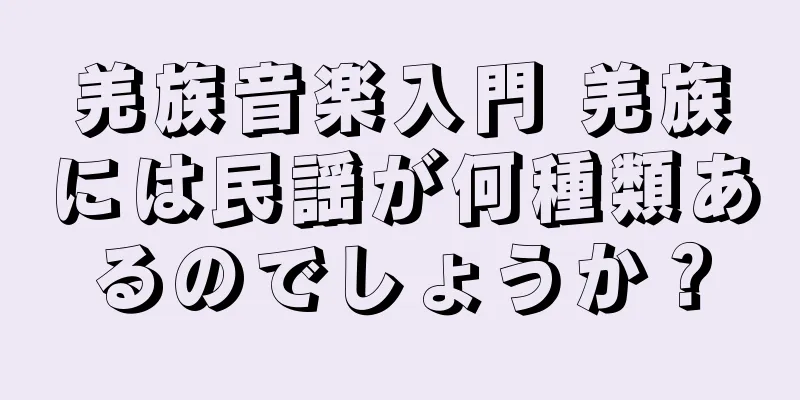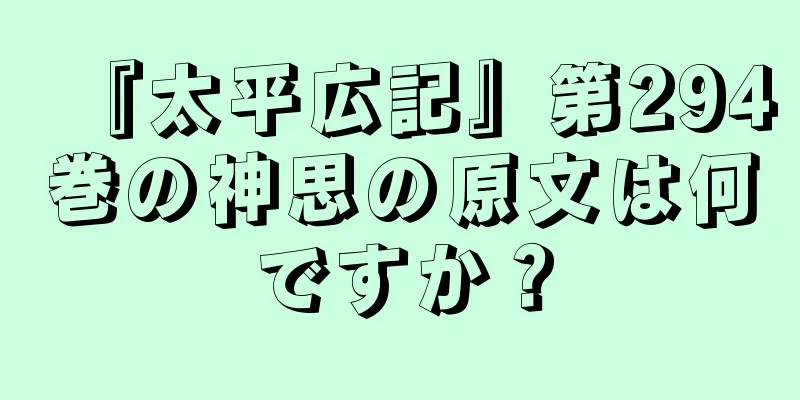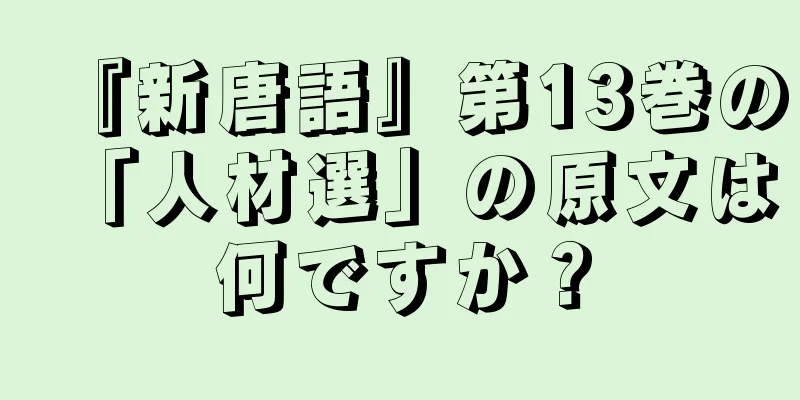古代の文人は春分をどのように描写したのでしょうか?彼らはどんな絵を描くのでしょうか?
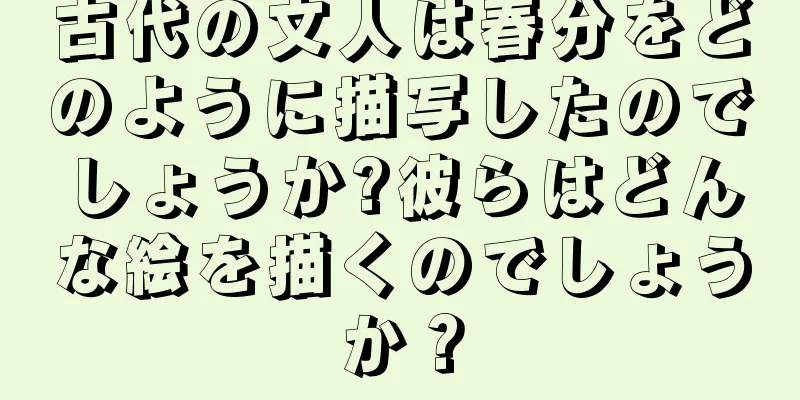
|
歴史上、春分に関する詩は数多く残されています。次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介します。見てみましょう! 立春の4日目は、春が最高潮に達した日です。 月は緑の野原の上に留まり、晴れた空には断続的に雲が現れます。 ツバメはまだ飛び、花はすでに散り始めています。 夫を恋しがる女性は夕暮れの高層ビルの中にいるが、彼女の歌声はもう聞こえない。 ——唐代の徐玄の「春分図」 晴れた日で、草は緑に覆われ、花びらが舞い、ツバメが舞い、若い女性たちが歌っていました。美しい春分の日! 『七十二候集』の「春分の日」の説明には、「二月の中旬、九十日のうちの半分に当たるので、春分という。」とあります。 『春秋飯録』には「春分は陰陽が等しく、昼と夜が等しく、寒暖が均衡する日である」とある。「春の色が真ん中にある」というのはこの原理を指している。 春のそよ風が最初に庭に梅の花を運び、続いて桜、杏、桃、梨の花が咲きます。 奥深い村にはナズナとニレのさやが咲き、春風が吹いていることを教えてくれます。 ——白居易、唐代、「春風」 この時期、土は香り、湧き水は青々と、柳は青々と、ニレの木は青金を垂らし、ナズナは白く、ウグイスは飛び、草は生い茂っています。黄金色のレンギョウとレンギョウの花は、家に帰る道を知らない酔った星のように、垂れ下がった枝の束の上にだらりと散らばっています。カサカサという音がした後、桜、杏、桃、梨の花が一斉に笑顔を見せに飛び出しました。 山の渓流沿いには「千の花が美しさを競い合う」(欧陽秀の「草踏図」)ように、花々が草原の火のように咲き誇り、美しい春の詩を作り出しています... 「春分の日の三つの兆し」、最初の兆しは黒い鳥の到来です。 「Xuanniao」はツバメを意味します。 新しいツバメがペアになって私の小屋に飛んできます。 古い巣はまだそこにあり、私たちは古い家に戻ります。 ——東晋の陶淵明による古詩の模倣九首 軒下では「梁の間から黒い鳥が鳴き、まるで人間の本性を理解しているようだ」(唐代、袁震『二十四節気詩』春分の二月中旬)昔のツバメも新しいツバメもやって来て、まるで古い友人と話しているかのように優しく優しくさえずり、ささやきながら、忙しく「持ち物」をまとめています。 ツバメは正月の祭りにやって来て、梨の花は清明節に散ります。 池には緑の苔が3、4個点在し、葉の下ではコウライウグイスが1羽鳴いています。 日が長く、飛んでいる花穂は軽い。 ——宋代、顔書、『伯貞子』 私はこの詩の芸術的な構想が特に好きです。ツバメがやってくると、春祭りになります。池には緑の苔が点在し、梨の花が舞い、柳の花穂が雪のように舞い、花は緑の陰に覆われ、オリオールが歌っていた。 コミュニティデーには2羽のツバメが飛び、春分の日には何百羽ものオリオールが歌います。 ——唐代の全徳宇:「公民の日と春分の日に端午の節句を生きることについての考察」 濃い黒と白のツバメの群れが野原と木々の間を素早く飛び回ります。ツバメのさえずりが春をさらに魅力的で明るいものにします。 春分の日は「草や池、暖かなそよ風がカーテンのように広がり、春の美しさを均等に分ける」(趙長清『蓬莱に酔う春中』宋代)。 この時代、古代の人々は遠出をしたり、船旅をしたり、花を鑑賞したりすることを好んでいました。 春の半ばに南の庭に出かけると、穏やかな風に馬のいななきが聞こえました。 青梅は豆ほどの大きさで、柳は眉毛ほどの大きさで、日が経つにつれて蝶が飛び回ります。 花は露で重く、草の煙は低く、人々の家のカーテンは引かれ、 ブランコに座りながら絹の服を脱ぐと、二羽のツバメが描かれた梁に戻ってきました。 ——宋代、欧陽秀の『阮朗帰』 青梅は豆ほどの大きさで、柳の葉は眉毛のようで、蝶、煙、ブランコ、ツバメが風景に溶け込んでいます。欧陽秀の詩は、清らかで明るく、穏やかで自然、静かでゆったりとしており、遠出の美しい風景を描写しています。 春分の日には雨音がかすかに聞こえ、柳の斜面に吹く風が客を家へと連れて行きます。 ——唐代の徐玄『覚醒』 春雨の洗礼の後、春の活力がいたるところに現れます。 渓流沿いの風景も春分の日を迎えました。霧のかかった夕暮れの絵画ホール。 一筋の線香の煙が水面を漂います。香り高いワインに酔いしれてください。 舞う袖は雪のように舞い、歌声は雲のように漂う。 これを世界で何回聞けるでしょうか?総理、怒るのはやめてください。 春の真ん中で、太陽がちょうど昇り始めた頃でした。 ——宋代の鍾兵の『華堂春即興曲』。 古代には、性別、年齢、身分を問わず、花を髪に挿し、外出したりお酒を飲んだりする習慣がありました。詩人の鍾兵は珍しく機嫌がよく、欄干に寄りかかって歌を聞き、舞踏を観賞し、春の煙と夕景に酔いしれていた。 太陽と月は空に等しくあり、黒い鳥は冷たい桃の花を気にしません。 今日は鶏が直立し、川の上の恋人が凧を揚げています。 ——漢代の司馬相如『春分』 春分の日頃は空気が上昇し、気候も暖かく穏やかで、景色も気持ちよく、立ち卵や凧揚げをするのに最適な季節です。春分の日は昼と夜の長さが同じなので、バランスをとるのが比較的簡単です。古代の人たちは、新鮮な卵を直立させるとその年に幸運が訪れると信じていました。 風の強さは羽毛の多さによるものではありません。 赤い線は空に伸び、青い空へと続く道があります。 ——清代呉有如の絵画詩 一列に並んだ凧が空に向かってまっすぐに上がります。昔の人は凧を揚げることで悪霊や不運を追い払うと願っていました。 『紅楼夢』では、凧揚げについて次のように描写されています。「黛玉は笑って言った。『しかし、私たちは誰がこの凧を揚げて不幸を招いているのか知っています。早く落ちさせてください。私たちの凧を取り出して、私たちも揚げて不幸を招きましょう。』」 凧の糸はどこで切れたのでしょうか?風に飛ばされて杏の枝に落ちました。 ——羅其蘭、清代、「春の閨房」 糸が切れた凧は「病気の根も一緒に運んでしまう」。 『続博物誌』には、「春には凧を揚げ、糸を上に導き、子供に口を開けて見させると、体内の熱を和らげることができる」とある。 雨が降った後、川の水が堤防を越えて流れ、村の子供たちが遅れてきた太陽に感謝するのを眺める。 竹馬は泥の中をよろめきながら進み、凧は風に吹かれて堂々と飛びます。 ——陸有「小川で遊ぶ村の子供たちを見る」 子どもが竹馬に乗って凧を持って地面を走っていたのですが、ふと「風に舞う凧」を見上げていたところ、突然、子どもも「馬」もよろめき、泥だらけの池に飛び込んでしまいました。子どもの無邪気でかわいらしく、幸せで気楽な表情が生き生きと描かれています。 3月、凧を手にして見上げると、凧が風に吹かれて高く舞い、予測不能な動きをしているのが目に入ります。本当に楽しいですね! 青柳、新燕、空いっぱいの凧。春の息吹は心を清め、魂を慰め、全身を温めてくれます。 街中の桃や梅の木は風雨を心配しているが、小川のほとりのナズナは春の訪れを感じて咲いている。 ——辛其記『ヤマウズラの空 路上の桑の木の若芽』 古代にも春野菜を食べる習慣がありました。春野菜は山菜です。ナズナは古くから愛されてきました。春分の日頃は山菜採りに最適な時期です。 香り豊かなご飯を炊くために山菜を探してみてください。 ——黄庭堅「春陰」 毎日故郷が恋しくて、シダや山菜を食べていますが、春になるとナズナが美味しくて、故郷に帰るのを忘れてしまいます。 ——陸有の「ナズナを食べる」 春のナズナは美味しく、熟したサクランボが最も有名です。 ——鄭板橋の『絵画詩』 これらの詩は詩人がナズナに対して抱いていた特別な愛情を表現している。 平野にはナズナの花とともに春が訪れ、雨上がりには耕されたばかりの畑の上をカラスが飛び回ります。 ——辛其記『ヤマウズラの空:雁湖を訪れて酒場の壁に酔って書く』 春の雨が降り、畑一面に白いナズナが咲き誇っていました。カラスは耕されたばかりの土地で餌を探していました。田舎の春の景色は絵のように美しく、ナズナも春の景色の一部となっています。 現代人にとって、山菜採りは、自然に親しむと同時に食欲も満たす、一種の生活の楽しみです。 時々彼は野生のナズナを探して小麦畑を歩き回り、修道士たちのために野生のスープを作らせました。 ——蘇軾の「子有の野菜栽培の韻を辿る、長い干ばつの後、育たなかった」 雨も降らず、干ばつもなかったので、食べるものが何もなかったため、蘇軾は麦畑を歩き回ってナズナを探さなければなりませんでした。そして近くの寺院に行き、僧侶に山菜の入った「山のスープ」を作ってくれるよう頼みました。飢えに苦しむことが多かった古代人にとって、山菜は自然からの贈り物であり、飢饉の時代に美しい春が与えてくれた贈り物でした。 屋根の上で春の鳩が歌い、村の横では杏の花が白く咲いています。 彼らは斧を手にして遠くの木を切り、鍬を持って泉を探します。 ——唐代の王維の『田園春』 春は花や植物にとって希望であり、春の耕作は農家にとって希望です。キジバトが鳴き、アンズの花が咲き誇る。美しい春の景色は、村人たちに、気候が暖かくなり、春の耕作に備える時期が来たことを実感させます。斧を持って桑の枝を切る者もいれば、鍬を持って泉の水路を調べる者もいた。桑の葉刈りと水の管理は冬が明けて最初に行う作業であり、農作業の前段階です。 野原の黄色い雀が群れをなし、山の仙人たちは昔話を語り合う。 牛に餌をやり、真夜中に妻に電話し、明日の春分の日の朝に木を植えましょう。 ——宋萬、清代、「春の農民たち」 春分の日は雨が十分に降り、麦がすくすくと育ち、菜の花が咲き、万物が春の成長期に入ります。老人は夜、牛に餌をやっていたとき、明日は春分の日なので急いで木を植えなければならないので、早く起きるように妻に思い出させました。 村のすべての家族が竹垣の外や野生の桃の木の横で、ワインを買うためにお金を出し合います。 穀物や絹の価格はずっと以前から通常の価格の2倍になっているので、老人たちは若くて強い人について語るのをやめるべきです。 霧雨の中、人々は香り高い草の元に遅く帰宅し、東風の中、牛は落ちた花の上で眠ります。 稲の苗も育ち、桑の芽も短くなり、春分の日や寒の節句で大忙しです。 ——李建、清代、「村の酒飲み」 村人たちはお金を集めて春節の酒を飲んだ後、遅く帰宅しました。東風が吹き、霧雨が降り、竹垣は荒れ、野生のサンザシが育ち、牛は落ちた花の上で眠っていました。それは平和でゆったりとした場所でした。春の静かで美しい田園風景の写真です。村人たちは「穀物や絹の値段が時とともに倍増した」と不満を抱きながらも、春の繁忙期が到来し、「畑を一回耕すと春雨の時期がわかる」。心の中に恨みがあっても、「老人が若者のことを語ってはならない」という世代間対立があっても、すべてを手放さなければならない。 「春分の日と寒の節句は大忙し。」春の耕作と植え付けは忙しく、豊作が期待できます。これは新年への希望であり、人生への希望です... 春分の日の穏やかさは独特です。太陽の光は暖かく明るく、川の水は澄んでいて、草は薄緑から濃い緑に変わり、人生の野原は色とりどりの色でいっぱいです。 春の時間を平等に分け、今日を最も大切に思う人は誰でしょうか? ——清代の顧振観「春分の青柳枝花節」 春分の日を過ぎても、春はまだ半分残っています。「春分の日が過ぎて、春はもうすぐ去ります。花の千本の松明の中で、私はここに春を留めようとします」(『滴蓮花』、葛聖中、宋代) 16歳の木の先端では、すべてが新鮮です。古代の詩では、春を楽しんでください!人生の美しさと春の美しさを感じてください! |
<<: 歴史上、春分について記述している詩は何ですか?春分の日にはどのような習慣が守られるのでしょうか?
>>: 「雨上がりの草の上を歩く」は欧陽秀によって書かれたもので、女性の恋愛に対する愛情を歌った詩です。
推薦する
曹操はもともと漢王朝に忠誠を誓っていましたが、いつ考えが変わったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
蔡氏の戦いはどの王朝で起こりましたか?採石場の戦いの導入と影響
1161年(南宋紹興31年、金正隆6年)、南宋の文官である于雲文は、金軍が川を渡り南下するのを阻止す...
『環溪沙 春の日』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
環西沙:春の日劉晨翁(宋代)遠くをさまよう蜂は家を忘れ、カラスは新しい柳の列の間で鳴き、過去について...
皇帝の芸術とは何ですか? 「天皇の芸術」の真髄を3つの文章にまとめました!
統治の芸術とは何か?「統治の芸術」の真髄を3つの文章でまとめました!皆様のお役に立てれば幸いです。現...
『西遊記』で太上老君が精製した魔法の武器は何ですか?太上老君の最高の魔法の武器をチェックしてください
「西遊記」で最も多くの魔法の武器を持っているのは誰ですか?それは間違いなく太上老君です。太上老君はあ...
清朝はかなり大きな軍隊を持っていましたが、緑陣営の兵士たちはどのような軍隊だったのでしょうか。
歴史上の軍隊といえば、清朝には多くの軍隊があったことは誰もが知っているはずです。当時の清朝の緑陣の兵...
十二支の守護神を見てみましょう。子年生まれの人の守護神は千手観音菩薩です。
干支のネズミの守護聖人である千手観音菩薩は、干支が「ネズミ」の人々の出生仏でもあります。次は興味深い...
鄭板橋の代表作「満江紅・郷愁」鑑賞
以下、Interesting History の編集者が、鄭謝の『満江紅・懐かしき故郷』の原文と評価...
顔継道の古典詩『于美人』を読んだことがありますか?
以下、面白歴史編集長が、厳継道の『于美人・曲欄外の天は水の如し』の原文と評価をお届けします。ご興味の...
宋仁宗には三人の息子がいたのに、なぜ趙叔が宮廷に入り、余の太子となったのでしょうか。
宋仁宗の趙真には幼少期に子供がいなかったため、景有2年(1035年)、宋仁宗は幼い趙叔を宮廷に連れて...
有名な哲学書『荘子』外篇:秋水(4)原文と方言訳
『荘子』は『南華経』とも呼ばれ、戦国時代後期に荘子とその弟子たちが著した道教の教義をまとめた書物です...
相撲はいつ始まったのですか? 『水滸伝』には相撲に関するどんなストーリーがありますか?
今日は、Interesting History 編集者が「宋代の相撲」をお届けします。ご興味がありま...
ナラン・シンデの「淡黄柳:柳への頌歌」:この詩は詩人の悲しい気持ちを表現している
納藍興徳(1655年1月19日 - 1685年7月1日)は、葉河納藍氏族の一員で、号は容若、号は冷家...
王維は霍去兵について詩を書いたが、それは読むと壮大で感動的である。
おもしろ歴史編集長と一緒に王維の詩を鑑賞しましょう! 「飛将軍が龍城にいる限り、胡馬は銀山を越えるこ...
戦国時代後期の作品『韓非子』:八評全文と訳注
『韓非子』は、戦国時代後期の朝鮮法家の巨匠、韓非の著作です。この本には55章が現存しており、合計約1...