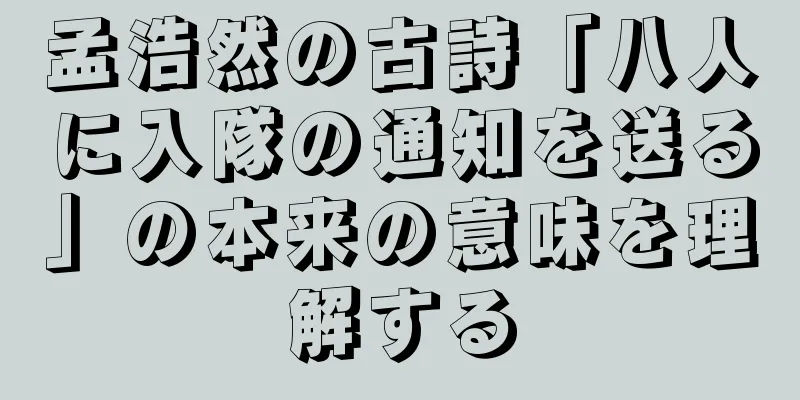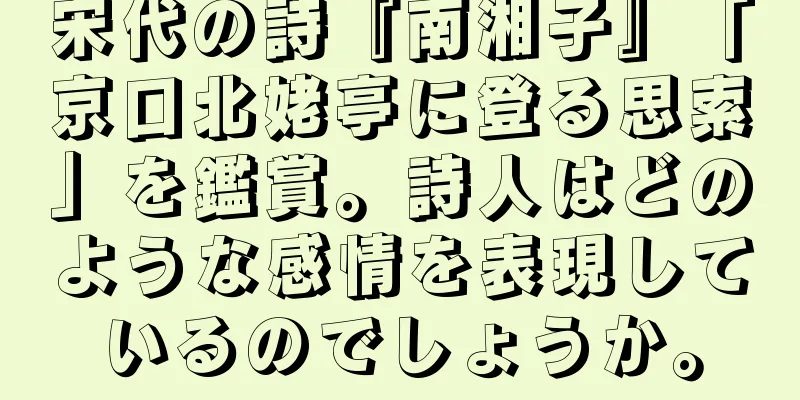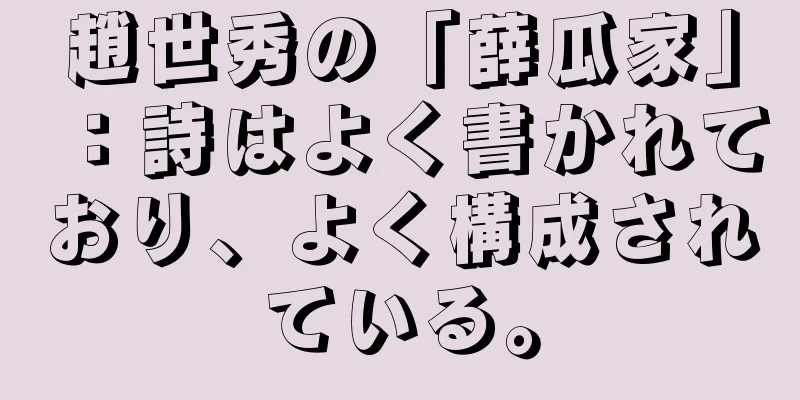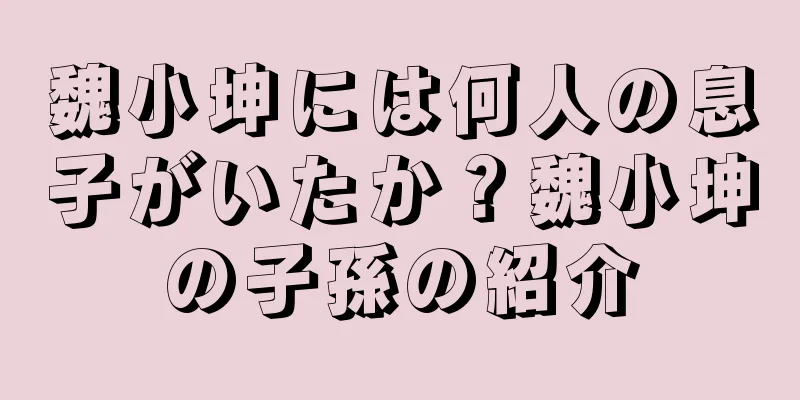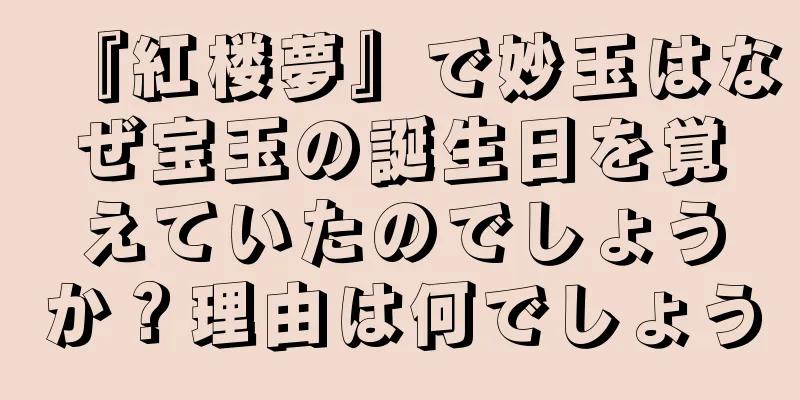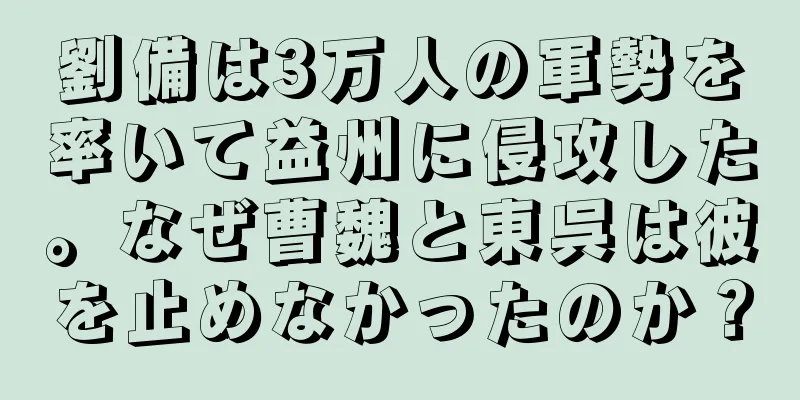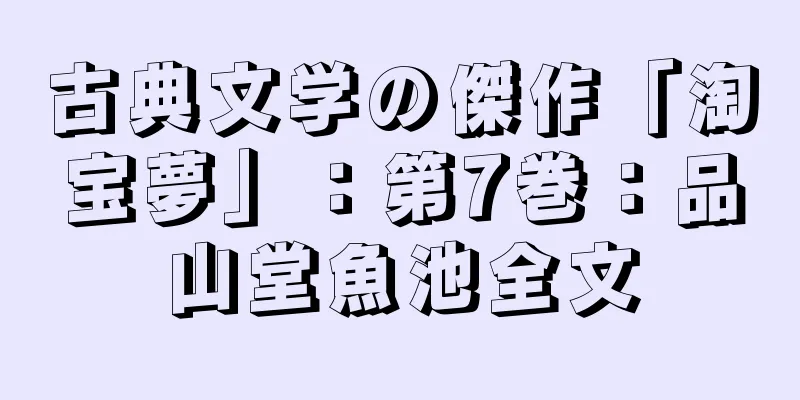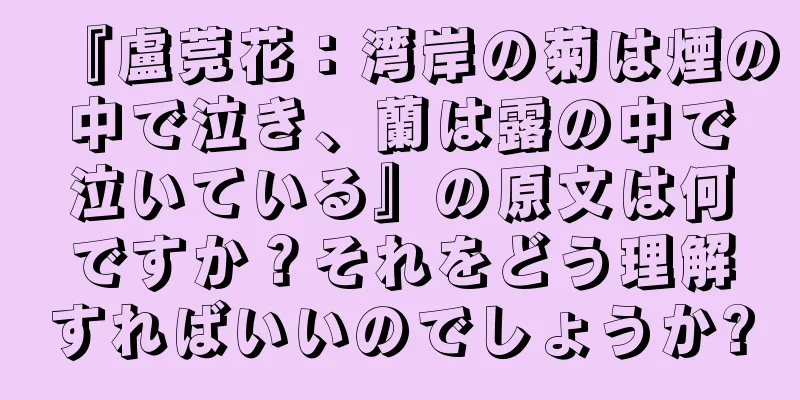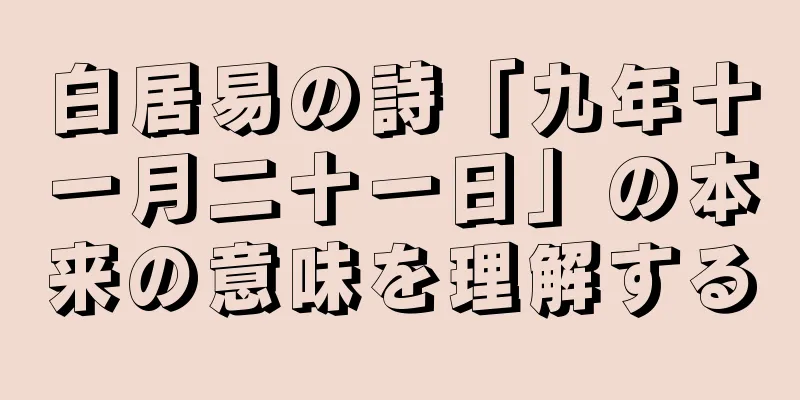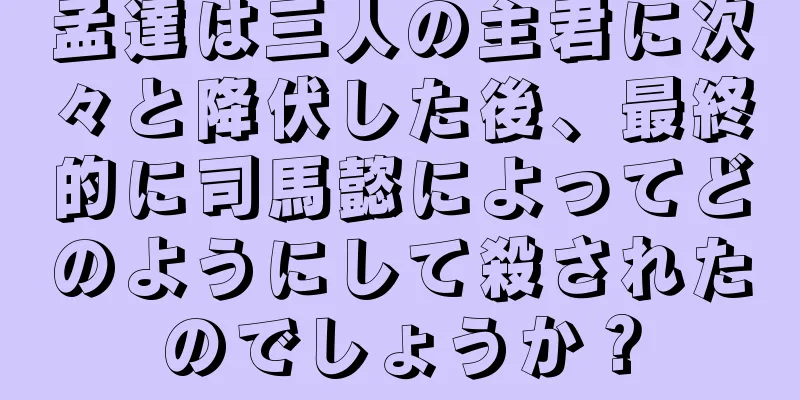白居易の「花は花にあらず」は、人生は夢、泡、霧、稲妻のようなものだという彼の気持ちを表現しています。
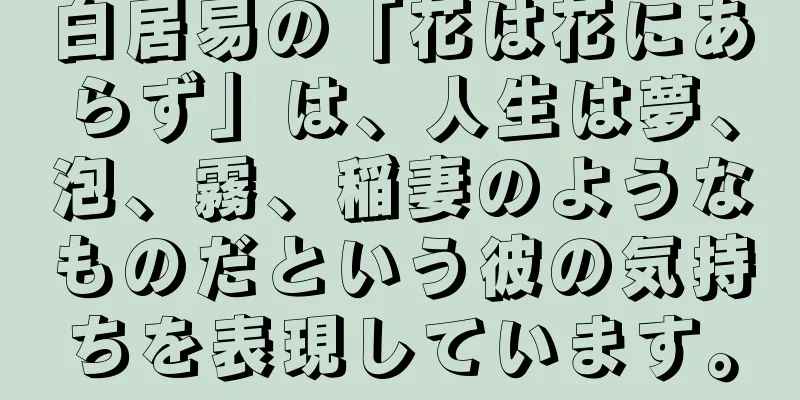
|
白居易は、字を楽天といい、別名を向山居士、随音献生とも呼ばれた。写実主義の詩人で、唐代の三大詩人の一人であり、後世からは「詩鬼」と呼ばれた。彼と袁震は共同で新月傳運動を提唱し、二人は合わせて「袁白」と呼ばれ、彼と劉玉熙は合わせて「劉白」と呼ばれた。興味深い歴史の編集者と一緒に、白居易の『花は花ではない』について学びましょう。 花は花ではない 白居易(唐代) 花は花ではなく、霧は霧ではありません。 真夜中に来て、夜明けに出発します。 春の夢が実現するまでにどれくらいの時間がかかるのでしょうか? 朝の雲のように消えて、どこにも見つからない。 翻訳と注釈 翻訳 花のようで花ではなく、霧のようで霧ではない。 真夜中に到着し、夜明けに出発します。 この美しい春の夢はいつまで続くのでしょうか? それが去ると、それは消えてどこにも見つからない早朝の雲のようなものです。 注記 花は花ではない: 合唱曲「花は花ではない」の流行はこの詩から始まりました。 来如:来るとき。 時間:あまり時間がありません。 消え去った後:朝に漂う雲のように、消えた後はどこにも見つかりません。 超雲:これは楚の襄王が武山の女神を夢に見たという物語を暗示しています。 簡単な分析 白居易は香山居士と呼ばれていたので、居士とは菩提果を修めて家庭で菩薩道を歩む人のことであり、この詩は白居易の身分という観点から考察する必要がある。 『花は花ではない』: 実際、それは自然の真の状況を描写しており、著者の実践と悟りの最良の説明です。つまり、人が花と名付けたからといって、花が育つわけではないのです。あなたの名前と同じように、それはあなたという人間を表すものではありません。それは人工的な名前です。道教の実践では、このような行為は人の心を汚す行為と呼ばれます。 霧は霧ではない: 上記と同じ。前者が「霧」という自然現象を指すのであれば、それは明らかに、誰もが思い浮かべる「霧」という漢字ではない。 春の夢のような日々はいつまで続くのでしょうか。次の文章は作者の思いを的確に表しています。人生は夢のよう、泡のよう、霧や稲妻のようであるという感覚。それは、著者の「以前」に対する感情であり、人生を経験し、花は花ではなく、霧は霧ではないという真実を理解した後もまだ理解していない人々に対する感情でもあります。 朝の雲のように消え去り、どこにも見つからない。上記と同じ。人は来ては去り、人生は短く、運命は予測不可能です。あなたは今、完全な人間ですが、死んだ後はただの灰の山になります。これは作者が世界の無常性を認識したことだ。すべての外見は空であるという認識。本当の心を誰が理解できるだろうか。それは春の夢のようにやって来て、朝の雲のように去っていく。 感謝 『花は花に非ず』は唐代の詩人白居易が書いた雑句詩である。この詩は、人生は夢のようで、泡のようで、霧や稲妻のようであるという気持ちを表現しています。人生に存在したが消えてしまった美しい人々や物に対する一種の追悼と後悔を表しています。詩全体が一連の比喩で構成されており、描写は曖昧だが現実的で、ぼんやりとした中にもリズミカルで緻密な美しさがあり、恋愛詩の傑作である。後世の人々が歌を作り、それが広く流布されました。 最初の 2 つの文、「花は花ではない、霧は霧ではない」は、人々に不安感を与えます。 「花ではない」と「霧ではない」はどちらも否定ですが、花のように、霧のようにという暗黙の前提が含まれています。したがって、これら 2 つは巧妙な比喩であると言えます。蘇東坡はこれにヒントを得たようで、「花のようで花ではない、散っても誰も気にしない」(『水龍敬』)という有名な一節を書いた。蘇軾の詩はポプラの花穂と柳の花穂について書かれているが、白石の詩ではそれが何についての詩なのかが明確に述べられていない。しかし、「夜中に来て、明け方に去る」という語りから、ここでは花と霧の比喩が、歌われているもののはかなさ、はかなさ、長続きの難しさを表すために使われていることがわかります。 「真夜中に来て、夜明けに去る」というフレーズを見ただけで、読者はそれが夢であると疑うでしょう。しかし、次の文「春の夢のようにやってくる」から、そうではないことがわかります。 「夢」も比喩であることがわかりました。ここでは、「来る」と「行く」という言葉が、音と感情の面で前のものと次のものをつなぐ役割を果たし、2つの新鮮な比喩を生み出しています。 「夜半に来る」は春の夢を意味します。春の夢は美しいですが、長くは続きません。そのため、「春の夢のようにいつまで続くのでしょうか」という疑問が生じます。「夜明けに見る」は朝焼けを意味します。雲は美しいですが、消えやすいです。そのため、「朝雲のように消えて、見つからない」というため息が生じます。 詩は一連の隠喩から成り、これをメタファーと呼びます。それらは密接に結びついており、スムーズかつ自然に流れます。説明されていない比喩を強調するために鮮明な画像を繰り返し使用します。 『十九古詩』の「南には北斗七星、北には北斗七星、牛飼いはくびきを負わず」(「夜は明るい月が輝く」)や何卓の『清遠』の「タバコ畑、街には花穂がいっぱい、梅が黄色い時は雨が降る」など、比喩をうまく使った詩の例は数多くあります。しかし、これらの比喩は詩の構成要素の 1 つにすぎません。この詩のように比喩だけで構成されている詩は非常に稀です。また、前者の例では、北斗七星、北斗七星、牛飼い座などの星座を比喩として用いており、「名前で呼んでも何の意味があるのか」という形で比喩が用いられている。後者の例では、タバコ、花穂、梅雨などの風景を比喩として用いており、「いくつあるかお聞きしてもよろしいでしょうか」という形で比喩が用いられており、比喩(比較対象)はどちらも明確である。しかし、この詩では、隠喩(隠喩として使われる対象)のみが示されており、隠喩の起源は示されていないため、興味をそそられる謎のようです。その結果、詩の芸術的概念は「ぼんやりとした」色に包まれます。 この詩の比喩的な意味は説明されていないが、作者は同様の感情を込めた他の作品とともに、この詩を詩集の「感傷性」のセクションに収録している。 1つは「Zhenniangの墓」で、詩は次のように書かれていますイアン」は、「2月の重い霜は来年結婚したいが、今年は死ぬ」と書かれています。この詩の最後の2つの文の比phorとまったく同じであり、音と感情は、人生に存在し、その後姿を消したことを思い出して後悔しています。 「花は花ではない」という詩は、この詩集の中で「単純な歌」の直後に収録されており、読者にこの詩の目的についてのメッセージを伝えています。この詩はおそらく『建建音』と同時期に同じ目的で書かれたものと思われます。 この詩は、三字文と七字文を交互に並べる形式(当時の民謡の三三七文構造を応用したもの)を採用しており、律動的な秩序と緻密な美しさを兼ね備えており、後の短詩とよく似ている。そのため、後世の人々は、この詩の手法を歌詞の旋律として採用し、その旋律を「華飛華」と名付けました。五字詩や七字詩との内容上の大きな違いは、詩が人の内面的な心境を表現する傾向があることです。この点では、この詩もciに似ています。唐代に最も早くから抒情詩を書いた詩人の一人である白居易の作品に「短い歌詞に似た詩」という現象が現れたのは当然のことである。 背景 『白居易全集』には「真娘墓」と「建前印」という二つの詩があり、どちらも哀悼詩である。 「花は花ではない」という詩は、上記の2つの詩と同じ巻に収められており、それらの後に並べられています。そのため、「花は花ではない」という詩は、「鑑鑑音」とほぼ同時期に書かれたと推測されます。 |
<<: 白居易の「池上図」は、子供の無邪気で素朴、活発でいたずら好きなイメージを描いています。
>>: 白居易の「魏志の夢」は古い友人への深い憧れを表現している
推薦する
ランタンフェスティバル中の漢民族の習慣は何ですか?
ランタンフェスティバルの風習ランタンフェスティバルは中国の伝統的な祭りなので、全国で祝われます。ほと...
蒸しパンの歴史はいつまで遡れるのでしょうか?なぜ諸葛亮が発明したと言われるのでしょうか?
中国人が蒸しパンを食べるようになった歴史は、少なくとも戦国時代にまで遡ります。もともとは「蒸し餅」と...
初唐の四大天才はどのようにして選ばれたのでしょうか?なぜ王毓が彼らの一人だったのでしょうか?
初唐四才とは、中国初唐の作家である王毓、楊璋、陸兆麟、羅斌王の総称であり、略称は「王洋陸洛」である。...
王安石の『王鳳源を想う三詩、その二』には、彼の古い友人に対する深い思いが込められている。
王安石は、号を潔夫、号を半山といい、北宋時代の政治家、改革者、作家、思想家であった。彼は文学において...
『西遊記』で、花果山が10万人の天兵に包囲されたとき、孫悟空はなぜ助けを求めなかったのでしょうか?
『西遊記』で、花果山が10万の天兵に包囲されたとき、孫悟空はなぜ助けを求めなかったのでしょうか?主な...
明代『志譚(選)』:淑女の知恵:陶観の母全文と翻訳注釈
『シンクタンク全集』は、明の天啓6年(1626年)に初めて編纂された。この本には、秦以前の時代から明...
『紅楼夢』の元陽はどんな女性ですか?
『紅楼夢』で最も力のある女の子は誰かと聞かれれば、間違いなく元陽でしょう。以下、興味深い歴史の編集者...
古典文学の傑作『太平天国』:陸軍省第41巻
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
水滸伝十二人のカンフーマスター:涼山十二人の武術を総合ランキング!
涼山英雄武術総合力ランキング比類のない勇気を持つ伝説の英雄たちが、アリーナで戦い、戦場を駆け巡ります...
水滸伝で宋江が朱家荘を3度攻撃した最終結果は何でしたか?なぜ負けたのでしょうか?
宋江は、雅号を公明といい、『水滸伝』全編の第一の登場人物であり、非常に特別な存在です。彼は涼山蜂起軍...
劉秀が郭聖通を廃し、代わりに殷麗華を即位させたのは、本当に彼女に対する深い感情からだったのだろうか?
劉秀の「もし妻を娶るなら、殷麗華と結婚したい」という言葉は、光武帝とその妻の美談を作った。しかし、皇...
李奇の「陳章甫への別れ」:別れによる悲しみを表現していない、実にユニーク
李斉(690-751)は漢族で、昭君(現在の河北省昭県)と河南省毓陽(現在の河南省登封市)の出身。唐...
ラヴォアジエの死: ラヴォアジエはなぜギロチンに送られたのか?
ラヴォアジエの生涯は短かったが、ラヴォアジエの伝記は偉大な科学者の生涯を世界に伝えている。ラヴォアジ...
漢民族の歴史における西周時代の「礼楽文明」の簡単な紹介
西周王朝(紀元前1027年? - 紀元前771年)は、夏王朝、商王朝に続く我が国の3番目の王朝であり...
薛宝才が悲劇的な人生を送ることになった最大の原因は何だったのでしょうか?彼女はどれほど無力なのでしょうか?
Interesting Historyの編集者がお届けする薛宝才に関する記事を見てみましょう。薛宝才...