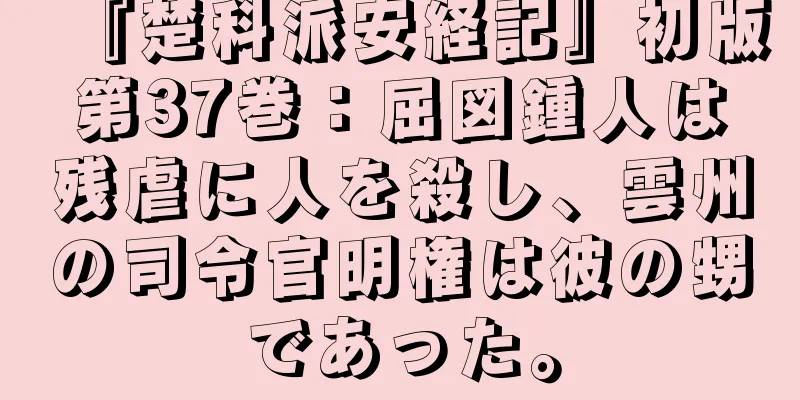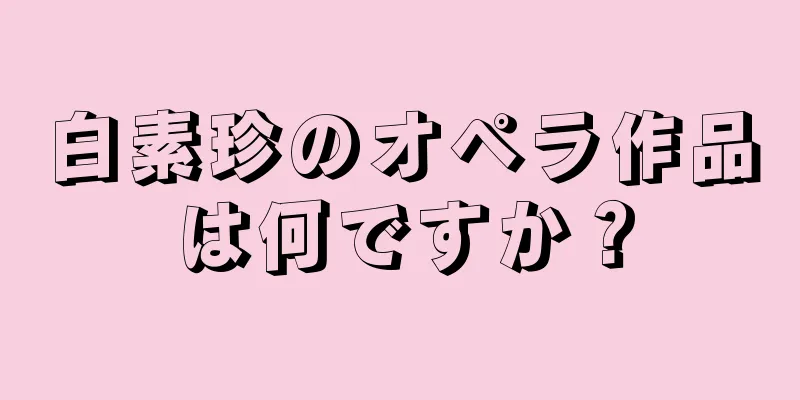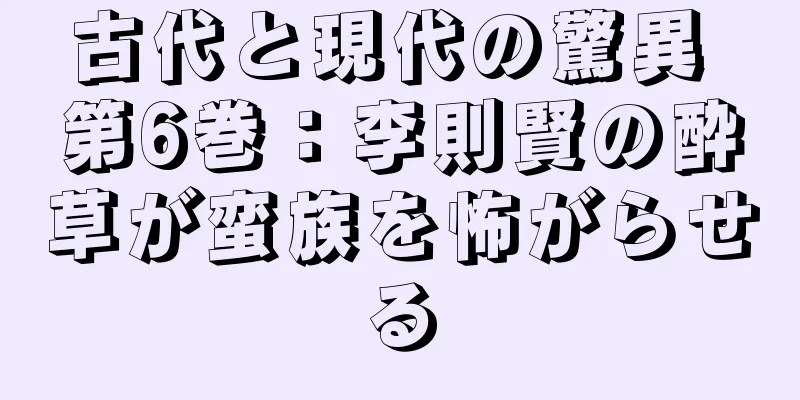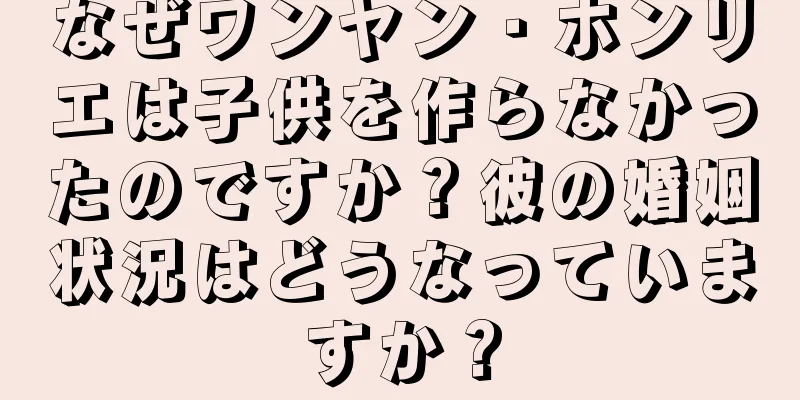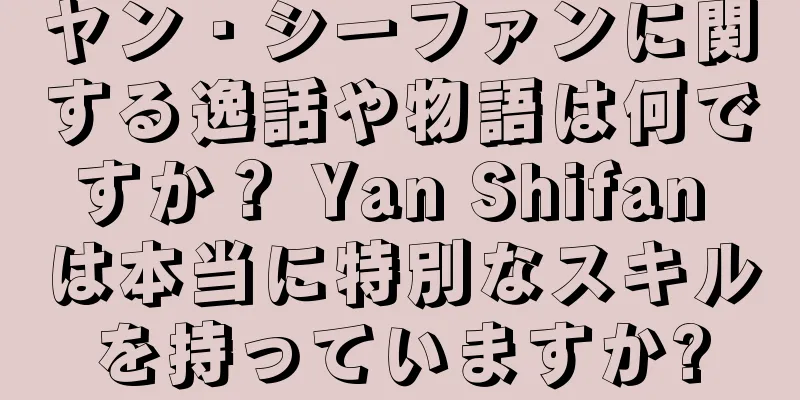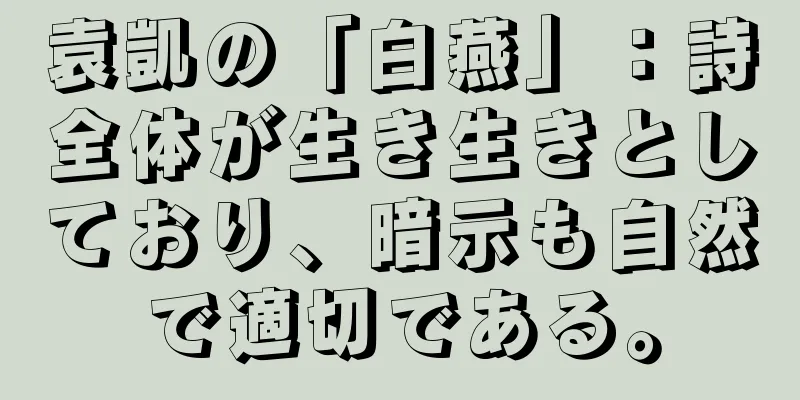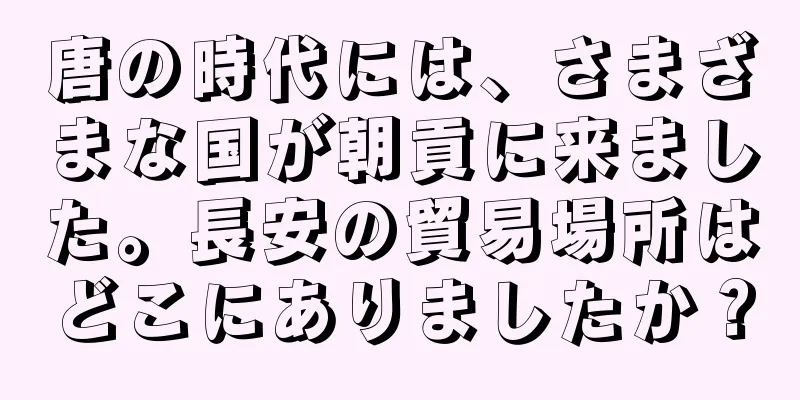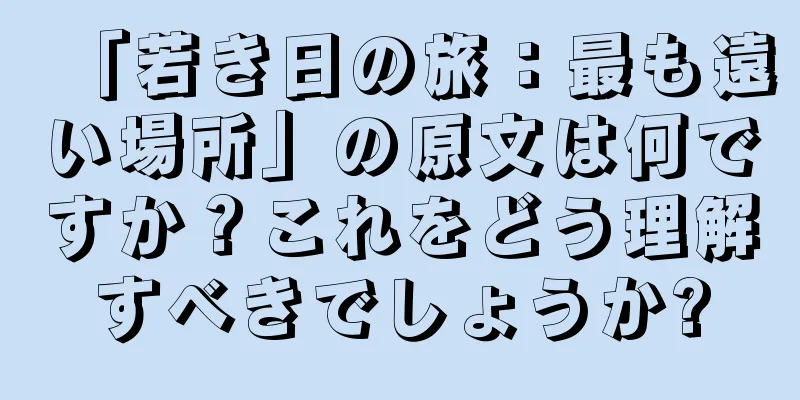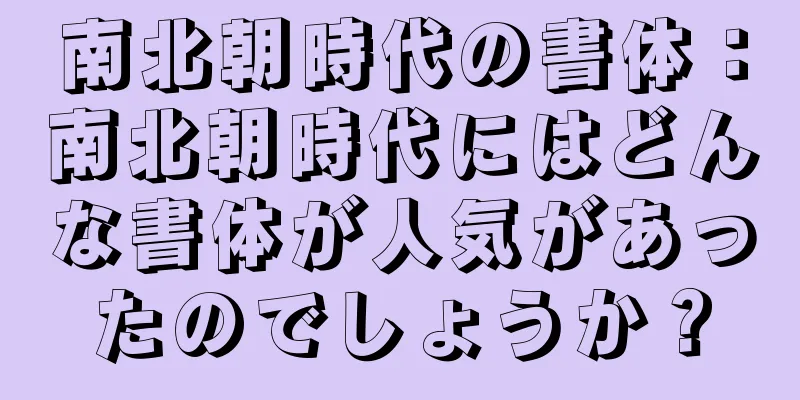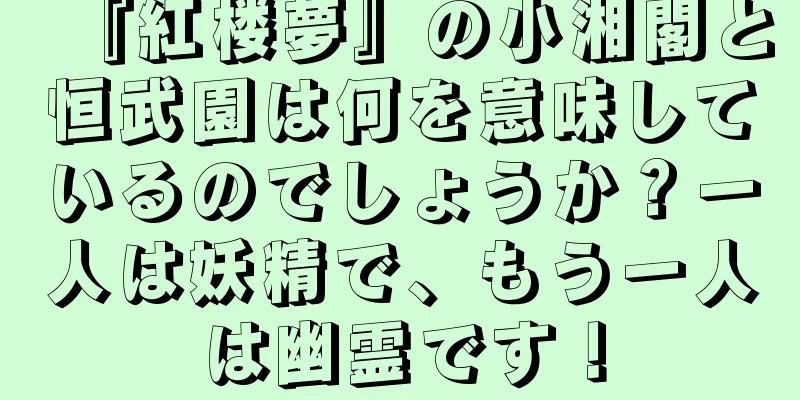韓愈の「池畔の花穂」は、池のほとりの花穂を愛でる詩人を描いています。
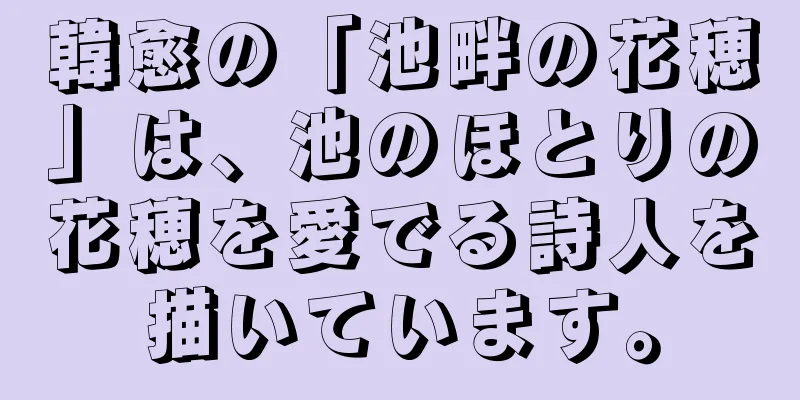
|
韓愈は、字を徒子といい、自らを「昌里の人」と称し、通称は「韓昌里」または「昌里氏」であった。唐代の著名な作家、思想家、政治家であり、唐代古文運動の提唱者であり、「唐宋八大家」のリーダーでもあった。劉宗元とともに「韓柳」とも呼ばれた。後世の人々は彼を、劉宗元、欧陽秀、蘇軾とともに「歴代の四大文人」と呼んだ。彼は、将来の出来事に指針となる重要な意味を持つ多くの執筆理論を提唱しました。興味深い歴史の編集者と一緒に、韓愈の『池の尾状花序』について学んでみましょう。 徐志尚 韓愈(唐代) 風はありませんが、池の向こうに太陽が沈み、晴れた日には柳の花穂が自由に舞います。 透明な鏡に華奢な体を密着させたいのに、濡れて戻れない。 翻訳と注釈 翻訳 池の上には風はなく、沈む夕日の残光だけが漂っていました。空が晴れると、ポプラの花穂が再び池から飛び立ちました。 その細かさを頼りに鏡のような池を渡ろうとしたため、花穂はびしょ濡れになって帰れなくなってしまいました。 注記 慧:日光。 楊花:柳の花穂としても知られる。 スレンダー: 細身の体型を指します。凌:越える、超える。清境:池の水を指す。 濡れている:濡れている。 感謝 これは柳の花穂を描写した韓愈の詩です。風もなく、空は柳の花穂でいっぱいでした。詩人は沈む太陽の下、鏡のように澄んだ池のほとりに座り、柳の花穂が静かに水に落ちていく様子や、繊細な綿毛が水に少しずつ湿って二度と飛ばなくなる様子を静かに見ていました。このような観察と描写は、詩人が美しい春の風景に限りない関心を抱いていることを示しています。 この詩は、夕暮れの湖畔の空を埋め尽くす柳の花穂や、水面に落ちたポプラの花穂が水に濡れて再び舞い上がれなくなる様子を詳細に描写することで、作者の美しい自然の景色に対する喜びを表現しています。この作品は、風景描写から始まり、比喩表現へと移っていく、突き抜けた作品だといえる。 この詩は風景の描写から始まり、その後比喩に移ります。その意図は、ポプラの花穂が自らを映すために水面に飛び上がり、その後水に落ちて二度と飛ばなくなるというものです。もちろん、Changli もその 1 つです。 「澄んだ鏡に細い体を当てるには、濡れて帰れない」この文章は、池のほとりの柳の花を愛でる場面をとらえています。柳の花穂が舞い、晩春を彩ります。避けられない季節なのに、なぜ水の中で自分を見なければならないのでしょうか。それはすべての人にとって同じことです。私たちは天と地の間に生まれ、自分の運命を持っていますが、名誉、権力、富を通して自分を示すことを選択します。郭襄の『荘子』の注釈では、聖人は物事に焦点を合わせないと述べています。 「物事に向き合わなければ」自分は存在せず、自分が存在しなければ自分を見る必要もありません。 |
<<: 韓愈の「貴州の医師に南の字を使わせる」は風景描写を通して深い友情を表現している。
>>: 韓愈の『霍林街』は、自分の才能が評価されていないことに対する作者の憤りを表現している。
推薦する
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 王紫安』の原文の筋書きは何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
「中国のスタジオからの奇妙な物語」からの「王子安」の原文東昌[1]の有名な学者である王紫安は、畑に閉...
荀子と孟子は人間性の問題に関してどのように競い合ったのでしょうか?
如家を代表する人物といえば、まず孔子、次いで孟子、荀子が思い浮かびます。では、孟子と荀子の具体的な状...
「牡丹鑑賞」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
牡丹鑑賞王建(唐)この花には異なる名前と値段があり、その美しい開花は帝都に栄光をもたらします。ポリア...
「東坡韻を用いた水音・平山堂の歌」鑑賞、詩人方月は中原の復興を志す
方月(1199-1262)は南宋時代の詩人、作詞家であった。名は居山、号は袁山、号は秋牙、居田。彼は...
『紅楼夢』の物語の原型は何ですか?曹寅と康熙帝の関係は何でしたか?
中国の四大名作の中で、最も文学的価値が高いのは『紅楼夢』です。『紅楼夢』を研究する学問は「紅楼夢学」...
二人とも劉備の周囲の将軍だったのに、なぜ関羽と趙雲は一緒に戦うことがほとんどなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
Qiang Salang はどんなところですか?どのように発展したのでしょうか?
チャン族の歌や踊りのほとんどの種類の総称であるチャン・サランは、チャン族の文化の発展過程における統合...
恵州の伝統的なレンガ彫刻の模様は何ですか?
恵州のレンガ彫刻は、明清時代から現れた恵州の伝統的な住宅建築芸術の重要な部分です。では、恵州の伝統的...
『紅楼夢』で王希峰はどれくらいの財産を所有していますか?このお金はどこから来るのですか?
王希峰は映画の中で最も魅力的な女性キャラクターの一人です。以下、Interesting Histor...
『紅楼夢』の王夫人はなぜ一宏院を調査したかったのでしょうか?なぜビヘンは追い出されなかったのか?
宝玉の部屋の二等女中ビヘンは、秋文の次位である。以下は、Interesting Historyの編集...
中国の歴史上のすべての王朝の中で、最も強力な軍事戦闘力を持っていた王朝はどれですか?
今日の世界は概して平和ですが、特に平和の概念があまり強くなかった古代においては、どの国も多くの戦争を...
イ族の祭りである条公祭は、ナポのイ族の村の伝統的な祭りです。
3日間続く条公祭は、広西チワン族自治区ナポ県のイ族の村の伝統的な祭りです。驛公祭は、イ族が外国の侵略...
陸游は生涯を通じて梅の花と深い関わりを持っていました。では、陸游の著作の中での梅の花はどのようなものだったのでしょうか?
陸游は生涯を通じて梅の花と深い関わりを持っていた。同世代の詩人として、陸游は梅の花に特別な愛着を持っ...
本草綱目第8巻草本植物の原文の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
Hu Lei という名前はどこから来たのですか?琵琶との違いは何ですか?
「胡雷」という名前は、一般的には「演奏すると突然雷鳴が鳴る」と解釈されるためこの名前が付けられました...