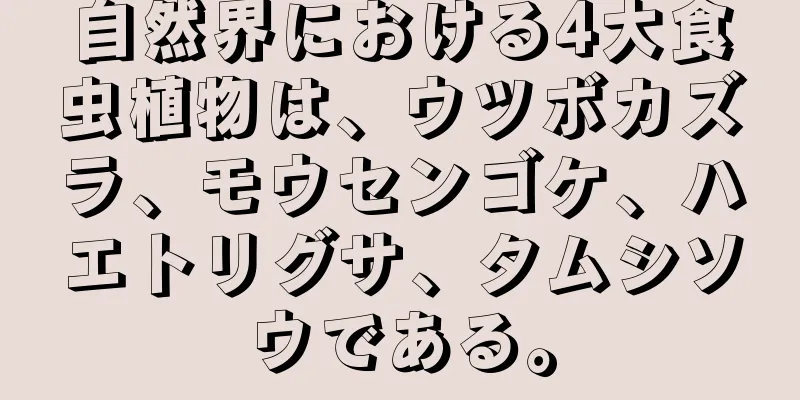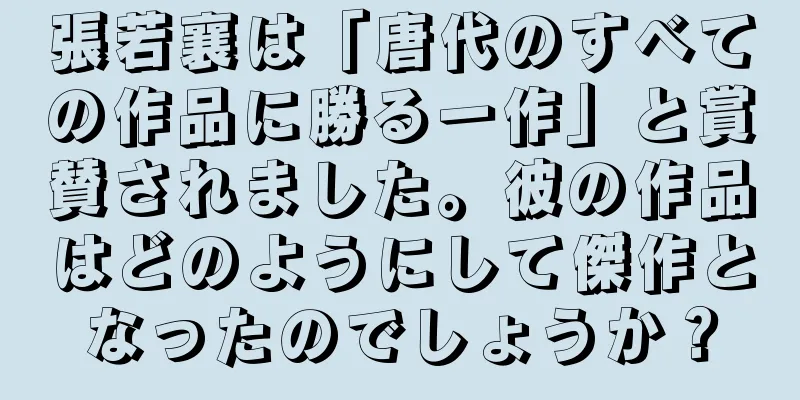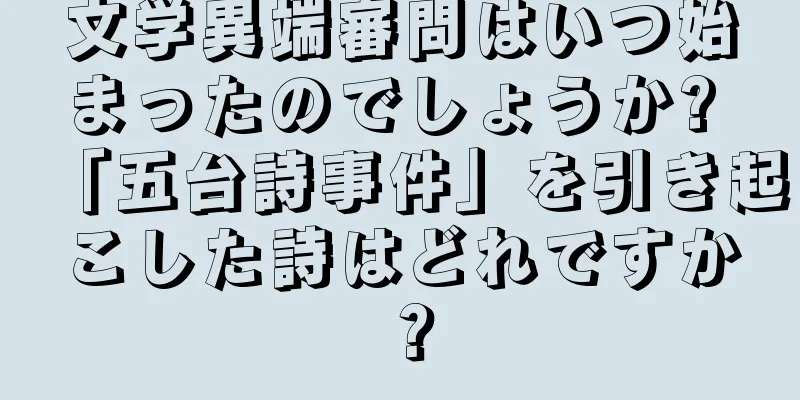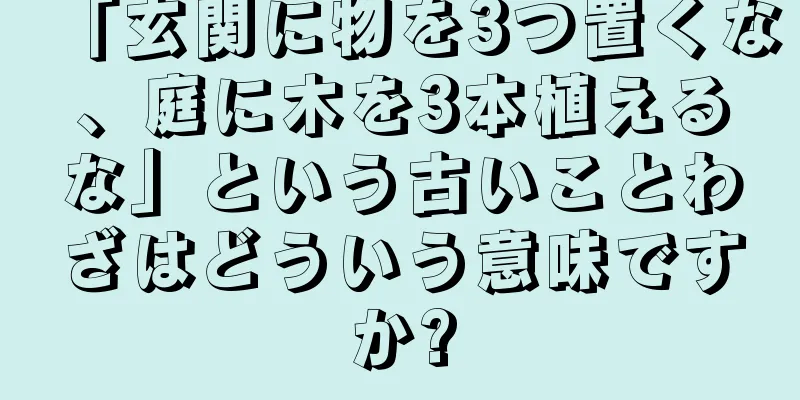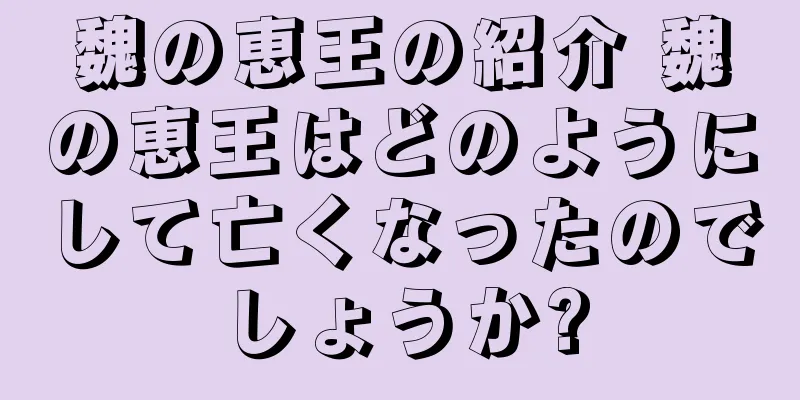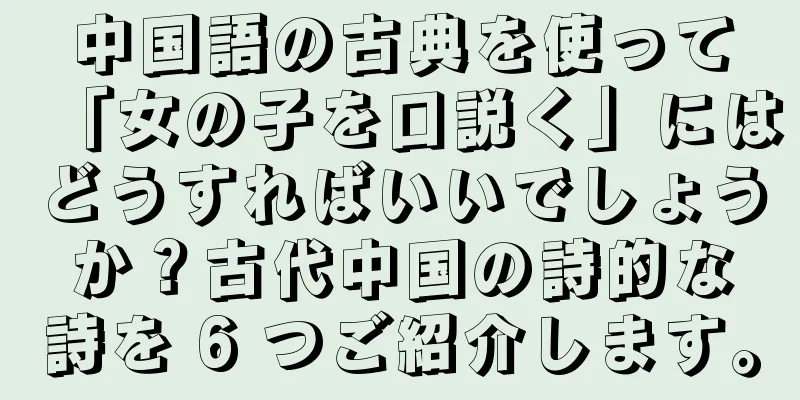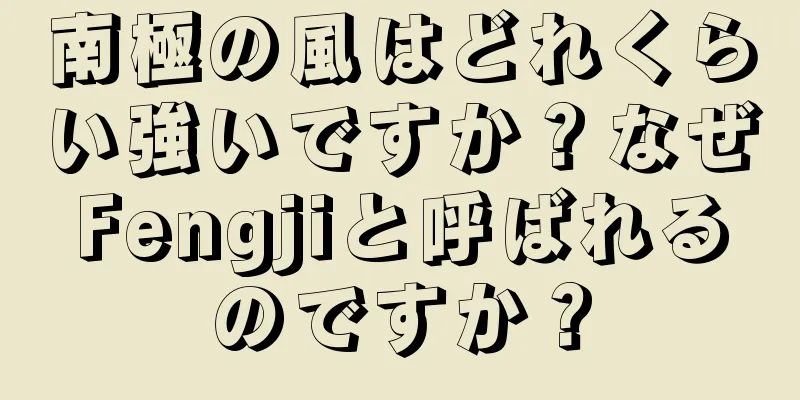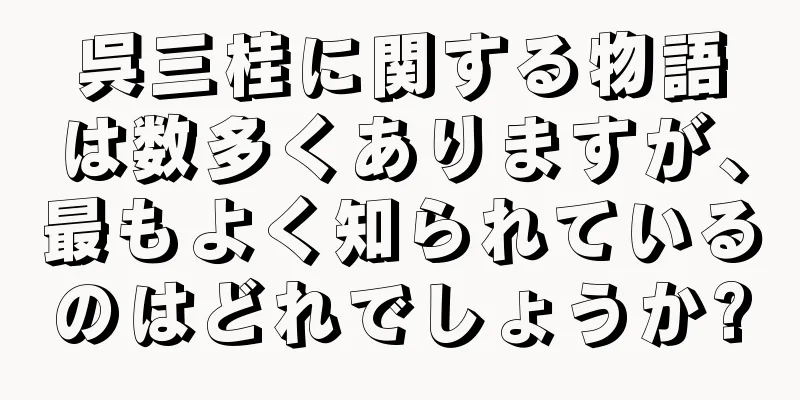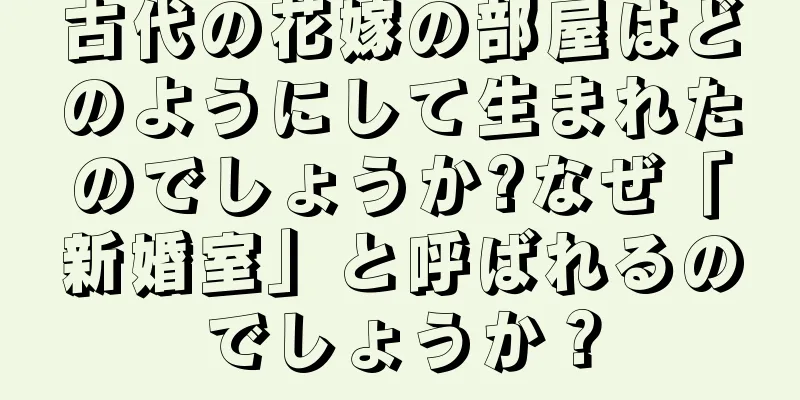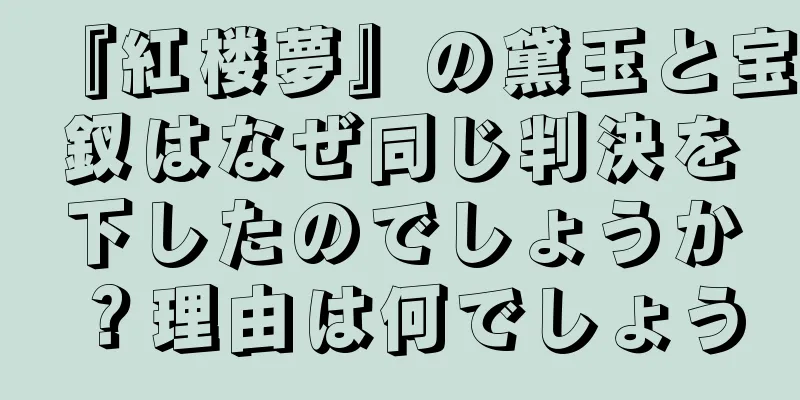廖世美の「ろうそくの明かりは赤く揺らめき、春の空は霧で満ちている」:詩全体が情景と雰囲気の完璧な組み合わせであり、言葉はシンプルだが感情は深い。
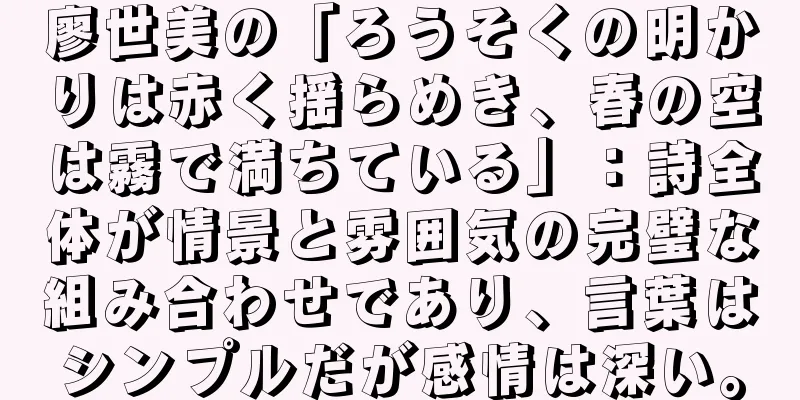
|
廖世梅は南北宋時代の変わり目に生きた詩人である。生涯の記録は残っていないが、安徽省東直県遼村の出身と伝えられている。現存する詩は 2 つ (3 つという説もある) あり、どちらも『唐宋詩選』に収められている。それでは、次の興味深い歴史編集者が廖時梅の「ろうそくの明かりが赤く揺らめく・春の霧の空」をお届けします。見てみましょう! 春の空は霞んでおり、雲の高い島の上にはペイントされた建物がそびえ立っています。サルスベリの木に登るのは最も感動的なことであり、詩を書く能力を自慢する素晴らしい方法です。老年期のあなたを哀しみながら、赤い柵のところで語り合った日々を今でも思い出します。辺境の雁のことは尋ね難く、岸辺の柳は果てしなく、私はあなたのことを心配しています。 年月はあっという間に過ぎ去り、昔流れていた水はどこへ行ったのだろう。なぜ私は沈む夕日に心を痛め、平原を見ると悲しくなるのだろう。夕方、波の音に雨が降る。船が静かに野原を渡っている。川にはいくつかの峰があり、地平線まで香りのよい草が広がり、霧の中には高麗人参の木が茂っている。 【感謝】 過去を回想し、風景を使って感情を表現することで詩人の気持ちを表現した詩です。最初の部分では寺院の壮大さと荘厳さが説明されています。 「札札」という2行は「劇的で雲の中にそびえ立つ」というイメージで、雲の上にそびえ立ち雄大な沙竹を見下ろす、雄大で高い富雲塔を表現しています。 「百日紅」の二行は、唐代の詩人杜牧が浮雲楼に登って眺める場面を詩人が連想したことを描写している。浮雲楼への賛美に杜牧は大いに感激し、素晴らしい詩を書いた。 「憂鬱」という一文は、詩人が晩年に塔を訪れた時のことを表現している。彼は杜牧よりも感情的であり、憂鬱と憧れを払拭するのは難しかった。 「あの日を思い出せ」の4行は、恋しさと愛情を表現しています。彼らはかつて赤い柵に寄りかかって一緒に話をしました。別れた後、砂漠を飛ぶ野生のガチョウしか見えず、恋人たちの行方を尋ねることは困難でした。川岸の柳は果てしなく伸び、花穂は舞い、別れの悲しみを引き起こしました。詩の後半では、塔を登りながら詩人が考えたことが述べられています。 「促す」の2行は、時の流れを表現しています。かつて手すりに寄りかかって話していた階下の水は、今ではどこに流れているのでしょうか。「悲痛な」の2行は、塔に登ることの憂鬱さと、ありふれた光景が人を悲しくさせることを強調しています。なぜ悲しい気持ちになるには、沈む夕日を見つめなければならないのでしょうか。「遅晴」の5行は、それぞれ情景を描写し、情景で感情を表現し、塔に登って月を眺めるゆったりとした気分を伝えています。詩全体は、シンプルな言葉ながらも深い感情で、場面と雰囲気を完璧に組み合わせています。 |
<<: 呂斌老の「不貞不運:春節の夜、遊郭」:歌詞に込められた愛の苦さと甘さが鮮明に記憶に残る
>>: 王璋の『典江春心月圓圓』:この詩の風景は澄んでいて美しく、広大で、風景の描写は感情を表現しています。
推薦する
「水蓮花:春が満ち、柱が水位を増す」という詩を書いた詩人は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】春になると水位が上昇します。風が吹く岸辺には、香り高い草やガチョウが青々と茂っています...
楊炯著『入軍』は、知識人が辺境に貢献したいという崇高な野心を示している。
楊璋(霊明とも呼ばれる)は唐代の大臣、作家であり、王毗、呂昭凌、羅斌王とともに「唐代初期四偉人」の一...
紅少年と鉄扇公主の関係はどのようなものですか?なぜ紅坊は唐僧を捕らえ、牛魔王だけを招待したのか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が「西遊記」...
拓跋鈞には何人の兄弟姉妹がいますか?拓跋鈞の兄弟姉妹は誰ですか?
拓跋濤(440年 - 465年)は、太武帝拓跋濤の孫で、景武帝拓跋濤の長男であり、母は南北朝時代の北...
古典文学の傑作『太平天国』:人材資源編第39巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
古典文学の傑作『太平天国』:陸軍省第87巻
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
仰韶文明はどのようにして誕生したのでしょうか?仰韶文明の起源の詳細な説明
仰韶文化は黄河流域で最も影響力のある原始文化です。では、この文化はどのようにして誕生したのでしょうか...
『西遊記』で孫悟空はなぜ天啓王を討伐する前に陳家村を去ったのですか?
霊感王は『西遊記』に登場する妖怪で、本来の姿は金魚の精霊でした。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹...
『清平月:后秋其端』の執筆背景は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】コオロギの鳴き声は悲しげで、西岸では人々が話し合っている。月は絹糸のように沙平河の上に...
蔣子牙、諸葛亮、劉伯温の中で誰がより強いでしょうか?彼らの主人は誰ですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、姜子牙、諸葛亮、劉伯温についての記事をお届...
ジャッジ・ディー第38話:手紙が誤って罠にかけられ、役所に入ると刑務所に送られる
『狄公安』は、『武則天四奇』、『狄良公全伝』とも呼ばれ、清代末期の長編探偵小説である。作者名は不明で...
『紅楼夢』における賈徴のイメージとは?彼は本当にあまりに細かいことにこだわりすぎているのでしょうか?
賈家は仲順王を怒らせ、また一連の過去の事件により略奪を受けた。小説『紅楼夢』のストーリーが展開するに...
当時、唐王朝は最盛期の終わりを迎えていました。安禄山の反乱軍はどのようにして長安に侵入したのでしょうか?
唐の玄宗皇帝李隆基の晩年で最も有名なものが二つあります。一つは彼と楊貴妃の物語、もう一つは安史の乱で...
「清平楽年年学里」の原文翻訳と鑑賞
清平楽·年年雪麗李清昭(宋代)毎年雪の中、梅の花に酔いしれることが多いです。善意もなく梅の花を摘み取...
崔有夫(読み方:イースン)は、皇太子の客人である孝公綿公の息子であった。
崔有夫は、雅号を易孫といい、皇太子の客である孝敏公の息子であった。彼は儀式と法律を自分の家とみなし、...