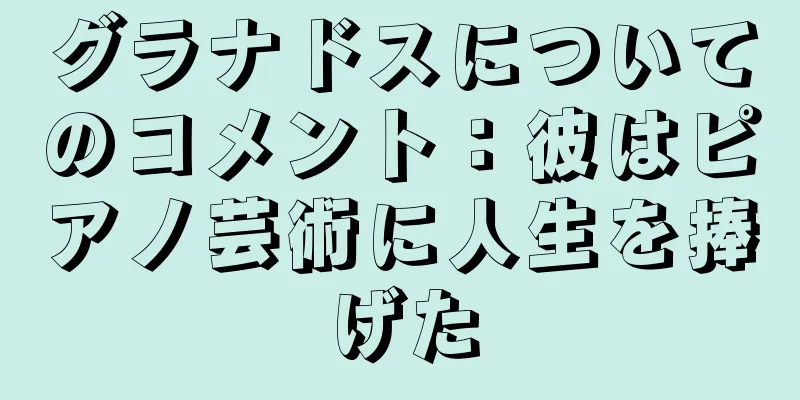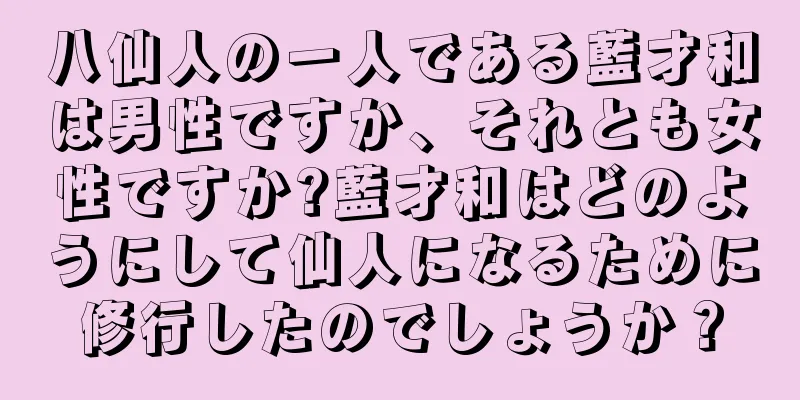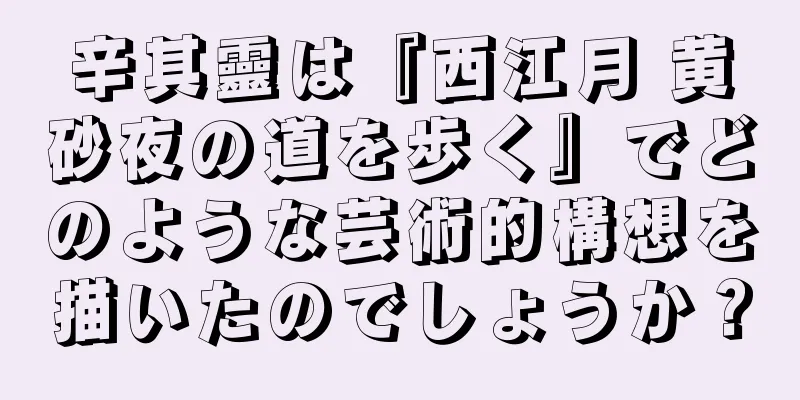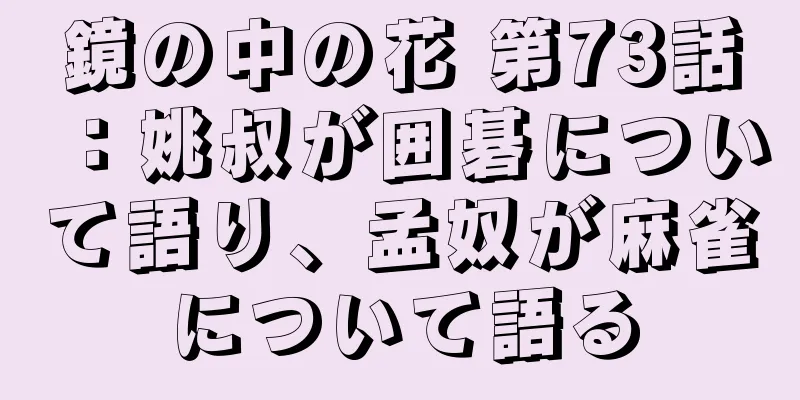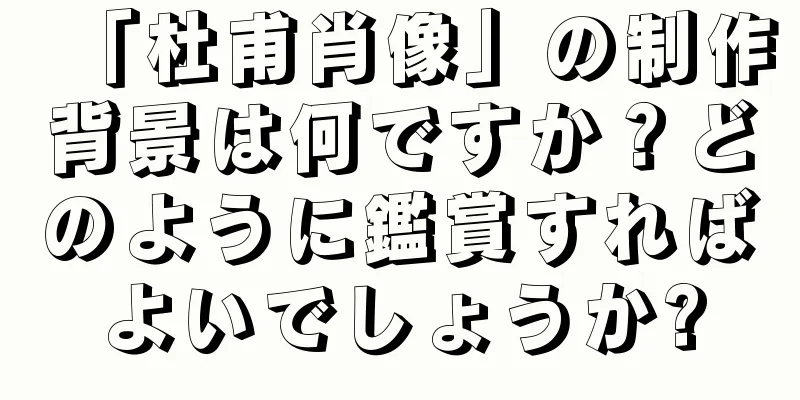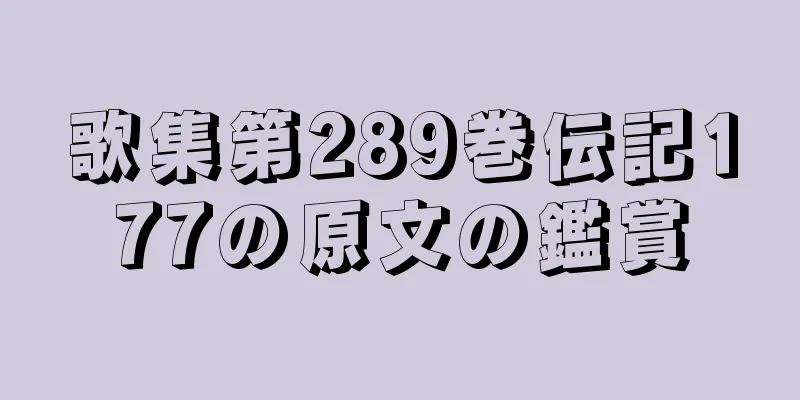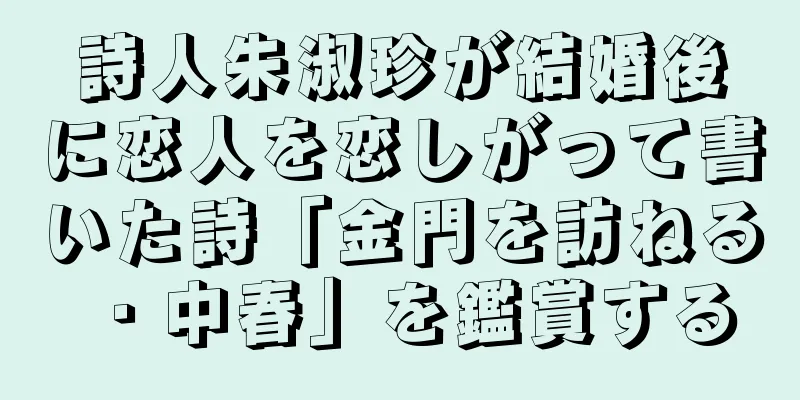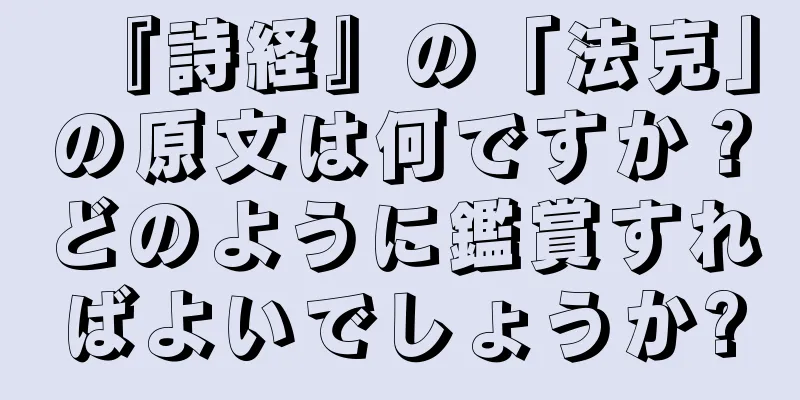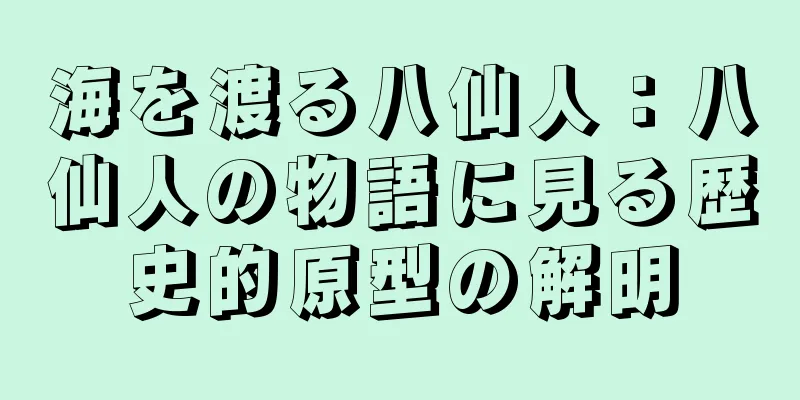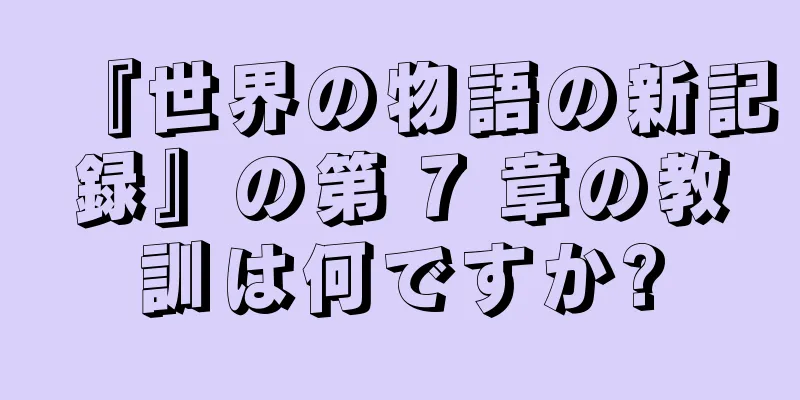朱一尊の有名な詩句を鑑賞する:沐湖の蓮の葉は貨幣よりも小さく、柳の木は船の邪魔にならない
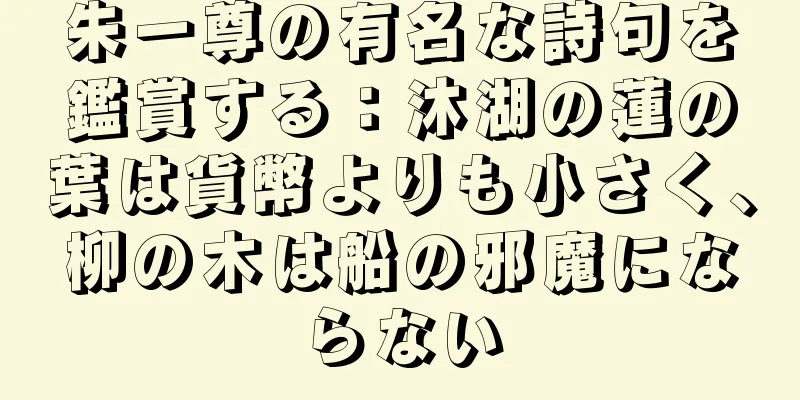
|
朱一尊(1629年10月7日 - 1709年11月14日)、字は西昌、別名は朱超、玉芳、小昌路漁師、金峰閣師。浙江秀水(現在の浙江省嘉興市)の人。清朝時代の詩人、学者、愛書家。朱一尊の作詞スタイルは優雅で、「詩渓流」の創始者です。陳衛松とともに「朱辰」と呼ばれています。王時珍とともに南北の二大詩人(南の朱、北の王)として知られています。 『百書亭集』80巻、『日夏九文』42巻、『精易考』300巻を著し、『明詩集』100巻、『慈集』36巻(王森が補筆)を撰述した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、朱一尊の『元陽湖蔵王百選二』をお届けしますので、見てみましょう! 沐湖の蓮の葉は硬貨よりも小さく、柳の木はたくさんあるが船の邪魔にはならない。 川の両岸には雨が降った後に新芽が生え、夕日を浴びて溝の水が田んぼに響き渡る。 屋根の上で鳩が鳴き、穀物雨の始まりを告げています。衡塘を歩く少女たちは、家へ帰るためにボートを漕いでいます。 桃の花が散ると蚕は一緒に水浴びをし、竹の子が育つとツバメがやって来ます。 【注意事項】 [1] 元陽湖:南湖とも呼ばれ、浙江省嘉興市の南3マイルに位置しています。漕ぎ歌:漕ぎながら歌う歌。 [2] 穆湖:穆渓とも呼ばれ、嘉興市の北東に位置する。 [3] 横たわる柳:枝が斜めに水面に横たわっている柳の木。 [4] 鳩の鳴き声は晴れた日を意味します。 「碧牙」には「鳩は曇りの時は伴侶を遠ざけ、晴れの時は呼び寄せる」とある。古宇:清明節句の後の節気。カイ:雨が降った後は空が晴れています。 [5] 衡塘:現在の江蘇省蘇州の南西部に位置する地名。東に分岐する川にちなんで名付けられた。陸游の「衡堂」:「衡堂には南北の堤防と東西の堤防があり、棒で水に浮かぶのが楽しい。」 ボートを漕ぐ:ボートを漕ぐ。 [6] カイコの入浴:カイコの飼育と選抜の方法。蚕の卵を塩水や山菜の花、ニラの花、白豆の花などから作った液に浸し、弱いものを除去し、強いものを残し、種子の選抜を行います。 【感謝】 生まれたばかりの蓮の葉は銅銭よりも小さく、水面を撫でるしだれ柳は船の航行を妨げず、詩人に斬新な感覚を与え、雨上がりの川の両岸に新芽が生え、夕日の下で溝の水がゴボゴボと音を立てている様子は、詩人に限りない生命力を感じさせます。この詩は、穆湖の美しい風景を描写しているだけでなく、詩人が美しい田舎に対して抱く心からの愛情も表しています。二番目の詩は蘇州の衡塘地域の風習を描写しています。最初の文は季節を指し、天気を説明しています。穀物の雨の季節には、キジバトが楽しそうに鳴き、雨が止んで空が晴れ、人々はリラックスして幸せな気分になります。最後の3文は詩人が見たものを表現している。「衡堂の放浪娘たちが船を漕いで家に帰る」。桃の花が散り、蚕が種を保存するために水浴びをし、竹の子が急速に成長し、春が戻ってツバメが飛び交うなど、ゆったりと活気のある情景が描かれている。田園の特色に富み、活気に満ちている。 |
>>: 呉文英の詩の有名な一節を鑑賞する:しだれ柳は私の裾を絡めない。長いのは、ボートに縛られている
推薦する
裏社会の階級ってどんな感じですか?地獄の王のリーダーは誰ですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が裏社会階級についての記事をお届けします。ぜひ...
黄元潔の伝記:明代末期から清代初期の美しい詩人、黄元潔の生涯
黄元潔(号:傑玲)は、明代末期から清代初期にかけて浙江省嘉興市に生まれた人物である。文献上、黄湘(象...
「初春に農夫と出会う」の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
春最初の農夫劉宗元(唐代)楚南部では春が早く訪れ、残寒はすでに繁栄をもたらしています。畑は油で覆われ...
海の女神、媽祖の紹介:媽祖はどのようにして亡くなったのか?歴史上、媽祖という人物は本当に存在するのでしょうか?
媽祖は中国原産の女神であり、媽祖信仰は北宋時代に始まりました。この神は、媽祖という称号のほかに、天后...
龍が頭を上げる2月2日になぜ髪を切らなければならないのでしょうか?
ほとんどの中国人は「2月2日、龍が頭を上げる」という風習を知っています。旧暦の2月2日頃は二十四節気...
「ハイビスカス亭」をどう理解したらいいのでしょうか?創作の背景は何ですか?
ハイビスカスパビリオン劉宗元(唐代)新しいパビリオンからは赤い柵が見渡せ、美しい木々には蓮の花が...
清風図第2章:大理中央メディアが強氏を花嫁として再婚
『清風帖』は清代の溥林が書いた長編民俗小説です。この本は32章から成り、物語の展開に応じて3部に分け...
『紅楼夢』で平児が殴られた後、賈おばあさんはなぜ胡博を訪ねさせたのですか?
平児は王希峰の侍女であり、賈廉の側室であった。 Interesting Historyの編集者が関連...
三英雄五勇士第68章:華帝と戦昭が結婚し、二人の英雄は景秀に運命を占わせる
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
李白の詩「龍山の勇士陳安を代表して司馬将軍が歌った歌」の本来の意味を鑑賞する
古代詩:龍山の戦士陳安に捧げる司馬将軍の歌時代: 唐代著者: 李白荒々しい風が古代の月を吹き、密かに...
西遊記続編第28章:二つの気を貫けば寒さも暑さもなく、陰陽に落ちれば生死がある
明代の神話小説『続西遊記』は、『西遊記』の3大続編のうちの1つです。 (他の2冊は『続西遊記』と『補...
水滸伝では、王倫は林冲を受け入れることを嫌がり、楊志を涼山に迎え入れようとしました。王倫は何を思っていたのでしょうか?
王倫は梁山泊の初代指導者であり、「白衣の学者」として知られていました。知らなくても大丈夫です。Int...
『易軒志』第12巻の主な内容は何ですか?
リン・ジインデ南江の出身の林季は、若いころに都に来た。蔡州に着くと、ある宿に泊まった。背中の股間に何...
なぜ鄧然達はこれほど多くの道教の仲間を死に追いやったのでしょうか?真実とは何でしょうか?
『封神演義』では、鄧然師匠が頻繁に登場し、その実力は並外れており、十二金仙をはるかに上回っています。...
三国志演義 第92章 趙子龍が5人の将軍を殺し、諸葛亮が3つの都市を占領
『三国志演義』は、『三国志演義』とも呼ばれ、正式名称は『三国志演義』で、元代末期から明代初期にかけて...