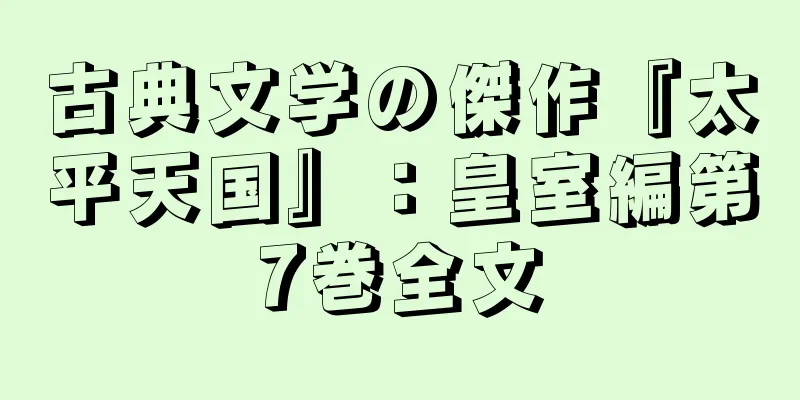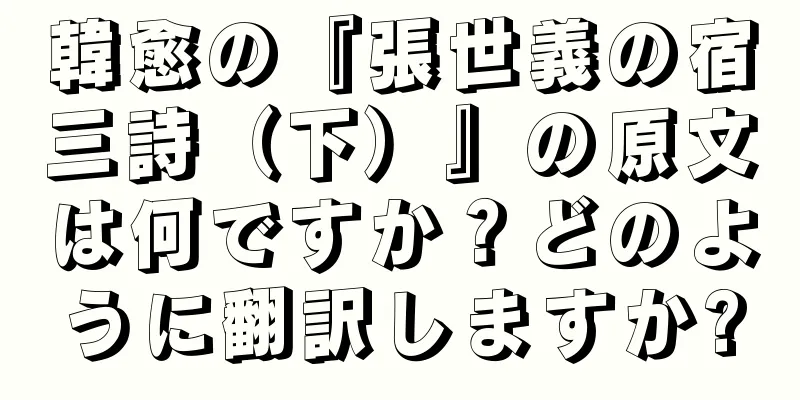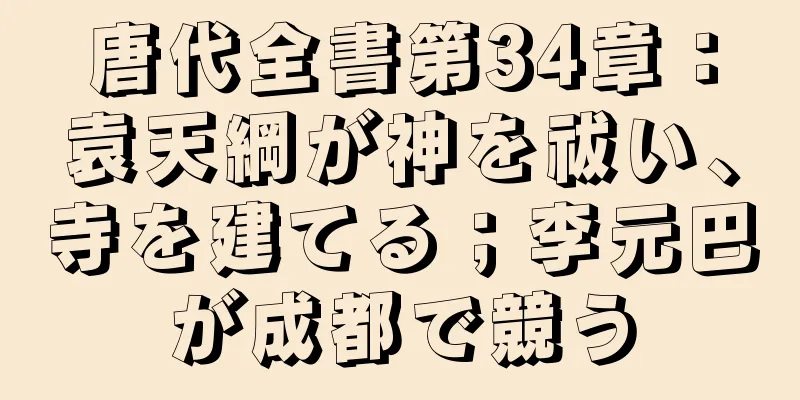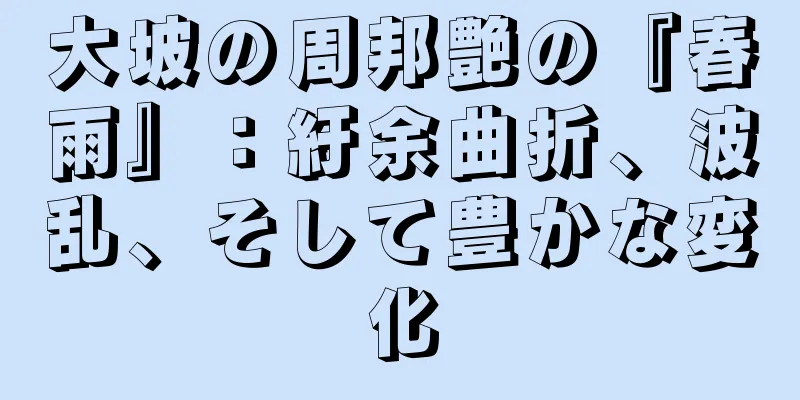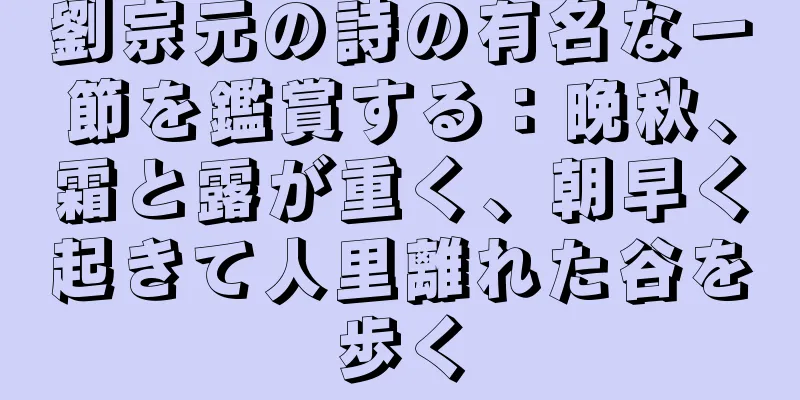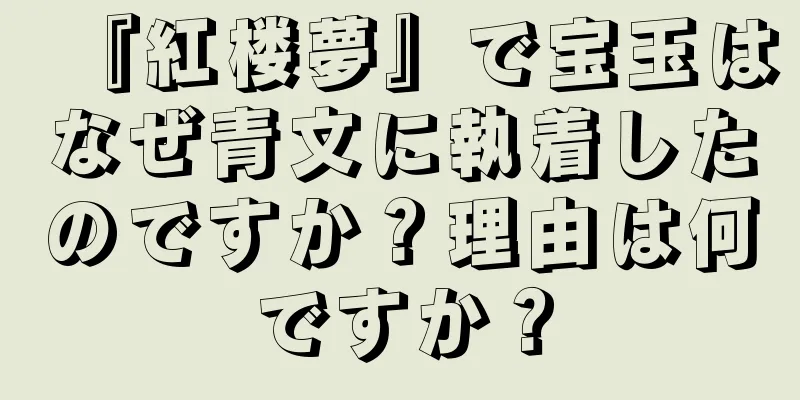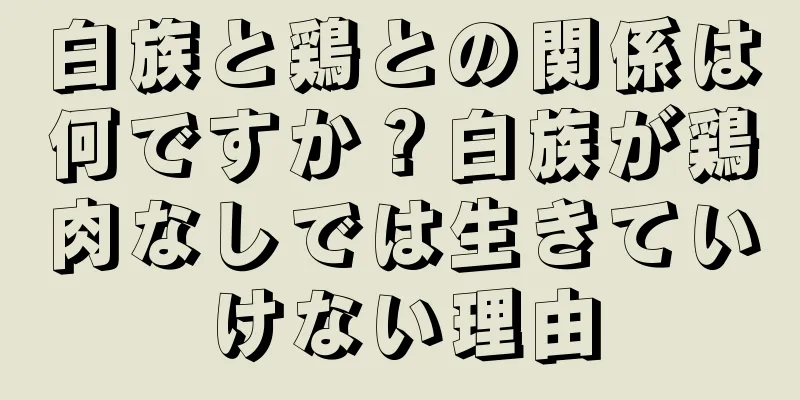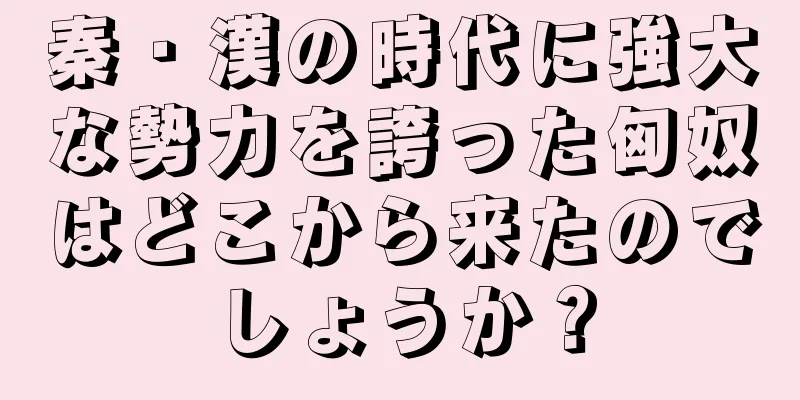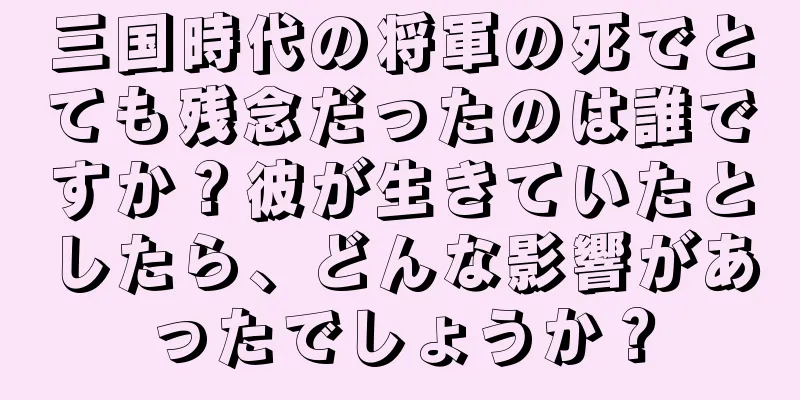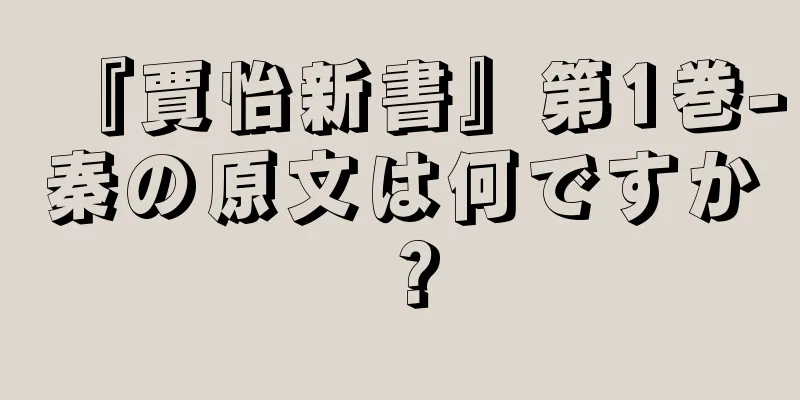古典文学の傑作『太平天国』:礼節編第27巻全文
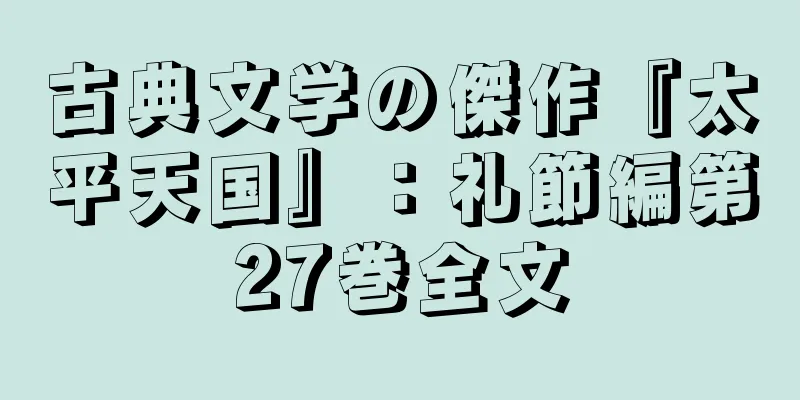
|
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂したもので、太平興国二年(977年)3月に始まり、太平興国八年(983年)10月に完成しました。 『太平毓蘭』は、55部550の分野に分かれ、1,000巻にまとめられた各種書籍のコレクションであるため、もともと『太平宗録』と名付けられていましたが、書籍が完成した後、宋の太宗皇帝が毎日3巻を読み、1年で全巻を読み終えたため、『太平毓蘭』に改名されました。本書は天・地・人・事・物の順に55部に分かれており、古代から現代まであらゆる事象を網羅していると言えます。この本には1000冊以上の古書が引用されており、宋代以前の文献資料も多数保存されている。しかし、そのうち7、8冊は失われており、そのことがこの本の貴重性をさらに高め、中国伝統文化の貴重な遺産となっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が、礼儀作法部門の詳細な紹介をお届けします、第27巻、見てみましょう! ○杖と靴 『礼記 喪服』には「棍棒は竹で作られている」とある。杖は桐材で作られています。全員が心を一つにして、エネルギーを最大限に活用します。スティックとは何ですか?それはタイトルです。称号でなければ棒の理由は何でしょう?それは主人の負担です。棒の持ち主でない人がなぜ手伝わなければならないのでしょうか?なぜ少年は杖を使わないのでしょうか?病気にならないからです。女性はなぜ杖を使わないのでしょうか?病気にならないからです。 斉の袈裟と草鞋を切るのは草鞋だとも言われています。君主に仕える役人や大臣は、草履を縛るために縄を使います。その縄は上質な木で作られています。薄くて悲しげなスカートとまばらなサンダルは、羅快家のそれと同じです。 『礼記 喪服の注意』には、禹族の場合、室内に杖を持ち込むことは許されず、葬儀の場合、ホールに杖を持ち込むことは許されないとある。 (鄭玄のメモにはこうある。年を取るほど、男性を尊敬するようになる。)女性が主人として杖をついていないのは、叔母が夫の杖をついているからだ。(叔母は女性を嫌っているわけではない。)母親は長男のために杖を切る。(男性の服を着るのが嫌なら、竹の杖を使うべきだ。母親が長男に着せる服は、自分の服より重要ではいけない。)女性と子供たちは家の中にいて、両親に仕える。葬儀の責任者が杖を使わない場合は、彼の息子の一人が杖を使えます。 (結婚している女の子も男の子です。男の子がいないなら、彼女が家長になります。彼女が杖を使わないなら、長女が杖で打たれます。彼女が20歳になると、結婚が許されます。彼女が20歳になると、男になり、杖を使うのは大人として正しいことです。) 『喪服の手記』には、平民の子息が杖をついて王位に就くことはできないとも記されている。 (息子にはふさわしくない。朝晩泣く立場である。)父親が妾の息子の葬儀を担当しない場合は、孫が杖をついて王位に就くことができる。 (祖父が孫を嫌わなければ、孫は神の力を得る。)父がまだ生きている間は、側室の息子は父と結婚し、杖を持って王位に就くことができる。 (叔父が側室の葬儀を執り行わない場合は、息子が正義を求めることができるでしょう。) 「雑記第二部」にもこう書いてある。「古代では、高貴な者も卑しい者も棍棒で殴られた。」舒孫武と舒超の治世中、車輪を軸に引っ張るために杖を使う車輪使いが見られ、そのため、その人物には称号が与えられ、後に杖が与えられた。 『葬式大録』には、高官の葬儀では、三日間の葬儀の後、主人、女主人、家の長老たちが全員杖を使うとも記されている。上級官吏が君主の命を受けるときは、杖を抜かなければならない。上級官吏が君主の命を受けるときは、杖をしまわなければならない。妻は妻の命令で杖を外し、世俗の女性の命令でその杖を他の人にあげました。 (王様が高官に杖を外すように命じる場合、これは高官の息子を指します。また、「夫」という言葉は、実際には高官の両親の葬儀を指します。人に杖を与えることは、それを持つように頼むのと同じです。)学者の葬儀では、棺を2日間置き、3日目に朝の儀式を行います。家の主人は杖を使用し、女性は皆杖を使用します。王と夫人の命令に関しては、彼は医者のようです。上級官吏または世襲婦人の命令は上級官吏の命令として扱われる。 (二日間埋葬される学者は下級官吏である。学者の作法によれば、死は過去の日、生は未来の日とみなされる。この二日間は死者のための三日間ともみなされる。女性はすべて鞭打ちにされ、これは君主の娘または子供を側室に許す女主人を指す。)息子はすべて鞭打ちにされ、王位に就くことは許されない。 (先生は一般の息子全員のことを言っていました。彼らが即位しなかった場合は、杖を抜かれるのと同じ罰でした。)役人や学者が葬儀で悲しむときは、杖で打たれ、棺で悲しむときは、杖で縛られました。 (葬儀で泣くことを「忌吐」といい、棺の前で泣くことを「忌后」という。官吏や学者の子は父を敬い、父と近いので、葬儀で棒を使って泣くことができる。皇帝や王子の子は父を敬い、父は遠いので、棒を寺の門に持ち込むことはできない。)棒を捨てる場合は、折って仙人に投げなさい。 (杖は最も尊敬される人の死を悼むために使用され、その功績により他の人々から賞賛される。) 「葬儀について尋ねる」ということは、「棒とは何ですか?」と言っています。時間は3年間、病気になり、父親がまだ生きていることを意味します。そして、道徳は天国から来ていません。それは地球から来ていません。父親がまだ生きているときは棒を使用していません。 『喪服四則』にも「棒とは何か?それは称号である」とある。 3日目には息子に杖が与えられ、5日目には役人に杖が与えられ、7日目には学者に杖が与えられます。あるものは主病を患っていると言われ、他のものは副病を患っていると言われています。杖を使わない女性や男の子は病気になりません。 「百胡同」はこう言っています。「なぜ竹や桐を杖として使うのか?それは、それが名前の由来だからだ。」竹はしわを意味し、桐は痛みを意味します。お父さんは竹を使い、お母さんは桐を使います。竹は陽で、桐は陰です。竹は切って使うので、その性質は陽です。 「韓子」曰く:儒教徒は3年間喪に服し、杖はひどく傷む。世界の支配者たちはそれを孝行とみなし、彼を尊敬した。 ○女性の髪の毛 『礼記』には、喪服について次のように記されている。夫の家族でまだ子供である女の子は、布製のヘッドバンド、矢形のヘアピン、お団子を頭につけ、3年間喪に服すべきである。宗は髷を結ぶという意味です。結ぶとは頭と端を結ぶことです。建吉は竹の切れ端を意味します。髷は髷をかぶるという意味です。男性が麻で髪を結ぶのと同じように、髷も麻でできています。麻を使って首から額まで髷を結び、ベールのように巻き付けます。『小吉』では、男性は帽子をかぶり、女性はヘアピンをつけ、男性は髷をかぶり、女性は髷をかぶると言われています。女性は同じ服、同じ服を着ると言われています。 また、女の子が男性と結婚するときは、両親が彼女に仕え、女性が叔父や叔母と結婚するときは、ヘアピンをつけず、髪を束ねるべきではないとも言われています。少女はついに泣き出し、頭につけていた簪を折って布で結びました。頭の付いたヘアピンが好きな人は、頭が付いていることが嫌いだと言われています。悪いヘアピンはコームヘアピンです。簪の頭を折るというのは、縁起のいい簪の頭を折るという意味です。縁起の良い簪は象牙の簪です。 『礼記譚公尚』には、南宮宇の妻の叔母が亡くなったとき、孔子は彼女に「甘やかし過ぎてはいけない、広すぎてはいけない」と教えたとある。(「诲」は教える、「尔」はあなた、「纵纵」は高すぎる、「阜乎」は広すぎる、「尔」は鲐を表す単語。) 『譚公尚』にも、魯の女が髪を束ね、喪服を着ていたため、壇上の魚に負けたと書かれている。 (葬儀の際には、家族全員が髪を束ねて互いに弔意を表します。生え際のない髪を「おだんご」といいます。) 『礼記外章』にはこう記されている。「喪に服した女性は髪を束ねる。」 (昔の人はお団子をとても大切にしていました。男性はお祝いの席でお団子を下ろして髪を見せ、簪と冠を着けていました。)紐のないお団子を「お団子」といいます。 (魯の女性が勝興の戦いで被害に遭ったとき、喪帽をかぶらずに、おだんごを出して哀悼の意を表した。)麻饅頭もあった。(女性が親の死に遭ったとき、麻を使っておだんごをまとめ、兄弟の前でもおだんごをまとめた。)布饅頭もあった。 (七夕以下の着用者の髪は布で束ねられています。)髽はほどけた髪の名称です。 (なくなってしまったので、花饅頭の形をした縦饅頭になっています。) 『左伝・襄公』はこう言っています。襄和は魯を救出するためにやって来て朱を侵略したが、胡岱に敗れた。国中の喪に服している人々は皆、髪を束ねています。魯の人々が髪を束ねるようになったのはその頃でした。 (髽は髪を束ねるという意味。喪服を用意できないため、忌明けに髽を着ることが多い。) 「Guangya」曰く:鞘は帺と呼ばれる。 (発音禁止) 『衛氏春秋』には、諸葛亮が司馬玄望を挑発して戦わせたが、女たちの警告が王を怒らせたとある。 ○ルー 『周書 天官 宮官』にはこう記されている:王宮の命令と指揮を担当する。大規模な葬儀の場合は、遺族の親族や身分を区別するために小屋が与えられます。 (鄭玄のメモにはこうある。「露社は白い部屋である。身近で高貴な者は伊露に住み、身分の低い者は白い部屋に住む。」) 『礼記』には、「喪中は喪服を着用し、下屋に住み、藁枕で眠るべきだ」とある。 (馬容はこう語った。「峠の北端、東の壁の下、西を向いて木に寄りかかって建てられている。」) 『礼記雑記』にはこう記されている。「高官たちは小屋に住み、学者たちは白塗りの部屋に住んでいる。」 『葬送大記』には、親を喪うときは、絵も描かずに小屋に住み、藁と木の枕で眠る、とも記されている。葬式以外のことについては話さないでください。王は小屋と宮殿を建て、大臣や学者たちは王のために衣服を着る。 (宮殿とは囲い地のこと)埋葬後、柱やまぐさが小屋の上に塗りつぶされ、目立たなくなった。王、大臣、学者たちは皆宮殿に配属されました。 (明らかな存在の前にいなければ、あなたは見られないでしょう。) また、葬式のことを尋ねると、墓が完成してから家に帰り、遠くにいる親族を悼むため、家に入る勇気もなく小屋に住むとも言われています。 『百胡同』にはこう記されている。「親を悼むときは、中央の門の外、東の壁の下、北に扉がある小屋に住むべきだ。」 また、「女性は小屋に住むべきではない」とも言われています。皇帝は7日間、王子は5日間、大臣は3日間喪に服し、門の外の東の壁沿いの小屋に住みます。 王粛の『喪服要項』には、魯の艾公が父を埋葬したとある。孔子は尋ねた。「葦小屋を建てますか?」艾公は答えた。「葦小屋は私の大叔父が建てたものです。私の大叔父は逃げて、顧公が亡くなったと聞きました。葬儀に出席するために戻ってきて、遺体を見せるために葦小屋を建てました。私の父は太伯公に対して罪を犯していません。なぜ私たちがこれを必要とするのですか?」 『孝子伝』には、王林は汝南市上菜の出身であると記されている。彼は10歳で両親を亡くし、弟のジはまだ7歳でした。二人の兄弟は泣き悲しみに暮れました。彼は墓の横に小屋を建て、自由に出入りすることはなかった。 (「小武」が見えます。) ○重い 『儀式の書:学者の葬儀の儀式』には、「重いので、木を彫るか、ノミで削って作る必要がある」と書かれています。滇人は中庭に重りを置き、それを南に 1 つずつ、合計 3 つの部分に分けました。夏珠は売店で残った米を取って、西の壁の下の二つの鍋に入れました。カバーは薄い布でできており、長い時間を経てハンマーで叩かれ、重いものが掛けられます。マットは葦で作られており、左の襟が北を向いています。ベルトは彼を祝福するために使用され、後ろで結ばれます。碑文を取って高い位置に置いていただきたいと思います。 (鄭玄曰く、「鍾」は木という意味。何かを掛けたいときは「鍾」という。簪を掛ける穴は、切ったり、彫ったり、鑿で作ったりして作る。学者の「鍾」の木の長さは3フィート。) 『祭祀書雑記』には、「重たいものを片付けた後、埋葬すべきである」とある。 (必要な場所に埋めてください。) 『礼記外篇』にはこうある。「最も重要なことは、埋葬前に主人の身代わりとして用いることであり、生きている主人を扱うのと同じであり、木製の主人を作るのは耐えられないことである。」 (精神を保つために使われます。)中庭に重りを置き、瓦鉢を吊るします。療養用の米を風呂に入れて、お粥にして重くし、葦の敷物をかぶせます。 (幽霊や神様もそれに応じて食べたり飲んだりします。)亡くなった人への最初の供物は米だけで、キビやモロコシは使われませんでした。 (下の真ん中にあるのは、生きていたときと同じキビとモロコシです。)殷の人々が権力を握った後、彼らは重りを結び合わせて寺院の梁に吊るしました。親族全員が亡くなった後、高祖帝の寺院に行き、彼を埋葬してください。周の人々は、人を埋葬する際には、棺を重い物と一緒に横に置き、寺院の外に置き、階段の間に埋葬して、最終的な決定を下しました。 ○邪悪の門(アタッチメント) 南史の孔林之はこう言っている。「魔門のヒノキ飾りは儀式から外れたものではなく、末王朝に始まり、習慣となった。庶民の葬式はたいてい近所で行われる。そのたびに数万ドルの費用がかかり、人々のお金と体力を無駄にしているが、何の価値もない。貧しい人は疲れ果ててしまう。家が鐘を吊るすほど美しいとしても、彼らはすべてのお金を使い果たしてしまう。これが儀式を伴う埋葬の意味なのか?魔門の習慣をやめる時が来た。」 王粛の『喪服要項』には、魯の艾公が父を埋葬したとある。孔子は「帥門を建てるべきか?」と尋ねました。艾公は「帥門は禹の由来である。禹は洪水を治めたので、その功績を記録するために門や家に印を付けた。私の父には功績がなかったのに、なぜこれを使うのか?」と答えました。 魏洪と蔡墨堅は、邪門について尋ねた。「父が生きていて母が亡くなったとき、邪門を立てるべきでしょうか?」彼はまた尋ねた。「父に別れを告げたとき、私たちは邪門を立てただけでした。私はまだ父にうんざりしているので疑問を抱いています。今は、父の正門の中に、父のためにもう一つの邪門を立てました。一家には二つの門があります。名前と意味から言えば、門は父のものです。今、あなたはもう一つの門を立てました。これは聖人の教えに沿っていますか?礼儀に反するなら、言及すべきではありません。だから私はあなたの助言を求めました。」蔡は答えた。「礼儀によると、死後初めて犠牲を捧げるには、二つの土器を使い、木製の葦の敷物を南側の庭に置きます。これを重門といいます。今、邪門は、これはそのイメージです。儀式では前奏の後に主人を作るのですが、今は主人がいないので、重いものが主人です。もともとは葬儀のために設置されたもので、門を表すものではありません。残念ながら、上と下を表すために使用すべきではありません。儀式によると、父と息子は官吏以上のために別の宮殿にいます。現在、卑しい私人の葬儀では、すべて別の門があります。最近これを行う人は皆、邪悪な門を持っているかどうかはわかりません。」 ファン・ジアンは邪悪な門についての質問に答えて、「帳簿は儀式のテキストから外れていないようですが、なぜこれを行うのですか?」と言いました。答えは、「邪悪な門は儀式ではありません。儀式によると、庭に重いものがぶら下がっていて、マットで覆われており、その形は邪悪な門のようです。後で取り出し、喪は門の外にあります。このことから、この習慣が踏襲されました。」でした。 『礼論』にはこうある。「もし『改葬の際、魔門を立てるべきか』と問うならば、蔡墨は『改葬するということは、葬儀を止めるということなので、魔門を立てるべきである』と答えた。」 死 『周書 春臣 氏族大君』には、葬儀の儀式で死者を悼むとある。 『礼記』には、「嫡」は皇帝の死、「洪」は王子の死、「祖」は大臣の死、「不禄」は学者の死、「思」は庶民の死とある。 (鄭玄のメモにはこうある。山頂が崩れることを崩落という。洪は崩れる音。祖は終わりを意味する。不禄は損失を補うことができないことを意味する。死は死を意味し、魂が消えたことを意味する。)敵の死を「冰」(普通の人とは違い、死後は損失を楽しむべきである)。長生きを「祖」、若くして死ぬことを「不禄」という。 (老いて死ぬと高官といい、若くして死ぬと学者といいます。) 『譚公夏』にもこう記されている。「孔子が泰山のふもとを通ったとき、墓の前で泣いている女性を見た。」子路にそのことを尋ねると、子路は「あなたが泣いているのは、とても心配しているようです」と言った。子路は「そうです。私の叔父は虎に殺され、夫もそこで亡くなり、今度は息子もそこで亡くなりました」と言った。師は「なぜ去らないのですか」と尋ねた。子路は「厳しい政府は嫌だ」と言った。師は「息子よ、あなたは知っています。厳しい政府は虎よりも凶暴です」と言った。 『葬送大記録』には、男は女の手によって死ぬことはない、女は男の手によって死ぬことはないとも記されている。王とその妻は道の寝室で亡くなり、大臣と側室は適当な寝室で亡くなり、妻は許可なく下の部屋で亡くなり、学者の妻は寝室で亡くなりました。 『左伝定夏』にはこう記されている。斉公が晋を攻撃したとき、畢無村の父は王位を継承しようとしたが、辞退した。彼は兄に「この戦いでは死なないだろうが、ガオ王国の誰かと結婚しよう」と言いました。彼は先に山を登り、門から脱出しようとしましたが、雨の中で亡くなりました。 『哀尚』には、次のように書かれている。 鑑子は群衆に言った。「畢竟は平民であった。七つの戦いに勝ち、百頭の馬を持っていた。彼は窓の下で死んだ。(畢竟は晋の献公の臣下であった。窓の下で死んだというのは、彼が長生きしたことを意味する。)あなたたちは彼を励ましなさい。彼は敵の手中に死ぬことはないだろう。(それは運命づけられていることを意味する。) 『艾夏』には、太子がこれを聞いて怖くなり、石奇孟を降ろして子路と戦わせ、槍で突き刺して房を折ったとも記されている。子路は言った。「君子は死ぬときも帽子を脱ぐべきではない。」彼は帽子を結んだまま死んだ。孔子は魏の反乱を聞いて、「柴は来るのか? 幽は死んだ」と言った。 『哀夏』には、晋の荀瑶が軍を率いて鄭を包囲したが、鄭の民は熊奎雷を捕らえ、政治の知識を買収して口封じし、死なせたとも記されている。 『古梁伝陰功』には、高侯が「破滅とは高位の人を表す言葉である。皇帝の死はその高位のしるしである。なぜ彼は死んだのか?彼は人民の上にいるから、死んだのだ」とある。 『春秋実録』序文にはこうある。「皇帝は倒れたと伝えられる。」 「ベン」は死を意味します。王子たちは死を主張した。 「洪」は突然死ぬことを意味します。医者は彼が死んだと告げ、彼の才能はついに消え去った。結局、彼の言葉は遮られ、彼は国から切り離されてしまった。学者は、給料を受け取らなければ忠誠心を失うだろうと言った。 「祝福されていない」という言葉は、その人の名前の削除につながります。一般の人が死ぬと、魂と精神は心から去っていきます。死とは、人の気力とエネルギーの終わりを意味します。 (百胡同にも記録あり) 「エルヤ」は言う:崩壊、死、不運、死、死、破滅はすべて死を意味する。 論語:李仁曰く:先生は「朝に真理を聞けば、夕方に死んでも満足する」とおっしゃいました。(死ぬときに、世の中に真理があるなどと聞かないという意味です。) 「子漢」はまた言う:子は病気です。子路は弟子たちに自分の病気について話すように頼み、こう言った。「あなたが私を騙したのはもう随分昔のことです。それに、私はあなたの手で死ぬより、あなたたちの二人か三人の手で死ぬほうがましです。盛大な葬式ができないとしても、道中で死ぬほうがましです。」 また、「Xianjin」には、Yan Yuan が死亡したと書かれています。孔子は言いました。「ああ! 天は私を見捨てた! 天は私を見捨てた!」先生は激しく泣きました。信者は言いました。「あなたはとても悲しんでいます。」彼は言いました。「どうして悲しむことがあるでしょうか?あなたがとても悲しんでいないのなら、誰がとても悲しんでいるのでしょうか?」 『仙津』には、季陸が「死について尋ねてもいいですか?」と尋ねたとある。季陸は「生を知らざるに、どうして死を知ることができようか?」と答えた。(幽霊や神や死については理解するのが難しいので、語っても無駄なので答えない。) 『紀氏』にも次のように書かれている。斉の景公は千頭の馬を持っていたが、彼が死ぬ日、人々は徳を積んでいなかったにもかかわらず、彼を賞賛した。伯易と叔奇は首陽山の麓で餓死したが、人々は今でも彼らのことを覚えている。 『五経の概意』には、「どの王が死の習慣を始めたか」とある。その答えは、「周以来である。なぜか?『史書』には「方舜が死んだ」とある。舜は「舒芳が死んだ」と言っている。武王が王になったので、武王以前には死というものがなかったことがわかる。成王が平和なとき、死の習慣が確立された。『史書』には「翌日、易周、成王が死んだ」とある。『名号の解説』には、「漢代以来、人々は死を『事の終わり』と呼び、すべてのものが朽ちることを意味する」とある。 『史記』には、秦の武王と孟越が龍の紋章のついた三脚を持ち上げ、二人とも膝頭の骨折で亡くなったと記されている。 (徐光曰く:斌は脈かもしれない。) また、樊於は秦の昭王を説得して「呉火と任弼の力、荊成、孟本、青季、夏羽の勇敢さがあれば、人が死ぬのは避けられない」と言ったとも言われている。 『後漢書』には、馬遠が孟紀に言った、「匈奴と五桓がまだ北境を乱しているので、私は彼らを攻撃するよう要請したい。人は辺境で死んで馬皮にくるまれて埋葬されるべきである。どうして寝床に横たわり、女や子供の手に委ねられることができようか」とある。孟紀は言った、「殉教者として、あなたはこうするべきです」 『後魏書』には、張愈は昔から古代人の玉の食べ方に感心していたため、藍田に掘ってみると、壁の周囲に大小さまざまな形の物体が百点以上見つかったと記されている。ぜひ見に来てください。すべてスムーズにプレイ可能です。そこで禹は七十粒を粉にして毎日摂取し、残りは他人のために用いた。その後、そのことを聞いた人たちは、翡翠が元々あった場所を探しに行ったが、何も見つからなかった。豊義の袁淮公らは玉を手に入れ、それを器物やペンダントに彫り、そのどれもが光り輝いて貴重であった。延命のために薬を飲むと効果があると言われていますが、世の中、食事や睡眠をコントロールすることはできませんし、飲み過ぎも意志を傷めてしまいます。馬車で出かけようとした時、長安は妻に言った。「もし山林に隠れて、欲を捨てて玉を飲めば、大きな神通力を得るかもしれない。しかし私は酒と女に溺れ、自分の過ちで死んだ。薬のせいではない。しかし、私の死体は違うはずだ。後世の人々に玉を飲んだことの恩恵が伝わるように、急いで埋葬しないでほしい。」7月中旬、長安は猛熱に見舞われていた。遺体は事前に4晩保管されており、色は変化しません。妻のチャンが翡翠のビーズ二つで彼をつねると、彼の口は閉じられました。チャンは彼に言った。「あなたは玉を食べると魔法の効果があると主張しています。それなら受け取ってみてはいかがですか?」彼が言い終えると、歯を開けて真珠を受け取りました。口から息を吐くと、汚れた空気が出ないからです。棺は、傾かずにしっかりと真っ直ぐな棺桶に納めます。彼の死後、数リットルの翡翠の破片が残っていたが、それらは袋に入れられ、棺の中に入れられた。 「文子」は言う。老子は言った。「賢者は死と生を分かち合い、愚者もまた死と生を分かち合う。賢者は死と生を分かち合うが、それは両者の違いを知っているからである。愚者は死と生を分かち合うが、その利益と害の違いを知らない。」 『荘子』はこう言っています。「人間の命は気によって決まる。」集まることは生を意味し、散らばることは死を意味する。 彼はまたこうも言った。「大地は私を形にして運び、生きている間は私を労苦させ、老いたときには私を楽にし、死んだときには私に安らぎを与えてくれる。」ですから、私たちが良く生きれば、良く死ぬこともできるのです。 また、荘子が楚に行ったとき、空っぽの頭蓋骨を見たが、それはまだ形を保っていた。荘子は馬の鞭で打たれたので、尋ねた。「先生、あなたは命を欲しがって理性を失ったためにこのようなことをしているのですか?国を滅ぼしたいから、あるいは槌と斧で罰せられたいからこのようなことをしているのですか?」そして、荘子は話すのをやめ、頭蓋骨を拾い上げて、それを枕にして横になった。真夜中、髑髏は夢を見て、「あなたはまるで弁論家のように話している。あなたが言っていることは、すべて人生の重荷についてであり、あなたが死んだら消えてしまう。死について聞きたいか?」と言った。荘子は「はい」と言った。髑髏は「死には上に君主はなく、下に臣下はなく、四季はない。たとえ天地が春と秋であっても、たとえあなたが南を向いて座っている王であっても、その喜びを超えることはできない」と言った。 『朔元』にはこうある。斉の景公が出てきて、死体を見た。景公は顔子に言った。「なぜ死んだのか?」 顔子の答えは、「餓死したのだ」であった。景公は言った。「ああ、私はあまりにも不道徳だ」。顔子は言った。「あなたの徳は明らかであるが、明らかではない。どうして不道徳なことができるのか?」景公は尋ねた。「どういう意味ですか?」 顔子の答えは、「あなたの徳は後宮や亭や台地の楽しみにまで及んでいる。あなたのガチョウは豆や粟を食べている。あなたの宮殿は幸福で、後宮の親族にまで及んでいる。どうして不道徳なことができるのか?しかし、あなたにお願いがある。あなたの望みに従い、人々に喜びを与えるなら、どうして不道徳なことができるのか?」 子貢は孔子に尋ねた。「人は死ぬと意識があるが、意識がないのだろうか?」孔子は答えた。「死者は意識があると言いたいが、孝行な子が命を犠牲にして死者を送り出すのではないかと恐れている。死者は意識がないと言いたいが、不孝な子孫が親を捨てて埋葬しないのではないかと恐れている。人が死ぬと意識がないことを知りたい。死んでからゆっくりと知るのも遅くはない。」 もう一つの逸話:魯の哀公が孔子に「賢者は長生きするか」と尋ねた。孔子は答えた。「はい。人間には3種類の死がありますが、それは運命ではなく、人間自身が引き起こすものです。適切な時間に眠らず、飲食をほどほどにせず、働き過ぎて休み過ぎた者は、病気で殺されます。低い地位にありながら君主に干渉し、酒に溺れ物欲に溺れた者は、刑罰で殺されます。多数を怒らせる少数、強者を侮辱する弱者、自分の力を測らない怒りっぽい者は、軍隊に殺されます。これらの3種類の死は運命ではありません。」 また、次のようにも言われています。「人々には 5 つの死因がある。賢者は 3 つを排除できるが、2 つを排除することはできない。」飢えや渇きで死ぬ者も追い払われるし、凍えや寒さで死ぬ者も追い払われる。たとえ5人であっても、殺された者は去ることができる。長期死で死亡した者を排除することはできず、また、癰癇で死亡した者を排除することもできない。 3つは削除できますが、2つは削除できません。 「倫衡」は言った。「人の死は火が消えるようなものだ。」火が消えれば光も消え、人が死ねば知恵も消える。この二つは同じものではなく、死者にも意識があると主張する評論家もいますが、これは混乱を招きます。 王莽の時代には五経の章と文の数は2000万にも達したとも言われています。博士の弟子である郭禄は、夜、古い理論の研究をしていたが、ろうそくの明かりの下で亡くなった。集中力が足りないと脈拍や呼吸が止まってしまいます。 楊泉の『物論』にはこうあります。「人は呼吸とともに生まれ、精気が尽きると死ぬ。それは絶滅と同じである。」それは火のようなものです。したがって、火が消えた後、炎は残りません。人が死んだ後、魂は残っていません。 |
推薦する
インド神話では、創造の神であると信じられているブラフマー王
はじめに:伝説によれば、世界中で大規模で壊滅的な火災、洪水、風災害が発生すると言われています。大火災...
司馬紹には何人の兄弟姉妹がいますか?司馬紹の兄弟姉妹は誰ですか?
明晋の皇帝司馬紹(299年 - 325年10月18日)は、字を道済といい、晋の元帝司馬睿の長男で、晋...
「水仙 梅の花を探して」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?
水仙:梅の花を探して喬記(元代)冬の前後にはいくつかの村があり、川の両岸には霜が降り、木々の頂上と下...
「秋の夜にひとり座る」の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
秋の夜に一人で座る王維(唐代)空っぽのホールで二回目の見張りが始まろうとしているとき、一人で座ってい...
老子の『道徳経』第 13 章とその続き
『道徳経』は、春秋時代の老子(李二)の哲学書で、道徳経、老子五千言、老子五千言とも呼ばれています。古...
トン族の食文化の特徴は何ですか?
私たちの印象では、一日三食食べるのが伝統になっています。しかし、ドン地域の人々は1日に4食、お茶を2...
神農の妻は誰でしたか?燕迪神農の妻の名前は何ですか?
炎帝とその妻(亭軒、赤水氏の娘) 『山海経』第18巻『山海経』には次のように記されている。「炎帝の妻...
蘇軾兄妹の戯曲をレビューします。蘇小梅は本当に才能のある女性です。
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting Historyの編集者が蘇暁梅につい...
馬尾郵便局を通過するとき、なぜ楊貴妃は民衆の怒りを鎮めるために死ぬよう求められたのでしょうか?
楊貴妃は安史の乱には参加していないのに、なぜ殺されたのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介...
厳吉道の名作「邑鶏天:色袖に玉鈴を懸命に握る」
以下、面吉道の『鷺空・色袖精励玉鈴』の原文と鑑賞文を面吉道の編集者がお届けします。興味のある読者と面...
『紅楼夢』の宝仔とメイドの小紅の関係は何ですか?
宝仔は『紅楼夢』のヒロインの一人です。林黛玉とともに金陵十二美女の第一位に数えられています。次の『お...
オーストリアの作家シュテファン・ツヴァイクはなぜこのような極端な死を遂げたのでしょうか?
歴史上有名な小説家として、ツヴァイクは多くの功績を残しました。ツヴァイクの生涯については多くの逸話が...
崔俊の「柳」:詩全体に「柳」という言葉は一つもないが、至るところに「柳」の影がある
孔鈞(961年 - 1023年10月24日)は、字を平中といい、華州下桂(現在の陝西省渭南市)の人で...
皇帝の剣は秦漢の時代から存在していました。本当に暴君や腐敗した役人を殺すことができるのでしょうか?
一部の映画やテレビドラマでは、上方剣を手にした宮廷の役人が、まるで本当に暴君や腐敗した役人を殺せるか...
張碩の「幽州の新年の詩」:この詩は唐代全盛期の詩に新たな雰囲気をもたらした
張朔(667-730)は、道済、朔子という芸名でも知られ、樊陽市方城(現在の河北省固安県)の出身であ...