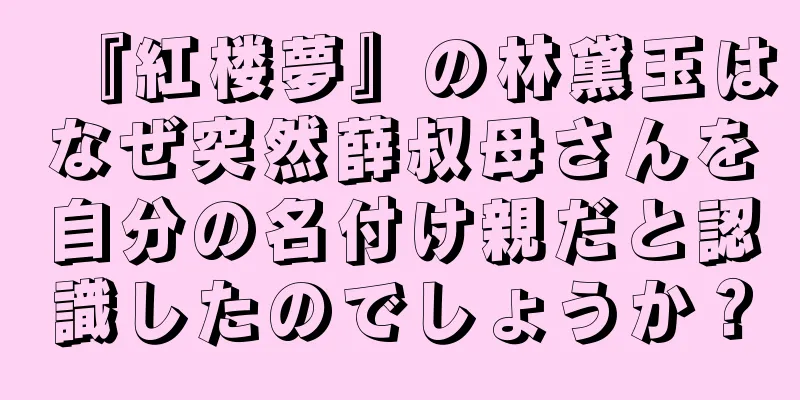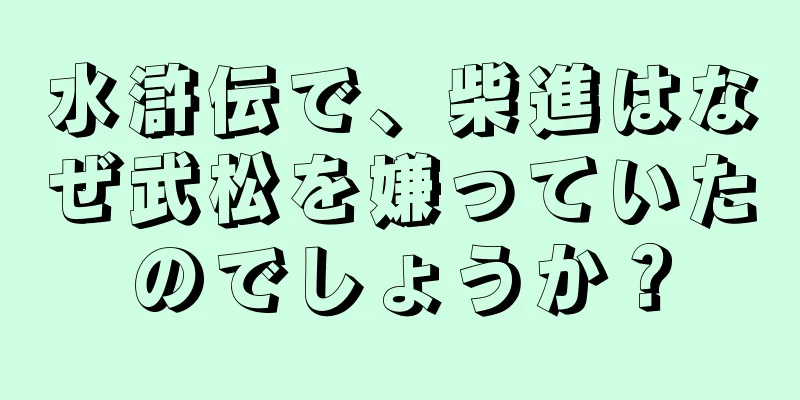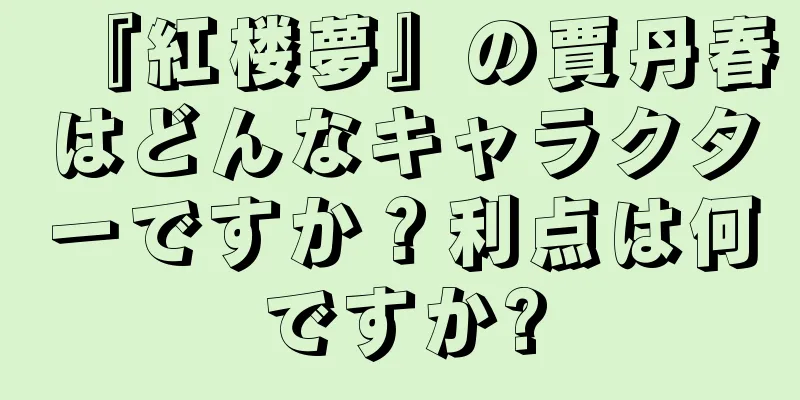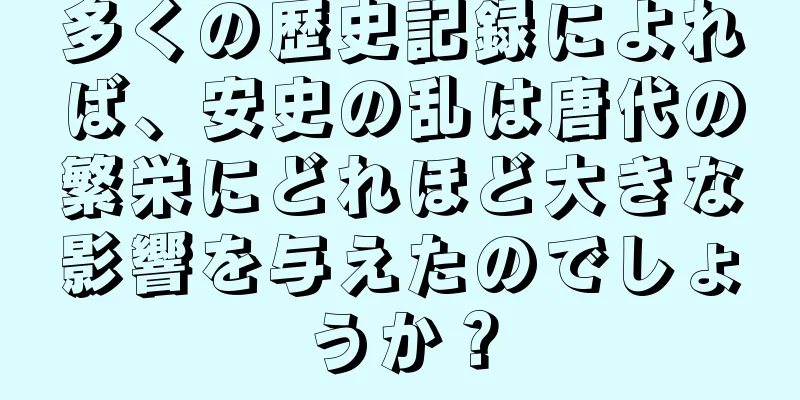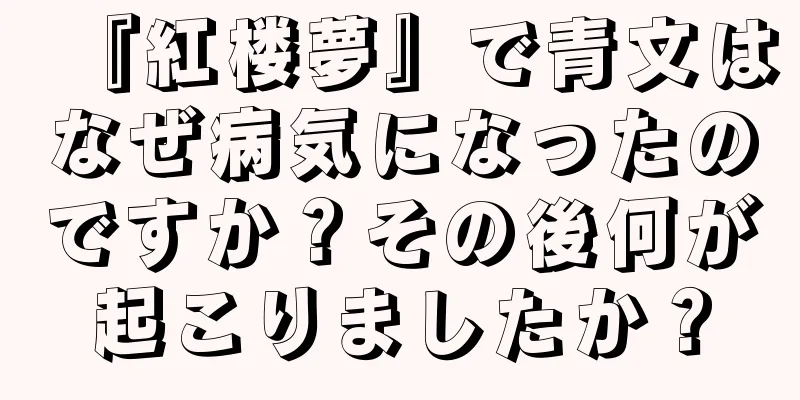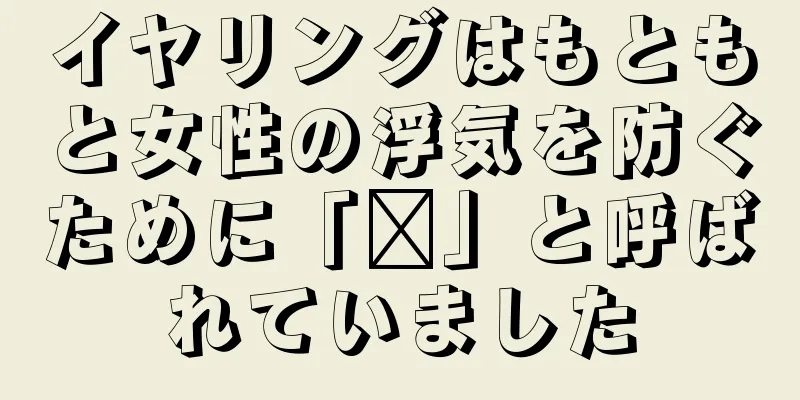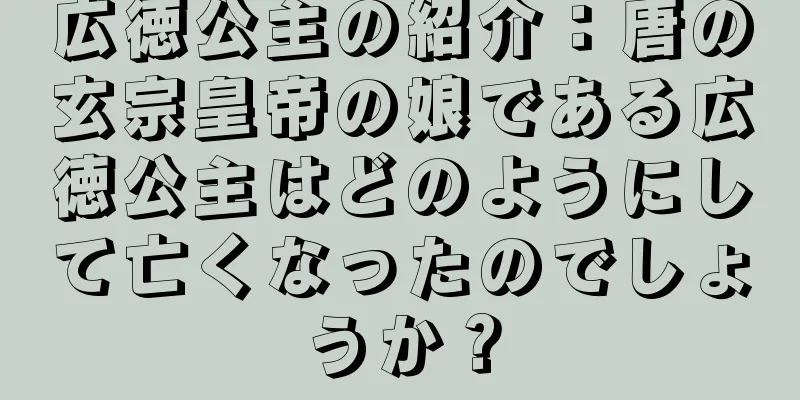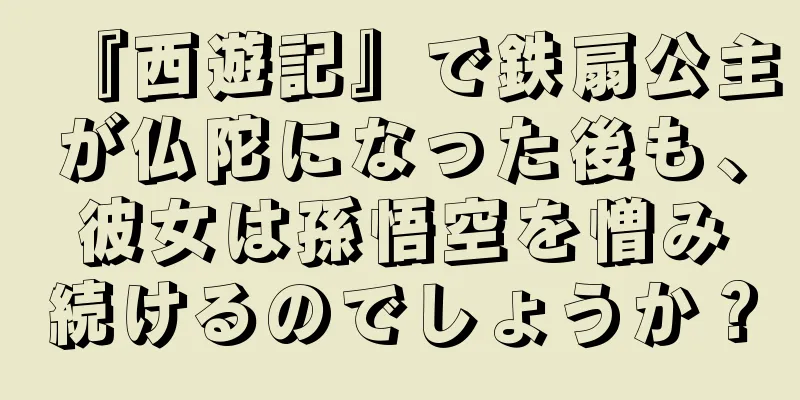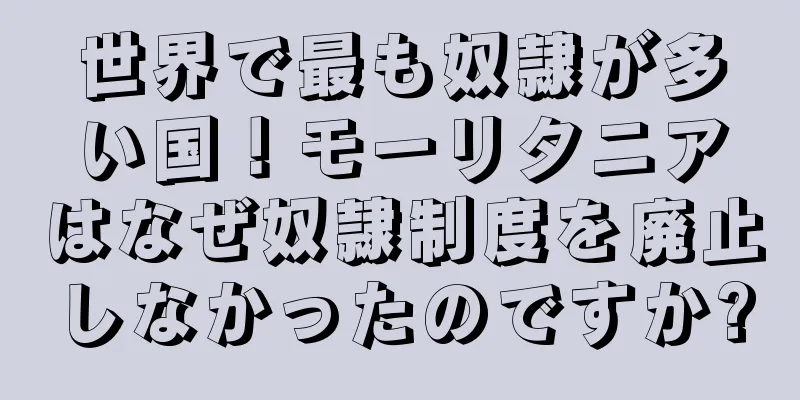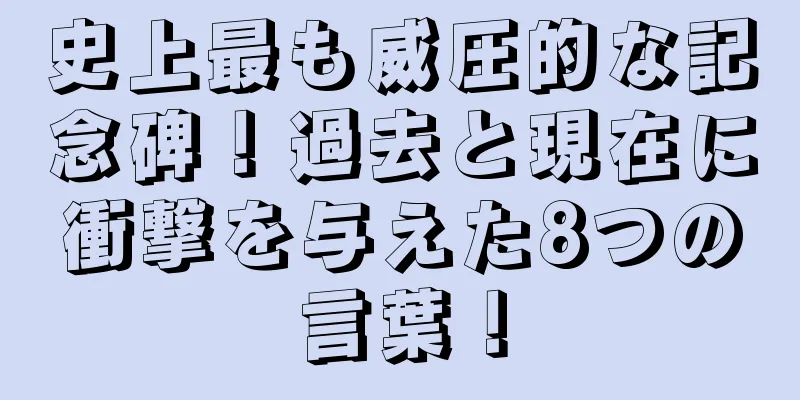『四聖心源』第3巻 脈法解説:村口仁英脈法全文
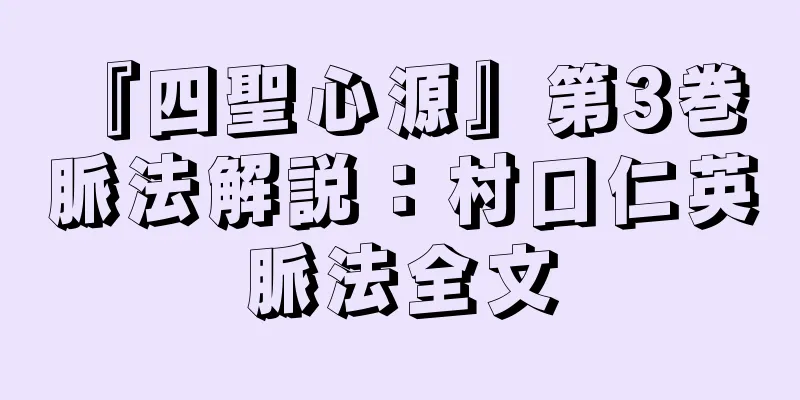
|
『四聖心源』は、1753年に清朝の黄元宇によって書かれた医学書で、『医聖心源』としても知られています。著者は黄帝、奇伯、秦月人、張仲景を医学の四聖人とみなしている。この本は『黄帝内経』『難経』『熱病論』『金堂要』の意味を解説しています。第2巻は天と人について、第26巻は気について、第3巻は脈法について、第4巻は疲労による損傷について、第5巻から第7巻は雑病について、第8巻は七穴について、第9巻は傷と潰瘍について、第10巻は婦人科について説明しています。伝統的な中国医学の基礎理論と臨床医学の一部を収録した総合的な著作です。次に、次の興味深い歴史編集者が、第 3 巻「脈法解釈: 村口仁英脈法」の詳細な紹介をお届けします。見てみましょう。 気口は手の太陰経絡の動脈であり、母指球の下にある。人陰は足陽明経の動脈であり、喉頭の隣に位置しています。太陰は三つの陰経に気を巡らせるので、閏口は五臓六腑を観察することができます。陽明は三つの陽経に気を巡らせるので、仁営は六臓六腑を観察することができます。太陰は五臓六腑の長であり、陽明は六腑の長である。 臓腑が強いときは、仁英は小さく、邑口は大きい。臓腑が弱いときは、仁英は大きく、邑口は小さい。傅陽が弱いときは、邑口は大きく、仁英は小さい。臓腑が強いときは、邑口は小さく、仁英は大きい。 「霊鷲禁薬」:村口は内を司り、仁営は外を司る。春夏には人陰脈がやや大きくなり、秋冬には村口脈がやや大きくなります。このような人を常人といいます。人陰が村口の2倍の大きさであれば、病気は足の少陽にあります。人陰が2倍の大きさで、患者が落ち着きがないなら、病気は手の少陽にあります。人陰脈が2倍大きい場合、病気は足太陽にあります。人陰脈が2倍大きく、患者が落ち着きがない場合は、病気は手の太陽にあります。もし人陰脈が3倍高ければ、病は足陽明にあり、もし人陰脈が3倍高くて患者が落ち着きがないなら、病は手陽明にある。過剰な場合は熱感、弱い場合は冷感、圧迫されている場合は痛みや痺れ、断続的な場合は、時には激しく、時には断続的です。人脈が4倍大きくて頻脈の場合、易陽と呼ばれます。易陽は外的な病状であり、治療しないと患者は死にます。もし、人陰の2倍の大きさであれば、その病は足の厥陰にあります。もし、人陰の2倍の大きさで興奮しているなら、その病は手の厥陰にあります。閏口の脈が2倍であれば、病状は足少陰にあります。脈が2倍で患者が落ち着きがないなら、病状は手少陰にあります。閏口の脈が3倍高ければ、足の太陰に病がある。脈が3倍高くて患者が落ち着きがないなら、手の太陰に病がある。病状が重い場合は、腹部膨満、中冷、消化不良などの症状がみられます。病状が弱い場合は、中熱、嘔吐、息切れ、尿の変色などの症状がみられます。病状が重篤な場合は、疼痛、麻痺などの症状がみられます。病状が断続的の場合は、断続的に疼痛がみられます。邊口の脈が4倍大きくて頻繁な場合、易陰と呼ばれます。易陰は内関であり、治療しないと患者は死にます。 「霊鷲景邁」:仁英と邁口は村口です。 4倍以上の強さの時は「関格」と呼ばれます。関格とは短い期間を意味します。 「霊鷲五色」:人陰脈が強くて硬い場合、患者は寒さで傷ついていることを意味します。気の口が強くて硬いと、食べ物によって害を受けます。気口は内を司り、飲食によって害を受けると陰が内側に沈むので、気口は強く堅固である。仁陰は外を司り、寒さによって害を受けると陽が外側に沈むので、仁陰は強く堅固である。 これが、閏孔と人陰を診断する方法です。経典には、村口脈と人陰脈が記されている。後世の人は、左が人陰脈、右が奇口脈だと言うが、これはナンセンスであり、説明できない。 |
推薦する
古典文学の傑作『淘宝夢』:第5巻:米公全文
『淘安夢』は明代の散文集である。明代の随筆家、張岱によって書かれた。この本は8巻から成り、明朝が滅亡...
明代の「装甲車」:孫成宗が最古の車両陣地を設立
明代の銃器は当時世界で非常に有名で、無敵とも言えるほどでした。明代の将軍たちも様々な銃器の発明に熱心...
『紅楼夢』における賈家の財産没収と宦官との関係は何ですか?真実とは何でしょうか?
『紅楼夢』の賈家は詩と礼儀と高貴さを兼ね備えた一族であり、富と贅沢を兼ね備えた一族である。 Inte...
荀夢片集第11巻の游の原文の鑑賞と注釈
司守謙作「子供のための片居」、明代霊岩亭と徳月塔。将軍に任命されるための基盤を築き、貴族の称号を授与...
三英雄五勇士第21章:首を投げて悪人を驚かせ、悪学者の沈千波を排除する
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
「扶瑪」はもともと「扶瑪」を意味し、南北朝以前は副馬車の責任者であった。
もともと「太子妃」は王女の夫でもなければ、皇帝の婿でもありませんでした。漢の武帝の時代には、副馬車の...
『紅楼夢』の薛宝才と林黛玉をどう評価すべきでしょうか?体臭が違えば態度も違う
本日は、Interesting Historyの編集者が皆様のために林黛玉さんについての記事を用意し...
『紅楼夢』ではなぜ丹春は不運な人だとされているのでしょうか?彼女の結末はどうなったのでしょうか?
賈丹春は『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人です。これについて言えば、皆さんも聞いたことがある...
『酒泉郷の宴会で酔って書いたもの』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
酒泉の知事の宴会で酔った後に書かれた岑神(唐代)酒泉の知事は剣舞が上手で、両親は夜になると酒を飲み、...
古代詩の鑑賞:詩集:ウサギの罠:ウサギの罠の音、コオロギの音
『詩経』は中国古代詩の始まりであり、最古の詩集である。西周初期から春秋中期(紀元前11世紀から6世紀...
世界の氷河が溶けたら何が起こるでしょうか?氷河が溶けるとどんな危険がありますか?
地球は私たちの故郷であり、そこで私たちは食べたり飲んだり、生活したり旅をしたりします。あなたの小さな...
なぜ魏晋の時代に儒教は絶対的に不利な立場にあったのでしょうか?当時の文学指導者たちは形而上学を尊重していた
魏晋時代の形而上学は老子の教えに従っていると主張していたが、彼らは「存在は非存在から生じる」というこ...
蒋子牙の『太公六道』:「六道・五道・三易」の作例と評価
『六兵法』は『太公六策』『太公兵法』とも呼ばれ、秦以前の中国の古典『太公』の軍事戦略部分と言われてい...
唐代の宋志文の『漢江渡』の鑑賞:この詩はどのような感情を表現しているのでしょうか?
漢江を渡った唐代の宋志文については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう。山...
南宋時代の明教とはどのような宗派だったのでしょうか?明教はなぜ「悪魔教」と呼ばれているのでしょうか?
南宋時代の明教とはどのような宗派だったのでしょうか?明教はなぜ「魔宗」と呼ばれたのでしょうか?『おも...