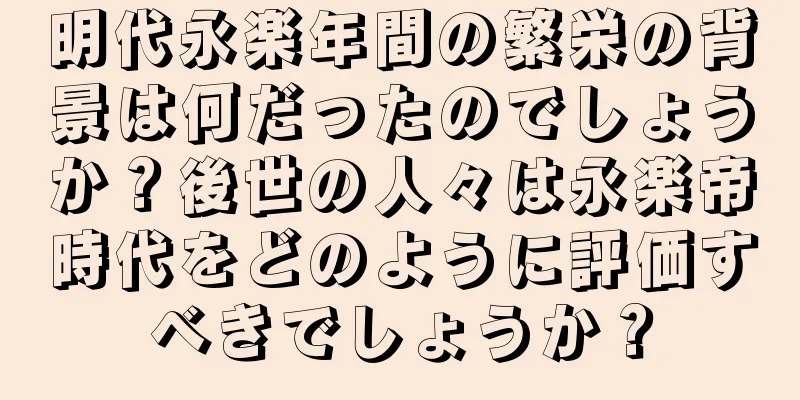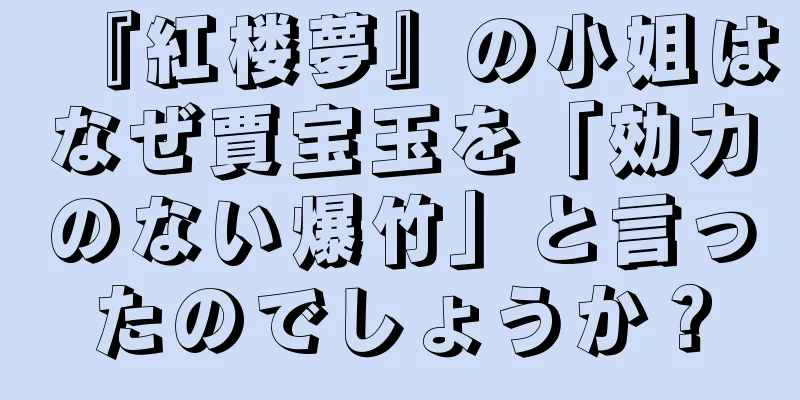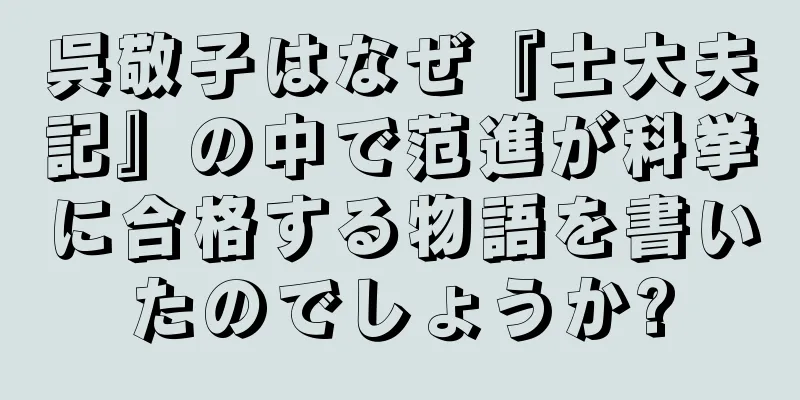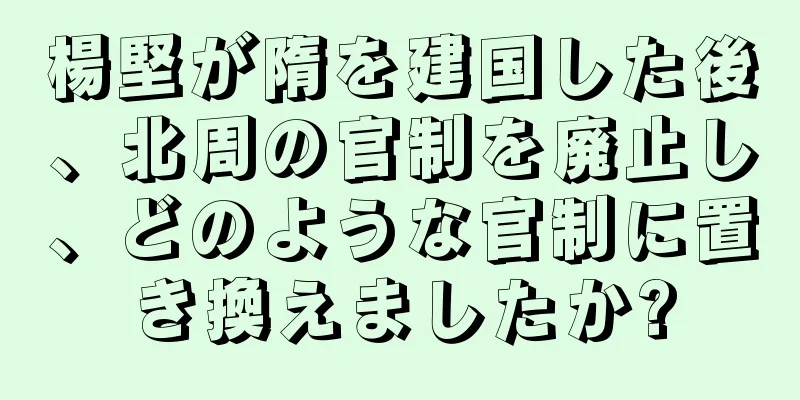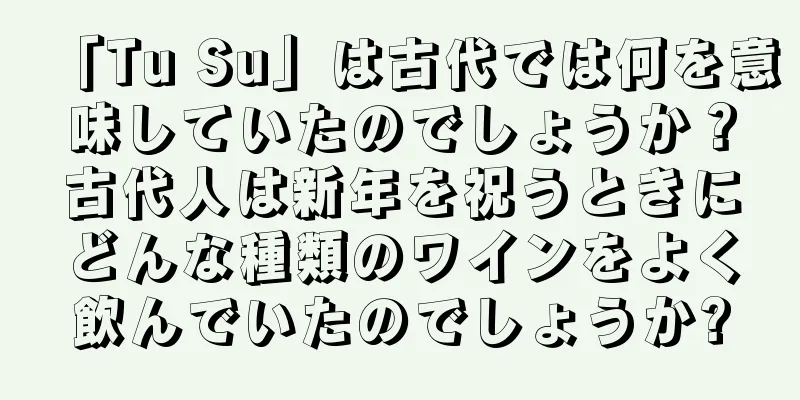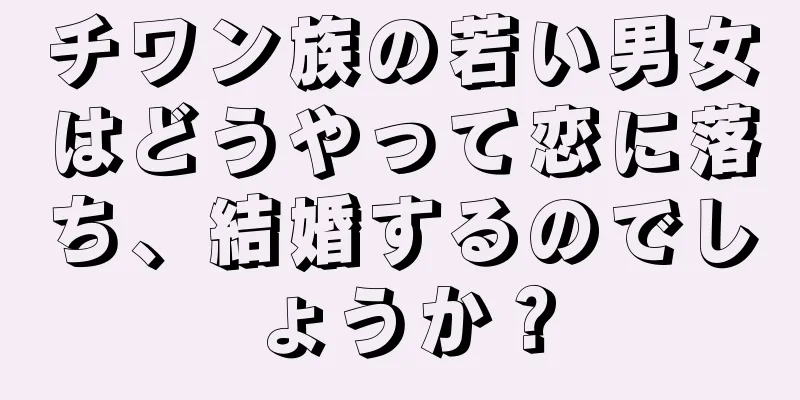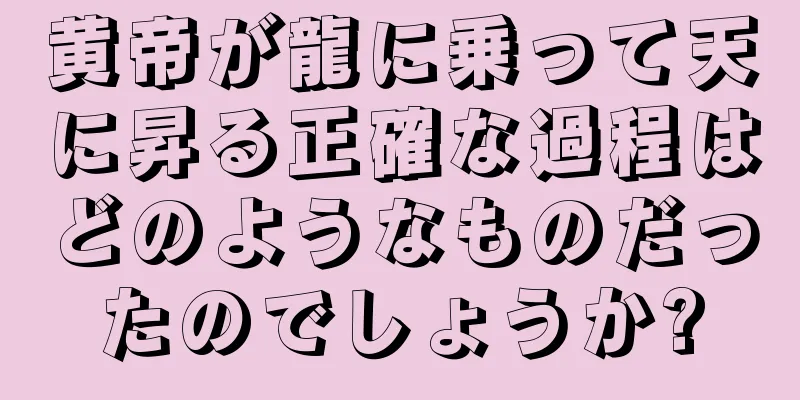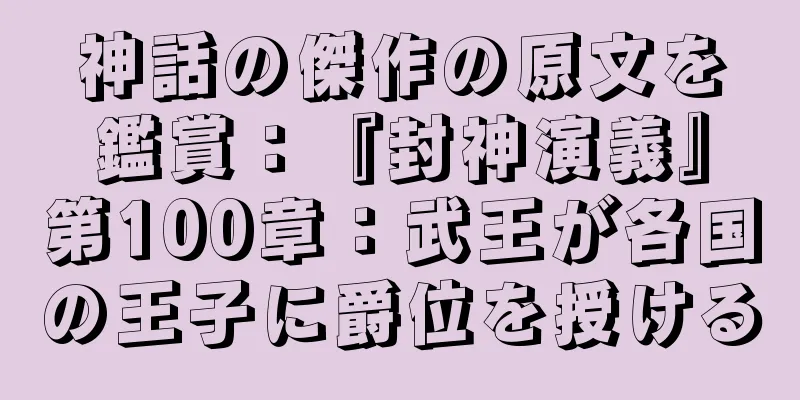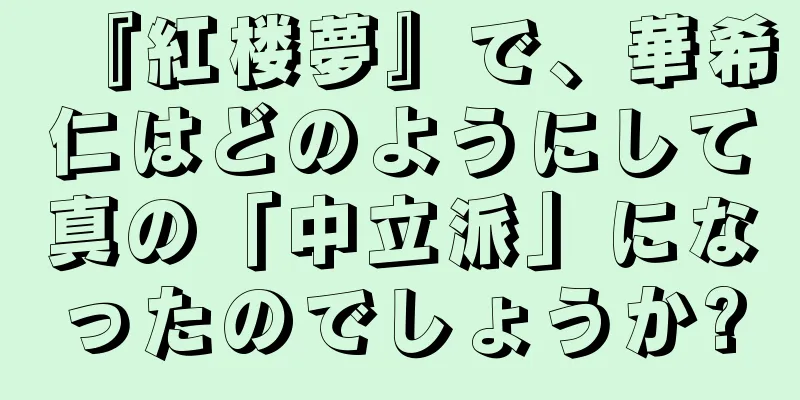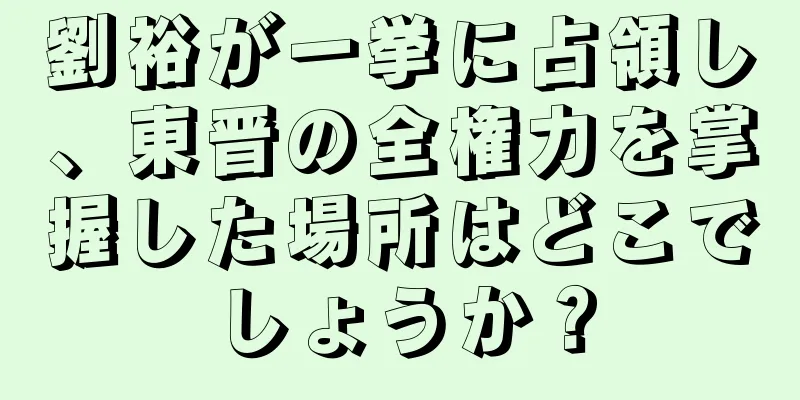分析:古代中国の歴史における少数民族王朝の世襲結婚制度
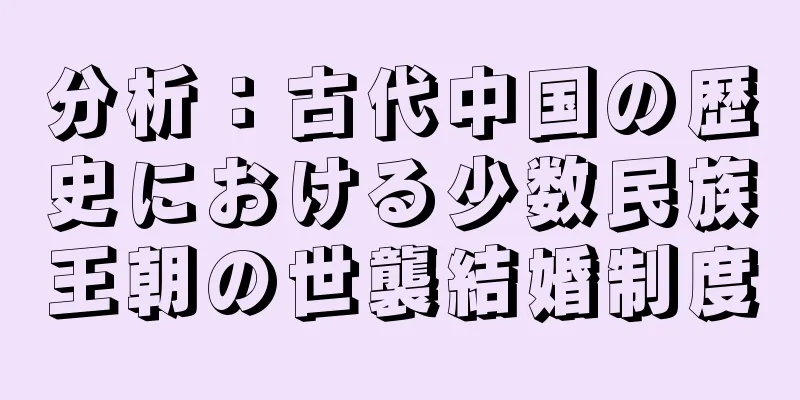
|
はじめに:歴史家陳銀科は『唐代李武衛楊婚姻組記』の中で、李唐王家はもともと関龍組であったため、当然最初は関龍組を結婚相手として選んだが、武則天の宮廷入りが大きな転機となり、山東組が李唐王家の結婚相手となり、いわゆる李武衛楊婚姻組が形成され、唐帝国の統治状況に適応したと指摘している。この婚姻集団が最高支配層の中核であった約100年間は、唐代の文武両道の業績が絶頂期を迎えた時期でもありました。安史の乱後、この集団の勢力は衰え、その結果、李唐の中央政府は国を統治する実質的な能力を失った。 この有名な歴史的事例の実際的な意義は、唐代の政治史研究の範囲をはるかに超えています。中国の歴史上の王朝では、李氏、呉氏、魏氏、楊氏のような「繁栄は共に、逆境は共に」タイプの結婚集団に似た結婚集団がほぼすべての王朝に存在していましたが、具体的な現れ方は異なっていました。君主制の下では、どの王族も結婚という絆を通じて、1つまたは複数の信頼できる有力な集団を味方につけ、あるいは頼ろうとし、そうすることで、1つの姓を持つ家族と国家は、より広範で強固な政治的同盟の基盤を持つことになる。 歴史上、中原の王朝は陳銀科が明らかにした利武衛楊型の婚姻集団を通じて政治的同盟を形成することが多かったとすれば、中原を支配するようになった少数民族の封建王朝は世襲婚姻制度を通じて継続的で安定した婚姻集団を形成することが多かった。女王や側室を任命するために外部の助けを求める必要はなく、王族の中から選ぶだけでよかったのです。妾の世襲結婚制度が生まれた理由は様々です。人類の結婚形態の進化の観点から見ると、近親婚制度は明らかに異族婚姻制度の名残であり、つまり、ある氏族の男性の配偶者は、他の氏族の女性でなければならない。明らかに、この世襲結婚制度は、これらの少数民族の王朝がそれほど昔の野蛮な時代から文明の入り口に足を踏み入れたことと密接に関係しています。政治統治の観点から見ると、中原に進出した少数王族は、一方では自らの王朝の支配基盤を拡大・強化するために、共通の利益を持ち苦楽を共にする部族との政治的同盟を強化することが急務であった。他方では、王家の血統の純粋性を保つために、王朝の継承者に被支配民族の血統が入ることを防ぐ必要があった。 世襲婚制度は交換婚の一種である。西周の時代、冀姓と江姓は代々結婚していた。周の皇帝の側室は斉の娘でなければならず、この結婚制度はすでに確立されていた。しかし、秦漢以降の漢王朝、さらには十六国や北朝などの少数王朝においてさえ、厳格な世襲婚制が実施されることは稀であった。皇帝とその側室の世襲結婚制度に関する記録が比較的豊富に存在するのは、遼、金、元、清の時代だけです。その中で、遼代の世襲婚制度が最も典型的で、次いで金、元の順であった。清代は関に入る前のみ世襲婚の傾向が強かったが、厳格な制度としては確立されていなかった。 契丹族によって建国された遼王朝では、古い突厥の慣習に従って女王を「ハトゥン」と呼んでいました。契丹語では「テリジャン」であり、敬意を込めて「ノウモ」と呼ばれていました。廖太祖愚呂阿保吉が建国する過程で、彼の妻である春琴舒平皇后は名家の出身で、戦略を立てるだけでなく騎馬戦闘にも長けた欠かせない人物でした。彼女の息子である遼の太宗皇帝は、「皇太后の一族は大きく、動かすことのできない古いヒノキの根のようだ」と言った。阿保吉は女王の一族に頼らざるを得なかった。建国当初、彼は王族は女王の一族とのみ結婚できると規定し、他の部族は特別な許可を得て両氏族と結婚することは許されなかった。阿保吉は漢の皇帝・高祖・劉邦を尊敬し、野呂氏に劉姓を与えた。また、野呂氏を漢の宰相・蕭何にたとえて、蕭姓を与えた。契丹族のシャオ氏族には、イシ氏族とバリ氏族が含まれており、バリ氏はおそらくシュル皇后の父と母の元夫の一族から構成されていたと思われる。そのため、遼朝の時代、子孫のほとんどは蕭姓を持ち、その多くが宰相を務めた。契丹の王女も蕭姓の男性と結婚することが多かったため、閉鎖的な婚姻グループが形成されていた。このように、天皇と皇后の結婚は君主と臣民の間の政治と結びついていました。 もちろん、遼朝では皇后だけが孝姓の者から選ばれなければならなかったが、側室については他の民族や姓の者もいた。例えば、遼の世宗皇帝の貞妃は五代後唐の宮女であった。彼女は世宗皇帝が即位する前に父の太宗皇帝に同行して南征した際に捕らえられた。彼女はその年41歳で、まだ美しかったためか、寵愛を受けていた。世宗が即位した後、彼女は一度は王妃となった。甄は皇后として即位した。これは『遼書』の『皇后列伝』や『契丹書』に記録されている。しかし、『遼史 皇后列伝』には、天暦末期に世宗皇帝が舒禄皇后の弟である蕭阿姑之の娘を皇后に立てたとも記されている。『遼史 世宗皇帝紀』では、この出来事は天暦4年(950年)とされている。蕭と禎はチャガの乱で亡くなりました。一人の女王はまだ生きており、もう一人の女王は即位しました。これには何らかの理由があったはずですが、残念ながら『遼書』には詳細は記録されていません。しかし、『遼史 皇后列伝』における甄の最初の称号は側室の称号のみであり、あるいは、蕭が即位した後に廃止された。甄の著書が『実録』に収録されていないのは、この行為が旧制度に違反していたためだと考えられる。このことから、この特別なケースは、最終的には肖氏を後継者にするという一般的な規則に従ったことがわかります。 晋朝は万延王族が庶民と結婚できないと規定していたが、特定の部族間の制限はあったものの、世襲婚姻制度の範囲は遼朝よりも広かった。 『晋史 皇后列伝』は、「王朝の伝説によれば、徒単、塘郭、普茶、納蘭、普山、荷社理、烏林達、烏群の各族は代々婚姻し、女王を娶っていた」と指摘している。『晋史 徒単明伝』によると、ペイマン一族は現代の王族であるワンヤン一族とも婚姻していた。これらの姓はすべて女真族の貴族に属し、「皇帝はこの一族の王妃と結婚しなければならず、王女はこの一族の王女と結婚しなければならない」のです。晋代の王族の世襲婚姓は遼代よりも多く、死後に皇后に叙せられた者や生前に第一妃に列せられた者の中には漢人や他の姓の者も時折含まれていた。金章宗には、衛兵の家に生まれた李世娥という妾がいた。晋の時代、戦争で捕らえられたり、犯罪で没収されたすべての女性は選別され、宮殿に送られて奴隷にされることを強制されました。李世児は宮殿の侍女であり、最も卑劣な身分であった。しかし、彼女は聡明で、思いやりがあり、教養があり、文章を書くのが上手で、詩や散文が得意で、金章宗に最も寵愛されていました。張宗の最初の妻は彼が即位する前に亡くなり、皇后の地位は長年空席となっていた。張宗は李世兒を中宮の皇后にしようとしたが、大臣たちは強く反対した。検閲官たちは抗議を続け、張宗はなすすべがなかった。張宗は李世兒を皇后に次ぐ地位である元妃に昇格させざるを得なかった。これはまた、金王朝の皇帝が正式に即位した後、世襲結婚が義務付けられている女真族の貴族の中からのみ皇帝を選べたことを示しています。章宗皇帝の治世中に中国化が加速し、皇帝は王たちに庶民の家庭から女性を選んで後継者を産ませるよう命じた。そのため、玄宗皇帝は即位する前に、漢王姉妹を側室として迎えました。即位後、妹を皇后に立て、文墩姓を与えました。これもまた、世襲結婚制度を変えるための手段でした。 チンギス・ハーンは軍隊を率いて様々な部族を統一し、モンゴル帝国を建国したとき、ホンジラ族を頼りにし、すぐにその娘であるボルタイ・シュジェンを後継者に据えました。洪吉拉氏族と天下統一の誓いを立てた時、彼は「洪吉拉氏族に女の子が生まれたら、代々女王となる。男の子が生まれたら、代々王女と結婚する」と約束したと伝えられている。そのため、元朝の女王のほとんどは洪吉拉氏族出身であった。モンゴルと元の時代は複数の皇后の制度を実施しました。他の姓の皇后もいましたが、制度によれば、主な皇后は必ず洪家臥氏族の出身者でなければなりませんでした。しかし、この結婚の原則の実施は、遼や金ほど厳格ではなかったようです。たとえば、オゴデイ・ハーンの皇后は内曼貞でしたが、元の英宗皇帝の皇后は易奇烈でした。 満州人が峠に入る前、アイシン・ジョロ王家は基本的に満州人とモンゴル人の間の結婚の方法を実行していました。これは、2つの民族が地理的に隣接しており、民族の慣習が似ており、政治的な目標も基本的に近いためです。しかし、モンゴル族は多くの部族が存在し、その一部は自らの利益をめぐってアイシン・ジョーロ族と対立し、戦争を起こすこともあった。そのため、満州人とモンゴル人の結婚においては、ホルチン族のボルジギト氏族のように、より安定した結婚相手となるモンゴル族の部族もいた。清朝初期の側室の多くはこの姓の出身であった。 『清朝史 皇后妾列伝』によれば、清の太祖には側室が1人、清の太宗には皇后が2人と側室が4人、清の詩祖には皇后が2人と側室が2人おり、いずれもボルジギト一族出身であった。清朝初期に結婚した61人の王女のうち、31人がボルジギト家と結婚した。このことから、峠に入る前、清朝初期には、清朝のアイシン・ジョロ王家とモンゴルのボルジギト氏族がかなり安定した婚姻グループを形成していたことがわかります。このような満蒙族の結婚は、厳格な世襲結婚制度と呼ぶほどではないが、それでも同様の傾向がある。清朝が中原に進出した後、こうした政略結婚は次第に衰退した。康熙帝以降の皇帝の側室の中で、ボルジギト一族が優勢ではなかったことは明らかである。これは、清朝が国を統一した後、皇后や側室を選ぶ候補者が、満州族、モンゴル族、漢八旗全体の女性にまで拡大されたことと大きく関係している。 礼武衛楊婚姻グループであれ、遼、金、元、清の世襲婚姻方式であれ、結局のところ、それは皆が共に栄え、共に苦しむ政略結婚である。君主制国家にとって、こうした結婚は政権の強化にプラスの役割を果たすこともあるが、時には統治を弱めるマイナス要因をもたらすこともある。メリットとデメリット、福と災いの両方があると言えるだろう。このような政略結婚に巻き込まれた側室たちにとって、彼女たちは同盟を強化するための単なる交渉材料であり、意のままに操られる駒に過ぎず、その運命は他の政略結婚に巻き込まれた側室たちと本質的に同じである。君主制下の妾制度に内在する非人道性、非人間性は、すべての妾にとって避けられないものである。 |
<<: 古代の「3フィート」には多くの意味がある。紙が発明される前は、法律を意味していた。
>>: 中南山の生ける死者の墓はどこにありますか?トゥーム・オブ・ザ・リビング・デッドを建てたのは誰ですか?
推薦する
韓非子は歴史の発展についてどのような見解を持っていましたか?主に何によって表されるのでしょうか?
韓非子の社会史観は、三代説によって最も影響力があり、代表的です。彼の改革主張の理論的根拠は、「三世界...
『彭公安』第198章:童金珠に養子を受け入れて三国志に入るよう説得するために古代の遺跡の物語を語る
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
プミの宗教 プミ チベット仏教
プミ族は原始的な宗教を信仰するだけでなく、チベット仏教も信仰しています。この地域ではチベット仏教は一...
わずか36人の部下を率いて西域を制覇し、漢王朝を有名にした有名な将軍は誰ですか?
西暦73年、班超は偽司馬として、助手の郭勲とともに西域への外交使節として出向いた。張騫が西域を開拓し...
チワン族の鮮やかなエビ捕りダンスはどのようにして人々の間で人気を博したのでしょうか?
エビ捕りの踊りは広西チワン族自治区徳宝県で人気がある。この踊りは、春の明るい日差しの中、若いチワン族...
白馬駅の惨事を引き起こしたのは誰ですか?ホワイトホースステーションの災害の影響
白馬駅の惨事の経緯は、朱文が朝廷の中央政府を段階的に簒奪していったことを反映している。朱文が知事だっ...
アチャン民族「出会いの街」:「青龍と白象」が仏陀を迎える様子
会忌は阿昌語で「澳鹿」と呼ばれ、毎年旧暦の8月から9月の間に行われます。仏陀をこの世に迎える日です。...
西晋の有名な将軍、楊虎の妻は誰でしたか?楊虎の息子は誰ですか?
西晋の有名な将軍、楊虎の妻は誰ですか?楊虎の息子は誰ですか?楊虎(221-278)、号は舒子、泰山南...
なぜ古代日本には「眉毛を剃る」「歯を黒く塗る」という習慣があったのでしょうか?日本には他にどんな習慣がありますか?
今日は、おもしろ歴史編集長が、古代日本にはどんな風習があったのかをお届けします。皆さんの参考になれば...
タジク人はどんな宗教を信仰していますか?
過去において、タジク人は一般的にイスラム教を信仰していました。イスラム教のイスマイール派を信仰してい...
『長公区・吉山情』の執筆背景は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】趙有の後の仙人は誰ですか?偉人の名前を挙げてみても、多くはありません。漁師のヤン・リン...
「金陵王」の叔母である王夫人はなぜ「半古い」家具を多く使っているのでしょうか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が王夫人につ...
第20章:燕王が遼東を攻撃する口実を作り、張羽が密かに滄州城を攻撃する
『続英雄譚』は、明代の無名の作者(紀真倫という説もある)によって書かれた長編小説で、明代の万暦年間に...
楊子が唐詩の最初の校訂者である袁大暁碩に宛てた手紙をどのように解釈しますか? 魏応武は詩の中でどのような感情を表現しましたか?
楊子の最初の投稿から元代大孝書、唐代の魏応武まで、興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみま...
文廷雲の「夏科星」:この詩は作者の華やかで繊細な作品とは全く異なる
文廷雲は、本名は斉、雅号は飛清で、太原斉県(現在の山西省)の出身である。唐代の詩人、作詞家。彼の詩は...