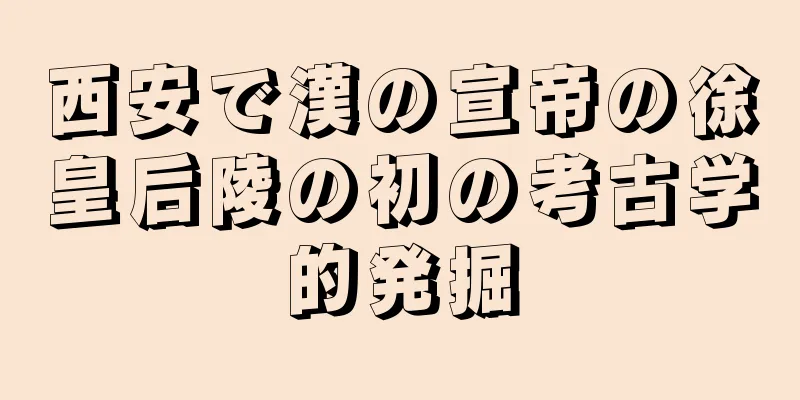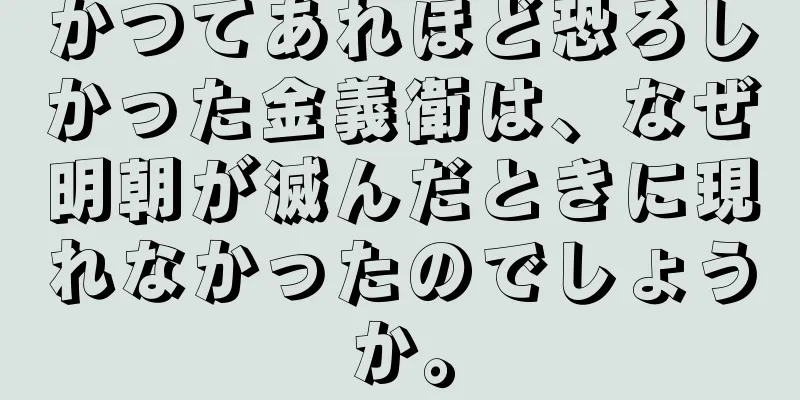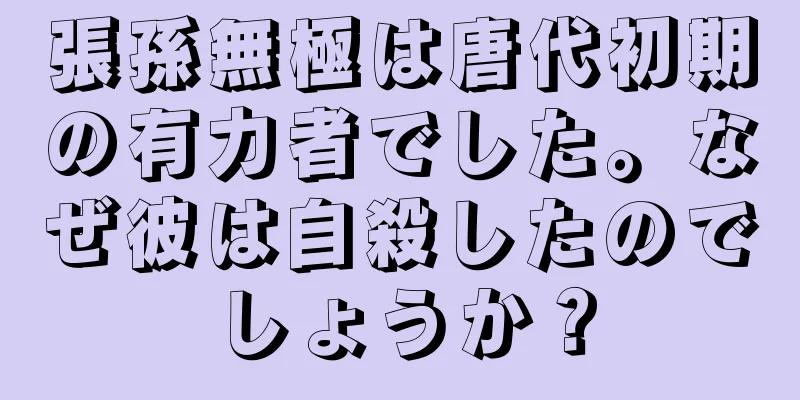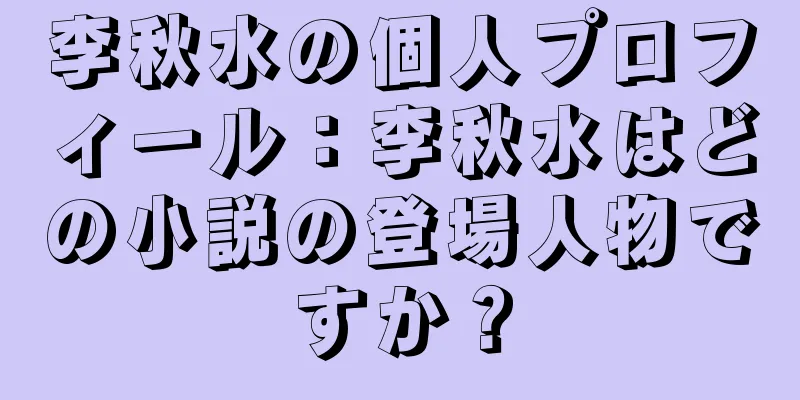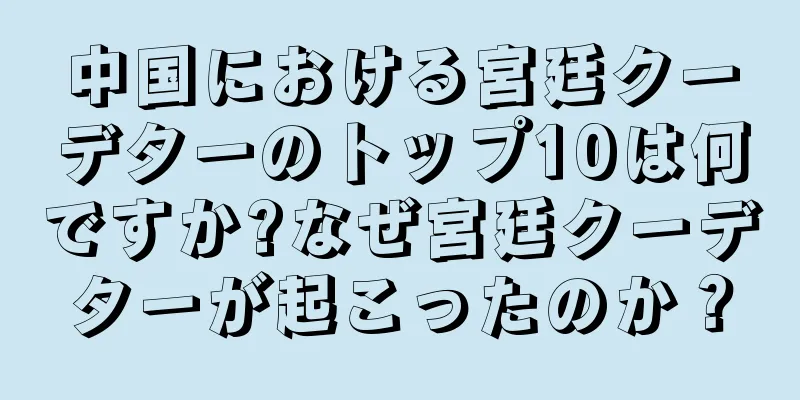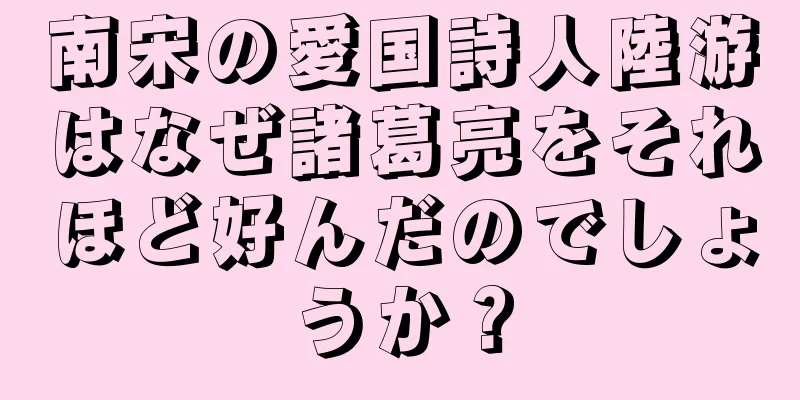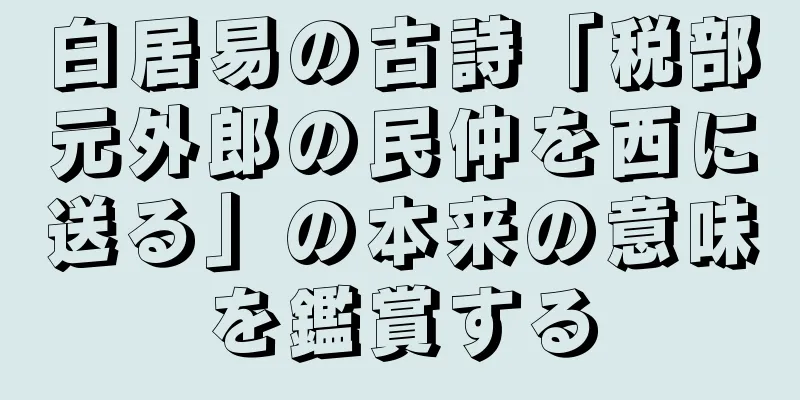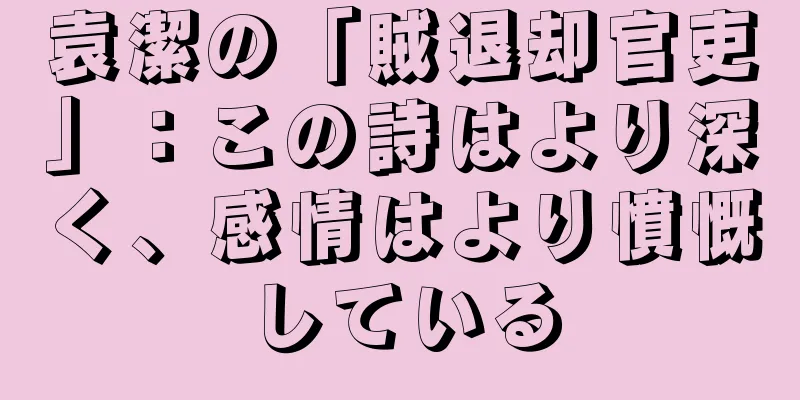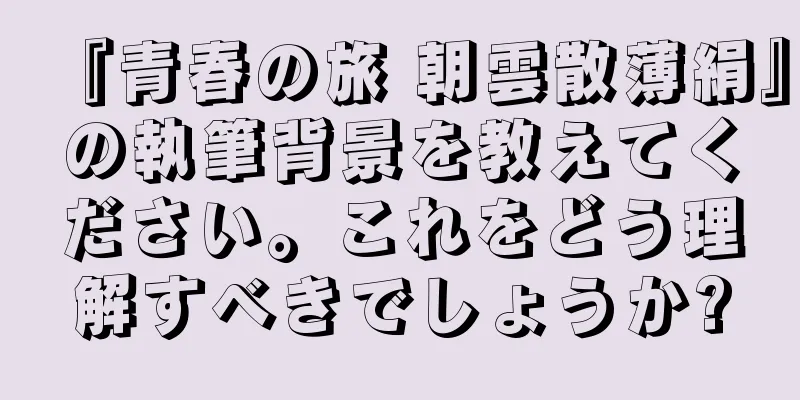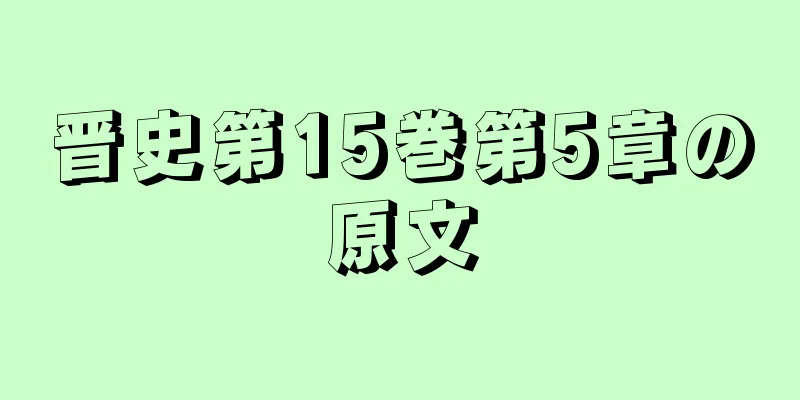なぜ「三つの手」が泥棒の同義語になったのでしょうか?
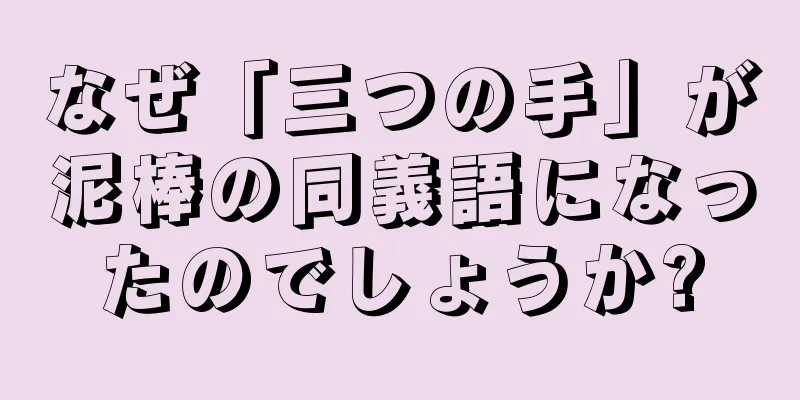
|
なぜ「三つの手」が泥棒の同義語になったのでしょうか? 泥棒はよく「三つの手」と呼ばれますが、このことわざの由来をご存知ですか? 「3つの手」という用語は、古代ローマの劇作家プラウトゥスの有名な喜劇「黄金の壺」で初めて登場したと一般に考えられています。劇中、守銭奴のユークリオは金の入った壺を失くし、手下たちに手を伸ばして調べるように要求する。しかし、泥棒はまだ見つかっていません。ついに幽霊のユールは激怒し、召使いに想像上の「第三の手」を見せるように頼みました。それ以来、「三つの手」は泥棒や盗みを働く人の同義語となりました。 実は、「三手」という言葉は中国では古くから存在していました。伝説によると、北宋の時代に東京に有名な泥棒がいたそうです。彼の窃盗のテクニックは非常にユニークです。道具は一切使いません。彼があなたの近くにいる限り、誰にも気づかれずにお金が彼のポケットに入ります。かつて、彼は「仲間」の前で演技を披露しました。その卓越した技を披露するため、彼は両手を高く掲げ、ある人物に近づき、まるで自分の体にもう一つの手があるかのように、皆の目の前でポケットの中の銀貨を取り出しました。そこにいた「同僚」たちは彼にとても驚き、尊敬の念を抱き、彼に「スリーハンズ」というあだ名を付けました。ここから「3つの手」という用語が生まれました。 なぜ私たちは人を侮辱するために「ドッグレッグ」という言葉を使うのでしょうか? 昔々、非常に悪い奴隷を飼っている暴君の地主がいました。召使いも犬を飼っていたのですが、これもまた非常に悪かったです。彼ら 3 人は、犬に力を頼り、犬も人間に力を頼っている集団です。人々は非常に怒っており、陰で彼らを邪悪な主人、邪悪な奴隷、邪悪な犬と呼んでいます。 その日、彼らはまた悪いことをしようとした。若い未亡人の家の壁を乗り越え、誤って暴力的な家主の足を折ってしまい、家主は痛みで悲鳴を上げてしまったのだ。召使はそれを見てさらに悲しくなり、主人にへつらって言いました。「ご主人様、私の足を切り取って、あなたに差し上げましょう。」主人はそれを聞いてとても喜びましたが、それでも言いました。「あなたはどうですか?」召使は振り返って凶暴な犬を見て、すぐに思いつきました。「犬の足をあげてもいいんじゃないですか?」「犬はどうですか?」いじめっ子は凶暴な犬が自分に対してしてくれたことをまだ覚えていて、愛情を込めて尋ねました。邪悪な奴隷は、ある考えを思いつきました。瞬きもせずにこう言いました。「泥の足をつけよう。」 横暴な地主は、この方法は適切ではないと考えましたが、自分の利益のため、そして奴隷のまれに見る孝行心のために、同意しました。こうして、召使いは自分の片方の足を切り取って主人に渡し、次に犬の後ろ足を切り取って自分の足につけ、さらに泥で後ろ足を作って犬につけました。 それ以来、人々は主人にへつらうことを好む人々を「従者」と呼ぶようになった。後になって、従者役の人たちはつま先立ちで歩いていたことが分かりました。これは意図的なものではなく、従者の足と自分の足の不一致によって起こる副作用だと言われました。 「バックドア」はどこから来るのでしょうか? 最近では、正当な手段を持たずに他人に助けを求めたり、賄賂を支払ったりして物事を成し遂げる行為を「裏口からやる」と呼ぶ人もいます。実際のところ、正門から入るか裏口から入るかは、合法か違法かという点では違いはありません。ここで問題となるのは、拡張された意味の問題です。 では、「バックドア」という用語はどこから来たのでしょうか? 北宋の宋哲宗の死後、宋徽宗が王位を継承した。蔡京は宋徽宗の王位継承の過程で多大な努力を払った。そのため、徽宗は権力を握るとすぐに蔡靖を大いに寵愛し、宰相に任命した。蔡靖は容認できる人物だったが、あまりにも厳格で、寛容さに欠けていた。例えば、蔡京は自分の政治的見解に反対する人々を抑圧する方法を見つけ出しました。蔡靖が権力を握ってしばらく経つと、政府と国民の間に広範囲にわたる不満が生じた。朝廷の文武官僚たちは不満でいっぱいで、民衆の間でも蔡静に関するスキャンダルがいくつかありましたが、蔡静は皇帝を大樹のように頼りにしており、誰も彼を揺るがすことはできませんでした。 この事件で蔡静を失脚させることはできなかったが、人々はさまざまな経路を使って、公職の売買や賄賂の受け取りなどの蔡静の悪行を暴露した。ある日、宋の徽宗皇帝が大臣たちのために宴会を催し、都の有名な歌劇団が宴会で風刺喜劇を上演しました。大まかに言えば、高官が法廷に座り、さまざまな事件を審理するというものです。この時、一人の僧侶がやって来て、北京の外へ旅行したいと言いました。難しいことは何もありません。公印を押すだけです。しかし、高官たちは彼の戒律証書が元有年間に発行されたものであることを知ると、直ちに彼の城外への出国を拒否した。 (蔡京は元鄭時代の政敵に対して非常に敵対的だったため、元鄭時代の物事に対して常に特に嫌悪感を抱いていたことが判明した)。その時、役人がやって来て報告した。「今日、財務省から給料として千連銭が支給されましたが、すべて元幽年間に鋳造された銅銭です。これをどうしたらよいでしょうか。」役人はすぐに部下に命じた。「では、裏口から持ち込め!」 それ以来、「裏口から入る」という言葉は、私的にえこひいきや汚職を利用し、物事を寛大なやり方で進めることを意味する冗談の言葉になった。 「目の中のとげ」 人々は、自分がひどく嫌っている人を表現するときに「目の上のたんこぶ」というフレーズをよく使います。この言葉の由来といえば、興味深い歴史的な話があります。伝説によると、北宋の真宗皇帝の治世中、宰相は丁維という名の裏切り者の悪党だった。彼は教育を受けておらず、権力争い、賄賂の受け取り、法律の逸脱しか知らなかった。一日中宦官と結託して政府を支配していた。彼の行動は当時の首相である崔俊の注目を集めたが、崔俊は丁維に対する証拠を何も持っていなかったため、秘密裏に調査を続けなければならなかった。丁維自身も、崔俊が公正で誠実な役人であることを知っていたため、自分が行った悪事が彼に暴露されるのではないかと恐れていた。そこで彼は皇帝の前であらゆる手段を使って崑崙を悪く言い、ついには崑崙を汴梁の首都から追い出した。 丁維の行為は当時の多くの高潔な大臣たちから厳しい批判を招いただけでなく、庶民からもこの腐敗した役人が非常に嫌われていた。民謡に「世の中に平和を望むなら、目の中の丁を取り除かなければならない。世の中を良くしたいなら、口老を召喚するより良いことはない」というものがあります。民謡の「丁」は、もちろん丁維のことを指します。 こうして、敵を形容する「目に鼎」という表現が次第に普及していった。その後、「丁」は次第に「釘」を意味する「钉」へと変化しました。 「二つの顔」 「二面性」とは、一般的には変装が上手で、言っていることと本心は違う人のことを指します。では、「二面性」という言葉はどのようにして生まれたのでしょうか? 実は、その裏には血なまぐさい物語があるのです! 元朝末期、朝廷の元軍と朱元璋率いる紅巾軍が黄河の支配権をめぐって綱引きを始めたと伝えられています。両軍が互いに戦い、攻撃したため、黄河沿いの人々はひどい苦しみを味わいました。都市の支配者が変わることは珍しくなく、誰が都市に入るにせよ、歓迎の意を表すために門の板に赤、緑、黄色のスローガンを掲げなければなりませんでした。当時、河南省懐清県の人々は、敵対する二つの軍に対処するために、良い考えを思いついた。薄い木の板の片側には元軍を歓迎するスローガン「国家と人民を守れ」を書き、もう片側には反乱軍を歓迎するスローガン「タタール人を駆逐し、中国を復興せよ」を書いたのである。こうすることで、どこから来た人でも、できるだけ早く歓迎の看板を掲げることができます。しかし、この方法は結局災難を引き起こしました。 ある年、朱元璋の将軍である張玉春が軍隊を率いて淮清州に侵入しました。人々はすぐにスローガンを「タタール人を追放し、中国を復興する」に変更しました。張玉春はこれらのスローガンを見て非常に喜びました。彼が喜んでいたちょうどその時、通りに突風が吹き、多くの家の標語が吹き飛ばされ、地元の人々の巧妙な手口が露呈した。チャン・ユチョンは激怒し、2枚の看板を掲げた全員の処刑を命じた。 最近よく言われる「二枚貝」は、実は淮清県の「二面性」から発展したものです。 |
>>: 古代中国と現代中国の地名にはなぜ「陽」という文字がよく使われるのでしょうか?
推薦する
「筆兔草歌曲」が作られた背景は何ですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
古代の草に別れを告げる白居易(唐代)平原の草は毎年枯れてまた生えてきます。山火事は消すことができませ...
ジ・カンさんの人生経験はどのようなものでしたか?なぜ司馬昭は彼を処刑するよう命じたのでしょうか?
済康は、魏の文帝の治世中の黄初5年(224年)、つまり4年(223年)に生まれました。彼の先祖は元々...
『紅楼夢』で賈おばあさんは大観園での賭博事件をどのように解決したのでしょうか?
賈祖母は、施夫人とも呼ばれ、賈家の最高権力者であり、「老祖」と呼ばれています。皆さんも聞いたことがあ...
赤壁の戦いの際、曹操は本当に龐統の計画に気づかなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
李淵には息子がたくさんいたのに、なぜ李世民よりも良心的な人物を後継者に選ばなかったのでしょうか?
李淵の退位は明らかに自発的なものではなかったし、李世民への帝位の継承も当然自発的なものではなかった。...
厳書の『臨江仙・紫山堂三十年』:この詩は物語から始まり、その独創性を示している。
顔叔(991年 - 1055年2月27日)、号は同叔、福州臨川県江南西路(現在の江西省臨川市)の人。...
ミケランジェロの恋人:男性も女性も多数
ミケランジェロは非常にロマンチックな人でした。ロマンチックな人は一般的に情熱的です。ミケランジェロに...
王維の古詩「趙太守を岱州に遣わして青字を得る」の本来の意味を鑑賞
古代詩「趙太守を岱州に派遣し、緑字を得る」時代: 唐代著者 王維天官が将軍星を動かし、漢江の柳の枝が...
閻吉道の果てしない憧れ:「ヤマウズラの空:月桂樹の葉の眉毛で新たに化粧した梅の花」
以下、面白歴史編集長が、厳吉道の『山葵空:梅花新化粧、桂葉眉』の原文と感想をお届けします。ご興味のあ...
探検する!唐代の女性はなぜ胸を露出することを好んだのでしょうか?
唐代を題材にした映画やテレビシリーズをたくさん観た後、唐代の宮殿にいる女性のほとんどが「胸を露出して...
ハニ族の歴史的起源は何ですか?ハニ族の簡単な歴史
ハニ族は主に紅河南岸の紅河、鹿春、元陽、金平の4県に居住し、ヤニ族はシーサンパンナ自治州と瀾滄県に居...
トゥ族の祭祀における「公讃」とはどのような儀式ですか?
ゴンサン公讃とは、犠牲の儀式の際に桑の葉を集団で燃やすことです。特定の日に特定のテーマで行われる儀式...
太平広記・巻59・仙人・太玄女をどのように翻訳しますか?原文の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
楊家の将軍2人、楊三郎の妻と息子は誰ですか?
楊延安と楊三郎の妻と息子は誰ですか?楊三郎の紹介: 楊家将軍の登場人物である楊三郎は、金剣を持つ老将...
古典『関子八行』の原文は何ですか? 「観子八行」の詳しい説明
『管子』は秦以前の時代のさまざまな学派の演説をまとめたものです。法家、儒家、道家、陰陽家、名家、兵学...