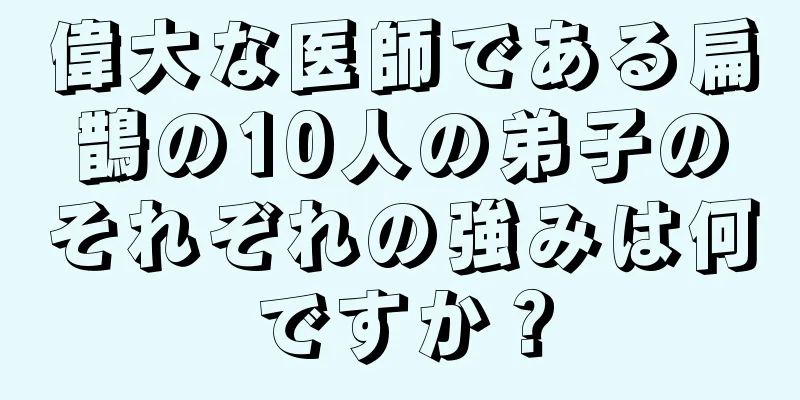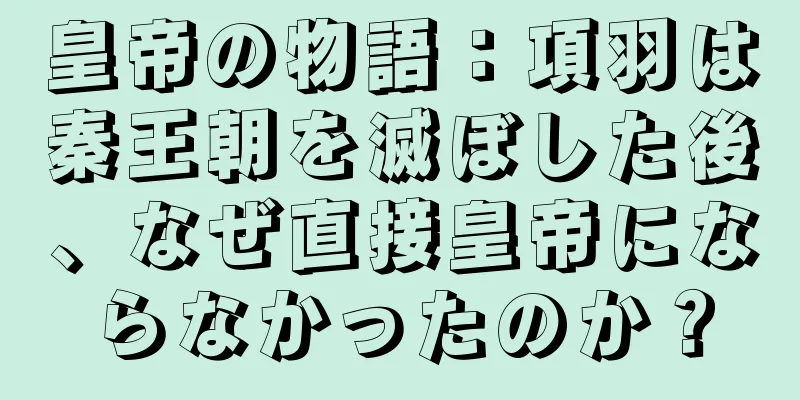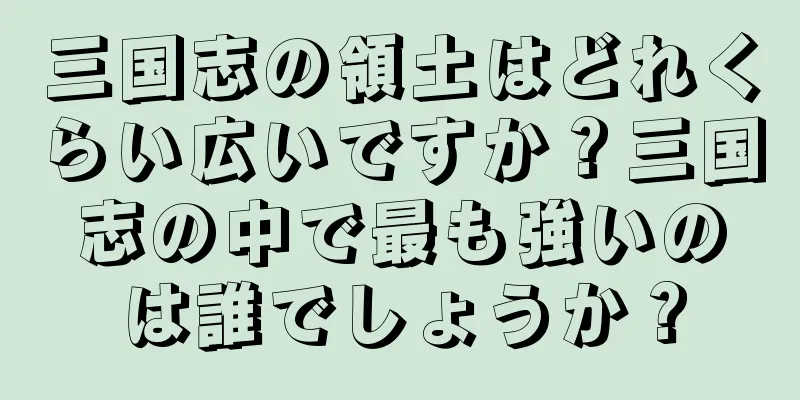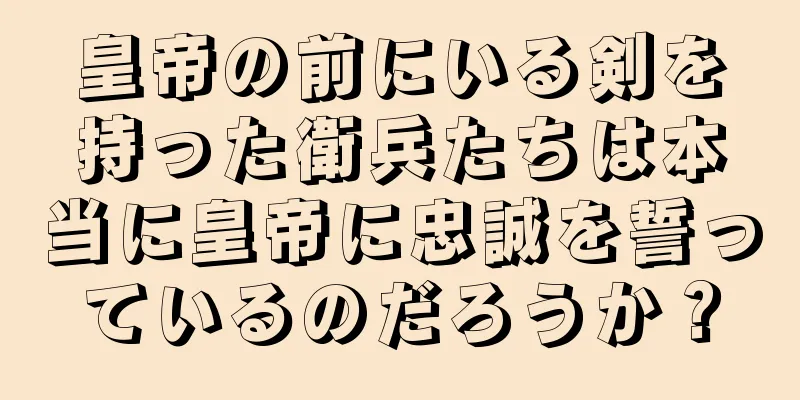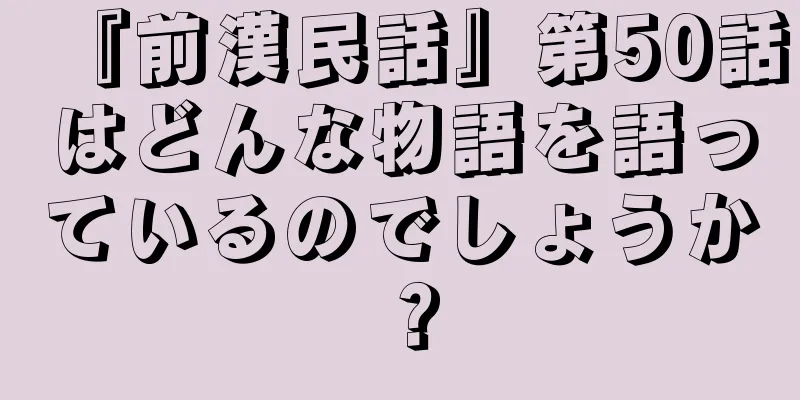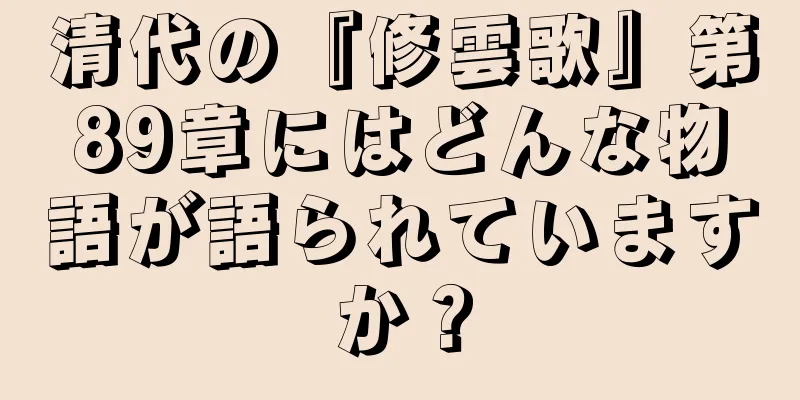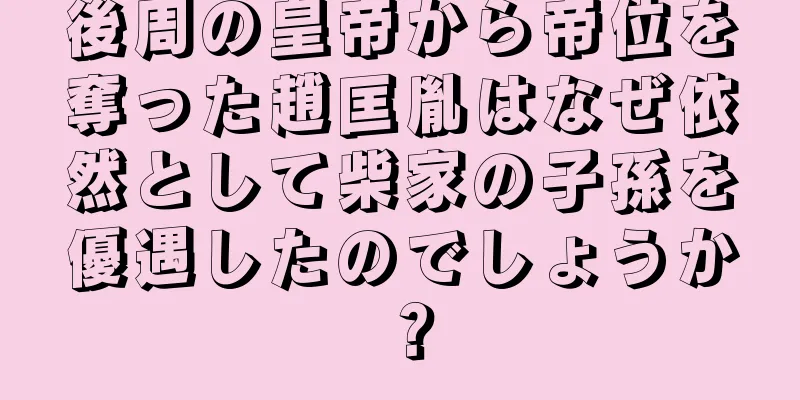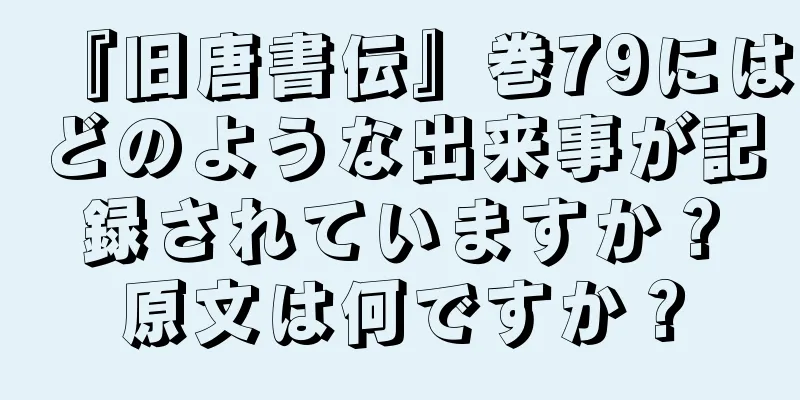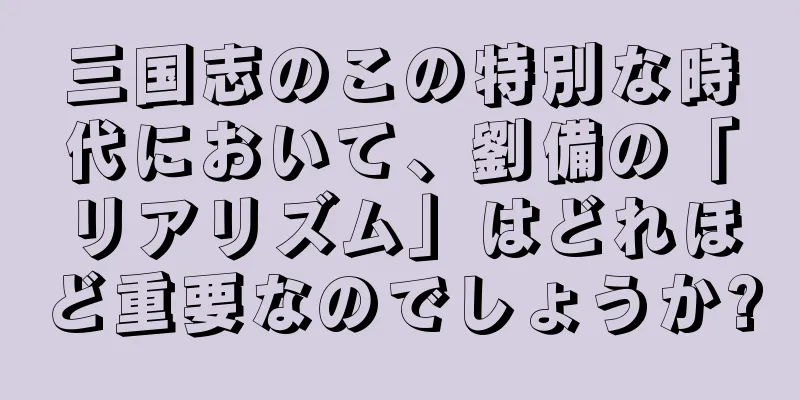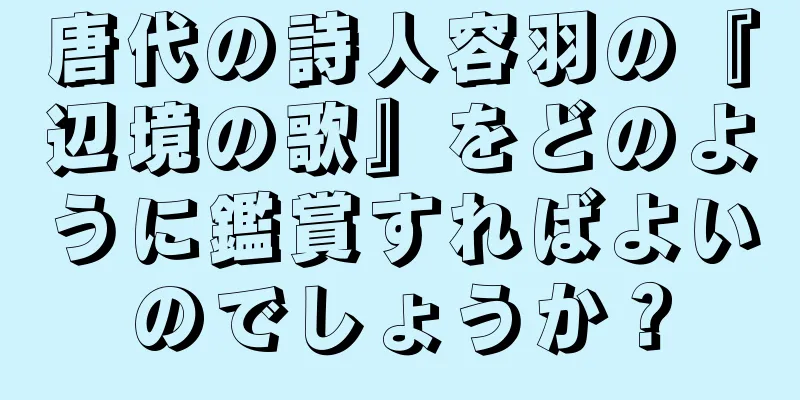蘇軾、蘇軾、蘇哲の関係を解明する:唐宋の八大師の第3部
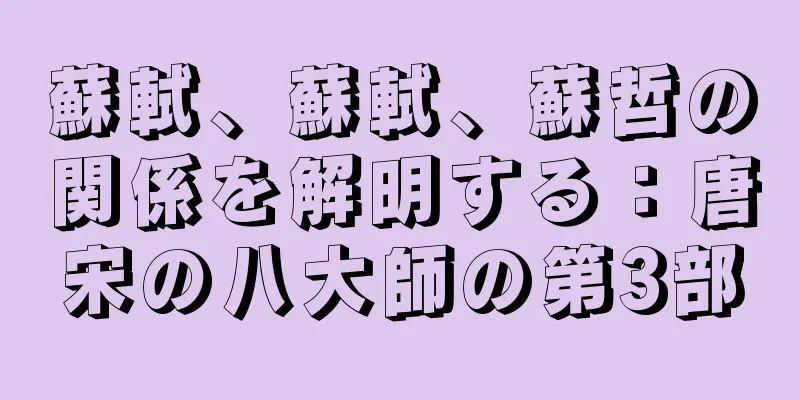
|
蘇荀 蘇氏 蘇哲 蘇遜は北宋時代の有名な作家でした。彼の二人の息子、蘇軾と蘇哲も当時よく知られた人物でした。彼ら三人は総称して「三蘇」と呼ばれていました。父と二人の息子はいずれも多才で、文学に多大な貢献をしただけでなく、政治、歴史学などの分野でも大きな業績を残しました。父親と3人の息子たちの主な紹介を一人ずつ見ていきましょう。 蘇遜は遅咲きの作家で、彼の作品が多くの人に知られるようになったのは50歳を過ぎてからでした。若い頃は読書は好きではなく、祖国の山や川を旅するのが好きでした。彼は30歳近くになってから一生懸命勉強し始めましたが、すべての試験に失敗しました。37歳のときに再び失敗したため、科挙を再び受けないことに決めました。 蘇遜の価値は、無理な科挙を受け続けるのではなく、独学で勉強し、好きなものを読み、最終的に独自の思想理論を形成したことです。 48歳の時、欧陽秀の強い推薦を受けて、彼の記事は次第に有名になった。 3体の蘇像 蘇軾と蘇哲の人生は父親の人生とは全く逆だった。二人は若い頃に科挙に合格したが、人生は非常に波乱に富んでいた。蘇軾は生涯を通じて各地の官吏を務め、地元で目覚ましい業績を残した。また朝廷では礼部大臣を務め、科挙など時代の変化を率直に語った。弟の蘇哲の発言は、彼よりもさらに激しく、鋭く、皇帝を非難し、皇帝は酒とセックスに溺れ、朝廷に時間通りに出席せず、大臣の意見を聞かず、一部の女性や子供の言葉に耳を傾けていると述べた。その結果、彼の発言は法廷内で騒動を引き起こし、多くの大臣たちがそのことについて話していた。蘇哲の才能は元有時代に十分に発揮された。 蘇哲の公式見解 蘇哲は「唐宋八大師」の一人であり、父の蘇勲、兄の蘇軾とともに「三蘇」として知られています。蘇哲は生涯に何度も官吏を務め、二度降格された。彼の人生の浮き沈みもまた、彼の官歴に我々の注意を惹きつける。 嘉祐二年、わずか18歳で科挙に合格し、その聡明さと知恵により兄の蘇軾と同時に進士となった。その後すぐに、彼は亡くなった母親を悼むために都から帰郷した。 嘉祐6年、蘇軾とともに科挙に合格したが、その時は親族を養わなければならないと上官に報告したため、官吏に任命されなかった。その後、大明州知事を務めた。西寧5年、彼は元の法制度を変更することはできないと考え、王安石の新しい法律に強く反対した。 王安石の改革に反対する過程で、彼は河南の知事を務めた。元豊二年、弟の蘇軾は朝廷を誹謗する詩を書いた罪で逮捕され、投獄された。彼は弟を救いたい一心で、官職を利用して蘇軾の罪を償うと手紙に書いた。しかし、蘇軾を救えなかったばかりか、この事件のせいで降格されてしまった。 元豊8年、旧党が朝廷を掌握し、彼は召還されて書記官と右検閲官に就任した。元有四年、朝廷の命により契丹へ外交使節として赴き、朝廷に帰還後、検閲長に任命された。 2年後、彼は尚書有成に任命され、この時点で彼の地位はすでに非常に高かった。元有8年、旧法派は打倒され、新法派が再び政権を握った。邵勝元年、蘇哲は新政策に反対する書簡を書いたため、左遷されて汝州、袁州、雷州に送られ、その後、荀州などに左遷された。蘇哲の人生には栄光の瞬間もあれば、最悪の時期もあった。彼は若くして成功を収めたが、知られざる多くの苦難も経験した。 Su Cheの発音 「浙」は車輪の跡を意味し、部首は「车」、画数は全部で16画です。古代中国語では複数の意味を持っています。 『曹桂兵論』の「轍を見下ろす」は車輪の跡を意味し、『白馬王彪に贈る』の「轍を変じて高山を登る」は車両の通る道筋を意味し、『後記 <指南>」の「轍は交わる」は車両のことである。 人々は蘇哲という文字に親しみを持っているため、「浙」という言葉にもはや馴染みがないわけではありません。 北宋時代の有名な作家、詩人である蘇哲は、唐宋時代の八大童子の一人でした。父の蘇遜、兄の蘇軾とともに三蘇として知られています。蘇哲は学問の研究において父親の影響を強く受けました。彼は主に儒教を学びました。彼が最も尊敬していたのは孟子でしたが、様々な学派の著作も読みました。 彼は政治と歴史の知識に優れていた。政治演説では世界情勢を包括的に考察した。『皇帝への手紙』や『六国論』など、彼の論文は鋭く、非常に的を射ていた。蘇哲は文章を書くことについても独自の考えを持っていました。彼は文章を書くには内面の修養だけでなく、豊かで幅広い経験も必要だと信じていました。そのため、彼は司馬遷が世界中を旅して各界の英雄たちと交流する能力を非常に羨ましく思い、尊敬していました。 蘇哲の筆も非常に特徴的で、「墨竹筆」では竹の形を非常にリアルかつ詩的に表現しています。蘇哲は詩を書き始めた当初は傑出した才能を発揮せず、その作風は兄の蘇軾とは大きく異なっていた。詩作は主に生活や風景の些細な事柄を題材とし、文体は簡素で平易であった。しかし、晩年になって詩を書く才能が徐々に現れ、彼の書いた詩は情緒豊かで感情を詩に盛り込んだものとなった。 蘇哲の名言 蘇哲は北宋時代の有名な作家、随筆家であり、「唐宋八大家」の一人であった。彼は数え切れないほどの作品を書き、多くの有名な名言を残しました。彼は、人としての在り方、物事のやり方、人との接し方、法律の制定などについて、独自の洞察力を持っています。蘇哲が後世に残した精神的な財産を見てみましょう。 教育の面では、蘇哲は「教えを受けても変わらない場合は、罰するべきだ」という見解を述べた。彼は、間違いを犯した人が教育を受ければ、大抵の人は謙虚に間違いを受け入れ、修正するだろうと信じていた。このとき、まだ頑固な人を罰することについては何も言うことはないだろう。この点に関して、蘇哲氏は教育の重要性を強調した。刑法を使って他人を罰するだけでなく、人々を教育し、影響を与えることにも重点を置くべきだ。 人間について、蘇哲はかつて「言葉で他人を批判するのは簡単だが、自分の正義を守るのは非常に難しい」や「自分を正さずして他人を正せる者はいない」といった見解を唱えた。前者は言葉で他人を批判するのは簡単だが、自分の正義を守るのは非常に難しいという意味であり、後者は自分を正さずして他人を正せる者はこの世にいないという意味である。これら 2 つの文の意味は基本的に同じです。どちらも、他人にそうするように求める前に、自分自身が適切に行動する必要があることを要求しています。自分自身が適切に行動していないのに、どうして他人に適切に行動するように求めることができるでしょうか。 物事をなすことに関して、蘇哲はかつて「複雑なことに遭遇しても一つのことのように、危険な状況に遭遇しても平地を歩くように」と「何もすることがないときは深く憂い、何かすることがあるときは恐れない」という見解を提唱した。前者は、複雑なことに遭遇したときは一つのことをしているかのように扱い、危険な状況に遭遇したときは平地を歩いているかのように扱うべきであるという意味である。この観点は、困難に直面しても冷静で落ち着いた態度を保つよう、また冷静で落ち着いた態度を保つよう、他の人に警告することです。後者は、物事が変わっていないときに長期的に考え、何かが起こったときに恐れないようにすることを意味します。危機感を持って事前に準備しておくよう警告するためです。 蘇哲の散文 蘇哲に関する著作は多く、その著作も非常に豊富である。文学界では「唐宋八大家の一人」として知られ、その著作の中では自身の文学思想の内面的な修養と豊富な経験の両方を強調している。 蘇哲の著作の多くは左遷された時期や夜間の暇な時間に書かれたもので、『樓成集』、『春秋集』12巻、『古史』60巻、『龍川別志』8巻、『龍川略史』10巻などがある。蘇哲は文学創作において、自分の思想や感情と芸術的なスタイルの統一性を重視し、執筆の過程は実践に基づいていることを強調した。彼は、個人の作品は他人の作品とは区別される独自のスタイルを持つべきだと要求しています。 彼のエッセイは彼の主要な文学的業績である。彼が書いたエッセイは、構造がしっかりしていて、言語が厳密で、表現が簡潔で流暢で、言葉遣いがシンプルで優雅です。彼の政治エッセイの多くにはこの特徴が見られます。こんなに短い記事でも、トーンの起伏や文脈の変化が反映されており、著者は推論力と論理的思考力が強いです。彼は政治や歴史に関する論文を書くのが得意で、世界を見て現状を分析し、過去を現在に生かし、問題点を鋭く指摘することができた。例えば、『六国論』では、当時の六国の君主たちが世界の大勢を知らず、団結して秦と戦わず、漢と魏の重要な防御壁を失い、その結果六国すべてが悲惨な滅亡に至ったと指摘している。例えば、『黄州快載閣記』では、風景描写、叙情、論考を統合し、叙情の過程で内面の感情を表現しており、これが彼の文章の特徴である。 |
<<: 唐宋の八大家とは誰ですか? 唐宋の八大家の中でリーダーは誰ですか?
>>: 高建礼は本当に歴史上に存在したのか?高建礼が琴を演奏した物語
推薦する
華旭って誰ですか?彼女はどうやって来たのですか?華胥王国ってどんな国?
まだ華旭を知らない読者の皆さん、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介するので、ぜひ読み続けてください〜...
権力を握っていた燕王后はどのようにして倒されたのでしょうか?なぜクーデターに関わった人々は全員宦官だったのか?
安帝は権力を握ってまだ数年しか経っていなかったが、顔光の治世4年(125年)3月、南巡の途中、イェ県...
蘇軾の『董伝』:読書と優雅な気質の必然的なつながりを説明する
蘇軾は北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、作詞、散文、書道、絵画などで大きな業績を残した。彼の文章は...
なぜ誰も秦の始皇帝の暴政に反抗しなかったのか?秦の始皇帝は反乱にどのように対処したのでしょうか?
秦の始皇帝の暴政に誰も反抗しなかったのはなぜか知っていますか? 知らなくても大丈夫です。Intere...
幸せな敵第1章:華二娘は巧みに恋人を認識する
『幸福な敵』は、『貪欲な快楽の報酬』、『喜びの驚異』、『今昔奇譚の第三続編』、『今昔奇譚の第四続編』...
将軍と指揮官は会ってはいけないというチェスのルールはどこから来たのでしょうか?それぞれ誰を代表しているのでしょうか?
チェスでは将軍と指揮官が対戦できないというルールはどこから来たのでしょうか? 彼らは誰を表しているの...
なぜ漢王朝はローマ帝国を大秦と呼んだのでしょうか? 2つの一般的な見解は何ですか?
ローマ帝国といえば、この国が世界に多大な影響を与えた国であることは多くの人が知っているでしょう。しか...
張暁祥の「年女嬌:帆が上がった」:詩全体は悲しみ、後悔、無力感が混ざり合っている
張孝祥(1132-1170)は、名を安国、通称を玉虎居士といい、溧陽呉江(現在の安徽省河県呉江鎮)の...
李和の「献酒の歌」:作者は感謝されないという考えを使って自分の考えを伝えている
李和(790-816)、雅号は昌吉とも呼ばれる。彼は河南省富昌県長谷郷(現在の河南省益陽県)に生まれ...
古代の女性が男性の服装をしていたと知ることは本当に不可能なのでしょうか?理由を説明する
古代に女性が男装していたかどうかを知ることは本当に不可能なのでしょうか?これは多くの読者が気になる疑...
明らかに:古代の特殊武器であるスリングショットも、隠し武器の1つです!
いわゆる隠し武器とは、持ち運びが容易で目立たない武器のことです。隠し武器は一般的にサイズが小さく、隠...
『紅楼夢』で賈正は黛玉と宝柴についてどう思っているのでしょうか?
賈正は、姓を淳周とも呼ばれ、曹雪芹の『紅楼夢』に登場する人物で、栄果屋敷の二代目主人です。今日は、興...
水滸伝における曹政の強さはどのくらいですか?彼とリン・チョンの関係は何ですか?
『水滸伝』の登場人物である曹政は開封県の出身で、林冲の弟子でした。これは多くの読者が気になる疑問です...
『紅楼夢』の林志暁はどんな人物ですか?彼の任務は何ですか?
『紅楼夢』の栄果屋敷の執事、林志暁は、とても控えめな人物です。本日は、Interesting His...
古代中国には、漆器の主な種類が 14 種類あり、どのような模様がありましたか?
様々な物の表面に漆を塗って作られた日用品や工芸品、美術品などを総称して「漆器」と呼びます。古代中国で...