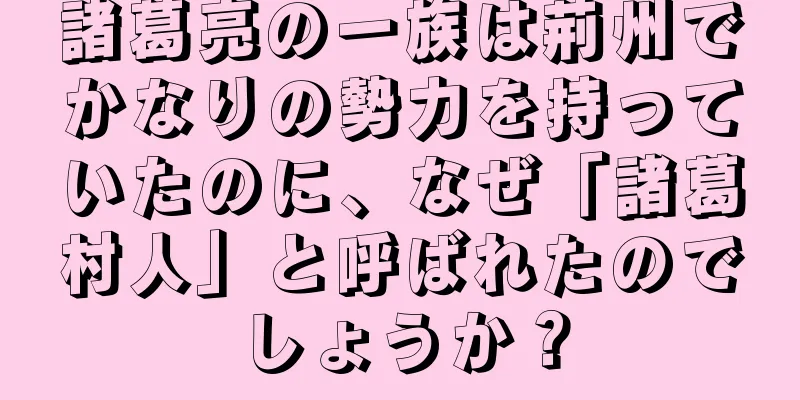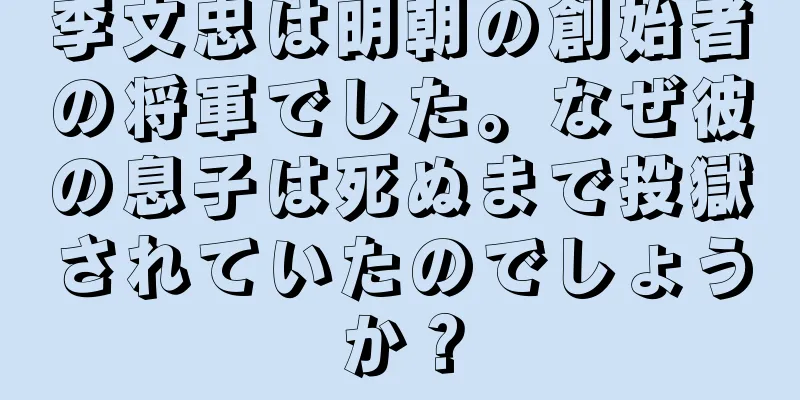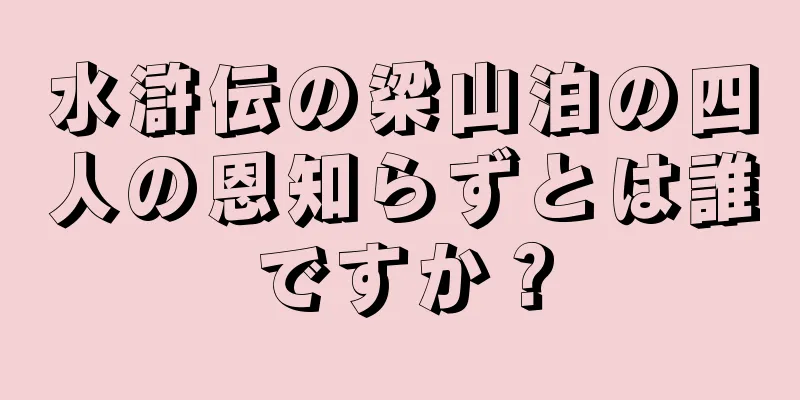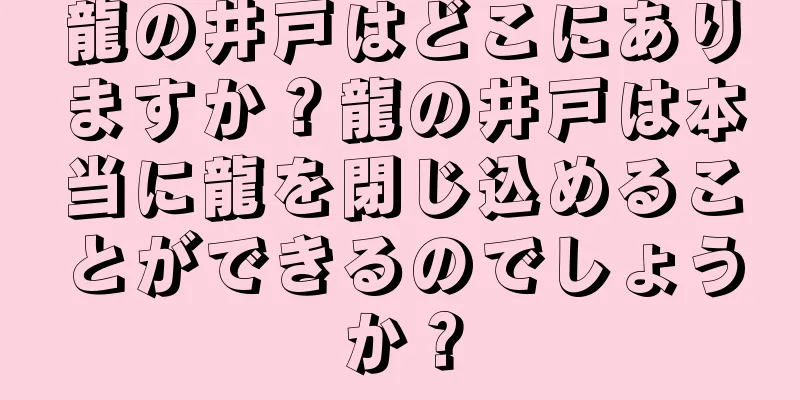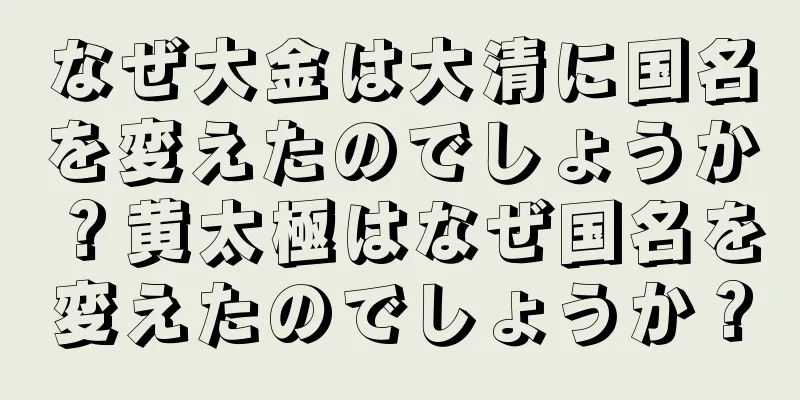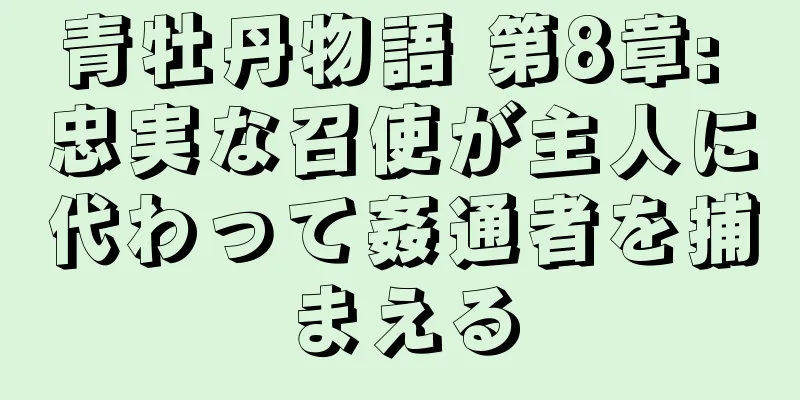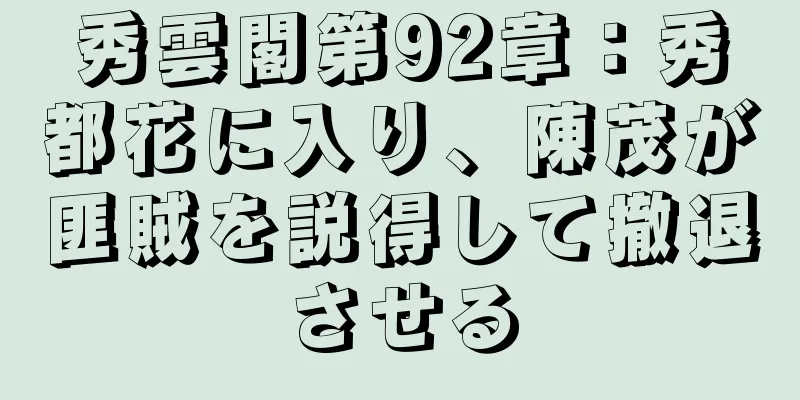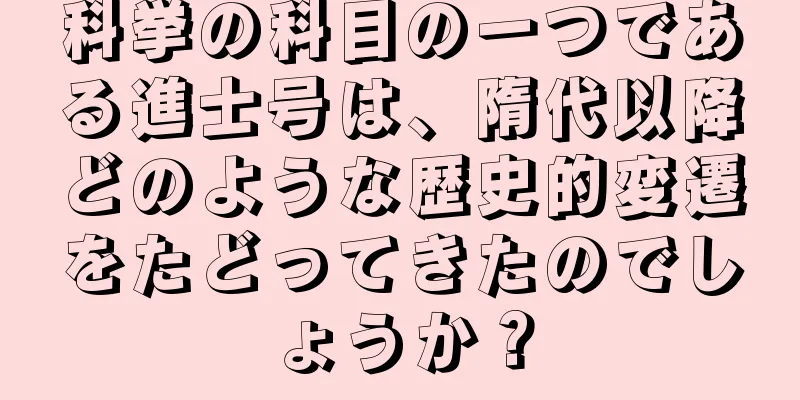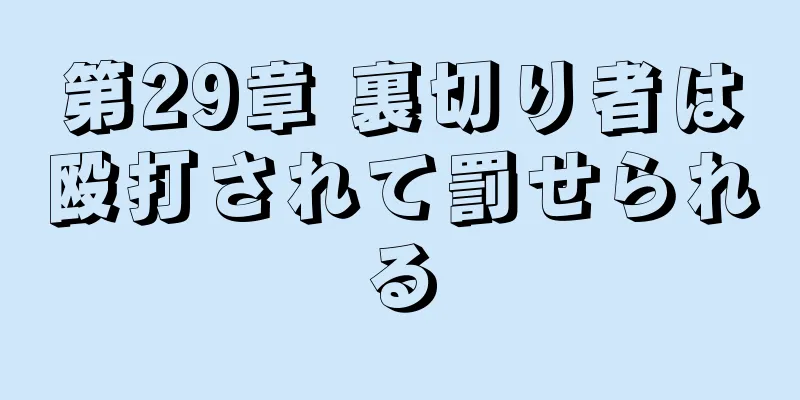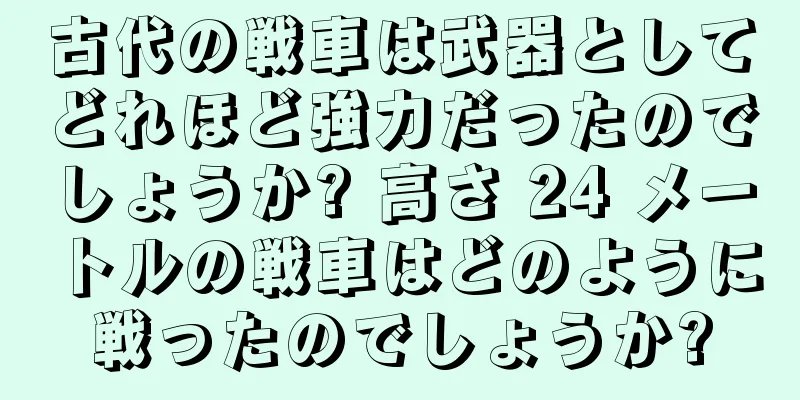解読:烏孫はどのような結婚制度を実施し、桀有公主の再婚をもたらしたのか?
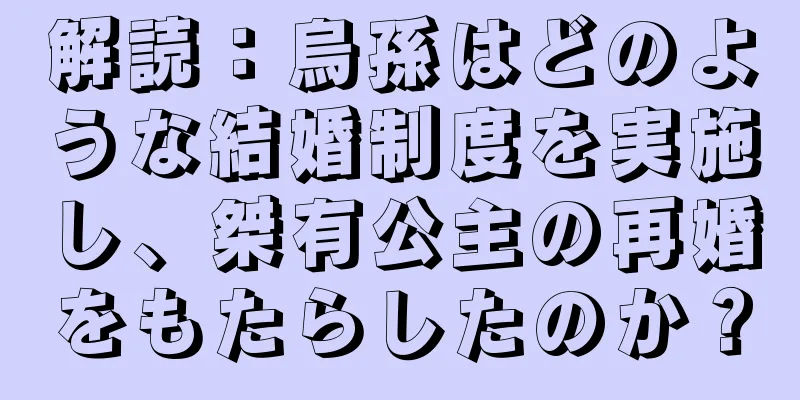
|
匈奴と同様に、烏孫族もレビレート婚を実践していたが、これは原始的な部族集団結婚制度の名残であった。集団結婚では配偶者という概念はなく、女性は部族内のすべての男性に属します。未亡人の財産は、相続人(継子)または夫の親族が相続します。主な理由は3つあります。 1. 烏孫族は広大な草原に散在し、互いに遠く離れていました。西域の国々の間では戦争が頻繁に起こっていたため、烏孫族は外界に対して非常に閉鎖的で、家族間の関係は非常に密接でした。 2. 異なる部族の男女が接触する機会はほとんどなく、未亡人の再婚は困難です。彼女たちの多くは、夫の家族の部族メンバーに養子として引き取られます。 3. 烏孫では、生産は家族単位で行われ、レビラト婚の慣習によって家族の統一性と安定性が維持されている。相続人の実母が高齢の場合、相続人が彼女を扶養することが多く、実母が若い場合は相続人の家族内で再婚する。 レビラト婚は、モンゴル人、カザフ人、キルギス人、ホジェ人、チベット人、満州人など、中国北部と中央アジアの遊牧民の間で一般的な慣習です。カザフ人は、馬が死ぬとその毛皮は所有者の手に渡り、兄弟が死ぬとその妻は弟の手に渡ると公然と言っている。 10 世紀のオグズ族、つまりトルクメン族やウースン族にもこの習慣がありました。韓国人の前身である扶余人や高句麗人にも、未亡人となった義理の姉妹と結婚する習慣がありました(高句麗初期には最高の結婚形態でした)。 前漢の劉邦と匈奴の茅屯然于は王族の結婚を結び、お互いを兄弟と呼んだ。劉邦の死後、茅盾は呂后に結婚を申し込む手紙を書いた。呂后は激怒し、使者を殺害し、軍隊を派遣して攻撃しようとした。俀布大臣は白登の包囲戦を例に挙げて匈奴を攻撃することの危険性を指摘し、手紙を書き直して丁寧に断った。そこで茅盾は両国の習慣が異なると言い訳して逃げ道を作った。その後、烏孫と結婚した禧君公主と桀有公主、匈奴と結婚した王昭君は、いずれも夫の死後、慣例に従って王位を継承した先王の息子と再婚した(禧君公主は孫と結婚した)。 この現象は五夷十六国の時代に顕著になりました。例えば、北斉などの鮮卑族が建てた政権では、皇帝が前皇帝の側室を寵愛するケースもあり、当時南方の漢民族政権からは批判されましたが、実はこれは当時の少数民族政権の慣習でした。 同世代または異世代間のレビラト婚は、元朝に保持されたモンゴルの伝統です。レビラト婚はモンゴル人の間ではほぼ合法だが、漢民族の影響で緩和されてきた。例えば、女性には夫に忠実であり続け、結婚しないという選択肢があるが、男性に妻がいる場合や、2人の年齢差が大きい場合はこの限りではない。漢民族は伝統的な慣習によりレビレート婚に強く反対しており、政府も制限を課している。例えば、元朝の文宗皇帝の直順元年(1330年)には、「自分の土地の慣習に従わない兄弟の義理の妹や息子の継母と結婚する者は、処罰される」という勅令が出された。 満州族には伝統的に、実母以外の兄弟の未亡人や亡くなった父親の未亡人と結婚する習慣がある。例えば、孝荘皇太后がドルゴンと再婚したという非公式の歴史的記録を裏付ける証拠はないが、当時の慣習ではそれは可能だった。しかし、清朝の成立後、漢文化の影響を受けて、転婚の慣習は禁止されるようになりました。 高句麗では、「兄の死後、兄の妻が兄の義理の妹と結婚する」(例えば、三尚王は兄の国川王の妻と再婚した)ことや、未亡人が再婚することが一般的であった。 |
<<: 解読:西域の強国烏孫はどのような政治体制を敷いたのか?
>>: 唐の時代には何人の皇帝がいましたか?その答えは皆を驚かせた。皇帝は32人いたのだ。
推薦する
彭元勲の「六つの醜いもの:昔の東風のように」:ポプラの花穂は、厳しい人生を送った詩人の心に響く
彭元勲は生没年不詳、荀武と号し、廬陵(現在の江西省集安)の出身。景定二年(1261年)、彼は試験に参...
『本草綱目第3巻 諸疾患及び瘡蓋の治療』の具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
「水仙・夜雨」は、元代の徐在思によって書かれた作品で、夜の雨を題材に、故郷を離れて暮らす思いを表現しています。
徐在思は、字を徳克といい、甘いものが好きだったため、天寨というあだ名がつけられた。元代の有名な詩人で...
爾珠容とは誰ですか?爾朱容はどうやって死んだのですか?
爾朱容(493-530)は北魏末期の有力者。北秀容(現在の山西省朔州)の出身。爾竹容の先祖は昔から爾...
古典文学の傑作『太平天国』:裁決篇第3巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
荀攸は曹操に助言を与えて常に助けていたのに、なぜ年老いてから曹操を裏切ったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「治徳二年金官門より」の原文、翻訳、鑑賞
治徳二年、私は北京の金光門を出て鳳翔に戻りました。乾元初頭、左市から華州に転勤し、親戚や友人に別れを...
毛文熙の『隋河柳煙図』は、隋の煬帝の過度の放蕩を柳の煙で風刺している。
毛文熙は、字を平桂といい、高陽(現在の河北省)あるいは南陽(現在の河南省)の出身で、五代前蜀・後蜀の...
朱文は始皇帝とみなされていたが、なぜ彼は自分の息子によって殺されたのか?
五代十国の歴史は我が国にあまり影響を与えなかったため、後梁の始皇帝である朱文についてはあまり知られて...
『紅楼夢』で賈舍を拒絶した後、元陽は何と言いましたか?意味は何ですか
元陽の結婚拒否は『紅楼夢』の多くのストーリーのうちの 1 つです。今日は、Interesting H...
チベット料理 チベットバター茶の生産工程と機能
ご存知の通り、お茶は世界三大飲料の一つです。地域の違いにより、お茶を飲む習慣は場所によって異なり、豊...
『西遊記』で、祝八戒が食べ物を乞うことに失敗したのは本当に怠け者だったからでしょうか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
霊岩閣の24人の英雄の由来:霊岩閣のリストに載っているのは誰ですか
唐代の長安城の皇宮である三清殿の隣に、霊岩亭と呼ばれる目立たない小さな建物がありました。貞観17年(...
羅隠の「猿人の赤いリボンの贈り物に感謝」:李唐の悪化する状況に対する詩人の秘められた不安が込められている
洛隠(833年2月16日 - 910年1月26日)は、元の名は洛衡、字は昭建で、浙江省杭州市阜陽区新...
隋の時代に起こった3つの大きな出来事は何ですか?その一つは科挙制度の創設であった。
隋王朝について語るとき、ほとんどの人は建国皇帝の楊堅を思い浮かべるでしょう。彼が隋王朝の初めに成し遂...