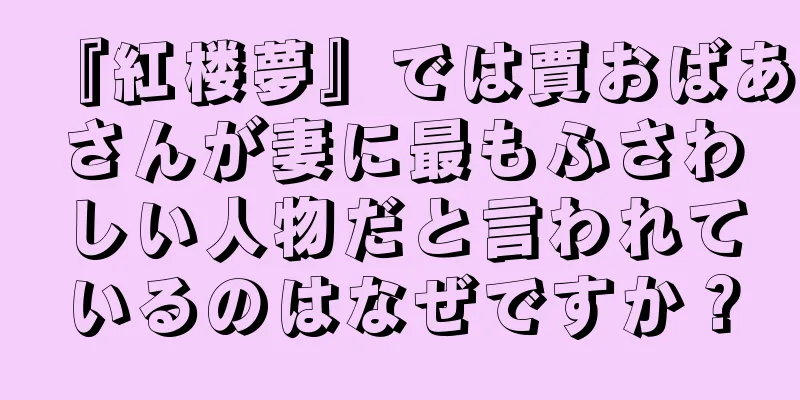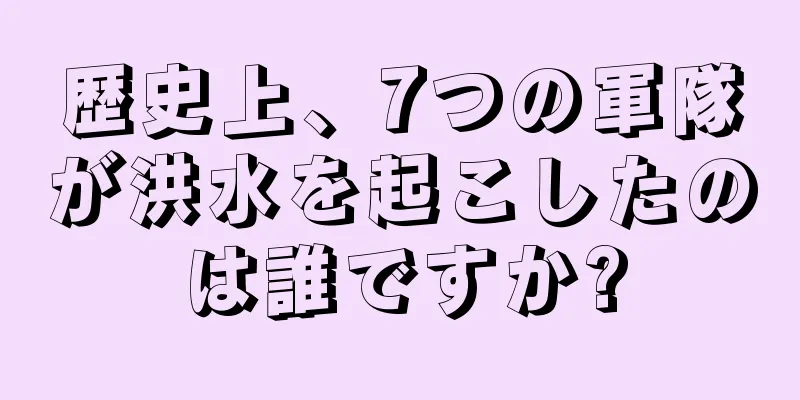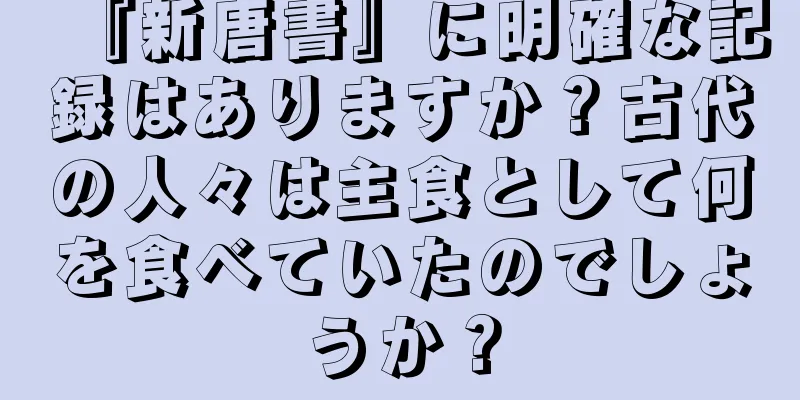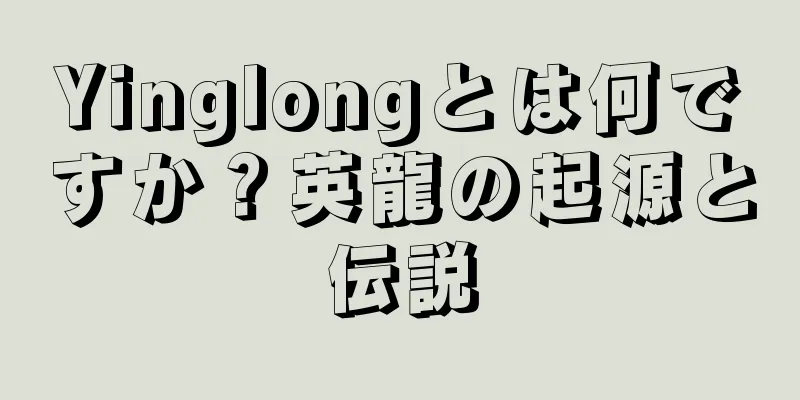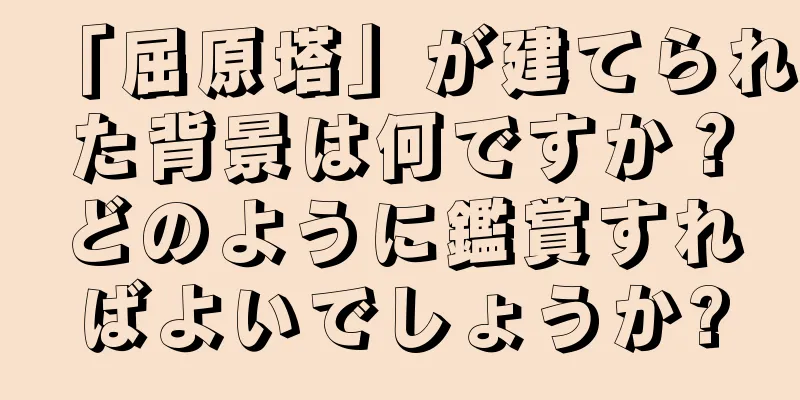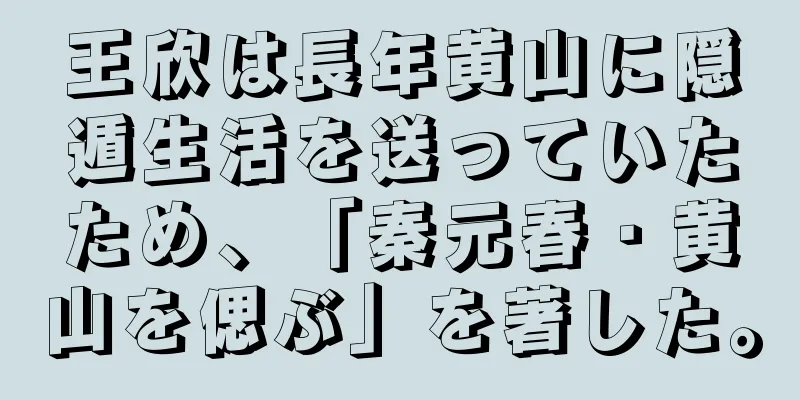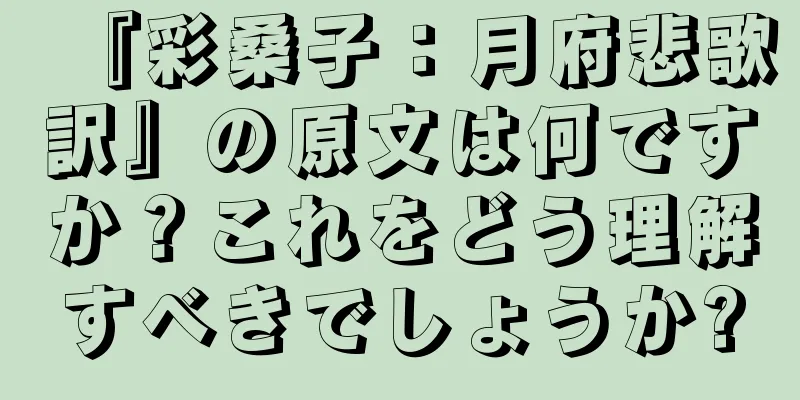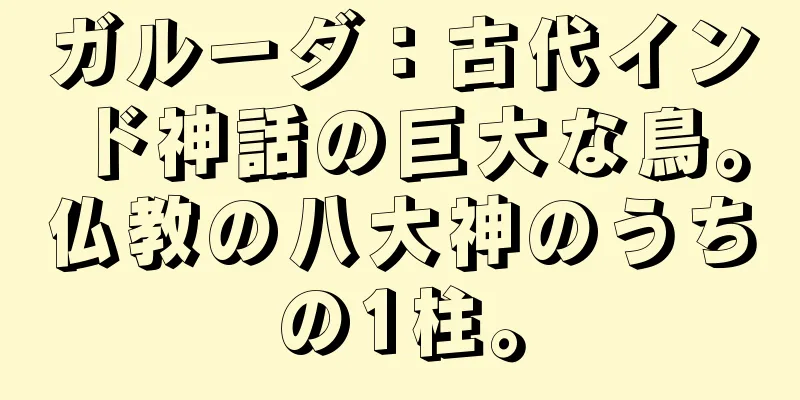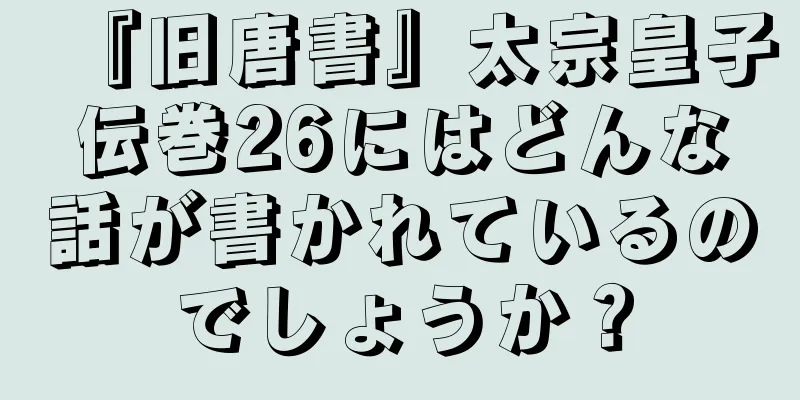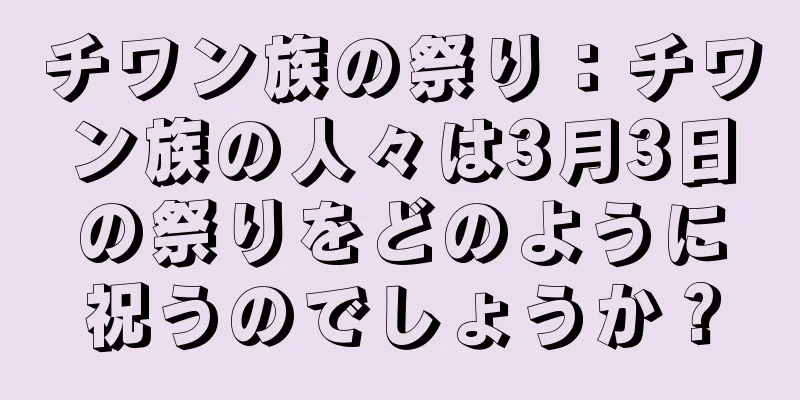仏教とヒンズー教の関係と、両者の違いは何ですか?
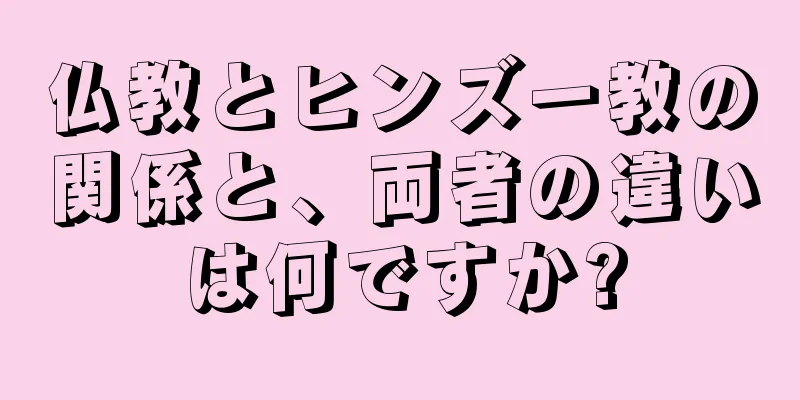
|
仏教とヒンズー教はどちらもインドで生まれた古代東洋の宗教ですが、仏教は世界中に大きな影響を与えてきました。 ヒンズー教はインドのバラモン教です。僧侶になる前、釈迦はバラモン教の信者であり、深い学問と理解を持っていました。しかし、仏陀は何も選択せずにすべてを受け入れたわけではなく、批判的な態度をとり、自身の実践と経験を通じて、バラモン教の主張に対する多くの新しい見解を提示しました。例えば、ヒンズー教では「私」が存在すると説くのに対し、仏教では「無我」と説く。ヒンズー教では「ブラフマン」が宇宙の本体と説くのに対し、仏教では原因と条件によって生じて消滅するすべての法の本質は空であると説く。ヒンズー教では階級を厳密に区別するのに対し、仏教ではすべての衆生の平等を主張する。後のヒンズー教の宗派では禁欲主義や享楽主義の実践が現れたが、仏教では実践の原則として「中道」を主張する、などである。 それぞれ独自の教義体系を持っていますが、2,500年以上にわたって、仏教とヒンズー教はインドで相互に融合し、インドの哲学思想を豊かにしてきました。特に、古代インドの四つのカーストが仏教に改宗し、悟りを開いたとき、そして中期インドにおいても、ヒンドゥー教は仏教を利用して自らの宗派を強化した。仏教の出現は、ヒンドゥー教にその過去に対する深い反省をもたらし、将来の大きな方向性を示したことは明らかである。 ヒンドゥー教入門 紀元前16世紀にアーリア人がインドに侵入し、インドの古代文明が始まりました。自然の山や川を崇め崇拝する他の原始部族と同様に、アーリア人も自らの生存を確保するために、すべての自然の神々を崇拝し、讃え、賛美の歌を歌い、その賛美歌を聖典にまとめて互いに伝え合う必要がありました。後期になると、人々の生活にもっと密接な関係のある神々が最も崇拝されるようになり、アーリア人は次第に「多神教」から「唯一神への信仰」へと移行していきました。 神と交信するために、犠牲を捧げることは重要な行事となりました。司祭は最高の権威を持ち、自分自身や他人のために犠牲を捧げ、神聖な経典を教えることができました。そのため、厳格な身分制度の社会において、僧侶はバラモンの最高位の階級として崇められ、「供儀は万能である」という神聖な権威のもと、神政色の強いバラモン思想が誕生した。 バラモン教では、「ブラフマン」は宇宙現象の存在論であり、人間の生命現象は「私」であり、宇宙の万物は「私」によって生まれたため、「ブラフマンと私」は本来一つであると考えています。人間はこの真理を理解していないため、輪廻転生で苦しまなければなりません。ブラフマンと私の一体性を理解することによってのみ、人間は解放されることができます。この考えは、紀元前6世紀に反バラモン教の思想家が現れるまで、当時のインド社会に浸透していました。彼らは犠牲に反対し、瞑想、苦行、享楽を通じて解放されることを主張しました。当時、苦しみを培い、幸福を培うという考え方が広まっていたことを考慮して、仏陀は、苦しみにも幸福にも傾かない中道の見解を修行の根本原理として提唱しました。 アショーカ王とカニシカ王の治世中、インドでは仏教が主流となり、バラモン教は衰退しました。紀元4世紀、バラモン教はグプタ王朝の強力な支援を受け、仏教や他の宗派の思想と融合し、大きな変化を遂げました。自らを「新バラモン教」と称し、かつての地位を回復しようとしました。これが今日「ヒンドゥー教」と呼ばれるものです。ヒンドゥー教の多くの宗派の中で、最も重要なのはヴィシュヌ派、シヴァ派、シャクティ派です。 8世紀以降、ヒンドゥー教の主たる思想家であるシャンカラは、バラモン教の根本的な教えを基礎に、ジャイナ教と仏教の利点を吸収し、ヒンドゥー教における宗教的実践の要素を増やし、元々の煩雑な理論を薄め、ヒンドゥー教は当時の知識人の主流となった。イスラム教がインドに侵入するまで、仏教は厳しい迫害を受けていましたが、ヒンドゥー教はイスラム教の思想と融合していたため、一部の地域では依然として大きな影響力を維持していました。 近代では、西洋の植民地主義の侵略と西洋文化の導入により、ヒンズー教は広範囲にわたる宗教改革を開始し、古代ヒンズー教に存在したカースト制度、偶像崇拝、複雑な宗教儀式、未亡人の焼き討ちなどの無知な現象に反対しました。しかし、今日に至るまで、ヒンズー教は依然としてインドで最も影響力のある宗教であり、大多数の人々が信仰している。人種や階級による不平等な扱いや未亡人の生き埋めなど、ヒンズー教の多くの民間慣習は完全に根絶されたわけではない。 仏教とヒンズー教の思想の違い 仏教もヒンズー教もバラモン階級を中心としたインドで生まれた宗教です。そのため、ヒンズー教は仏教だと誤解している人が多くいます。実際、ヒンドゥー教はヴェーダの啓示、供儀の全能性、ブラフマンの至高性という3つの大原則を持ち、神政色が強いのに対し、仏教はヒンドゥー教本来の全能性を否定し、4つのカーストの平等を主張し、すべての人が仏性を持っていると信じ、現実の生活の検証を通じて実際の実践と実現に重点を置いています。したがって、2つの宗教の異なるアピール方法は、それぞれ独自のイデオロギー体系を形成しました。 異なる信念 ヒンズー教はヴェーダの思想とブラフマンの無限の権威を信じており、犠牲を通して人々と神は直接コミュニケーションをとることができます。人々は自然を賞賛し、自然を讃える歌を歌い、特にブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァといった自然の神々を崇拝します。 3大神はそれぞれに役割があり、宇宙のすべてを共同で支配しているため、人々は彼らを崇拝しています。ブラフマーは宇宙を創造し、人類の運命を支配しています。ヴィシュヌは宇宙の平和を維持し、善を報い悪を罰する恐れのない精神を示しているため、人々から最も尊敬されています。シヴァは宇宙を破壊するだけでなく、悪魔を征服し、現世の活動を再生(再現)することもできます。したがって、人々は神の力に従い、主神から与えられた命を崇拝し、神権政治の考えによって制限された既存の不平等なカースト制度に厳密に従うことしかできません。 仏教は神の存在を否定しませんが、神は支配者でも創造主でも唯一の存在でもありません。神は祝福を積み重ね、偉大な超自然的な力を持っていますが、物事の根源と自然の空を理解する般若の知恵を持っていなければ、依然として六道輪廻の衆生の一人に過ぎません。仏陀は完全に悟りを開いた存在です。バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラのいずれであっても、戒律、集中、知恵に従い、一歩一歩実践すれば、阿羅漢、菩薩、仏陀の地位に達することができます。仏性とは悟りのことです。すべての人は物事の根源を悟る能力を持ち、仏陀になる可能性を持っています。これは、ブラフマーが創造主であるというヒンズー教の信仰とはまったく異なります。 カルマと輪廻 ヒンズー教では、生と死の輪廻の根本的な原因はカルマにあると信じられています。カルマとは、太古の昔から人々の無限の「愛」と「無知」によって生み出される善と悪の行為のことです。こうして、「無知から始まり、欲望に基づいて意志を形成し、意志から業を形成し、業から結果」という輪廻のサイクルが形成されたのです。また、ヒンズー教では、「私」が人生の輪廻の主人公であると信じられています。人間の身体は「私」から生まれ、人間の活動も「私」によって引き起こされるため、「私」は常に存在します。今生の苦しみは前世の行為によって引き起こされます。今生の善悪の行為も前世のカルマと結びつき、来世の人生に影響を与えます。このことから、バラモン教の輪廻転生の概念と業の理論は三界を通じて一定であり、「本当の」自己という考えに基づいており、真の自己の理論と結びついていることがわかります。 仏教は「恒久的な自己」の理論を否定し、業は固定された「自己」に付随するものではなく、生命継続の原動力であると信じています。つまり、輪廻における「私」は多くの因縁の組み合わせから生まれ、外部の肉体と、感情、思考、行動、意識などの内部の精神機能で構成されています。さらに、それぞれの原因と条件は、他の原因と条件の組み合わせの結果です。したがって、縁起の空虚の中では、常に変化し、一瞬で集まり、破壊され、人々は自分の望むことをすることができません。したがって、永遠で不変の「本当の私」は存在しません。薪を燃やすとき、それぞれの炎は突然上がっては消えますが、火自体は燃え続ける状態で広がり続けます。多くの因縁が重なってできたこの生命は「無明を父、貪欲を母」として、過去の業の結果を背負いながら六道を循環している。したがって、仏教の輪廻の概念は、時間と空間の無限の循環における三生の因果関係において、「人は自分の行いによって報われる」というカルマの考えを確立することです。 実践を通して解放するという思想 形式的には、仏教とヒンズー教は精神修行を通じて肉体的および精神的苦痛からの解放を主張していますが、内容的には、ヒンズー教は「ブラフマンとアートマンは一つである」ことが解放であると主張しています。解放への道は、ヴェーダを学び、供儀を行い、施しをし、苦行を実践するほかに、名声、富、妻、子供、親戚、友人を捨て、僧侶になり、ヨガと瞑想を実践し、心を静めなければなりません。自分自身を知ることで、「ブラフマンとアートマンは一つである」という知恵を得て、「ブラフマンとアートマンは一つである」という真の解放の境地を実現することができます。仏教は異なる見解を持っています。実践の面では、自己認識を重視し、解脱は四諦の個人的な実現を通じて達成されなければならないと信じています。縁起の考えの指導の下、八正道をたどり、「無我」の究極の空を達成します。 ヒンズー教では、戒律の遵守に関して、ブラフマチャリア段階、家庭段階、森林段階、放浪段階という人生の4つの段階を実施しています。各段階で規定された義務に従って、解放を求めるために犠牲、祈り、戒律の遵守、禁欲を行うことに専念します。仏教には、在家の信者の他に、厳格な戒律を指導理念とする僧院組織もあります。どちらも「五戒」に従いますが、仏教は生活の中での実践を重視しているため、従いやすいです。 ヒンズー教の苦行や礼拝の厳しい条件と比較すると、仏教はすべての法が相互依存的で相互条件付きであると信じており、したがって苦しみにも幸福にも偏らない中道の修行と、世界とすべての生き物を助ける利他的な行動を採用しています。 仏教がヒンズー教に与えた影響 バラモン教の聖典には、カースト制度におけるバラモンはブラフマー神の口から生まれ、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラはそれぞれブラフマー神の腕、脚、足から生まれたと記録されています。異人種間の結婚は認められておらず、ブラフマン教に入信できるのは上位 3 つのカーストのみであった。カースト制度のもとで形成されたこの人種差別は、仏教の開祖である釈迦牟尼仏が「四つのカーストの平等」という思想を提唱するまで、何千年も奴隷状態に陥っていたインドの人々に光をもたらすことはありませんでした。 当時の社会的背景から、釈迦はバラモン教の人種制度を承認しませんでした。彼自身はクシャトリヤ王族の一員であったが、クシャトリヤの権威を利用して民衆を支配し抑圧することは望まなかった。それどころか、仏陀は慈悲と平等の真理を用いて、厳格な階級制度に断固として戦いを宣言したのです。そのため、菩提樹の下で悟りを開いたとき、彼は「地上の生きとし生けるものはすべて如来の智慧と徳を備えている」という平等の原理を説き、当時の人種制度に抑圧されていた人々に、運命は天によって決められるものではなく、神でさえ私たちを行商人にすることはできないと教えました。私たちが今日このような違いを持っているのは、私たちの過去の身、口、心の行為によるものです。誰も私たちを支配することはできません。私たちを支配できるのは私たち自身だけです。私たちのさまざまな経験は、私たち自身の行為によって引き起こされるので、宇宙にはいわゆる「固定された」「不変の」「永遠」の要素は存在しないことがはっきりとわかります。すべては、瞬間ごとに変化しています。したがって、その本質は「空」であり、常に同じ人種であるということは不可能です。4つのカーストの人々は皆平等です。 したがって、シュードラは常にシュードラであるわけではなく、バラモンは常にバラモンであるわけではありません。たとえば、ウパリはもともとシュードラ族の理髪師でした。後に、彼は仏陀の十大弟子の中で戒律を守る最も優れた人物として尊敬されました。マダナはシュードラ族の社会から疎外された女性でした。彼女はアナンダの美しさに惚れ込み、仏陀の教えに従って尼僧となり、後に阿羅漢の身分を得ました。ニティはもともとシュードラ族の糞収集家でした。僧侶になってから懸命に努力し、阿羅漢の地位を獲得しました。釈迦の十大弟子の中で、舎利弗と目連はそれぞれ最も賢く、最も優れた超能力者でした。彼らはもともとバラモン教の指導者でした。釈迦が「すべての法は因縁から生じ、すべての法は因縁から消滅する。私の釈迦、大僧正は常にそうおっしゃる」とおっしゃったのを聞いて、彼らは釈迦のもとで仏教に改宗し、大阿羅漢の地位を得ました。 これらの事実が証明しているように、外的な階級の区別は、人々が解放されるかどうかを決定するものではありません。誰もが仏陀の縁起と空の教えに従って実践する限り、必ず涅槃と解放の彼岸に到達できるでしょう。 さらに、ヒンズー教は仏教の多くの習慣や信仰を吸収してきました。仏教がなければ、ヒンズー教が現在の状態になることは決してなかったでしょう。マハトマ・ガンジーが言ったように、仏教はヒンズー教に新しい命、新しい意味、新しい解釈を与えました。たとえば、ヒンズー教徒はかつて、羊や馬、さらには人間を神への供物として殺すことで幸福がもたらされると信じていました。後に、仏教のカルマの考えにより、殺さないことが第一の美徳とみなされるようになりました。仏教がヒンズー教に与えた影響は、ドラヴィダ地方の寺院組織や僧侶の規律、シャンカラの哲学、そして純粋に宗教的な範囲を超えたインドの論理の発展にも見られます。 以上の議論から、仏教の教えが他の宗教を超越していることは容易に分かります。ヒンズー教の伝統的な神への信仰は、結局のところ、人間の肉体と精神の苦しみや束縛を解消し、究極の解放を達成することはできず、むしろ、厳格なカースト制度を堅持しながら、すべての生き物の既存の平等な尊厳を破壊しています。一方、仏教は、内なる意識を育むことに重点を置いています。この「意識」が究極まで探求されると、仏性が完成します。したがって、仏教では、すべての人に仏性があり、誰もが仏になれると説いています。この平等な扱いは、宇宙のすべてのものは縁起を担いで相互に依存し合っているという仏陀の認識から来ており、インドラの網のように、網の中の各ビーズは無限の光を反射し、その無限の光は同時に網の中の一つのビーズに含まれ、絡み合って無限に続くのです。したがって、いかなる法も単独で生じることはなく、法は同じ体であり、互いに共存しています。この縁起と自性の欠如の理論は、「ブラフマン」は永遠であるというヒンズー教の主張とはまったく異なります。 縁起と無我の理を理解すれば、万物は一つであり、私はすべての生き物であり、すべての生き物は私であることがわかります。心と仏とすべての生き物の間に違いはありません。誰もがお互いを尊重し、寛容になれば、仏教の真の精神である「無縁の大悲、衆生大悲」という大乗菩薩思想をさらに発展させることができます。 仏教とヒンズー教の闘争(西暦7世紀~11世紀) インドは昔から宗教色が強い地域です。ヴェーダ宗教の原型は紀元前1500年頃に現れ、比較的成熟したバラモン教は紀元前900年頃に現れました。紀元前500年頃には「諸宗教勃興」の時代に入りました。仏教が急速に興隆し、ジャイナ教やチャールヴァカなどの「六宗派」も発展しました。同時に、伝統的なバラモン教の中にも「六つの哲学学派」が生まれました。仏教は長い発展の過程を経て、まずさまざまな宗派に分裂し、その後、本来の宗派とは異なる「大乗」仏教が出現しました。バラモン教は、ある程度の挫折を経験した後、徐々により成熟したヒンズー教へと改革されました。同時に、遠く離れたアラビア半島で新しい宗教が出現しました。それは、ユダヤ教とキリスト教の一神教の思想を批判的に吸収し、アラブ国家の軍事的征服を媒介として、すぐに大西洋岸からインダス川までの広大な地域に広まりました。しかし、7世紀から11世紀にかけてのインドでは、最も影響力のある宗教はヒンドゥー教と大乗仏教と小乗仏教でした。 インドにおける仏教の発展は多くの紆余曲折を経てきました。マウリヤ朝やクシャーナ朝の君主たちは仏教を積極的に推進し、一時は国教、あるいは国教に近い地位を獲得したが、その後のグプタ朝や南インドの小国の君主たちはことごとくバラモン教を国教とした。仏教は保護されていたものの、その発展の勢いは衰えていた。 西暦7世紀、ハルシャ帝国は再び北インドで短期間の統一を達成しました。ハルシャ王は仏教を積極的に推進し、仏教復興の時代をもたらしました。有名な仏典翻訳者の玄奘三蔵もハルシャ王の治世中にインドに到着しました。しかし、仏教の発展は明らかに衰退の傾向を示しており、ハルシャ帝国の崩壊とともに、仏教の黄金時代は永遠に失われました。仏教はセイロン、東南アジア、中国、韓国、日本で大きな成功を収めたが、その起源であるインドでは衰退し、デリー・スルタン朝の征服者たちが最後の一撃を加え、インドから完全に消滅した。インドにおける仏教の衰退は主に以下の理由によるものだと思います。 まず、仏教における宗派分裂、特に大乗仏教と小乗仏教の分裂は、仏教の発展に深刻な影響を及ぼしました。仏教はキリスト教やイスラム教とは異なり、創始当初から厳格な組織や統一的な管理体制があったわけではありません(仏教全体の編纂活動は何度かありましたが)。そのため、釈迦の死後100年も経たないうちに、原始仏教は仏教の宗派に分裂し始めました。西暦 1 世紀までに、それまでの宗派とは異なる「大乗」仏教が出現しました。 「大乗」は世界観や道徳観において本来の「小乗」とは大きく異なり、小乗を激しく貶め、敵対する存在である。仏教は、バラモン教とそこから派生したヒンドゥー教からの激しい挑戦に常に直面してきました。当時、大乗仏教と小乗仏教の宗派間の内紛により多くの小さな仏教国が困惑し、仏教のさらなる普及を妨げていました。その後、大乗仏教の中から「中観派」や「瑜伽派」などの宗派が生まれました。玄奘三蔵が7世紀にインドに到着したとき、彼が目にしたのは「それぞれに長所を持つ十八の宗派、それぞれに居場所を持つ大乗と小乗」でした(『大唐西域記』巻10)。当時、小乗を信仰する国は大乗を信仰する国よりまだ多く、大乗と小乗の競争はかつてないほど熾烈でした。しかし、玄奘三蔵の推測によれば、ハルシャ帝国の仏教が最も発達した地域でさえ、仏教徒は人口の半分しか占めておらず、他の地域でも同様であった。宗派間の分裂により、仏教の教えはますます複雑になっていった。僧侶たちは長い間哲学的な議論に没頭し、現実の生活から大きくかけ離れた状態だった。彼らが下層階級の大多数の支持を得ることは、もちろん不可能だった。 第二に、ヒンドゥー教と仏教の区別がますます小さくなり、仏教の生存空間が圧迫されつつある。仏教とジャイナ教はともに、バラモン教の「ヴェーダの啓示、供儀の全能性、ブラフマンの至上性」という3つの原則を厳しく批判してきました。それ以来、バラモン教は長い緩やかな変化の期間を経て、多神教から3つの主要な神の崇拝へと徐々に変化し、「ブラフマンとアートマンは一体」という一神教の萌芽的な形を生み出し、神学理論において大きな進歩を遂げました。また、宗教儀式の大幅な簡素化も実現し、カーストによる抑圧もある程度緩和されました(ただし、不本意な緩和でした)。ヒンドゥー教も厳格な組織を持たず、仏教よりもさらに緩い宗教ではあるが、民俗習慣に深く根ざしており、仏教とは比べものにならないほどの深い歴史的蓄積と大衆的基盤を持っている。ヒンドゥー教は極めて包括的で柔軟性があり、いつでも異教の神々を自らの神々の集合体に吸収することができます。最後には、仏陀はヒンドゥー教の神ヴィシュヌの化身でもあると宣言し、仏教を同化・吸収するという目的を達成しました。 8世紀のヒンドゥー教改革者シャンカラは、神学的な考えから組織の形態まで、あらゆる面で仏教から学びました。改革されたヒンドゥー教と大乗仏教はすでに非常に近いものでした。しかし、大乗仏教は釈迦を神格化し、「三世十方の仏」や大小さまざまな菩薩を創造し、釈迦本来の教えに反し、ヒンドゥー教の主神崇拝にますます近づいていった。西暦7世紀に仏教の中に新たな「密教」が出現したが、これはヒンズー教の性崇拝と全く同じものであり、仏教の独自性は失われた。この時点で、仏教はヒンドゥー教との闘争においてもはや何の優位性も持たず、徐々にヒンドゥー教に同化されていった。 再び、インドの商業の衰退により、仏教は重要な支持者を失った。インド仏教では昔から商人が中心であり、原始仏教徒の中に商人の割合が非常に多い。仏教が急速に広まったのは、主にインドの商業、特に外国貿易の発展によるものでした。バラモン教は、厳格な社会組織を持つ極めて保守的な宗教です。人口移動に強く反対し、海上貿易さえも大罪とみなしています。これでは商人の支持を得ることは絶対にできません。バラモン教の厳格なカースト制度は、ヴァイシャカースト以外の人々がビジネスに従事することを制限しており、これは当然、ビジネスで富を得たいと思っていたクシャトリヤにとっては不快なことであった。一方、仏教は都市文化や商業文化と密接な関係があり、商業活動に理論的な支えを与えています。マウリヤ朝とクシャーナ朝が北インドで大規模な統一を果たし、商業活動が活発化し、それに伴い仏教も大きな発展を遂げました。しかし、ローマ帝国の衰退とインドの政治情勢の変化により、インドの対外貿易は西暦5世紀以降徐々に衰退していきました。西暦6世紀半ばまでに、インドと東ローマ帝国およびペルシャとの貿易は基本的に停止し、海上貿易は低いレベルでしか維持できなくなりました。西暦7世紀にアラブ帝国が台頭した後、アラブ人は徐々にインド洋、特にインド西海岸の海上貿易を支配するようになり、インド商人の力はさらに衰え、仏教への支援も自然に減少しました。さらに重要なのは、外国貿易によって金や銀などの貴金属を海外から輸入することができなくなったため、インドの通貨価値が下がり、商品経済が抑制され、農村の自然経済の地位がさらに高まったことです。これはもちろん、自然経済に根ざしたヒンドゥー教の発展には有利でしたが(人口の流動性が低下したため、ヒンドゥー教のカースト制度もより安定しました)、商品経済に適応した仏教の発展には不利でした。 第四に、中世におけるインドの長い分裂は、仏教よりもヒンズー教に有利に働いた。古代インドの歴史において、マウリヤ朝、クシャーナ朝、ハルシャ朝など、比較的統一性の高い大帝国は、いずれも仏教を高く尊重していた。グプタ朝はバラモン教を国教としていたが、仏教を保護する政策も採った。インドの各地域の経済や文化状況は大きく異なっていたため、帝国は統治の安定性を維持するために比較的統一されたイデオロギーを必要としていました。当時、バラモン教はまだ改革を完了しておらず、そのイデオロギー体系は未成熟でした。この条件に最も適した唯一のイデオロギーは仏教でした。統一された帝国内では、物質的および文化的交流が比較的頻繁に行われ、農村の自然経済が影響を受け、バラモン教(後にヒンドゥー教)よりも仏教が好まれました。バラモン教はカースト制度を重視し、人口の移動を禁止したため、統一された帝国に遠心力をもたらし、地元の分離主義的傾向を悪化させるだけでした。特にクシャーナ朝のような外来民族が築いた帝国では、その支配者はバラモン教のカースト制度の下では「不浄なクシャトリヤ」としかみなされず、土着のバラモンやクシャトリヤよりも地位が低い。彼らはそのような扱いに耐えられるはずもなく、カースト制度の影響を打ち消すために仏教を積極的に推進するしかなかった。しかし、ハルシャ帝国の分裂以来、インドは500年間、比較的統一された帝国を持たなかった。北インド地域でさえ、長年にわたり国家間の戦争状態にあった。封建的分離主義の状況は極めて混沌としており、国家間の経済的つながりは厳しく抑制され、自給自足の地方経済が絶対的な優位を占めている。ヒンドゥー教は、この機会を利用して繁栄した。分裂状況が常に深刻だった南インドでは、ヒンドゥー教が常に支配的な地位を占めてきました。これは、仏教が触媒として統一された政治状況を必要とするのに対し、ヒンドゥー教は分裂した政治状況で繁栄することをさらに証明しています。 第五に、西暦7世紀と8世紀に出現したシャクティ教やバクティ教などの新しいヒンズー教の宗派は、大衆に強い魅力を持っています。昔のバラモン教は女性を差別し、厳しいカースト抑圧があったため、多くの女性や低カーストの人々が仏教に改宗せざるを得ませんでした。しかし、シャクティ教、バクティ教、リンガ教などの新興宗派は、すべての信者の平等を主張し、男女間やカースト間の違いを否定または軽視しています。これらの宗派は人々の間で非常に人気がありました。ヒンズー教の主流ではなかったにもかかわらず、多くの仏教徒を惹きつけ、仏教の衰退にさらに貢献しました。 こうして、西暦7世紀半ばのハルシャ帝国の崩壊とともに、仏教の偽りの「黄金時代」は終焉を迎えた。インドには仏教を支持する大帝国は一度も存在したことはありません。マガダやベンガルなどの一部の地域を除いて、仏教はどこでもヒンズー教によって抑圧されてきました。そのため、11世紀にトルコが侵攻すると、仏教は土足の巨像のようにあっという間に打ち負かされ、大量のインド仏典が取り返しのつかないほど失われました。これは人類文化にとって大きな惨事でした。 |
>>: 孫悟空の原型はヒンズー教の猿神ハヌマーンでしょうか?
推薦する
本草綱目第8巻本草類Psoralea corylifoliaの具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
『臨江仙:夜に小亭に登り、羅中の昔の旅を思い出す』の執筆背景は何ですか?
まだ分からない:宋代の陳玉毅の「臨江仙・夜小亭に登り洛陽の昔を偲ぶ」の執筆背景は何だったのか?当...
趙固の有名な詩句を鑑賞する:雲は暗く、夜明けは流れ、漢王朝の宮殿は秋の高潮に動いている
趙固(806年頃 - 853年頃)、号は程有、滁州山陽(現在の江蘇省淮安市淮安区)の出身で、唐代の詩...
李白の古詩「金陵三号」の本来の意味を鑑賞
古詩「金陵第3号」時代: 唐代著者: 李白六つの王朝の興亡。ワインを3杯お出しします。元芳と秦には土...
孟浩然 - 詩「清明紀詩」の本来の意味を理解する
古詩「清明節の事」時代: 唐代著者: 孟浩然皇城は清明節を非常に重視しており、人々は当然心配している...
なぜ孫悟空は孫悟空と呼ばれるのでしょうか?孫悟空の名前の由来
孫悟空が弟子になったとき、彼の師である菩提祖師は彼に法名を与えました。マスターは笑顔で言った、「あな...
チェチ王国の3匹の怪物は唐僧の肉を食べたくなかったのに、なぜ孫悟空は彼らを殺したのでしょうか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
雨水節気の文化的慣習を探ります。 穀倉に水を入れる祭りでは何をする必要がありますか?
雨水は二十四節気の第二節気で、雨が降り始め、次第に雨量が増えることを告げるものです。次の Inter...
ジブラルタル海峡はなぜ有名なのでしょうか?現在、この2つの要塞はどちらの国に属しているのでしょうか?
今日は、Interesting History の編集者が、ジブラルタル海峡にある 2 つの主要な要...
第55章 傘を奪って破壊する
『鮑公案』は『龍土公案』とも呼ばれ、正式名称は『都本鮑龍土百公案全伝』で、『龍土神段公案』とも呼ばれ...
なぜ菩提祖師は孫悟空に自分の名前を言うことを許さなかったのでしょうか?理由は何でしょう
菩提祖は西遊記の中で最も謎めいた人物です。彼については、西遊記のファンの間で常に議論されてきたことが...
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 織りの章』のあらすじは何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
「智成」の原文(中国のスタジオからの奇妙な物語より)洞庭湖[1]では水神が船を借りに来ることが多い。...
本草綱目第8巻朝用法の本来の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
王守仁の「陸千仙の韻を踏む正月初日の清春の日」(原文、翻訳、注釈)
王守仁は、本名は王雲、号は伯安、号は陽明で、明代の優れた思想家、著述家、軍事戦略家、教育者であった。...
なぜ曹操は関羽を漢寿亭侯に任命したのですか?関羽はついにその称号を受け入れたのでしょうか?
関羽の漢寿亭侯の爵位は曹操から授けられたものではなく、漢の献帝から授けられたものである。曹操は単に「...