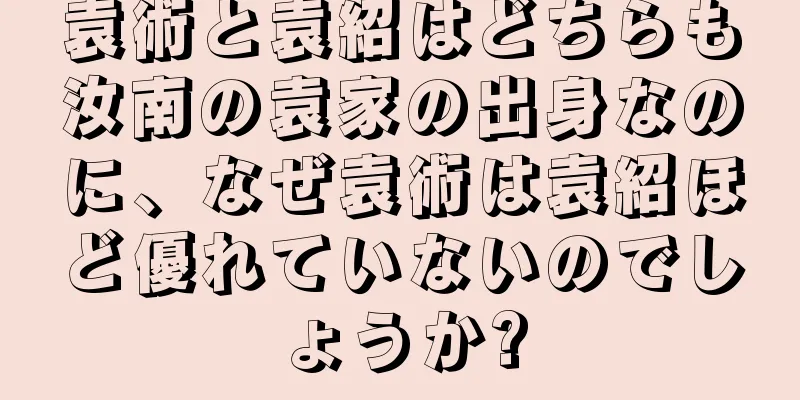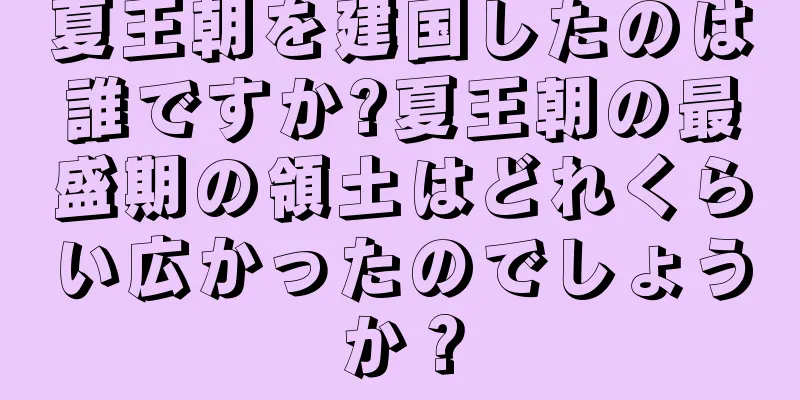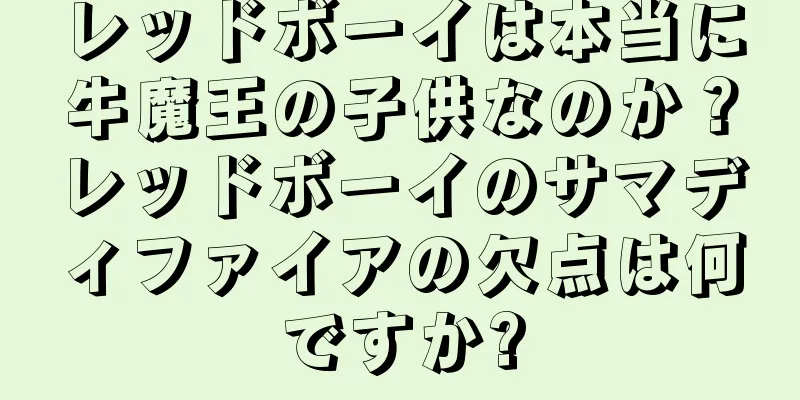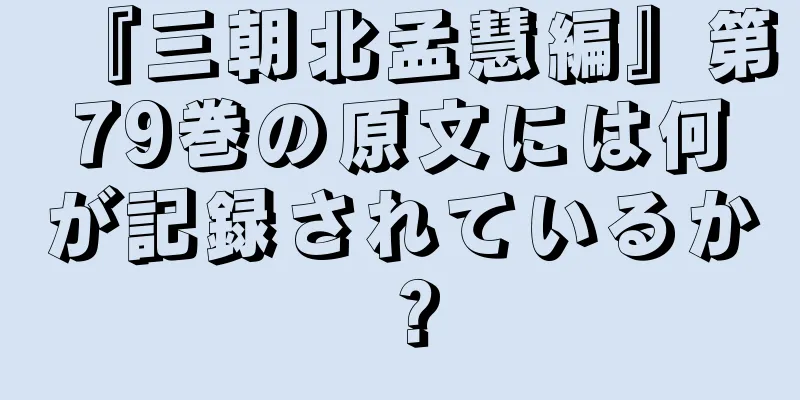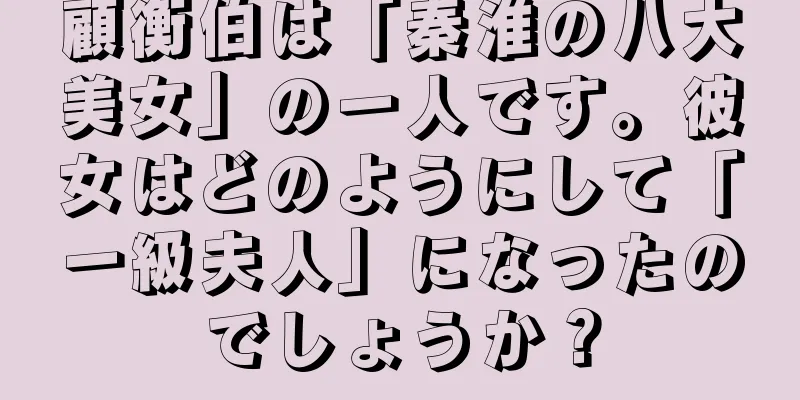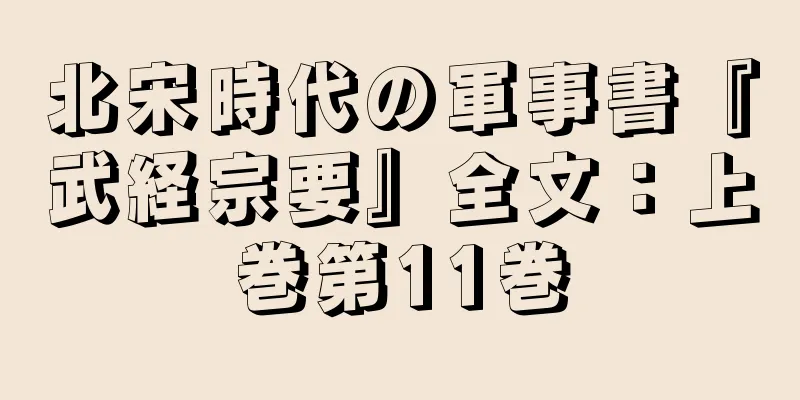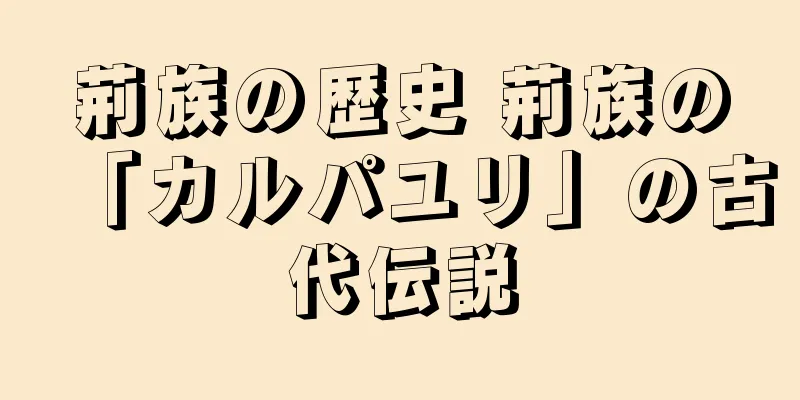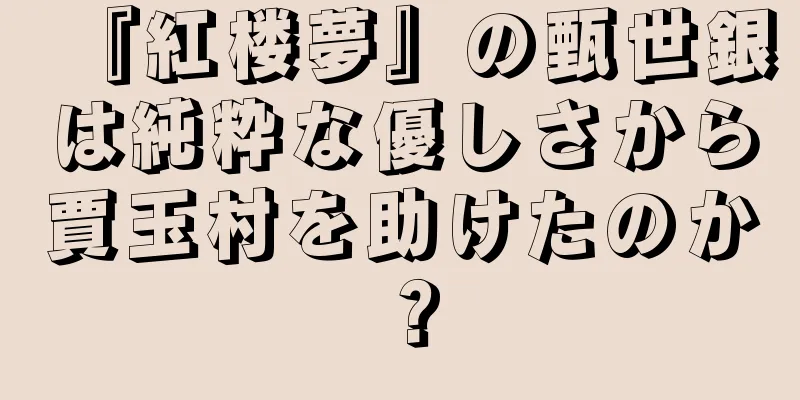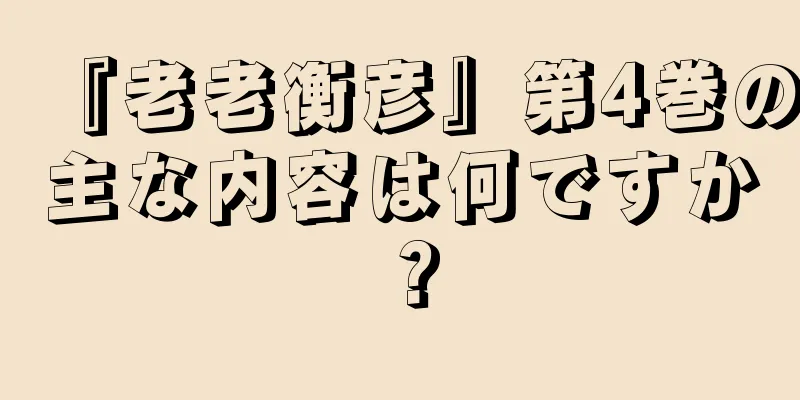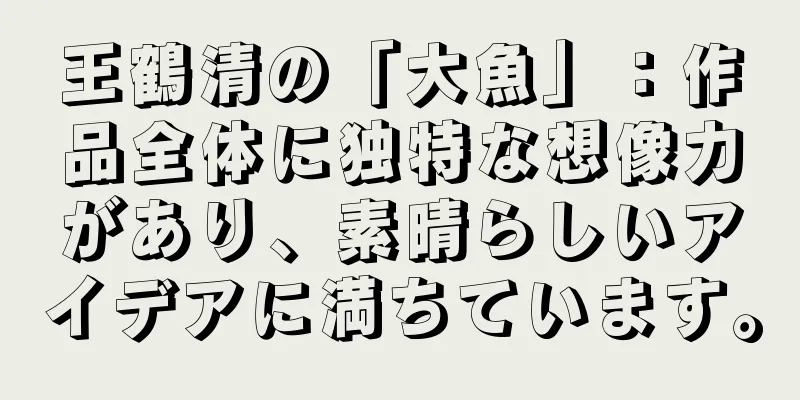私たちがよく使う言葉のうち、日本人が作ったものはどれでしょうか?
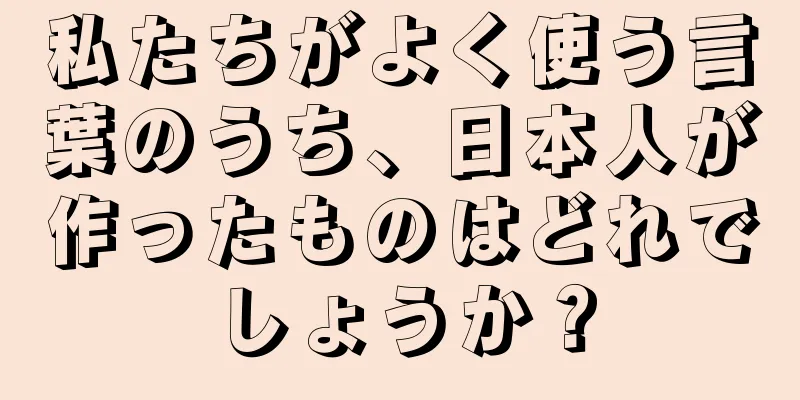
|
日本では、漢字を使って言葉や荘厳な名前を作る場合、その出典のほとんどは中国の儒教の古典に遡ります。それは彼の儒教に対する深い知識と漢字を創造する能力を反映しています。 例えば、私たちがよく知っている「靖国神社」。 「経国」という言葉は、『春秋左伝・羲公二十三年』に由来しています。「叔父叔父たちが『どうやって国を治めるのですか』と尋ねたところ、彼らは『私が国を治めるのです』と答えました。」 「経国」とは、国を安定させ、国家を統治することを意味します。 靖国神社本殿の横には、故人ゆかりの品々や功績などを展示する展示館「遊就館」もあります。 「游就」(旅と旅)という2つの単語は、荀子の『学問のすすめ』から来ています。「君子は住むには良い場所を選び、旅をする時にはその土地の人々を選ばなければならない。」それは死者の魂を故郷へ呼び戻すことを意味します。 「物理学」という言葉は、道教の古典『管子』に初めて登場します。管子(紀元前300年~220年頃)は、戦国時代後期の楚の国の道教徒でした。 『皇子書 王府編 第9章』にはこう記されている。「龐子は言った。『私は人間の本質と自然の法則について聞きたい』。それでは、どうすれば万物を天地と結び付け、神々とともに正義の道を体現できるだろうか?」 また、「維新」の「維新」という言葉も『詩経・大雅・文王』から来ています。「文王は天に高く、天に澄み渡っている。周は古い国だが、その運命は維新される」。日本人はよく「文明開化」の時代について言及します。「文明」という言葉は『文経・順典』の「賢く聡明な文明」から来ており、「啓蒙」は顧凱之の『天命論』から来ています。「極度の啓蒙を確立した夫は、健全を確立し、危険にさらされた」。 日本の皇居の御苑は、後に「後楽園」と改名されましたが、これは北宋時代の范仲厳の『岳陽塔碑』にある「自分のことを心配する前に世間を心配し、自分のことを喜んだ後に世間を喜ぶ」という意味から取られたものです。 日本の「厚生労働省」は、我が国の民事、健康、労働の各部門に相当します。 「后生」という言葉は『尚書大于墨』に由来する。「于曰く:…徳は治めることにあり、治めることは民を養うことにある…徳を正し、物を利用し、生活を調和させる。」これは人々の徳を正し、人々が物を利用しやすくし、人々の生活を豊かにし、人々が調和のとれた環境で生活できるようにすることを意味します。 例えば、日本の天皇の位号は、大臣や高官、学者が漢籍から言葉を選び、天皇に上奏して確認するという方法で決定されます。天皇が幼い場合は、摂政が決定します。この方法は日本では伝統的な習慣となっています。現代(現代)の天皇の年号を例に挙げてみましょう。 江戸時代後期の孝明天皇(在位1846年~1867年)は、「文久」「元治」「慶応」の3つの年号を使用しました。 「文殊」は後漢書の謝蓋伝に由来し、「文武両道で長期計画を達成する」という意味です。 「元治」は「周易・千・文厳」から来ており、「千元用九、天下を治める」という意味です。 「慶應」は、漢の皇帝高祖が『文宣』の『功臣頌』の中で「瑞雲は光に応え、朝廷は技を受ける」と書いたことに由来する。現在の日本の「慶應義塾大学」もこの時代にちなんで名付けられたと思われる。 明治天皇(1868年 - 1912年)は、本名を睦仁(むつひと)といい、日本の第122代天皇であった。 「明」という語源は3つあります。「明」は明るさを意味します。…聖人は南を向いて世間に耳を傾け、光の中で統治します。」 『易経』:「九つを用いる…大明が統治を始め、時を経て六つの地位が確立され、それらが確立されると、六つの龍が天を制する。」 『論語』:「知恵を養い、五つの要素を統御し、五つの尺度を設け、民を慰め、四方を測る。」 大正(1912年 - 1925年)は、明治天皇の息子である嘉仁天皇の在位名であった。 「大政」の由来は『周易格卦』に由来しています。「団長曰く:文明は喜びであり、大政は繁栄であり、後悔はない。」 『易経:臨牟』:「トゥアンは言った。「喜んで従順であり、堅固で応答性があり、正義で繁栄すること、これが天の道である。」 『易経:大虚卦』:「卦は言った:堅固は優れ、徳を重んじる。強者を止めることができ、非常に義理深い。」 ” 昭和(1926年 - 1988年)は、大正天皇の息子である裕仁の治世の称号です。これは、歴史書『堯経』に由来しています。「九つの氏族が和合すれば、民は平等に治まる。民が啓蒙されれば、国家は調和する。」 『五皇大系』には「九つの氏族が調和すれば民は悟りを開く。民が悟れば万国は調和する」と記されている。 平成(1989年 - )は現天皇の在位称号です。 「平成」「秋分」「正化」の3つの候補から選ばれたと言われています。調べてみると、『禹大王の指示書』には「地は平らで天は完全、六省三事は調和し、天下は永遠に頼りになる」と記されている。 『五皇大系』には「舜は八人の大臣を任命して、父を義とし、母を慈しみ、兄弟を親しくし、弟を敬い、息子を孝行させ、国を外は平和で繁栄させるように教えを広めた」とある。これは、国内外、天地の間に平和と繁栄があり、吉兆に満ちているという意味である。 日本の天皇の名前は、ほとんどが我が国の儒教の古典から選ばれており、現代の天皇の名前にはすべて「仁」という文字が含まれています。論語:「先生は言った:仁者は他人を愛する。」爾雅:「平和な人は仁者である。」 董公啓雲は言う。「政務を執り成功することを仁という。」 明治天皇の名前は睦仁(むつひと)でした。実際のところ、彼は「友好的」でも「慈悲深い」わけでもなかった。1894年から1895年にかけて日清戦争を起こし、清政府に下関条約に署名させ、軍隊を派遣して青島を占領した。 昭和天皇の名前は裕仁であり、「国が繁栄し、国民が平和である」という意味です。実際、彼らは「裕福」ではありませんでした。彼らは中国に対して侵略戦争を起こしましたが、それは失敗に終わり、降伏しました。また、原子爆弾の攻撃を受け、人々はひどい苦しみを味わいました。平成の現在の天皇は明仁(1933年 - )であり、現在の皇太子は徳仁(1960年 - )である。 一般の日本人の名前にも儒教文化的な色合いがあり、縁起の悪い漢字や下品な漢字を避けています。 たとえば、人名の中の「忠」「孝」「仁」「义」「礼」「智」「信」という文字は、倫理や道徳を表します。 梁、季、羲、甲などは吉祥を、桂、和、宋、千余などは長寿を、君代などは長寿を、光、伯、浩、陽などは知恵を象徴します。 男性の名前の多くは、力強さ、ハンサムさ、忠誠心などを表します。現在、「Lang」、「Xiong」、「Nan」、「Fu」などで終わる名前が多くあります。男性の名前の特徴としては、太郎、一郎、次郎、三郎など、生まれた順番で名付けることが挙げられます。 女性の名前には、一般的に、ユリコ、ハナコ、ジュンコ、ハルコ、サチコ、ヨシコ、チエコ、ヒデコ、トモコ、ヨシコ、トモコなど、美しく、上品で、柔らかい発音の言葉が使われます。また、江、戴、梅、志などで終わる名前もたくさんあります。 海外との交流が活発化するにつれ、日本人の名前に使われる伝統的な吉祥漢字の組み合わせの中には、「欧米式」の発音を考慮しなければならないものもあります。例えば、「涌大」はもともと威厳のある漢字ですが、英語の「You Die」の発音に似ているため、このような漢字は採用されません。 注目すべきは、現代の言葉の多くは、日本が中国の古典に基づいて最初に作り、その後中国に逆輸入されたものであるということです。それらはすべて漢字で構成されているため、私たちはそれらを「外来語」とは見なしていません。一部の人々はそれらを「中国固有の言葉」であると誤って信じていました。実際、これは誤解です。たとえば、日常生活でよく使われる次の言葉は、日本人が最初に作った言葉です。 昼夜、半径、飽和、保険、保護、スペアパーツ、背景、編集、照明、訪問、常識、機会、場所、構成要素、メンバー、認識、乗客、出口、外観、保管、貯蓄、感染症、作成、代表者、スポークスマン、道徳教育、登録、出版、敵意、抵抗、発明、法律、法人、裁判所、反応、反対、配布、分析、封鎖、否定、拒否、サービス、取る、、要約、概要、概念、予算、固定、固体、失敗、関係、広告、広い、誘導、化石、化学、化粧品、グループ、集中、、代理店、機械、アクティブ、ベース、計画、マーク、記録、建物、評価、講師、演壇、講義、講義、教育、指導教育、階級、キス、節約、結核、解放、緊張、進歩、進化、進化論、進歩、資金、経済、経済、経験、精神、繁栄、警察、劇場、決算、絶対、主題、科学、決定可能、目的、オブジェクト、コース、肯定、スペース、会計、拡散、労働、労働者、労働、累積削減、タイプ、理論、概念、ディレクター、理想、合理性、理由、メカニズム、スタンス、臨床、領海、空域、領土、論理、フォーラム、討論、敗北、脈動、漫画、コミック、トーク、盲目的服従、媒体、美的、美化、美術、民主主義、感受性、明確、、命題、母体、母校、目標、目的、内閣、裏話、事務作業、内容、内面、エネルギー行動、能力、偶然、派遣、判断、陪審、批判、飛行機、評価、騎士、企業、ガス、気質、最前線、力、違反、侵略、奉仕、清算、諜報、権威、権限、権利、人格、人権、ヒューマニズム、候補者、スケジュール、ビジネス、社会、社会学、社会主義、社会的、コミュニティ、アイデンティティ、無効化、時間、時事、適時性、思想、盲点、所得税、探査、サーチライト、専門、スパイ、共感、同計画、体操、スポーツ、理想主義、唯物論、衛生、文化、図書館、文明、文学、プロレタリア、舞台、物理学、物理学、憲法、相対的、想像力、シンボル、消火、消費、消化、宣伝、宣戦布告、選挙選挙、制度、社会、学歴、学士、学位、パフォーマンス、スピーチ、運動、義務、決議、議会、芸術、意識、意味、銀行、スクリーン、要素、ガーデニング、原動力、原理、意欲、原則、運動、スタジアム、原子、雑誌、展示会、前線、哲学、政策、政党、支部、支配、支線、知識、直観的、直接的、直径、直感、DC、制約、品質、終点、調停、能動的、主観的、主人公、主食、主題、主義、資本、資本家、データ、自制心、自然淘汰、自由、宗教、包括的、総動員、首相、総領事、構成、内閣、組み合わせ、組織、最恵国、左翼、作品、作物、著者、セミナーなど。 また、プロレタリア、社会主義、共産主義、共産党などの政治用語や、ラジオ、発電機、電池、乾電池、電圧、電流などの科学技術用語もすべて日本語です。 現代中国語には、本当に「国内的な」言葉はあまりないようです。 日本人が中国の膨大な古代書物の中にこのような深遠な暗示の起源を見出し、彼らの「祖先」の故郷でも受け入れられる豊かな語彙を創り出すことができたという事実は、彼らの儒教に対する深い知識と漢字で言葉を創り出す能力を示しています。これは私たち中国人にとっても熟考し学ぶ価値のあることでもあります。 |
<<: 仏教の四法印を理解すればするほど、精神世界が高くなるのはなぜでしょうか?
推薦する
欧陽秀の「環西沙:堤防の観光客が絵のついた船を追いかける」:この詩は非常に表現力豊かでユーモラスである
欧陽秀(おうようしゅう、1007年8月1日 - 1072年9月22日)、字は永叔、晩年は随翁、劉義居...
「建門路小雨に遭遇」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
建門路に小雨陸游(宋代)服には旅の埃やワインの跡が付いていて、どこへ行っても悲しい気持ちになります。...
独特の魅力を持つ李玉の詩:「于美仁:風は小庭に帰り、庭は緑になる」
以下、Interesting Historyの編集者が、李游の『于美人・風は小庭に帰り、庭は緑なり』...
『紅楼夢』では、宝仔は一晩中泣き続けました。彼女は何を経験したのでしょうか?
宝仔は曹操の『紅楼夢』のヒロインの一人です。林黛玉とともに金陵十二美女の第一位に数えられています。こ...
水滸伝の涼山の英雄たちはなぜ馬に乗らないのでしょうか?何か特別な理由があるのでしょうか?
水滸伝に非常に興味がある方のために、Interesting History の編集者が詳細な記事を参...
孫権は曹操に降伏を求めるために人を派遣した。なぜ曹操は降伏を快く受け入れたのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
星堂伝第63章:池成祥の最初の軍事訓練、老秋瑞の瓦岡山への2回目の攻撃
小説『大唐興隆』は『大隋唐』『大唐興隆全物語』とも呼ばれています。関連する古典小説には、清代乾隆年間...
リトルサイクロン柴進はなぜ涼山に加入してから無名になったのか?ちょっとした計画が頭の中にあるから!
小竜騎柴進はなぜ涼山に入隊した後も行方不明のままだったのか?それはただ、何か裏の目的があったから!『...
蜀漢には少なくとも3回天下統一のチャンスがありました。それがどの3回だったかご存知ですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』の登場人物はなぜ最後に宝玉と結婚して、彼の叔母になるという夢を叶えなかったのでしょうか?
希仁は『紅楼夢』の登場人物。金陵十二美女の2番目であり、宝玉の部屋の4人の侍女のリーダーである。 I...
黄巾の乱はなぜ失敗したのか?
はじめに:黄色のターバンの反乱または黄色のターバン災害としても知られていますが、漢王朝の農民の蜂起で...
史公安第174章:黄天覇は皇帝に召喚され、安楽亭で武術を披露する権利を与えられる
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
「花を探しに川沿いを一人歩く 第五部」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
花を探して川沿いを一人歩く - パート 5杜甫(唐代)黄石塔の前を川が東に流れ、春風に吹かれて眠たく...
易経の卦「肥遁、无负」をどのように理解すればよいのでしょうか?
多くの友人は易経の合卦「飛卦、不利」をどのように理解するかに興味を持っていますか?次の興味深い歴史編...
『二十四史』第65巻第41章の原文
◎カーサービス大車、玉車、大馬車、小馬車、歩行車、大梁歩行車、木輿、耕耘車、側室車、皇太子以下の車、...