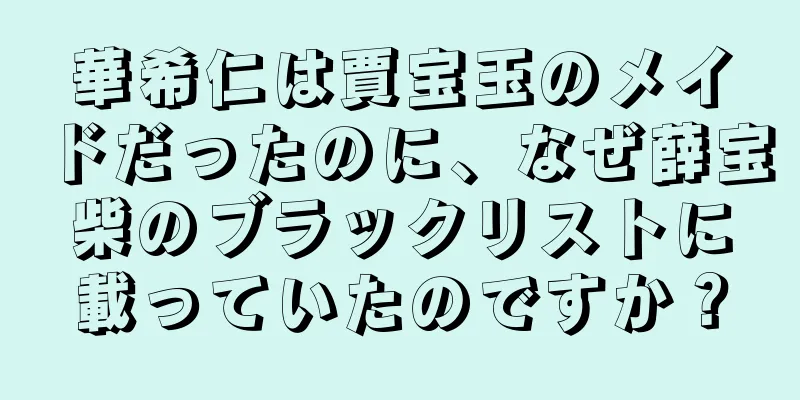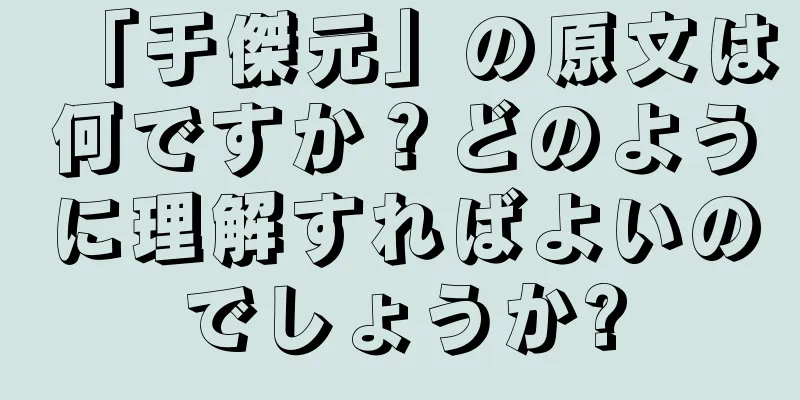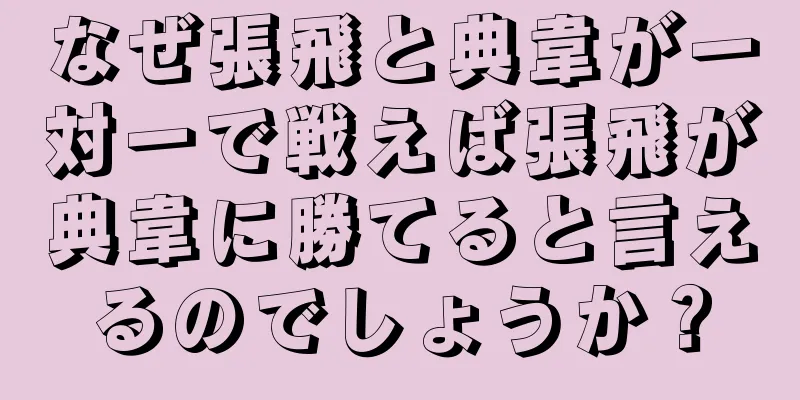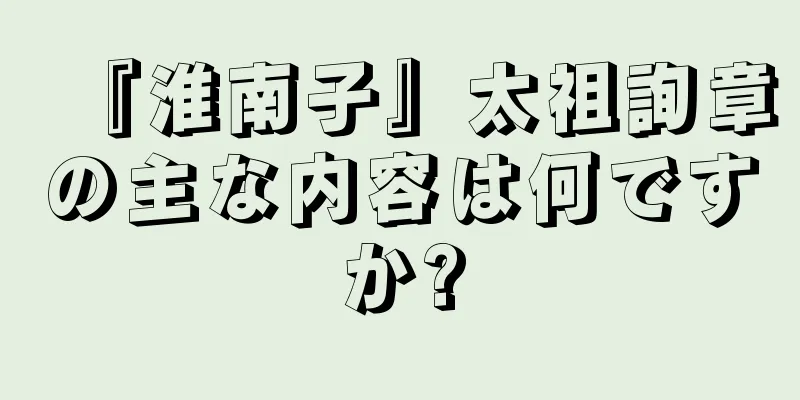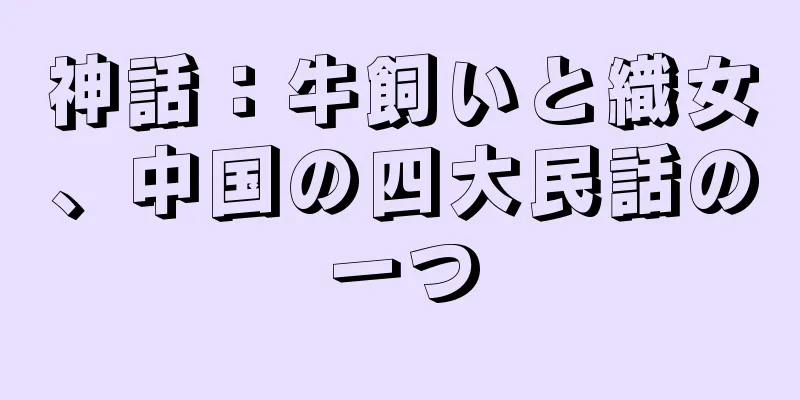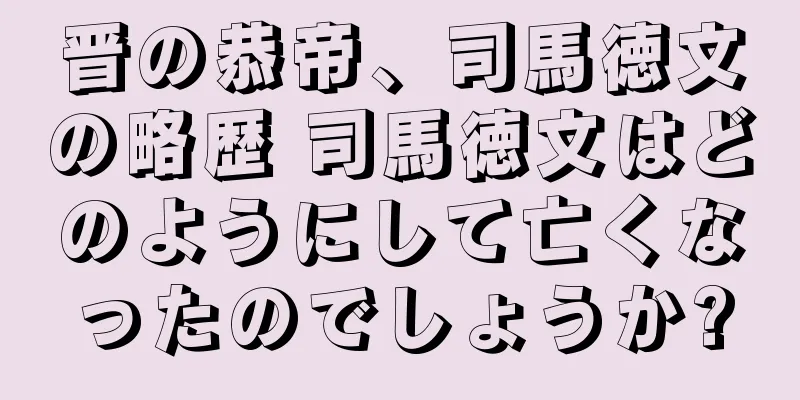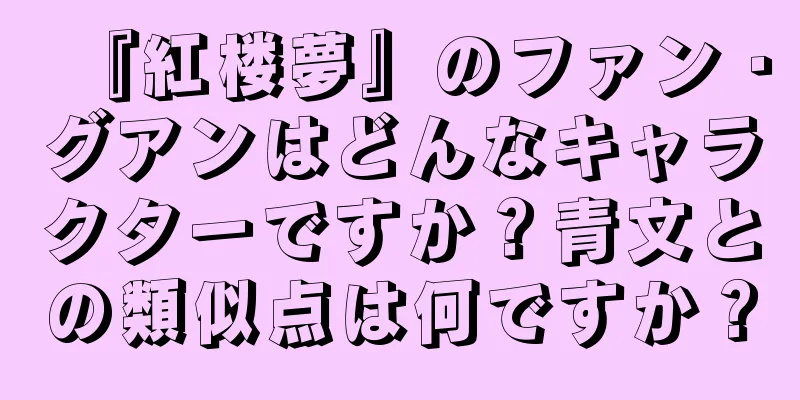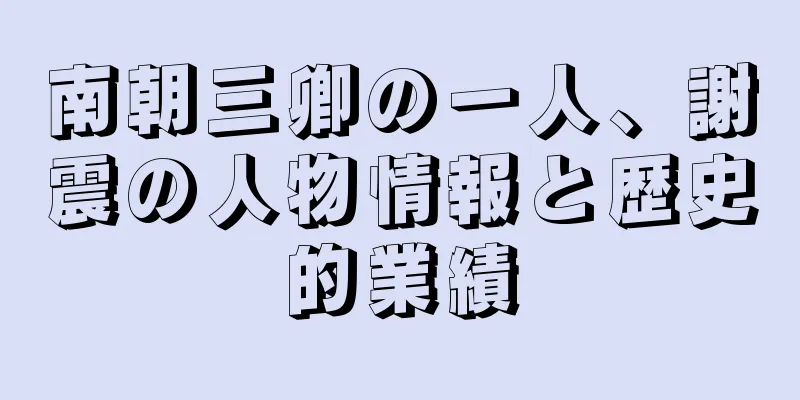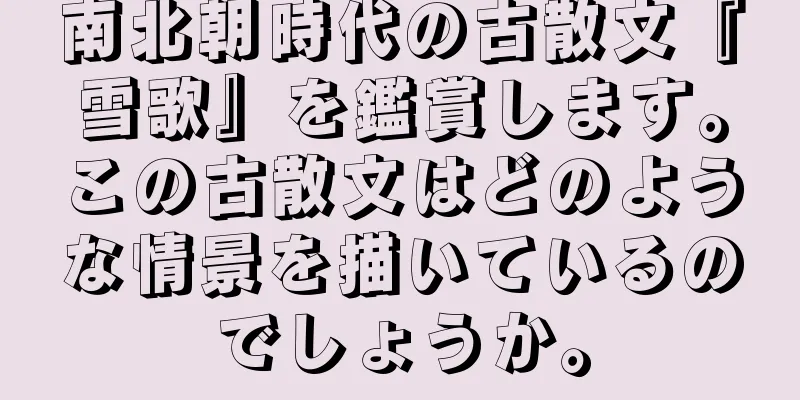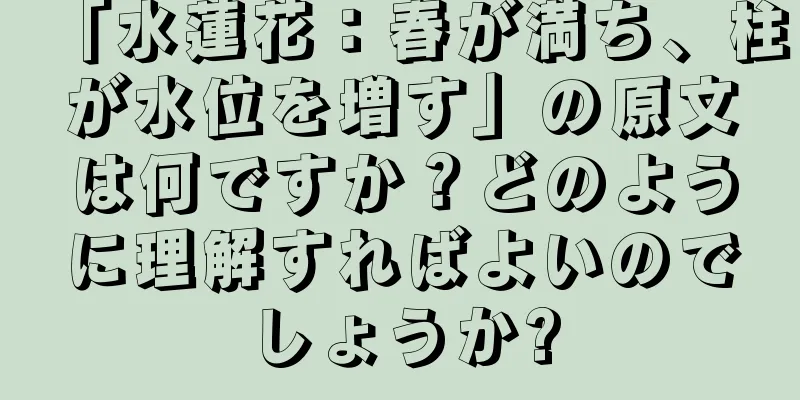学者・羽田徹氏:厳密な歴史観で後世に影響を与える
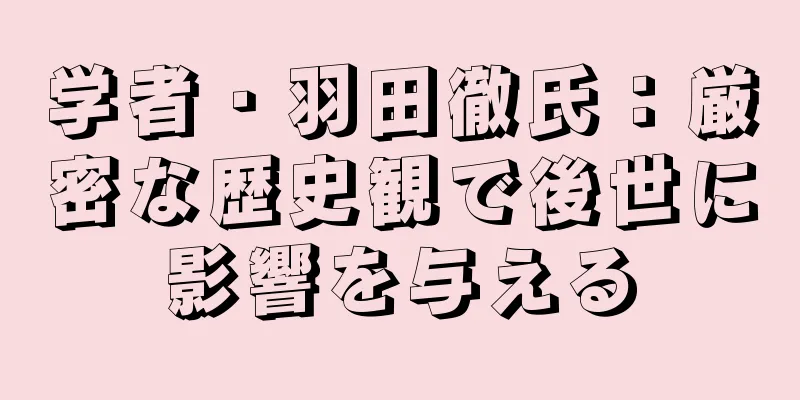
|
近代日本の敦煌学者、羽田亨は1882年に京都府で生まれました。羽田徹の伝記によると、彼の本来の姓は吉村であり、中学に入ってから羽田家の養子となり、後に羽田徹となった。 羽田 徹の作品 野英治博士は、羽田亨の紹介の中で、羽田亨は子供の頃からとても頭が良く、聡明だったと述べています。彼が地元の小学校の教師になったとき、彼は14歳にも満たず、当時の人々は彼を神童と呼んでいました。将来ジャーナリストになるという夢を叶えるため、彼は19歳で名門校である京都第三高等学校に入学した。 3年後、羽田亨は優秀な成績で東京帝国大学史学科に進学した。彼の指導教員は全国的に有名な白鳥久慈博士であった。 後代の学者たちは、羽田亨の伝記に基づいて、羽田亨が東京帝国大学在学中に中国の辺境史や民族史に強い関心を抱き始め、その際に彼の生まれながらの外国語の才能が役立ったと推測している。白鳥久慈博士の指導の下、羽田徹はすぐに専門史の研究に進みました。 1938年、羽田亨は東京帝国大学第12代総長に任命されるという栄誉に浴し、彼の人生は絶頂期を迎えた。 5年後、彼は日本学士院会員となり、東洋文化研究所所長となった。在任中、彼は読書を続け、古代中国の歴史の研究に力を入れた。 以来、羽田亨氏は勲一等瑞宝章、フランス・ジュリアン・シノロジー賞、日本文化勲章などの特別賞を相次いで受賞している。これは、羽田徹氏の研究成果を肯定するものであると同時に、間接的に羽田徹氏の業績の大きさを反映しているものでもある。 1955年4月13日、羽田亨氏が74歳で逝去した。 羽田徹の功績 羽田 亨氏は近代日本を代表する歴史学者であり、日本の学界に大きな影響を与えました。羽田徹氏は多くの功績を残しており、その学術的成果は今日世界にとって大きな財産となっている。 羽田徹の昔の写真 羽田徹氏の業績は主に学問に反映されている。元代史と西域・中央アジア史は日本の東洋史学の二大分野であり、羽田徹は両分野において並外れた業績を残している。彼は10か国語以上の外国語に堪能という強みを生かして、多くの研究分野で先駆者となり、また日本の歴史学界において特別な意義を持つ京都西域学・敦煌学を創始しました。羽田亨は、元やモンゴルの歴史、西域の歴史、敦煌の文化に精通していたほか、清西交易の歴史にも精通していた。その中で、元代モンゴル史の激動の時代は彼の歴史研究の出発点となり、敦煌文化の研究と西域歴史の探究で学問の頂点に達し、中西文化交流の研究で生涯の終焉を迎えた。また、羽田徹氏は辛亥革命後、中国文化の深い研究を行うため自ら中国を訪れ、当時のわが国の著名な学者であった王国衛氏と多くの歴史交流を行い、多くの斬新な歴史観を表明したと言われています。胡適氏もその後、米国からの帰国の途中、羽田亨氏の評判の高まりを見るためにわざわざ日本を訪れた。 学術分野と比較すると、羽田徹の教育分野における影響力はそれほど顕著ではありません。 1936年に瀋陽で開催された東方文化協会の創立会議に出席した以外、彼は教育分野における歴史文化や対外交流の促進にほとんど何もしなかった。 羽田 徹のコメント 羽田亨は日本の歴史学界、さらには世界の歴史学界に大きな影響を与えました。同時代および後世の多くの学者が彼を高く評価しました。 羽田 徹の作品 羽田徹氏について最もよく言われるのは、歴史分野における類まれな研究力と、洗練された力強い語学力だ。彼は生涯をかけて、中国西部地域のさまざまな民族間のコミュニケーション、進化、変化、そして最終的な統合の歴史を学界に伝えた。彼は西部地域のさまざまな民族の言語、さらには同じ民族の言語にも精通しており、アルタイ語族の補足と改善への貢献は大きな意義があった。彼は中国の奥深い文化に憧れ、大学在学中に古代中国の歴史を学ぼうと決心した。彼はモンゴル人の領土拡大と世界征服の優位性に執着し、元モンゴルの歴史を踏み台にして、モンゴル人が起こした奇跡を自らの言語で世界に知らしめた。彼は自分の不確かな歴史的結論に非常に後悔しており、自分の推論を証明する十分な証拠がなかったために眠ることも食べることもできないこともあった。 歴史に対する彼の厳格な姿勢もまた、羽田徹氏を高く評価する理由である。彼は歴史体系を完成させるために推測や想像に頼ることはほとんどなかった。彼は、確認できなかった歴史上の疑問については、何度も数千マイル離れた新疆ウイグル自治区まで出向き、自ら現地調査を行い、自分が求めていた歴史の真実を手に入れた。羽田亨は、やがて西域史研究の先駆者となり、その生涯をかけた著書『西域文明史大系』や『西域文化史』も西域文化史の金字塔となった。彼は歴史に対する厳格なアプローチで後世の学者に影響を与えたが、これは多くの歴史家が生涯で達成するのが難しいことである。 |
>>: 「高潔な詩人」陳彬にはどんな逸話が残されているのでしょうか?
推薦する
紅楼夢第15章:王鳳傑が鉄観寺で権力を振るい、秦景青が饅頭寺で楽しむ
宝玉が見上げると、北京水容王子が銀の翼のある白い冠をかぶり、五爪の龍の模様が描かれた白い蛇の衣を着て...
「彭公の場合」第293章:季有徳が木羊陣を再訪し、雷神が道を遮断する
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
『紅楼夢』で黛玉はなぜ賈祖母に育てられたのですか?
黛玉は『紅楼夢』のヒロインであり、金陵十二美女の一人です。本日は、Interesting Histo...
李夢陽の『秋景色』:この詩は郭子怡という人物の生まれ変わりを繰り返し呼びかけている
李孟陽は明代中期の作家であり、維新派の七師のリーダーであった。彼は「散文は秦漢の時代から、詩は唐の時...
中国最古の天文学と数学の本:周壁算経の簡単な紹介
『周壁算経』は、もともと周壁と呼ばれ、算経十巻のうちの1冊です。中国で天文学と数学に関する最古の書物...
薛剛の反乱 唐編 第24章:揚州王が反乱を起こし、金陵の両軍が対峙する
『薛剛の反唐』は、汝連居士によって書かれた中国の伝統的な物語です。主に、唐代の薛仁貴の息子である薛定...
「金糸の服」は杜秋娘によって書かれたもので、一言で言えば「楽しい時間を無駄にしてはいけない」という意味です。
杜丘(791年頃 - ?)は、『支志同鑑』では杜中陽と称され、後世では「杜丘娘」と呼ばれることも多い...
李志の女性に関する有名な名言は何ですか?彼は何て言ったの?
李志は明代の有名な思想家であり文化人であった。彼の思想と行動は当時大きな論争を引き起こした。彼は男性...
古代中国の伝説に登場する6種類の龍
【インロン】 1. 古代の伝説に登場する翼のあるドラゴン。伝説によると、禹が洪水を治めていたとき、応...
王莽は暴君ですか?王莽は一体何をしてこれほどの不満を引き起こしたのでしょうか?
王莽は漢王朝を簒奪し、新王朝を建国した。王莽はわずか13年間皇帝の座にあったが、その治世中に成し遂げ...
南北朝時代の詩『玉街園』と『夕宮真珠幕』の内容は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
玉段告訴·晩宮真珠幕[南北朝]謝条、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみ...
リン・ジェンにはどんな能力がありますか?なぜ彼は宋江から重要な地位を得られなかったのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、Ling Zhenについての記事をお届けし...
『紅楼夢』では、王希峰は血を流して倒れた後も医者を呼ばなかった。なぜか?
『紅楼夢』を読んで、多くの人が王希鋒に感銘を受けています。 Interesting Historyの...
曹植の『名都志』は、主に主人公の若者の北京と洛陽での行動を描いています。
曹植は、字を子堅といい、曹操の息子で、魏の文帝曹丕の弟である。三国時代の有名な作家であり、建安文学の...
春秋戦国時代に改革を行った国はどこですか?最終結果はどうなりますか?
魏における李逵の改革。改革者李逵は、三家が晋を分裂させた直後の魏文厚の時代に改革を実行しました。改革...