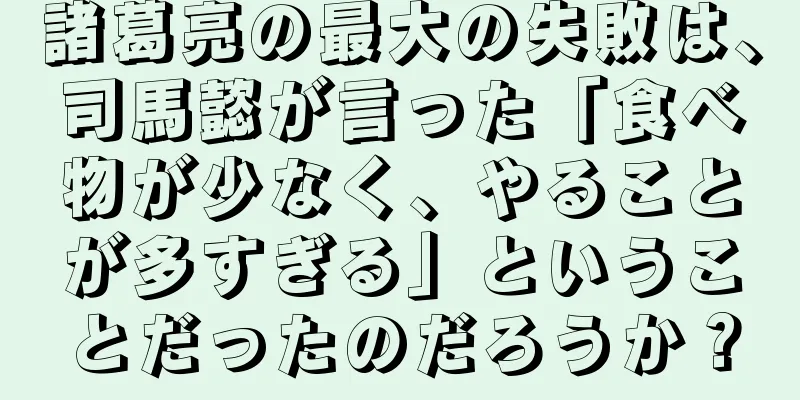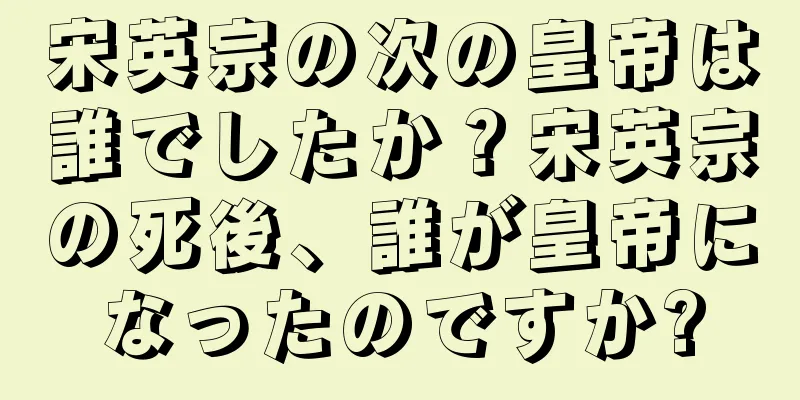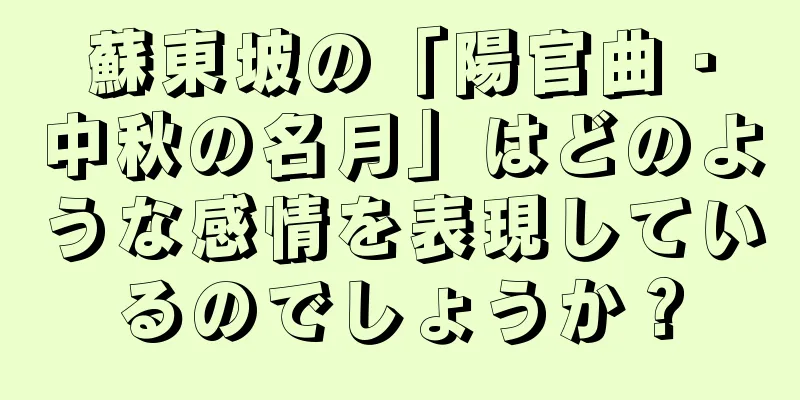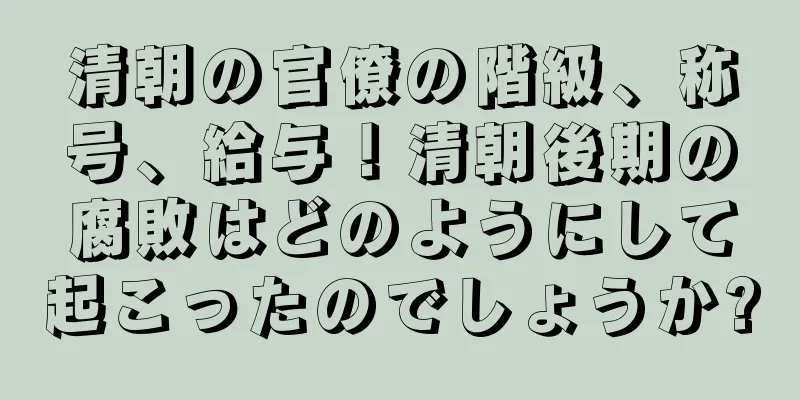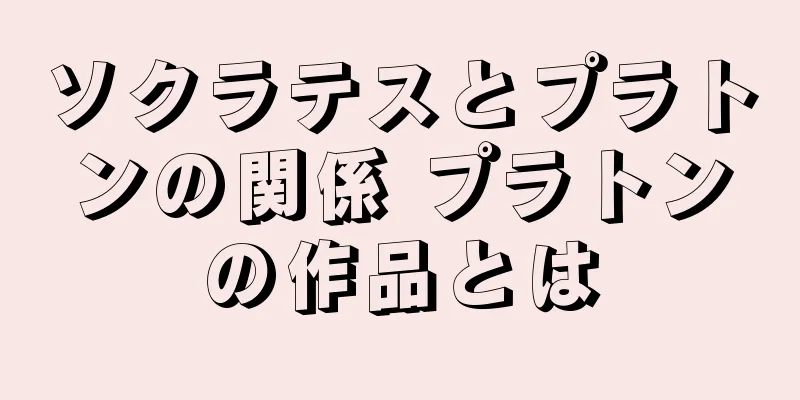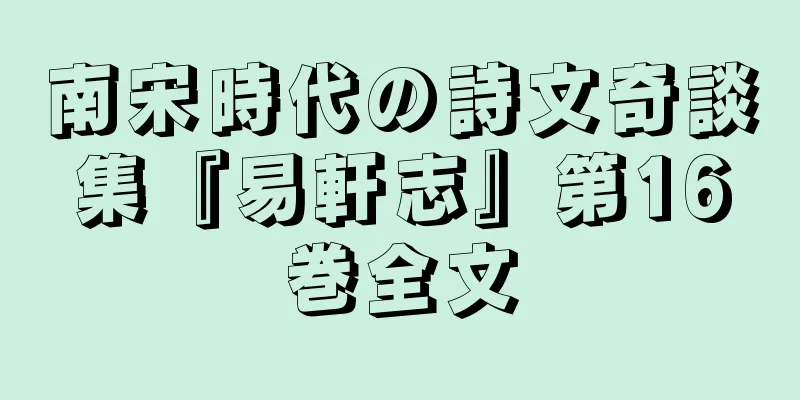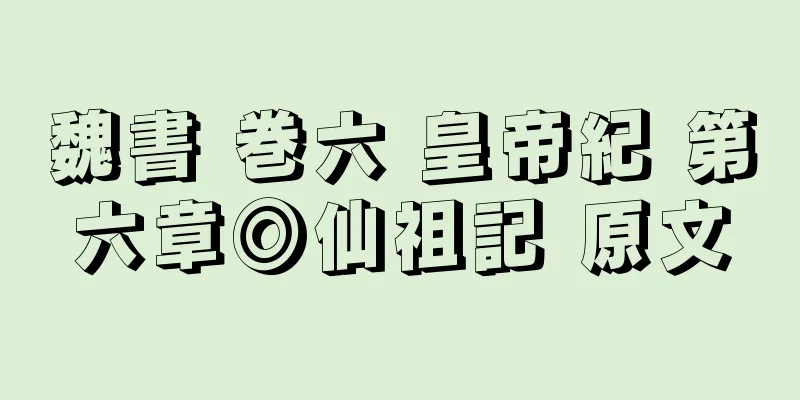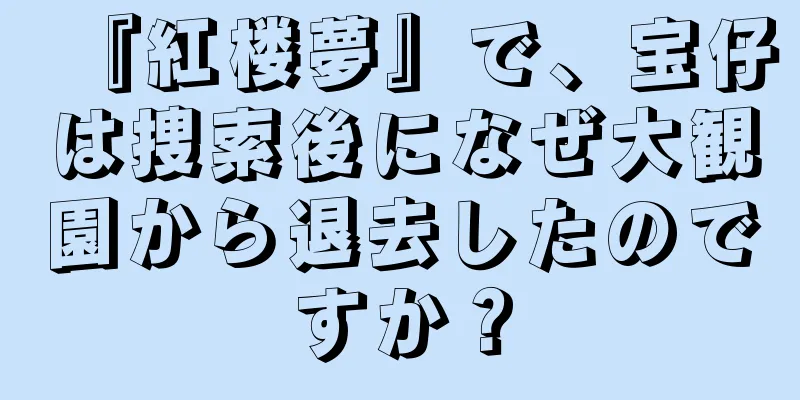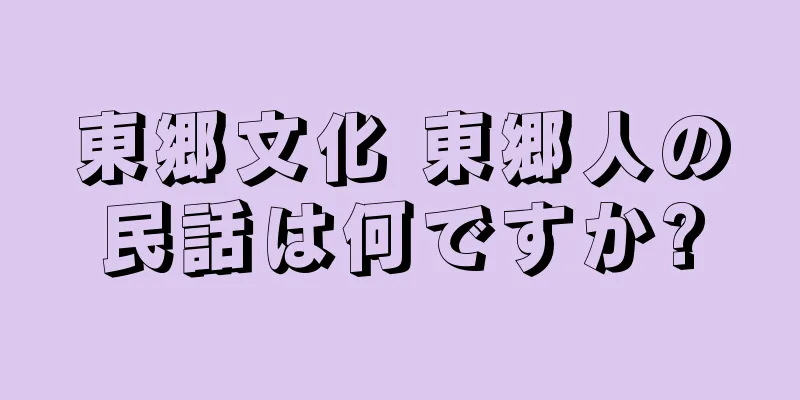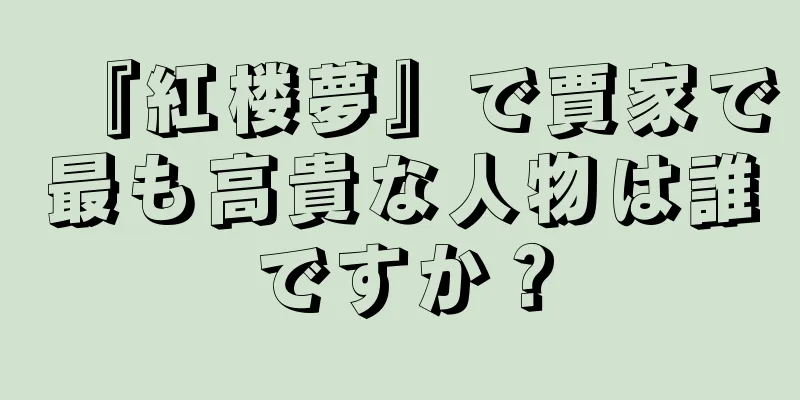遅れたら負けますよ! 1000年前の秦の興隆と斉の衰退がそれを物語っています。
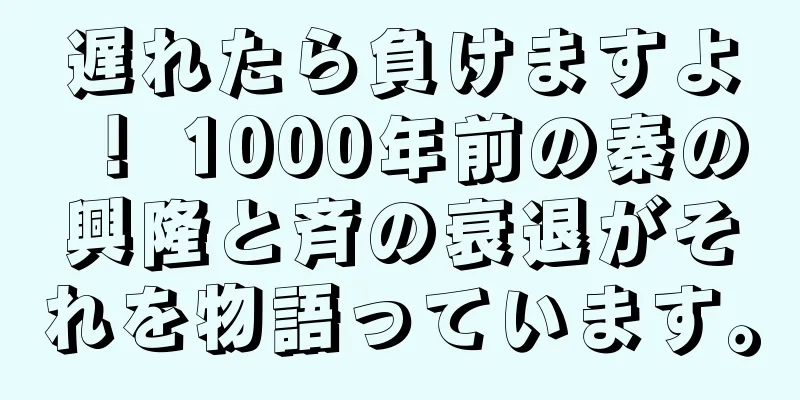
|
遅れをとれば負ける! 1000年前の秦の興隆と斉の衰退がそれを物語っています! 次の「おもしろ歴史」編集者が詳しくお答えします。 管仲は管義武としても知られ、古代中国の有名な経済学者、哲学者、政治家、軍事戦略家でした。彼は春秋時代の法家を代表する人物でした。その後、斉の桓公元年(紀元前685年)に宰相を務め、「中夫」と称えられた。彼は在任中、国を豊かにし、軍隊を強化するための大規模な改革措置を開始した。彼は外交において尊王攘夷の政策を採用し、九つの国を統一して天下に平和をもたらし、斉の桓公が春秋五覇の第一位となるのを助けた。 その後、ほぼ半世紀にわたって、斉は中原地域の最終決定権を持つ兄貴分であり君主であった。後世の発展とともに、田家が斉に取って代わり、三家が晋を分割し、戦国時代が始まりました。斉は依然として楚、趙、秦と競争できるほどの力を持っていました。しかし、なぜ斉は秦の手によって悲劇的に死んだのでしょうか? 周の安王11年(紀元前391年)、斉の康公は、当時の権力と権威を握っていた統治者、田和によって斉の海の近くの島に追放されました。その後、田和は斉王を名乗り、斉の太公として知られるようになった。周の安王16年(紀元前386年)、田和は当時の周の皇帝、周の安王によって臣下に列せられました。それ以来、江氏の斉国は名目上完全に消滅し、田氏の斉国は周の皇帝によって聖国とされ、当時の臣下国の一つとなりました。 地理的な観点から見ると、斉と楚は当時、広大な領土と豊富な資源を持つ肥沃な土地であったと言えます。喬と漢の拠点があった秦と比べると、斉と楚の人々は豊かで、文化は栄え、多くの賢人が住んでいました。斉国には荀子がかつて教鞭を執った蔡霞書院があり、また戦国時代の四大君子の一人として名高い孟昌君もおり、人材の登用や友人作りで有名であった。 しかし斉国は、自らの優位性をうまく生かしきれず、一方では有能な人材を真に評価せず、自らの優位性に甘んじて傲慢になりすぎていた。孟昌君が斉にいた頃、斉王は彼を宰相に任命したが、孟昌君の諸国での名声が次第に高まるにつれ、斉の閔王は彼の功績が大きくなりすぎることに脅威を感じ、次第に孟昌君を信用しなくなった。そこで彼は田佳の人質事件を利用して孟昌君に責任をなすりつけようと計画した。孟昌君はそのメッセージを感じ取り、斉王はもはや自分を信じておらず、殺されるかもしれないと悟った。そこで孟昌君は一夜にして魏の国へ逃げた。魏の昭王は直ちに彼を宰相に任命した。 このことから、臣民を統制できず、彼らに疑いを抱く王は、臣民を不安にさせるだけでなく、世界中の賢者の士気を低下させることになることがわかります。一方、秦国は才能ある人材を重視しました。張儀、司馬崑、白起、樊遂、王建、魏然などは秦国で高く評価され、秦国で才能を発揮し、秦国に多大な貢献をしました。しかし、斉国には才能ある人々が才能を発揮する舞台がありませんでした。 周の南王31年(紀元前284年)、魏の宰相孟昌君の協力と指導の下、魏は西の秦、北の趙と連合し、岳邇の指導の下、燕が祖国斉を攻撃するのを支援した。この戦いで斉国は一瞬にして敗れ、七十余りの城を失い、国は滅亡の危機に瀕したといえます。斉は田丹率いる最後の反撃により失った領土を取り戻すことができたが、同時に斉の襄王を新たな王として即位させた。しかし、この戦いの後、斉は大きな損害を受け、秦に対抗できるほどの力を持つことは困難でした。内なる力の修養という点では、斉はすでに大きく遅れをとっていました。これが斉が秦の手によって悲劇的な死を遂げた2番目の理由です。 最後に、斉国は初期には積極的に対外的に拡大し、対外的に野心を示し、真っ先に頭角を現しましたが、国内では臣民をなだめたり、獲得した領土を強化したりしませんでした。国は時代の流れに沿った政策を導入できず、適時に改革することができず、貴族や貴族の利益が依然として優先され、本質的には秦の国とは大きく異なっていました。 秦の興隆と斉の衰退は、困難に直面した時には変化を求めなければならないという真実を物語っています。変化は成功につながり、成功は成功につながります。このような不毛の地で、秦国は新たな生命を得て、世界を征服する力を蓄えた。しかし、斉国は贅沢三昧の暮らしをし、秦の手によって悲劇的に滅びた。歴史の避けられない流れ。 |
<<: 独身でいることは違法ですか?郭堅は越国の人口を増やすために奇妙な勅令を出した!
>>: 皇帝自ら軍を率いたら事故は起きるのでしょうか?皇帝が自ら軍隊を率いて勝利した歴史上の例にはどのようなものがありますか?
推薦する
宋仁宗には10人以上の子供がいたのに、趙叔はどうやって皇帝になったのでしょうか?
宋仁宗の側室たちは、楊王昭芳、雍王昭欣、荊王昭熙の3人の息子を含む10数人の子供を産んだ。しかし、こ...
漢王朝を400年以上も存続させた英雄は誰ですか?それは本当に王莽のせいでしょうか?
前漢末期の社会問題は非常に深刻でした。一方では、国があまりにも長い間平和で、人口が急激に増加していた...
建章宮の神々の祭壇はまだ残っていますか?神明台を建設したのは漢王朝のどの皇帝ですか?
神明台は漢の武帝の時代に建てられた台地の名前です。漢の長安城の遺跡内にあり、建章宮の重要な部分です。...
なぜ公孫瓚は一流の将軍である呂布を恐れず、自分のレベルを超えて挑戦したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
辛其記の古典詩「年女教・西湖民謡」を鑑賞する
以下、Interesting History の編集者が、辛其記の『年女嬌・西湖人韻』の原文と評価を...
『紅楼夢』に登場する多くの女性の中で、商人の出身は誰ですか?
『紅楼夢』は中国文学の四大傑作の一つで、閨房にいる女性たちに関する多くの興味深い物語を描いています。...
古代の兵士は夏に戦うときに何を着ていたのでしょうか?完全武装時の戦闘効率の低下を回避するにはどうすればよいでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、古代の兵士が夏に戦うときに何を着ていたかを...
唐代の作家、洛隠の『鸚鵡』の原文、翻訳、注釈、鑑賞
羅隠の「オウム」、興味のある読者はInteresting Historyの編集者をフォローして読み進...
張恒の人生経験の簡単な紹介 張恒はどのような人生経験をしたのでしょうか?
張衡は西暦78年、美しい山と川のある南陽市西鄂(現在の河南省南陽市臥龍区石橋鎮下村)に生まれました。...
白玉堂の結末は?彼はどうやって死んだのですか?
中国の伝統的な武侠小説『三勇五勇士』には、仙空島の五鼠の中の医者である白玉堂という人物が登場します。...
軍事著作「百戦百策」第1巻:全文と翻訳注
『百戦奇略』(原題『百戦奇法』)は、主に戦闘の原理と方法について論じた古代の軍事理論書であり、宋代以...
『紅楼夢』では、華希仁は賈家の側室になることに失敗しました。彼女は自分のせいしか考えられないのでしょうか?
寶玉と初めて親密な関係を持った女性として、希仁は『紅楼夢』で重要な役割を果たしています。興味のある読...
歴史上、夏を描写した詩にはどのようなものがありますか?古代人はどうやって暑さを逃れたのでしょうか?
歴史上、夏を描写した詩は数多くあります。興味のある読者は、Interesting History の...
金長旭の「春恨」:この詩は余韻に満ち、無限の魅力を持っている
金長緒(生没年不詳、大中時代以前に生きた)、生涯は不明、おそらく浙江省余杭出身、唐代の詩人。現在残っ...
「四聖心源」第4巻:疲労と損傷の説明:中気全文
『四聖心源』は、1753年に清朝の黄元宇によって書かれた医学書で、『医聖心源』としても知られています...