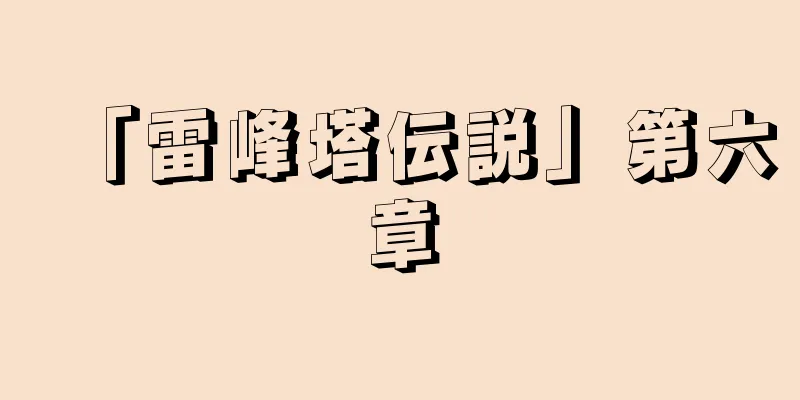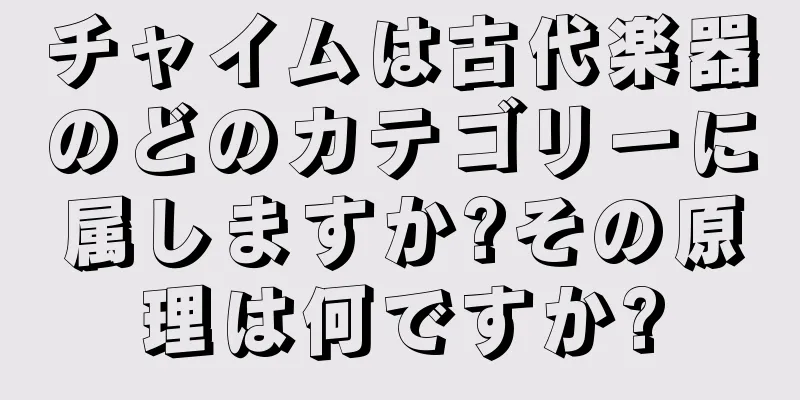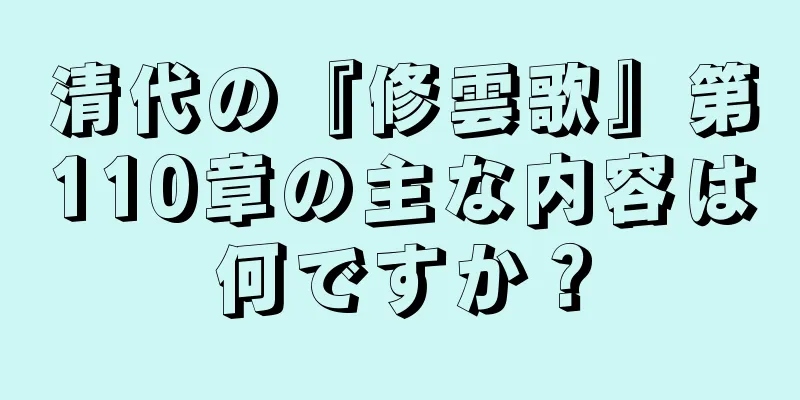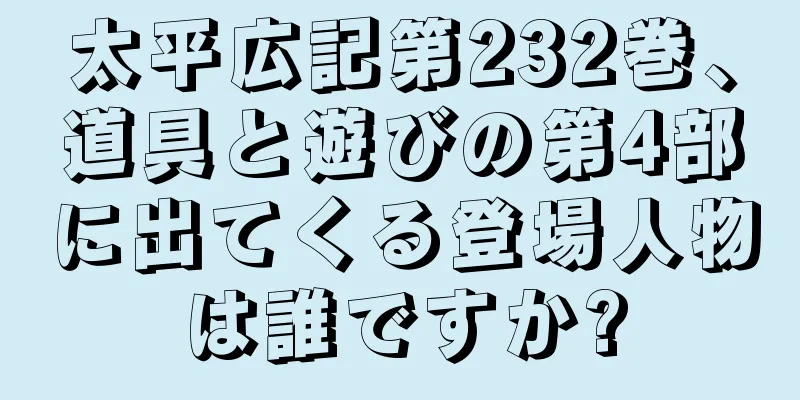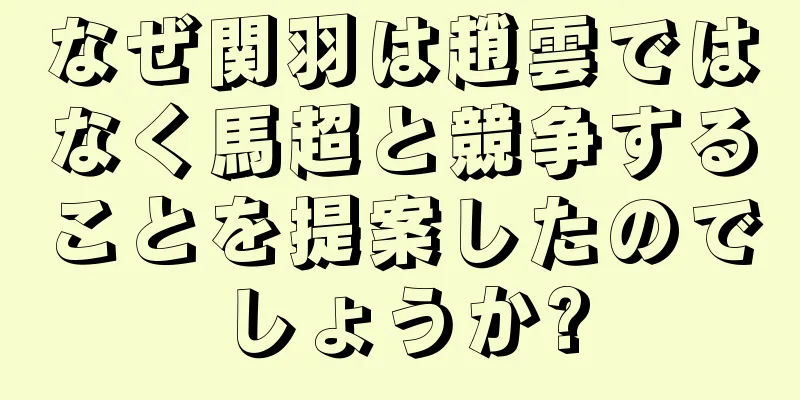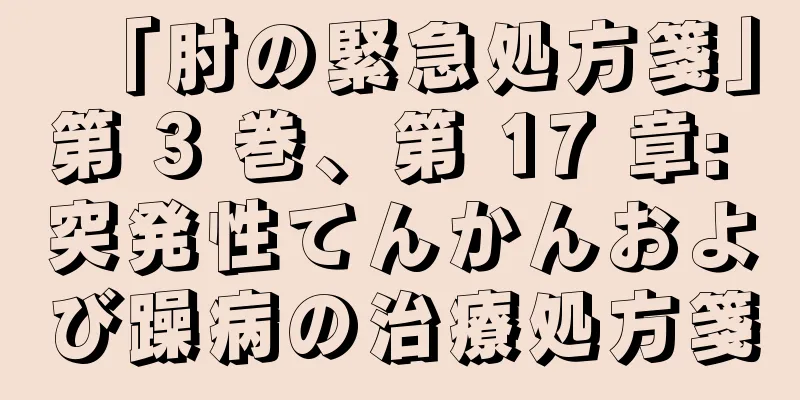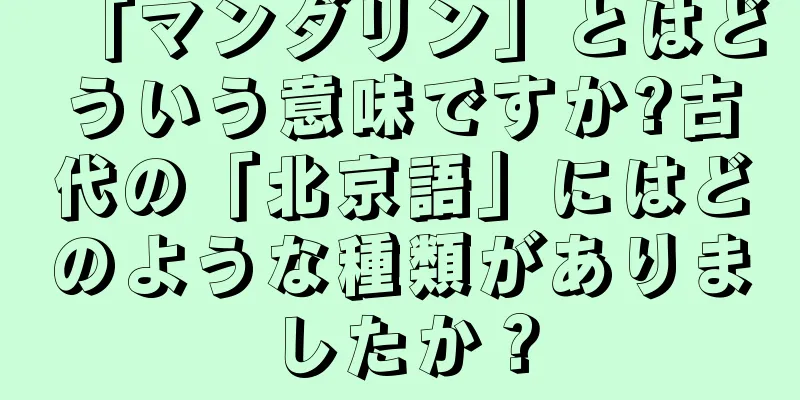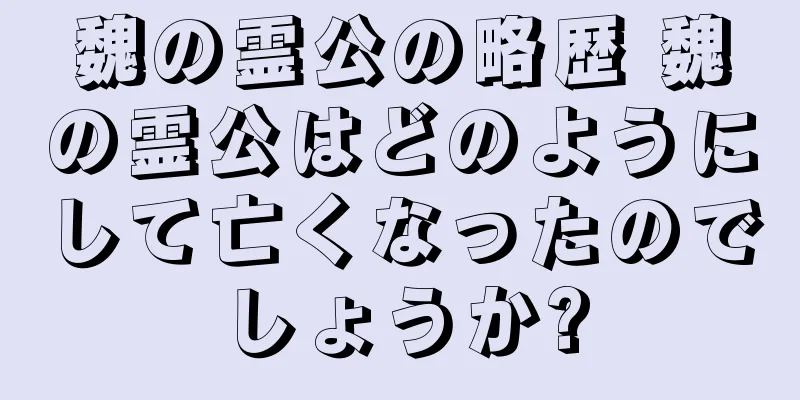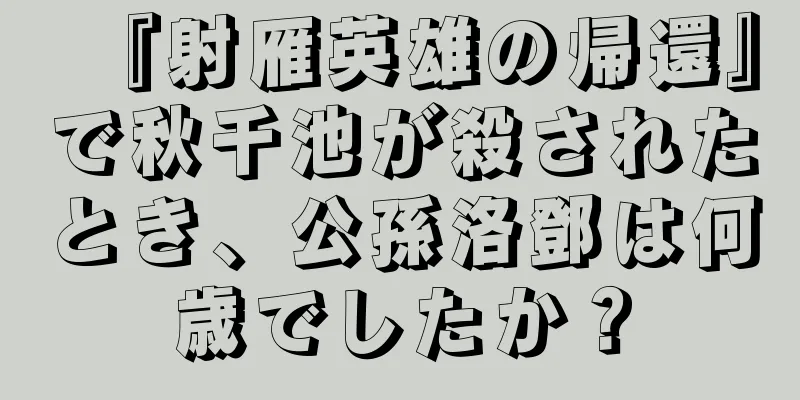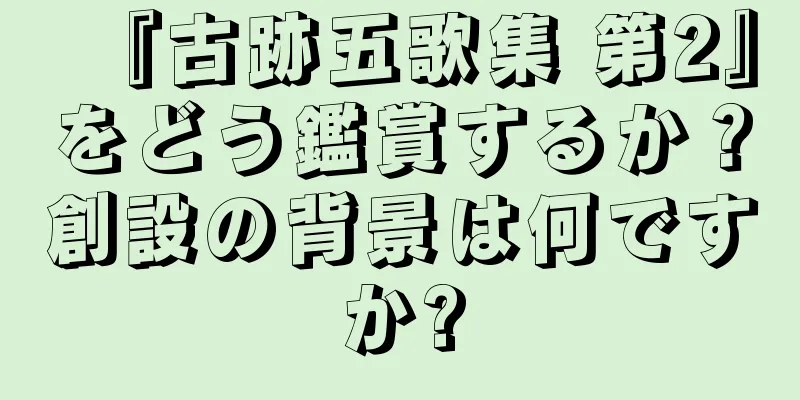清朝の官僚の階級、称号、給与!清朝後期の腐敗はどのようにして起こったのでしょうか?
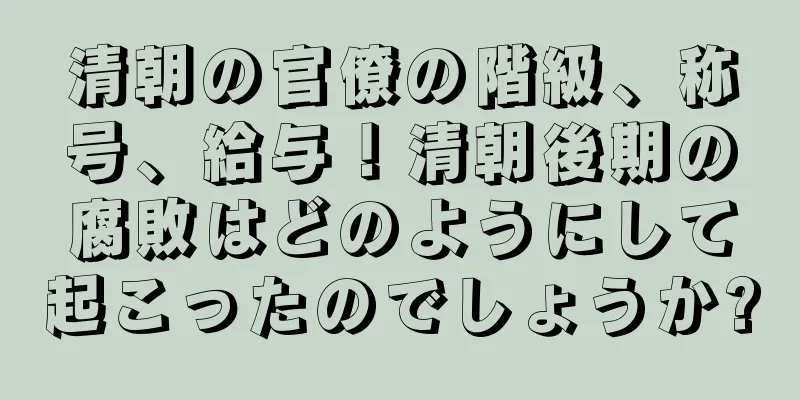
|
今日は、Interesting Historyの編集者が、清朝の官僚の階級、肩書、給与についてご紹介します。皆さんのお役に立てれば幸いです。 著者は清朝の官僚の階級、称号、給与について多くの記事を書いているが、基本的に焦点が異なり、十分に包括的ではない。最近、多くの読者から、この点に関して私が状況をより包括的に紹介できることを期待して、私にプライベートメッセージを送ってきました。本来、官位や俸給は経理帳簿のような項目に過ぎず、読むには退屈なものであるが、読者の参考のために体系的に論じる必要がある。 まず役人の階級についてお話しましょう。 清朝は明の制度に倣い、官位を9等級に分けた。各等級は2つのレベルに分かれていたため、「九等十八階級」と呼ばれた。 18 レベルに入らない人は「主流ではない」と呼ばれ、第 9 レベルにランク付けされます。また、官吏の中には平官と下官に分けず、九つの階級のみで評価する者もいる。各種官吏の階級と肩書は以下のとおりです。 ファーストクラス: 文官職: 大典官、大導師、大護国師、宮廷大書記官。 軍事上の役職:近衛大臣、近衛大臣。 最初の製品から: 文官職:師範、師範、護国師範、太子太師範、太子太師範、太子太守、副太書記、各省・宮廷の大臣、左右の検閲官。 軍の役職: 九門歩兵哨戒隊提督、五個大隊司令官、大書記官、八旗守備隊長、総司令官、提督。 2位: 文官職:皇太子侍従、皇太子師範、皇太子護衛、各省庁の左・右副大臣、内務省長官、各州知事。 軍職:左右の先鋒軍司令官、八旗近衛軍司令官、勅使、副司令官、将軍。 2番目の製品から: 民間職:内閣学者、翰林学院長、知事、省知事。 軍事上の地位:三治大臣、副将軍。 第三位: 文官:左・右検閲官、朝廷副長官、行政大臣、最高裁判所大臣、宮内大臣、宮内大臣、順天府知事、奉天府知事、検閲官。 軍職:一級衛兵、銃器大隊司令官、建瑞大隊司令官、前衛司令官、近衛司令官、騎兵司令官、王宮主任史官、城衛司令官、総司令官、総司令官。 3つの製品から: 文民職:光禄寺大臣、太朴寺大臣、塩運委員。 軍事上の地位:保義衛隊長、保義騎兵隊長、一級近衛兵、遊撃隊、五旗隊長、副隊長、使節、総司令官。 第四位: 文民職:行政部副部長、大理寺副書記、瞻史宮副書記、太昌寺副書記、太普寺副書記、検閲官六部書記、順天州副書記、奉天州副書記、各省道源省書記。 軍事上の地位:二等衛兵、雲旗使、副衛兵司令官、副前衛司令官、副騎兵司令官、内務省馬牧場長、北楽邸宅主席儀礼官、衛兵リーダー、防衛中尉、副司令官、司令官、宣衛部副知事。 4番目の製品から: 文官職:内閣学士、帝国学士、帝国学士、帝国大学壽九、知事、地方知事、塩運局運輸官。 軍事上の地位:城門司令官、宝邑副衛兵司令官、宝邑副騎兵司令官、宝邑副司令官、四等礼官、二等衛兵、和平特使、和平特使副。 第五位: 民間人の役職:左右の春芳樹子、同正寺候補生、光魯寺少書記、介時中、宗人府部長、各省の郎中、皇室病院長、同志、屠同志、支州。 軍事職位:三等近衛兵、儀礼長、歩兵副中尉、歩兵大佐、監督、副指揮指揮官、峠守備、守備、駐屯、宣威部副書記、宣威部副知事、千戸。 5年生から: 民間職:帝室学院学長、帝室学院講師、洪禄寺少書記、帝室財政局西馬、帝室氏族局副局長、帝室検閲官、各省副局長、知事、地方知事、塩運副使、塩税監察官。 軍事上の職位:四等近衛兵、任命先鋒指揮官、任命近衛指揮官、任命銃砲指揮官、任命先鋒近衛兵、任命先鋒近衛兵、下五旗近衛兵、五等礼官、印璽官、三等近衛兵、守備指揮官、河営副守備指揮官、鎮撫使、募集使、鎮撫使部副使、副指揮官。 第六位: 文官職:内閣司令、左右の春芳仲雲、皇学院長、殿長、師範、検閲官、経験、大理寺左右の寺助、皇族局経験、太昌寺満漢寺助、皇室天文台監督、皇室病院判事、神楽局長、僧籍左右の山師、道籍左右の正義、首都県銅版、首都県知事、銅版、地方銅版。 軍事職位: 近衛兵、帝国近衛兵、近衛学校、前衛学校、衛兵学校、銃衛学校、騎兵学校、歩兵学校、門番、大隊長、宣伝平定部次長、安府部次長、募集副特使、首席特使、百人隊長。 6年生から: 民間職:左右春芳残山、漢林書院編纂、光魯寺長、帝国天文台満蒙五官長、漢軍秋官長、和合長、僧籍所左右禅教、道教籍所左右延法、省政所経験、利文、雲班、直隷県長、県長、原住民県長。 軍事上の地位:内務省六等蘭陵将、六等典邑、近衛軍前宗、和平弁公室副使。 第七位: 翰林書院編集者、大理寺左右判事、太昌寺医師、皇学監、内閣簿記、同正寺経験、知事、太昌寺簿記、太福寺主任書記、省寺会計、軍事部副司令官、太昌寺満州語読み官、参里朗、洪路寺満州語明参、景県郡書記、県知事、安咸寺経験、教授。 軍歴:城門史官、宮内省馬牧場副司令官、大尉、鎮撫使官室副長官。 第7位から: 民間職:帝国学院評議員、近衛兵経験、秘書局、内閣、站師夫主任書記、光魯寺副書記、簿記係、帝国学院医師、助教授、帝国天文台監督、祭祀寺、和合弁事務所副書記、北京政府経験、省政部、塩運部経験、直隷県裁判官、県裁判官、原住民県裁判官。 軍職:七等礼官、盛京遊牧軍副司令官。 第8位: 文官:書記、五経博士、帝室学院学院長、学問記録官、帝室天文台書記長、帝室医師、帝室礼寺法官、僧籍部左右講師、道籍部左右志霊、省財務部大使、塩運財務部大使、検閲局長、県経験、県知事、地方県知事、四学学問記録官、省学校長、講師。 軍事的地位:外部委員会の1,000人の指揮官。 8年生から: 民間職:翰林書院簿記、皇学院簿記、洪綬寺簿記主任、皇室天文台長、祖廟副所長、神楽局副所長、僧籍局左右爵位、道籍局左右智義、省政局昭墨、塩運局長、講師。 軍職:八等儀仗士官、帝国陸軍委任士官、前衛軍委任士官、騎兵隊委任士官。 第9位: 民間職:礼部四訳大使、天文台監督、書記、台昌寺の韓瓚里朗、安刹寺の昭莫、州知事、副知事、銅版知事、県書記。 軍事的地位:各大隊の蘭陵軍長および外部任命将校。 第9位から: 帝国学院の皇帝秘書、満州公母、礼部の四訳、帝国学院の簿記、洪禄寺の韓明山、懲罰部の獄、帝国天文台の朝、医師、帝国病院の書記、礼部の学部長、工部部の学部長、官庁部の主任、国書記、帝国財務大使、税務部大使、税務部大使、官庁倉庫大使、監察官、地方監察官。 軍事上の役職:太平寺馬場委員会の副司令官、追加委員。 主流ではない: 帝学院書記、帝監、礼部印章局大使、軍事部書記、崇文門副使、書記、地方書記、税関大使、茶許可検査所大使、塩茶局大使、郵便局長、地方郵便局長、河川湖局官、県倉庫大使。 軍事的地位:白昌、土社、土木。 上記の成績については、いくつかの説明と補足が必要です。 上記の官職は完全ではなく、特に清朝末期に新しい官職制度が実施されて以降は、階級や等級が欠けている。また、「都内の官吏」と「都外の官吏」という用語も相対的です。たとえば、「太師」「少師」「太子太師」「太子少師」という尊称は、太書、尚書、十郎などの都内の官吏や、都督、地方督にも当てはまります。 一部の役人の階級は大きく変化した。例えば、内閣大書記官は当初、満州族が第一位、漢族が第二位とされていたが、後に両者とも第二位に設定された。順治15年7月、清朝は三内廷を内閣に改め、太書に内閣の称号を与えたが、その位階は五位に降格した。康熙帝の治世6年に、満州族の官吏は順治帝の治世14年以前に存在していた慣習を再開したが、漢族の官吏は康熙帝の治世9年まで二位の地位を取り戻さなかった。雍正8年に一位に昇進した。 例えば、各省の大臣は、もともと満州族が一等、漢族が二等であったが、順治二年に二等に改められ、康熙六年に満州族が一等に復し、九年に再び二等に改められ、雍正八年に一等に昇格した。 同様の変化は、さまざまな中央省庁、寺院、アカデミーでもある程度起こっています。また、官吏の階級についても、上下関係を合理的にするため、例えば、県と道の関係を明確にするため、知事を四等官から四等官に降格するなど、若干の調整が行われた。上級の州知事は第四位と評価されていたため、より低い地位の知事が州知事と同じレベルにランクされることは絶対にありませんでした。 なお、上記の総督は二等官であり、総督は二等官であり、官位を指す。清朝の総督は通常陸軍大臣の称号を持ち、総督は陸軍副大臣の称号を持っていたため、一級と二級の称号を持つことができました。 清代には、まだ階級の上下が区別されていない官僚が少数いた。例えば、翰林書院の書記官は七等官の給与を受け、帝都天文台の天文学学生は九等官の給与を受けていた。また、都には七等官吏がおり、七、八、九等の書記官もいた。曲阜孔子廟の執事には三位から九位までの階級の区別はない。 清朝の階級制度を見ると、名誉称号や、比特使や孔子廟執事などの一部の特別な称号を除いて、地位と階級は結びついていたことがわかります。特定の官職には特定の階級があり、通常は切り離せないものでした。一部の人物が本来の職務に加えて追加の称号を授与されることについては、称号を分離するよりも、権力を強化することが主な目的です。 スパイカーシステムについて話しましょう 清朝では、官職と称号が同時に存在することが多く、通常は「世襲称号」と呼ばれていました。清朝の世襲貴族制度は、万里の長城の外側の時代にすでに形成されていました。太祖天明5年(1620年)に「功績に応じて5つの階級が設けられた」。太宗の天宗8年(1634年)、按邦張景、梅楽張景、托蘭張景、牛路張景を含む一級、二級、三級の官吏が設立された。順治元年、順治は公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵の世襲爵位を授けられた。 乾隆元年(1736年)、漢の爵位に準じて清斉都衛、斉都衛、雲斉都衛の爵位が制定された。乾隆帝の治世16年(1751年)、世襲の七位官吏に恩啓衛が任命され、9階27等級の世襲貴族制度が確立されました。彼らです: 雄、1級から3級に分かれ、雄、超級。 侯爵、一級侯爵と雲騎将一名に分かれ、一級侯爵から三級侯爵、超級。 伯爵は、一級伯爵と雲騎兵隊長、一級伯爵から三級伯爵、超級伯爵に分かれています。 子弟は一等子と雲騎中尉に分かれ、一等子から三等子までが第一位である。 兵は一等兵と雲騎兵隊長に分かれ、一等兵から三等兵まで、二等兵。 軽騎兵司令官は、一等軽騎兵司令官と雲騎兵司令官に分かれており、一等軽騎兵司令官から三等軽騎兵司令官までが三等階級である。 騎兵司令官、雲騎兵司令官を兼任する騎兵司令官と騎兵司令官 II に分割され、第 4 位。 雲奇衛、第五位。 恩啓衛、第七位。 上記の世襲称号は雲奇衛の位を基準としており、その後、軍功やその他の功績があった人、または父や祖父から世襲称号を受け継いで功績により称号を授与された人は、これらを組み合わせて上位の位に昇格することができます。雲奇衛を二つ加えれば、斉都衛に昇格できる。さらに雲奇衛を一つ加えれば、斉都衛と雲奇衛一つになる。このようにして、二十六回数えたら一級の公爵になれる。 爵位を継承する方法は2つあります。1つは世襲で、子孫が代々継承できるもので、朝廷から勅命を受けて特権的に継承されます。通常、世襲爵位は継承回数が決まっていて、一般的には1世代ごとに1段階ずつ減ります。最後に、爵位は恩啓衛に授与され、代々継承されます。ただし、戦死ではなく武功により世襲称号を授与された場合、または負傷や死亡により世襲称号を授与された場合は、継承が完了した後に世襲称号は取り消され、恩卿中尉の称号は授与されなくなります。 清朝では、世襲貴族の叙任は主に軍事上の功績に基づいて行われ、明らかに八旗一族に偏っていました。雍正2年(1724年)、清朝は明朝の子孫である朱之廉に一等侯爵を授けた。雍正8年(1730年)10月、清朝は張廷宇と蒋廷熙に「政務を助け、公平無私で、思慮深く徹底し、何事にも妥協した」として一等軽騎兵指揮官の世襲称号を与えた。これは漢族の官吏が世襲貴族になる始まりであった。 その後、乾隆帝は『康熙実録』を読んで、張雍、趙良東、王金豹らの三藩平定の功績や、葛丹との戦いにおける孫世克らの優れた武功に感銘を受け、彼らの子孫が途切れることなく爵位を継承できるようにするという勅令を出した。これは、グリーン陣営の将軍の称号が後継者に継承される前例となる。 清朝末期、咸豊帝と同治帝の治世後、八旗軍は完全に腐敗し、清政府は太平天国の乱を鎮圧するために地方防衛軍の力にさらに頼らざるを得なくなった。その結果、世襲称号を得た漢人官僚の数が増加した。例えば、曾国藩、左宗棠、李鴻章などは侯爵の称号を授けられており、位階的に言えば、この三人はいずれも上等であった。 最後に、定期的な給与と誠実さの維持について話しましょう 定期給与 清朝の官吏の給与は、正規官吏か一般官吏かに関係なく、階級に応じて計算されました。詳細は以下の通りです。 一等:銀180両、米180斤。 二等:銀155両、米155斤。 三位:銀130両、米130斤。 第四位:銀105両、米105斤。 五等分:銀80両、米80斤: 六等:銀60両、米60斤: 7位:銀45両、米45斤 八等級:銀40両、米40斤: 九等:銀33両、米33斤: 主流ではない:銀31両と米31胡。 雍正年間から、北京の官吏は補助金が不足し生活が苦しかったため、(米の量を変えずに)給料を2倍にするという勅令が出された。これがいわゆる「叙爵給与」である。太守、尚書、士郎などの高官の米給も倍増された。文武官吏の給与は毎年春と秋に支払われ、その締め切りは春は旧暦1月20日、秋は旧暦7月20日です。通常は各官庁で徴収され、その後順次支給されます。 インテグリティシルバー 清朝の官吏の給与水準は、すべての王朝の中では比較的低いはずであるが、その一方で、支出は比較的多額であった。そのため、清朝初期から雍正年間にかけて、各級の官僚は多くの違法な手段で私腹を肥やした。これは「郑銭」と呼ばれ、課税の過程で税金を追加したり、過剰に徴収したりすることで、民衆の負担を増やした。 そこで、雍正年間から清朝政府は、横領の割合を定め、それを国民に返すことを基本として、貞潔銀制度を実施することにした。つまり、貞潔を保つ目的で、横領銀の一部を取り出し、各級の官僚に分配したのである。扶持銀は、まず省・県・郡の地方官吏を対象に実施され、その後、軍人や首都の役人にも徐々に拡大されていった。 留意すべきは、扶養銀の額は官位によって決まるのではなく、官職の重要性と事務の複雑さによって決まるということである。同じ役職の知事でも給料は異なり、最高で2万両、次いで1万8千両、1万5千両と続き、最低でも1万3千両に過ぎませんでした。他人に味方するために人の地位に基づいて金額を決める方法よりも、物事の複雑さに基づいて誠実さを維持するための金額を決定する方法の方が合理的であるように思われます。 清朝の光緒年間の『法例集』の記録によると、地方知事、州知事、県官の給与は次の通りです。 知事:20,000~13,000両 知事:15,000~10,000両 州知事:9,000~5,000両 省監視委員:8444-3000両 道教の役人:6,000~1,500両 知事:5000~1300両 知事:2000~500両 郡守:2,000~400両 さらに、河川長官は6,000両、河川管理者は4,000~2,000両、穀物輸送長官は9,520両、塩輸送長官は5,000~2,000両、塩税長官は4,240~2,000両を受け取った。また、総督や州知事などの下級官吏や、県、郡、市の補佐官吏も、貞潔を保つために相応の銀を受け取ったが、その額は一般官吏よりもはるかに少なく、最低でも20両であった。 一般的に言えば、雍正帝の治世以降、官吏の給与は非常に高額になりました。しかし、最大の問題は、中央政府があらゆるレベルの地方政府に割り当てる公的資金が少なすぎるため、役人が給与を寄付することで問題を解決しなければならないことが多いことです。また、多くの客人や召使を養わなければならなかったため、「腐敗行為」が横行した。これらの「腐敗行為」による収入は、通常の給料や清廉潔白を保つための銀貨の数倍に上った。これにさまざまな腐敗が加わり、清朝末期には官僚制度は極めて腐敗していた。 |
<<: 明代に猛威を振るった日本軍の侵略が、なぜ清代には消え去ったのか?清朝はどのようにして日本の海賊を排除したのでしょうか?
>>: なぜ、解度使の役職が唐代に現れたのでしょうか?唐代における解度使の問題はどれほど深刻だったのでしょうか?
推薦する
ジェラオ楽器の特徴は何ですか?
ジェラオ族の民族楽器、ジェラオ八音太鼓楽器は音楽を運ぶものです。楽器を使って、柔らかな音楽や衝撃的な...
『清平月・善源書評で見たもの』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
清平月:善源書評で見たもの新奇集(宋代)雲の中に松と竹があれば、これからはすべて十分です。ボスは杖で...
華厳詩派の創始者は誰ですか?華厳派、万月派、豪芳派の特徴は何ですか?
今日は、興味深い歴史の編集者が、華堅派、万月派、好方派の特徴をお伝えします。皆さんのお役に立てれば幸...
天府祭の目的は何ですか?歴史上、天府祭にはどのような習慣や行事がありましたか?
天府節句は「6月6日」、「帰母節」、「昆虫王節」とも呼ばれています。 「6月6日」は比較的行事の少な...
「張谷農家」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?
張谷農家楚光熙(唐代)郡知事は清潔で質素で、深い谷間には人々が住んでいます。道は冷たい竹林へと続き、...
マスク・ムーンはどのようなミスを犯して、李婉と王希峰が何を考えているのか人々に知られてしまったのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
劉勇の「真夜中の音楽:凍った雲と暗い天気」:「暗い」で始まり、「壊れた野生のガチョウ」で終わる
劉雍(984年頃 - 1053年頃)は、もともと三弁、字は景荘であったが、後に劉雍、字は斉青と改めた...
金庸の小説『射雁英雄伝』についてのコメント:郭静が英雄になるまでの道のり
『射雁英雄伝説』は非常に成功した小説であり、郭静は非常に成功したキャラクターです。陳家洛や袁承志の高...
『紅楼夢』で賈震が王希峰に賈家を管理させた本当の意図は何ですか?
賈震が王希峰に寧国屋敷の管理を手伝わせた理由は何でしょうか?次は、興味深い歴史の編集者が歴史の真実を...
戦国時代になると、小さな属国が徐々に減っていきます。楚はどの属国を滅ぼしたのでしょうか。
今日は、おもしろ歴史編集長が楚国が滅ぼした属国をお届けします。ぜひお読みください~周知のように、戦国...
『紅楼夢』では、王希峰が寧国屋敷で騒ぎを起こしたとき、なぜ王夫人は傍観していたのですか?
『紅楼夢』の中で、王希峰が寧国屋敷で事件を起こしたとき、王夫人はなぜ傍観していたのでしょうか? これ...
「夜行」が作られた背景は何ですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
旅行の夜の思い杜甫(唐代)穏やかな風が吹く岸辺の薄い草、夜にマストが危険にさらされている船。星は広大...
「別れの思いと東流の水、どちらがいいか聞いてみろ」という有名な言葉はどこから来たのでしょうか?
まだ分からない:有名な一節「東流の水に尋ねてみよ、どちらに別れの気持ちが長いか、短いか」はどこか...
ドゥロン族が最もよく使う交通手段:ジップライン
ジップラインは川を渡る最も原始的な手段です。古くは「荘」と呼ばれていました。これは、渓流の急流の上に...
「草を踏む:冷たい草と煙が広がる」の鑑賞、詩人コウ・ジュンは王維の詩的な意味を引用した
孔鈞(961年 - 1023年10月24日)は、字を平中といい、華州下桂(現在の陝西省渭南市)の人で...