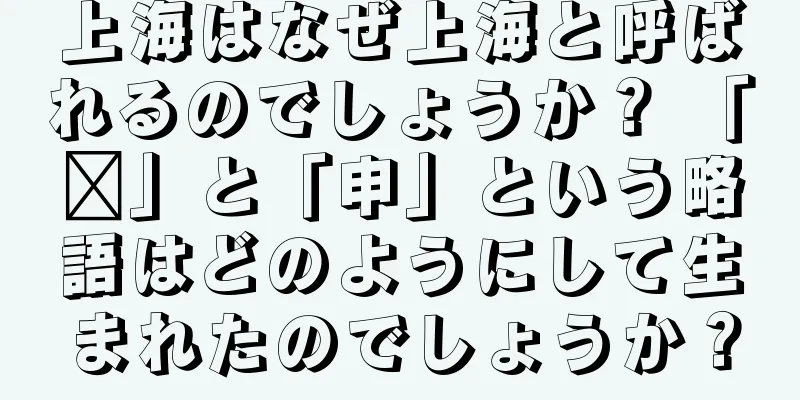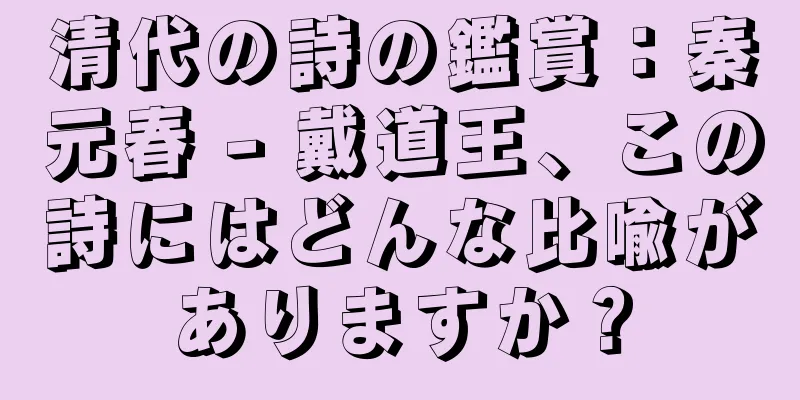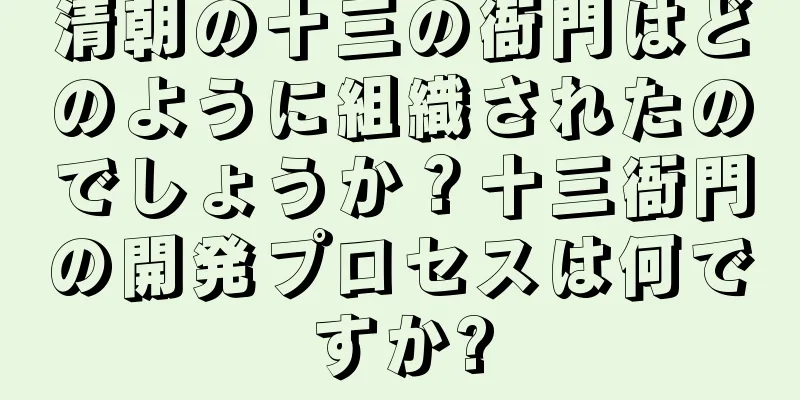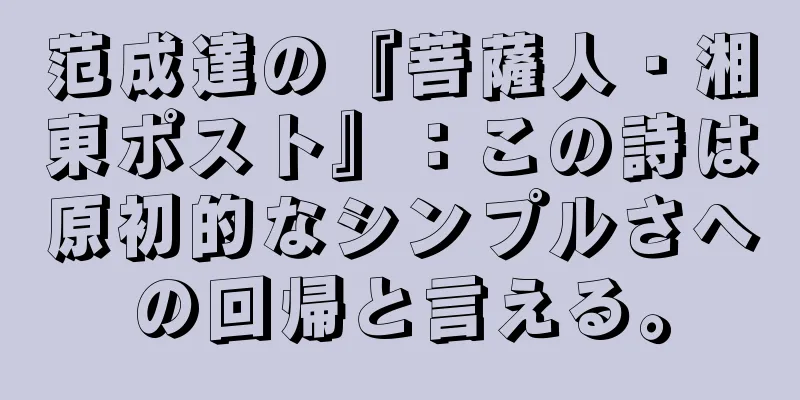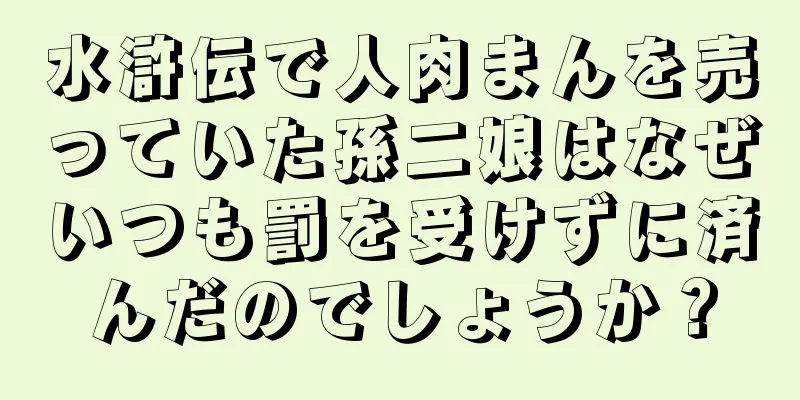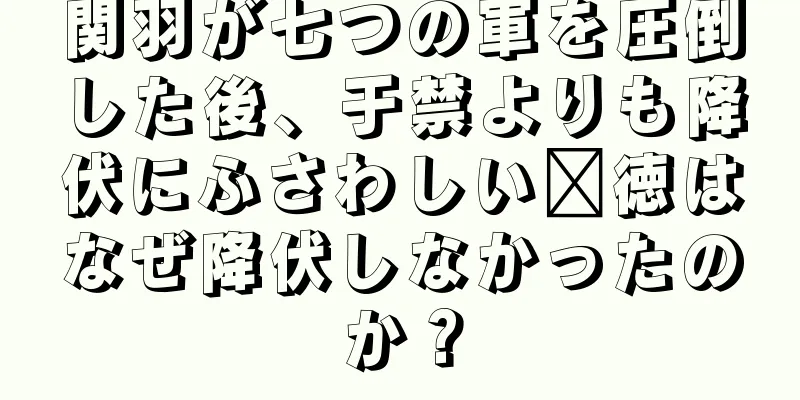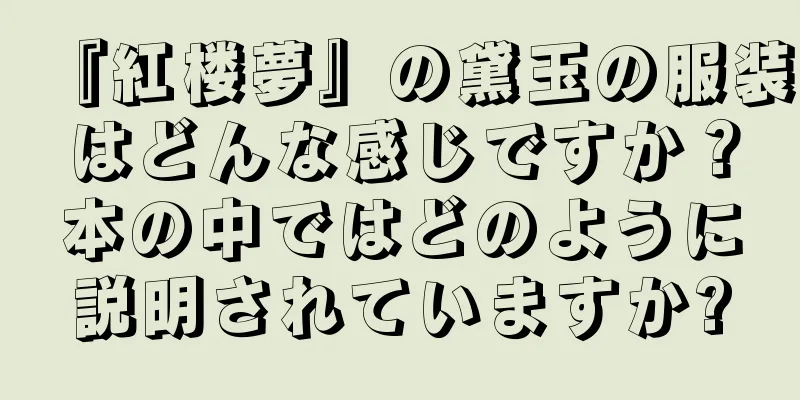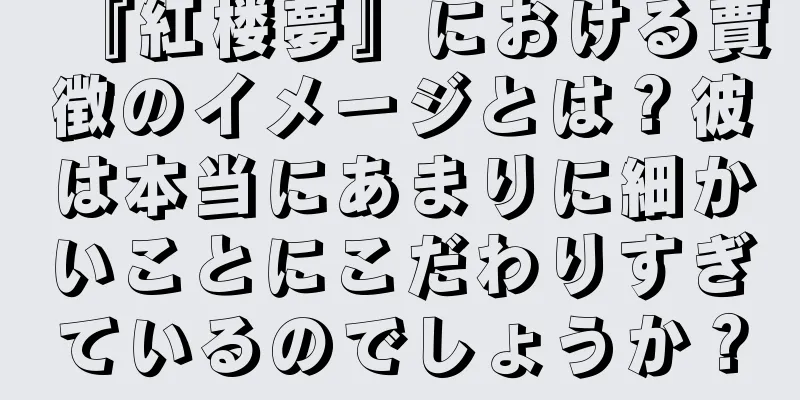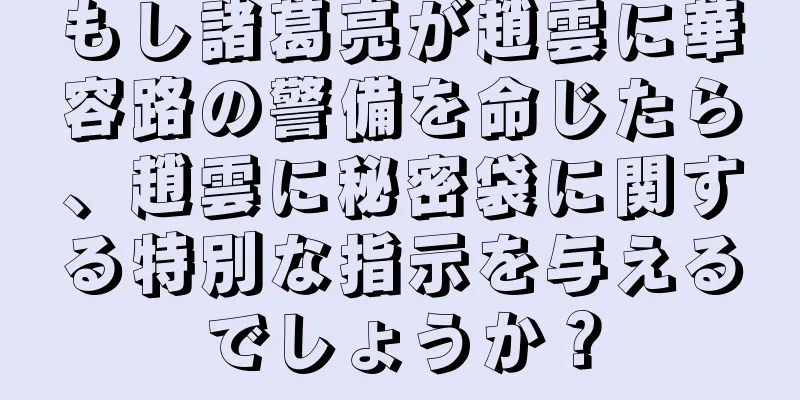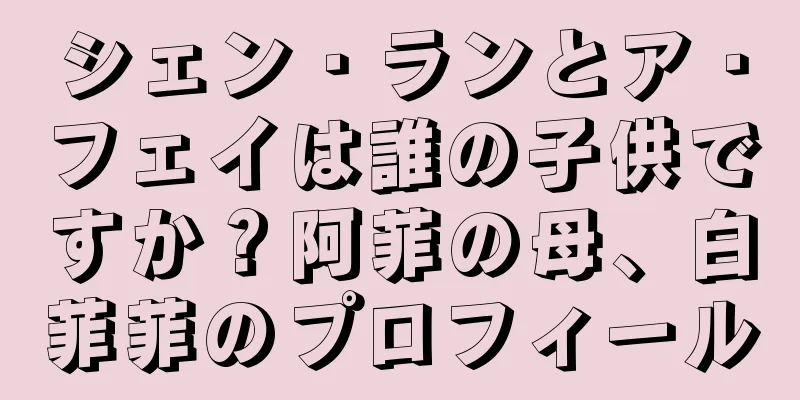日本の忍者はどうやって生まれたのでしょうか?忍者の全盛期はいつでしたか?
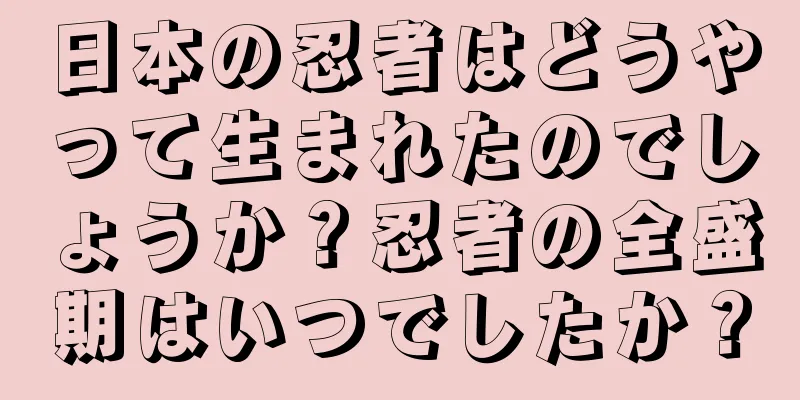
|
今日は、Interesting History の編集者が、皆さんのお役に立てればと、日本の忍者の起源についてご紹介します。 ゲームでは、古代日本を反映したシーンがよく見られます。つまり、黒仮面の男が夜陰に紛れて猛スピードで走っているところ、突然空中に飛び上がり、手から数本の手裏剣を放ち、すべての矢が標的に当たり、数人の悪者が地面に倒れるというシーンです。悪党のリーダーが刀を手に駆け寄ると、仮面の男は冷静に背中の忍者刀を抜いた。一瞬にしてリーダーは地面に倒れた…これが、はるか昔に登場した伝説の日本の忍者だ。 1. 忍者の起源は飛鳥時代に遡る 望月重家の『忍術扇伝』によれば、飛鳥時代の日本には、聖徳太子のスパイであり、日本最初の天皇である推古天皇の摂政であった「大伴兵遠」という男がいた。 聖徳太子は日本の飛鳥時代の天皇の政治家であり、大化の改新を推進した人物です。彼の最大の功績は、607年に隋の使節を中国に派遣し、外交関係を確立し、中国の制度を学び、日本初の文明を推進したことです。 1958年から1983年まで、日本の1万円札の肖像は聖徳太子でした。 歴史の記録によると、聖徳太子は「八耳の王子」として知られ、王子や貴族から庶民まで、あらゆる人のことを知っていました。これは、聖徳太子の目となり耳となった大伴へらとのお陰です。大伴へらとおは、さまざまな立場で現れ、聖徳太子にとって有益な情報を数多く収集しました。 さらに、この時代の日本は、豪族が政治を牛耳っていた時代であり、聖徳太子のような高貴な権力者であっても、政敵に殺される可能性はいつでもありました。推古天皇の前任者である崇峻天皇は、有力な蘇我氏によって暗殺された。したがって、聖徳太子にとって総合的な知性を持つことは、国を治めるために必要であるだけでなく、自分自身を守るためにも必要であった。 しかし、肖像画すら伝わっていないこの謎の大伴勇者は、当時は忍者ではなく、日本語で責任を意味する「しのべん」と呼ばれていました。しかし、後世では彼が忍者の祖であり、甲賀流忍者の創始者であると一般的に認識されています。 また、歴史の記録によれば、同時代の日本の最高権力者であった蘇我氏にも、同様の諜報員がいた。しかし、彼らの「忍弁」は、蘇我氏の権力を揺るがす恐れのある政敵を排除するために主に使われていたという違いがある。実はこの男は殺人者であり暗殺者です。 蘇我氏の忍者の話は噂に過ぎなかったが、後世の記録には、この時代に忍者が殺人者として使われていたことが明確に記されている。同じく飛鳥時代の天武天皇の治世には、天武天皇と弘文天皇が権力を争った「壬申の乱」の際、多武宮という忍者が天武天皇のために軍事的に重要な貢献をした。これは忍者が正式な戦争に参加した最も古い記録です。 つまり、日本の飛鳥時代、つまり7世紀には、忍者の最も重要な2つの任務である情報収集と武力攻撃が正式に確立されていたのです。そこから栄光と死が隣り合わせた長い歴史の道が始まった。 2. 忍者の起源と中国 大伴ヘラトが最古の忍者とみなされるならば、彼の出身地である日本の甲賀地方は忍者、さらには忍者文化の発祥地です。 甲賀は、現在の日本の関西地方にある滋賀県周辺の地域です。滋賀県は面積はそれほど広くありませんが、日本最大の湖である琵琶湖を有しています。古くは近江国に属していました。研究によれば、滋賀県の初期住民の多くは中国大陸や朝鮮半島からの「移民」や「帰化人」であったため、ここは日本で初めて異質な文化や技術、血縁が融合した場所であった。 中国人の日本への移住は、中国の商王朝、春秋戦国時代から始まりました。秦・漢の時代になると、日本への中国人移民の勢いはさらに高まり続けました。歴史には「陳勝らが蜂起すると、全世界が秦に反旗を翻し、燕、斉、趙の数万人の民が朝鮮に逃れた」と記されている。このうち相当数の民が朝鮮半島を経由して海を渡り、日本列島にやって来た。秦末期には、始皇帝の扶蘇や胡亥などの王族も次々と日本に逃れた。 紀元前109年、漢の武帝が4つの郡を設置して朝鮮北部を直接統治した後、多くの漢人が商売のために朝鮮の4つの郡に移住し、これらの商人の子孫のほとんどがそこに留まりました。 313年、朝鮮半島の楽浪郡と帯方郡が高句麗の手に落ち、そこに住んでいた漢人は国を離れざるを得なくなった。一部の漢人は祖国に帰還したが、他の漢人は南下して海を渡り日本に移住した。 日本の歴史書『日本書紀』には、この時代に中国から日本列島に渡来した移民の例が数多く記録されている。 応神14年、弓月君は百済の120郡の民を率いて日本へ渡りました。 応神16年、百済から王仁がやって来て、太子の土道智浪子が彼の師となり、様々な経典を学んだ。 応神20年、阿智主とその子の司主は17ヶ国から信者を率いて日本に来ました。 応神37年、阿吉士珠、杜家士珠らが高麗を通じて呉に派遣され、裁縫娘を求めた。その後、呉王は雄元、帝元、武志、安志の4人の娘を連れて帰った。 … 中国から日本への渡来人は、弓削君を祖とする秦氏と阿智志主を祖とする漢氏の二大系統に大別され、その数は相当な数に上ります。公月君の秦氏は3万5千人にも達し、阿志士竹の漢氏を加えると、その総数は6万から7万人に達する。 これらの「移民」は、農業、土木工学、陶器の焼成、繊維と養蚕、金属の精錬、軍事戦略、さらには仏教文化までも中国から持ち込んだ。彼らは、統一された中央集権的な大和朝廷の樹立にも重要な役割を果たしました。 大和朝廷は、彼らの文化や技術の習得を容易にし、また彼らの動向を監視するために、これらの「渡来人」に京都に近い関西地方への居住を許可しました。これにより、滋賀県、三重県、和歌山県など、当時未開発であった地域が急速に発展しました。これらの郡は、将来、忍者が大量に出現した最初の地域でもありました。 これはまた、忍者文化の起源が「移民」にまで遡る可能性があることを間接的に示しています。このように、大友氏や服部氏のような渡来系忍者一族が出現したことは、驚くべきことではありません。聖徳太子が伊賀服部氏を情報収集に派遣したという史料によれば、服部氏は伊賀流忍者の祖先かもしれない。 3. 忍者は支配者の武器に過ぎない しかし、忍者という職業が栄えた戦国時代までは、後世のいわゆる忍者は忍者とは呼ばれず、統一された呼称もありませんでした。飛鳥時代には「忍弁」、奈良時代には「斥候」など、時代によって呼び名が異なり、戦国時代に最も多く使われた呼称は武田信玄が与えた「乱馬」でした。 また、どの時代においても忍者の地位は低いものでした。初期の忍者のほとんどは高貴な武士ではなく貧しい農民の出身でした。日本の貴族の目には、忍者は単なる武器や道具に過ぎません。任務上、正面から敵と戦うことはほとんどなく、目的を達成するためにはあらゆる手段を講じる。そのために忍術が生まれた。 ほとんどの忍者は(リーダーを除いて)相手に正体がバレないようにマスクを着用しています。彼らは誰にも本当の顔を見せることはできず、生涯匿名のままでいなければならず、将来犯罪が暴露されないように一言も残すことはできない。業務を遂行する上では、命令に絶対的に従わなければならず、自由は一切ありません。 しかし、彼らの仕事は概ね似ており、主に主人のために秘密計画、破壊活動、暗殺、敵の最前線情報の収集、敵の支援基地の混乱、その他のスパイ活動を実行します。 いわゆる忍術については、その理論的基礎は主に中国から日本に伝わった孫子の兵法と、「風のように速く、森のように遅く、火のように攻撃的で、山のように動かない」という意味の「風林火山」という四字熟語、そして山中での魔法や待ち伏せ術などから構成されています。 4. 忍者の黄金時代 - 日本の戦国時代 戦国時代は忍術が栄えた時代でした。乱世の時代、各地の台頭する大名は、戦いや情報収集のために忍術を緊急に必要としていた。 例えば、「戦国時代最初の軍師」として知られる武田信玄は、忍者の熱心な支持者でした。彼は生来疑い深く、他人が自国の秘密を知ることを嫌うため、探知と暗殺といった問題に対処するために特別に忍者のグループを訓練した。彼は甲斐、信濃、越後の浮浪者や山賊を組織し、山岳戦などの戦闘技術を教え、偵察隊や諜報員として育てた。これが有名な武田の「乱覇」である。 一方、この時代は、外国からの技術の導入や、さまざまな産業の職人の増加により、多くの忍者が民芸職人としての技術を生かして諜報活動に従事するようになりました。 この時点で、忍者の職業にはすでに完全なシステムと理論があり、4つの基本的な教訓が含まれていました。 忍術を乱用しない(公務にのみ使用可能) 自尊心をすべて捨て去る(逃げることが最も重要です) 沈黙しなければならない(たとえ命を失うとしても) 正体を明かしてはならない(身を隠すのは忍術の基本) Ninjaの組織管理システム: 忍者:上忍、中忍、下忍。 シンクタンク忍者とも呼ばれる上忍は、全体的な戦闘手順の計画を担当しています。 中忍は最前線の戦闘の指揮官であり、当然ながら忍術も優れている必要があります。 下忍は「肉体の忍者」としても知られ、最前線の戦士です。 3 つの間には厳格な階層関係があり、明確な区別があります。 忍者が使用する武器は、その特殊な用途のため、非常に特殊です。敵から身を守るだけでなく、逃げる、盗む、混乱を引き起こすなどの機能も備えています。忍者の多くは、通常の武士の刀よりも少し短い忍者刀や、鎖棒などの武器を使い分け、「一刀両断」の武器を持っていました。例えば、忍者刀の鞘には登山に使えるロープが巻かれていることが多く、刀の下部は開いて潜水時の呼吸管として、盗聴時のメガホンとして使うなど、様々な用途がありました。 国内の武将の間で権力が分割された結果、さまざまな忍術の流派が自然に形成されました。流派名は、忍術が発達した地域の地名に由来するものが一般的で、武蔵流、甲斐流、越後流、信濃流、甲賀流、紀伊流、伊賀流などがある。また、青森中川流、山形羽黒流、新潟上杉流、加治流、長野甲陽流、芥川流などもある。 その中でも伊賀と甲賀の忍術が最も強力です。これら 2 つの場所は、険しい山々と危険な障害物に囲まれた小さな閉鎖盆地に位置し、独自の小さな世界を形成していますが、日本の中心部に近いため、その戦略的な位置は非常に重要です。 さらに、甲賀・伊賀には数多くの神社、寺院、荘園があり、京都文化の影響を深く受けています。戦国時代に荘園制が崩壊し、この地は「小戦国」となりました。狭い土地に60もの小藩が乱立し、熾烈な争いが繰り広げられたことが伺えます。彼らは互いに同盟を組み、互いにスパイし、互いに殺し合った。誰であっても、一度倒されてしまうと、再び立ち上がることは難しい。 その結果、有力な一族は忍者戦士を飼うようになりました。統計によると、各一族には30~40人の忍者がいました。その結果、修行に便利な山岳地帯であると同時に、常に激しい戦いが繰り広げられる場所であったこの地が、忍者発展の拠点となったのです。時が経つにつれ、伊賀忍術は日本一になりました。 5. 伝説の忍者 ほとんどの忍者ははかない存在であり、たとえ激動の戦争を生き延びたとしても、名前や功績を残せないかもしれません。しかし、忍者という職業のトップレジェンドになったり、忍者という職業自体を超えて後世に名を残すような人も非常に少ないのです。 蜂須賀小六 豊臣秀吉の右腕、穂香小六。かつては美濃の盗賊団「河鍋の水」の頭領であり、壁登りや屋根上走などの武術を極めました。 その後、秀吉は織田信長に寝返り、信長のもとで着々と勢力を伸ばしていきました。秀吉を助けた武功により、穂香小六らは正規軍に編入され、盗賊の汚名を晴らされました。彼らはのちに豊臣秀吉の忍者部隊となり、大きな戦いで活躍しました。保須賀小六は盗賊としての身分を清算した後、保須賀正勝と名を変え、阿波国の領主として生涯を終えた。 服部半蔵 戦国忍者に関して言えば、もうひとり紹介しなければならないキャラクターが、服部半蔵としても知られる竹中青紫です。伝説によると、この忍者はついに、何世代もの忍者が成し遂げられなかった忍者の真の意味を悟ったそうです。服部半蔵の家族は実は中国人でした。彼の先祖の本来の姓は秦でした。彼は幼少期に中国から日本に渡り、京都の近くに定住しました。その後、伊賀に移り住み、地元の住民に溶け込むために姓を服部に改めました。 服部半蔵は徳川家康に仕え、天下征伐に多大な貢献をした。 1583年、織田信長が京都本能寺で武将の明智光秀に暗殺されたとき、徳川家康も京都におり、信長に同行したものの兵士は連れずに京都へ向かった。信長が亡くなるとすぐに、信長の忠実な同盟者であった家康は危険にさらされました。この時、服部半蔵は即断即決し、徳川家康を連れ一夜にして京都を出発し、人里離れた山道を通り、数日後に無事三河領に帰還した。 服部半蔵の優れた功績により、服部忍者一族は徳川時代に高く評価され、大きな発展を遂げました。服部半蔵は服部忍者一族のリーダーの世襲称号となった。 結論:実は、忍者という名称が本格的に定着したのは江戸時代(徳川幕府時代)になってからでした。しかし、この時代から日本はより長い平和な時代に入り、戦いやスパイ活動を生業としていた忍者たちの歴史上の活動は次第に衰退していきました。忍者の職業は衰退し、多くの忍術が失われていきました。忍者の活動に関する最後の記録は、1637年の島原の乱のときで、忍者は幕府によって派遣された正規軍として戦った。 |
<<: 清軍の関への侵入は漢文化にどのような影響を与えたのでしょうか?清朝が中国に与えた影響を美学の観点から見てみましょう!
>>: 海外で展示が禁止されている文化財は何ですか?なぜこれらの文化財は海外での展示が禁止されているのでしょうか?
推薦する
宋真宗と劉鄂は非常に親密な関係でした。伝説によると、どの王位が劉鄂と関係があるのでしょうか?
宋の真宗皇帝と劉鄂は非常に親しい関係にあった。天熙という帝号は劉鄂と関係があると言われている。次は興...
孟浩然の古詩「東山を出て漢川を見る」の本来の意味を鑑賞する
古詩「東山を出て漢川を眺める」時代: 唐代著者: 孟浩然漢川への旅で書かれたタイトルこの外国は私の土...
欧陽秀の「秋の思索」:この詩は自然に流れ、華美な言葉はないが深い愛国心が感じられる。
欧陽秀(おうようしゅう、1007年8月1日 - 1072年9月22日)、字は永叔、晩年は随翁、劉義居...
五天仏が倒せない神はどれですか? 1つは孫悟空
テレビシリーズ「続西遊記」を見たことがある観客は、このテレビシリーズで最も印象に残るのは3回繰り返さ...
程蓋の「高楼・古思」:この詩の構成芸術は独特である
程蓋は、雅号を鄭伯といい、眉山(現在の四川省)の出身であった。蘇軾の従兄弟である程志才(号は鄭福)の...
『善花子:我ここに我が心問ふ天上』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
善花子:私の気持ちは天に尋ねたい劉晨翁(宋代)ここでの私の気持ちを天国に聞きたいのですが、次に会える...
蜀漢末期、諸葛亮はなぜ張豹の死という悲しい知らせを受け入れることができなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
当時、李白は唐の玄宗皇帝の勅命を受け、「南陵入都子告」を著した。
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
なぜ王希峰は、人生の最後の瞬間まで平児を側室に昇格させることを望まなかったのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
李克用とはどんな人物だったのでしょうか?唐代の名将、李克用は歴史上どのように評価されているのでしょうか?
李克用(856-908)は、神武川新城出身で、唐代末期の将軍であり、沙托族の一員であった。愛称は「李...
『剣客』における朱其其の友人であり追跡者、パンダ・エルの簡単な紹介
古龍の小説『武林外史』の登場人物である熊茂児は朱其其に恋をしている。 2000年のテレビシリーズ「武...
鄭板橋の詩「桃葉渡し」鑑賞
ピーチリーフフェリー橋には低い赤い板があり、秦淮河は長く、緑の柳が揺れています。春風はツバメの舞いを...
『紅楼夢』に王希峰という男が登場しますが、彼の名前の意味は何ですか?
『紅楼夢』には王希峰という男が登場します。彼は『風秋鸞』の男性主人公です。当時はこれが普通でした。 ...
太平広記・巻102・報復・趙文馨の原作の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
汝南の袁家はどれほどの力を持っているのでしょうか?なぜ袁術と袁紹はいつも彼のことを言及するのでしょうか?
古代の長い歴史の中で、興亡を経た家は数え切れないほどありますが、記憶に残るのはほんの一握りです。今日...