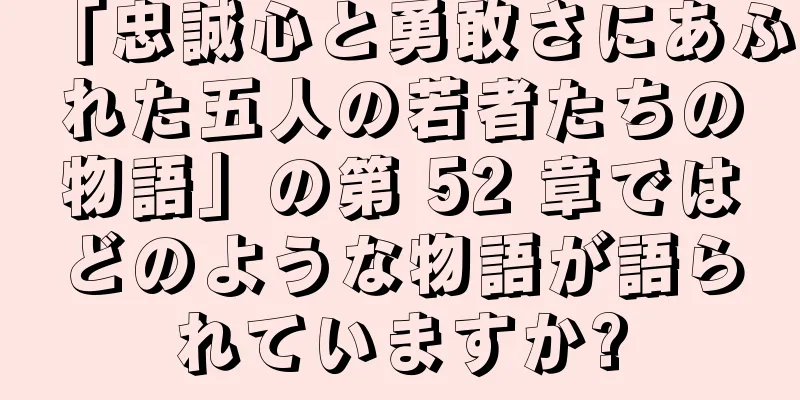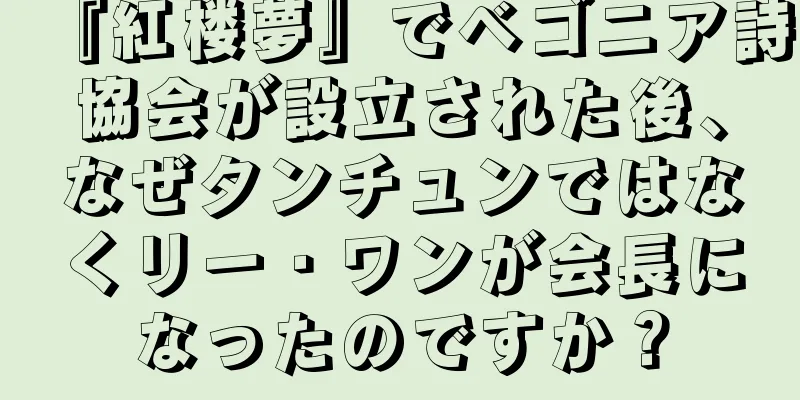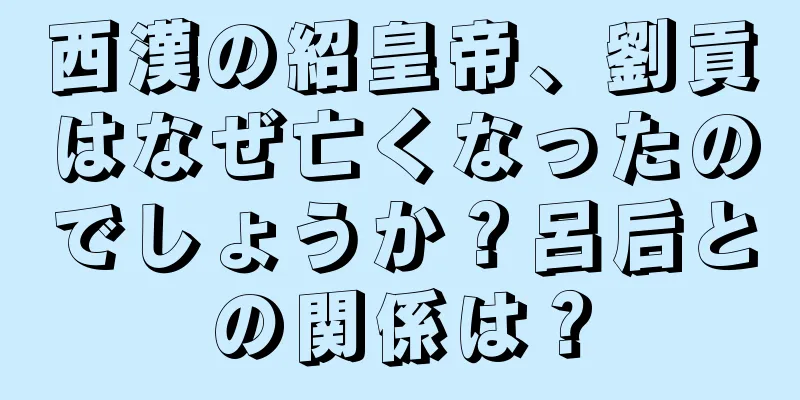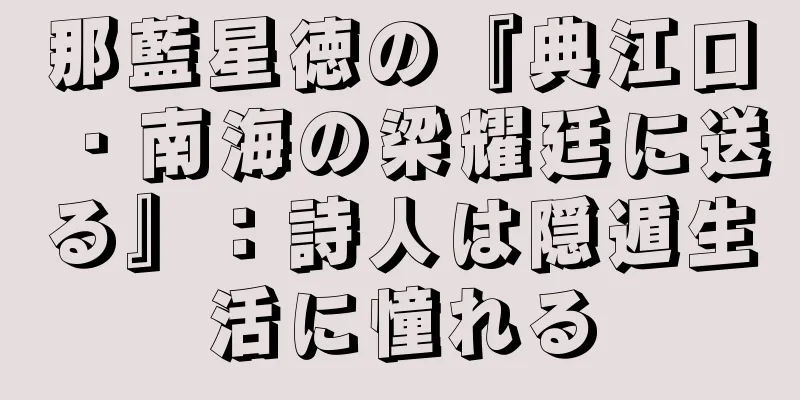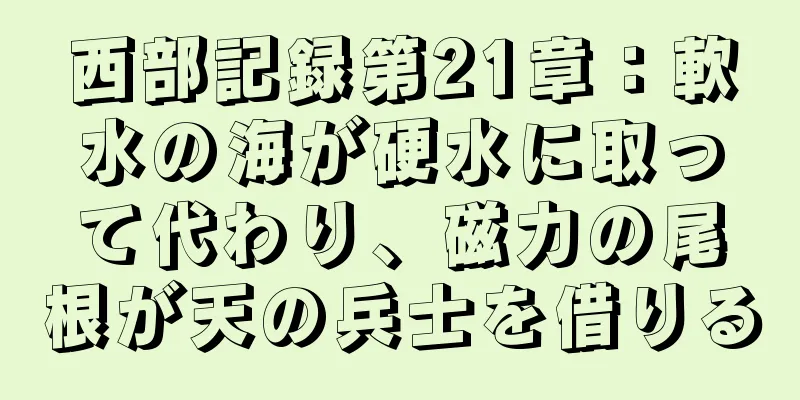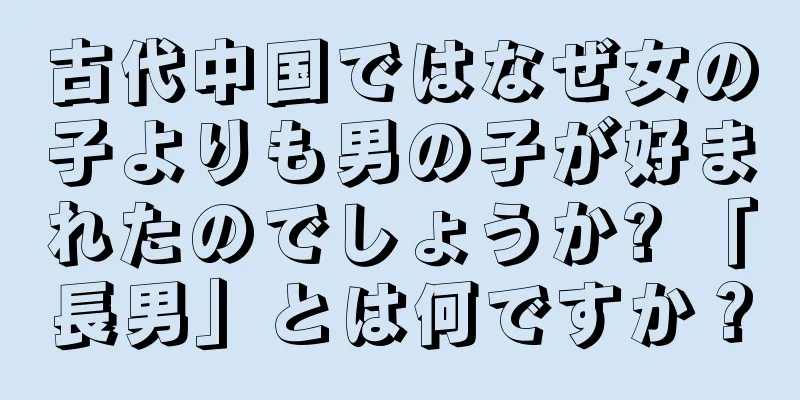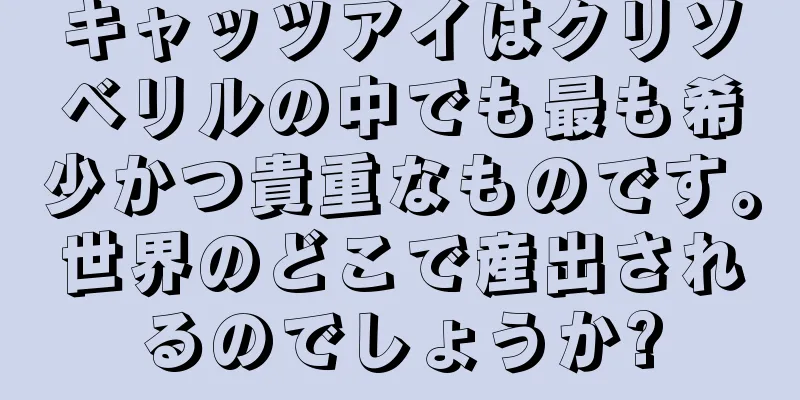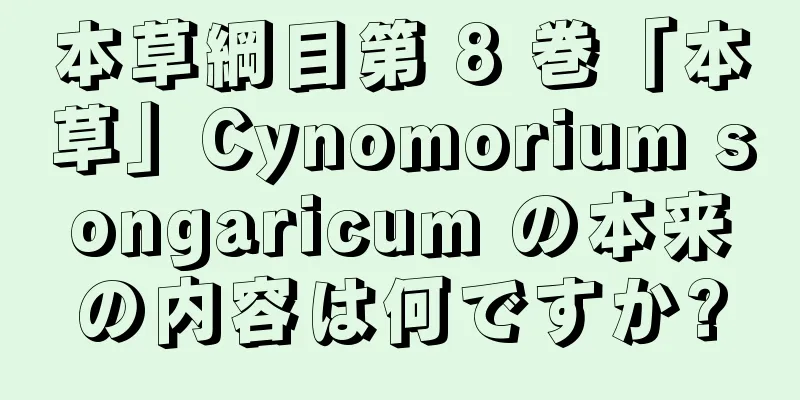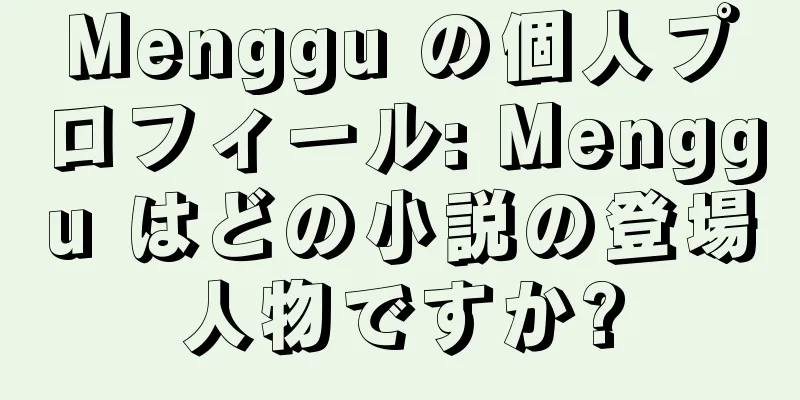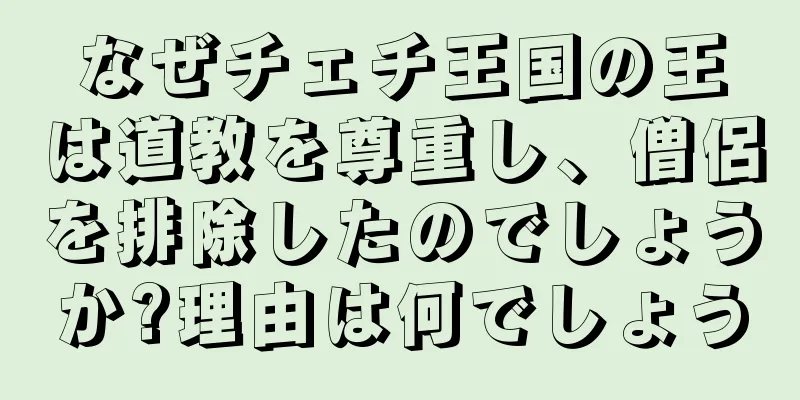明朝の内閣の大臣はどのようにして選ばれたのでしょうか?内閣総理大臣はどの程度の権限を持っているのでしょうか?
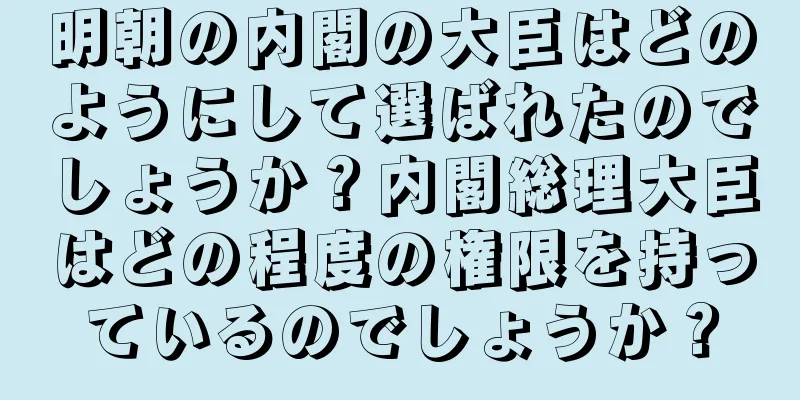
|
内閣総理大臣がどれだけの権力を持っているかご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。Interesting Historyの編集者がお教えします。 実際、明王朝が成立した当初は宰相という役職があり、明王朝では多くの人が宰相を務めました。しかし、「胡維勇事件」が起こった後、朱元璋は首相の地位を直接廃止した。朱元璋は非常に勤勉な皇帝であったため、「早起きして夜寝る」と言われていました。しかし、彼のエネルギーには限界があり、修行中に自らこの制度を廃止しました。彼は決して宰相を立てませんでした。皇帝は皆朱元璋のような人物ではないので、彼には多少の調整しかできず、内閣の宰相が誕生しました。 内閣総理大臣の最大の権限は、重要な朝廷文書に関する取り扱い意見を起草し、天皇が採択できるようにすることである。これが一般に「ピャオニ」と呼ばれているものです。天皇はそれを検討した後、赤ペンで草案に対する最終決定を下しました。これは一般に「赤インク承認」として知られています。内閣総理大臣の権力と地位は、天皇が「提案」をどの程度採用するかによって決まる。天皇が採用する思想が多ければ多いほど、内閣総理大臣の権力と地位は当然高まり、その名声はより高まるであろう。逆に。内閣の首席大臣は、内閣において第一位の大臣である。明代において、「寿夫」は内閣の「慈夫」や「秦夫」に対抗する、内閣の第一級大臣(内閣に直接入った翰林学者も数人いた)の尊称であった。一説には明の英宗天順年間の李仙に始まるとされ、明の仁宗の治世に第一大臣で教師を務めた楊士奇に始まる、明の成祖が内閣を開いた時、明の神宗の治世に始まるという説もある。朱棣は、主に宮廷の大臣と内閣の大臣から構成される内閣を設立した。その内閣の官位は五位で、人数は様々であった。彼らの主な役割は皇帝に助言を与えることであった。その後、内閣大書記官の権力は拡大し、天皇に助言を与えるだけでなく、軍事や国政の意思決定にも参加するようになった。嘉靖年間には、内閣大書記の朝廷出席の地位は六大臣の地位を上回り、事実上の官房となった。内閣の首席大臣は首相ほど有名ではないものの、事実上の首相となっている。 建文4年(1402年)8月、朱棣は謝進、胡広、楊容など翰林書院の7人の官吏を武門に派遣し、文院に勤務させて政務に参加させた。この政務は次第に「内閣」と呼ばれるようになった。当初、内閣の大臣たちは階級は異なっていたものの、地位は似ており、権限にも明らかな違いはありませんでした。その後、閣僚は徐々に分裂し、「三人の楊」と陳勲が相次いで内閣で比較的特別な地位を占めるようになった。 天順・成化年間に李賢が丞相を務めたころから「丞相」という職が生まれ、徐々に制度化されていった。嘉靖年間、明代の世宗皇帝は勅令や勅令の中で、内閣の最高大臣を指すのに初めて「寿福」「袁福」「寿辰」「宰相」という用語を公式に使用した。 嘉靖、隆清、万暦初期にかけて、内閣の大臣は相当な権力を持っていた。内閣では、文書の起草に独断的な傾向がある。最終決定を下すだけでなく、他の閣僚の意見を聞かない。内閣外では、6つの省庁に強い影響力を持つ。 同時に、張聡、夏燕、厳松、徐潔、高公、張居正らが相次いで首相の座をめぐって激しい競争を開始した。張居正の治世中、内閣の太守の権力は頂点に達した。一方では内閣のトップであり、閣僚は太守の部下に降格されたが、他方では各省庁の空席、特に人事部と陸軍部の大臣の任命と昇進は、実質的にすべて張居正によって決定された。 張居正の死後、皇帝の不信、内閣と六省の争い、宦官の権力の再拡大などにより、内閣長の権力は衰え始めた。首相をはじめ、閣僚の大半は無能のまま留任し、かつてのような「有力大臣」は存在しなくなった。 |
<<: 明代の三大天才は誰ですか?なぜ唐伯虎は選ばれなかったのですか?
>>: 歴史上、ひどい時代とはどのような時代でしょうか?繁栄している時代でも、誰もが不安を感じる時があります。
推薦する
お茶に関する詩にはどんなものがありますか?詩はどこから来たのですか?
本日は、『Interesting History』の編集者が、お茶に関する古代の詩 30 編をご紹介...
宋仁宗の次の皇帝は誰でしたか?宋仁宗の死後、誰が皇帝になったのですか?
宋仁宗の次の皇帝は誰でしたか?宋仁宗の死後、誰が皇帝になりましたか?宋仁宗の次の皇帝は宋応宗趙叔であ...
唐寅の「菊」:詩人は菊を使って自分自身を例えており、これはバニラ美のスタイルに属しています。
唐寅(1470年3月6日 - 1524年1月7日)、号は伯虎、号は子維、別名は六如居士。蘇州府呉県南...
歴史上最も古典的な茶詩:陸同の「孟建義が私に新しいお茶を送ってくれたことへの感謝の気持ちを書いた」
お茶は間違いなく中国人の最も好きな飲み物の一つです。お茶の歴史も非常に長く、漢の時代から人々の目に触...
「忠勇五人男物語」第四章の主な内容は何ですか?
燕公は泣きながら金毛鼠の公孫策に印章泥棒を騙すよう説得した。封印が解かれたとき、五代目師匠は密かに嘆...
歴史上の尚官婉児:尚官婉児は文学史にどのような貢献をしたのでしょうか?
はじめに:唐代の美しい宰相、尚官婉児について、『新旧唐書』は彼女の暗い面を誇張している。唐代の『昭科...
本当に小雀は西人によって趙叔母さんと一緒になるように手配されたのでしょうか?
本日は、Interesting History の編集者が、皆様のお役に立てればと願って、小闕につい...
趙霊芝は『脱ぎたいけど寒さは引かない』でどのような修辞技法を使ったのでしょうか?
趙霊芝が「脱ぎ捨てたいが、寒さは去らない」でどのような修辞技法を使ったか知りたいですか?この詩は感情...
建張宮遺跡:土塁と漢王朝の石碑のみが残る
建章宮前殿の遺跡建章宮前殿の遺跡は高宝子村にあります。高い土塁は今も地面に残っており、その上には巨大...
『清河を渡る』の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
川を渡って清河渤へ王維(唐代)川を漕いでいくと、水は世界の果てまで届きます。突然、空の波が開き、郡内...
「阿農歌:江陵から揚州へ」は南朝時代の民謡で、川沿いの旅の生活を歌っている。
南北朝時代は、南朝と北朝の総称です。民族の分裂が激しく、北方の少数民族と漢民族が南方へと大移動し、同...
トン族の衣服の特徴は何ですか?
梁思成:「国家の傲慢さや劣等感は、いずれも自国の歴史や文化に対する無知から生じます。自国の過去を理解...
「四聖心の源」第 4 巻: 疲労と怪我の説明: 便に血が混じる 全文
『四聖心源』は、1753年に清朝の黄元宇によって書かれた医学書で、『医聖心源』としても知られています...
白居易の有名な詩の一節を鑑賞する:竹やヒノキはすべて凍死し、裸の人々はなおさらだ
白居易(772-846)は、字を楽天といい、別名を向山居士、随隠仙生とも呼ばれた。祖先は山西省太原に...
なぜ賈歓を称賛しながら、王希鋒と賈廉とその妻の顔を平手打ちしたのか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...