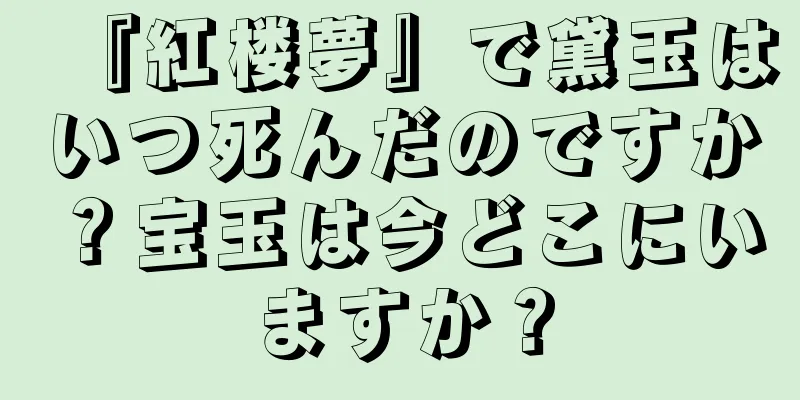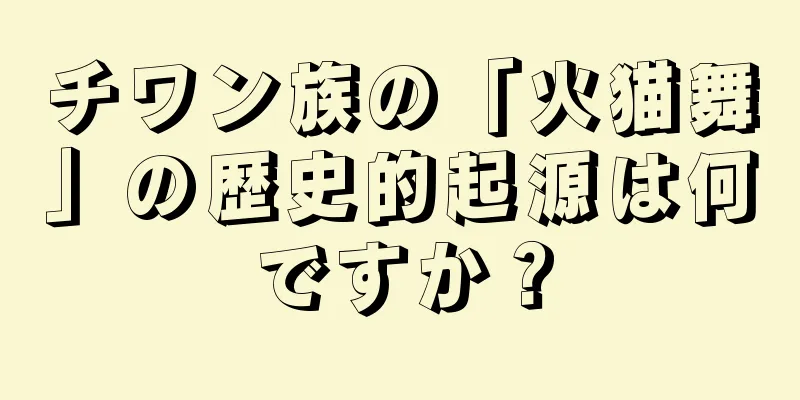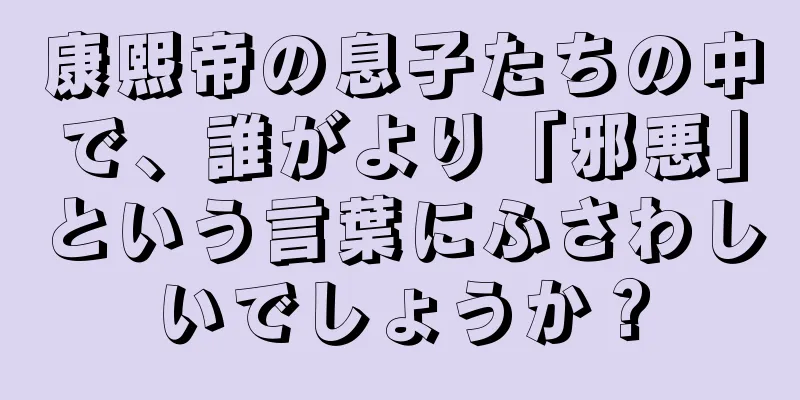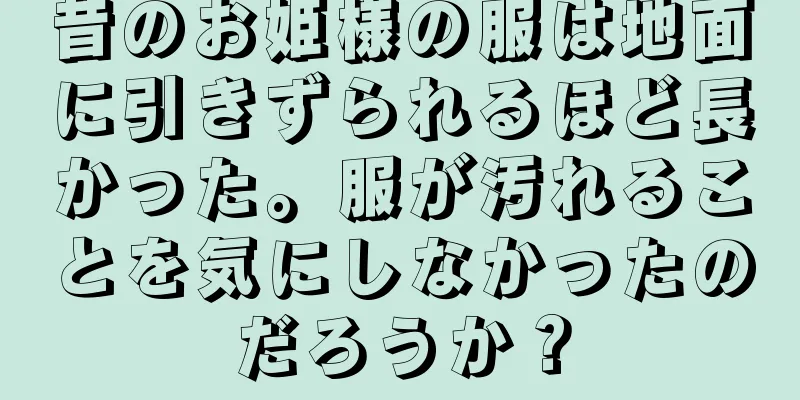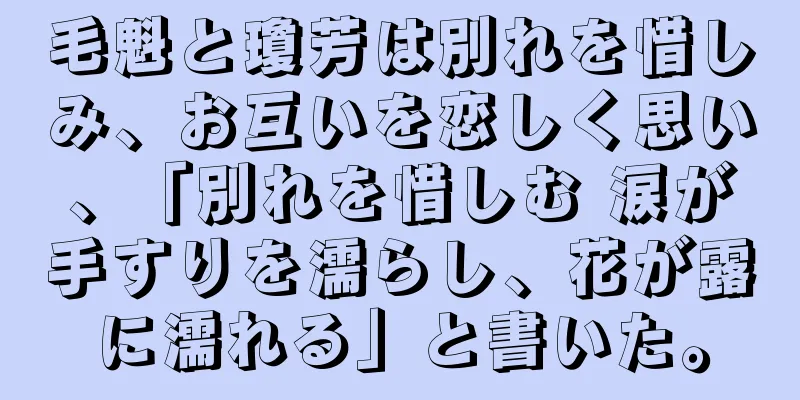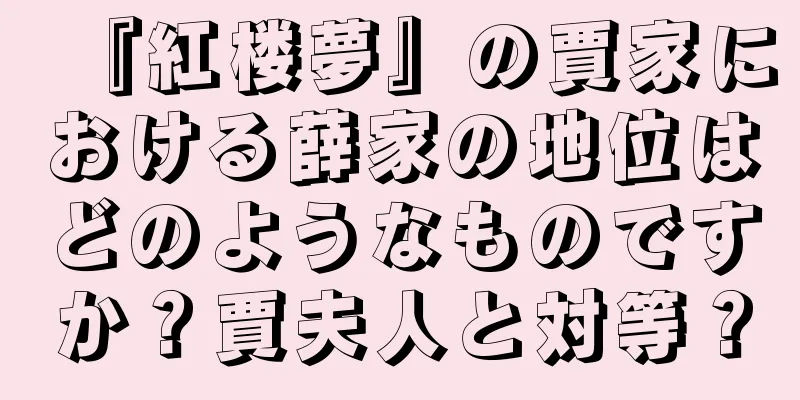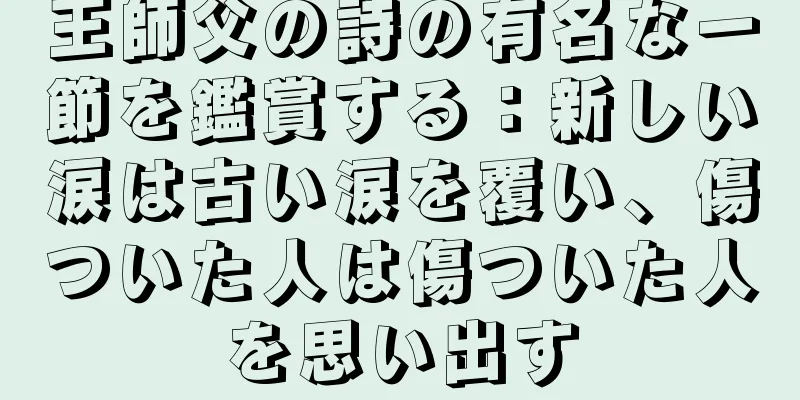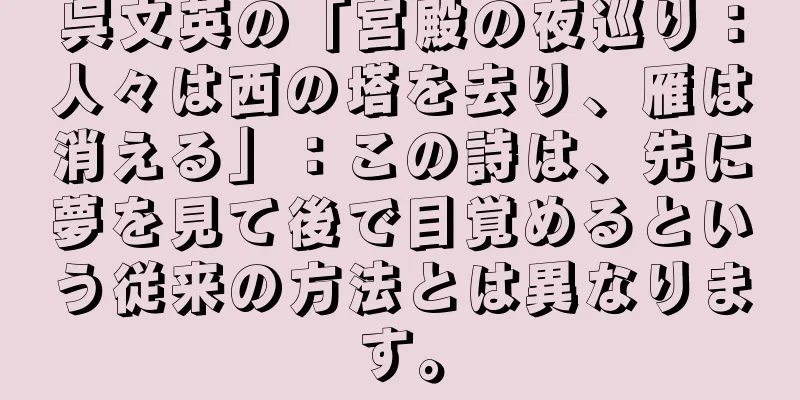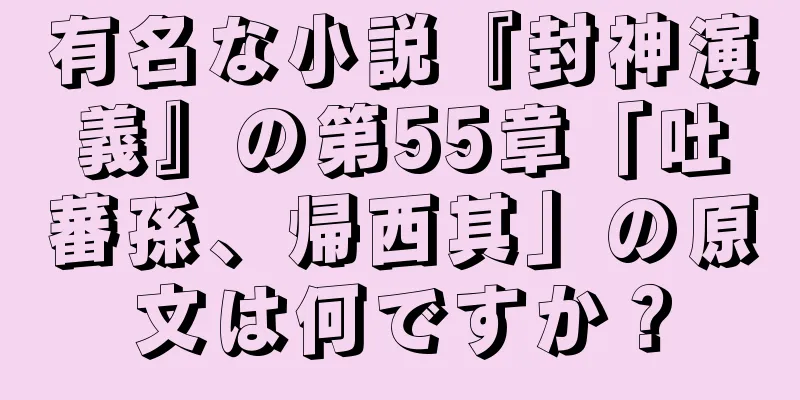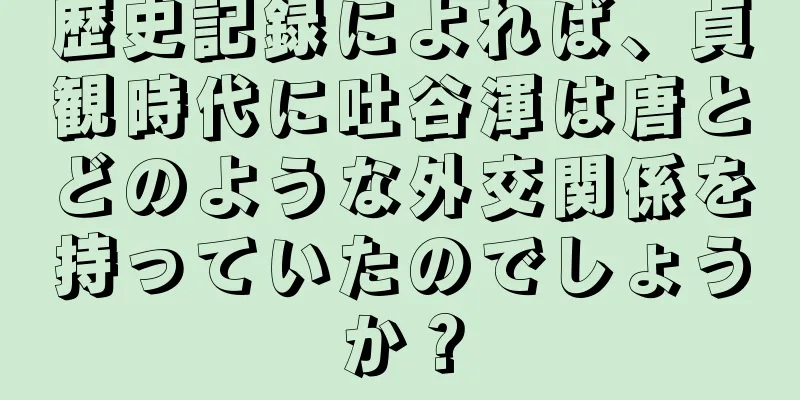趙匡胤はどのようにして国を統治したのでしょうか?趙匡胤の文政は良かったのか悪かったのか?
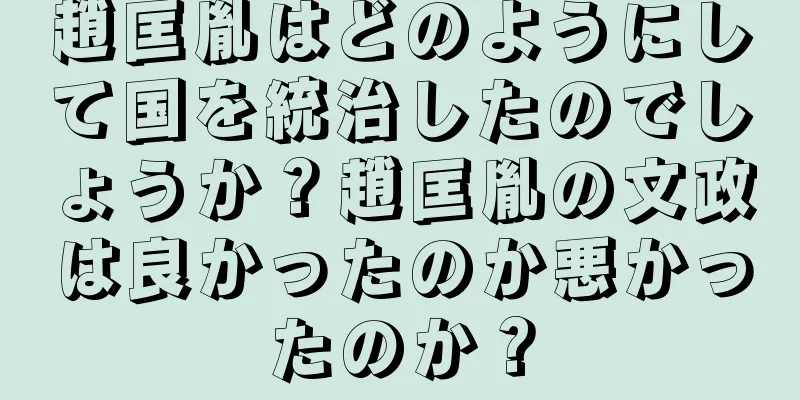
|
今日は『面白歴史』編集長が趙匡胤の文芸統治は良いのかどうかについてお伝えします。興味のある読者は編集長をフォローして見てください。 宋王朝は中国史上、五代十国を経て元の王朝に続く王朝です。北宋と南宋の2段階に分かれ、計18人の皇帝がいました。この王朝は300年以上続き、2度にわたり外国の侵略により倒されました。中国史上、内紛によって滅亡しなかった唯一の王朝です。 960年、後周の将軍たちは陳橋の乱を起こし、宋州導軍太守の趙匡胤を皇帝として擁立し、宋王朝を建国した。趙匡胤の治世中、趙普宰相の「まず南、次に北、まず易きに難きに」の戦略に従って、国の統一に尽力し、荊南、武平、后蜀、南漢、南唐などの南部の分裂政権を次々と滅ぼし、ついに国の大半の地域の統一を成し遂げた。 宋代以前の多くの王朝では、どの皇帝も文官よりも軍官を重視していました。結局のところ、古代は冷兵器の時代であり、皇帝は馬に乗って王国を征服しました。 しかし、趙匡胤が政権を握ってからは文官主義の傾向が広がり始めた。正直に言うと、趙匡胤は実に賢明な皇帝でした。彼は即位後、先代の皇帝のように帝国の中央集権化や中央集権化を追求しませんでした。それどころか、彼は「権力の分立」と「抑制と均衡」の方法を用いて、文官が帝国の権力に制度的な脅威を与える可能性を完全に排除した。 まず趙匡胤は、もともと宰相に属していた権力を分割し、軍事権を枢密院に委譲し、政治権の一部を新設した副宰相に委譲した。さらに、国の財政力を管理する3つの部署を特別に設置し、首相の財政力をさらに分散させた。趙匡胤は中央政府に加え、地方レベルでも「地方分権」と「牽制と均衡」を利用して、諸侯の権力を分散させた。 勅令が発布されるだけでなく、中央政府から地方官も派遣され、その任期は3年間に限られていました。こうすることで、地方の情勢を効果的に管理できるだけでなく、役人が地方に長く留まりすぎることで反抗的な傾向が強まるのを防ぐこともできます。また、皇帝は地方に派遣した官吏が権力を握ることを防ぐため、各県に統班を設置し、地方官吏の言動を監視し、反抗的な考えを持たないようにした。 科挙制度は唐の時代に確立されましたが、科挙制度を頂点にまで発展させた王朝は間違いなく宋の時代でした。 しかし、宋代は文官を重視しすぎて軍事を軽視したため、長きにわたって「官吏過剰」の構図が形成されたのである。このやり方が王朝にとって良いことなのか悪いことなのかは誰にも分からない。結局のところ、趙匡胤はこのような統治方法によって、財政、政治、軍事の権力を独占したのだ。こうして彼は「百年の悩み、一日の悩みは皇帝一人が負い、他の大臣は関与しない」という独裁政治の状態も実現した。 趙匡胤の国を治めるやり方からも、彼が思考力と創造力に優れた皇帝であったことがわかります。彼自身も軍の将軍であり、軍の将軍が反抗的な考えを抱くと国にどれほど大きな影響を与えるかを知っていた。そのため、彼が国を建国した後、国全体が文人を尊敬するようになりました。しかし、趙匡胤の独特な統治思想によって、当時の中国人の性格は大きく変化したのです。 兵士が戦争に行くとき、反乱を防ぐために「軍の監督者」が必要です。また、戦争中、兵士は定められた戦闘隊形に従って部隊を配置する必要があります。そうしなければ、たとえ勝ったとしても、大丈夫で、皆が平和に暮らすことができます。負ければ将軍たちは非難され、少なくとも降格され、最悪の場合は斬首されるかもしれない。その結果、戦士たちは自由に戦うことができず、当然勝つよりも負けることが多くなりました。思想的には、戦士には地位がありませんでした。 その結果、宋王朝は中国で初めて軍事的功績を誇らない国となった。「人間なら兵になるな、鉄なら針になるな」という諺さえあった。その名の通り、「人間なら軍隊に入るな、鉄なら針を作るな」という意味です。この一文から、宋代の兵士や将軍の地位が極めて低かったことが深く理解できます。 宋代には、戦場でどんな功績をあげた将軍でも、帰国後に朝廷で同位の文官と肩を並べることはできなかったといえます。もっとはっきり言えば、数十万の軍勢を率いて四国十六県を奪還した将軍の栄誉は、科挙に合格した学者の栄誉ほど大きくないのかもしれない。学者と武士の間の不公平な扱いのせいで、ますます多くの人々が武術よりも文学を重視するようになったのです。 時が経つにつれ、宋代の男たちは次第に武士の精神を失い、先人たちほど熱心に武術や軍事戦術を訓練しなくなりました。それどころか、ほとんどの男たちは、いつか科挙を受け、合格者名簿に名前を載せ、家族に名誉をもたらすために、昼夜を問わず書物に没頭し、来る日も来る日も何年も懸命に勉強した。 文学を標榜して国を治めるこの方法は、趙家の安全を効果的に保証したが、同時に全国の兵士が何もできず、国の戦闘力が失われ、国全体の安心感も失われた。当時の宋王朝は物質的資源の面では他国よりはるかに優れていたが、戦闘力の面では「四蛮」にはるかに劣っていた。 そのため、敵が攻めてきて我が軍が敗北するたびに、我が国の平和と安定を確保するために敵国に物資を送り、土地を割譲し、賠償金を支払ったのです。しかし、盲目的に屈服することで、本当に敵を満足させることができるのでしょうか。実際、それはできません。敵が 1 体いれば、2 体になります。敵は、あなたの戦闘力が敵より劣っていることを知ったら、あなたを逃がすでしょうか? そのため、北宋はいくつかの非常に屈辱的な敗北を経験した後、何度も移動を余儀なくされました。 それで、趙匡胤の文政は本当に悪いのでしょうか? 実際は悪くないが、文官と武将の待遇の差が大きすぎる。国を富ませ、人民を強くしたいなら、全面的に発展し、文武両道でなければならない。もし両者の待遇の差がそれほど大きくなかったら、宋代に国中の男たちが文学を崇拝し武術を蔑むような状況は生まれなかっただろうし、国の軍事力は徐々に弱体化することもなかっただろうし、敵が攻めてきたときに国が全く反撃できないような状況も生まれなかっただろうと私は信じています。 しかし同時に、このような国を統治するやり方があったからこそ、趙家は何百年も安泰であり、国の安定した経済発展が保証されてきたのです。では、それが正しいのか、間違っているのか。誰にもわかりません。 |
<<: 宋王朝は儒教で国を統治しました。繁栄しましたが、儒教のせいで滅びました。
>>: 「劉家だけが王になれる」という言葉はどこから来たのでしょうか?劉邦はなぜこの規則を定めたのでしょうか?
推薦する
黄庭堅の名詩を鑑賞する:春風と旗が何千人もの男を抱きしめ、幕の後ろの将軍は枯れた草を思う
黄庭堅(1045年6月12日 - 1105年9月30日)、字は盧直、幼名は聖泉、別名は清風歌、善宇道...
孟浩然の古詩「少女情」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「少女の恋」時代: 唐代著者: 孟浩然別れてから、あなたの服がどれくらい長いか短いか忘れてしま...
史公の事件 第215章: 英雄たちは運河の長を訪ねることを話し合い、10人の英雄は月明かりの夜に滄州へ向かう
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
『西院物語』の著者は誰ですか?主な内容は何ですか?
『西室物語』は元代の有名な坐禅文字です。正式名称は「西室月待ち崔英英」で、「西室月待ち張俊瑞」とも呼...
なぜ法正は蜀漢で最も急速に台頭した戦略家だったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
蘇軾の最初の妻、王福を惜しむ詩「滴蓮花:火に降り注ぐ雨雪」
以下、興史編集長が蘇軾の『滴蓮花・雨霙散散火』の原文と感想をお届けします。ご興味のある読者と興史編集...
三英雄五勇士第120章:安定君山の偉大な道と湖北の成功
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
辛其吉が千山に住んでいた時、従兄弟の茅家と別れを告げ、「于美仁:茅家十二兄弟に別れを告げる」を書いた。
辛其基(1140年5月28日 - 1207年10月3日)、元の字は譚復、後に幽安と改め、中年になって...
秦の恵文王には何人の息子がいましたか?秦の恵文王の息子一覧
はじめに:紀元前354年に生まれた秦の恵文王は、秦の恵王または秦の恵文公としても知られ、英思と名付け...
ドラゴンは本当に存在するのでしょうか?歴史上のドラゴンについての手がかりは何ですか?
ドラゴンは本当に存在するのでしょうか?歴史にはドラゴンに関する手がかりが残っているのでしょうか?興味...
清朝の経済:手工業は賦役から代用税へと変化した
農業清朝は、生産量を増やすために、荒れ地の開拓、国境地域への移民の定住、新しい作物の促進などの対策を...
岑神の古詩「崔竹布を夏陽に送る」の本来の意味を理解する
古代詩「崔先生を夏陽に送る」時代: 唐代著者: セン・シェン私はいつも霞陽県が大好きで、何年も前に訪...
なぜ牛魔王と黒熊魔王は西遊記に参加できなかったのでしょうか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
鴻門の宴の他に、中国史上最も重要で有名な3つの宴会は何ですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が中国の歴史を変えた3つの晩餐会を紹介します。...
オボイはかつて太宗皇帝と順治皇帝を補佐したのに、なぜ康熙帝の治世中にこれほど暴君的になったのでしょうか?
諺にもあるように、人がいれば川があり湖がある。闘争はほぼ人間の本能となっており、長い歴史を持つ中国人...