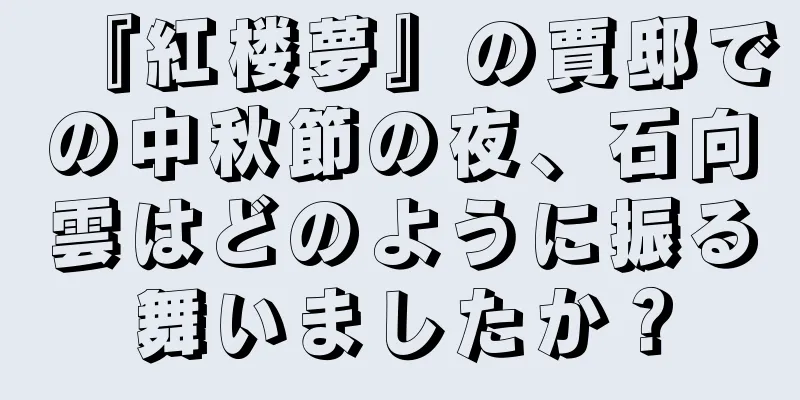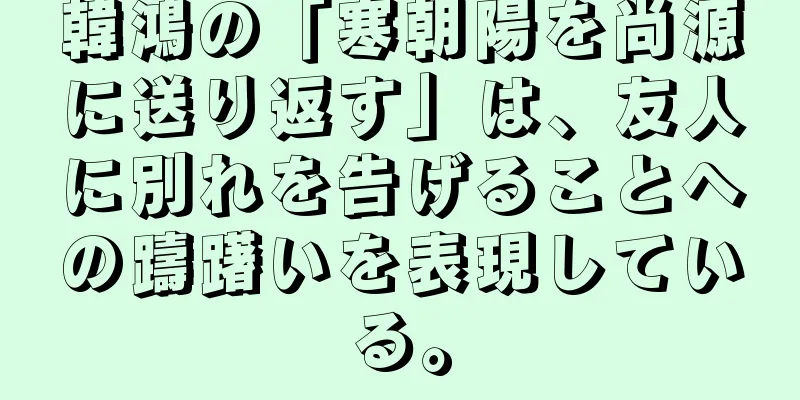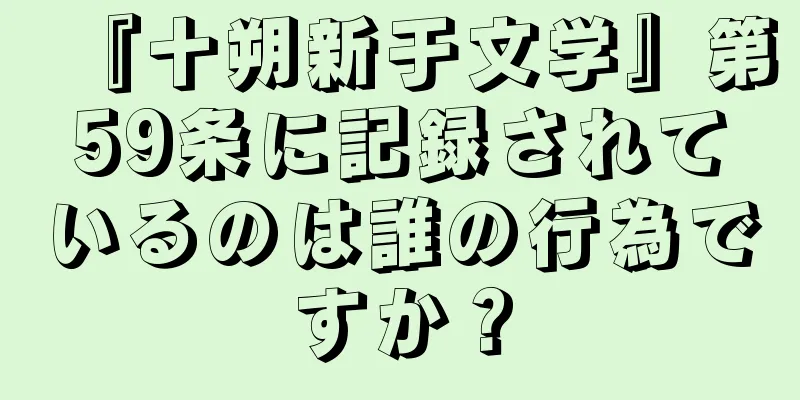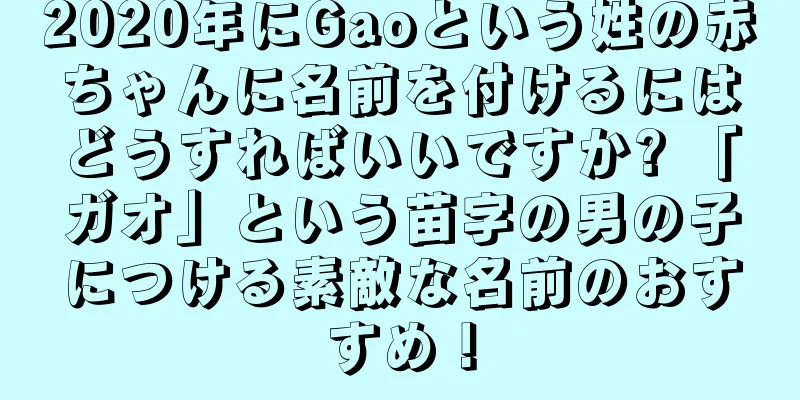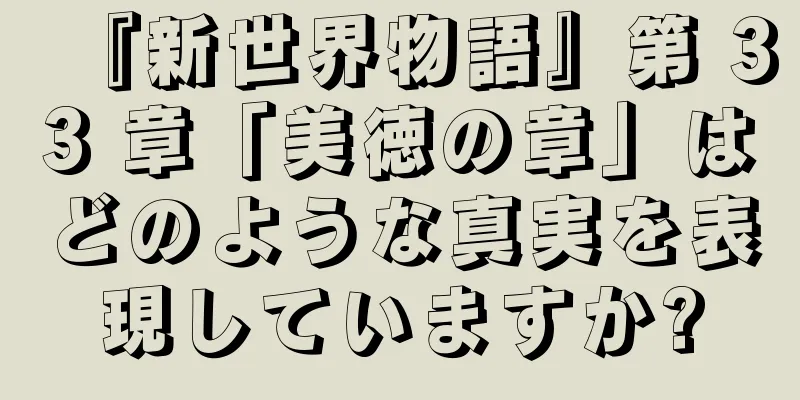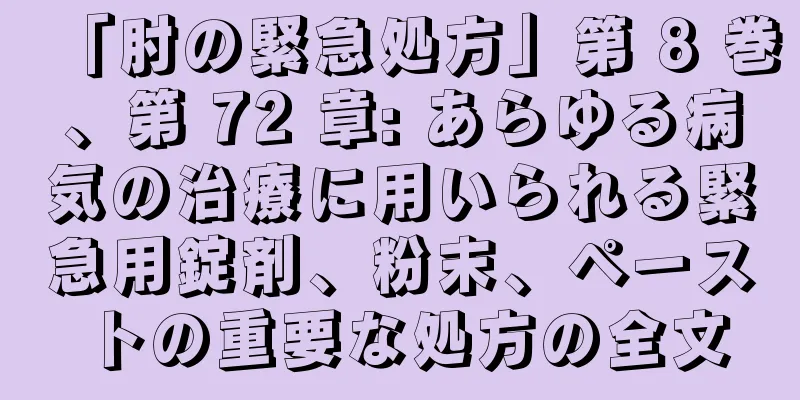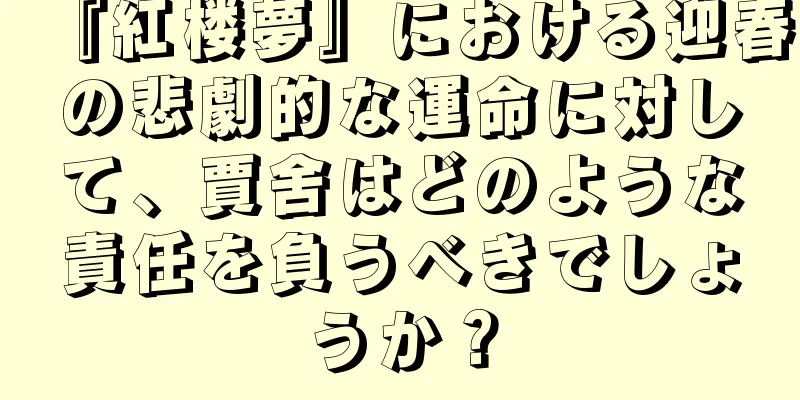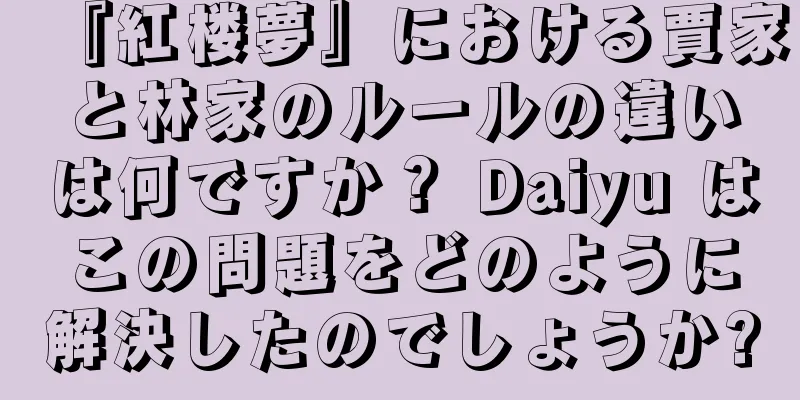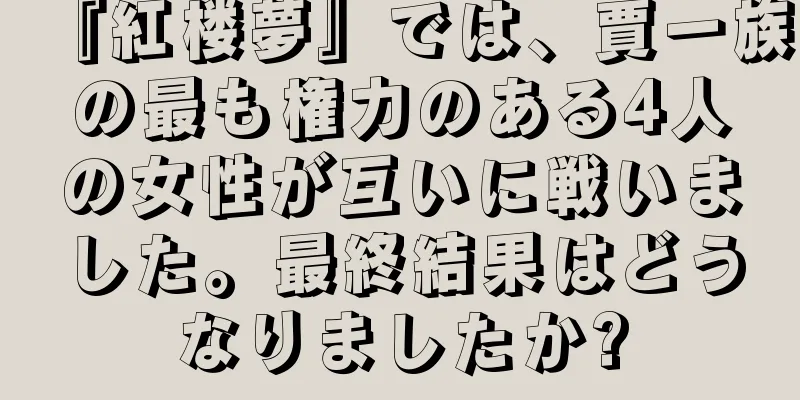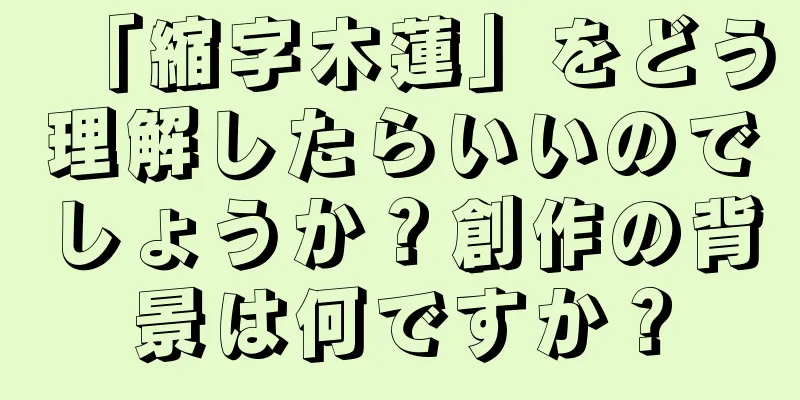夏に足を浸す必要があるのはなぜですか?夏に足湯に浸かるとどんなメリットや効果がありますか?
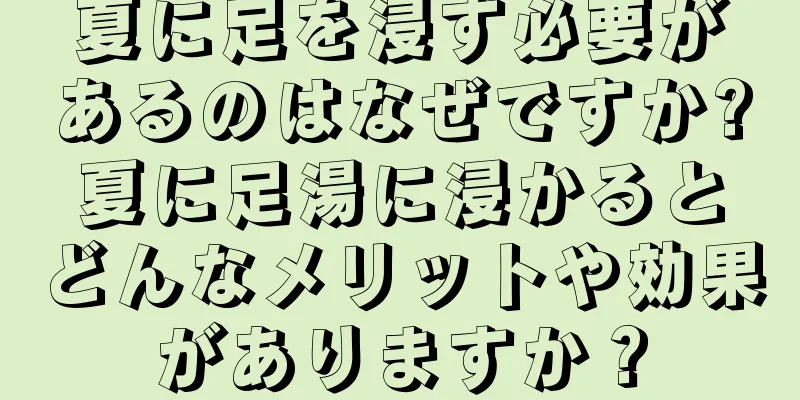
|
夏の暑い時期に足を浸すと健康に悪いことはないと言われています。古いことわざには、「春に足を浸すと太陽が昇り、体が強くなり、夏に足を浸すと夏の湿気がなくなり、秋に足を浸すと肺と腸が潤い、冬に足を浸すと丹田が温まる」というものがあります。この一節だけでも、夏に足を浸すことのメリットが十分にわかります。今日は、Interesting Historyの編集者が、夏に足を浸すことの効果と機能を詳しくお伝えします。 夏の足湯の効能と機能 毎日15分ほど足を浸すことは健康効果があります。例えば、40度くらいのお湯に足を浸すと、15分から20分ほどで頭痛がかなり和らぎます。これは足の血管が拡張し、頭から足に血液が流れるため、脳の鬱血が比較的軽減され、頭痛が緩和されるからです。 風邪や発熱による頭痛の場合、足をお湯に浸すと熱が下がります。 足を浸しながら、手で雁泉ツボを継続的にマッサージし、足の甲にある親指の後ろと外側の太衝ツボを押すと、血圧を下げる効果もあります。 また、足を定期的にお湯に浸す足湯療法の応用範囲は非常に広く、リウマチ、脾臓胃病、不眠症、頭痛、風邪、下半身麻痺、脳外傷、脳卒中、腰椎椎間板ヘルニア、腎臓病、糖尿病などの重病、重病後のリハビリ治療など、全身疾患に効果があります。 足を浸すのに最適な時間:午後9時 足湯の4つのタブー 1. 食後や空腹時に足を浸さないでください 2. 水温が高すぎるのは避けてください。40〜50度が適切です。 3. 長時間の露出は避けてください。20~30 分間軽く汗をかくのが最適です。 4. 感染を防ぐため、皮膚に傷や潰瘍がある場合は足を浸さないでください。 高齢の方は足を浸してはいけません!特に高血圧や虚弱体質の方は!漢方では虚弱を補えないと言われています。そのような方は足を浸さない方が良いです。妊婦や出血症状のある方も足を浸してはいけません。 足湯の注意点 上半身は汗をかかないのに下半身は汗をかく場合は【腎寒】です。これは主に腎寒によるもので、伝統的な中国医学では陰陽の不均衡の現れとされています。クルミやゴマなどの食品を多く摂取し、運動を強化し、喫煙や飲酒をやめ、精神を整えることが推奨されます。 女性の場合は、主に体力の低下や冷えが原因です。中医学では、気血を補うことで調整したり、足を長時間浸して経絡や汗腺を開いたりすると良いと言われています。 上半身は熱があるのに下半身に発汗がないのは気虚の兆候です。気虚は一般的に、体力不足、体力とエネルギーの不足、少し仕事をしただけで疲れを感じるなどの症状として現れます。症状がそれほど深刻でない場合は、大豆と豚肉のスペアリブのスープを多く飲んだり、ナツメ、鶏肉、ヤムイモを食べたりするなど、食事で調整できます。 |
<<: 夏に湿気を除去する方法は何ですか?夏に足を浸すと水分が取れますか?
>>: 中国はなぜ不滅の文明なのでしょうか? 現代の歴史家はどのような見解を持っているのでしょうか?
推薦する
程蓋の有名な詩句を鑑賞する:私は一人で上の階に上がり、建物の外には緑の山々が遠くに見える
程蓋は、雅号を鄭伯といい、眉山(現在の四川省)の出身であった。蘇軾の従兄弟である程志才(号は鄭福)の...
隋代の通貨の特徴は何ですか?隋代にはどのような種類の通貨がありましたか?
隋代初期の貨幣は極めて乱雑で、北斉の昌平五珠や私鋳の昌平銭、北周の五興大布や永通万国銭、南朝の陳五珠...
「ザクロスカート」ってどんな感じ? 「女に惚れる」ということわざがあるのはなぜですか?
「ザクロスカート」とは何でしょうか?「ザクロスカートにひれ伏す」ということわざはなぜあるのでしょうか...
曹植の『君子の道』原文、翻訳、注釈
曹植は、字を子堅といい、曹操の息子で、魏の文帝曹丕の弟である。三国時代の有名な作家であり、建安文学の...
北宋時代の軍事書『武経宗要』全文:第二巻、第21巻
『武経宗瑶』は北宋の政府が編纂した軍事書である。著者は宋の仁宗の治世中の文官、曾公良と丁度である。二...
古代中国にはピンインはありましたか?古代の人々はどのようにして読み方を学んだのでしょうか?
中国にはもともと表音文字がなく、漢字の発音を示すために直接発音またはファンキー方式が使用されていまし...
張元干の「毓章武城山に詠んだ風が道を塞いだ」:この詩は風景から始まり、感情で終わる。
張元干(1091年 - 1161年頃)は、字を中宗といい、呂川居士、真音山人とも呼ばれた。晩年は呂川...
屈原の『九歌東神』はどのような場面を描いていますか?
屈原の『九歌・東君』はどのような場面を描いているのでしょうか?この記事の崇拝対象は東君、つまり太陽神...
三国時代の呉の将軍、周泰はどのようにして亡くなったのでしょうか?
三国時代の呉の将軍、周泰はどのようにして亡くなったのでしょうか?周泰は、雅号を有平といい、九江の下菜...
漢代初期の帝国の外交政策の80年の歴史を詳細に記述:孫子から覇権国へ
はじめに:春秋戦国時代、秦の暴政から秦末期、楚漢戦争まで、中国は600年近く戦争、破壊、衰退、暴政を...
『紅楼夢』の焦星と賈玉村の関係は何ですか?彼女の本当の姿とは?
『紅楼夢』で最も幸運な人物は、おそらく焦星だろう。以下の記事はInteresting History...
『紅楼夢』で黛玉はなぜ賈屋敷に戻ったのですか?真実とは何でしょうか?
『紅楼夢』のヒロインである黛玉は、『金陵十二美女』本編に登場する二人の美女のうちの一人です。興味のあ...
『啓東夜話』第十四章の主な内容は何ですか?
○図書館で絵画鑑賞易海年の秋、黄全如基事務総長が私を彭省への10日間の訪問に招待し、私は正装して有文...
本草綱目第6巻土壌部ミミズ泥の原文の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
昔、「作家」は軽蔑的な言葉でした。王維はかつて「作家」という言葉を使って人々を風刺しました。
「だからそういうことだ」では、「作家」は実は古代では蔑称だったと説明している。王維は「作家」という言...