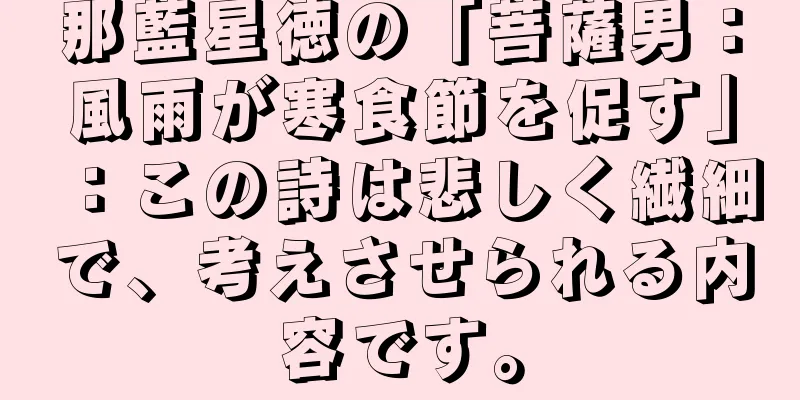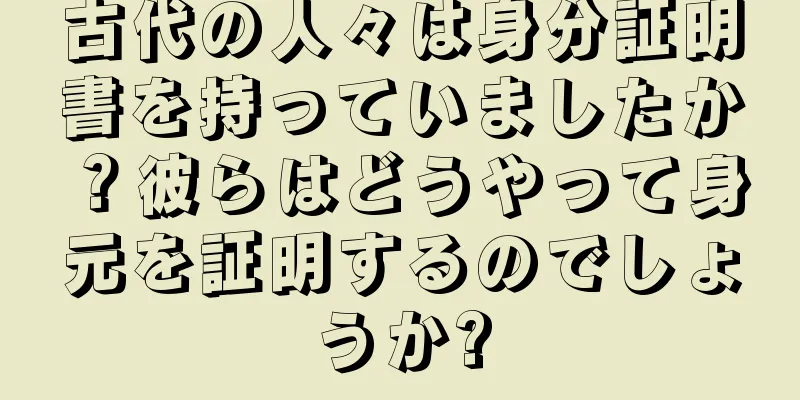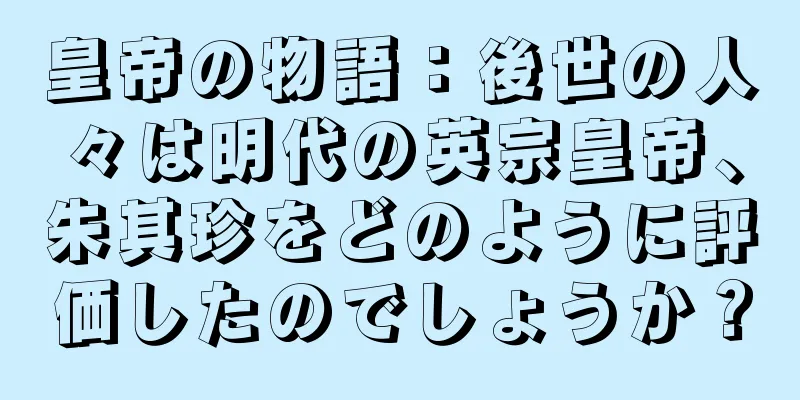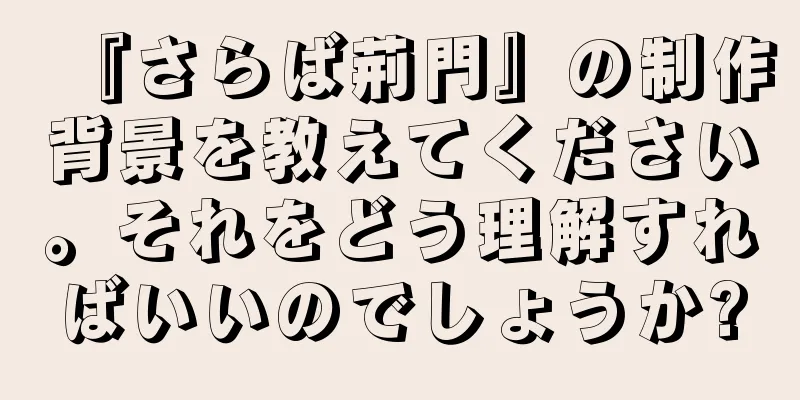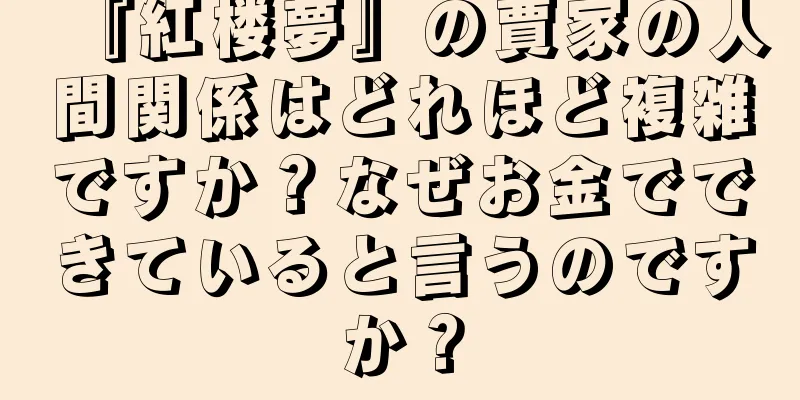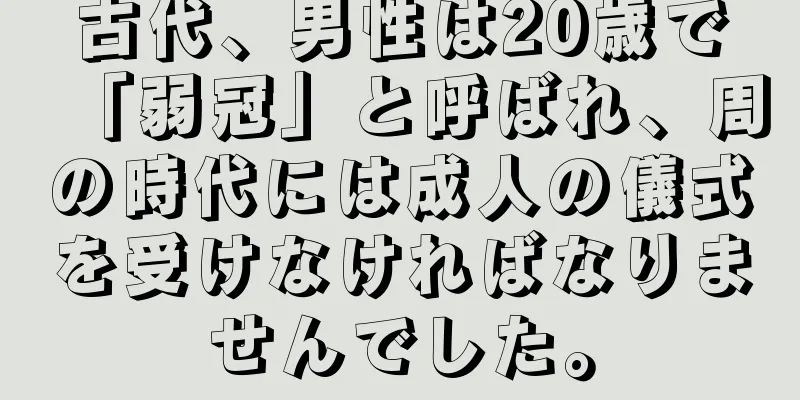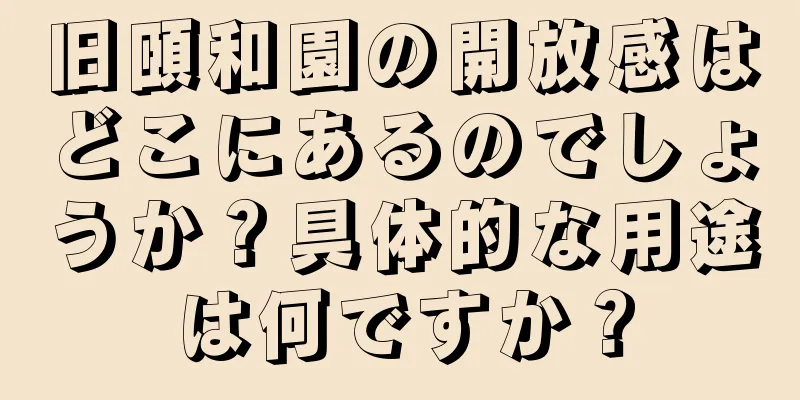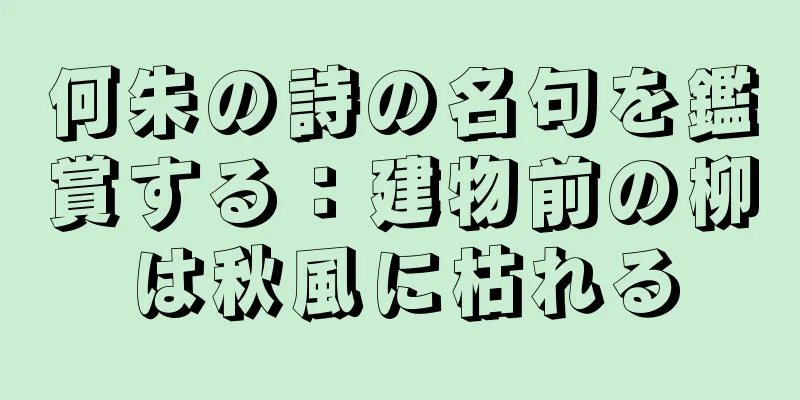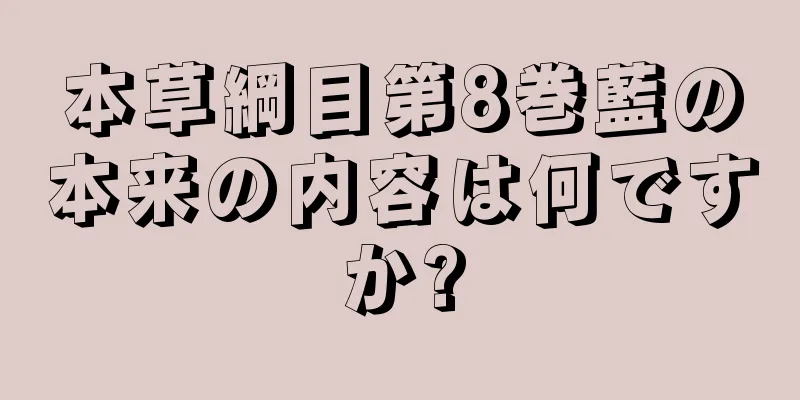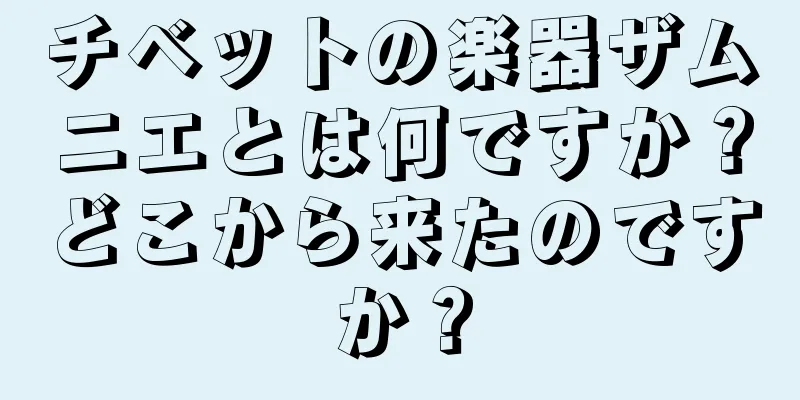屈原の公式の立場は何でしたか?三鹿大夫はどのレベルの官職に属しますか?
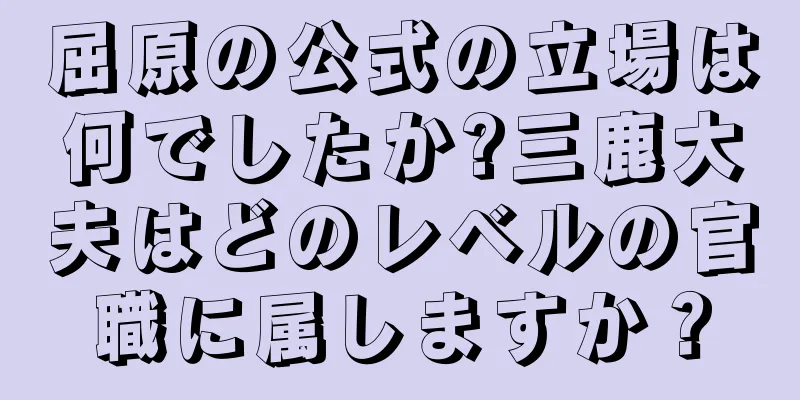
|
「三鹿大夫」は、戦国時代に楚国が特別に設けた官職で、祖先の廟での祭祀を司り、屈・荊・趙の三家の子弟の教育も担当する雑役であった。屈原は降格された後にこの地位に就いた。 『史記 屈原伝』の裴雍の注釈にはこうある。「雍の『李索序』の注釈にはこうある。三禄の地位は、王家の三つの姓、すなわち趙、屈、景を管理することである。元(屈原)は彼らの系図を整え、徳の高い人々を率いて国の人材を奨励した。」三鹿大夫は三大姓の氏族事務を担当する役人であったことが分かる。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 屈原が釈放される前の最後の官職は「三鹿医師」であった。 屈原は中国文学史上、最も偉大で傑出した浪漫詩人でした。後世の人々は彼の作品を「楚辞」と呼びました。代表作は屈原の作品の中で最も長い抒情詩『礼索』で、全373文、2,777語に及ぶ。この詩は、詩人が自らの政治思想を貫くために受けた打撃や迫害を描写しており、詩人の内面の痛みと、国民と祖国に対する揺るぎない思いを深く表現している。 公式タイトル調査 屈原は詩と散文の達人であり、歴史上の人物です。学者が彼の生涯を研究するとき、彼らは通常、彼が楚の淮王の下で務めた二つの官職、左臂と三鹿大夫について語ります。誰もがこの二人がどんな役人なのか知りたがっている。しかし残念なことに、学者たちは知恵を絞ってさまざまな推測をした結果、歴史的資料に基づいて4つの結論に達しました。 歴史資料: (1) 『史記 屈原・賈勝伝』:「屈原は、名を平といい、楚の姓と同じ。楚の淮王の右腕であった。博識で意志が強く、乱世を治める知識があり、弁論術に長けていた。宮廷にいるときは、国王と国政を協議し、命令を出し、外出中は客を迎え、諸侯と交渉した。王は屈原を非常に信頼していた。」 (2) 『史記 屈原・賈懿伝』:「屈原は髪をほどき、湖のほとりで詠唱していた。やつれて衰弱した様子だった。漁師が彼を見て尋ねた。「あなたは三鹿の役人ではないのか。なぜここにいるのか?」 (3)王毅の楚辞序文:礼索:「礼索は屈原によって書かれた。屈原は楚と同姓で、淮王の下で三鹿太守を務めた。三鹿太守の職は、趙、屈、荊の王族の三つの姓を管理することであった。屈原は彼らの系図を整理し、徳の高い人々を率いて国の才能を奨励した。宮廷にいるときは、国王と国事を協議し、疑問を解決し、外出しているときは、部下を監督し、王子たちと交渉した。」 (4) 楚辞の漁師:「屈原は流刑になった後、湖畔で詠唱しながら川や池をさまよっていた。彼はやつれて衰弱していた。漁師が彼を見て尋ねた。「あなたは三鹿の役人ではないのか?なぜここにいるのか?」 上記の資料は次のことを示しています。 最初は「Zuotu」について言及しています。原文では「左図」がどのような官職なのかは説明されていません。司馬遷は、屈原がこの地位に就いていた頃のことを「知識が豊富で意志が強く、乱世を治める知識があり、弁論術に長けていた。宮殿にいるときは国王と国事を協議し、命令を出し、外にいるときは客を迎え、王子たちと交渉していた」とだけ述べている。それだけである。 張守傑の『史記評』には「おそらく現代の遺失物拾いの左右の役人のようなもの」とあり、この役職は検閲官(注:楚には「真陰」あるいは「真陰」という検閲官がいた)を意味しているようだ。おそらくこの数文から彼が受けた印象はそういうものなのだろう。しかし、「おそらく」という言葉が前に付いている彼の言葉は、単なる憶測であり、必ずしも現実に基づいているわけではないように思われた。唯一判断できることは、おそらく霊隠や司馬より下の官職だったが、それほど低くはなかったということだ。『史記・楚氏記』には、楚の高烈王が「左図を霊隠に任じ、武の爵位を与え、春神君と名付けた」とある。黄懿は「左図」から「霊隠」に直接昇進しており、この官位がそれほど低くなかったことがわかる。 2 番目の記事は 4 番目の記事から派生したもので、内容は似ています。このことから、屈原が釈放される前の最後の官職は「三鹿医」であったことがわかります。 第三条には、「屈原は楚と同姓である…宮中にいる時は国王と国事を協議し、疑惑を裁定し、外にいる時は部下を監督し、君主に答える」など、第一条と似た言葉がいくつかあります。違いは、「左途」が「三鹿大夫」に置き換えられていることです。そのため、一部の学者は、「三鹿大夫」と「左当」は同一人物である可能性、あるいは「左当」の部下である可能性もあると考えています。 (2)「三鹿大夫」について、王毅は「三鹿の役職は趙、屈、荊の三王家を管理することであり、屈原は彼らの系譜を整理し、有能な人々を率いて国の人材を奨励した」と説明した。この役人は王族を管理し、その家系を管理する責任があり、その機能は東周の「宗伯」「宗仁」「宗老」「公祖」(または「公祖大夫」)の役人と類似していた。 (3)春秋時代、屈族が就いた官職は、最も多かったのは莫澳であった。歴代楚王莫澳の称号は、屈族の父子によって継承されることが多かった。【注:莫澳は戦国時代の文献にも非常に多く登場する。曽、楚などの出土文書では、「莫澳」を称号として使用している。これは楚の国で非常に伝統的な官職であり、霊隠と司馬に次ぐ非常に高い地位にあり、これは我々の左與の地位の推定に近い。一部の学者は、これはおそらく楚の官僚の中では「莫敖」であったと考えている。しかし、古代の文献資料の中に「左図」と「三鹿大夫」は見つかっておらず、「墨澳」との関係を判定する方法がないため、これらの記述を確認することはできない。 |
<<: 「Mi」という姓は歴史上どのように始まったのでしょうか? Mi姓の先祖は誰ですか?
>>: モチョウヌと屈原の関係は何ですか?モチョンヴについてはどんな話がありますか?
推薦する
『譚址歓喜舎』の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
環溪沙を広げる李清昭病気になったとき、こめかみが白くなりました。横になって窓から欠けていく月を眺めて...
王維と玉貞公主の忘れられない物語
【勅命に応えて玉真公主の山荘を訪れ、勅命に応えて石壁に十韻の詩を書いた】青い空と煙の向こうには、おと...
夏侯惇はどれほどの力を持っているのか?関羽はなぜ彼と対峙して屈服したのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
雲岡石窟はどのように発展したのでしょうか?雲岡石窟の歴史的発展の軌跡!
雲岡石窟はどのように発展したのか?雲岡石窟の歴史的発展の軌跡とは?『Interesting Hist...
孟子:孟子書第10章~第14章、原文、翻訳、注釈
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸...
太平広記・第95巻・奇僧・洪芳禅師の原作の内容は何ですか?どのように翻訳しますか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
北宋時代の程浩が書いた「春日折詩」は詩人の内なる誇りと喜びを表現している。
程昊は、号を伯春、号を明道といい、通称は明道氏。北宋代に朱子学を創始した。弟の程毅とともに「二人の程...
華雄が孫堅を破り、同盟軍の将軍2人を殺したとき、曹操はなぜ戦いを要求しなかったのですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『太平広記』第411巻第6章「草木篇」の登場人物は誰ですか?
果実の下の桜、ナツメ、柿、樫の木の果実、柿皿、栄豊梨、六錦梨、紫梨、ヘーゼルナッツ、酸っぱいナツメブ...
書道の歴史において宋代の書道を語るとき、なぜ蔡祥は欠かせない人物なのでしょうか?
蔡祥は北宋時代の高官で、書家でもあり、宋代四大家の一人でもありました。彼の書道は依然として晋唐の規則...
宋代の役人の帽子はどんな感じだったのでしょうか?趙匡胤はなぜそれを発明したのでしょうか?
はい、昔のテレビドラマを見ると、宋代の官僚の帽子にも2つの長い耳があり、階級が上がるほど耳が広くてま...
「六策・文涛・文師」とはどのような内容が書かれているのでしょうか?どのように翻訳しますか?
中国の伝統文化は歴史が長く、奥が深いです!今日は、興味深い歴史の編集者が「六策・文道・文師」の関連コ...
歴史上、「春秋五覇」が誰であったかについては、いくつの異なる説があるでしょうか?
「春秋五覇」とは、春秋時代に最も有能で権力を握り、歴史の発展に最も貢献した5人の君主を指す歴史的な称...
杜遜和の『農夫』は封建社会の重税に対する強い抗議を表現している。
杜遜和は、字を延芝、号を九花山人といい、唐代末期の官僚詩人であり、写実主義の詩人である。彼は詩が優雅...
世界で最も高価な花は何ですか?花はいくらですか?
今日は、Interesting History の編集者が世界で最も高価な花を紹介します。興味のある...