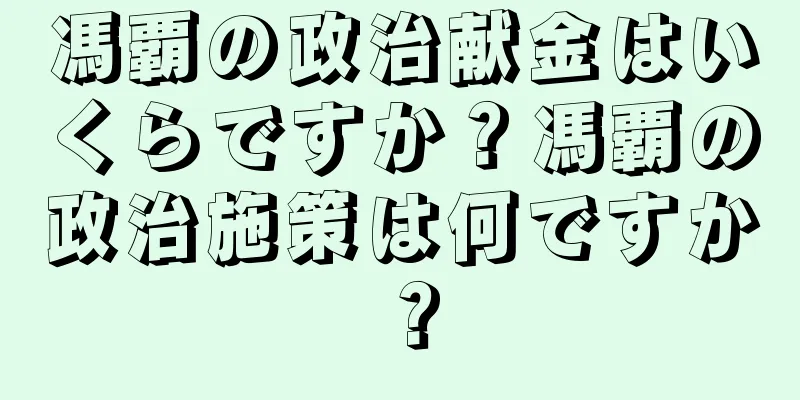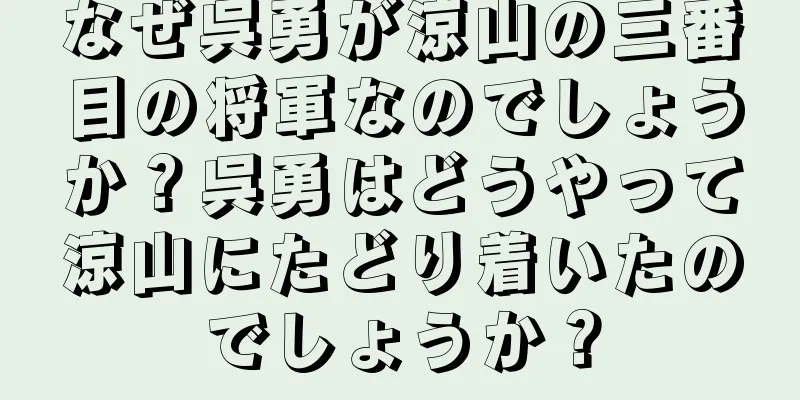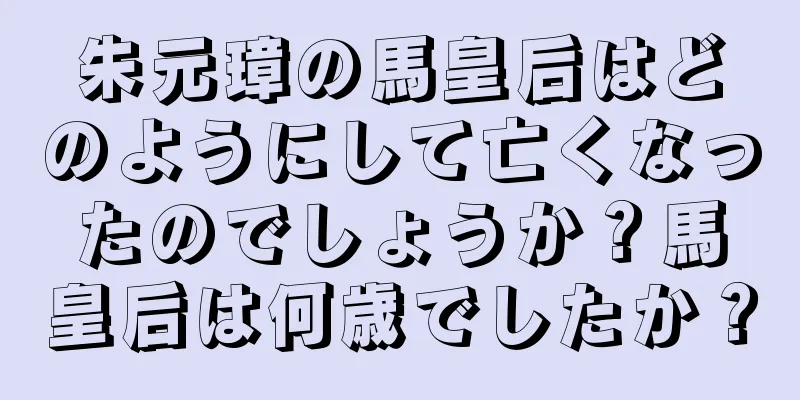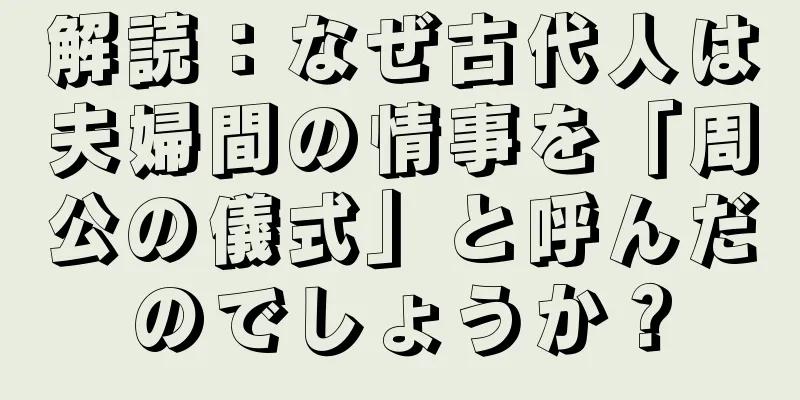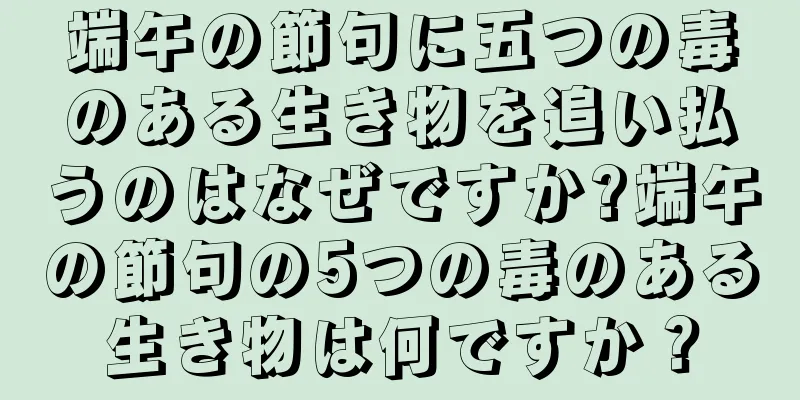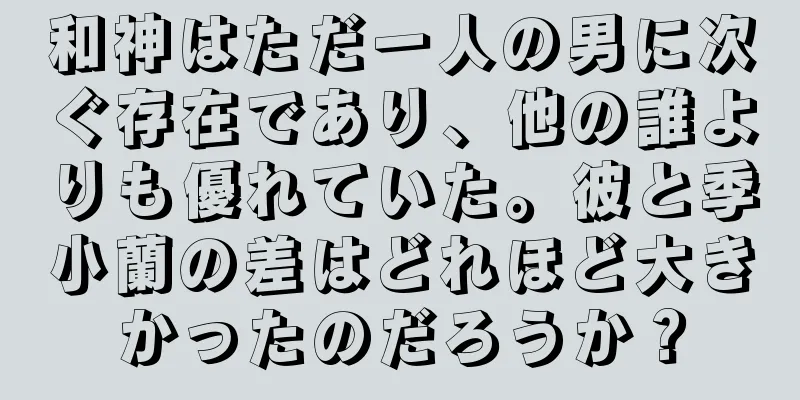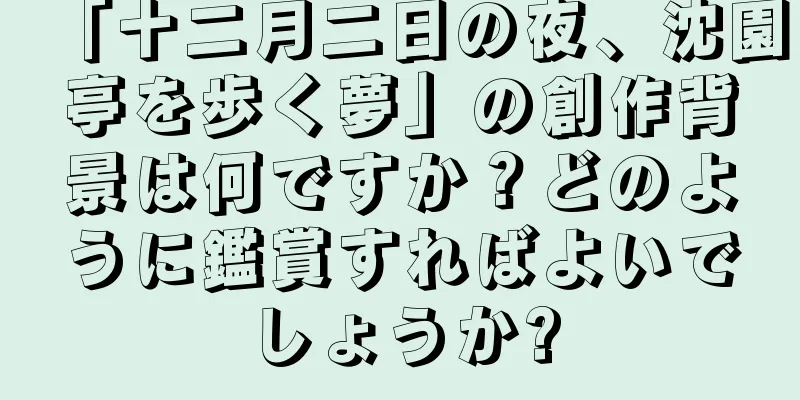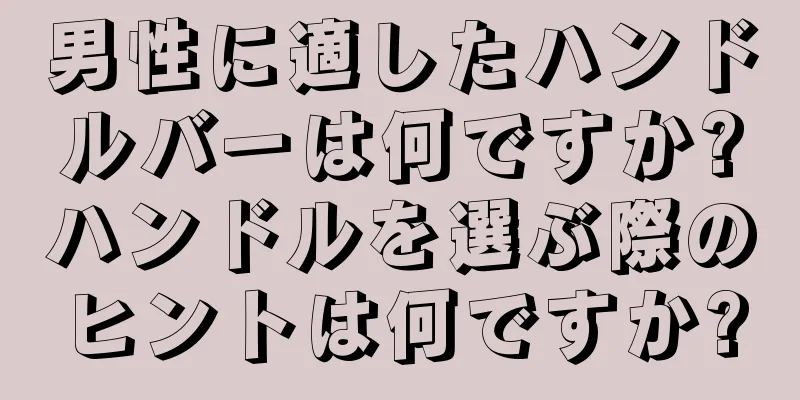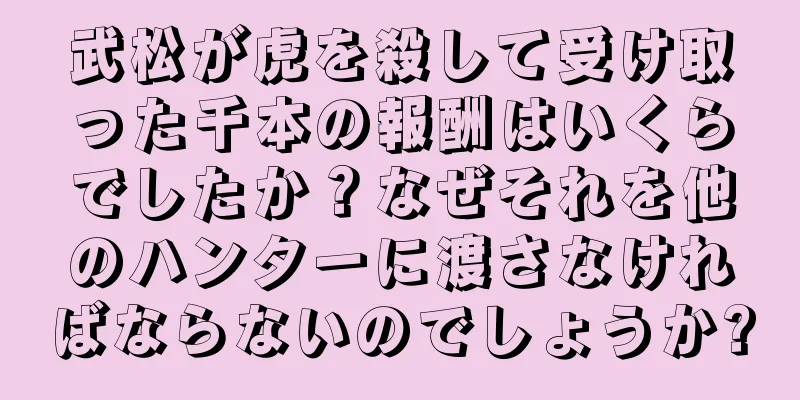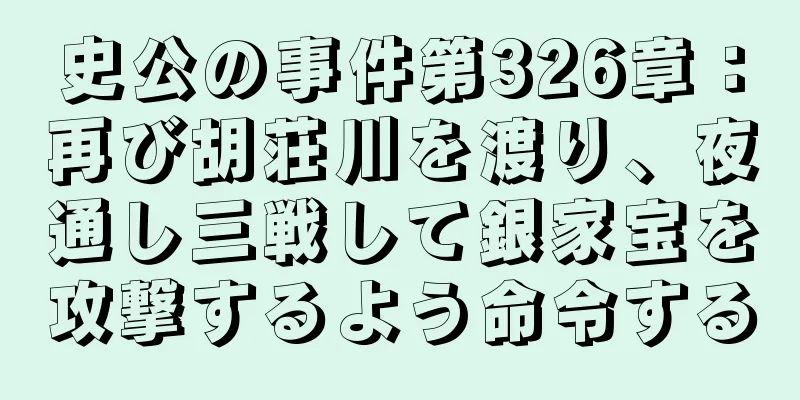アザラシは歴史上どのように誕生したのでしょうか?印章を発明したのは誰ですか?
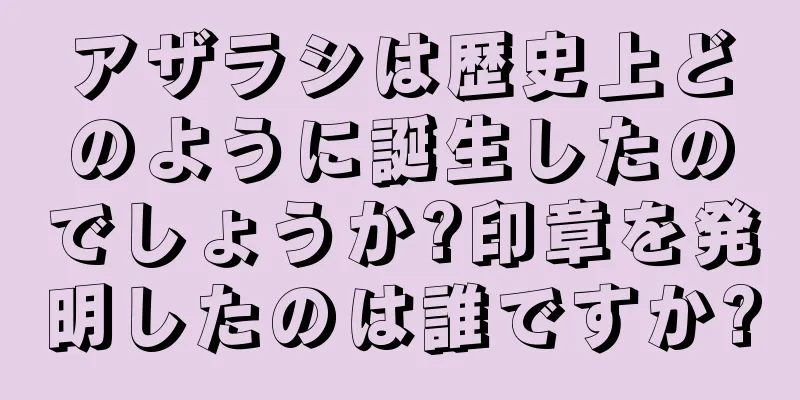
|
印刷は古代中国の労働者の四大発明の一つです。木版印刷は唐代に発明され、唐代中期から後期にかけて広く使用されました。宋代の仁宗皇帝の治世中に、畢勝が活版印刷術を発明した。宋代には活版印刷が登場したが、広く普及することはなく、木版印刷が依然として広く使用されていた。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 印章は秦以前の時代から存在しており、通常は名前、官職名、または機関を示す数語のみが刻まれています。印章の文字はすべて逆さまに刻まれており、否定と肯定の異なる種類の文字が刻まれています。紙が登場する前は、公文書や手紙は竹簡に書かれていました。書いた後は縄で縛られ、結び目に粘着性のある泥印が押されました。印は泥の上に押されたので、泥印と呼ばれていました。泥印は泥の上に印刷するもので、当時の秘密保持手段でした。紙の出現後、泥印は紙印へと進化し、公文書の継ぎ目や公用紙袋の封印に押されるようになりました。北斉の時代(西暦550年~577年)には、公文書に押印する印章を、まるで小さな彫刻板のように非常に大きく作ったという記録があります。 1. 戦国時代(紀元前475年~221年)の印刷技術。 2. 晋の時代の有名な錬金術師である葛洪(284年 - 363年)は、著書『包朴子』の中で、当時の道教徒がすでに4インチ四方(13.5×13.5)で120の文字が刻まれた大きな木製の印章を使用していたと述べています。これはすでに小さな彫刻です。 3. これに触発されて、仏教徒は仏典の冒頭に仏像を印刷して、より鮮明に表現することがよくあります。このような手作りの木版画は、手描きよりもはるかに簡単です。 4. 石碑拓本技術は木版印刷技術の発明に大きな役割を果たしました。石彫刻の発明は非常に古い歴史を持っています。唐代初期、陝西省鳳翔で10個の石鼓が発見された。これは紀元前8世紀の春秋時代の秦の国の石彫であった。秦の始皇帝は巡業中に重要な場所に7回石を彫りました。東漢の時代以降、石碑が普及した。漢の霊帝4年(175年)、蔡邕は朝廷に進言し、太学門の前に『詩経』『史記』『易経』『礼記』『春秋』『公陽伝』『論語』など7つの儒教経典の石碑を建てさせた。46枚の石碑には計20万9千字が刻まれている。石碑1枚は高さ175センチ、幅90センチ、厚さ20センチで、5千字を刻むことができる。石碑の両面に文字が刻まれている。彫刻を完成させるのに8年かかりました。それは当時の学者の間で古典となりました。多くの人がそれを真似しようとしました。その後、特に魏、晋、六朝の時代には、経典が適切に管理されていなかったり、放置されていたりしたという事実を利用し、経典を紙に拓本して、自分用や販売用にする人がいました。その結果、広く流通するようになりました。 5. 擦り付けは印刷技術の出現にとって重要な条件の 1 つです。古代の人々は、石碑の上に少し湿らせた紙を置き、柔らかいハンマーで軽く叩くと、石碑の文字のくぼみに紙が沈むことを発見しました。紙が乾いたら、綿を布で包み、インクに浸して紙を軽く叩きました。こうすると、石碑とまったく同じ白黒の文字が紙に残りました。この方法は、手書きでコピーするよりも簡単で信頼性があります。こうして拓本が誕生したのです。 6. 木版画には、印刷や染色の技術も大きな影響を与えています。印刷や染色とは、木の板に模様を彫り、染料で布に印刷することです。中国では、エンボスプレートと中空プレートの 2 種類の印刷プレートがあります。 1972年(紀元前165年頃)に湖南省長沙市の馬王堆漢墓1号墓から出土した印刷紗2枚は、エンボス版を使用して印刷されていました。この技術は秦や漢の時代以前に存在していた可能性があり、戦国時代にまで遡ることができます。紙が発明された後、この技術は印刷にも利用できるようになりました。布を紙に変え、染料をインクに変えれば、印刷物は木版画になります。敦煌石室には唐代の浮彫紙や中空紙に印刷された仏像が収蔵されています。印捺、摺り、捺染の3つの技法が互いに刺激し合い融合し、さらに中国人の経験と知恵と融合して木版印刷技術が誕生しました。 7. 木版印刷は唐代(7世紀頃)に発明され、唐代中期から後期にかけて広く使用されました。 初期の印刷活動は主に民間で行われ、主に仏像、経典、誓詞、暦などを印刷するために使用されました。唐代初期、玄奘三蔵は慧峰紙に普賢菩薩の像を印刷し、僧侶や尼僧、信者に与えた。 8. 北宋時代(11世紀頃)に畢勝が活版印刷を発明しましたが、広く普及せず、木版印刷が広く使用されていました。 |
<<: 火薬はいつ登場したのでしょうか?火薬は人類の戦争の歴史をどのように変えたのでしょうか?
>>: 印刷技術はいつ登場したのでしょうか?印刷術は科挙にどのような影響を与えたのでしょうか?
推薦する
劉老老の喜びと比べて、王夫人の態度はどうだったでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
「何心浪・西湖」鑑賞、詩人文継翁とその仲間は科挙合格後、西湖を旅した
文継翁(生没年不詳)、号は世学、号は本心、綿州(現在の四川省綿陽市)の人であり、呉興(現在の浙江省湖...
于旭の物語 于旭と絡み合った根の物語とは何でしょうか?
于胥(?-137年)、雅号は盛卿、愛称は定干。彼は陳国武平県(現在の呂邑武平)に生まれた。東漢時代の...
「于章星庫相片」の原文は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
【オリジナル】女性である私にとって、言葉で表現するのは難しいほど惨めで謙虚な気持ちです。男は一家の長...
袁浩文:金末期から元初期の文豪。詩によって驚異的な名声を得た。
本日は、Interesting Historyの編集者が袁浩文の物語をお届けします。ご興味のある読者...
「リトルファイブヒーローズ」第115章:2人のハンマーは心優しいウェン氏をいじめ、凶悪犯を恐れる
『五人の勇士』は、古典小説『三人の勇士と五人の勇士』の続編の一つです。正式名称は『忠勇五人の勇士の物...
古代の亭衛の立場は何だったのでしょうか?それは大きな力ですか?
古代の廷衛の地位はどのようなもので、どれほどの権力を持っていたのでしょうか。この地位は戦国時代の秦国...
「江南を偲ぶ三詩」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
江南を偲ぶ三つの詩白居易(唐代)長江の南側は美しく、私は昔からその景色を知っています。日の出の時には...
清朝における文学審問の特徴は何ですか?文学異端審問が社会に及ぼす害と影響
清朝における文武審問は、思想的抑圧を強化し、統治を強化し、文化統制を強化するために統治者によって考案...
十二支の守護神を見てみましょう。辰年生まれの人の守護神は普賢菩薩です。
龍の守護聖人は、龍の星座を持つ人々の出生仏でもある普賢菩薩です。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹...
歴代の著名人は司馬相如をどのように評価したのでしょうか?司馬相如は詩において最高の詩人であり、司馬遷は散文において最高の作家である。
司馬相如は、中国文化と文学の歴史における傑出した代表者であり、漢の武帝の治世下、西漢全盛期の作家であ...
『紅楼夢』では、脇役の劉おばあさんがどのようにして主要人物として有名になったのでしょうか?
劉おばあちゃんの物語は好きですか?今日は、興味深い歴史の編集者が詳しく説明します〜劉おばあさんは『紅...
漢民族の歴史における西周時代の「礼楽文明」の簡単な紹介
西周王朝(紀元前1027年? - 紀元前771年)は、夏王朝、商王朝に続く我が国の3番目の王朝であり...
宋江が毒殺されたとき、武松は何をしていたのですか?事前の救助もなければ、事後の復讐もない
ウー・ソンと聞くといつもテレビに出ていたあの人を思い出すので、彼について詳しく話さなければなりません...
禅源条約は北宋にとって屈辱的なものだったと言われていますが、歴史上本当にそうなのでしょうか?
宋代の歴史を語るとき、避けて通れない話題が一つあります。それは、真宗皇帝の治世中の「禅源同盟」です。...