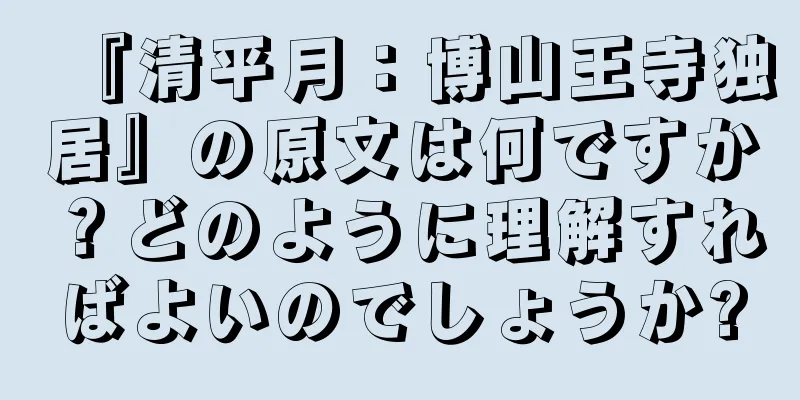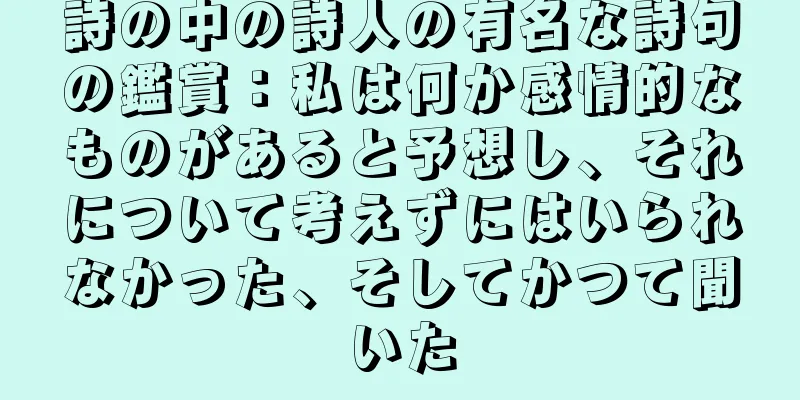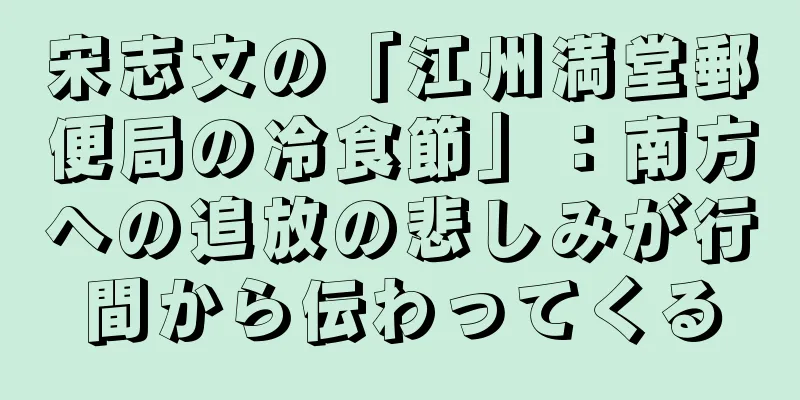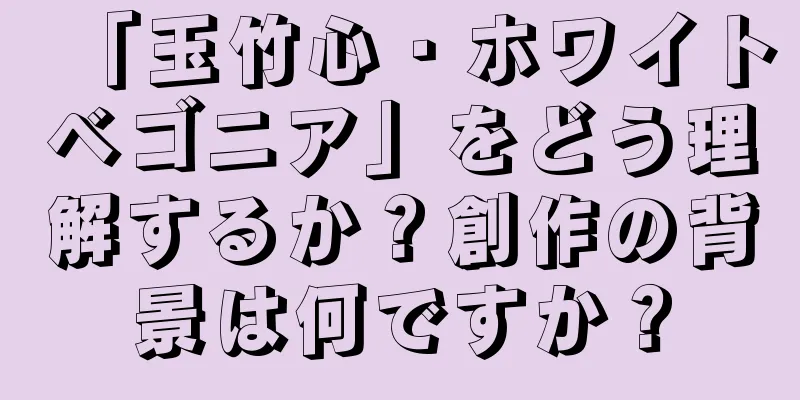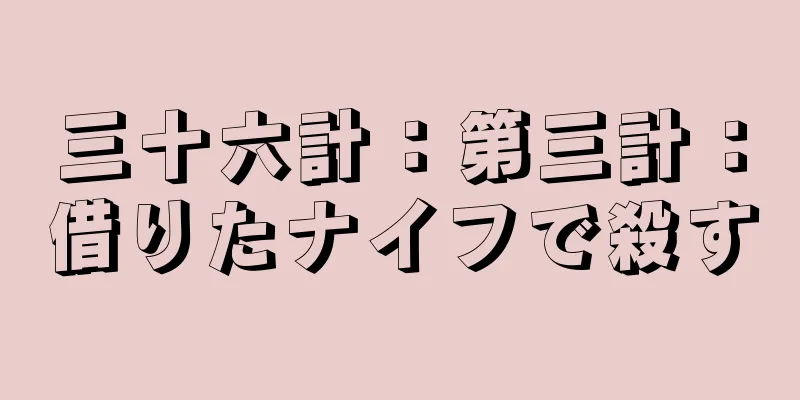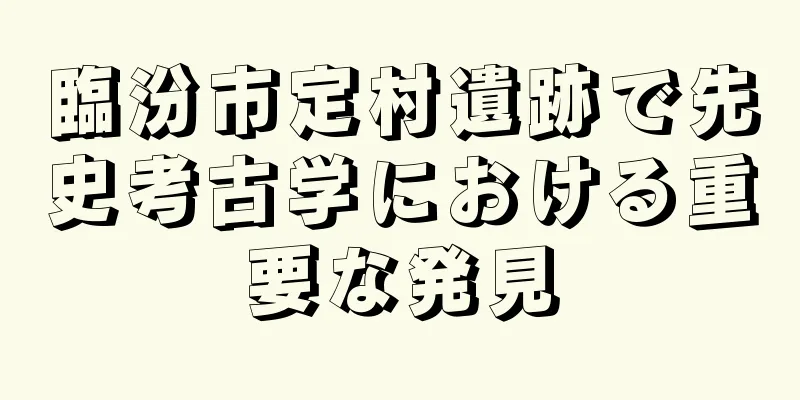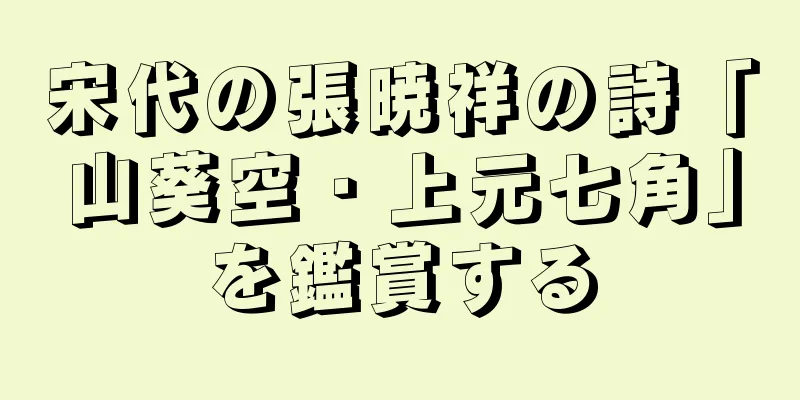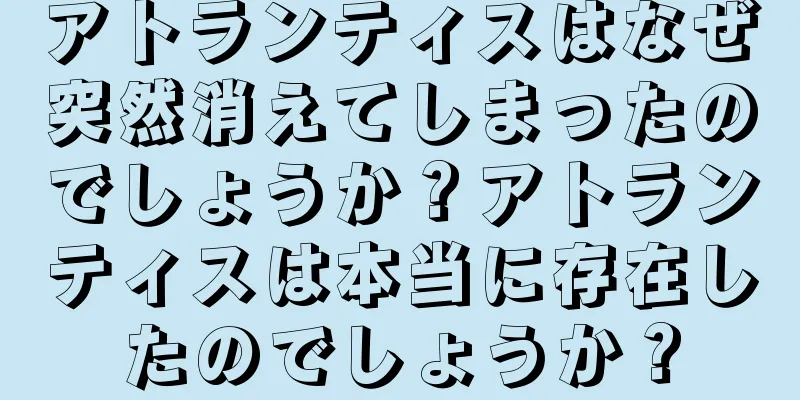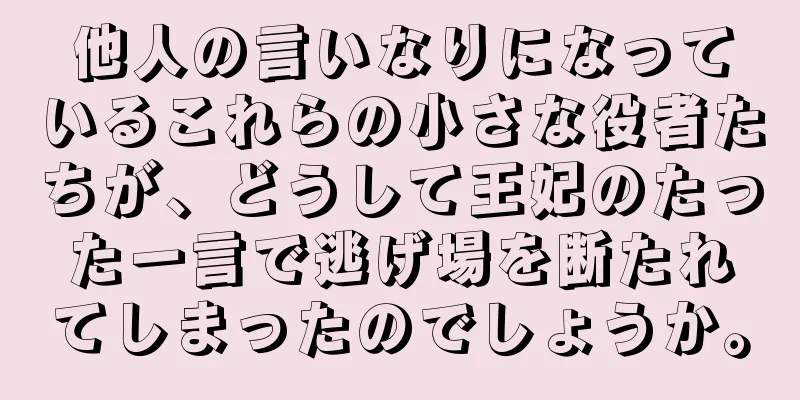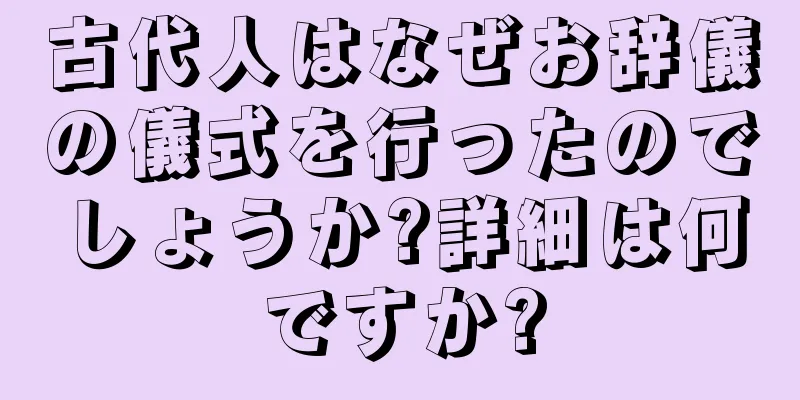南宋時代の祠と俸給制度について簡単に紹介します。学者の道徳や官僚の行政にどのような影響を与えたのでしょうか。
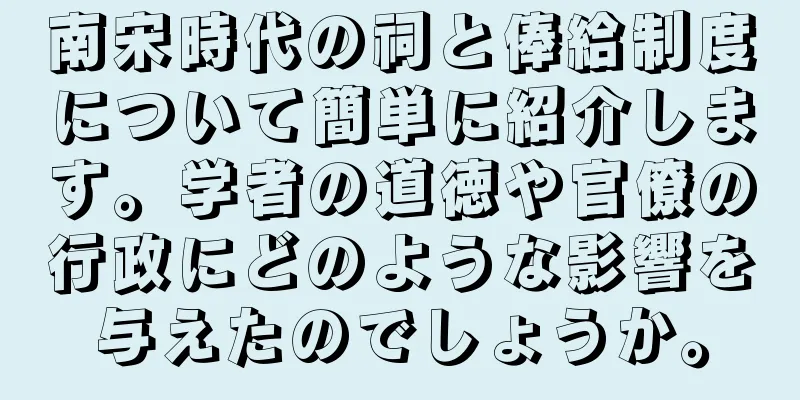
|
廟俸制は宋代独特の官制であり、隋唐代には盛んにならず、明清代にも継承されなかった。宋代の有文政策の産物の一つであり、唐代の宮廷寺制度に遡ることができるが、その性質はかなり異なっている。唐代の宮寺使は、宮廷や寺院の事務を実際に管理する宮廷官吏であった。宋代の神社や寺院を管理する役人は「某寺の監督」や「某宮寺の監督」と呼ばれていましたが、宮寺の事務とはほとんど関係がありませんでした。「神社」と「給料」は基本的に分離されており、役人は給料を受け取るための借り物の名前にすぎませんでした。この制度は宋代の真宗皇帝の時代に初めて確立されました。その本来の目的は「老人と善人への依存」であり、特に高官に提供される福祉政策でした。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 清代の学者趙毅は著書『二十二史注』の中で、次のように明確に述べている。「真宗皇帝が玉清昭応宮使の職を設けて以来、王丹がその職に任命された。その後、王丹は病気で引退したため、皇帝は太衛に命じて玉清昭応宮使を率いさせ、宰相の半額の給料を与えた。これが祖貢制度の始まりである。」当時の祖貢制度は「この重要な地位を占め、大臣の管轄下にあった」(『宋大勅集』巻59「項民忠著 静霊宮使制度」)。これを受けたのは高位の者で、人数も非常に少なかった。王安石が改革を断行すると、祠や俸給制度は「新法に異論のある者への対応」(宋代の王旭の『演義一謀略』巻1)の制度に変わり、欠員数は大幅に増加し、対象は中級官僚にまで広がり、それまでの数人から100人近くにまでなった。その後、発展の勢いは急速に進み、南宋初期には、今日数えられる寺院や俸禄を担当する官吏の数は1,400人を超えました。南宋の領土の縮小や官吏の欠員の減少などの要因を考慮すると、この数は驚異的です。 南宋代には、勅旨を受けなかった中高級の学者や官僚はほとんどいなかった。誤って弾劾されれば、「勅旨を乞う」か「職を解かれて勅旨を受ける」運命だった。これは当然、出世を熱望する学者官僚にとっては人生の挫折となるが、官僚としての昇進を目指していない、あるいは目指すことができない人にとっては良い逃げ道となる。例えば、偉大な儒学者の朱熹は、官僚になってまだ間もないが、しばしば辞職を求めた。なぜなら、「官僚として仕える」ことのほうが、彼にとって確かに良い選択だったからだ。「皇帝に仕えることはできないのなら、故郷に戻って講義をしたり、哲学について書いたりしたほうが、国からいくらかのお金をもらえるだろう。」 南宋代には「寺給」が普及していたため、官職で成功しなかった多くの学者は「寺給を請求する」という逃げ道に慣れており、当然南宋朝廷に経済的圧力をもたらした。そのため、歴史学界では比較的否定的な評価を下している。例えば、香港の学者梁天熙は、その代表作『宋代寺俸制の研究』の中で、寺俸制は経済的負担をもたらしただけでなく、学者の風格や官僚の行政にも多くの悪影響を及ぼしたと考えている。 (1)党員が皇帝を崇拝すると、党の災難はより深刻になる。 (2)腐敗した役人たちが皇帝を崇拝し、富を蓄積することが流行した。 (3)義務の履行や祖先を祀る寺院の不履行により公的統治の悪化を招いた。 (4)自制心の喪失と祖先の寺院の喪失は、これらの結論は信頼できる。 しかし、別の観点から見ると、祖廟給与制度には積極的な意義があり、特に南宋時代の文学や学問の発展に与えた影響は積極的に評価され、十分に評価されるべきである。 |
<<: 宋代の枢密院について簡単に紹介します。枢密院と三衙門の関係は何ですか?
>>: 宋代の二政体制について簡単に紹介します。二政体制は北宋時代のものでしょうか、それとも南宋時代のものでしょうか。
推薦する
南中王派の紹介:代表的な人物には斉仙、朱徳之、薛応奇、薛嘉などがいる
王陽明は、朱熹、陸九遠などと並んで名高い宋明代の儒学者です。陸九遠の心の理論を継承・発展させ、宋明の...
「関山月」は李白によって書かれた。詩人は古代の辺境での戦争を見つめた。
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
古典文学の傑作『論衡』第24巻 卜占篇 全文
『論衡』は、後漢の王充(27-97年)によって書かれ、漢の章帝の元和3年(86年)に完成したと考えら...
「峨眉山月歌」はどれほど美しいでしょうか?詩「峨眉山の月の歌」鑑賞
『峨眉山月歌』はどれほど美しいのか?『峨眉山月歌』のどこがよいのか?これらは多くの読者が気になる疑問...
「君主に対する苦情」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
李青昭の「君子への苦情」の歌詞湖面には風が吹き、波は大きく、秋も終わりに近づき、赤い花も香りもほとん...
『紅楼夢』で西仁と賈宝玉の秘密の性行為がどうして世間に知られるようになったのか?
紅楼夢では、西仁と賈宝玉が密かにセックスをしていました。秘密の試みと呼ばれていたので、とてもプライベ...
昔、バッグは男性の持ち物でした。女性がリュックを背負うのが流行したのはいつからでしょうか。
昔、バッグは男性の持ち物でした。女性がリュックを背負うのが流行ったのはいつからでしょうか?興味のある...
雅歌集の主な内容は何ですか?雅歌集にはどのような部分がありますか?
詩篇の内容の簡単な紹介スタイル分類『詩経』は、章と文を繰り返す形式を主に章構成に採用しており、その主...
『三朝北孟慧編』第194巻はどんな物語を語っているのでしょうか?
『延行』第二巻は94部構成です。それは紹興9年嘉神3月4日に始まり、4月に終わった。 4日目、嘉深、...
『本草綱目 第3巻 眼科諸疾患の治療』の具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
賈宝玉と碧翰は数時間お風呂に入っていました。何をしていたのでしょうか?
『紅楼夢』では、賈宝玉と碧翰が何時間も風呂に入っていました。二人は何をしていたのでしょうか?ベッドと...
唐僧はなぜ前世で金禅子と呼ばれていたのでしょうか?本当に大蝉なのでしょうか?
『西遊記』で最も多くの称号を持つ人物といえば、唐僧同志でしょう。如来の二番目の弟子、李世民の弟、殷宰...
劉果の「四字詩:高き感情と真意」:この詩のテーマは、別れを懐かしみ、思い出すことです。
劉果(1154-1206)は南宋時代の作家であり、雅号は蓋之、別名は龍州道士としても知られている。彼...
漢代の儒学者劉鑫の『西京雑記』:序文:古代の歴史ノートと小説のコレクション
『西京雑記』は古代の歴史ノートや小説を集めたものです。漢代に劉欣によって書かれ、東晋に葛洪によって編...
賈怡の新著第10巻にある胎教の原文は何ですか?
『易経』には「根本を正せば天地の理は整う。少しの過ちが大きな違いを生む。だから君子は初めに慎むべきだ...