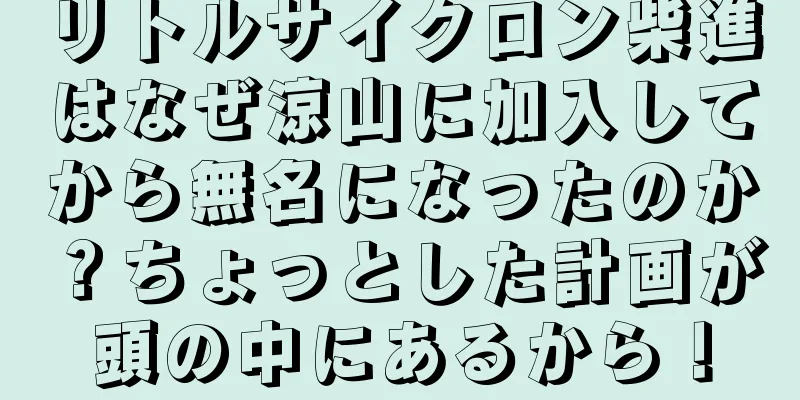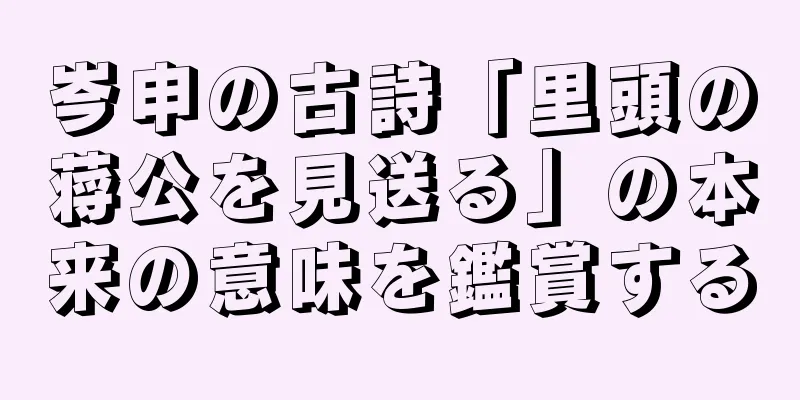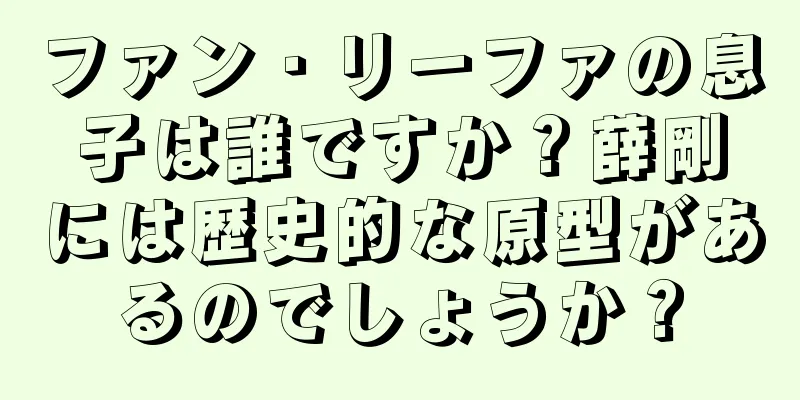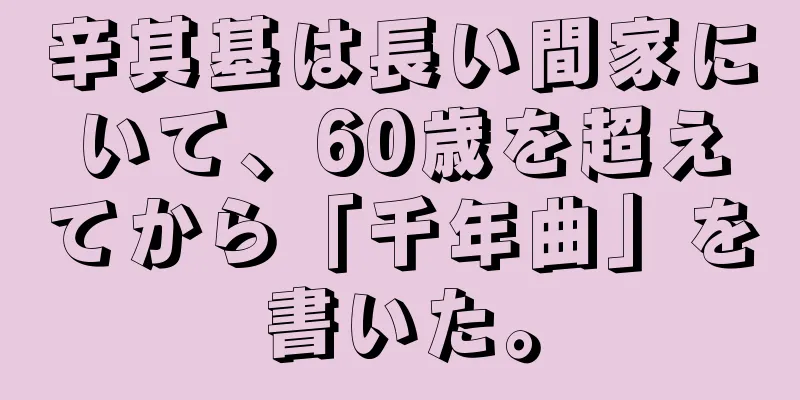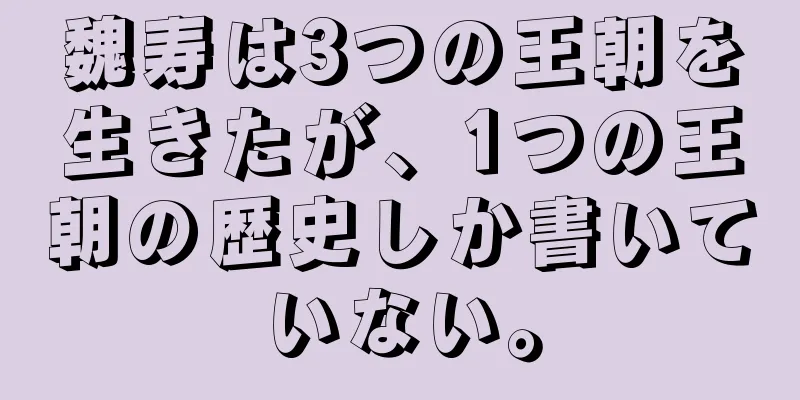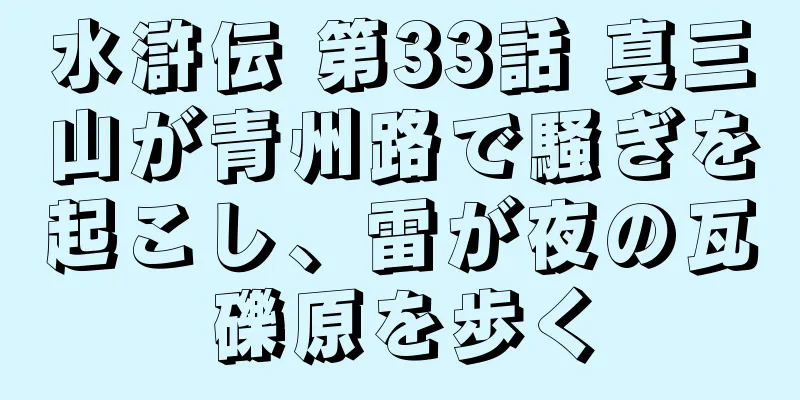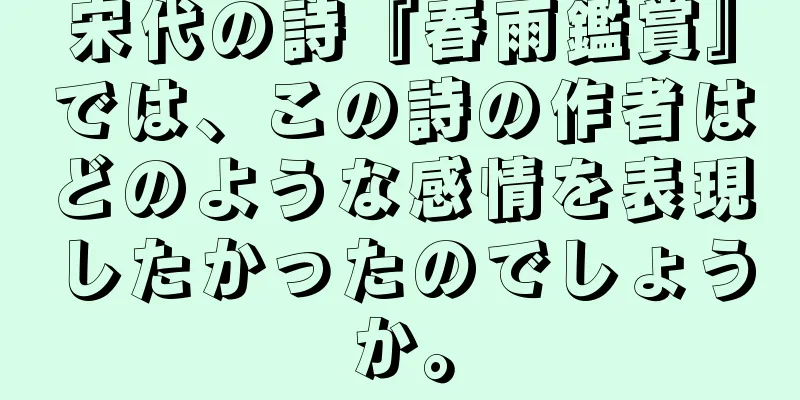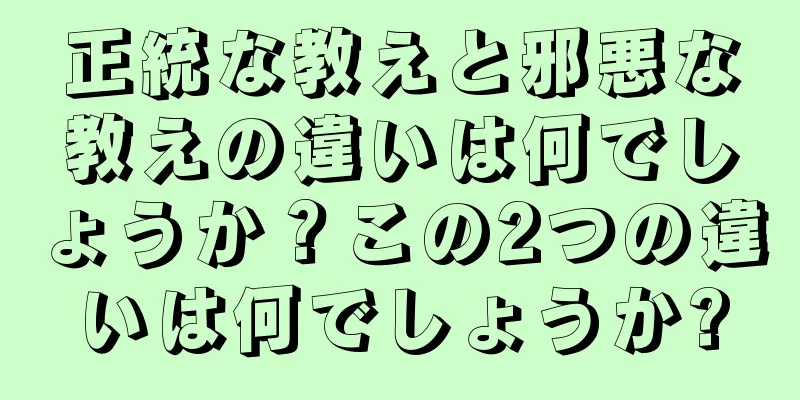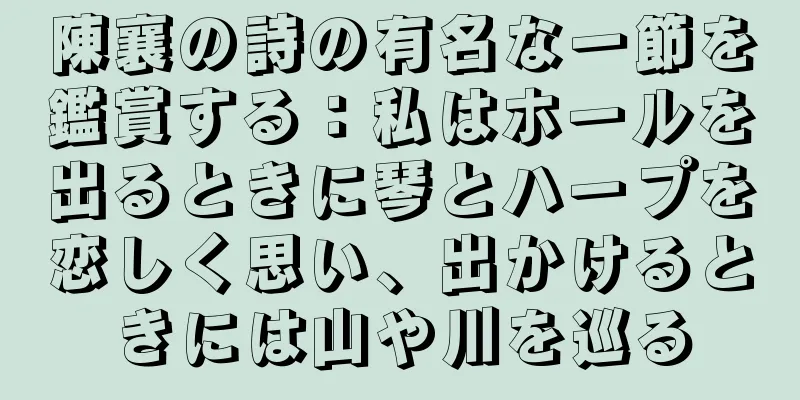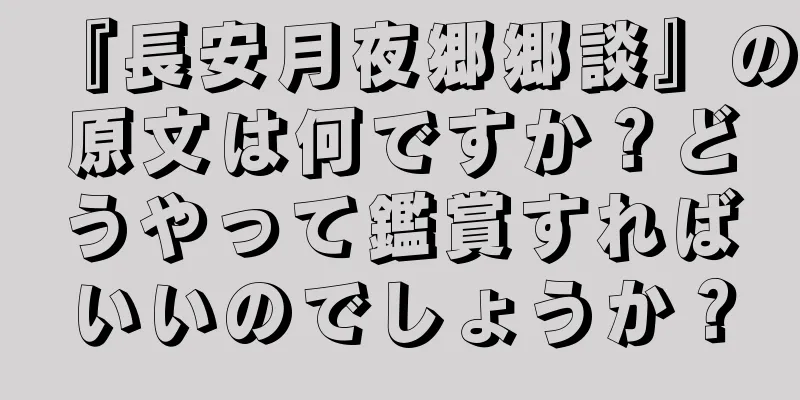ファン・リーに関する逸話や物語は何ですか? 「鳥は殺され、弓はしまわれる」ということわざはどのようにして生まれたのでしょうか?
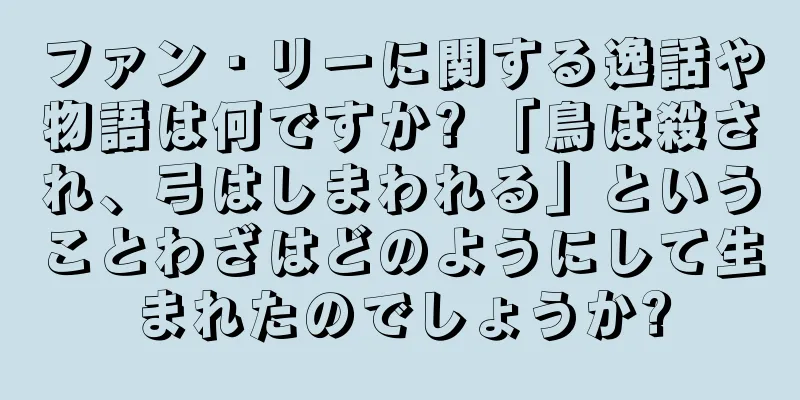
|
中国語の慣用句「鸟绝弓藏」は「niǎo jìn gōng cáng」と発音され、鳥がいなくなると弓も隠されて使われなくなるという意味です。何かが成功した後、それに貢献した人々が追い出されるという比喩です。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 慣用句の由来 『史記 越王 郭堅伝』:「飛ぶ鳥が消えたら、良い弓は片付けられる。狡猾なウサギが死ねば、走る犬は調理される。」 慣用句と暗示 ファン・リー 春秋時代末期、呉と越は覇権を争っていた。越は呉に敗れ、和平を求めて降伏した。 越王の郭堅は奮闘し、大臣の文忠と范礼を任命して国政を立て直した。10年間の屈辱に耐え、国を治めるために奮闘した後、国を弱小から強国へと変え、ついに呉を破って国辱を洗い流した。越の王、郭堅が呉を征服した後、武宮で大臣たちを宴会に招いているときに、范離が行方不明になっていることに気付きました。翌日、范離の上着が太湖のほとりで発見され、誰もが范離が湖に飛び込んで自殺したと考えました。しかし、それから間もなく、誰かが文忠に手紙を送り、そこにはこう書かれていた。「鳥が全部撃たれたら、投石器をしまっておく。野兎が全部捕まったら、猟犬を殺して煮る。敵国が滅んだら、顧問を捨てるか殺す。」 越王は、幸福ではなく逆境を共に分かち合える人です。医者はまだ彼を見捨てておらず、彼は間もなく殺されるに違いない。 「この時、文仲は范礼が死んでおらず、隠遁していたことに気づいた。手紙のすべてを信じていたわけではないが、范礼は病気を理由に朝廷を欠席することが多く、次第に郭堅の疑惑を招いた。ある日、郭堅は文仲を訪ね、文仲が自殺するように刀を残した。文仲は郭堅の意図を理解し、范礼の忠告に従わなかったことを後悔し、刀を抜いて自殺せざるを得なかった。 ハン・シン この慣用句は、劉邦が建国に多大な貢献をした将軍たちを全員殺害した西漢の時代の状況にも言及しています。劉邦は皇帝になった後、韓信の権力を弱めるため、当時「斉王」であった韓信を「楚王」に任命し、韓信が財を成した地から遠ざけようとした。その後、誰かが韓信を「謀反」と告発し、劉邦は韓信を「淮陰侯」に降格させた。数か月以内に、呂志は韓信を長楽宮に誘い込み、反逆罪で殺害した。 劉邦は紀元前202年に天下を取り、韓信は紀元前196年に斬首された。苦難を共にした君主と臣下の二人は、天下が落ち着いてからわずか1年余りしか一緒に暮らしていなかった。処刑される前に韓信は「狡猾なウサギが死ねば走っている犬も煮え、鳥が消えれば良い弓も隠される、敵国が敗れると顧問も死ぬ」と嘆いた。 慣用句の使用 短縮形。述語または形容詞として使用され、軽蔑的な意味を持ち、「ウサギが死んだ後に犬が調理される」という場合によく使用されます。 例 1. 「弟は方拉討伐から帰ってきて、東人の私に隠遁生活を送るよう勧めた。鳥が消えれば弓も片づくだろう、といった災難が来ることを知っていたのだ」清代陳塵著『続水滸伝』第22章 2. 三国志・曹丕の『華麗なる都洛陽紀行』:「淮陰の五つの罰、鳥は去り、弓は隠れ、自らを守り、名誉を保つ唯一の方法は紫方である。」 3. 清代の敦路による「ボーイスカウト帰郷図」:「私はスカーフを外して腕を上げて褒美を求めたが、鳥を全部殺して弓をしまってから考え直し、故郷に戻った。」 |
<<: 范麟の思想的功績は何ですか?ファン・リーの考えにはどのような側面が含まれていますか?
>>: ファン・リーに関する逸話や物語は何ですか?三度の集合と三度の離散はどのようにして起こったのでしょうか?
推薦する
董小婉が「秦淮の八大美女」の一人になった後、彼女はどのようにして茅皮江と知り合ったのでしょうか?
明王朝(1368年 - 1644年)は、太祖朱元璋によって建国された中国史上の王朝です。首都は当初南...
禅源条約とは何ですか?禅源条約の主な内容は何ですか?
禅源条約とは何を意味するのでしょうか?禅元条約は、数々の戦争の後に北宋と遼の間で締結された同盟でした...
有名な哲学書『荘子』雑集・徐無帰(2)原文と方言訳
『荘子』は『南華経』とも呼ばれ、戦国時代後期に荘子とその弟子たちが著した道教の教義をまとめた書物です...
明代のどの皇帝が西洋館を設立しましたか?なぜ数年後に取り消されたのでしょうか?
明王朝(1368年 - 1644年)は、太祖朱元璋によって建国された中国史上の王朝です。首都は当初南...
『紅楼夢』の母と娘、丹春と趙叔母の類似点は何ですか?
タンチュンと趙おばさんの関係は非常に複雑で、単純な好き嫌いではありません。次回は、Interesti...
Guanという姓の男の子にはどのように名前を付けたらいいでしょうか? 「Guan」という姓を持つおしゃれな男の子の名前を厳選しました!
今日、Interesting History の編集者が、Guan という姓を持つおしゃれな男の子の...
中国史上最大の大型船:東呉船は3,000人の兵士を乗せることができた
1. 大翼軍艦:春秋時代の呉の国で初めて登場した。中国最古の軍艦であり、春秋時代最大の軍艦でもある。...
劉備はすでに荊州に4つの郡を持っていたのに、なぜ孫権から南郡を借りる必要があったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
姜逵の『琵琶仙人』の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
蒋魁の『琵琶仙人』の原文は? どのように翻訳する? これは多くの読者が気になる質問です。次に、興味深...
張居正と海叡はともに朝廷の役人であった。なぜ高い地位にあった張居正は海叡を利用しなかったのか?
張居正と海睿はともに明代中期の宮廷官僚であった。年齢で言えば、海瑞は張居正より10歳年上だった。官吏...
古代の詩の鑑賞: 詩集: Liou'e: Liou は I であって、I ではない。
『詩経』は中国古代詩の始まりであり、最古の詩集である。西周初期から春秋中期(紀元前11世紀から6世紀...
『紅楼夢』の真紅の雲石の指輪とは何ですか?この裏話は何ですか?
『紅楼夢』は古代中国の四大傑作の一つで、章立ての長い小説です。これについて言えば、皆さんも聞いたこと...
孟浩然は仙寿山に登り、楊公の碑を見て、「弟子たちと仙寿山に登る」と書いた。
孟浩然(689-740)は、浩然、孟山人としても知られ、襄州襄陽(現在の湖北省襄陽市)の出身です。唐...
唐や宋の時代と比べて、明や清の時代にはなぜ詩人が少なかったのでしょうか?
明清時代には文化が栄え、現在でも語り継がれる四大小説だけでなく、多くのオペラも受け継がれました。しか...
魏夫人:晋の偉大な書家、王羲之の女性教師
魏夫人は、本名を魏索といい、東晋時代の有名な女性書道家でした。彼女は書道の才能に恵まれ、その業績は男...