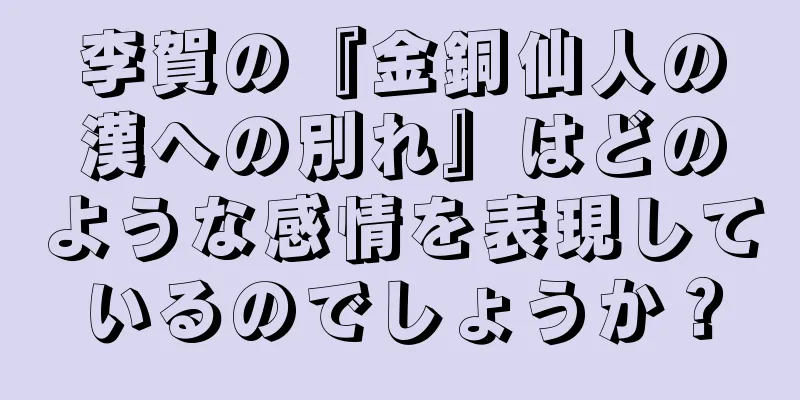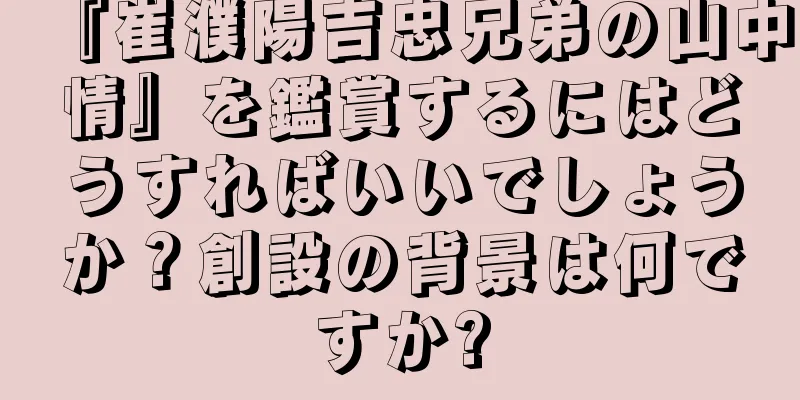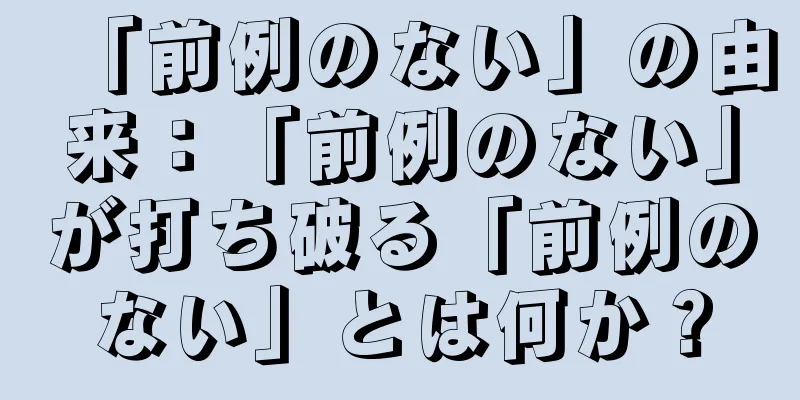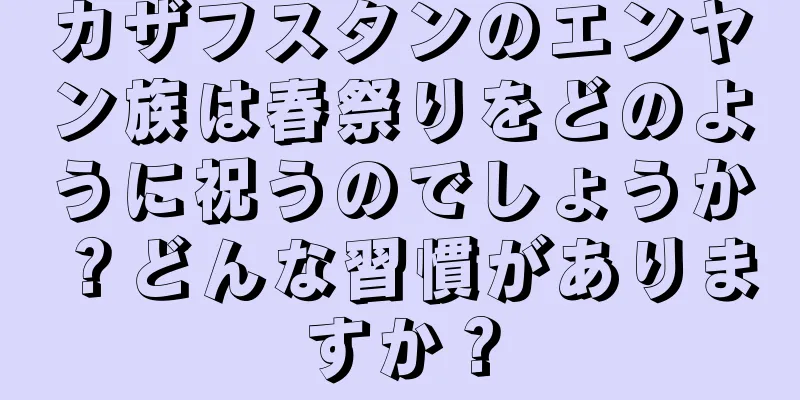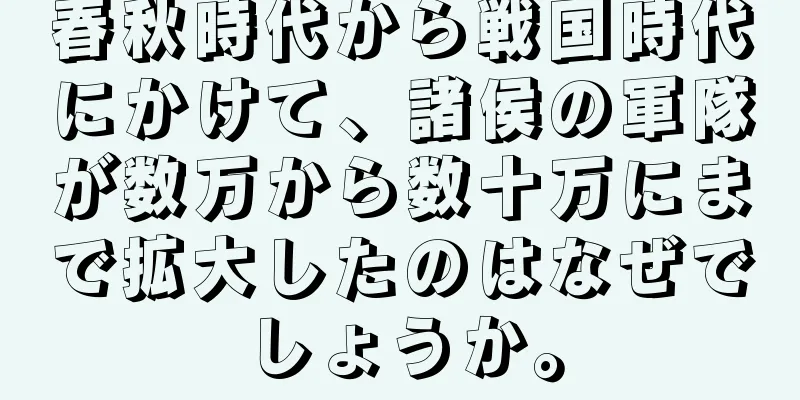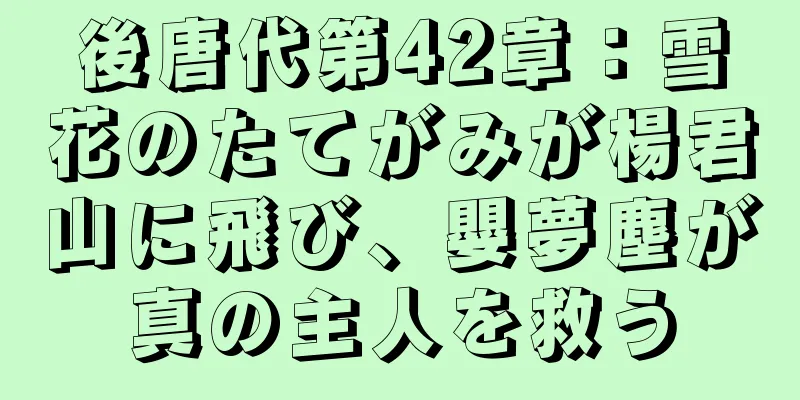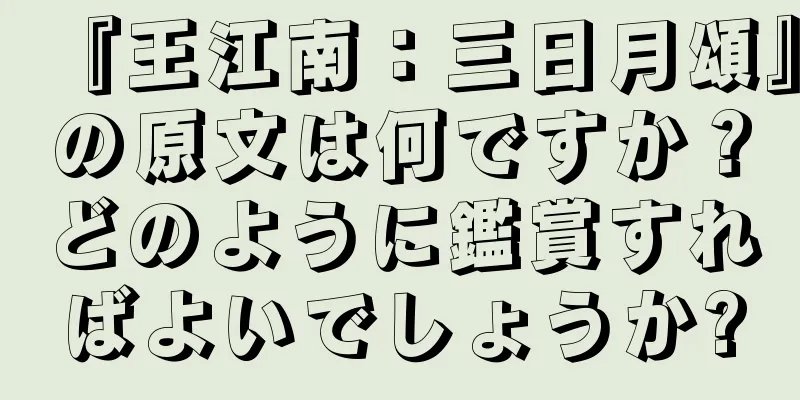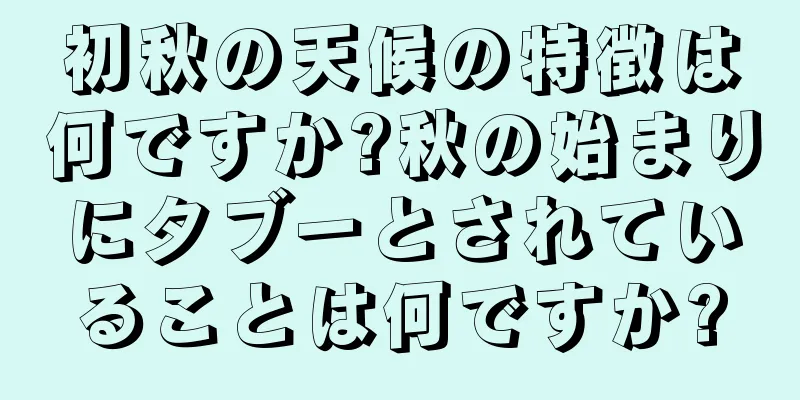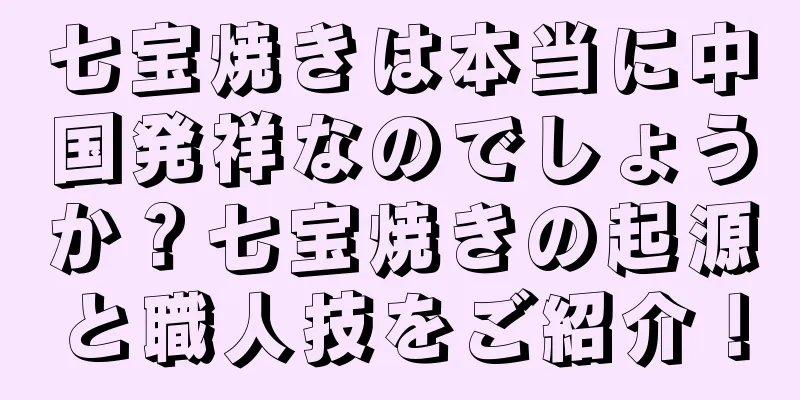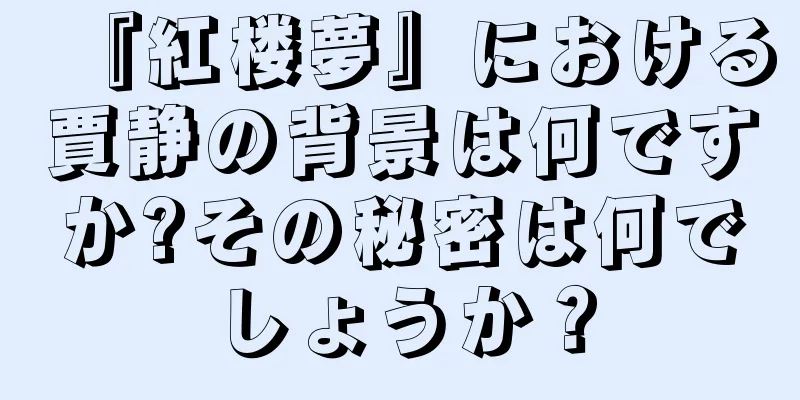「一枚の紙切れで四人の宰相が殺された」北宋の宰相、韓起にとって、これはどれほど困難なことだったのだろうか。
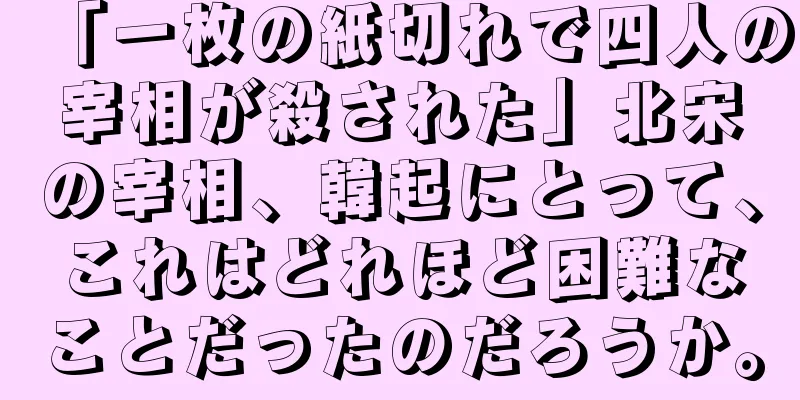
|
北宋の仁宗皇帝の景有三年、蜀州の職に就く予定だった韓起は、都に留まり右検閲官を務めるよう命じられた。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 翌年、景祐三年に河東で地震が発生し、一万人以上の死傷者が出たため、西夏の元昊は辺境の国々を侵略し、西夏王国を建国した。 この二つの出来事は、長らく平和を享受していた宋代に前例のない圧力をかけることとなった。河東地震は天からの罰を意味し、不吉な前兆と考えられていた。西夏の元昊は宋朝の属国状態から脱却し、国境沿いの十数ヶ国を占領し、西北地域は再び戦乱の時代を迎える可能性が高い。 こうした背景から、韓其氏と宋其氏が率いる「若い世代」の学者官僚政治団体は、自らの意見を表明し、現在の政治を批判し、裁判所に方針転換を求める嘆願書を提出した。同時に、彼らは自然災害であり人災でもある河東地震について大騒ぎした。宋代の腐敗した無能な「権力者」が神を怒らせたと信じられていたため、世界のすべてのものを支配する「天」は「権力者」に警告するために人々に災害を送ったのです。 「権力者」とはどういう意味でしょうか。天皇を直接責めることはできないので、首相が責任を取らなければなりません。宝元元年、韓起は「宰相と副宰相に適任者がいない件について報告する」と題する申文を提出した。彼は、当時の首相の王遂、陳耀作、副首相の韓毅、史忠礼が災害に対処できず、北西部の国境問題への対応に全く無力だったと非難した。彼は「無能な役人たちにそれを勝手に破壊させた」として彼を叱責した。 仁宗皇帝は追悼文を読み上げ、同日中に4人を解任した。これはいわゆる「一枚の紙が四人の首相に落ちた」事件であり、韓奇の生涯におけるハイライトでもあった。 実際、いわゆる「一枚の紙切れが4人の首相を殺した」という事件の背後にある政治的論理、そしてその制度構築と発展のプロセスは非常に興味深い。この出来事は単なる古代の政治的出来事ではありません。同時に、これは北宋の仁宗皇帝の治世における「皇帝、宰相、諫言」の三つ巴の駆け引きの初期の典型でもあり、北宋の「正規の権力」システムの発展における重要な段階でもあった。 「一枚の紙で四人の首相を解任」、この作戦はどれほど難しいのだろうか。明代の沈廉が首相の燕松を「十罪の碑」で弾劾し、鞭打ち刑に処せられ、庶民として宝安県に流刑され、後に燕松に迫害されて死んだ事件を思い起こすことができる。 こういうことをするのはちょっと危険です。綱の上を歩くと、ちょっとしたミスで粉々に砕け散ってしまうこともあります。宋朝は明朝よりもずっと温和で、公衆の面前で棒で罰することはなかったが、首都から追放することは不可能ではなかった。 では、宋代の検閲官であった韓起が、朝廷の宰相 4 人を同時に弾劾し、しかも罰を受けずに済んだのはなぜでしょうか。こんなに難しい手術が、控えめに言っても完了できるのでしょうか? 韓起は当時、右検閲官であり、「太極」グループの役人であり、すべての役人を監督する権限と皇帝に助言する責任を持っていました。彼は七位の官吏である。王、陳、韓、史はいずれも首相だった。韓奇には助言権があったが、一度に4人の首相を弾劾することは国のためにならない。 さらに、仁宗皇帝が韓起のたった一つの陳情書に基づいて4人の宰相を解任することは不可能であった。宋代は文人と共同で国を統治し、文人の中核的な代表は文官の最高位である宰相であった。 4人の首相を急遽解任し、天皇が首相の役割を担うとすれば、天皇自身の行政能力だけでは複雑な国政に対処しきれないだろう。 宝元元年のある日、韓奇が「若い」学者官僚として仁宗に会うために宮殿に入ったと想像できます。内外の混乱の時代、王・陳・韓・史はいずれも宰相になる資格がなかった。仁宗皇帝は彼らを廃位しようとしたが、先祖の法律によって制限されており、理由なく宰相を廃位することはできなかった。そこで、韓起と協議し、韓起に四大臣を弾劾する旨の申立書を提出させ、四大臣は長い間高官の地位にありながら何の功績もあげていないとして罷免した。 常識的に考えれば、たとえ皇帝が宰相を罷免する意図を持っていたとしても、右検閲官の韓起の誦文のみに基づいて4人の宰相が同じ日に罷免されたという事実は、古代政治の正常な内部統制プロセスに沿うものではない。この点に関しては、仁宗皇帝の治世中の「太極」制度について話す必要があります。 「太監」とは何でしょうか?公式の説明は、「宋代には、副監察、宮監察、監察監が訂正と批判を担当し、一般的に太官と呼ばれていました。建医、実医、部闕、正眼は、諫言と諫言を担当し、一般的に建官と呼ばれていました。両者の職務は類似していたため、総称して太監と呼ばれていました。」です。 一般的な説明は、検閲官と、すべての役人を監督し、皇帝を諫言する責任を負う譴責官を組み合わせたものであるというものです。これは、古代の官僚制度内の監督機関、いわゆる「譴責官」に属します。 「太極」制度の発展は、仁宗皇帝の治世中に最も重要かつ典型的であった。 そのため、「監察官の職務は建国当初は軽かったが、仁宗皇帝の時代に重くなり、建国当初は単なる官職であったが、仁宗皇帝の時代には高位の職となった」という言い伝えがある。 仁宗皇帝の治世初期、張賢皇太后は裏で政務を担当していた。検閲官は皇太后に権力の返還を何度も促したが、これらの提案は皇太后によって基本的に抑圧された。 仁宗が権力を握った後、陸毅堅の時代が訪れました。陸毅堅の治世中、彼は絶対的な権力を握り、「太監」を抑圧しました。その結果、「太監」の地位は非常に低く、権力を行使することができませんでした。 仁宗の清暦年間、范仲厳や欧陽秀といった改革派大臣が権力を握って初めて、「太極」は権力者から強い支持を受け、物言う精神が培われ、宰相に対抗できる政治勢力が形成された。 呂毅堅を解任した後、仁宗は政治的制約を取り除き、「世の中の悪を正したいので、検閲官を増やした」。彼は王粛、欧陽秀、蔡祥、于静を相次いで検閲官に任命した。そして、「今後、検閲官を任命する際には、現職大臣が推薦した者を用いてはならない」という厳しい命令を出した。首相の検閲官任命権は直接剥奪された。これにより、検閲官は官僚集団の支配から逃れることができました。 仁宗は検閲官たちを非常に丁重に扱った。于静が提案したとき、「暑い夏で、静は皇帝に厳しい口調で言った。静はきちんとした服装をしていなかった。皇帝は中に入って言った。「私はあなたの臭い汗で息が詰まり、私の顔に唾を吐いた。それでも皇帝は検閲官たちをこのように容認した。」しかし、このような状況でも、仁宗は基本的に検閲官の助言を受け入れ、時には「検閲官の言うことだけを聞く」ことさえあり、検閲官から攻撃を受けた人が解雇されることはほとんどなかった。 仁宗皇帝の治世中、夏宋、陸毅堅、文延波、范仲燕はいずれも検閲官によって弾劾され、その後職を解かれたり降格された。 したがって、韓起が「一枚の紙で四人の宰相を辞任させる」ことができた理由を理解するのは難しくない。これは皇帝権力の支援だけでなく、検閲官の力が強まっていたことも理由の一つである。宰相団がますます巨大化したため、次第に天皇の権力を抑圧するまでに至った。 したがって、帝国勢力グループは、帝国勢力に代わる勢力を育成し、帝国勢力と競争できるようにする必要がある。検閲官が最も適任だったのは明らかだ。仁宗が「太極」制度を改革した後、検閲官団は発言権だけでなく、監督権も持つようになった。 同時に、中央機関に従属せず、支配集団の束縛から解放され、次第に首相と競争できる新たな勢力となっていった。 皇帝の過剰な支援は必ずしも良いことではない。仁宗が「太極」機関に頼りすぎたとき、制度は発展の過程で創始者の本来の意図に反することになったかもしれない。欧陽秀はかつてこう語った。「検閲官が時々デマを流しても、黙認される。誰かが解任されたら、弾劾された人も免れない。近年、多くの首相が自らの失策や彼らに反対する声をあげた人々のせいで解任されている。」 検閲官の個人的な処遇については、「私は検閲官長の王素に三等軍服を与え、于静、欧陽秀、蔡翔に五等軍服を与えた。面会指導の日に私は言った。「あなたたちは皆私が選んだ者であり、ためらうことなく多くの事柄を論じたので、これを与える。」 仁宗の支援により、本来は監督官に過ぎなかった「太監」の権力は限りなく拡大し、中央の意思決定にまで介入するようになった。蘇軾はかつて検閲官についてこう言った。「皇帝は皇帝の馬車に関しては表情を変えるが、朝廷に関しては宰相が処罰される。そのため、仁宗皇帝の治世中、批評家たちは宰相が検閲官の命令に従っただけだと批判した。」 新しく晋氏となった王夫之は傅弼に尋ねた。「あなたは宰相でありながら、検閲官の指示に従うだけです。傅弼は答えられません。」 范震はかつてこう言った。「陛下は今、自ら善悪を判断せず、内閣大臣や枢密院大臣を責めています。内閣大臣や枢密院大臣は善悪を判断する勇気がなく、善悪を判断するのは検閲官だけです。」彼は公務員グループの長として検閲官の命令に従わなければならなかった。また、検閲官は弾劾と調査のみを担当していたが、朝廷の権力の支援を受けて権限を逸脱し、政府の行政に介入することができた。これは、検閲官を積極的に推進するという仁宗の当初の意図に反するものであることは明らかである。 「台江」組織の力が強まるにつれ、その構成員はますます多様化し、記念碑の対象や理由も徐々に変化していった。劉航氏は「清暦の時代から検閲官が権力を握っている。検閲官は朝廷が発するすべての命令を、それが適切かどうかに関わらず議論し、勝つまで止めない。また、人々の秘密を暴き、学者や官僚を中傷することにも力を入れている」と語った。 検閲局を設立した目的は、他人の些細な過ちを弾劾することではなく、「皇帝の過ちを調査し、大臣の犯罪を正すこと」であった。仁宗後期には、「君主が宮中でちょっとした過ちや些細なことをすると、皇帝はそれを大げさに言いふらし、皇帝を批判する口実にする」という状況が生まれた。 「他人事への干渉」が皇帝の頭にまで達したとき、仁宗は「太極」の道は迷ってしまったように感じた。やがて、仁宗は検閲の風潮がますます蔓延していることに気づき、「朝廷の利益や損失、あるいは人民の利益や問題以外の理由で他人を弾劾してはならない。これに違反した者は処罰される」という勅令を出した。 しかし、「太極」が新たな政治勢力となった後、皇帝の権力は勅令によってその活動を止めることはできなくなり、仁宗皇帝の時代から「太極」の動向がますます激しくなるにつれて、徐々に党派闘争の「黒幕」となっていった。裁判所職員らは書面で意見を表明するという口実で互いに攻撃し合った。 「太極」制度は、すべての役人を監督する機能を完全に失った。 しかし、宋代の君主や大臣たちは常に「祖先の法」を重視し、この習慣を代々伝え続け、神宗、哲宗、徽宗の治世後、宋代の滅亡まで宮廷を席巻する悪しき風潮となった。 |
<<: 曹太后のような女性の場合、韓奇はどのようなトリックを使って幕を外したのでしょうか?
>>: なぜ韓奇は寛大で寛容であると言われるのでしょうか?翡翠の杯は割れたが、誰も彼を責めなかった。
推薦する
許楚、于進、李典に殴られた趙雲は無事に逃げることができたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
なぜ関羽は4回も矢に撃たれたのに、趙雲はほとんど矢に撃たれなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
紅楼夢第34章:妹への愛の中の愛、兄を説得するための間違いの中の間違い
『紅楼夢』は、中国の四大古典小説の一つで、清代の章立て形式の長編小説です。通俗版は全部で120章から...
劉克荘は、自分の才能が認められていないことへの不満を、歌姫の声で表現し、「宴会で歌を聞いた時の気持ち」を書いた。
劉克荘(1187年9月3日 - 1269年3月3日)は、原名は卓、字は千福、号は后村で、福建省莆田県...
士公の事件第446章:徳の高い父と娘が泥棒を誘い出して捕らえ、若い夫婦が好色な僧侶を殺害した
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
子羊は何を表していますか?雅歌の子羊をどのように評価すればよいでしょうか?
ラム[先秦] 匿名さん、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきますので、見てみましょう...
『前漢民謡』第47章の主な内容は何ですか?
竇皇后は兄弟たちと会えて喜び、文帝は蛮族に征服された。しかし、文帝は母親が到着したことを聞くと、郊外...
涼山の英雄張青の人生はどのようなものだったのでしょうか?彼の息子は何を成し遂げたのでしょうか?
張青の物語は好きですか?今日は、興味深い歴史の編集者が詳しく説明します〜涼山の英雄の中には張青という...
本草綱目第8巻生薬編Leaky Basketの具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
ハニ族の衣服 ハニ族の衣服も国民的特徴である
ハニ族の人々は、衣服を作るのに紺色の布を好んで使います。布を漂白して染色する工程は、藍の染料を容器に...
『海潮を眺める 東南の美しい風景』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
望海潮·南東風景区劉勇(宋代)東南は美しい地であり、銭塘は三武の首都であり、古くから繁栄してきました...
大足保定石刻にある石像は何ですか?特徴は何ですか?
大足保定石刻の石像とはどのようなものですか?その特徴は何ですか?保定山の崖彫刻は南宋時代に初めて彫ら...
明代の四大宦官の一人である王直は、最後にはどのようにして良い結末を迎えたのでしょうか?
成化12年(1476年)、悪人の李子龍が魔術を使って宦官の衛佗と共謀し、密かに宮殿に入り、事件後に処...
「紅楼夢」の2つの詳細は薛宝才の顔を平手打ちし、彼女が全体的な状況を理解していないことを示している。
『紅楼夢』では、薛宝才の大観園での性格は冷静で理性的ですが、本当にそうでしょうか?次の2つの詳細から...
杜甫の詩「二十三番目の叔父の記録官を郴州に送る」の本来の意味を理解する
古詩「二十三番目の叔父である記録官を郴州に送る」時代: 唐代著者: 杜甫徳と才能のある人は裕福な...