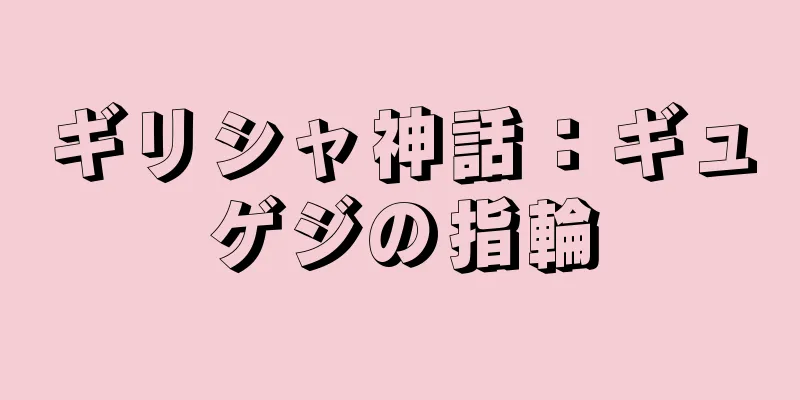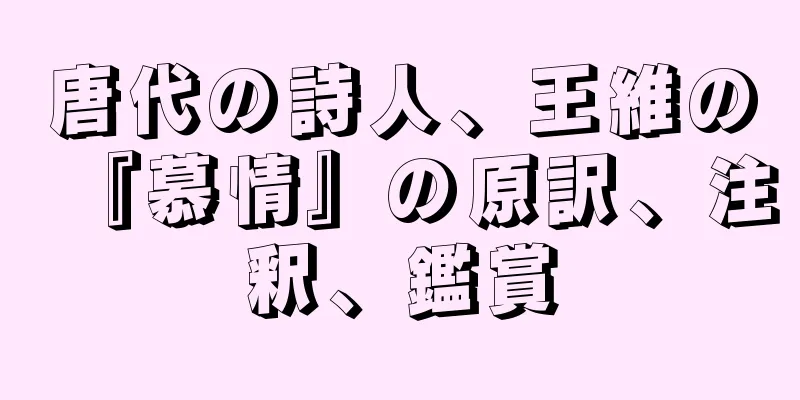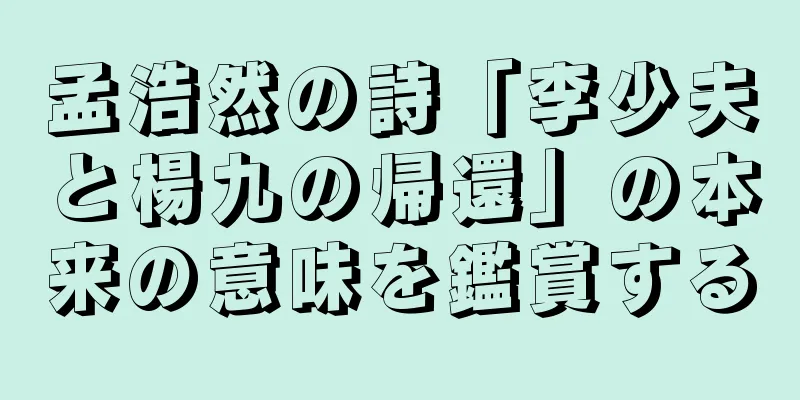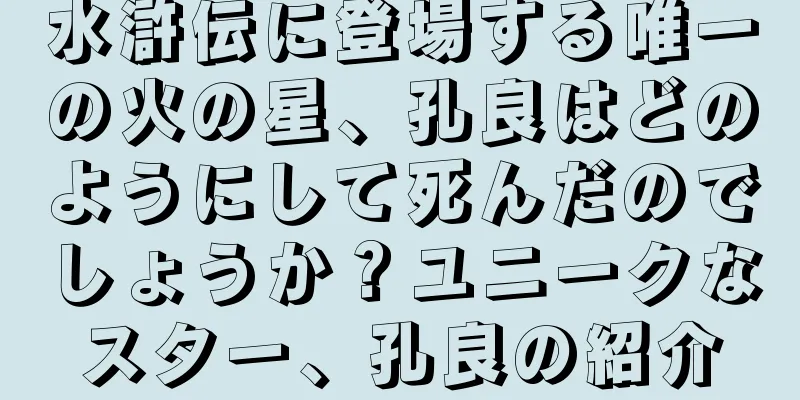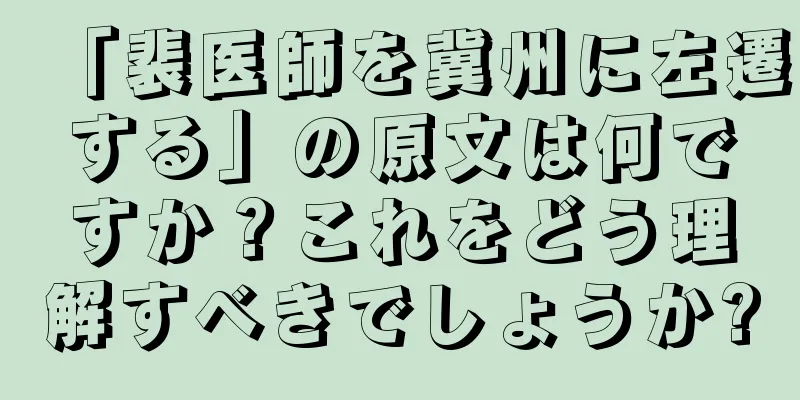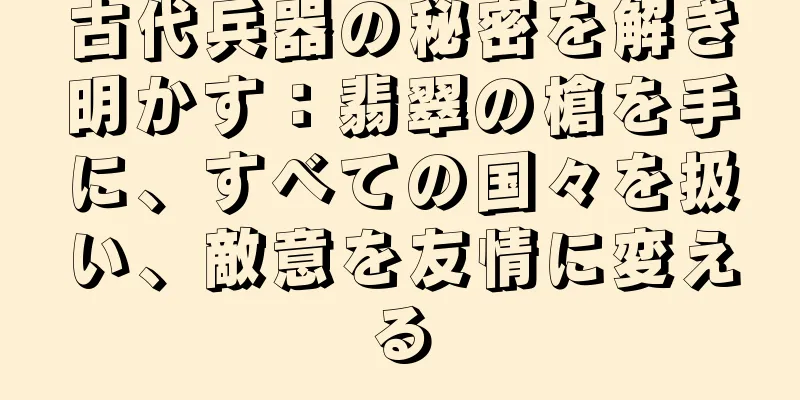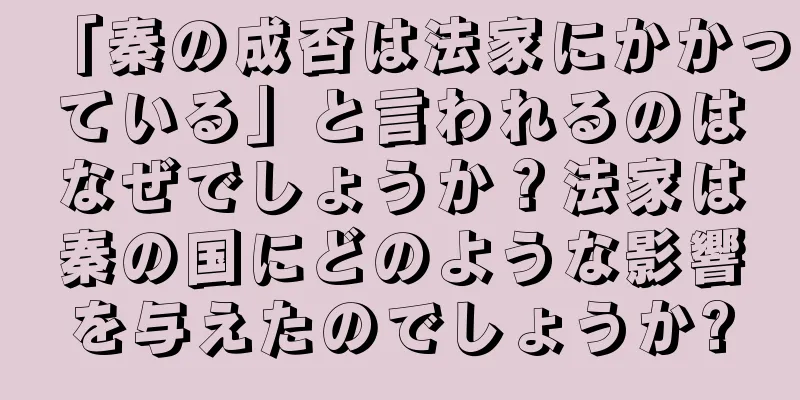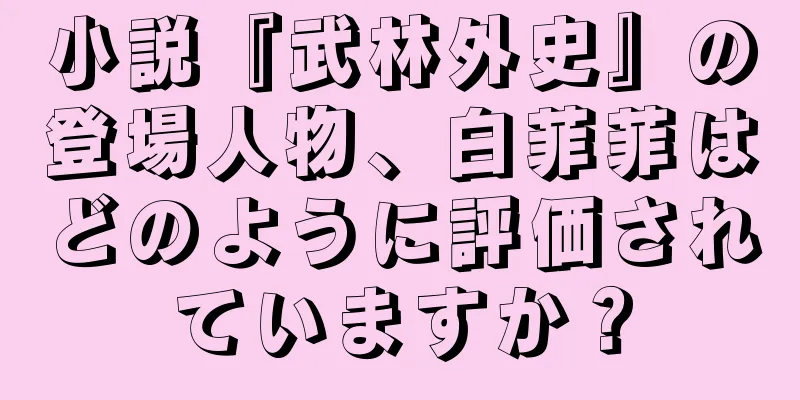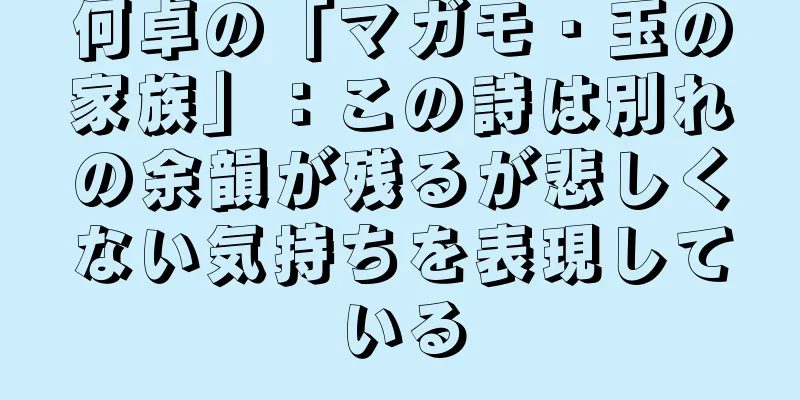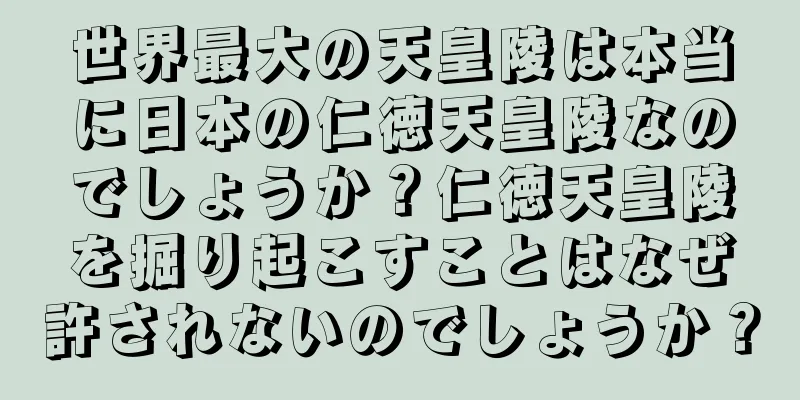息子を産むなら孫仲武のような子がよいと言われているが、ではなぜ孫権は晩年無能になってしまったのか?
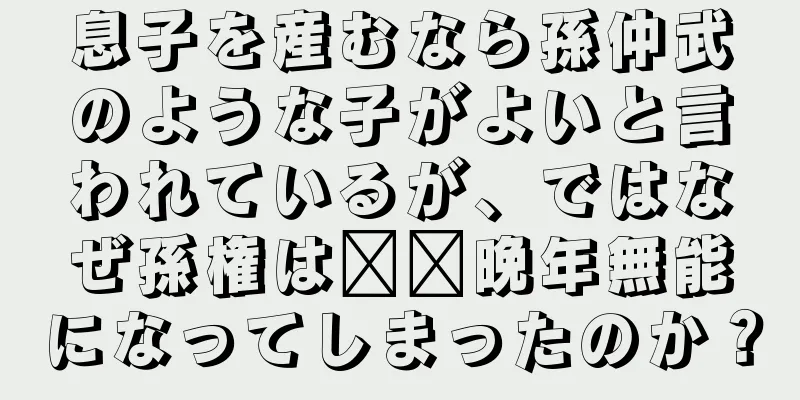
|
孫権が晩年に無能になった理由について、Interesting Historyでは、次の4つの側面が原因だと考えています。 1. 孫権は賢い君主ではなかった。孫権の権力は兄の孫策から受け継いだものであったが、能力の面では孫策にはるかに劣っていた。孫策と周瑜はかつては親しいパートナーであったが、孫権が権力を握ると、周瑜は常に抑制された。孫権は周瑜を大将軍に任命したが、実際には東呉の軍事力は周瑜の他に程普の二人によって指揮されていた。この二重軍事力体制は東呉の軍事的発展に非常に悪い影響を及ぼした。赤壁の戦いの後、周瑜はそれ以上の功績を挙げることができなかったが、その大きな原因は程普の地方分権化にあった。周瑜が亡くなった後、孫権は弟たちを「副官」として軍に派遣することが多くなったが、これは当然軍の指揮に支障をきたし、また東呉軍の戦績は特に強力な敵に直面していないときには悪くなった。 この状況は北宋時代の状況とほぼ同じです。軍の分散化から、孫権が部下を信頼していなかったことが実際に分かります。心が狭く、誰に対しても牽制と均衡を図る人物が賢いと言えるのでしょうか? 2. 外部環境の安定性。曹丕が皇帝になる前後、赤壁の戦い、夷陵の戦い、小用津の戦い、合肥の戦いなど、東呉、蜀漢、曹魏の間で多くの戦争が起こりました。その主な理由は、領土がまだ不安定で、さまざまな政治グループがまだ争っていたためです。その後、曹丕の死により曹叡は曹魏政権を統制することができなくなり、いくつかの貴族の間で長い内部政治闘争が続くことになった。同時に、曹叡は享楽に貪欲で、見せびらかすのが好きな人物でもあり、国の人的資源と物的資源を深刻に浪費した。蜀漢は曹魏に対しても戦争の兆しを見せ、諸葛亮は数回にわたる北方遠征を開始した。 両家が争うと、東武に対する外圧は弱まった。唐の荘宗皇帝と後蜀の最後の君主の経験はすでに真実を明らかにしている。外部からの圧力がなくなると、自制心の乏しい君主はすぐに失脚するのだ。前述の通り、孫権は賢い君主ではなかった。外部からの圧力がなくなった今、彼が暴君の方向に滑り落ちるのは容易なことだろう。 3. 孫権の領土における複雑な権力構造 東呉の政治構造は、おそらく三国時代の中で最も複雑です。支配的な孫一族は政治的基盤を持たない部外者であり、発展するには地元の氏族に頼らなければなりません。これにより、東呉政権は根本から不安定化した。孫権の最も批判された後継者問題に関しては、複数の氏族が孫権の息子に依存し、互いに陥れ合い、抑圧し合い、一時は孫権に脅威を感じさせたこともあったことがわかります。 外部にまだ敵が存在していた頃、孫権は指導部の団結と安定も考慮する必要があり、大臣たちに対して簡単に行動を起こすことはなかった。外部情勢が安定すれば、大臣たちとのやり取りに何の躊躇もなくなるだろう。孫権による無差別殺人はこのような状況の中で始まった。 4. 東呉の財政危機。三国時代の江南地域は現在とは異なり、経済的に未発達な地域でした。そこで三国時代を振り返ってみると、東呉は大きな波を起こすことができず、その主な理由は経済が追いつかなかったことにあります。孫権は財政問題を解決するために、かつて大規模な墓荒らし運動を起こし、江南の裕福な家庭や各王朝の王や王子たちの墓をほぼ完全に荒らした。曹操はかつて陵墓荒らしの部隊を組織したことがあったが、それは戦時中の特別な措置にすぎず、魏の国が安定すると、曹一族は二度とそのようなことはしなかった。しかし孫権は違った。彼はそのような不道徳な行為を普通のことだと考えていた。 この場合、先祖の墓を掘り返された人々は孫権を呪わないだろうか?しかも、孫権が好んだ先祖の墓の所有者は、発言権を持つ地元の大家族に違いない。たとえ孫権が将来、かつて賢く権力を握っていたとしても、彼らの噂話によって非難されるだろう。この場合、孫権は暴君か暴君のどちらかでした。 |
<<: 歴史資料や非公式小説などを調べてみると、大喬が再婚したという記録はあるのでしょうか?
>>: 劉備は夷陵で敗れた後、なぜ成都に戻らず、白堤城で病死したのでしょうか?
推薦する
『南湖早春』の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
南湖の早春時代: [唐代] 著者: [白居易]風は吹き去り、雲は消え、雨は止みます。湖畔には再び太陽...
バックシザースの習慣はどこから来たのでしょうか?なぜ中国人だけがこの習慣を持っているのでしょうか?
研究によると、手を後ろにはさみ込む最も古い習慣は、元朝初期に始まったそうです。最初の説は清朝の『雲南...
「紅楼夢」の林黛玉は常に標的にされてきたが、彼女は決して怒ったことはなかった
皆さんご存知の通り、『紅楼夢』の林黛玉はいつも狙われていますが、本当に怒ったことはありません。なぜで...
「端平入洛」とは何ですか?南宋軍にどのような影響を与えたのでしょうか?
金朝の滅亡後、かつて金朝が支配していた河南省は二つに分割され、陳(現在の河南省淮陽市)と蔡(現在の河...
陸機のプロフィール:三国時代の孝子、二十四孝子の一人、「オレンジを背負って親を離れる」
『二十四孝典』の正式名称は『二十四孝典詩全集』で、元代の郭居静が編纂したものです。一説には、郭居静の...
何の玉の話と何の玉が趙に無傷で戻ってきた話
楚の卞和は楚の山中で原石の玉を見つけ、楚の李王に献上した。李王は玉職人に鑑定を依頼しました。玉工は「...
「武昌で書かれた」をどう鑑賞するか?創作の背景は何ですか?
武昌で徐真卿(明代)洞庭湖の葉はまだ落ちていませんが、小湘では秋が近づいています。今夜、高寨では雨が...
梁宇勝の『剣の伝説』に登場する世界一の悪魔、喬北明のキャラクター紹介
喬北鳴は梁宇勝の武侠小説『剣の伝説』の登場人物で、西方の崑崙山の星秀海出身で、「天下一の魔神」と呼ば...
「そこにはいつも新鮮な草がある」というフレーズはどこから来たのでしょうか?詩全体ではどのような感情が表現されているのでしょうか?
「世に新草あり」ということわざはどこから来たのか? 次回はInteresting History編集...
陸倫の「張普社に答える辺境の歌・第4号」:この詩の言語は比較的洗練されており、暗黙的である。
陸倫(739-799)、号は雲岩、河中普県(現在の山西省普県)の人。祖先は樊陽涛県(現在の河北省涛州...
賈容はずっと従順だったのに、なぜ賈廉に「黄金の家に美女を隠す」よう勧めたのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
星堂伝第54章:曹州将軍は麒麟村に避難し、高山王は隠者の家で友人と会う
小説『大唐興隆』は『大隋唐』『大唐興隆全物語』とも呼ばれています。関連する古典小説には、清代乾隆年間...
『紅楼夢』で林黛玉が劉おばあちゃんを「イナゴの母」と呼んだのはどういう意味ですか?
劉おばあさんは『紅楼夢』に登場する他の多くの登場人物の中でも、極めて平凡な人物です。次回は、Inte...
『西遊記』で、祝八戒が食べ物を乞うことに失敗したのは本当に怠け者だったからでしょうか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
清明節の気候の特徴:長江南部は曇りと晴れ、雨が多い
『七十二候集』には「三月、この頃、万物は清らかで澄んでいる」とある。したがって、「清明」とは、気温が...