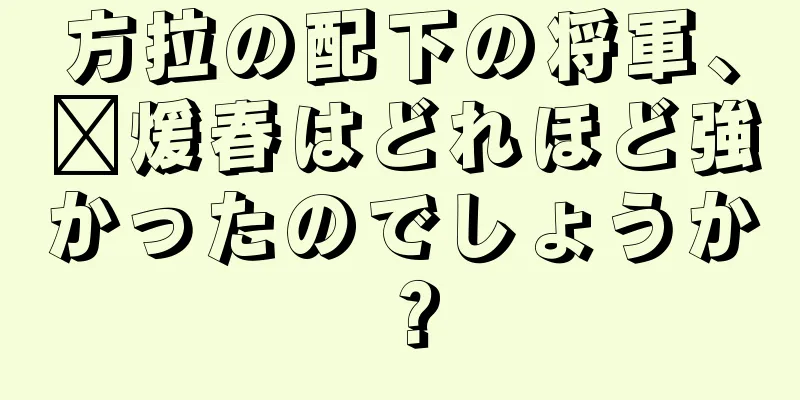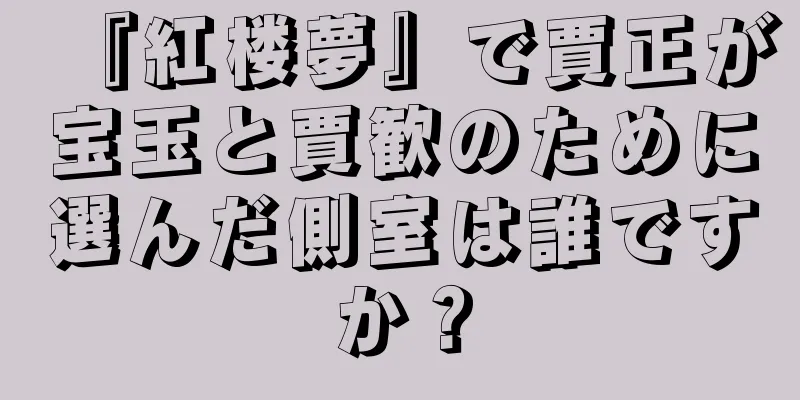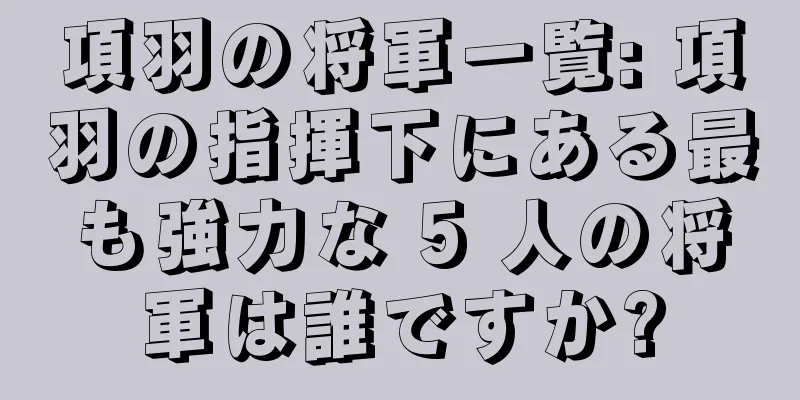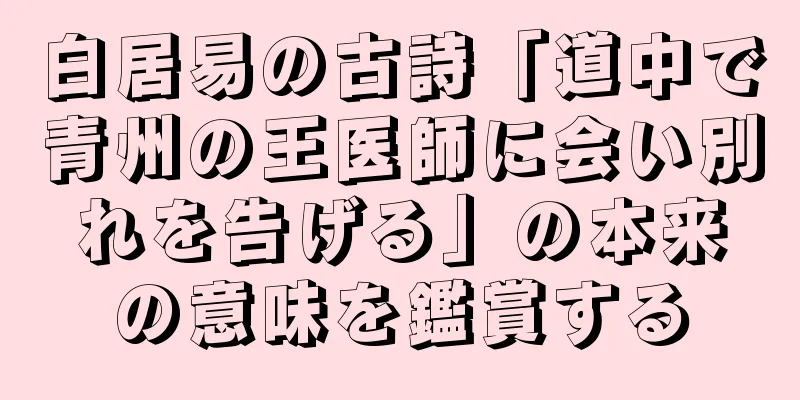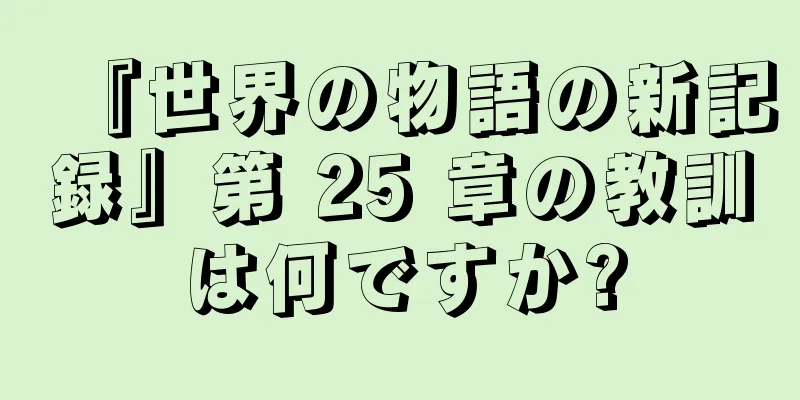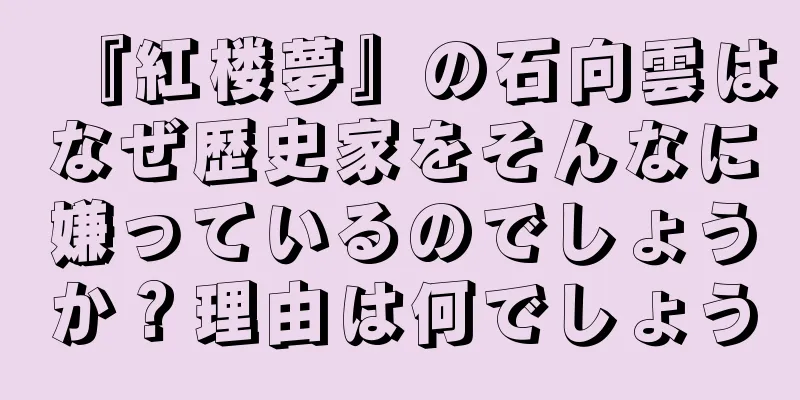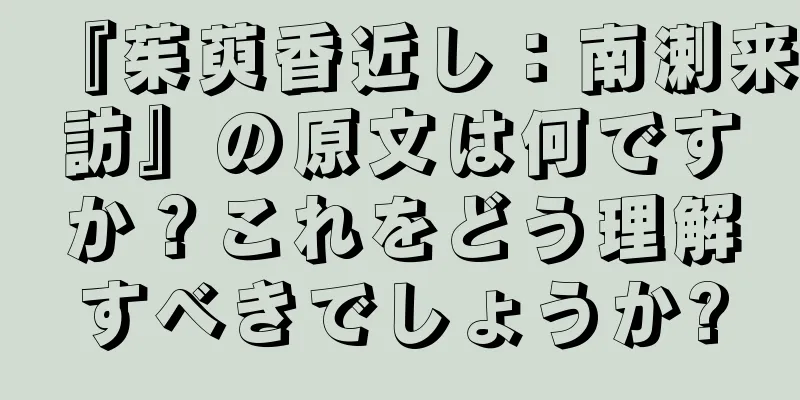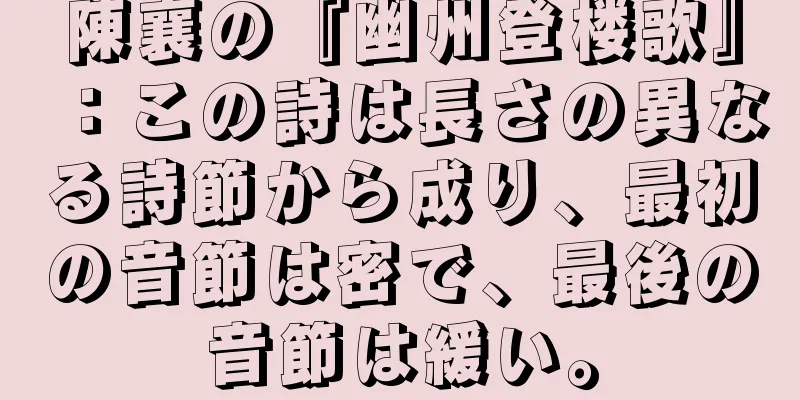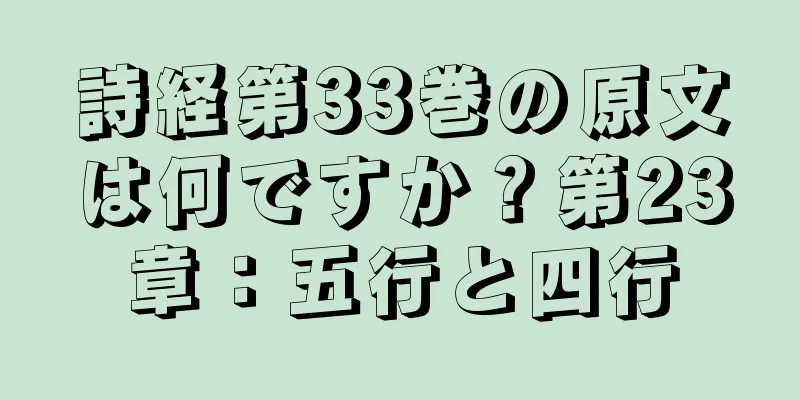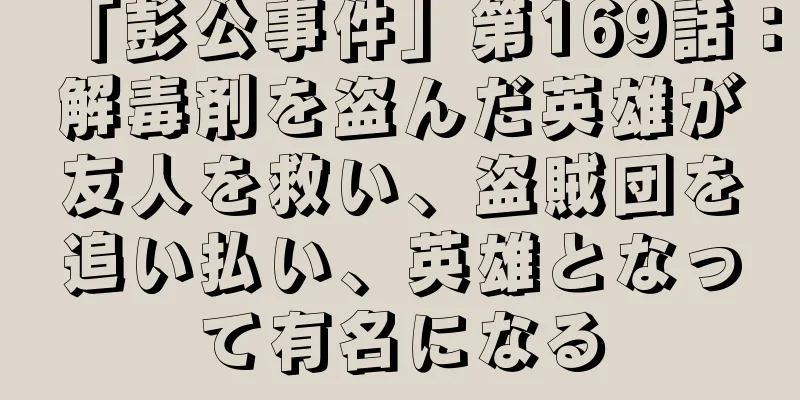明代において胡椒はどれほど貴重だったのでしょうか?なぜペッパーの価値はその後下落したのでしょうか?
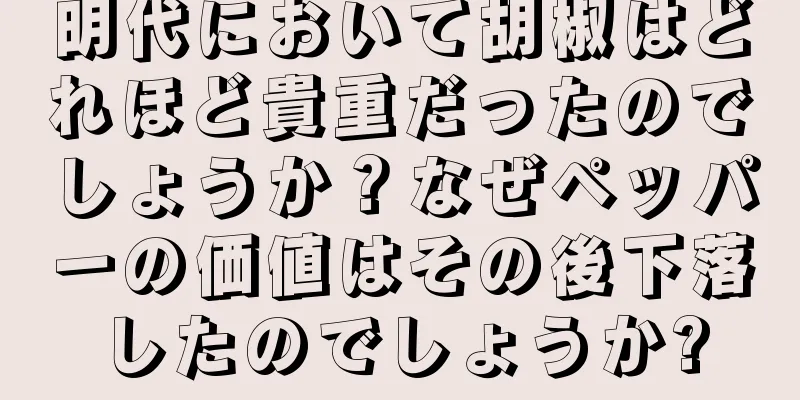
|
以下は、Interesting History編集部がお届けするコショウにまつわる物語です。ご興味がありましたら、ぜひお読みください。 コショウといえば、皆さんもよくご存知だと思います。これは現代の私たちの生活の中で非常に一般的な調味料です。コショウは輸入品です。漢の時代にはすでに、シルクロードを通って胡椒が我が国に伝わっていました。その後、明代の海上貿易の発展に伴い、わが国に輸入される胡椒の量も増加しました。 しかし、もともと私の国ではコショウは貴重な薬用物質やスパイスとしてみなされていました。役人や非常に高い地位にある人だけがコショウを所有し、使用することができました。しかし、だんだんと胡椒の価値は下がっていき、今では胡椒は誰にとっても日常的な調味料となっています。なぜこんなことが起こったのでしょうか? コショウの導入とその二重の価値の発見 コショウは食用価値と薬用価値の両方を持つ食品です。輸入品である胡椒は中国に伝わってから香辛料と薬用として二重の役割を果たしてきました。 『後漢書』には「インドの国には香、岩蜜、胡椒がある」と記されている。これは、漢王朝時代にシルクロードが発達し、西域が開拓され南越が平定された際に胡椒が中国に導入されたことを示しています。しかし、鄭和が西洋へ航海するまで、コショウはスパイスとして広く使われることはありませんでした。 結局のところ、宋代や元代には、乳香や沈香などの「本物の」香辛料が依然として貿易の大部分を占めていた。さらに、宋代には、コショウは主に薬として使われていました。元代中期から後期にかけて、胡椒の実用価値は大きく高まりました。理由は簡単です。モンゴル人は肉をたくさん食べており、当時コショウは肉の保存料や調味料として広く使われていました。 高級外貨から一般的な家庭用品まで 中国に胡椒が伝わった後、胡椒は長い間贅沢品とされ、富裕層や権力者だけが所有していました。隋唐の時代には、宰相の袁載の家に800個の胡椒が置かれており、贅沢の象徴と考えられていました。宋代と元代には、胡椒は王族の食事の重要な要素となりました。しかし、高貴な地位の象徴であった胡椒は、明代になると格下げされ始めました。非常に重要な証拠として、元朝では胡椒が給料や報酬の支払いに使われていたことが挙げられます。 永楽12年に初めて胡椒が給料の補填に使われました。この後、胡椒は役人の給料の支払いに大規模に使われるようになりました。例えば、明代の成祖帝の治世中、都の文武官の給料は胡椒とウルシで支払われるよう命じられ、胡椒1ポンドは現金16束、ウルシ1ポンドは現金8束に相当した。 明朝では、胡椒は給料を減らすために使われただけでなく、将校や兵士への褒美としても使われていました。データによれば、20万人以上の北京の将校や兵士への褒賞として胡椒が使われていた。さらに、鄭和が西方へ航海するにつれて、胡椒は継続的に導入されました。胡椒は明朝の財政において重要な役割を果たした。一方、明朝が財政危機に陥ったとき、胡椒は給与補助として財政的緊張をある程度緩和しました。 しかし、当時は、コショウを給与削減に使うにしても、報酬削減に使うにしても、価格はかなり恣意的に設定されており、割引額が市場の状況に応じて調整されることはなかった。まさにこのため、市場に流通する胡椒の価値にはある程度の混乱が生じ、胡椒の地位が低下する土壌もできてしまったのです。 なぜコショウの価値は下がったのでしょうか? まず、社会の発展の傾向から見ると、銀の台頭と発展に伴い、通貨の代替品であるコショウが歴史の舞台から消滅するのは必然です。宝貨幣の劣化と銀の貨幣化に伴い、コショウの硬貨としての性格も薄れつつあります。 さらに、コショウの降格は、給与や報酬を削減するためのコショウの使用と密接に関係しています。朝廷が給料を減らすためにコショウを使用したとき、コショウの本来の高貴な性質も変化しました。コショウの薬効は以前から発見されていました。しかし、輸入品であったため、コショウは依然として上流階級だけのものでした。しかし、コショウが給料と引き換えに外貨として使われていた頃は、役人はそれを市場に持ち込んで取引したり、物々交換したりすることができた。また、このため、胡椒は王室から宦官の家に流れ、最終的には一般の人々の手に渡ったのです。 結局のところ、コショウが最初に導入されたとき、それは希少な商品であり、希少性は物を価値あるものにしますが、高貴な品物が広く流通すると、その価値は下がります。コショウが市場に流通するにつれて、個人間の取引も頻繁に行われるようになりました。成化・洪治の時代になると、胡椒は市場で非常に一般的になり、その価値は自然に低下しました。 |
>>: 中国ではお茶の歴史は長いですが、功夫茶はどのように淹れればよいのでしょうか?
推薦する
古梁邇が著した『春秋実録古梁伝』には、閔公元年に何が記されているか?
古梁邇の『春秋実録古梁伝』には、閔公元年に何が記されているのでしょうか?これは多くの読者が関心を持っ...
『紅楼夢』に登場するメイドの中で、自分を変えるために努力してきたのは誰ですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立ての長編小説で、中国古典四大傑作の第一に数えられています。今日は、おもし...
諸葛亮はなぜ魏延を倒す計画を立てていたとき、将軍馬岱を選んだのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
古代人はなぜ葬儀中に長男に「土鍋を壊す」ことを許したのでしょうか?長男に「土鍋を割らせる」風習の起源
葬送文化では、亡くなった先祖を埋葬する際に長男が土器を割ることが定められています。これにはどのような...
北涼の聚屈孟勲には何人の子供がいましたか?聚屈孟勲の子供は誰でしたか?
聚曲孟勲(366-433)は、臨松緑水(現在の甘粛省張掖市)出身の匈奴民族の一員であった。十六国時代...
目録: 秦の始皇帝と漢の武帝に関する詩
秦の始皇帝と漢の武帝について書かれた詩を知っていますか?いくつ読んだことがありますか?興味のある読者...
『霜の空と暁の角笛:儀徴河の夜の停泊』の執筆背景は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】漢江で一泊。長く口笛を吹く川の歌。水中の魚や龍は驚き、風が地面を吹き飛ばし、波が家々を...
段延卿ってどんな人ですか?段燕青を評価する方法
「邪悪に満ちている」段延卿は、四人の悪人のリーダーです。彼は最も邪悪で、最も残酷で、冷酷ですが、最も...
劉雲の「七夕に針に糸を通す」:この詩の人物描写は極めて繊細である
劉雲(465-517)、号は文昌、河東省斌県(現在の山西省運城市)の出身。南梁の大臣、学者であり、南...
聖パウロはキリスト教にどのような貢献をしましたか?彼はローマの暴君によって斬首されたのですか?
『聖パウロ』の序文に登場する聖パウロは、非常に特異な経験をした非常に特異な人物であり、キリスト教の信...
岳飛伝説第54章:秦檜は権力を乱用したために降格され、皇帝の使節である唐淮は自殺させられた。
『岳飛全伝』は清代に銭才が編纂し、金鋒が改訂した長編英雄伝小説である。最も古い刊行版は『岳飛全伝』の...
「女仙の非公式歴史」第49章:鄭衡は最初の戦いに敗れ、景龍は最後に称号を授与された。
『女仙秘史』は、清代に陸雄が書いた中国語の長編歴史小説です。『石魂』や『明代女仙史』とも呼ばれていま...
北宋時代の軍事書『武経宗要』全文:第二巻、第20巻
『武経宗瑶』は北宋の政府が編纂した軍事書である。著者は宋の仁宗の治世中の文官、曾公良と丁度である。二...
三国志の正史において、本当の最高将軍は誰でしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』の賈宝玉は結局乞食になったのでしょうか?彼の結末はどうなったのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...