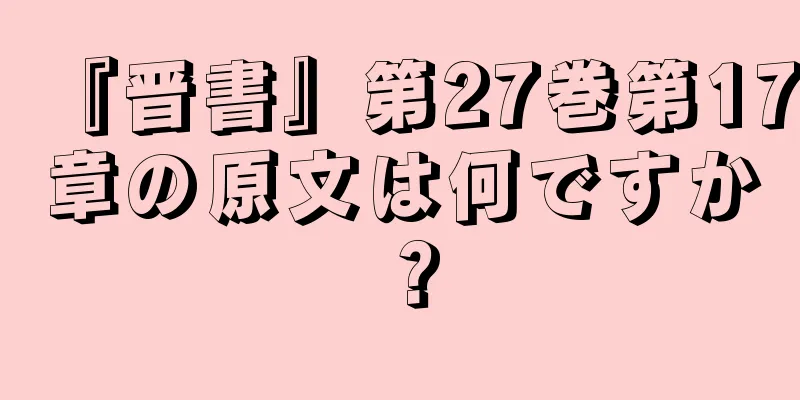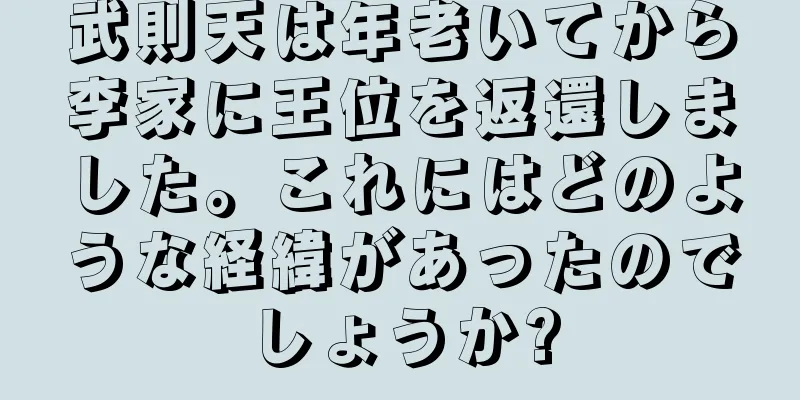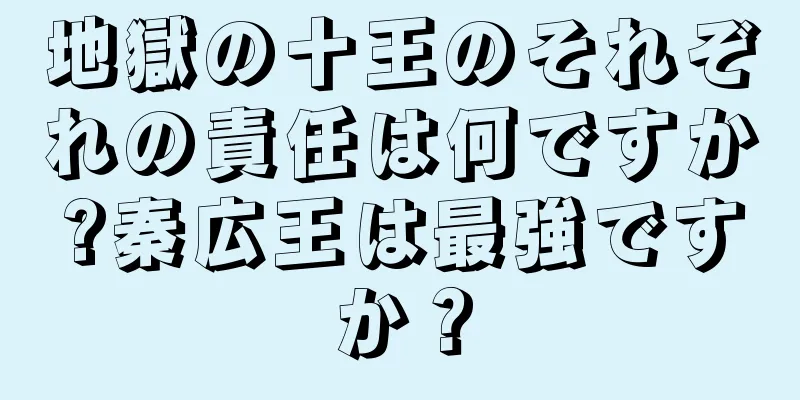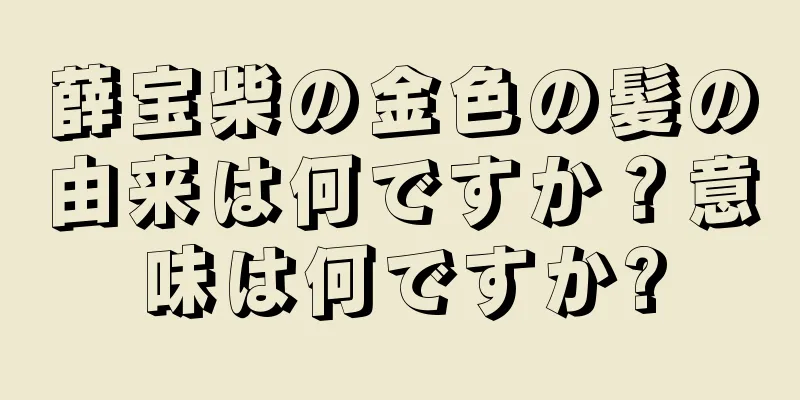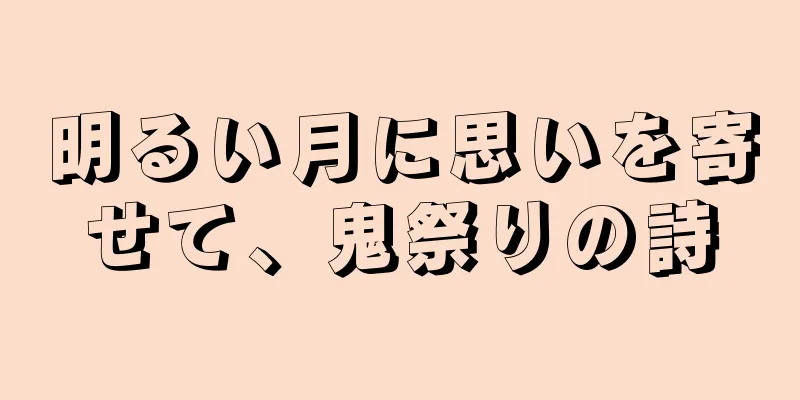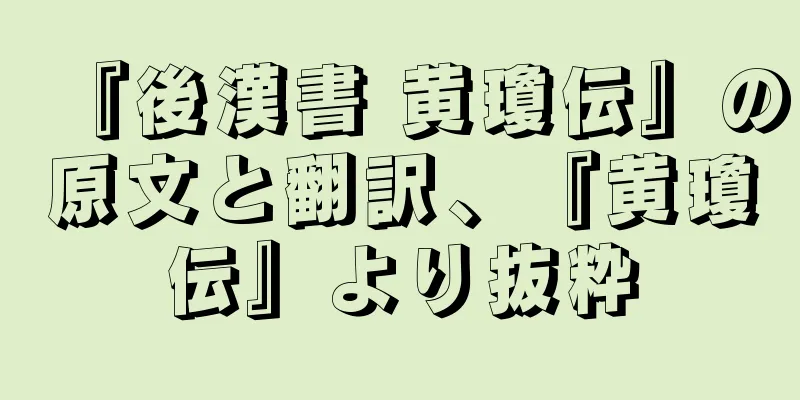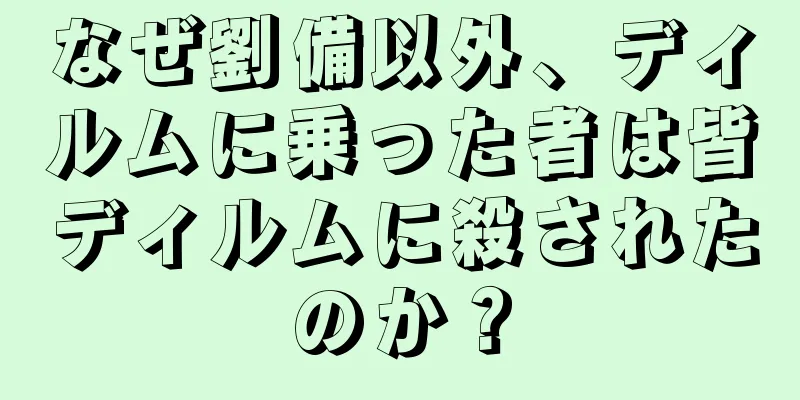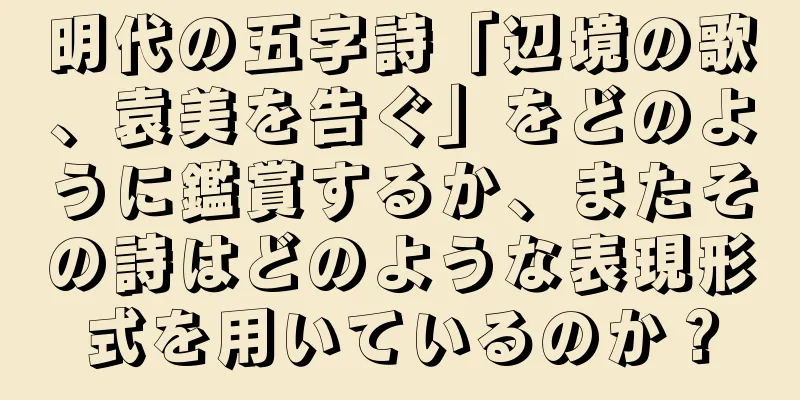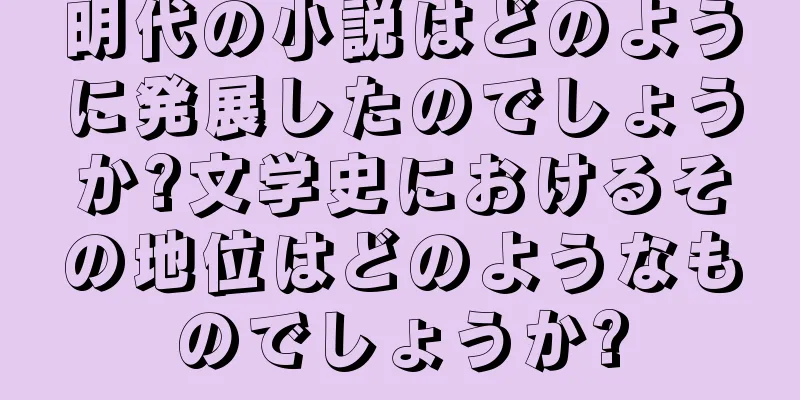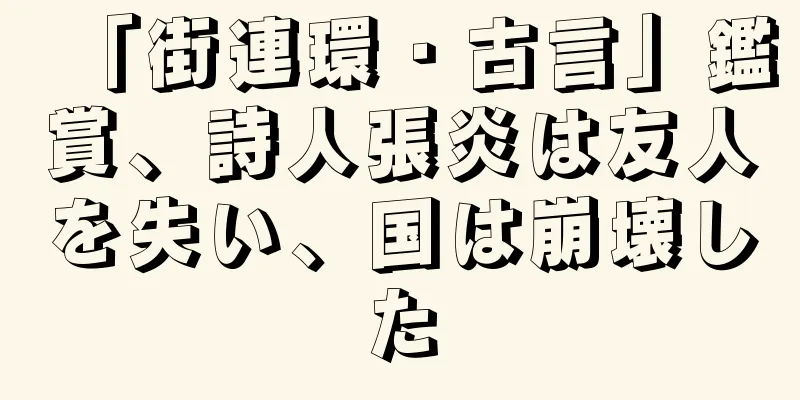永斉は烏蘭羅皇后の子として生まれたのに、なぜ母親のせいで乾隆帝に無視されたのでしょうか?
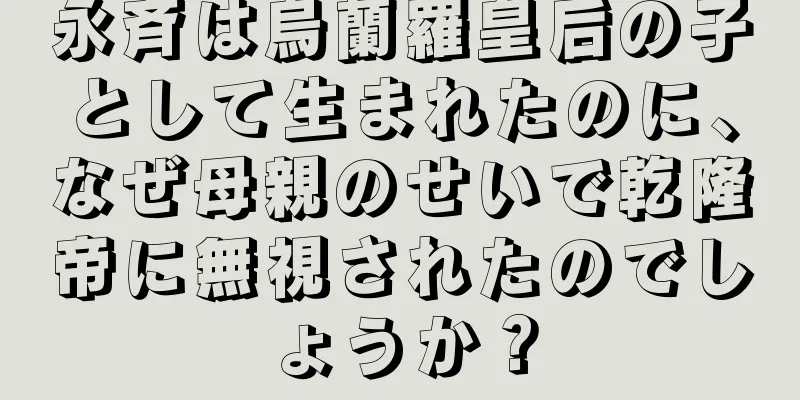
|
乾隆帝には17人の息子がいたが、そのほとんどが悲劇的な結末を迎えた。その中で最も無実の王子は、乾隆帝の12番目の息子である永斉であった。乾隆帝はかつて、次男の永廉、七男の永聡、五男の永斉、十二男の永基、十五男の永厳の五人の王子を皇太子にしようと考えていた。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 乾隆帝の最初の子は、彼に死ぬほど怖がらせられました。2番目の息子である永連と7番目の息子である永聡は、どちらも乾隆帝の皇后である扶揺の子として生まれました。この2人の王子は、最も強力な王位継承者でした。 ところが、次男の永廉が9歳のとき、風邪をひいてしまいました。昔は医療技術が発達していなかったため、永廉はすぐに風邪で亡くなりました。 七番目の息子である永聡も、2歳にもならないうちに病気で亡くなりました。三男も乾隆帝に脅されて死ぬことになり、四男は他の一族に養子として引き取られたため、五男の永斉が乾隆帝の期待の次世代王子となった。 五男の永斉ももちろん野心家で、幼いころから読書家で、乗馬や射撃が得意でした。書道も十一男の永厳と並んで有名でした。 1763年、雍斉は乾隆帝とともに頤和園の九州青岩殿を訪れていたが、九州青岩殿で突然火災が発生した。わずか22歳の雍斉は乾隆帝を背負って火事から逃れた。 しかし、雍斉が和朔容王の位を授かったとき、彼はすでに骨潰瘍を発症していた。乾隆帝は、五男の永斉に加え、十二男の永基も皇太子にふさわしい人物とみなした。 12番目の息子である永基は、乾隆帝の2番目の皇后である烏蘭羅の嫡子であり、永斉より11歳年下であった。 乾隆帝の治世30年、雍斉が和碩容王に叙せられたとき、12番目の息子である雍斉の母である烏蘭羅皇后が乾隆帝の南巡に同行した。 南巡が始まったばかりの頃、皇帝と皇后の関係はまだ非常に良好で、乾隆帝は烏蘭羅の48歳の誕生日を祝ったほどだった。しかし、2月18日、烏蘭羅は晩餐会に現れず、乾隆帝は同日、烏蘭羅を船で都へ送り返すよう命じた。 その後、ウラナラは一時失脚し、イクン宮殿の奥殿に幽閉されたが、これは王妃の地位を剥奪されたに等しいものであった。 乾隆帝自身が後に、烏蘭羅が髪を切ったことが非常に無礼で親不孝だったためだと説明した。もちろん、部外者はこれが本当に理由かどうかは知らない。しかし、烏蘭羅の12番目の息子である永斉は、母親の寵愛が薄れたため、乾隆帝の目のとげとなった。永斉もまた、乾隆帝の無視により、非常に寡黙になり、ほとんど話さなくなった。 乾隆31年、5番目の息子である永斉が骨癌で亡くなり、もう1人の後継者候補も亡くなった。宮廷の大臣たちは皆、皇帝に手紙を書き、王妃の嫡子である12番目の息子である永吉に爵位を与えるよう要請した。しかし、乾隆は12番目の息子の母親のせいで、依然として同意しなかった。 雍斉は乾隆帝の寵愛を失った後、口数が少なくなり、外出もほとんどしなくなった。彼は20歳のとき、「皇室編纂満蒙文学集」の編纂を志願し、完成までに4年を要した。 つまり、『勅撰満蒙文書』が完成してから1年後に永斉は病死したが、乾隆帝は永斉にいかなる爵位も授けず、皇族として直接埋葬したのである。 母の寵愛が薄れたために疎んじられていたこの嫡子は、一度も過ちを犯さず、結局爵位も与えられず、貧困に陥った。まさに最も純粋な王子と言えるだろう。 |
<<: 玄武門の変の際、李建成は李世民に対処するために軍隊を動員する権利を持っていましたか?
>>: 長孫皇后の他に、後宮で李世民に寵愛された側室は誰ですか?
推薦する
なぜ曹操は白門楼にいた時に劉備に呂布の生死について意見を求めたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
劉宇とは誰ですか?劉宇はどうやって死んだのですか?
劉游(? - 西暦193年10月)、別名は伯安。彼は東海市潭(現在の山東省潭城市)の出身であった。漢...
明代末期の裏切り者、洪承晩の紹介。洪承晩はどのようにして死んだのか?
洪承周(1593-1665)、号は延延、号は衡九、福建省泉州市南安県英都(現在の英都鎮下梅涼山村)の...
詩空書の「残魯琴卿」:この詩は新しい独特のスタイルで書かれている
司空書(720-790)、号文初(『唐人伝』では文明と表記、ここでは『新唐書』による)、広平(現在の...
『紅楼夢』では、林黛玉は西仁と青文のどちらが好きですか?
周知のように、『紅楼夢』の賈宝玉は8人の侍女に囲まれており、その中で最も特別なのは希仁と青文である。...
三英雄五勇士第21章:首を投げて悪人を驚かせ、悪学者の沈千波を排除する
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
『西遊記』で孫悟空が仏陀になった後、霊鷲菩薩はなぜ祝賀宴に出席しなかったのですか?
<『西遊記』の孫悟空が勝利の仏になった後、如来は霊山で祝宴を催しただけでなく、霊山の位階も更新...
なぜ賈宝玉は夜中に華希人への真っ赤なハンカチを交換したのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
『紅楼夢』の丹春はどのようにして大観園の捜索について知ったのでしょうか?
以下は『紅楼夢』の丹春が大観園の捜索をどのようにして知ったのかを『面白歴史』編集者がレポートしたもの...
古代皇帝の龍のローブはどのようなものだったのでしょうか?ドラゴンローブにはどんな秘密が隠されているのでしょうか?
古代皇帝の龍のローブにどんな秘密が隠されているかご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。Intere...
劉晨翁の『永楽・碧月月情』:著者は自身の悲しみと他人の喜びを描写する
劉晨翁(1232-1297)、雅号は慧夢、号は許熙としても知られる。彼はまた、徐喜居士、徐喜農、小娜...
歴史上、一度もセックスをしたことのない女王は誰ですか?
古代の歴史において、女性は常に宮廷闘争の犠牲者となってきた。彼女たちは政治的な目的で結婚から逃れるこ...
古代のカップルはなぜ新婚の部屋に入った後に盗み聞きされたのでしょうか?
新築祝いも結婚式場見学も、どちらも我が国の伝統的な結婚式の風習であり、場所が違っても似ています。花嫁...
明治維新の先駆者、高杉晋作の簡単な紹介 高杉晋作はどのようにして亡くなったのでしょうか?
高杉晋作は、江戸時代後期の有名な政治家、軍事戦略家でした。長州尊皇派の指導者の一人であり、奇兵隊の創...
「ウズラの鳴き声」の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
ヤマウズラの匂いを嗅ぐ有統(清朝)ウズラの鳴き声とともに西に日が沈み、道中の兵士たちは皆頭を下げた。...