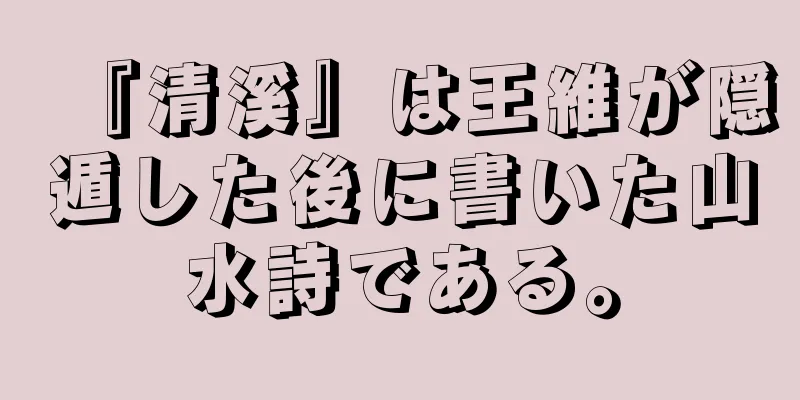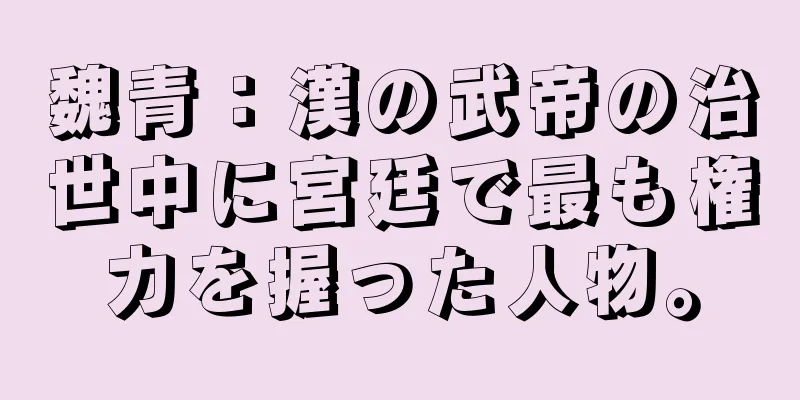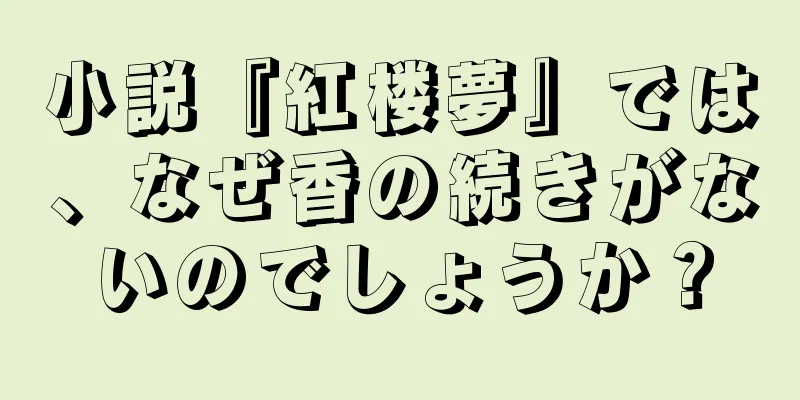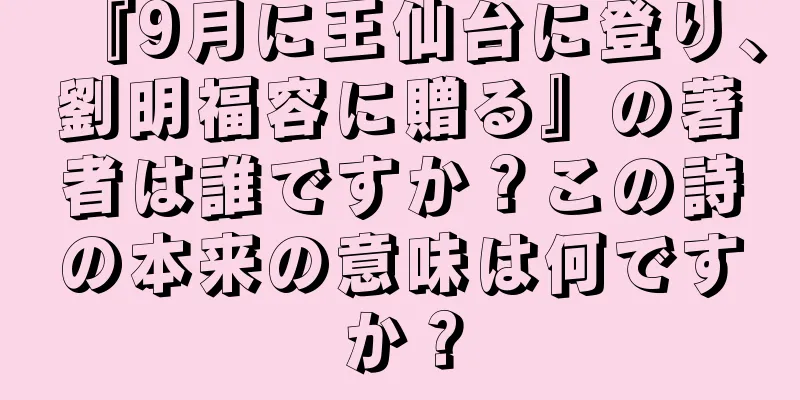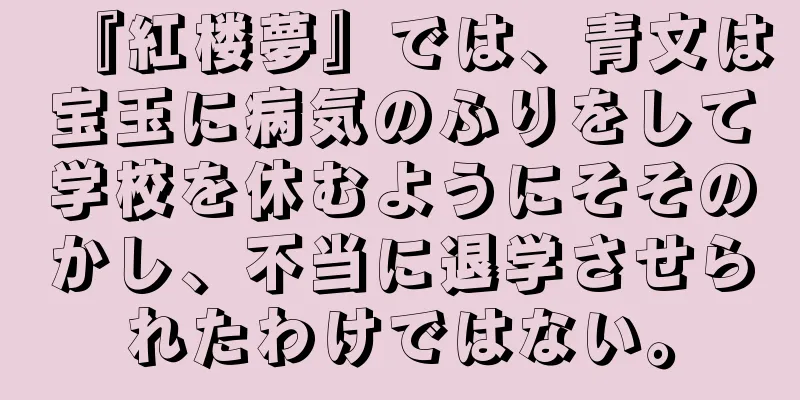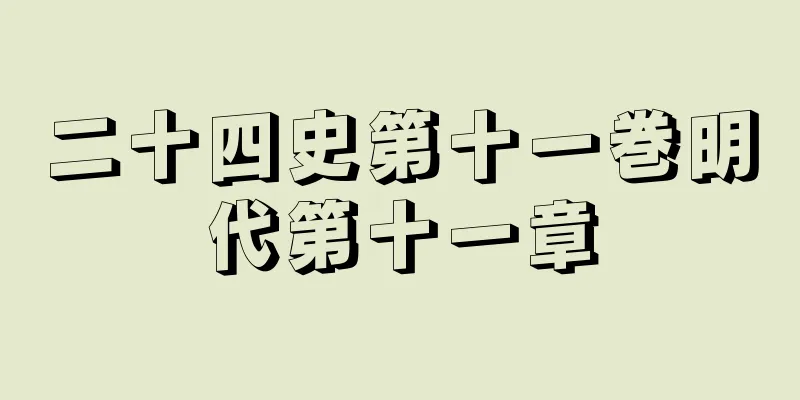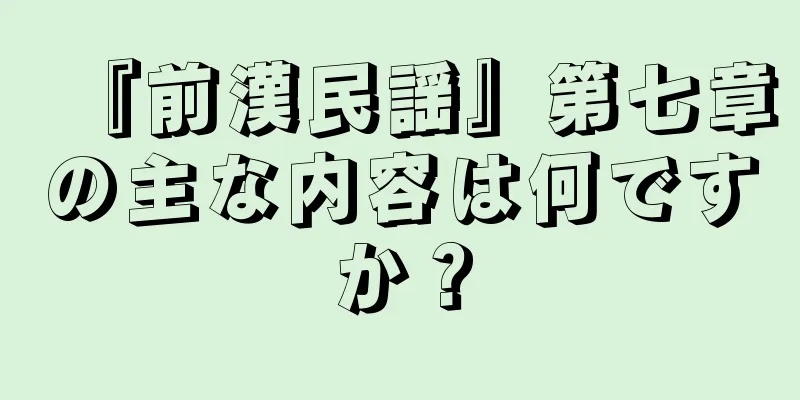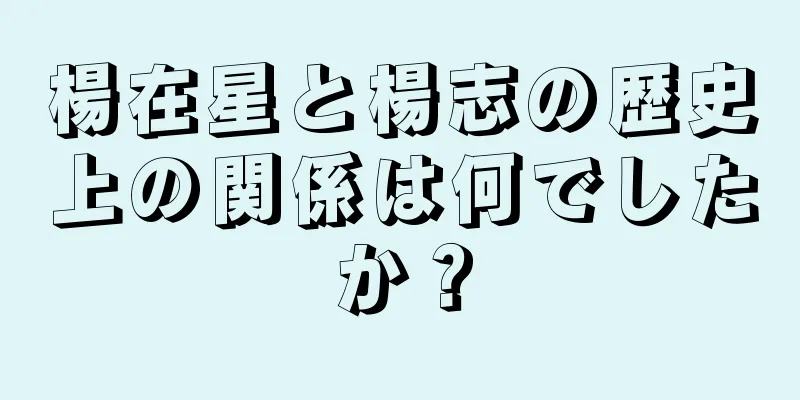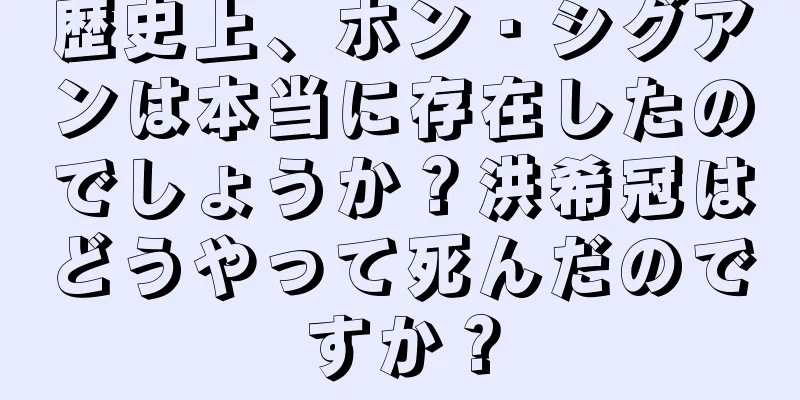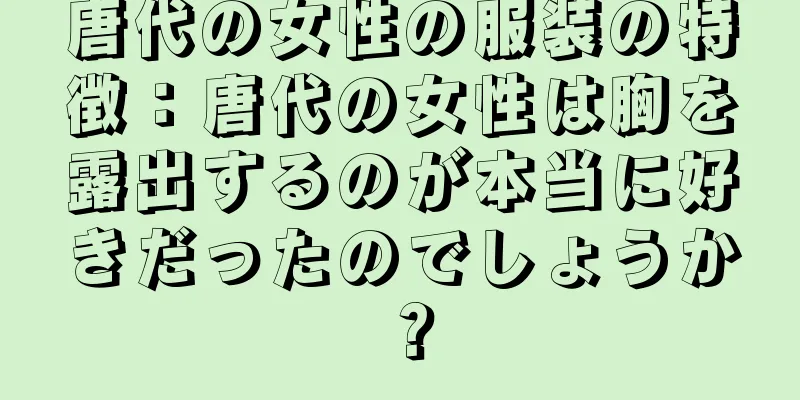一部の時代劇では、宮殿に氷が出てくるのは普通のことでしょうか?
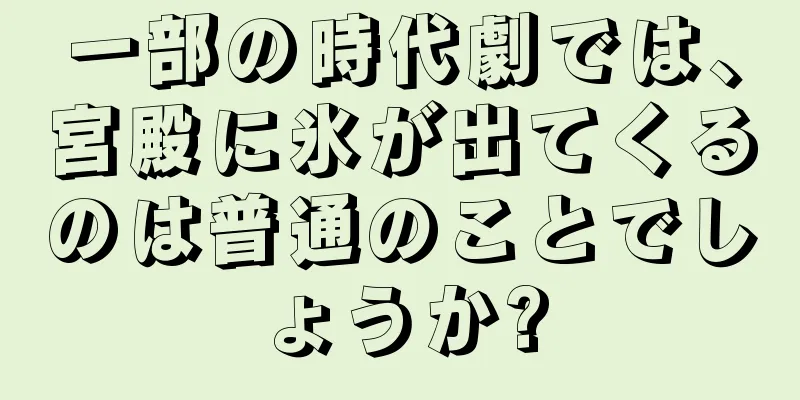
|
暑い夏が近づき、エアコンや冷蔵庫は夏の必需品となってきました。エアコンを楽しみながらアイスクリームを食べているとき、昔の人はどうやって夏を涼しくしていたのだろうと考えたことはありませんか? あるいは時代劇を見ていると、宮殿に氷が置かれているのを見て驚きますか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう! 実際、周の時代にはすでに氷の貯蔵に関する記録が残されている。『詩経』には「二日目に氷を切り洗い、三日目に天陰に氷を貯蔵する」とある。 寒い冬の間は、氷を削り出して涼しい場所に保管します。この方法はどの王朝でも使われ、夏に氷を取り除いて使用しやすくするために特別な氷除去機構が設けられました。 冬には、凍った湖から氷が削り出され、特別な氷室に保管され、夏まで溶けません。 皆さんも「真歓伝」などの時代劇で見たことがあると思いますが、毎年夏になると、各宮殿に涼を取るためにたくさんの氷が置かれます。同時に、氷を入れるための特別な容器「アイスコンテナ」も登場します。中に氷を入れることで、容器内の冷気が発散し、冷却や暑さの緩和に役立ちます。 もちろん、氷を保管するだけでなく、氷を作ることもできます。繁栄していた唐の時代に、人々は硝石を開発しました。硝石を一定期間水に入れて冷やし、凍らせることができるため、冬に氷を保存するよりもはるかに便利でした。しかし、古代人の知恵は無限です。これら以外にも、私たちが知らない涼をとる方法がたくさんあるはずです。そうでなければ、暑い夏をどうやって乗り越えればいいのでしょうか。 |
<<: 古代の人々は敵との戦争を始める前にどんな言い訳をしたでしょうか?
>>: 古代では反乱は重大な犯罪であったのに、将軍が反乱を起こしたときに抵抗する兵士が少なかったのはなぜでしょうか。
推薦する
なぜ水景氏は諸葛亮を隠遁から解放したが、「正しい師匠は見つかったが、正しい時が来なかった」と言ったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
明代の有名な儒学者、唐順治の有名な著作は何ですか?
『唐順治の毛路門知事への返答』は、明代の非常に有名な散文です。唐順治の『荊川氏全集』第7巻に収められ...
中国語の「gong」という4つの文字はどのように発音しますか? 幽陽の「天書」は長年未解決のまま
4つの「工」は何という字でしょうか?5つの「口」は何と発音するのでしょうか?「口」の真ん中にある「乌...
「春夜洛城の笛を聞く」は李白が洛陽を旅したときに書かれたものですが、具体的な内容は何ですか?
「誰の玉笛が暗闇の中で鳴り響き、春風に吹かれて洛陽城中に広がる。夕方に柳が折れる歌を聞き、故郷を思い...
雲霄仙人の結末は?彼女はどうやって死んだのですか?
神を授けるのは道の災難!災難という言葉には、感動的な物語がたくさん含まれています。冊封では、天の朝廷...
「放浪子の歌」は孟嬌によって書かれたもので、平凡でありながら偉大な母の愛を讃える詩です。
孟嬌(751-814)、号は東業、湖州武康(洛陽とも言う)の出身で、唐代の有名な詩人である。孟嬌は詩...
『紅楼夢』で黛玉はなぜ賈屋敷に戻ったのですか?真実とは何でしょうか?
『紅楼夢』のヒロインである黛玉は、『金陵十二美女』本編に登場する二人の美女のうちの一人です。興味のあ...
元代の胡思惟著『飲食要項』全文:第1巻:乳母の食事禁忌
『陰氏正瑶』は、元代に胡思惟によって書かれ、元代天暦3年(1330年)に完成しました。全3巻から構成...
狄仁判事第60章:四方八方から軍隊が派遣され、フェイ・シオンは罠にかかり、二人の将軍が死亡し、馬容が陣営に戻る
『狄公安』は、『武則天四奇』、『狄良公全伝』とも呼ばれ、清代末期の長編探偵小説である。作者名は不明で...
なぜインドの王女は寺院で愚かなふりをしたのでしょうか?理由は何でしょう
また、経典を手に入れるための旅全体において、この時点で玉皇大帝が最終的な受益者であることもわかります...
なぜ文殊菩薩は十二金仙の一人なのでしょうか? 『神々の叙任』における彼はどのようなイメージを持っているのでしょうか?
十二仙人とは、明代の幻想小説『封神演義』に登場する十二人の仙人で、禅宗玉虚宮の元師天尊の十二人の弟子...
「風が止んで花は深く散る」という詩は、自然に過ぎ去る春の悲しみをどのように表現しているのでしょうか。
李清昭の『風が止まり花が深く散る』は、春の悲しみをどのように自然に表現しているのでしょうか。これは、...
韓小英とは誰か——郭靖の最も美しい師匠
韓小英とは誰ですか?多くの人はすぐには思い出せないかもしれませんが、よく考えてみると、韓小英は偉大な...
首都の戦いはどの歴史時代に起こりましたか?
京城の戦いは、北京の戦い、北京の戦い、明の京城の戦い、明の京城防衛の戦いとも呼ばれ、明の正統14年(...
三国志演義には才能と勇敢さにあふれた男たちが数多く登場します。五虎将軍を倒せるのは誰でしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...