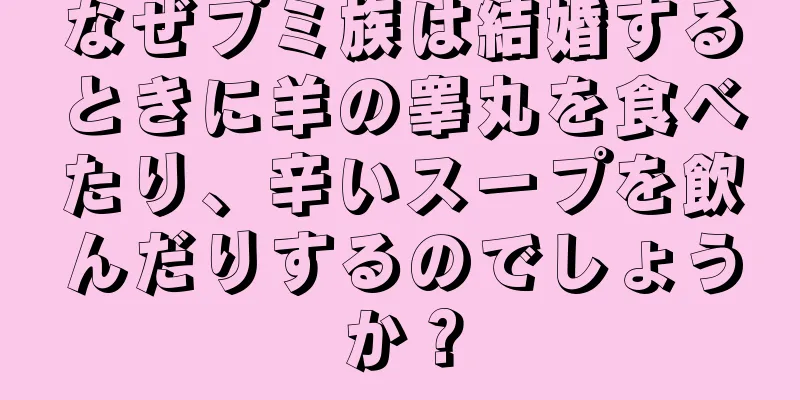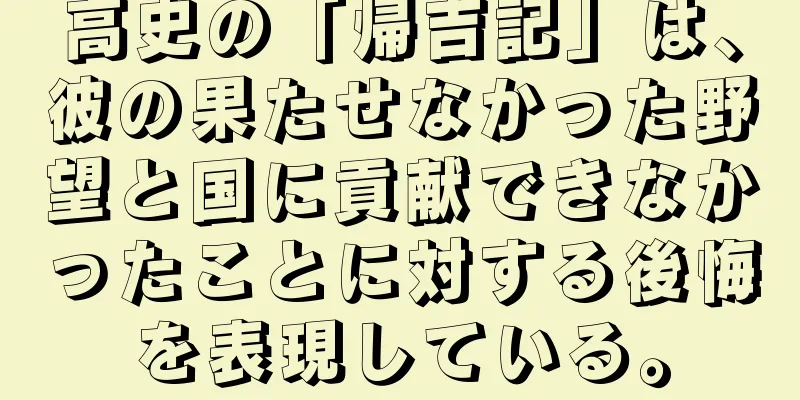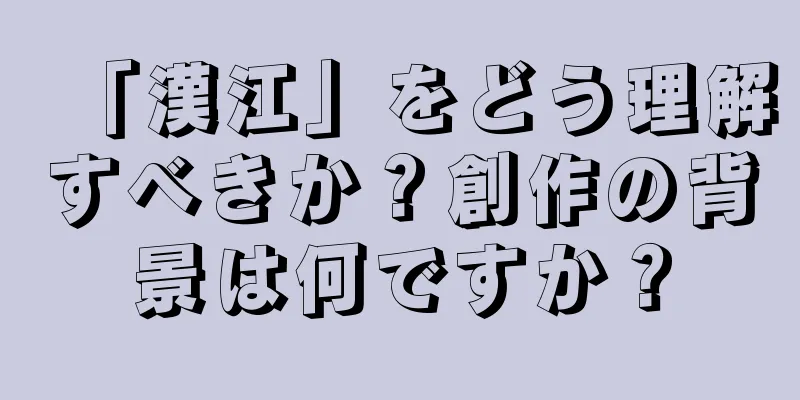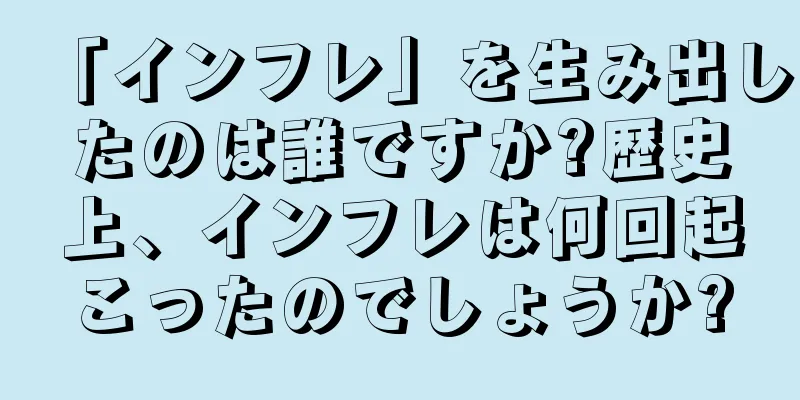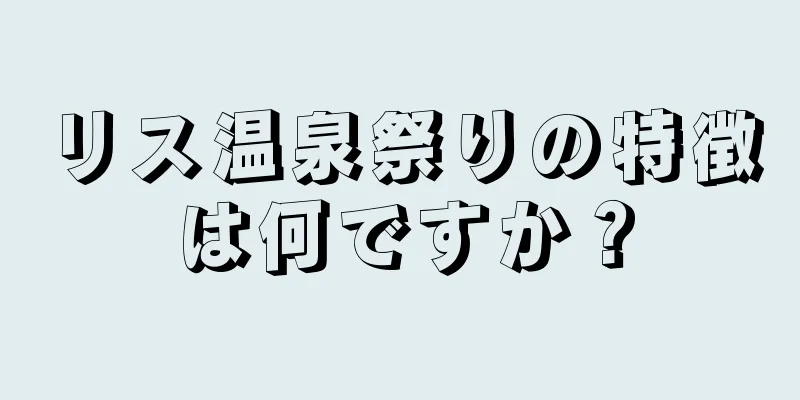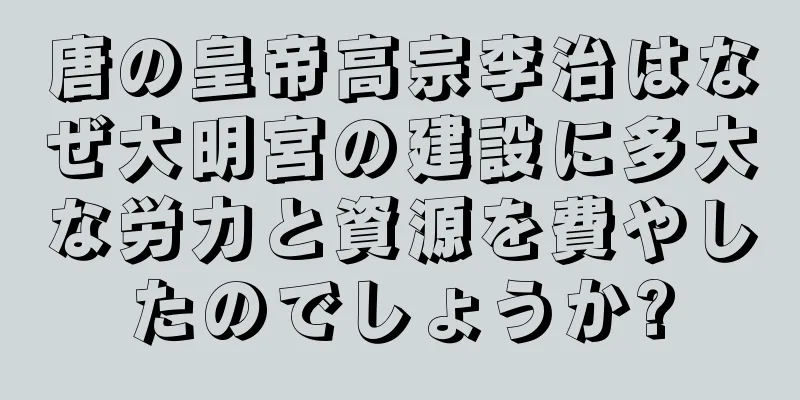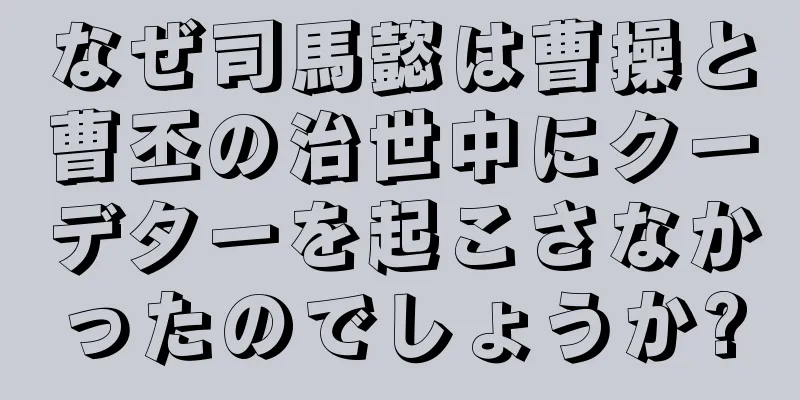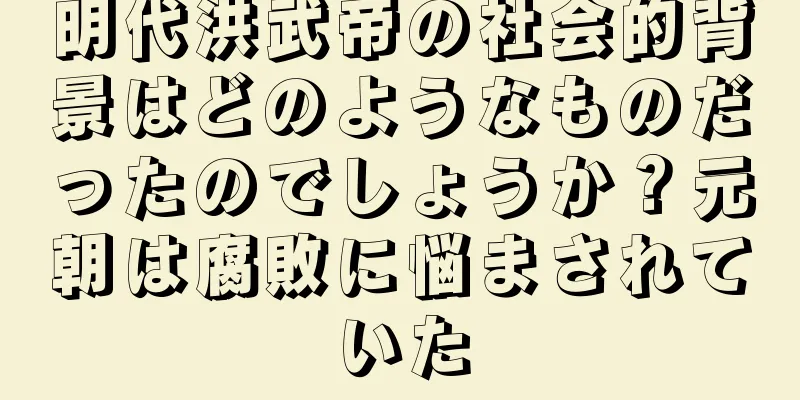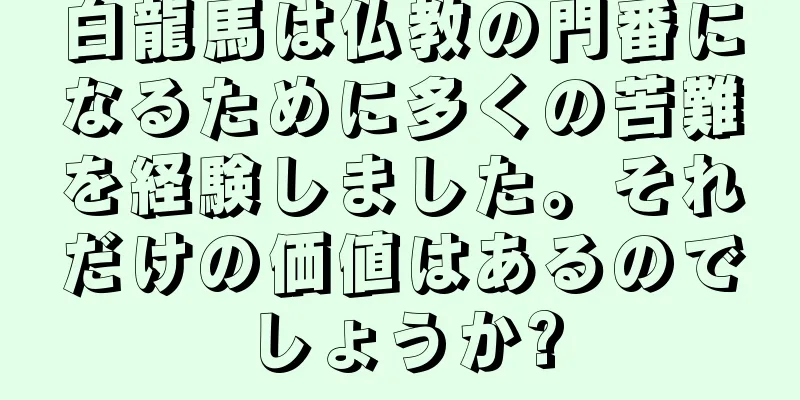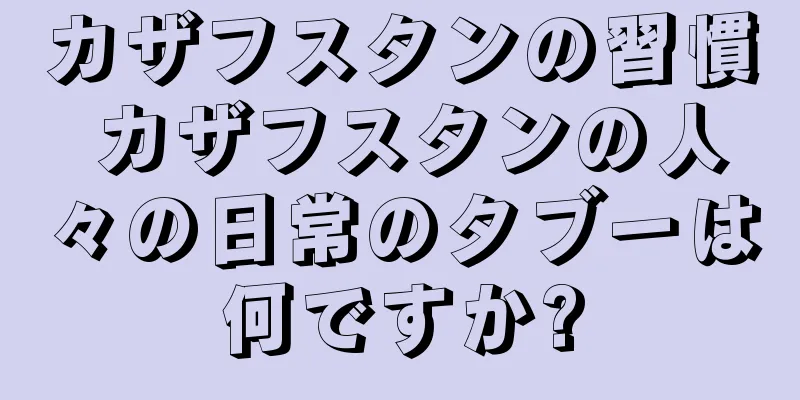三国時代における仏教の発展過程はどのようなものだったのでしょうか?
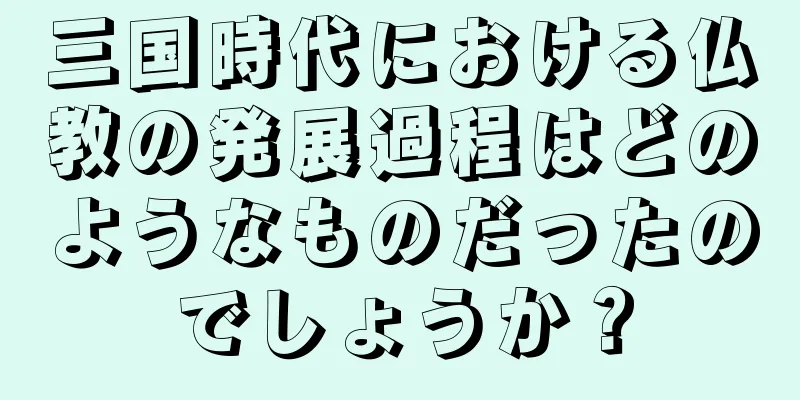
|
三国仏教には、西暦 220 年から 265 年までの魏、呉、蜀の時代の仏教が含まれます。では、この時期の仏教の発展過程はどのようなものだったのでしょうか。今日は、Interesting History の編集者が関連コンテンツをお届けします。興味のある方はぜひご覧ください。 そのうち、魏は後漢を継承し、洛陽に都を置きました。その文化はすべて後漢の遺産を受け継いでおり、魏の仏教は後漢の仏教の延長であると言えます。 この時期には、譚克我洛、譚迪、康生楷などインド、パルティア、康州などの国の僧侶が次々と洛陽に来て、経典の翻訳に従事した。魏の明帝(227-239年)はかつて仏教を大規模に推進しました(『魏書 仏道記』参照)。陳思王曹植も仏典を読むことを好み、仏教の聖歌を作曲しました。呉は揚子江の南を占領し、建業に首都を置いた。仏教は中原から中国に伝わりました。当時、智謙、康僧慧らが次々と呉に入った。 孫権は智謙に経文の奥義を尋ね、智謙を医者に任命し、魏昭らとともに皇太子の家庭教師をするよう命じた(『大蔵経』第13巻参照)。康僧慧は遺物を手に入れようと思い立ち、孫権に遺物のための寺院と塔を建てるよう依頼し、その寺院と塔は建初寺と名付けられました。尚書霊官則は孫権の問いに答えて「三つの宗教を比較し、仏教を推進せよ」と言った(『光洪明甫』第1巻『武書』より引用)。その後、孫権の孫である孫昊が即位し、仏教寺院を破壊し、仏像を冒涜しようとしましたが、康僧慧の説法に心を動かされ、ついに五戒を授かりました。 蜀は西方の奥地に位置している。古い記録によると、蜀には『首楞厳経』二巻と『普光経』(『大蔵経』第二巻)二巻があり、仏教にも伝わったようである。しかし、蜀で流布していたこの二つの経典は、はるか昔に失われ、内容も記録されていない。そのため、各王朝の経典には、魏と呉の記録しかなく、蜀の記録はない。 戒律の導入は三国時代の仏教における大きな出来事でした。魏の領土では当初仏教が普及していたものの、僧侶たちは髪を切るだけで戒律は受けず、断食や供養の儀式はすべて伝統的な祖先崇拝に基づいていた。 魏の肥帝の嘉平二年(250年)、中印の仏教学者である僧侶譚克嘉洛(法時の意味)が洛陽に旅し、すべての行いは仏陀に従うべきだと説きました。その結果、洛陽の僧侶たちは共同で戒律の翻訳を要請しました。カラは戒律が複雑すぎて一般大衆に受け入れられないのではないかと恐れ、大サンギカの戒律をまとめた『僧伽戒心』を翻訳し、地元のブラフマー僧侶を招いて戒律の業を行って戒律を伝えた。 これが中国における戒律と戒律の実践の始まりであり、後世の人々はカラを律宗の創始者とみなした。当時、パルティア王国の僧侶で、律学にも長けた譚迪(法師ともいう)がいた。魏の高貴公元年(255年)、洛陽に来て、白馬寺で『譚武徳業』を翻訳した。この本はその後ずっと中国で人気を博している。それは、もともと法界宗派の広範な律蔵、すなわち「四部律蔵」に由来し、後に中国の律蔵宗派は、それと関連のある「四部律蔵」のみを尊重するようになったからです。当時、この業に従って得度し始めた者には朱世興らがいた。世興は一般に中国における仏教僧の始まりとされている。 魏代の翻訳者には譚克峨と譚迪のほか、嘉平末期に洛陽に来て『烏峨長老問答』1巻と『無量寿経』2巻を含む4冊の著作を翻訳した康居僧侶の康僧楷がいた。 また、高貴公の時代の甘暦3年(258年)に、クチャの博厳という僧侶が洛陽に来て、『無量清平等覚経』2巻、『茶経』1巻、『菩薩行経』1巻、『除災経』1巻、『首乱迦牟尼経』2巻を含む7冊を翻訳した。また、魏の時代にはパルティアの僧侶である安法仙が『羅什経』3巻と『涅槃経』2巻を翻訳したが、翻訳時期は不明で、その著書は失われている。 呉代における仏典の翻訳は武昌で始まり、建業で盛んになりました。翻訳者は、毓済南、朱江(別名、洛厳)、志謙、康僧慧、志強良傑の 5 人でした。韋済南はインド出身の僧侶であった。孫権の黄武3年(224年)に、 彼はサンスクリット語版の『法句経』を武昌に持ち込み、そこで仲間の朱江岩と志謙がそれを二巻に翻訳し、後に改訂されて現在も残っている。黄龍2年(230年)、朱江岩は楊都(建業)で孫権のために『三昧経』と『仏意経』を各1巻ずつ翻訳した(現存)。そのうち『仏意経』は智謙と共同で翻訳した。智謙はこの時代の仏典の偉大な翻訳者でした。彼の先祖は月氏出身で、祖父の法度は後漢の霊帝(168-189)の治世中に生まれました。 彼は数百人の部下を率いて東へ渡り、帰化しました。そして、志謙が中国で生まれました。若年期は智晨の弟子智良に師事した。漢の献帝の晩年、混乱を避けるために武昌に逃れ、その後建業に赴いた。武帝の非帝の建興年間(252-253)まで仏典の翻訳に専念した。翻訳は大乗般若経、梵語経、大乗釈迦牟尼経など、大乗・小乗の経典・戒律を幅広くカバーしており、合計88巻と118巻に及び、現在、そのうち51巻と69巻が現存している(『開元世教録』による)。 第2巻)。重要な翻訳古典としては、『維摩経』全2巻、『大明経』全4巻、『太子霊験応縁経』全2巻などがある。後漢の智塵元は般若の教えを広め、魏晋時代に流行した『般若経』10巻と『衆乱禅定経』2巻(現在は失われている)を翻訳した。 志謙は志陳の思想体系を継承し、「道興」の翻訳を「明度」に変更しました。文体も長く難解なものから簡潔で流暢なものへと変化しました。完全に自由な翻訳が使用されており、これまで翻訳されたことのないマントラも例外ではありません(無量門秘真言経の8文字マントラなど)。彼はまた、経典注釈の最も古い作品である『本生死覚経』(『大蔵経』巻6、83)の独自の翻訳の注釈も書きました。 康僧慧の先祖は康州族で、何代にもわたってインドに住んでいました。彼の父親は商売のために交趾に移住しました。僧慧は10代の頃、僧侶になり、大蔵経を理解しました。赤武10年(247年)、建業に来て『六波羅蜜経』9巻(現存)と『五品経』(『般若経』5巻、現在は失われている)を翻訳した。 彼はまた、『無量寿経』、『法経』、『道書』という三つの経典に注釈を書き、それらすべてに序文を書いた。若年期、陳慧らから安世高の「安班」の教えを受け継ぎ、「安班序」では、心の乱れは六つの内外感情によって引き起こされ、それを治療するには「安班」、すなわち呼吸を数える、従う、止める、観察する、返す、浄化するを修行する必要があると論じた。これが僧伽の教義の要点です。 鄭無為は、武豊2年(255年)、梁武帝の治世中に膠州で『法華三昧経』(現在は失われている)の六巻を翻訳した。これが『法華経』の最初の翻訳である。また、古今東西の記録には魏・呉時代のものとされる失われた経典の翻訳が87冊ある(『開元録』第2巻)。 この時期、中国から来た僧侶、朱世行が法を求めて西方へと旅を始めました。怡州出身の石星は僧侶になってから般若経を学んだ。 この経典の古い翻訳は、説明が困難であるため、彼はしばしば、より完全な「西部地域にはマハプラジナパラミタ・スートラ」があると聞いたので、ガンルの5年目(260年に西)を捜索しました。砂を渡り、ユイティアンに到着しましたユアンカンの最初の年(西暦291年)のシュランと「プラジナパラミタの光の経典」と名付けられました。彼自身は玉田に留まり、80歳で亡くなった。 三国時代の仏教の普及はそれほど広範囲ではなかったものの、徐々に既存の文化と融合していった。 例えば、智謙と康僧慧はともに西域に祖先が住んでいたが、漢民族の地域で生まれ、漢文化の影響を深く受けた。彼らの翻訳は言語が優雅であるだけでなく、老子の慣用句を自由に用いて仏教の思想を表現している。第二に、智謙は『阿弥陀経』と『中観経』に基づいて連綿とした経文三巻を編纂し、康僧慧も『涅槃二巻』に基づいて涅槃に関する経文一巻を編纂した。 彼らは皆、音楽ではよく使われる聖書の物語を讃える賛美歌を作曲しました。古い伝説によると、康僧慧が仏教を広めるために呉に来たとき、インドの仏教絵本も持参しました。当時の画家曹不興は、その絵をもとに仏像を描き、有名な芸術家になりました。これらはすべて仏教の普及に大きな影響を与えました。寺院や仏塔の建築や仏像の彫刻については、いずれも一定の規模を有していたが、遺物が残っていないため、詳細に記述することは困難である。 |
<<: 韓信が「軍事の天才」であると最初に提唱したのは誰ですか?
>>: 歴史上、中国の仏教は晋代、南北朝時代にどのように発展したのでしょうか?
推薦する
後趙の皇帝、石之には何人の兄弟がいましたか?石之の兄弟は誰でしたか?
石之(?-351)は、斥候族の一人で、上当郡武郷(現在の山西省)の出身である。十六国時代の後趙の武帝...
京劇のバンシィにおけるバンヤンとは何を指しますか?京劇バンヤンの紹介
まだ分かりません:京劇スタイルのバンヤンとは何を指しますか?実は、伝統的な歌唱では、ビートに合わ...
『紅楼夢』でタンチュンは賈家を乗っ取った後、どんな問題に直面しましたか?
賈潭春は『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人です。これに非常に興味がある方のために、『興味...
『霊陵県慈心亭』の原文は何ですか?どのように理解すればよいのでしょうか?
慈心亭、霊嶺県范靼(南北朝)遠くの川岸には木々が浮かんでおり、空の果てには一本の煙が上がっている。川...
伝説の唐宗の隠し武器とは何ですか?
1. 手投げダーツは主に投げて人を傷つけるために使用されます。通常、ダーツは鉄や銅などの金属で作られ...
ブイ族の行動や習慣におけるタブーは何ですか?
ブイ族の文化は古代から現代まで発展し、多くの民族的タブーを継承してきました。これらの民族的タブーは、...
2020年にYuという姓の赤ちゃんに名前を付けるにはどうすればいいですか? Yuという姓を持つ素敵な女の子の名前の完全なリスト!
今日、Interesting Historyの編集者が、Yuという姓を持つ素敵な女の子の名前の完全な...
『射雁英雄の帰還』の呂占元とは誰ですか?呂占元の役割をどう評価するか
10年というのはとても長い時間です。憎しみは減るだろうと思っていましたが、憎しみの中には上質なワイン...
袁震の『涼州の夢』:この詩は簡潔だが、構成がよく、感情にあふれている。
袁震(779-831)は、衛之、衛明としても知られ、河南省洛陽(現在の河南省)の出身です。唐代の大臣...
北宋時代の軍事著作『何伯氏備論』:『衛論』全文II
『何博士随筆』は古代の軍事書であり、中国の軍人に関する評論を集めた最初の本である。北宋時代の武術博士...
陶淵明は官僚としての立場にいつも不満を抱いていたため、何度も田舎に引退したいと思った。
今日は、Interesting Historyの編集者が陶淵明についての記事をお届けします。ぜひお読...
「茅葺きの家の青柳とまばらな柵」を鑑賞した詩人楊無礙は、裏切り者の大臣秦檜に自分を従わせることを望まなかった。
楊無窮(1097-1171)は、布志とも呼ばれた。楊は楊とも書かれ、また本名は布志、雅号は無窮という...
なぜ薛叔母さんは夏金貴を嫁に選んだのでしょうか?彼女のどんなところが好きですか?
薛おばさんの話を知らない人は多いでしょう。『Interesting History』の編集者と一緒に...
『紅楼夢』で宝玉はなぜ宝仔と結婚したのですか?強制されたのですか?
宝玉は中国の古典小説『紅楼夢』の男性主人公です。興味のある読者とInteresting Histor...
毘馬文の由来:古代我が国に毘馬文と呼ばれる官職はあったのでしょうか?
毗馬文の起源: 西遊記の第 4 章では、孫悟空が太白金星とともに初めて天に昇ったときの物語が語られ、...