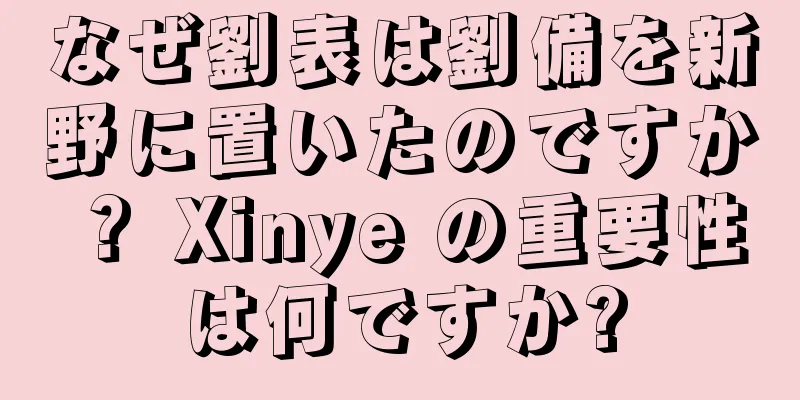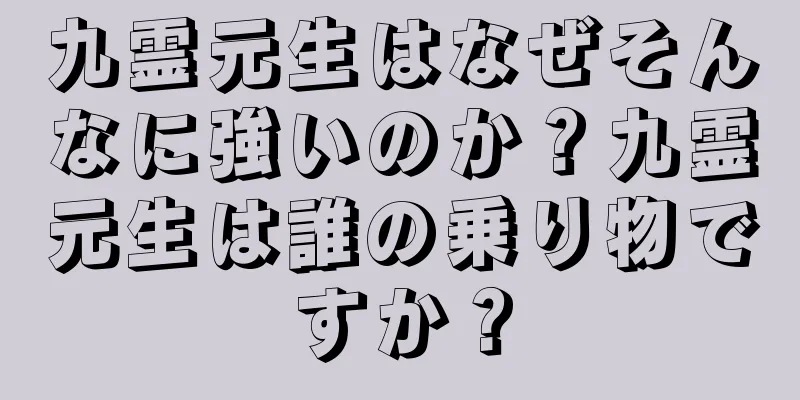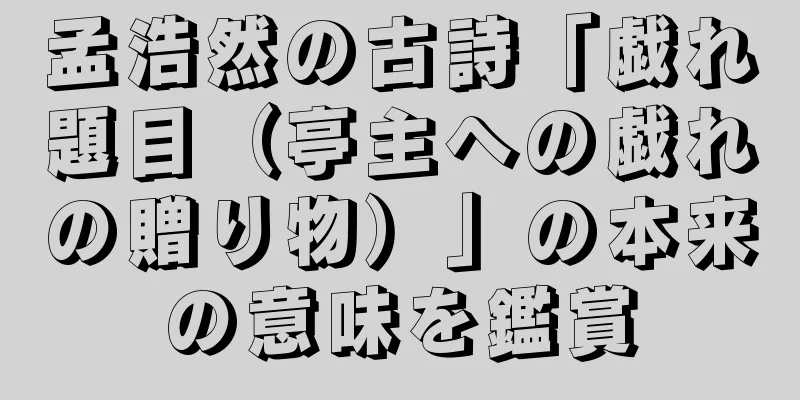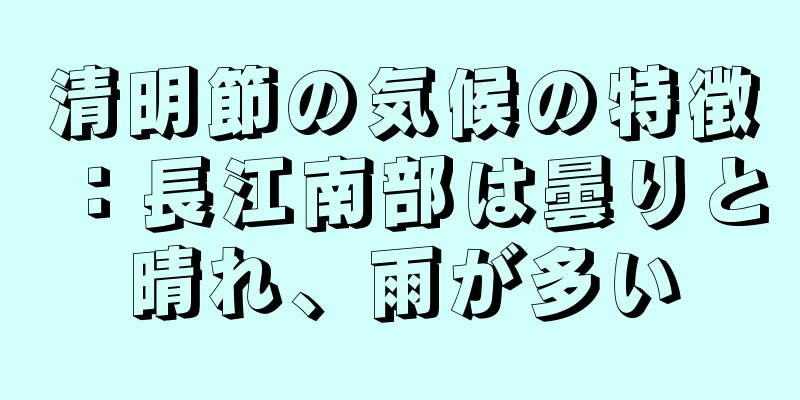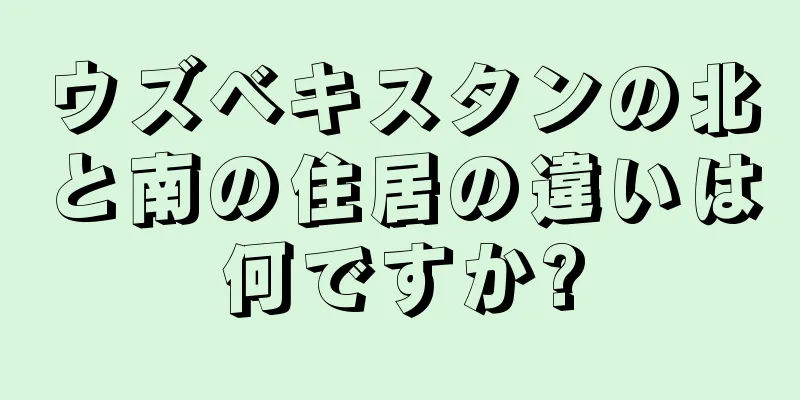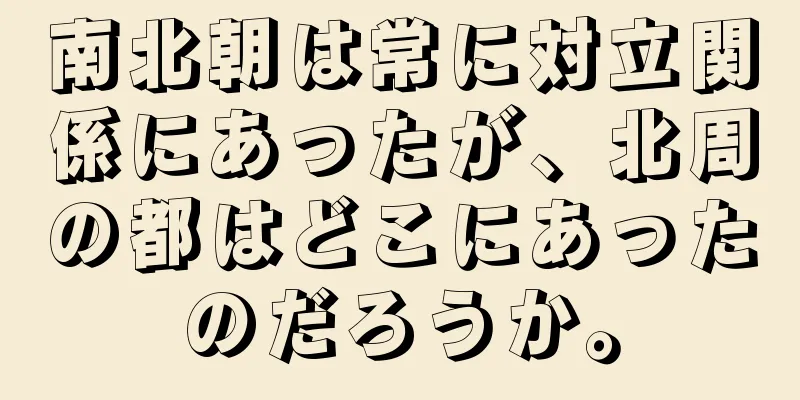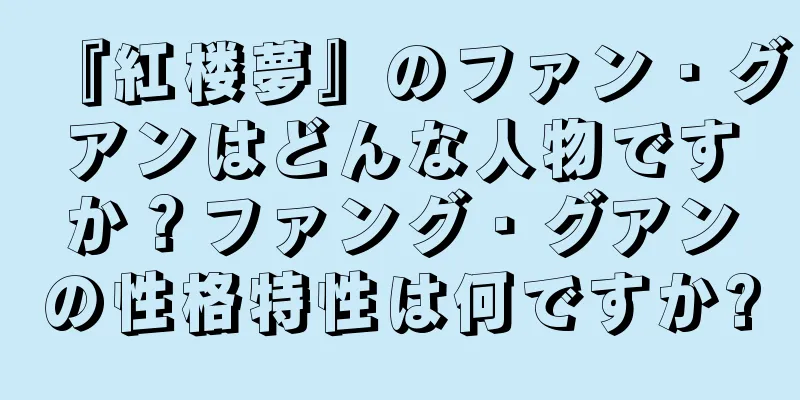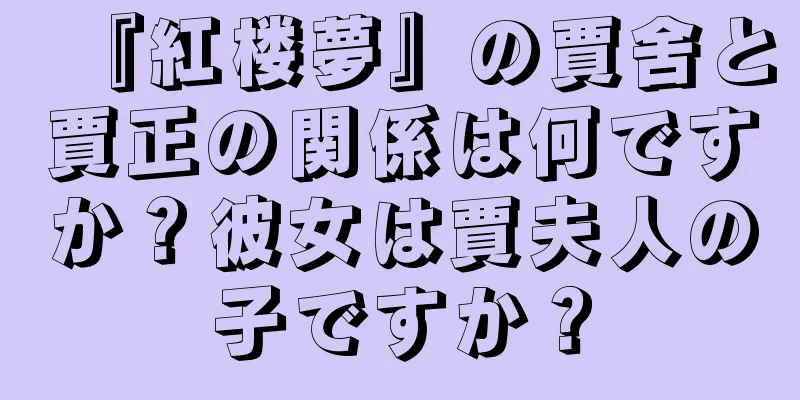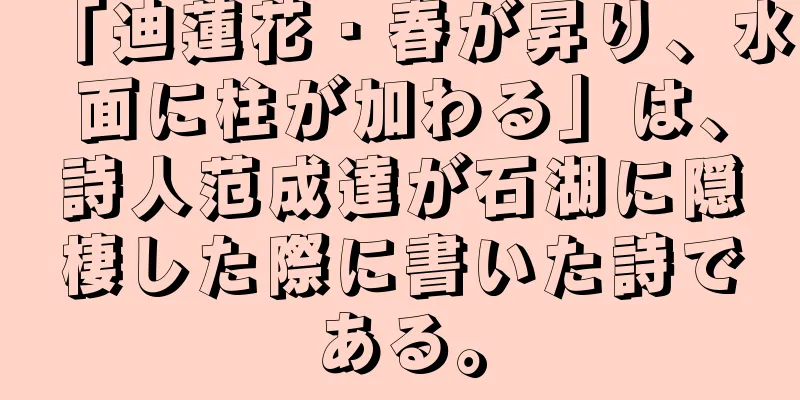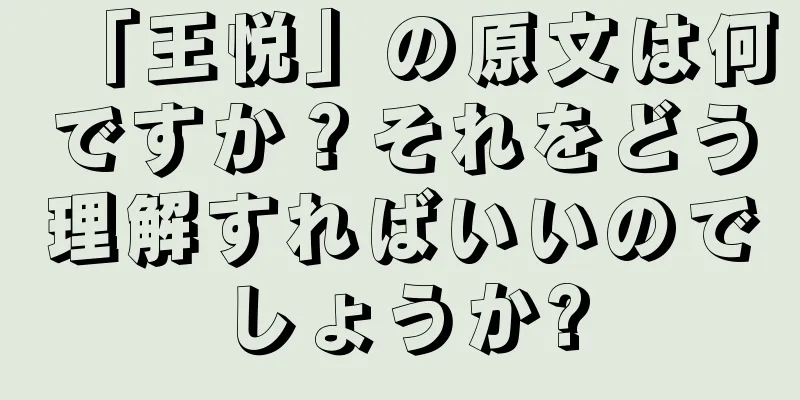陸倫の有名な詩は何ですか?なぜ彼はダリ時代の十人の才能の持ち主の一人に挙げられたのでしょうか?
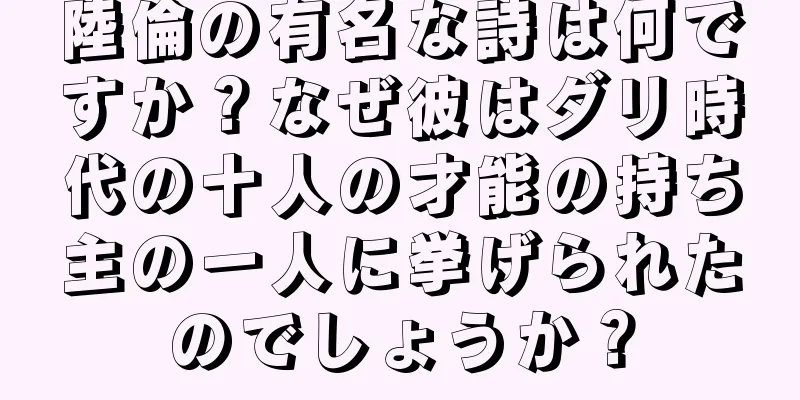
|
大理十才は、唐代皇帝代宗の大理時代の10人の詩人によって代表される詩の流派です。共通点は詩の形式や技法を重視している点だが、この10人の生没年は不明である。姚和の『集玄記』と『新唐書』によると、10人の優秀な学者とは、李端、陸倫、季仲福、韓洪、千奇、思空舒、妙法、崔董(董とも呼ばれる)、耿玄、夏侯神であった。宋代以降も様々な説があるが、そのほとんどは信憑性がない。いくつかのバージョンにはLi Yiが含まれています。それでは、次の興味深い歴史編集者が呂倫についての詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! 陸倫(739-799)、号は雲岩、河中普県(現在の山西省普県)の人。祖先は樊陽涛県(現在の河北省涛州)に住んでいた。樊陽陸家の北祖第四支流に生まれた。北魏の冀州太守、広呂大夫の陸尚志の子孫。唐代の詩人で、大理十才の一人。 玄宗の天宝時代末期に科挙を受けたが、混乱のため不合格となり、代宗の時代に再度科挙を受けたが、何度も不合格となった。大理六年、宰相袁載に推挙されて延祥衛に任じられ、後に宰相王進に推挙されて冀県の学者、書記局の校閲者となり、検閲官に昇進した。彼は山州の家臣と河南省ミ県の県令に任命された。その後、袁載と王進は有罪判決を受け、関与が疑われた。唐の徳宗皇帝の時代に、彼は再び昭応県の知事に任命され、その後、和中の渾渾于元帥の邸宅の裁判官を務め、後に税部監察官に昇進した。彼はその後すぐに亡くなった。 呂尚文の詩は風景描写に優れ、言葉遣いが簡潔で勢いが抜群である。特に『辺境の歌』は有名である。彼は『呂虎浮詩集』を著した。 バイオグラフィー 有名な詩人である陸倫は、とても不幸な人生を送った。彼が短期間官吏として務めることができたのは、権力者の推薦があったからに過ぎず、社交の恩恵を受けたと言える。陸倫が交流した人物の中には、有力な官僚が多かった。前述の袁載、王進といった宰相のほか、実際に宰相を務めた人物としては、張雁、李綿、斉英、陸志、賈丹、裴軍、霊湖初、渾渝、馬遂、魏高などがいた。彼らは宰相を務めたことはなかったが、やはり大きな権力を持っていた人物であった。 陸倫の詩は主に五字・七字の規則詩で、ほとんどが歌いながら互いに応答する作品である。しかし、軍隊生活中に書いた「辺境の歌」などの詩は、力強い文体と寛大な心情を込めたもので、後世まで受け継がれています。若い頃、彼は戦争を避けて各地で暮らし、現実と接していた。彼の詩の中には、「村の南で病気の老人に会う」など、戦後の人々の生活の貧困や社会経済の不況を反映した作品もある。他にも、初期に書かれた七字詩「鄂州に遅れて到着」は、安と施の反乱を避けるために南下する途中で一泊した時の心境や経験を描写しており、リアルで生々しく、深い感動に満ちています。七字歌「咸寧王軍が寅日に虎を捕らえるのを観る歌」は、武士と虎の戦いを描いたもので、迫力満点で力強い歌調で書かれている。清代の関世明は著書『独学山房唐詩集』の中で、「大理時代の学者の中で、陸倫と韓愈は七字古詩を書くのに最も優れていた。墨傑(王維)や董川(李斉)と比べると、彼らはより専門的であると言える」と述べている。 『呂虎浮詩集』は現在10巻が現存しており、『唐詩百人全集』に収録されている。明代の正徳年間に出版された『陸倫詩集』3巻本もあり、これには『唐詩全集』10巻本と失われた詩5編が含まれている。 『全唐詩集』は彼の詩を5巻にまとめたもので、彼の業績は『旧唐書・陸建慈伝』と『新唐書・文芸伝』に掲載されています。 陸倫は唐代大理時代の十才の一人であり、詩作で有名であったが、科挙に何度も失敗し、人生も官職も極めて不成功であった。しかし、彼の広い社交界は彼を社交界の活発な人物にし、ついには官職に就いた。 生没年は未確認 陸倫の生誕年は、一般的には唐の玄宗皇帝天宝7年(748年)頃と文献に記されている。また、游国恩らの『中国文学史』では天宝生誕7年とされている。これらはいずれも文一多氏の『唐詩全集』を根拠としており、定説となっているようだ。 傅玄聡氏は『唐詩人研究集』の中で、748年説は成り立たないと主張している。その理由は、姚何の『継玄集』と『旧唐書・陸建慈伝』に、陸倫が天宝末期に科挙に失敗したと記録されているからである。唐五代の人物の記録は信頼できるはずである。もし彼が天宝7年(748年)に生まれたとすれば、天宝末期には8、9歳の子供であり、科挙に合格することは不可能であった。陸倫はまた、彼の詩のいくつかは直徳年間に書かれたと主張した。もし陸倫が748年に生まれたとしたら、直徳年間にはまだ10代だったはずで、これらの詩を書くことは不可能だっただろう。フーの意見の方が理にかなっている。温一多と有国恩は自らの意見を裏付ける証拠を示さなかったため、傅月が正しいとみなすべきである。 傅玄聡は、陸倫の生年は748年ではなく、それよりずっと前、開元25年(737年)か、それより数年前に生まれたはずだと主張した。陸倫の死去年については、多くの参考書では鎮元の16年、つまり800年頃としているが、これも信憑性に欠ける。傅玄聡の著書の詳細な文献研究によれば、陸倫は鎮元の14年から15年の間、つまり798年から799年の間に亡くなった。 少年科挙 陸倫が幼かった頃、彼の家は裕福ではなく、世の中は混乱し、父親は早くに亡くなり、彼自身も病気が多かった。彼の生活は良くなく、叔父の家で多くの時間を過ごしていたかもしれない。 「倫吉世朗中夫思空郎中叔妙元外遣崔不韋洞」という詩では、「私は8歳で勉強を始め、その後四方に兵がいた。…私は命令により孤児となり、謙虚になり、幼い頃から病気をしていた。」と述べている。「池州に行き叔父を訪ね、叔父の高公郎中の家に泊まる」という詩では、「孤児と謙虚は簡単だ、どうしてこんなに似ているのだろう。同じ一族の少数が繁栄し衰退し、多くの人が外国の家庭で育つ。他の国の桑の木はまだここにあり、衣服は血と涙で汚れている。失われたガチョウを哀れみ、霜と雹は霧の波に送られる。」と述べている。 数年後、陸倫は科挙を受けたが、再び多くの挫折に遭遇した。前述のように、『衍玄記』と『旧唐書』には、陸倫が天宝末期の科挙に失敗したことが記録されている。陸倫には「科挙に失敗、中南山の別荘に帰る」という詩があり、その中で「私は長い間名声に惑わされ、春の終わりに山に帰った。自分の運命を話すのは恥ずかしく、人に会うときは顔をこわす」と言っている。「倫と副大臣の紀中夫…」には「私は粟と金を見たばかりだが、あなたと私のことを知らない。10回試みても無駄で、3年経っても成果がない」とある。これらの詩から、陸倫は天宝年間に科挙に失敗後、中南山に住み、勉強し、何度も科挙を受けたが、毎回失敗したことが分かる。その後、彼は「両親を追って鄱陽に逃げた」。これは、彼が科挙に何度も失敗し、おそらく生活や家庭の不幸によって鄱陽に逃げざるを得なかったためである。おそらく、当時、彼の叔父の家族は鄱陽地区に住んでいて、彼は叔父のところへ移って暮らしたのでしょう。大理の初めに、陸倫は科挙を受けるために邵陽から長安へ行った。『新唐書』の伝記によると、大理の初めに陸倫は科挙に何度も失敗したという。試験を受ける途中で、彼は完全に失敗した。 キャリアと社会的なつながり 陸倫は科挙に何度も失敗し、生活も官職も極めて不振であったが、詩の世界では次第に名声を高め、交友関係も広く社交的で、官職に就くことに繋がった。大理時代には長安や鄱陽に滞在し、季仲福、思空叔、妙法、崔東、耿薇、李睿などと交流し歌を歌ったため、「大理十傑」と呼ばれた。陸倫は十才の頂点ともいえる人物で、宰相の袁載や王進に高く評価され、推挙され、詩の世界から官職に就いた。袁載は呂倫の詩を皇帝に献上し、彼を延郷の衛に任命した。その後、王進に招かれ、薊県書院の学者と検閲官となり、この間、河南省公県の県令も務めた。袁在と王進が有罪判決を受けたとき、陸倫も関与が疑われ拘留された。徳宗が即位した後、陸倫は昭応県の知事に任命されました。朱泗の反乱が勃発した後、咸寧王渾于は和中の統治に赴き、陸倫を元帥府の裁判官に召し出した。軍隊生活は陸倫の詩風をより荒々しく大胆なものにした。軍隊生活や辺境の要塞を題材にした彼の詩は非常に生き生きとしており、これは大理十才の他の詩人にはなかなか達成できないことだった。彼の詩は徳宗皇帝に高く評価され、税部郎中に昇進した。官僚機構のトップに上り詰めようとしたまさにその時、彼の人生は終わった。 陸倫はこのような不遇の人生を歩んだが、短期間官吏として務めることができたのは権力者の推薦によるものであり、人脈の恩恵を受けたと言える。陸倫が交流した人物の中には、有力な官僚が多かった。前述の袁載、王進といった宰相のほか、実際に宰相を務めた人物としては、張雁、李綿、斉英、陸瓚、賈丹、裴軍、霊湖聡などがいた。渾渝、馬遂、魏高などは宰相を務めたことはなかったが、やはり大きな権力を持っていた。呂倫はまた、地方の知事、重要な朝廷の役人、官職や昇進を統制する人々とも交流していました。 詩の鑑賞 病気の兵士 「私は旅を続けて病気になり、食べる物も無くなりました。何千マイルも旅しましたが、まだ家に着いていません。古城の下で悲しみにため息をつき、傷に染み入る秋の空気に耐えられません。」この詩は、病気のため除隊となり、帰路につく兵士について書かれています。詩の題名から判断すると、作者が目撃した人生の出来事に基づいているのかもしれません。詩人は、集中した描写と誇張した表現を用いて、登場人物のイメージを形作ることに重点を置きます。詩の中の負傷兵は軍隊から除隊した後、悲劇的な運命がまだ自分を待っていることをすぐに知りました。たくさん歩くと疲れるのは必然ですが、病気が加わると、道中の人たちにとって状況はさらに厄介なものになります。病気になって歩けなくなると、「留まる」という考えに陥ります。しかし、滞在場所を見つけるのは容易ではありませんでした。軍を離れると補給が途絶え、長い旅の後に乾いた食べ物が底をつきます。食糧不足の状況を遅らせれば遅らせるほど、私たちはより大きな苦しみを味わうことになるでしょう。最初の文章はたった7語ですが、「病める兵士」の3つの苦しみを描写し、窮地に陥り出口のない悲惨な状況を明らかにしています。これは「二重化」の技法の見事な使い方です。 2番目の文は、前の文の「行」という単語を引き継いで、登場人物の状況をさらに説明しています。 2フロアに分かれています。 「何千マイルもの旅を終えて家に帰る」ことが「病める兵士たち」の目標であり希望である。故郷で幸運が待っているはずはないが、「故郷の丘で狐は死に、木の葉は根に落ちる」という諺にあるように、「病める兵士」にとって唯一できることは故郷で死ぬことだけだった。私はこれまでたくさん旅行してきましたが、故郷は何千マイルも離れており、まだ旅行していない場所がたくさんあるはずです。田舎で死にたいという哀れな願いさえも実現するのは難しいかもしれない。そのため、「まだ故郷に着いていない」という3つの言葉には、言い表せない悲しみと憤りが込められており、読者は悲しい気持ちになります。ここで、「何千マイルも旅して家に帰る」というのは、詩的な感情を甘やかすための、偽装された祝福である。しかし、「家に着く前に」というのは、悲しみが続く「喜び」であり、詩的な感情を捉えたものである。このようなエスケープメントのおかげで、この詩は何度も繰り返し読むことができ、いつまでも余韻が残ります。 詩の最初の2行は登場人物の外見を直接描写していません。声は聞こえるけど、人は見えない。しかし、誇張した描写と歌唱により、キャラクターイメージが浮かび上がってきている。最初の 2 つの文の準備に基づいて、3 番目の文では、適切な環境に置かれた彫像のように、キャラクターの外見をより鮮明かつ際立たせて描写します。 「もがく髪」という二つの言葉は、疲れて、病気で、寒くて、空腹で、苦しんでいる人のイメージを鮮やかに描写しています。 「泣き声」は病気や飢餓、特にトラウマの発症によって直接引き起こされます。 「病気の兵士」は負傷しており(「金の傷」)、秋の空気が到来して天候が悪くなったため、古い傷が再発しました。このことから、彼の服は薄くてぼろぼろで、寒さを防げないことも分かります。したがって、4番目の文は3つの「耐えられない」を表現しています。さらに、明確に書かれていないが読者には理解しやすい別の層があり、それは「病める兵士」が道中で死んだり異国の地に置き去りにされたりするのを恐れ、心の中に絶望と痛みを感じることが多いということです。肉体的苦痛と精神的苦痛が組み合わさっているからこそ、彼の「泣き叫び」は聞くに耐えないほどなのだ。作者は、髪を振り乱しうめき声を上げる負傷兵のイメージを「古代都市」という文脈の中に巧みに配置し、兵士のやつれ具合と孤独な状況を何倍にも強調している。街の端にいる蟻のように、いつ死んでもおかしくないという印象を人々に与える。 このように、二重の技法によって人物描写や背景設定がなされ、飢え、寒さ、疲労、病気、負傷といった「病兵」の苦しみが集中的に表現され、「その悲惨さは言い尽くせないほどである」(南宋時代の范希文『床上の夜話』)とある。これは客観的に見て社会に対する告発であり、また詩人が書いた登場人物に対する深い共感も表している。 陸倫の辺境の歌六選(第2部) 森は暗く、草は風に揺れ、将軍は夜に弓を引く。朝になって白い羽を探したのですが、石の縁に埋もれていました。 陸倫の『辺境の歌』は6編の詩から成り、命令を発したり、敵を狩って倒したり、勝利を祝ったりする軍隊生活を描いています。張普社に返事をするために書かれた詩なので(詩の題名は「張普社に返事する辺境の歌」とも呼ばれる)、その言葉には多くの賛辞が込められている。これはシリーズの2番目の詩です。夜に狩りをしていた将軍が、深い森の中で草がざわめくのを見た。将軍はそれが虎だと思い、弓を曲げてそれを射たという話です。夜が明けると、矢は実際に石に当たりました。この典型的な筋書きは将軍の勇敢さを示しています。この詩の題材は『史記・李将軍伝』から取られている。漢代の名将、李広は弓術に長けていたと記録されている。李広が幽北坪の太守を務めていたとき、次のような劇的な体験をした。「李広は狩りに出かけ、草むらに石を見つけた。虎だと思って射た。矢じりが石にめり込み、それが石であることが分かった。もう一度射たが、またも石を貫くことはできなかった。」 最初の文では、将軍の夜の狩猟場所が暗い森であると描写されています。すでに夜も遅く、突風が吹いて草や木が倒れていました。これは特定の時間と場所を説明するだけでなく、雰囲気も作り出します。幽北坪は虎の多い地域で、山が深く、森が密集しているところは百獣の王である虎の隠れ家です。虎は夕暮れや夜行性で、山からよく出てきます。「森は暗く、草は風に驚いている」。「驚いている」という言葉は、人々に今にも現れそうな虎の存在を自然に思い起こさせ、非常に緊張した雰囲気を作り出すだけでなく、将軍がどれほど警戒しているかを暗示し、下の「弓を引く」ための道を切り開きます。次の文章は引き続き撮影について書きます。しかし、「射る」ではなく「弓を引く」という言葉が使われています。これは詩が韻を踏む必要があるだけでなく、「弓を引く」ことが「射る」ための準備動作であるためでもあります。このように書くことで、読者は危険に直面した将軍がいかに冷静で落ち着いていたかを想像し、理解することができます。 「驚愕」の後、将軍はすぐに弓矢を引き、素早く力強い動きをしながらも慌てることはなかった。彼の動きは威厳があり、イメージはより鮮明になった。 最後の2行は「矢が石に突き刺さり、羽根を飲み込んだ」という奇跡を描いており、時刻を翌朝(「夜明け」)まで延期しています。将軍は獲物を探して、矢に射られたのは虎ではなく、石の上にしゃがんでいる人であることに気づきます。これを読むと、人々は最初は驚き、そしてため息をつきます。なぜなら、矢尻に取り付けられた白い羽根の付いた矢が「石の端に突き刺さり」、石に3/10まで突き刺さっていたことが判明したからです。この書き方は、時間や場面の変化がより複雑であるだけでなく、よりドラマチックでもあります。 「石稜線」とは石の突出部分であり、矢が貫通することは考えられません。神話的な誇張が詩的なイメージにロマンスの層を加え、特に楽しく読めるようになっています。その美しさを感じるだけで、間違っているとは思わないのです。清代の呉喬はかつて、米を使って「意」を生き生きと表現しました。散文では米を炊いて米を作り、詩では米を醸造して酒を作ると言いました(『衛鹿詩談』参照)。彼の言葉はとても素晴らしいです。詩は読者の感情に訴える必要があるため、一般的に散文よりもイメージに重点が置かれ、言語はより簡潔で、芸術的概念の創造に重点が置かれ、より酔わせるワインのような作品となっています。 『史記』では、ただの回想だったが、詩人によって洗練され加工されると、芸術的な魅力に満ちたこのような短い詩に昇華された。それは、米と粟を上質なワインに変えるようなものではないだろうか。 陸倫の辺境の歌六選(第3部) 月は暗く、雁は高く飛び、雁羽は夜に逃げます。軽騎兵を率いて追撃したかったのですが、大雪で弓や剣が隠れてしまいました。 「国境の歌」シリーズには 6 つの詩があり、これは 3 番目の詩です。陸倫は中唐の詩人であるが、その辺境詩は依然として繁栄した唐代の風格を保っており、雄大で大胆、言葉には勇壮さがあふれ、読むと感動する。 最初の 2 行、「月は暗く、雁は高く飛び、雁羽は夜に逃げる」は敵の退却を描写しています。 「暗い月」は光がないことを意味します。 「ガチョウは音もなく高く飛ぶ」暗く静かな夜を利用して、敵は静かに逃げていきました。チャンユは古代の匈奴の最高統治者であり、ここでは侵略者の最高司令官を指します。彼らは完全に崩壊した様子を見せながら、夜に逃げた。 夜の闇にもかかわらず、敵の行動は我が軍に察知された。 3番目と4番目の文「軽騎兵で追撃したいが、大雪で弓や刀が隠れてしまう」は、追撃の準備をしている我が軍の状況を描写しており、兵士たちの勇ましい気概がうかがえる。想像してみてください、騎馬隊が出撃しようとした瞬間、突然弓と刀が大雪で覆われるなんて。なんともスリリングな光景でしょう! この詩から判断すると、陸倫はイメージと機会を捉えるのがとても上手です。彼は典型的な意味を持つ画像を撮影できるだけでなく、その瞬間を最も芸術的な効果で表現することもできます。詩人は軍隊がどのように攻撃したか、敵に追いついたかどうかについては何も書いていません。追撃の準備をしている場面だけを描写し、当時の雰囲気や感情を力強く伝えています。 「軽騎兵を率いて追撃したかったが、大雪が弓や剣を覆ってしまった。」これは戦いのクライマックスではなく、クライマックスに近づく瞬間です。この瞬間は、弦に張られた矢が今にも発射されそうな瞬間であり、最も魅力的な力を持っています。成果が出なかったために不満を感じるかもしれません。しかし、このようにしてのみ、作品はより感動的になり、読者の連想や想像力を喚起することができます。これは「言葉は有限だが、意味は無限である」と言われています。龍は頭は見えますが、尾は見えません。尾がないわけではありません。尾が雲の中に浮かんでいるので、さらに興味深く魅力的です。 |
<<: 李端にはどんな有名な詩がありますか?なぜ彼はダリ時代の十人の才能の持ち主の一人に挙げられたのでしょうか?
>>: 梁世成は宋の徽宗皇帝からどれほどの寵愛を受けたのでしょうか?なぜ彼らは最終的に北宋の六盗に分類されたのでしょうか?
推薦する
儒教古典原典の鑑賞:荀子・臣の道 第13章
世俗の人々はこう言います。「主な道はすべての人に利益をもたらす。」そうではありません。主人は民衆の声...
なぜ朱元璋は朱雲文に帝位を譲ったのですか?建文帝になった後、彼はどうやって姿を消したのでしょうか?
歴史上、皇帝が王位を継承する際、第一候補となるのは当然ながら息子でした。また、息子がおらず兄弟を選ん...
北斉史第二十巻第十二伝原文の鑑賞
張瓊、葫璋、姚雄、宋仙王、澤慕容少宗、薛欣宜、志烈平布、大果、薩慕容燕張瓊は、名を連徳といい、ダイ族...
戦国時代の東周王朝はどれほど弱かったのでしょうか?戦国七英雄にも及ばないレベルだ。
西周の末期、周の有王は鮑汀を寵愛し、沈侯の娘である皇后と皇太子の怡九を廃し、鮑汀を皇后に、鮑汀の息子...
歴代の王朝で秋の食べ物を描写した詩は何ですか?詩人はそれをどのように表現しているでしょうか?
秋は美しいだけでなく、人々にいつも多くの驚きをもたらす収穫の季節でもあります。どの王朝にも秋の食べ物...
Yan QingとLi Shishiの関係は何ですか?彼はなぜ涼山に行ったのですか?
Yan QingとLi Shishiの関係は何ですか? 『水滸伝』の顔青は宋江に代わって朝廷と交渉し...
魏英武の「福徳慕于別れ里周」:詩全体が首尾一貫しており、一体化している
魏英武(生没年不詳)、号は易博、荊昭県都陵(現在の陝西省西安市)の出身。魏蘇州、魏左司、魏江州として...
太平広記・第85巻・奇人・蒋舜卿の具体的な内容は何ですか?どのように翻訳しますか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
白黒無常の起源は何ですか?彼らはカップルですか?
「白黒無常」という言葉をよく耳にしますが、その言葉を聞くと、みんな怖く感じます。これは、ドラマの登場...
『紅楼夢』の青文は本当に悪女なのか?彼女は何をしたのですか?
青文は『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の第一号であり、第二巻の第一号でもある。賈宝玉の部屋の四大...
『紅楼夢』で蔡霞が王夫人によって賈邸から追い出された本当の理由は何ですか?
『紅楼夢』で蔡霞が王夫人に賈屋敷から追い出された本当の理由とは?次は『おもしろ歴史』編集者が関連記事...
「紅楼夢」で最も教養のある人物は誰ですか?それはリン・ダイユだ
『紅楼夢』で最も教養の高い人物は誰でしょうか?実は、この小説に登場する「四大家」は詩、文学、礼儀作法...
鉄を泥のように切り裂く剣がこの世に本当に存在するのだろうか?鉄を泥のように切ることができるという噂はどこから来たのでしょうか?
鉄を泥のように切り裂くことができる刀といえば、やはり面白いですね。鉄を泥のように切り裂くことができる...
世夷公主の簡単な紹介 漢の武帝の娘である世夷公主はどのようにして亡くなったのでしょうか?
石邑公主は、前漢の武帝の娘で、名前や生年は不明。唐木鎮は石邑。この王女は『史記』や『漢書』には登場し...
東晋の葛洪の『包朴子』:内篇と雑答の全文と翻訳と注釈
『包朴子』は晋の葛洪によって書かれた。包埔([bào pǔ])は道教の用語です。その由来は『老子』の...