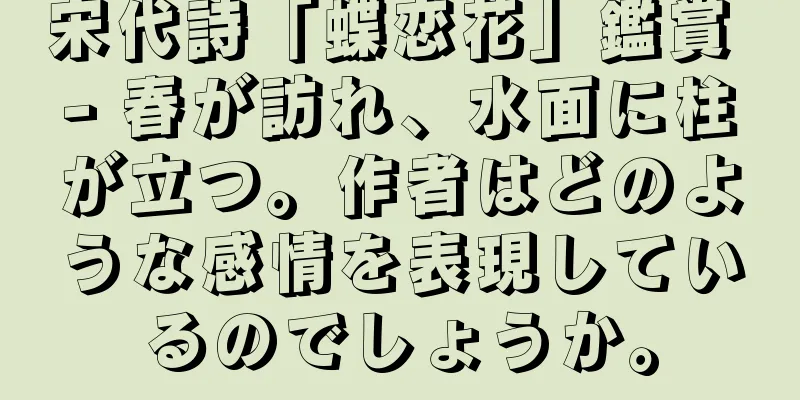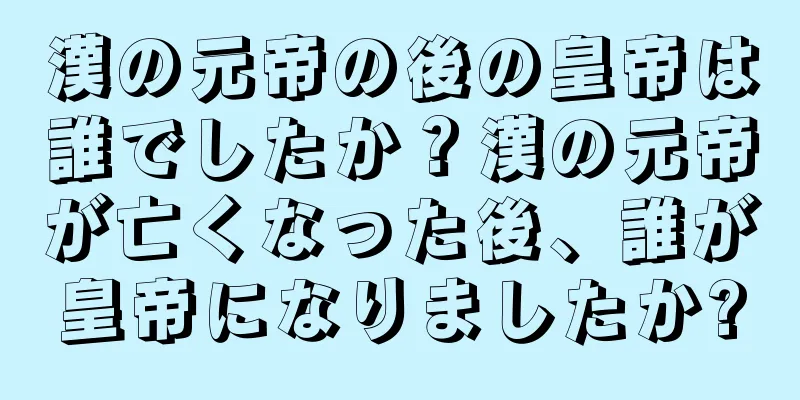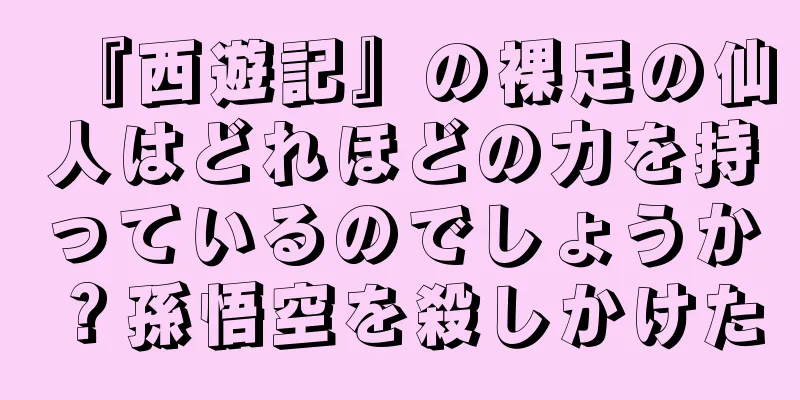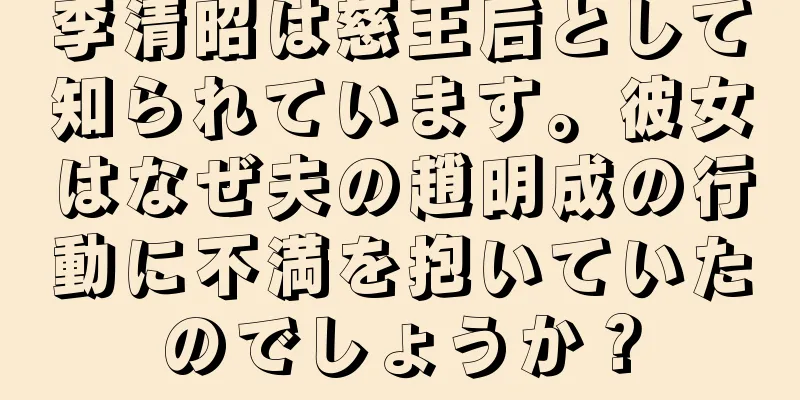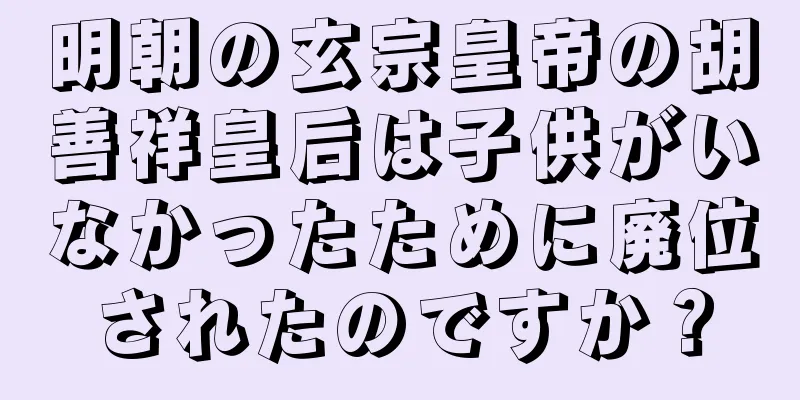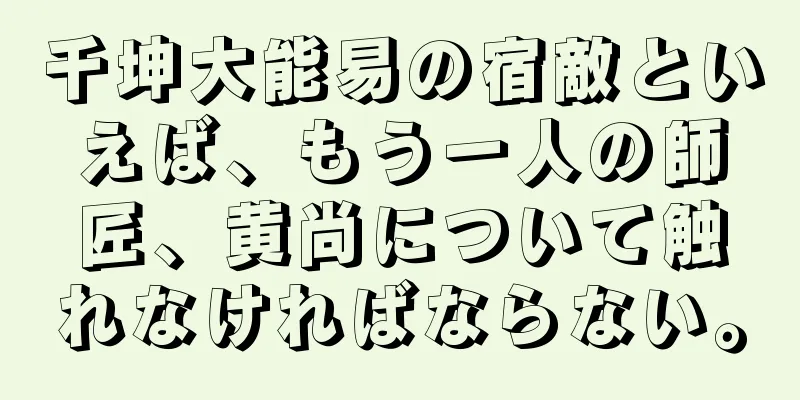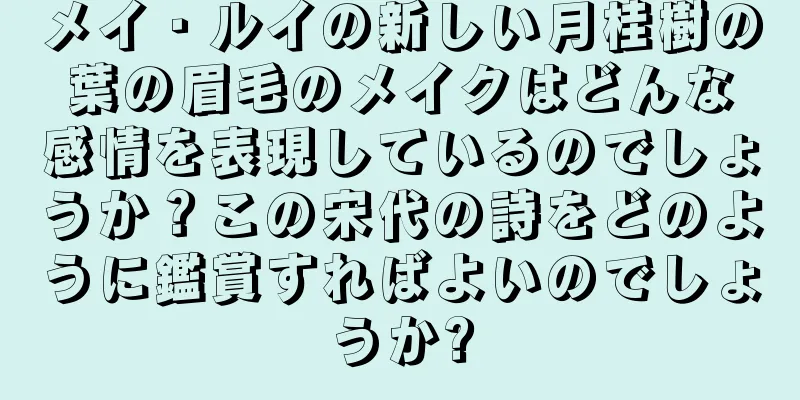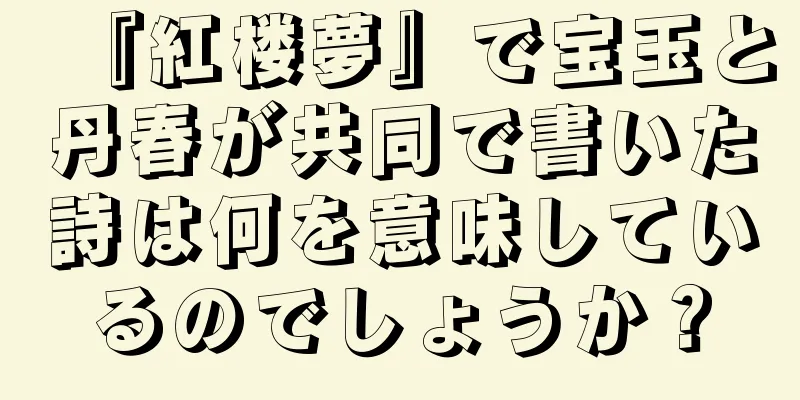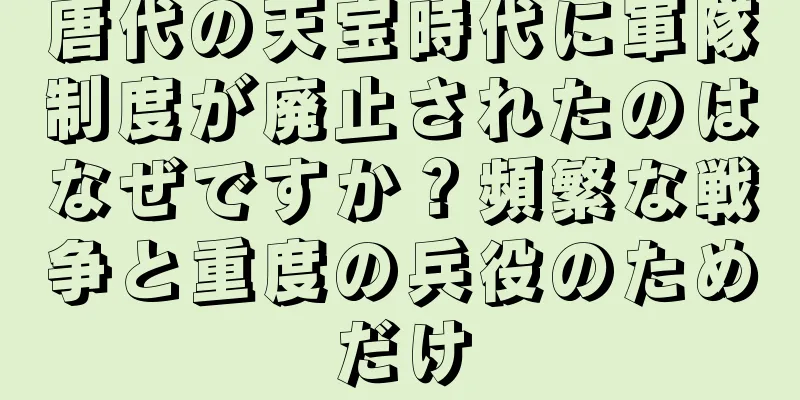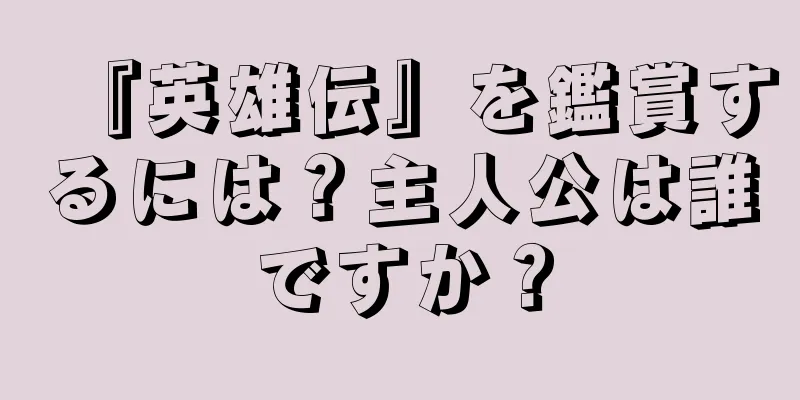もし曹爽が司馬懿に降伏していなかったら、状況は変わっていたでしょうか?
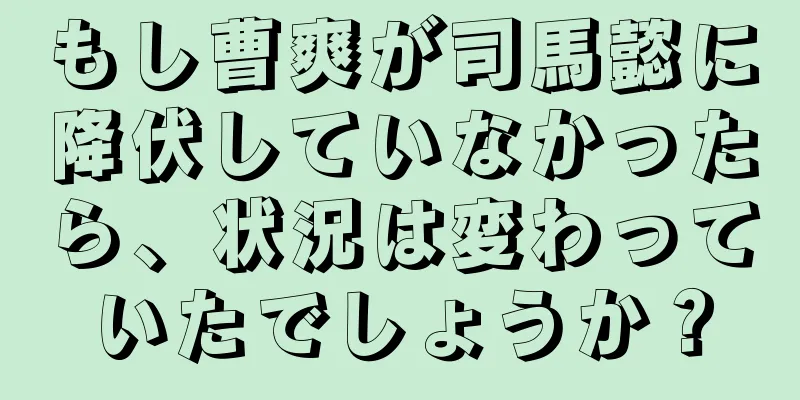
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、高平陵の変における曹爽の積極的な降伏について詳しく紹介します。曹爽が司馬懿と戦っていたら、どちらが勝利したでしょうか? 見てみましょう! 三国時代の歴史にはいくつかの重要な出来事がありました。彼らは三国志の歴史の流れを直接変え、中国の歴史に大きな影響を与えました。その一つが曹魏で起こった高平陵の変です。この事件により曹魏の権力は司馬懿に移り、曹家はその後ますます弱体化していった。最終的に、司馬一族が建国した晋王朝が曹魏政権に取って代わり、国を統一した。この時代の歴史を見ると、曹爽兄弟は臆病で無能だったという印象を誰もが抱く。彼らは自ら軍事力を放棄し、司馬懿に降伏したが、それが自らに災難を招いたのだ。それで、彼らが降伏しなければ、状況は変わるのでしょうか? 1. 高平嶺事件。 249年、曹魏の当時の君主で皇帝の世話を任されていた大臣の曹爽とその兄弟たちは皇帝を高平陵に案内しました。彼らが首都を去ったとき、国内に潜伏していた司馬懿がクーデターを起こした。息子の司馬師は、長年育てた忠実な戦士3,000人を召集して司馬懿を護衛させ、寒い宮殿に住んでいた郭太后を解放した。彼はまた、郭太后の名で勅令を出し、洛陽の門を閉ざし、武器庫を占領し、洛河の浮橋を守るために軍隊を派遣した。 司馬懿もまた皇帝に嘆願書を提出し、曹爽らの罪を非難し、抵抗をやめて自発的に降伏するよう要求した。司馬懿はまた、曹爽とその兄弟たちと親しい者を派遣し、彼らに自発的に軍事力を放棄し、それぞれの居住地に戻り、司馬懿が彼らに危害を加え続けないことを保証するよう説得した。曹爽たちは予想外の事態に全く準備ができていなかった。その知らせを受けてから、私はしばらくジレンマに陥りました。 彼らが必死に防衛準備をしていたちょうどその時、彼らのシンクタンクである歓帆が首都から到着した。当時の状況を考慮して、桓範は曹爽とその兄弟たちに武力で司馬懿に抵抗するよう説得しようと全力を尽くした。彼は曹爽とその兄弟たちに皇帝を許都まで護衛し、国中に王を守るよう命じるよう提案した。徐渡には、多数の軍隊に武器を供給するために使用できる、昔から残っている武器庫があります。残された物流と食糧の問題に関しては、桓凡は農業大臣の印章を携行しており、どこからでも徴発して解決することができた。桓範の助言に従っていれば、曹爽とその兄弟たちは依然として司馬懿と戦うことができただろう。 しかし、曹爽とその兄弟たちは桓凡の提案に躊躇した。一晩中悩み、考えた後、彼らはついに司馬懿に降伏することを決意した。桓凡は彼らに激怒し、泣き崩れながら彼らを無知な小動物だと叱責した。司馬懿は曹爽とその兄弟たちの降伏を受け入れた後も彼らを解放しなかった。その後間もなく、司馬懿は曹爽の兄弟とその一族、そしてその追随者たちを殺害した。それ以来、曹魏の権力は司馬家の手に移った。 では、曹爽とその兄弟たちが桓範の助言に従って司馬懿に降伏せず、司馬懿と死闘を繰り広げていたら、誰が勝ったでしょうか。この疑問に答えるには、以下の側面から分析する必要があります。 2. 軍事力の面では、曹爽は司馬懿に敵わなかった。 曹叡が息子を託す人事を見れば、曹操の遺言の影響というヒントが見つかる。曹操が存命中、彼は司馬懿を自分の陣営に招集した。曹操に召喚されるのを避けるために、司馬懿は数年間病気のふりをしていた。結局、天下の大局は決まり、曹操は司馬懿を殺そうと決意したので、司馬懿は出てきて曹操の陣営に加わった。 曹操は洞察力によって、司馬懿の脅威を本能的に察知した。しかし、司馬懿は非常に慎重で、曹操から与えられた仕事はどれも真剣にこなしました。また、曹操を強く支持し、助言を与え、曹操の即位を承認した。こうしたことすべてにより、曹操の疑念は徐々に薄れていった。曹操が司馬懿を曹丕に配属した後、司馬懿は曹丕の信頼を得て、司馬懿の安全が確保された。 しかし、曹操は死ぬ前に曹丕に司馬懿を警戒するよう指示することを忘れなかった。そのため、曹丕の治世中、司馬懿は軍事力を獲得することができなかった。曹叡の治世中、曹叡と司馬懿の友好的な関係により、司馬懿の権力も拡大した。曹叡は部下の忠告を無視し、曹真に代わって諸葛亮の北伐に抵抗するよう司馬懿に依頼した。これにより、司馬懿は軍務に精力的に取り組み、自らの影響力を獲得することができました。 曹叡は亡くなった後も司馬懿を非常に信頼していた。彼は、司馬懿が遼東戦線から急いで戻り、息を引き取る前に葬儀の準備をするまで耐え抜いた。しかし、曹叡は息子の世話をする大臣を任命する際に、まだ独自の考えを持っていたことがわかります。彼は司馬懿に諸葛亮から学び、若い君主を助けるよう頼んだ。しかし、曹爽に将軍の地位を譲った。このように、司馬懿と曹爽はともに若き皇帝の世話を任された大臣であったにもかかわらず、実際の権力は依然として曹一族の手に握られていました。 ここに曹操の意志の影が見える。しかし、曹叡の計らいから判断すると、曹爽と司馬懿の能力差は明確に理解していた。曹叡は朝廷全体の中で司馬懿の敵は誰もいないと見抜いていたため、息子を他人に託す際に司馬懿の心を動かされたのである。そして、権力を分配する際には、万が一に備えて司馬懿の権力を制限すべく曹叡は曹爽に将軍の地位を与えた。 司馬懿は軍隊を率いて戦いに臨んで以来、一度も敗北したことがない。この点では曹爽は彼よりはるかに劣っている。諸葛亮の第五次北伐が終わった後、司馬懿は蜀軍が内紛に陥り、魏延が殺されたことを知り、すぐに曹叡に蜀を攻撃する許可を求めた。曹叡が彼を拒否したのは、ただ楽しみたかったからであり、そうでなければ、司馬懿の聖戦はとっくに蜀漢に降りかかっていただろう。 曹爽の興市の戦いとは対照的に、当時、曹爽は威信を高めるために、夏侯玄とともに関中の軍を動員し、蜀を攻撃する戦争を開始した。しかし、王平の妨害により、曹爽は蜀軍の防衛線を全く突破できなかった。結局、曹爽は軍を撤退させざるを得なくなった。撤退中に曹爽は費毅の攻撃を受け、大きな損害を受けた。この結果、関中が滅亡したと歴史書に記録されている。この戦いで曹爽の真の軍事力も完全に露呈した。そのため、軍事力の面では曹爽のレベルは司馬懿のレベルには遠く及ばない。もし両者の軍事力が同等であったなら、曹爽は間違いなく敗北したであろう。 3. 曹爽の軍隊は司馬懿の軍隊に敵わなかった。 双方の軍事力に差があったため、戦争に勝つためには曹爽が軍事力で優位に立つ必要があった。これはまさに、歴史記録によってもたらされた誤解です。なぜなら、歴史の記録から、曹爽が将軍としての権力を使い、世界各地から軍隊を動員して王を支えれば、軍事力の面で司馬懿よりも優位に立つことができたと思われるからです。この場合、曹爽の降伏は極めて卑怯な行為であった。 しかし、これは本当にそうなのでしょうか? 司馬懿の軍事力についての歴史書を見ると、事件の冒頭で司馬師が3000人の死戦士を召集したとしか書かれていません。司馬懿が指揮できたのは、この3000人の死戦士だけだったようです。そうなると、司馬懿の軍事力は当然曹爽に敵わないことになる。しかし、実際はそうではありません。 歴史書に記されている3000人の死の戦士は、クーデターを起こす準備の整った軍隊に過ぎなかった。当時、司馬懿は自分の屋敷に隠遁生活を送っており、使える兵力もそれほど多くありませんでした。クーデターを起こすどころか、彼らには自らを守る能力すらありません。司馬師が召集した三千人の死闘士は、クーデターを起こす初期段階で司馬懿の安全を守るための保証として使われた。 しかし、司馬懿がクーデターを起こして首都の政治・軍事権力を掌握すると、この三千人の死闘士たちの役割は消えた。司馬懿は、この三千人の暗殺者だけでなく、さらに重要なことに司馬師の権力に頼ってクーデターを起こした。司馬師は当時、中央衛兵将軍であり、軍事力を持つ重要な地位にあった。 クーデターを起こす前日、司馬懿は司馬師と協議した後、司馬昭にこう告げた。その夜、司馬師はいつものようにぐっすりと眠り、司馬昭は寝返りを打っていました。司馬師は長い間この日のために準備をしていたからである。今や東風を除いてすべて準備が整っていた。当然、彼は自信を持って、いつものようにぐっすりと眠った。この観点から、司馬師が首都の全軍に対して綿密な準備を行っていたことがわかります。 クーデター後、司馬懿は郭太后の命令により、直ちに首都の軍を掌握し、軍を軍営に派遣した。彼は武器庫も押収し、軍隊はすぐに十分な武装を整えた。彼は洛河の浮橋を守るために軍隊を派遣し、攻撃も防御もできる位置に身を置いた。 対照的に、曹爽は軍隊を率いて戦うのではなく、皇帝を高平陵に参拝するために護衛した。彼が一度に率いていたのは小さな軍隊だけで、装備のほとんどは儀仗兵が使う武器だった。首都でクーデターが起こったことを知った曹爽は、近くの農村から急いで兵士を集めて防衛陣地を築かざるを得なかった。軍事力、装備などにおいて、曹爽は司馬懿に全く及ばなかった。 曹爽が部下を徐都に導いたとしても、司馬懿に追われれば徐都にたどり着くのは困難だろう。たとえ徐都にたどり着いたとしても、曹爽が事態を救うのは難しいだろう。これは、曹魏の最も精鋭な中央近衛兵が司馬懿によって統制されており、曹爽が王を守るために募集した軍隊は、精鋭さの点で近衛兵に匹敵しなかったためである。数の面では曹爽に有利はないだろう。関龍軍団は司馬懿が長年率いてきた軍隊であり、軍の士気は長い間司馬懿に向けられていました。 曹爽が関龍軍を徴兵した場合、この軍は司馬懿に寝返る可能性が高いと考えられます。このように、曹爽は実際に敵に力を与えていたのです。南軍に関しては、中央に司馬懿がおり、東呉の妨害もあったため、到着がさらに困難だった。したがって、もし曹爽が徐渡に抵抗することを決意したとしても、彼の指揮下にある軍隊は人員、装備、精鋭レベルの面で司馬懿に匹敵するものではないだろう。 4. 曹爽が司馬懿と戦ったらどうなるでしょうか? 歴史には、桓範が曹爽のもとに避難したとき、司馬懿が「曹爽に賢明な助言が下ったらどうなるだろうか」と言ったと記録されています。蒋杰は「それは納屋で豆にしがみつく鈍い馬のようなものだ」とコメントしました。曹爽は絶対に桓範の助言を採用しないでしょう。それは誰もが曹爽の性格をはっきりと理解しているからです。彼には司馬懿と戦う能力がなく、依然として運に期待していた。したがって、誰もが彼の失敗をはっきりと見ました。 もし曹爽が桓範の助言に従い、部下を率いて曹芳皇帝を徐都まで護送していたら、上記の分析から、依然として不利な状況にあったであろうことが分かる。司馬懿は郭太后の名で命令を出したので、義を主張した。これにより曹爽の皇帝の権力は弱まった。さらに、曹爽の長期にわたる不正行為は皆の敵意を呼び起こし、彼を政治的に極めて孤立した立場に置いた。 曹爽が徐都に到着すると、数人の大臣が軍隊を率いて徐都に行き、王を援護するだろう。首都圏の曹魏軍の主力は司馬懿によって統制されていた。さらに、曹魏の長年の制度により、全国に散らばった王たちは独自の軍隊を持つことが許されず、囚人のように厳重に監視されていました。これにより、曹爽が外国からの援助を得られるという希望はさらに断たれた。曹爽が各地から兵士を募集して定住させ、農業をさせたとしても、時間がかかり、一時的な武装と組織では戦闘能力が保証されない。 司馬懿の兵力運用のスタイルからすると、兵力と武器で優位に立った後、かつて曹爽を攻撃した際に孟達を攻撃したのと同じ戦闘方法を採用し、直ちに徐都に強力な攻撃を仕掛けたと想像できる。曹爽は軍事指揮においては司馬懿ほど優れておらず、彼の軍隊は司馬懿ほど訓練されておらず、武装も司馬懿ほど良くなく、軍事力も司馬懿ほど優れていませんでした。そうなると、彼を待っている道はただ一つ、完全な失敗だけだ。 司馬懿が桓範の離脱を気にしなかったのは、まさにその絶対的な軍事的優位性があったからである。司馬懿は軍事力を背景に、甘い言葉で曹爽を誘惑し、より大きな損失を避けるために自発的に軍隊を降伏させることができた。曹爽は自分が失敗するのは避けられない運命だとはっきりと悟っていたため、司馬懿に許されて裕福になれることを望み、司馬懿に降伏した。 結論: 高平嶺の変の際、曹爽の降伏は誰からも批判された。歴史上の記録やいくつかの文学作品の劇的な描写から、曹爽が桓範の助言を受け入れて皇帝とともに徐都へ行けば、事態は好転したと思われる。しかし、現実はそうではありません。 司馬懿の長期にわたる準備と、彼の二人の息子が中央近衛隊で強力な地位を占めていたことによる。事件が勃発すると、司馬懿はすぐに首都の軍隊、兵器庫、洛河の浮橋を掌握し、軍事的優位を確立した。この瞬間から、曹爽とその兄弟たちがいかに奮闘しようとも、司馬懿の目には彼らは壺の中に閉じ込められたままとなった。 曹爽が皇帝とともに徐渡に来て、国中を動員して王を支えても、郭太后の名のため、誰も司馬懿を助けに来ないだろう。彼は各地から兵士を募集し組織して定住と農業を始めましたが、兵士たちの装備や訓練が不十分で時間がかかりました。司馬懿の軍事力を考えれば、曹爽に勝ち目はないだろう。司馬懿は電光石火の戦術を採用し、徐都に突然攻撃を仕掛けた。曹爽はあらゆる面で不利な立場にあったため、失敗する運命にあった。 |
<<: 歴史記録によると、諸葛亮に関して未解決の謎は何でしょうか?
>>: 劉備には多数の文武官がいたのに、なぜ陣営の欠陥に誰も気づかなかったのか?
推薦する
「蘇中清錦・雨上がりの空気は清々しい」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
蘇中清が近い。天気は晴れて爽やかだ劉勇(宋代)雨が止んで空気が新鮮になったので、川の塔の上に立って外...
李白は胡思という隠者を訪ねるために中南山に行き、「中南山を下って胡思を訪ねて泊まり酒」を書いた。
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
商阳の改革は計画的だった!商鞅の改革の目的は何でしたか?
商阳の改革は計画的だった!商阳の改革の目的は何だったのか?興味のある方はぜひ見に来てください。 20...
唐代の詩『西施頌』をどのように鑑賞すればよいのでしょうか? 王維はこの詩をどのような意図で書いたのでしょうか?
唐代の習近平、王維については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!美は世界...
親孝行物語二十四選:親に鹿乳を捧げる話
譚子はわが国の東周時代の譚という小国の王であり、彼の孝行の評判は広く知られていました。両親は高齢で、...
咸陽宮の地理的環境:黄河下流の属国を見渡す
『漢書』と『水経注』によれば、秦の咸陽は渭水の北、荊水の南に位置していた。秦の咸陽城の地形は北が高く...
朱文の養子、朱有文の略歴。朱有文はどのようにして亡くなったのでしょうか?
朱有文(?-912)、号は徳明、本名は康欽、五代十国時代の後梁の初代皇帝朱文の養子であった。朱有文は...
「エリート層の南への移住」とは何ですか?歴史上、「エリート層の南への移住」という出来事はいくつあったでしょうか?
「エリートの南部への移住」とは何かご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。Interesting H...
壁画芸術の起源と発展を探ります。唐代に壁画文化はどのように発展したのでしょうか?
唐代は中国史上最も繁栄し発展した時代の一つで、当時は政治、経済、文化などさまざまな分野で世界の最先端...
曹操の「五大将軍」はいずれも偉大な軍事的功績を残しましたが、彼らの子孫はどうでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
前梁の創始者、張石とはどんな人物だったのでしょうか?歴史は張石をどのように評価しているのでしょうか?
張定(271-320)は、張定とも呼ばれ、字は安勲、安定(現在の甘粛省荊川市)の出身で、十六国時代の...
紅楼夢では、姉妹たちが大観園に集まりましたが、そのうち赤いマントを着ていないのは4人だけでした。
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
「Mountain Home」の作者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
マウンテンハウス劉隠(元代)馬のひずめが水面を踏みしめ、明るい雲が乱舞し、酔った袖が風に向かい、落ち...
張九玲の『情と出会いの詩十二篇第四』:作品の意義は意味そのものをはるかに超える
張九齢(673-740)は、雅号は子首、通称は伯武で、韶州曲江(現在の広東省韶関市)の出身である。唐...
定公七年の儒教古典『春秋古梁伝』の原文は何ですか?
定公七年の儒教経典『春秋古梁伝』の原文は何ですか?これは多くの読者が知りたい質問です。次の興味深い歴...