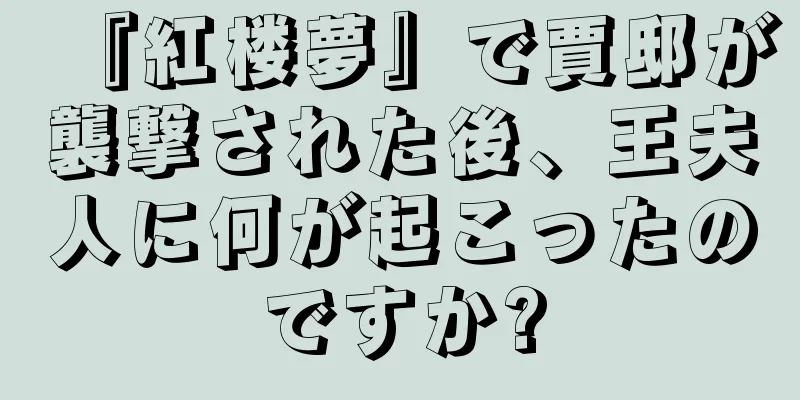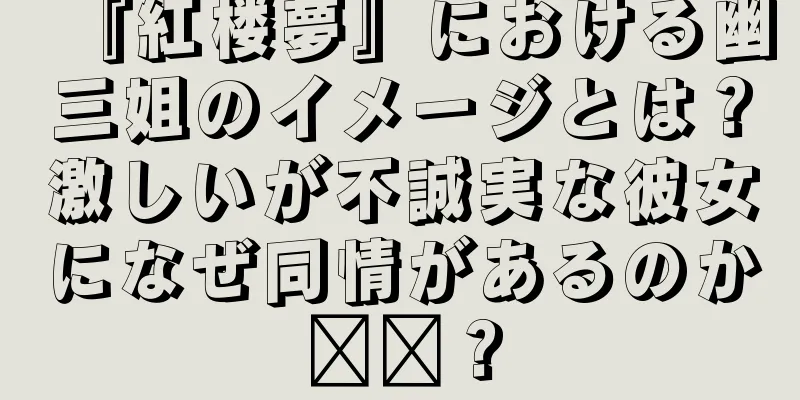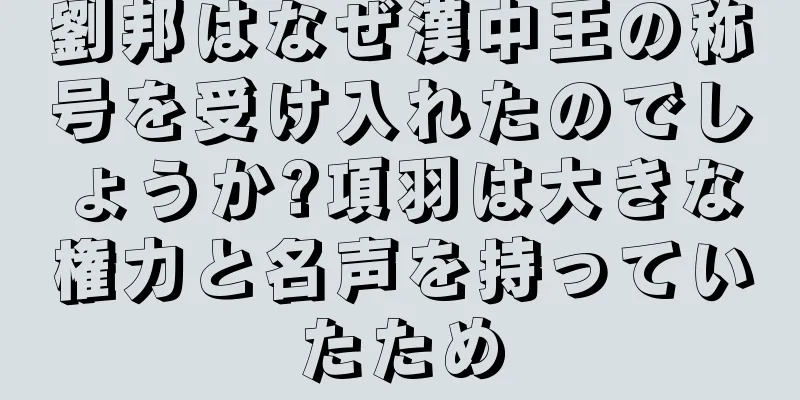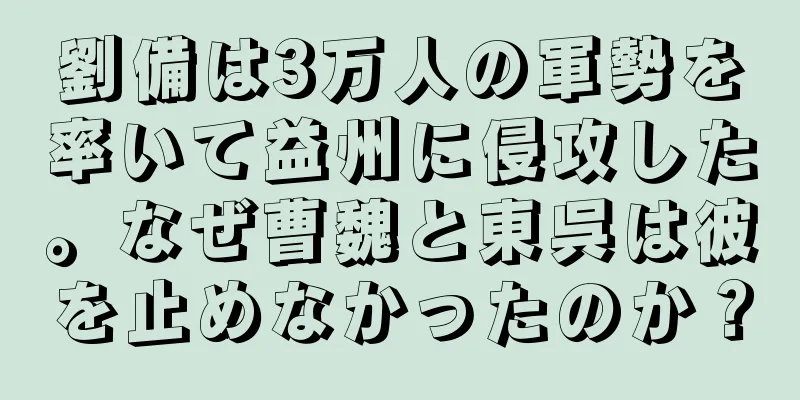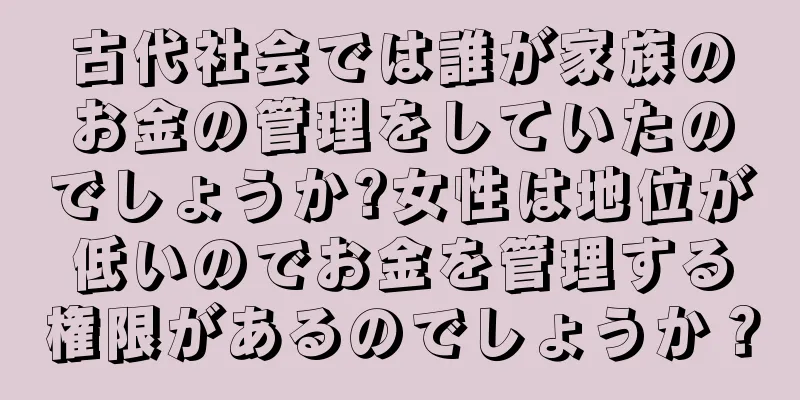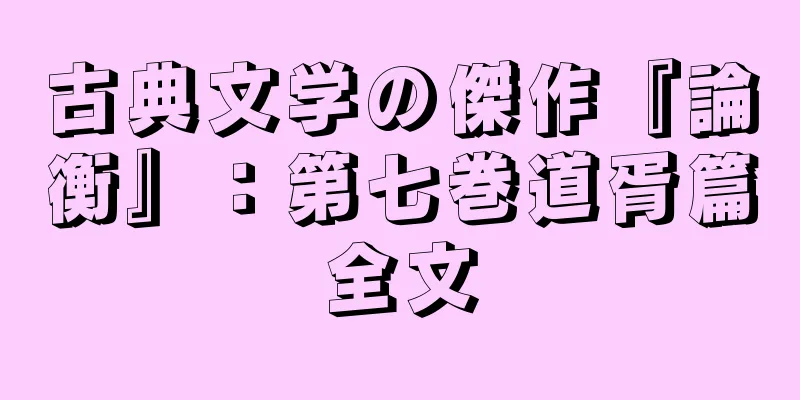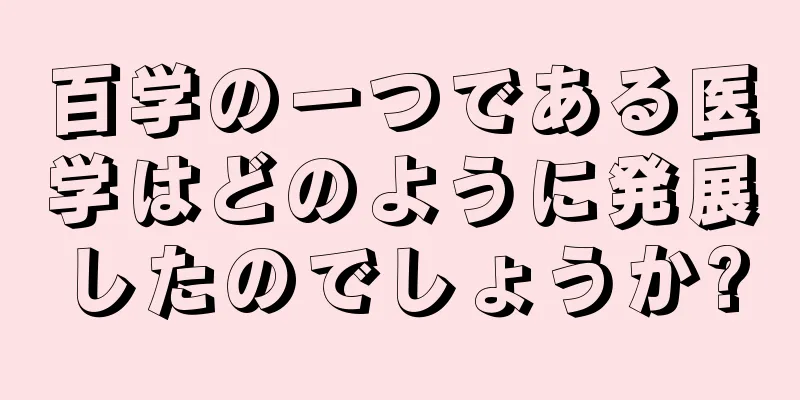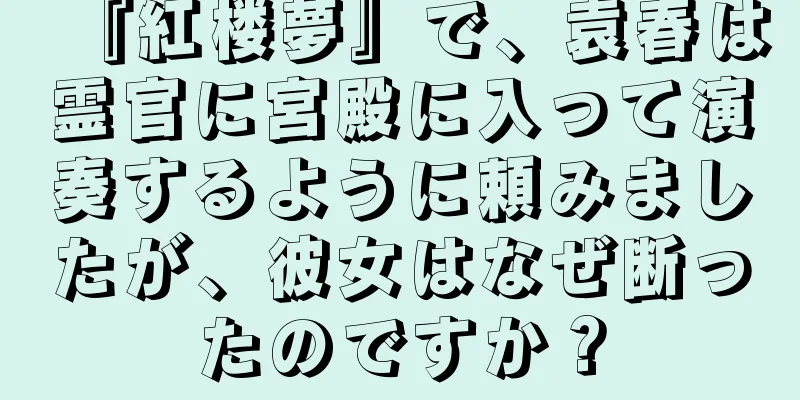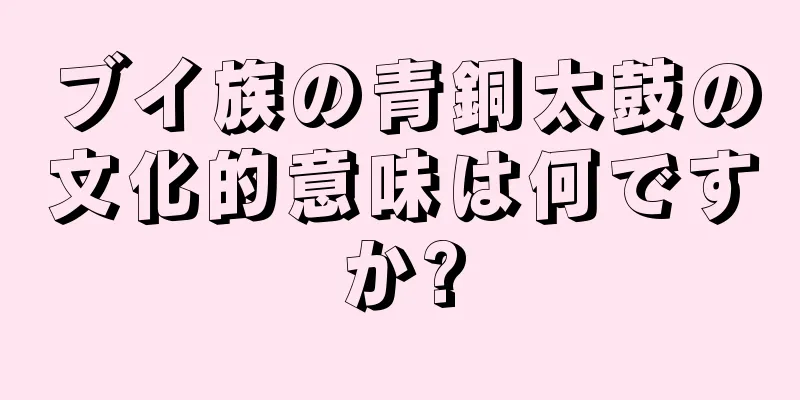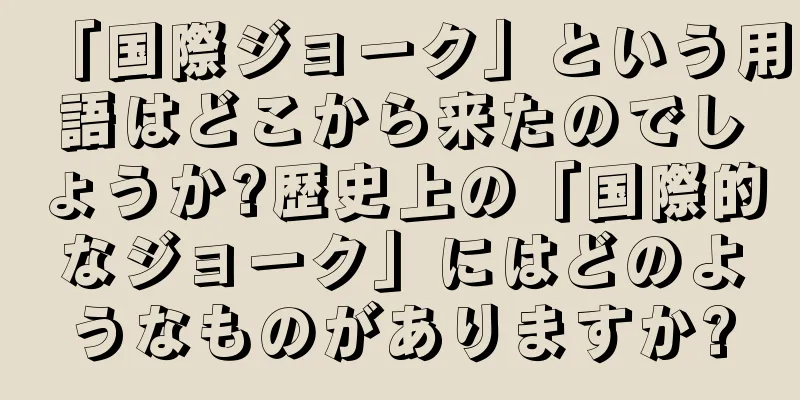郭嘉が生きている限り諸葛亮は出てこないと言われていますが、本当にそうなのでしょうか?
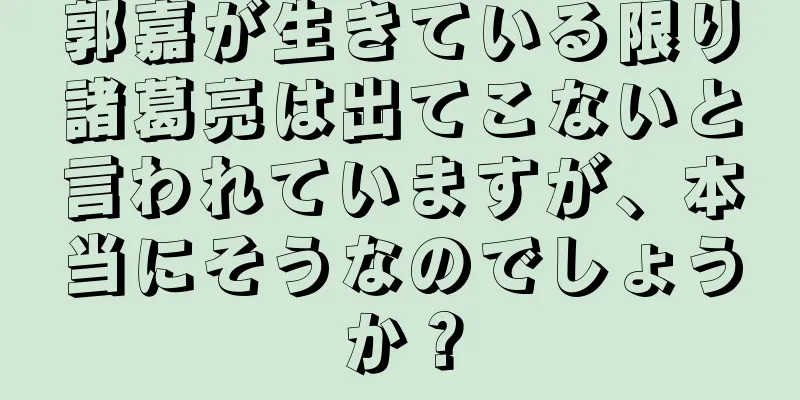
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、郭嘉が死ななければ臥龍は出ないと言う人がいることについて詳しく説明しますが、歴史的事実から見て、この言葉は本当に正しいのでしょうか?見てみましょう! 後世の人々は三国時代の人物について多くのコメントを残しています。曹操陣営の顧問の中には郭嘉を尊敬する者が多かった。中には、郭嘉を諸葛亮と比較し、「郭嘉が死ななかったら、諸葛亮は出なかっただろう」と言う者もいた。郭嘉が早くに亡くなっていなければ、諸葛亮は生まれなかったかもしれないと言っているようです。それで、これは本当にそうなのでしょうか? 1. 郭嘉が死ぬまで諸葛亮が出てこなかった理由。 郭嘉は曹操の重要な戦略家であった。彼は最初袁紹のもとへ行ったが、袁紹が覇権を握れるほどの達人ではないとわかり、去ることにした。この時、曹操の顧問である西之才が亡くなりました。曹操は相談できる顧問がいないので、荀攸に賢人を探すよう頼みました。荀攸は郭嘉を推薦しました。曹操と郭嘉は一目惚れし、そこから二人は共に闘う旅を始めた。 曹操に仕えていた間、郭嘉は曹操の経歴において重要な役割を果たしました。曹操は軍の計画作成を手伝わせるために郭嘉を司空軍の首席学者に任命した。曹操は重要な瞬間に躊躇するたびに、郭嘉と協議した。そして郭嘉は曹操を指導するために全力を尽くします。袁紹が曹操を脅かしたとき、郭嘉は曹操のために両者の違いを分析し、有名な「十勝十敗」の理論を提唱し、曹操の袁紹との戦いに対する自信を強めた。 曹操が呂布と戦っていたとき、呂布は自ら進んで出てこようとしなかった。兵士たちが疲れて撤退しようとしたとき、郭嘉が攻撃を続けるよう曹操に助言し、ついに呂布を倒した。孫策が許都を攻撃する準備をしていたとき、郭嘉は孫策が暗殺者の手で必ず死ぬだろうと判断し、曹操の不安を和らげた。 郭嘉は袁紹との戦争でも多くの優れた戦略を立案した。袁紹の死後、曹操は状況を利用して河北を攻撃した。何度も勝利した後、郭嘉は曹操に撤退を勧めた。彼は、袁紹の二人の息子、袁譚と袁尚が互いに譲り合うつもりはないと考えたので、攻勢を緩めて二人で戦わせるべきだと考えました。そして、お互いを弱体化させることを前提に攻撃します。これは郭嘉の有名な言葉です。「物事を急ぐと、両者は膠着状態に陥ります。ゆっくりすると、戦いたいという欲求が生じます。」この主張は、三国時代のさまざまな闘争の中で繰り返し真実であることが証明されました。 案の定、曹操が軍を撤退させた後、両元は冀州の支配権をめぐって内紛を起こし、曹操は河北を容易に平定することができた。その後、曹操は三郡の袁尚と五環を攻撃した際、郭嘉の助言に従って軽快に進軍し、予想外に白浪山で敵の主力部隊を壊滅させ、大屯禅于を戦死させた。袁尚と袁熙が遼東に逃げた後、郭嘉はすでに病死していた。しかし、曹操は郭嘉の意志に従い遼東を攻撃せず、遼東の分離派軍である公孫康が両元を殺害して降伏することを許した。 郭嘉の生涯から判断すると、彼は確かに優れた戦略家であった。曹操によれば、郭嘉は曹操が決断できなかった事柄について決断を下すのを手伝うことができたという。残念なことに、郭嘉は若くして病気で亡くなり、曹操は非常に悲しみました。彼はまた、自分の将来のことを郭嘉に託したいと部下たちに伝えた。 諸葛亮の功績はさらに広く知られています。劉備が三度諸葛亮の別荘を訪れ隠遁生活から抜け出すよう求めて以来、諸葛亮は劉備のために尽力してきた。劉備一派の戦略策定において、諸葛亮は有名な「龍中の策」を提唱した。彼は北で曹操に抵抗し、東で孫権と和平を結び、荊と邇を占領して時を待つことを提案した。機会が訪れると、劉備の一行は漢王朝を支援し、漢王朝を再建するために2度の北伐を発足させた。 諸葛亮の「龍中の策」はかなり複雑ですが、これは劉備が弱すぎたためです。諸葛亮が劉備の援軍に現れたとき、劉備はキャリアの中で最もどん底にいた。当時、劉備の兵力は1000人にも満たず、張と趙雲以外の将軍はいなかった。諸葛亮の援助と「龍中の策」の指導により、劉備の権力はますます強大化し、最終的に蜀漢政権を樹立しました。劉備の死後、諸葛亮は白帝城で劉備の息子の世話を任された。蜀漢政権が混乱していたとき、流れを変えたのは諸葛亮でした。彼は孫権と和解し、軍隊を再建し、内乱を鎮圧し、経済を発展させた。彼は生涯に5回にわたり曹魏に対して北伐を行い、死ぬまで蜀漢政権に人生を捧げた。 郭嘉と諸葛亮が結び付けられ、郭嘉が死ぬまで諸葛亮が表に出なかった主な理由は 2 つあります。第一の理由は、郭嘉が生きていた時代には諸葛亮は登場しなかったことです。しかし、郭嘉が死ぬと、諸葛亮が劉備の援軍として現れたが、これは偶然のようだ。これは、もし郭嘉がまだ生きていたなら、諸葛亮は隠遁生活から抜け出すことを選ばなかったであろうことを示しているようだ。 2つ目の理由は、曹操が赤壁の戦いで敗北した後、郭嘉が生きていたら、このような悲惨な敗北を喫することはなかっただろうと嘆いたことです。したがって、郭嘉が死ななかったら、曹操は赤壁の戦いで敗北することはなかったでしょうし、劉備と孫権もおそらく滅んでいたでしょう。詩にあるように、「東風は周朗に不利で、春の終わりに喬姉妹は銅雀楼に閉じ込められている。」そうなると諸葛亮が引退から復帰しても劉備の役には立たないのではないか?しかし本当にそうだろうか? 2. 郭嘉の死と諸葛亮の隠遁生活との関係。 実のところ、郭嘉の死は諸葛亮の隠遁生活とは何の関係もなかった。郭嘉は亡くなったときまだ38歳だった。彼の死因は病気であり、完全な事故だった。郭嘉の死後の葬儀で、曹操は荀攸らに「我々は皆同世代であり、郭嘉は末っ子だ」と言った。わたしは、世が平定するまで郭嘉に仕事を任せようと思っていたが、彼がこんなに早く亡くなるとは誰が知っていただろうか。これはまさに運命だった。 したがって、病気がなかったら、通常の状況であれば、郭佳はもっと長く生きることができていたはずです。そうなれば、隠遁から出てきた諸葛亮に出会う可能性も高くなる。諸葛亮は当時何をしていたのでしょうか? 諸葛亮の初期の人生に関する歴史的記録は詳細ではない。わかっているのは、彼が叔父を追って荊州に定住し、黄承燕の娘と結婚したということだけだ。諸葛亮は広範な社交関係を持っていたため、荊州で明るい未来を築くことができたかもしれない。彼の叔父は劉表と古くからの付き合いがあったため、当然劉表の世話になった。劉表の妻と義母は姉妹で、二人とも地元の裕福な家である蔡氏の一員であった。義母の弟である蔡茂は荊州で軍事力を握っていた人物であった。 諸葛亮の二人の姉妹のうち一人は、地元の別の名家である開艺一族の開斉と結婚し、もう一人は地元の名士で龐統の従兄弟である龐徳公の息子である龐山民と結婚した。こうした複雑な社会的関係から判断すると、諸葛亮も荊州の上流社会の一員であったと考えられます。このことは、劉表の長男である劉琦が諸葛亮を高く評価していたことからもわかります。 しかし、諸葛亮は荊州で官職に就くことを望まず、世を離れて田畑を耕していた。諸葛亮が毎日『良夫の歌』を歌うのを好み、自分を管仲や岳夷と比較していたことから、これが諸葛亮の真意ではなかったことがわかります。これは主に諸葛亮が劉表のグループに不満を抱いており、彼らのために働くことを望まなかったためである。一方で、彼は研究し人々を訪問することで知識を豊かにし、他方では、適切な時期と自分が仕える領主を待ちました。 郭嘉が曹操に同行して河北を平定したとき、劉備も荊州に避難した。劉備が賢者を探し、自らを強化していた一方で、諸葛亮も彼を観察し、試していた。劉備が諸葛亮の別荘を三度訪れた後、諸葛亮はついに劉備に会いに現れ、彼の戦略計画「龍中の策」を劉備に提示した。 「龍中の策」を注意深く研究すると、その構造は比較的複雑で実行が難しいものの、劉備一派が採用できる唯一の戦略計画であることがわかります。そして、この計画は実行中に予想外の紆余曲折に遭遇したものの、最終的にはほぼ成功しました。 『龍中兵法』では、諸葛亮は当時の世界の各勢力の情勢について的確な判断を下した。 諸葛亮は劉備の内部事情もよく知っていた。北伐の際には関羽のために重要な地位を確保した。これは関羽の性格と感情を考慮して特別に作られています。この点から、劉備が諸葛亮を訪ねる前に、諸葛亮も劉備を観察していたことがわかります。諸葛亮は劉備を認めた後、劉備が彼の別荘を三度訪れた際に、劉備を助けるために出向いた。 そのため、郭嘉が亡くなる前、劉備と諸葛亮は互いに訪問し、観察し合っていた時期であった。諸葛亮が隠遁生活から出てきたことは郭嘉とは何の関係もなかった。たとえ郭嘉が病死しなかったとしても、劉備は郭嘉の別荘を三度訪れなければならなかったし、諸葛亮も「龍中の計」で忠告し、劉備を助けるために出向く必要があっただろう。 3. 郭嘉の生存が赤壁の戦いに与えた影響。 では、2番目の理由、つまり郭嘉が死んでいなかったら赤壁の戦いの結果に影響があったかどうかを見てみましょう。赤壁の戦いの後、曹操は郭嘉が死ななかったら、このような壊滅的な敗北を喫することはなかっただろうと嘆いた。しかし、もし本当に郭嘉が生きていたなら、曹操は赤壁の戦いで敗北を免れたでしょうか?私はそうは思いません。 曹操は赤壁の戦いで敗北した後、自らの経験と教訓を総括していました。彼が郭嘉を嘆いたのは、郭嘉の有名な言葉「物事を急げば双方は膠着状態に陥る。物事を緩めれば戦闘意欲が湧く」を思い出したからである。この主張は河北の袁兄弟を鎮圧する戦争や遼東を鎮圧する戦いで非常に効果的でした。しかし、赤壁の戦いの際、曹操はこの発言を忘れてしまった。 当時、曹操は荊州を難なく占領し、当陽の長阪坡で劉備を破り、劉備の主力歩兵部隊を壊滅させた後、次の戦略行動で成功を収めることに意欲を見せた。江夏に逃げた劉備軍と東呉に陣取った孫権軍に直面した曹操は、一挙に彼らを殲滅しようとした。 彼は姻戚関係にある孫権に手紙を書き、脅迫によって孫権を降伏させることを望んだ。彼とその部下たちは、降伏の見返りとして孫権が劉備を攻撃するのではないかとさえ妄想した。曹操が最終的に直面することになるのが孫・劉連合軍の抵抗だとは誰が知っていただろうか。曹操はこのような状況に事前に備えていなかったため、最初から不利な状況にありました。結局、曹操は赤壁の戦いで大敗し、三国志の基礎が築かれました。 郭嘉がまだ生きていたなら、河北の袁兄弟や遼東の公孫康に対してしたように、劉備と孫権をどう扱うべきか曹操に間違いなく助言を与えただろう。彼は曹操に、孫権に圧力をかけないように劉備への攻撃を延期するよう進言した。曹操は荊州で戦略的な防御に切り替え、軍隊を休ませて再編成し、荊州での勝利の成果を消化した。孫権と劉備が対立して戦い始めたとき、曹操は彼らを滅ぼすために軍隊を派遣しました。もしそうなら、曹操の状況はずっと良くなるだろう。 しかし、郭嘉氏の提案が実行可能かどうか疑問視する要素が 2 つあります。第一の要素は、曹操が郭嘉の助言を採用するかどうかです。曹操の郭嘉に対する評価を見ると、曹操は決断できないときには郭嘉の助けを頼るだろう。つまり、曹操が決定を下した場合、郭嘉がそれを変更するのは難しいということです。 赤壁の戦いは曹操によって決着した。世の中には、結果からその起源を推測できるものがたくさんあります。赤壁の戦いの失敗後、曹操が部下を戦闘から休ませず、すぐに東呉に対する軍事作戦を開始するのは危険な行動だと誰もが考えたことがわかります。しかし、曹操の脅迫が成功すれば、孫権は張昭らの圧力により曹操に降伏することになる。曹操が孫権と劉備の軍を一撃で滅ぼしたとしたら、我々は曹操の迅速に決断し戦い続けた精神を称賛するだろう。 したがって、赤壁の戦いの前に曹操の選択は理にかなったものだった。曹操は戦争の進展を早める希望を見出して、赤壁の戦いを開始した。曹操はすでに決心していたので、郭嘉が説得しても無駄だろう。こうすれば、赤壁の戦いは依然として勃発し、曹操は敗北することになる。 2つ目の要素は孫家と劉家が争うかどうかだ。もし曹操が郭嘉の助言を採用していたら、赤壁の戦いは避けられたかもしれないが、曹操が想像していたような孫権と劉備の戦いは必ずしも起こらなかっただろう。これは孫権と劉備の陣営が袁の陣営ほど近視眼的ではなかったためである。劉備陣営の諸葛亮と孫権陣営の魯粛は同盟を結ぶことを決意した。彼らの努力により、孫・劉同盟は確実に形成され、維持されるだろう。 孫権と劉備はともに天下を気にかける君主であり、曹操を最強の敵とみなしていた。曹操は荊州を占領した後、揚子江の上流域を占領したため、孫権と劉備の双方にとって大きな脅威となった。当時、劉備は江夏に、孫権は江東におり、両者は相互依存関係にあった。たとえ曹操が戦争を始めなかったとしても、彼の大きな脅威が孫と劉の同盟の根拠となった。さらに、両家は戦略目標を達成するために荊州を占領したいと考えていました。そのため、荊州を占領したことで曹操は双方の共通の敵となった。 このような状況では、郭嘉が想像した孫文と劉文の連合軍が互いに戦うという状況は、短期的には発生しないだろう。それどころか、曹操は孫・劉の連合軍に攻撃されるかもしれない。孫氏と劉氏は自らの戦略的安全を確保するために、上流の荊州を奪還しなければならなかった。彼らは曹操がまだ確固たる地位を築いておらず、勝利の成果を消化する時間もないうちに反撃を開始した。そうでなければ、曹操が足場を築けば、孫劉同盟にさらに大きな軍事的圧力をかけることになるだろう。 この二つの要因により、たとえ郭嘉が生きていたとしても、孫劉連合と曹操との戦争を止めることはできなかっただろう。彼が採用しようとした戦略は、諸葛亮と魯粛の存在、そして劉備と孫権の戦略的ビジョンのせいで実現できなかった。したがって、曹操と孫劉連合との戦争は避けられなかった。もし赤壁の戦いが起こらなかったら、孫劉連合は曹操に対して攻勢を開始していただろう。結局、曹操は失敗を避けることができなかった。 結論: 「郭嘉は死なず、諸葛亮は出ず」には二つの意味しかありません。まず、諸葛亮は郭嘉の死後に初めて劉備の援軍として現れた。諸葛亮の出番は郭嘉の存在にかかっているようだ。第二に、曹操が言ったように、もし郭嘉が死ななかったら、曹操は赤壁の戦いで敗北することはなかっただろうし、諸葛亮に助けられた劉備は壊滅的な災難に見舞われていただろう。歴史的な観点から分析すると、どちらの意味も間違っていることがわかります。 最初の意味は誤りです。なぜなら、郭嘉の死は諸葛亮の隠遁生活とは無関係だからです。郭嘉の死は事故だった。彼はわずか38歳で病気で亡くなった。郭嘉が死ぬ前に、諸葛亮と劉備はお互いを捜し求め、調査し始めました。郭嘉が死んだかどうかは関係なく、劉備が諸葛亮の別荘を三度訪れ、隠遁生活から抜け出すよう求めるのを阻止することはできなかった。 2 番目の意味は誤りです。なぜなら、たとえ郭嘉が死ななかったとしても、慢心した曹操が赤壁の戦いを開始するのを止めるのは困難だったでしょう。さらに、曹操が郭嘉の助言に従って劉備と孫権に対して軍事行動を起こさなかったとしても、孫劉同盟の成立を阻止することはできなかった。結局、水軍を欠いた曹操は孫・劉連合軍の攻撃によって敗れた。ただ、孫・劉連合軍は一息ついた分、赤壁の戦いの時よりも強くなっているだろう。こうなると曹操はさらに惨めな敗北を喫することになる。しかし、もし郭嘉が死ななかったら、彼は諸葛亮と同じ戦場で戦い、私たちの子孫にもっとエキサイティングな歴史を残したでしょう。 |
<<: 関羽は、夏侯惇が何千マイルも一人で馬に乗っていたときに、なぜ殺さなかったのでしょうか?
推薦する
黄庭堅は6歳の時に詩を書きました。最後の2行は考えさせられる内容です。
本日は、Interesting Historyの編集者が黄庭堅の物語をお届けし、皆様のお役に立てれば...
『紅楼夢』で賈夫人と王希峰は宝釵をどのように見ているのでしょうか?
宝仔は『紅楼夢』のヒロインの一人で、林黛玉とともに金陵十二美女の第一位に数えられています。今日、興味...
『紅楼夢』では、薛宝才が一晩中一人で泣いていました。何が起こったのですか?
薛宝才は『紅楼夢』のヒロインで、林黛玉と並ぶ存在です。今日は『おもしろ歴史』の編集者が記事をお届けし...
残りのモンゴル軍が南下する機会を逃すのを防ぐために、明朝はどの 9 つの重要な軍事都市を設立しましたか?
九辺鎮は、明代に国境防衛線に沿って設置された9つの重要な軍事鎮であり、古代の万里の長城のもう一つの重...
「彭公安」第171話:龍のローブを失った皇帝の使者が手紙を見て古い真実を語り、于家荘で大騒ぎを起こす
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
皇帝の物語:もし項羽が呉江で自殺していなかったら、再起できたでしょうか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
厳吉道の「清平楽・小煙小雨」:春と別れの悲しみを詠んだ詩
顔継道(1038年5月29日 - 1110年)は北宋時代の有名な詩人である。名は書源、号は蕭山。福州...
「梅雨」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
梅雨杜甫(唐代)南京の西浦路では、4月に黄色い梅が実ります。澄んだ揚子江が流れ、霧雨が降る。茅葺き屋...
西周時代の通貨の特徴は何ですか?西周時代の貨幣の分析
諺にもあるように、お金は世界を動かすものです。これはどの王朝でも同じです。では、西周王朝で使用されて...
「紅楼夢」で賈一家は皇帝の疑いを避けるために何をすべきでしょうか?
『紅楼夢』では、賈一族の没落が一連の悲劇を引き起こした。賈一族の没落により、金陵十二美女の人生は基本...
七剣十三英雄第38章:孫堅は金のために別れることを嫌い、沈立全は銀貨を捨てようと企む
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
前漢の時代に異族の権力はどのようにして生まれたのでしょうか?実際、問題を引き起こしているのは権力のすべてである
劉邦が亡くなると、漢の恵帝・劉嬰は弱体化し、呂后が政権を握りました。呂后は劉家をより良く統制するため...
飛龍伝全集第4章:父の血の復讐のため、雹が宮廷を襲う
本日は、Interesting History 編集者が『飛竜全伝』第 4 章の全文をお届けします。...
本草綱目第8巻「サボテン草」の具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
明代の読書本『遊学瓊林』:第3巻 貧富 全文と翻訳注釈
『遊学瓊林』は、程雲生が書いた古代中国の子供向けの啓蒙書です。 『遊学瓊林』は、明代に西昌の程登基(...