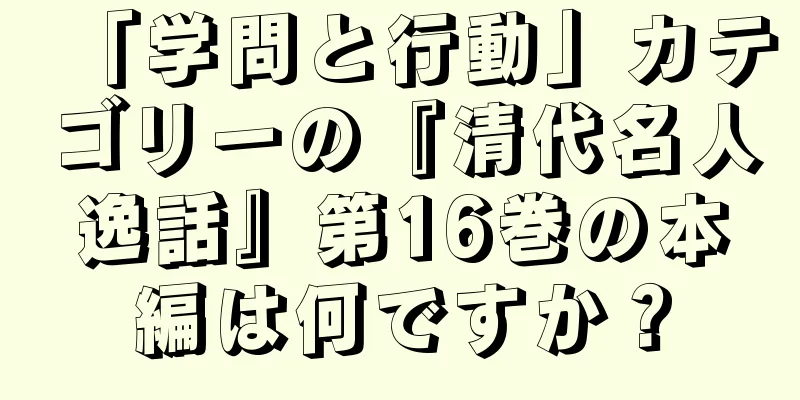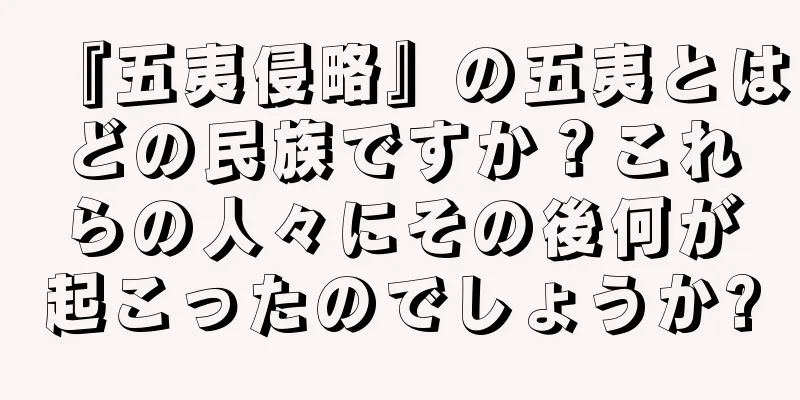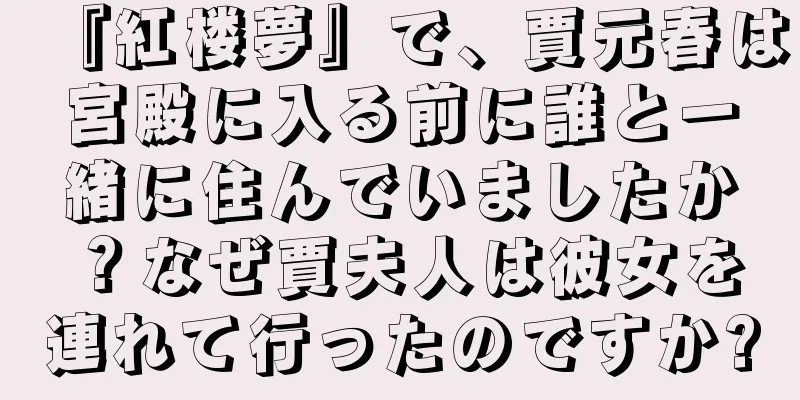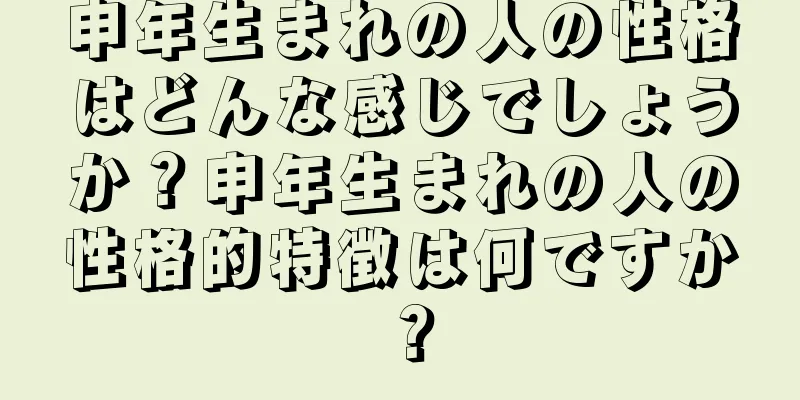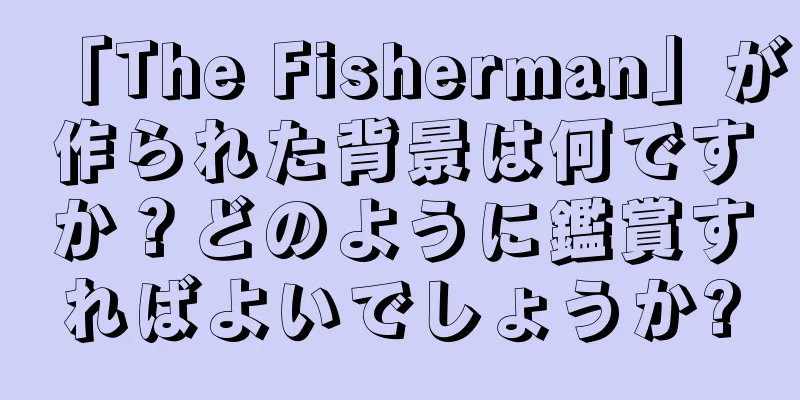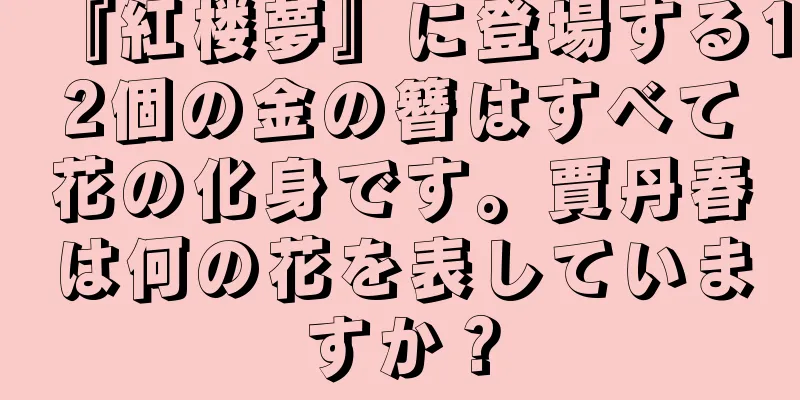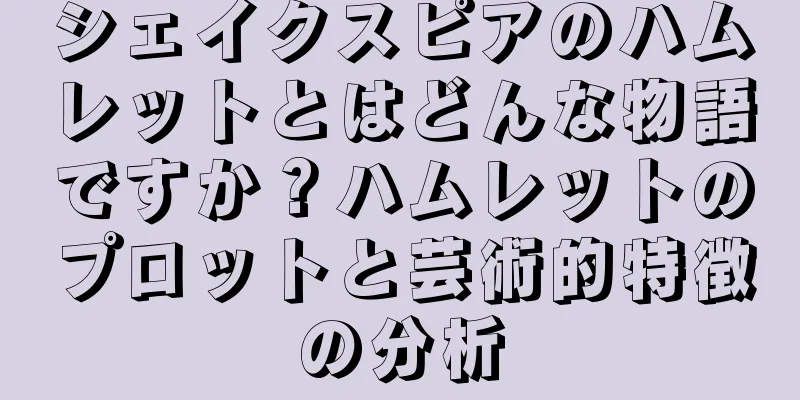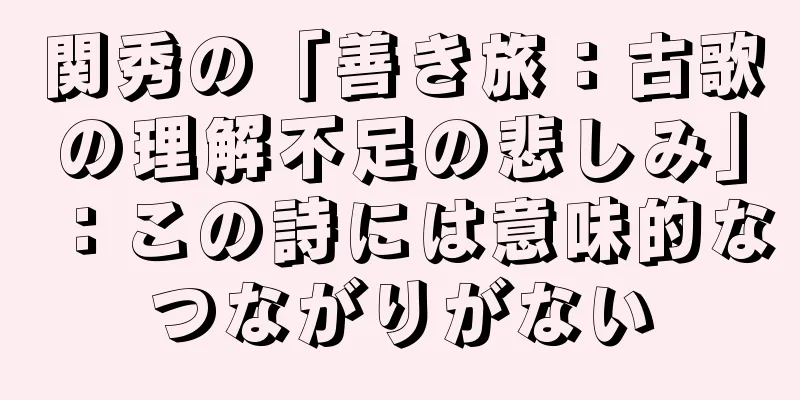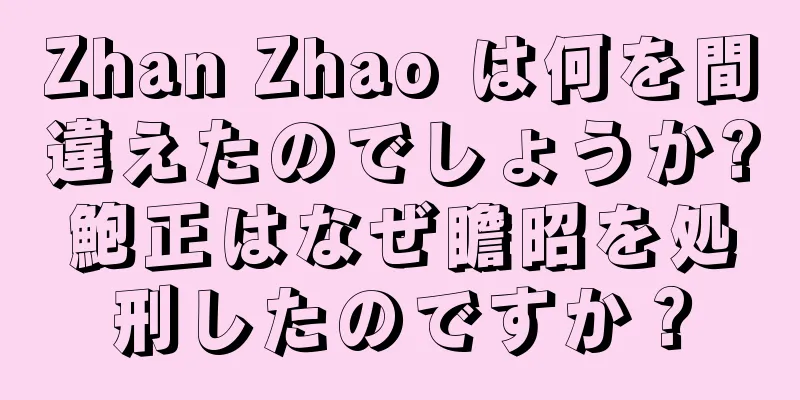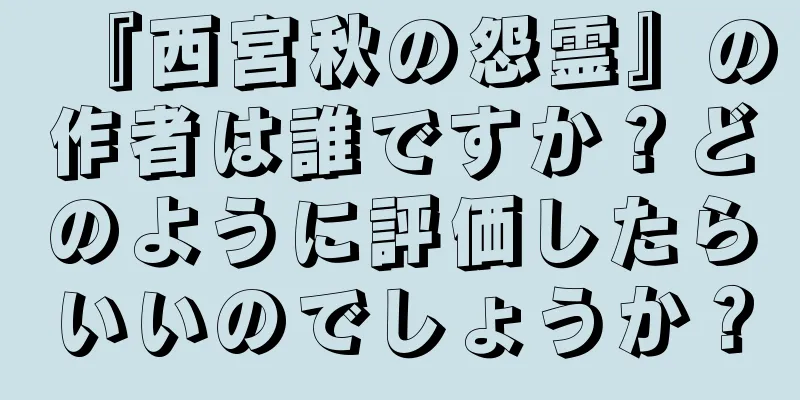古代の人々は七夕をどのように祝ったのでしょうか?古代の男性と女性は中国のバレンタインデーをどのように祝ったのでしょうか?
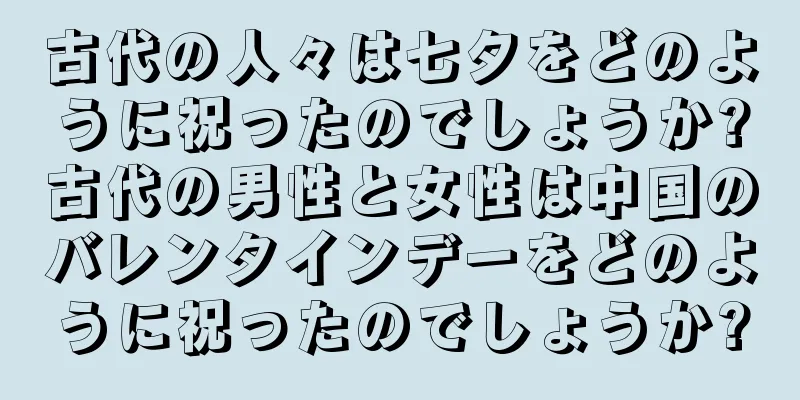
|
「七夕」とは、旧暦の7月7日を指します。民間の伝説によると、この日は牛飼いと織姫がカササギ橋から天の川を渡って出会う日です。七夕祭りは「七橋」とも呼ばれています。人々の心の中で、織姫は優しくて美しくて器用な仙女です。そのため、7月7日の夜、女性、特に未婚の女性は織姫に「器用さを乞う」必要があります。そうすれば、自分も賢い心と器用な手を持つことができます。そのため、長い年月を経て、中国のバレンタインデーは次第に「幸せな愛」と「巧みな手腕」という2つの意味を帯びるようになり、近年ではこの日は「中国のバレンタインデー」とも呼ばれています。 2006 年 5 月 20 日、中国のバレンタインデーは国務院によって正式に国家無形文化遺産リストの第一陣に含まれました。人々はこの日に中国のバレンタインデーを記念し、祈りを捧げますが、多くの場合、「精神」と「巧みさ」という2つのテーマを中心に、さまざまな記念形式と民間活動が形成されています。特に古代においては、こうした習慣は非常に豊かで多彩なものでした。 七橋祭 七渓の民俗行事をみると、そのほとんどは七渓の民俗習慣の2つの大きなテーマである「技能の乞食」と「結婚と恋愛」と密接に結びついており、七渓の民俗習慣のほとんどすべてがこの2つのテーマから発展した習慣であると言えます。同時に、この2つのテーマは女性と密接な関係があるため、七夕の民間記念活動の主体は若い女性です。そのため、七夕は中国の伝統的な祝日では「娘の日」または「女性の日」と呼ばれています。清代のアルバム『月満清遊図』は、1年12か月間の裕福な家庭の女性たちの貴族生活を描いています。 「桐の木の下で技を乞う」と題された絵画の一つは、北京の「七夕」の風習を描いている。絵全体は、旧暦7月7日に北京の女性たちが手先の器用さを乞う場面を詳細に描いている。旧暦7月の夜、女性たちは水盤に水を満たして庭に置き、その中に針の束を撒く。人々は水にできる模様を見ようと駆け寄る。模様の形が美しいほど、針を撒く人の手先の器用さが優れていると言われている。これは清朝時代のバレンタインデーに流行した「手先の器用さを祈る針投げ」で、「手先の器用さを祈る針投げ」とも呼ばれています。裁縫に関わる「七劫」活動は最も重要な位置を占めています。主なものとしては、「蜘蛛の糸で器用さを乞う」「針に糸を通し器用さを乞う」「針を投げて器用さを乞う」「蘭の夜に器用さを乞う」などがあります。 知恵を乞う蜘蛛 『荊楚隋史記』には、「7月7日はアルタイルとベガが出会う夜である。その夜、女性たちは絹糸を結び、七つ穴の針に糸を通したり、庭に酒、干し肉、メロン、果物を並べたテーブルを設えて手先の器用さを祈る。メロンに蜘蛛の巣があれば幸運の兆しとされる」と記されている。蜘蛛は小さな蜘蛛を指す。唐の劉延石の『七夕歌』には「青空は露に濡れ、花から蜘蛛の糸を乞う」とある。杜甫も詩『牛飼いと織女』の中でこの風習について「蜘蛛の糸は小さな人の形をしており、瓜や果物と絡み合っている」と書いている。宋代の『東景夢花録』には「女性は月を見て針に糸を通したり、小さな蜘蛛を受精卵に入れたりする。翌日それを見て、巣が丸くてまっすぐなら幸運だ」とある。 「幸せな蜘蛛は賢さに応えます」または「蜘蛛の糸が賢さを乞う」は、唐代に流行した賢さを乞う方法です。女性はバレンタインデーの夜に蜘蛛(幸せの種とも呼ばれる)を捕まえ、事前に用意した小さな箱に入れます。翌朝早く箱を開け、蜘蛛が一晩で編んだ糸を事前に設定された基準に従って評価し、どれだけ賢くなったかを判断します。この習慣はおそらく南北朝時代に始まったものと思われます。五代の王仁宇の『開元天宝易志』には、「7月7日、皆で蜘蛛を小箱に入れて夜明けに開ける。蜘蛛の巣の密度は幸運の兆しと考えられている。巣が密であればあるほど幸運が多く、疎であればあるほど幸運が少ない。人々もこのルールに従っている」と記されている。後世では運を測る方法が少し異なっていた。南北朝では巣の有無を見ていたが、唐代では巣の密度を見ていた。宋代では巣の丸さを見ていた。後世は主に唐代の習慣に従った。 知恵を乞う蜘蛛 針に糸を通す 周沐の『風徒記』には「七月七日、夜、庭を掃き、露の中にいくつかの宴席を設け、酒、干し肉、季節の果物を並べ、宴席に香粉を撒いて、合谷(アルタイル)と織姫を祀る」とある。唐の詩人祖庸の「七夜求技」には「娘が天女に祈るが、夜遅くまで心は終わらない。玉庭に粉敷を広げ、絹の袖に金の皿を握る。月に向かって針に糸を通すのは簡単だが、風に逆らって糸をまっすぐにするのは難しい。誰がより上手いかはわからない、明日にしよう」とある。針に糸を通し、技を祈る人は、色のついた糸を使って針に糸を通し続けることで、七つ穴の針や九つ穴の針に糸を通すことができる。 「瑞翁丹禄」:「実はこの針は使えません。針は細くて穴が大きいのです。」 「針に糸を通し、技巧を祈る」というのは、技巧を祈る昔ながらの方法の一つです。まず、二穴、五穴、七穴、九穴など、技巧を祈るためのさまざまな針を作ります。そして、旧正月の夜に、若い女性が手に絹糸を持ち、月明かりに向かって針に糸を通します。最初に糸を通した人が「幸運の人」です。針に糸を通すことで器用さを乞う習慣は、漢代にまで遡ります。この習慣に関する最も古い記録は、東晋の葛洪の『西都雑記』にあります。「漢代の色とりどりの女性たちは、7月7日によく襟開きの塔に七つ穴の針に糸を通し、人々はそれに慣れていました。」南朝の『荊楚随氏記』にも、「7月7日は牛飼いと織女が集まる夜である。その夜、家族の女性たちは色とりどりの塔を立て、七つ穴の針に糸を通した。」と記録されています。 5つの王朝の王レニューは、Qixiフェスティバルでカラフルなパビリオンを録音しただけでなく、脱deのために懇願するための針を読む競争のルールを含めて、「カイユアンTianbao Yishi」に詳細に記録しました。それは果物、ワイン、ローストした食べ物で飾られており、牛と女の子の2つの星を崇拝しています。 Qixi Festivalの器用さを求める場所。 針に糸を通す 針を投げる 『燕京隋史記』には次のように記されている。「七月七日、都の女たちは鉢に水を張って太陽に当て、小さな針を水の中に投げ入れる。そしてゆっくりと水底に映る太陽の影を観察する。それは花のように散らばっていたり、雲のように動いていたり、糸のように細かったり、針のように太かったりする。影を見て女の賢さや不器用さを占う。一般に『針を投げる』という。」あるいは『賢い針を投げる』とも呼ばれる。清代の詩人、呉曼雲は『江湘節詩』の中で、「私は毎年北の隣人と針に糸を通し、また自分の裁縫の腕を試している。龍の杼の影を一人で見る者はいるだろうか。私は誰も助けずにオシドリを刺繍することができる。」と書いている。 時代の発展とともに、技を乞う形式も進化してきました。女の子たちは「針に糸を通し技を乞う」だけでなく、「針を投げて技を試す」こともあり、これは「針を投げて技を占う」や「針を投げて技を占う」とも呼ばれ、「針に糸を通し技を試す」という民俗風習のバリエーションとも言えます。手順は次のとおりです。旧正月の正午に、きれいな水を入れた水盤を屋外の太陽の光の当たる場所に置きます。しばらくすると、水面に浮かぶほこりが薄い膜を形成します。この時、針を水の上に置きます。薄いフィルムのサポートにより、針は水に浮き、沈みません。水面にさまざまな針の影や波紋が現れます。花や雲、鳥や動物などの形が現れたら幸運を意味します。逆に、影が糸のように細かったり、ハンマーのように太かったりする場合は、その技を習得していないことを意味します。この習慣は明朝と清朝の時代に特に人気がありました。 「首都の景色の簡単な説明」の記録は、王王朝のYu Yizhenによると、上記のスキルのテストの具体的な再現です。「7月7日に女性が太陽の水を露出させますS、花、鳥、靴、ハサミ、または水のえみの形をとる人もいます。彼らの作品の不器用さをテストするための影、そして夜に彼らはまだスキルのためにウィーバーの少女に祈ります。」清代の于民中の『日夏九文考』に引用されている『万書雑記』は、上記の技能試験の過程をさらに裏付けている。「七月七日に、燕都の女性たちは、水を張った鉢に太陽を当て、それぞれが小さな針を水面に投げ込み、ゆっくりと水底の太陽の影を観察した。花のように散らばっているものもあれば、雲のように動いているものもあり、糸のように細いものもあれば、錐のように太いものもあった。そのため、これを使って女性の技能を占ったのである。」 5月の端午節やバレンタインデーには、インパチェンスの花を叩いて爪を赤く染めるという民間習慣があります。例えば、『燕京随氏記』には、「ツルニチニチソウは、貫骨草とも呼ばれ、爪草とも呼ばれる。5月に花が咲くと、閨房の娘たちはそれを取って叩いて爪を染める。鮮やかな赤色は骨に浸透し、何年も持続する」とある。また、洪良基の『十二ヶ月詞第7』には、「七月七日、明け方に化粧をし、牛飼い寺で香を焚く。東方の家の娘が仕事を終え、爪を花のように赤く染めるのを見たことがないか。ジャスミンの花を旗印にかぶり、髪に香りを漂わせている」とある。 中国のバレンタインデーに爪を染める習慣は今でも広く普及しており、この習慣は四川省、重慶市などの南西部のほか、貴州省や広東省でも行われている。多くの地域で、若い女性は祭りの時に水に混ぜた樹液で髪を洗うのが好きです。伝説によると、これは彼女たちを若く美しくするだけでなく、未婚の女性ができるだけ早く理想の夫を見つけるのにも役立つと言われています。花や植物で爪を染めることも、祭りの期間中の多くの女性や子供たちの趣味であり、豊穣の信仰と密接に関係しています。 マリーゴールドの花びらで爪を染める習慣は、今でも田舎で見ることができます。インパチェンスの花びらとミョウバンを適量取り、ボウルに入れてペースト状になるまで潰します。用意したペーストを少量取り、爪に塗ります。桑の葉など適度な通気性のある葉で指を包み、綿糸で結びます。翌日開けてみると、爪が赤くなっていました。指を包むときは、布切れやビニール袋を使うのではなく、桑の葉など、通気性のよい葉を選びましょう。これは主に、布切れは通気性が高すぎて、ペーストがすぐに乾燥してしまうためです。ただし、指をビニール布で包むと通気性が悪くなり、不快感を感じることがあります。 『東京孟化録』には「蘇州の麻虎薇は極めて精巧で、木渡の袁氏の作るものはさらに精巧である」と記されている。宋代、蘇州虎丘に「虎丘玩具市場」と呼ばれる玩具市場があり、色鮮やかで細工の細かい粘土人形や粘土美人などが売られていた。杭州西湖のおもちゃは「湖上の地上の儀式」と呼ばれ、粘土の子供、コウライウグイスの歌、花の湖のボートなどが含まれます。南宋の『夢』には、「内庭や貴族の家に、モヘレ(マホラとも呼ばれる)の像がある。この子像は、すべて粘土と木で作られ、色とりどりの台座で飾られ、緑の紗で覆われ、テーブルの上に置かれ、緑と青の金箔のテーブルクロスで囲まれ、または金、ヒスイ、真珠、ヒスイで飾られている」と記されている。宋代の徐渭の詩「土の子」には、「木度産の粘土片が豪華に彫刻されている。二重に覆われた赤いガーゼのカーテンが、花瓶の底に優美に立っています。若い女性は初めて酸っぱいものを味わい、その遊びに大喜びしました。私は密かに菩薩にあなたのような息子を産んでくれるよう祈っています。 赤いマニキュア 麻帆羅は「まほら」「まはら」とも表記されます。唐、宋、元の時代には、粘土、木、蝋などを使って赤ちゃんの形をしたおもちゃを作る習慣がありました。これは主に、中国のバレンタインデーに子供を授かるシンボルとして使用されます。原語はサンスクリット語の「マホラガ」です。残念なことに、さまざまな理由により、百家フォーラムで馬衛都氏でさえ「麻帆羅」を説明する際に曖昧な表現をしていました。 1930年代、傅雲子氏は『宋元代における『モヘレ』の研究』の中で次のように記録している。「それは仏教の経典に由来する。インドから伝来し、中国化を経て、蛇の頭を持つ人間の姿から美しく愛らしい子供の姿に進化した。それは『七夕』の供儀の一つである。」これはどうしても一方的である。実は、このものは唐代に起源を持ち、「華生」と呼ばれていました。鮮卑族はこれを「マホラガ」と呼んでいました。これは「車輪の赤ちゃん」と訳すことができます。昔、「マホラ」は、男の子の誕生を祈願して人々が崇拝していた、衣服を着た粘土、木、または蝋人形でした。その後、結婚式の際に義理の両親に贈る贈り物として開発され、子供たちに喜ばれたことから、おごらない人形として作られるようになりました。唐代や宋代には、モヘレ、モヘラオ、マハラなど、他の多くの名前もありました。宋代と元代の庶民は中国語で「土偶」と呼んでいました。マハーラーの彫刻で最も精巧なものは蘇州(宋代)で作られました。 まほらへのお供え 清朝時代の台湾の習慣によると、7月7日には、女性は織姫を崇拝するのに忙しく、男性は最高の学者を選ぶ神である奎星に犠牲を捧げるために犬を屠殺するのに忙しくしていました。人々は科挙に合格し、仕事で成功することを期待して奎星を崇拝しました。清代の鄭大樹の詩『台湾竹詩・七夕』には、「今宵、牛飼いと娘は楽しく過ごし、海外ではカササギが枝を踏むこともない。犬を屠って供物にする意味はどこにあるのか、いつ豆を煮て縁を結ぶのか」とある。銭奇の詩『台湾竹詩・文昌を拝む』には、「色とりどりの亭の前では七娘に祈り、三つの村では文昌を拝む。橋の上はカラス、カササギ、星が争って満ち、天上と地上の人々はそれぞれ自分のことで忙しい」とある。地元の人々は織女を「七娘」と呼び、文昌は文芸の神である文曲星とも呼ばれている。 民間の伝説によると、7月7日は奎星の誕生日であり、「奎星は文芸を司る」と言われています。福建省や台湾では、特に学者の間で、七夕に奎星を崇拝し、試験の幸運を祈る習慣があります。奎星は北斗七星の最初の星です。昔、学者が科挙で首席を獲得すると、奎星が試験運を司っていることから、「天下一の学者」または「一挙に一位を獲得した者」と呼ばれました。 「拝奎星」の儀式も月明かりの下で行われます。福建東部地域では、「七夕」の夜、庭に「拝智女」と「拝奎星」の2つの香台がよく設置され、女性たちが集まり、男女の異なる2つの小世界に分かれて向かい合います。とても賑やかで面白いです。 昔、学者が科挙で首席を獲得すると、奎星が試験運を司っていることから、「天下一の学者」または「一挙に一位を獲得した者」と呼ばれました。現在でも各地の奎星塔は大変人気があります。現代社会の競争はますます激しくなり、親は皆、我が子の成功を望み、学生は皆、合格者名簿に名前が載ることを望み、皆が奎星を崇拝しに来るからです。各奎星塔には、長年にわたり文系と理系の大学入試で地元トップの成績を収めた人々の名簿が掲げられています。 「奎星塔」または「奎星閣」は中国各地に建てられており、塔の正殿には奎星の像が彫られています。 奎星を崇拝する 『二亜易』第2巻には、「荊楚では7月に経典や衣服を天日干しする。長い年月を経ると巻物に白い魚が現れると信じられているからである」と記されている。魏晋の時代には書物を干すのは7月7日で、後に真夏の6月6日に変更された。 『燕京隋史記』には「6月6日、都では衣服や本を天日干しして虫がつかないようにする」と記されている。清代の潘一儒は「6月6日に本を干す」という詩を書いた。 澄み切った青空と灼熱の太陽が照りつける真夏、気分も明るくなります。旧暦の6月6日、学者たちがまず考えることは、本や書画などを天日干ししてカビを落とし、虫を殺して腐らないようにし、長く受け継がれるようにすることです。 本を乾かし、経典を読む 夏の暑い時期に本を天日干しするのは、魏晋の時代から続く伝統だが、旧暦の7月7日に限られていた。「郝龍は7月7日に出て谷間に仰向けに寝た。人々が理由を尋ねると、彼は『天日干しをしている』と答えた。」(『新世界物語』白駁)その後、この習慣は徐々に6月6日に本を干すようになった。 「六」にしても「七」にしても、本を干すという習慣は珍しくなりました。 この習慣は徐々に消えつつありますが、本を干したり経典をひっくり返したりする小話は今日まで伝わっています。司馬懿は地位と権力が高かったため曹操に疑われ、当時の政治の闇を鑑みて、自分を守るために気が狂ったふりをして家に隠れたと記録されています。魏の武帝はそれでも安心できず、信頼できる書記官を派遣して密かに真相を調査させました。 7月7日、狂ったふりをした司馬懿も家で本を乾かしていた。書記官は戻って魏の武帝に報告したが、武帝は直ちに司馬懿に朝廷に戻って職務に就くよう命じ、さもなければ逮捕するとした。司馬懿は命令に従い、朝廷に戻った。困難な時期に、不規則な生活を送ることで憂鬱さを表現するタイプの人もいます。彼らは礼儀作法を軽蔑し、当時の慣習に反対した。劉易清の『新世界物語』第25巻には、7月7日、皆が本を乾かしていたが、郝龍だけが走って日光浴をしていたと書かれている。人々が理由を尋ねると、郝龍は「本を乾かしている」と答えた。これは、一方では本を乾かすという習慣に対する軽蔑であり、他方では自分の才能を自慢する方法でもあります。お腹を日光浴させるということは、本を日光浴させるということです。漢の時代に衣服を天日干しする習慣があったため、魏晋の時代には富裕層が富を誇示する機会が生まれました。 「竹林の七賢」の一人である阮仙は、このスタイルを軽蔑していました。 7月7日、近所の人が洗濯物を干していたとき、干し台にリンロシルクがぎっしり詰まっていて、眩しいほどだった。阮仙は竹の棒で静かに古びた衣服を拾い上げました。誰かが何をしているのかと尋ねると、彼は言いました。「私は世間の風習から逃れることができません。だから、ただ教えているだけです!」これらの短編から、七夕に本や衣服を干すという風習が当時どれほど一般的であったかがわかります。 |
<<: 七橋節の起源:七夕節はなぜ七橋節とも呼ばれるのでしょうか?
>>: 諸葛亮があと20年生きていたとしても、蜀漢は曹魏を倒せなかったと言われているのはなぜですか?
推薦する
唐代の詩『南京鳳凰塔登り』をどのように鑑賞すればよいでしょうか? 李白は詩の中でどのような芸術技法を用いているのでしょうか?
唐代の李白が金陵の鳳凰塔に登ったことについて、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみま...
『紅楼夢』で賈の祖母の誕生日のお祝いが彼女自身の死の前兆となっているのはなぜでしょうか?
『紅楼夢』で賈萊の祖母の誕生日のお祝いが彼女の死を予兆しているのはなぜでしょうか?これは多くの読者が...
『西遊記』の朱八戒はなぜ転生するために別の体を乗っ取らなければならなかったのでしょうか?
『西遊記』では、通常、神が地上に降り立つ方法は3つあります。では、なぜ朱八戒は他人の身体に憑依して転...
三国志の正史では、関羽が顔良を殺したとき、一体何が起こったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『西遊記』の霊山には四大菩薩がいます。なぜ孫悟空だけが観音を恐れないのでしょうか?
『西遊記』では、霊山には観音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、地蔵菩薩の四大菩薩がいます。では、なぜ孫悟空だ...
中秋節はいつ始まったのでしょうか?どのような習慣や習慣がありますか?
中秋節はいつ始まったのでしょうか?次は、Interesting Historyの編集者が歴史の真実に...
黄夫人が寧国大厦で騒ぎを起こしたとき、幽二潔は何をしたのですか?
黄おばあちゃんが寧国屋敷で事件を起こしたとき、幽二潔はどうしたのでしょうか?次は、面白歴史の編集者が...
明代の小説『英雄伝』第41章:熊天瑞が降伏を受け入れ、再び反乱を起こす
『明代英雄伝』は、『雲河奇行』、『明代英雄伝』、『明代英雄伝』などとも呼ばれ、明代の無名の著者(徐渭...
「お正月作品」の執筆背景は?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】新年を迎え故郷が恋しくなり、空を見ながら一人涙を流す。年老いたら他人の下で暮らすが、春...
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 雲洛公主』の原文は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
中国のスタジオからの奇妙な物語からの雲洛姫の原文安大業は洛龍[1]の出身であった。彼は生まれたときか...
賈宝玉に対する苗玉の秘密の恋は失敗する運命にある。真実を語る4つの言葉は何でしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
『紅楼夢』の宝玉の処方箋は本当に林黛玉の病気を治せるのでしょうか?その背後にある比喩は何でしょうか?
『紅楼夢』の第三話では、林黛玉が賈一家に初めて会う。初めて会ったとき、誰もが彼女の内気な顔と艶めかし...
「忠誠心と勇敢さにあふれた五人の若者たちの物語」の第 3 章ではどのような物語が語られていますか?
清蓮湖は戦いを見守る間に殺され、白玉堂は印章を失い盗賊を追った。二人が崇暁楼に向かって走っていると、...
玄武門の変の後、なぜ李淵自身の近衛兵は李世民を鎮圧しなかったのか?
玄武門の変の後、なぜ李淵自身の近衛兵は李世民を鎮圧しなかったのか?第二に、玄武門の変の後、なぜ李淵の...
歴史上、「晋」と「楚」は何回覇権を争ったのでしょうか?ジンとチューはなぜいつも一緒にいられるのでしょうか?
今日、「Interesting History」の編集者は、皆さんのお役に立てればと願って、金と楚の...