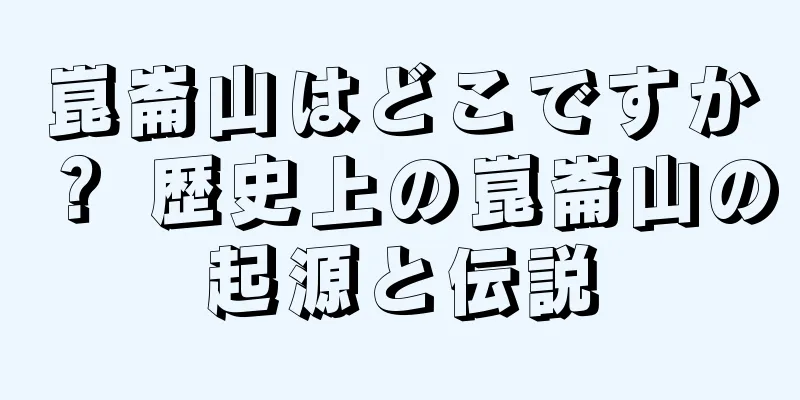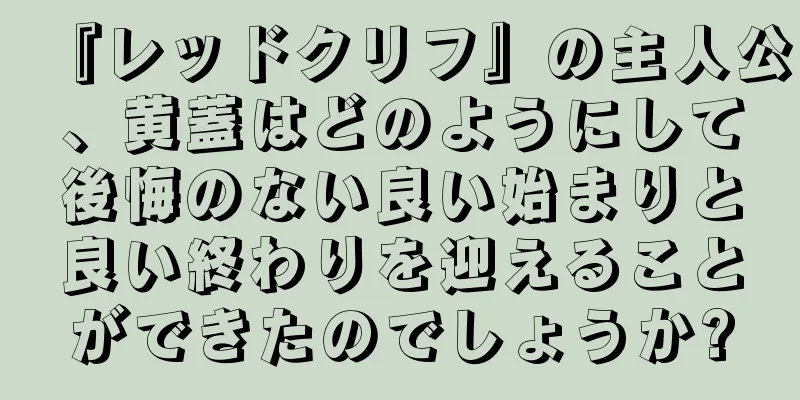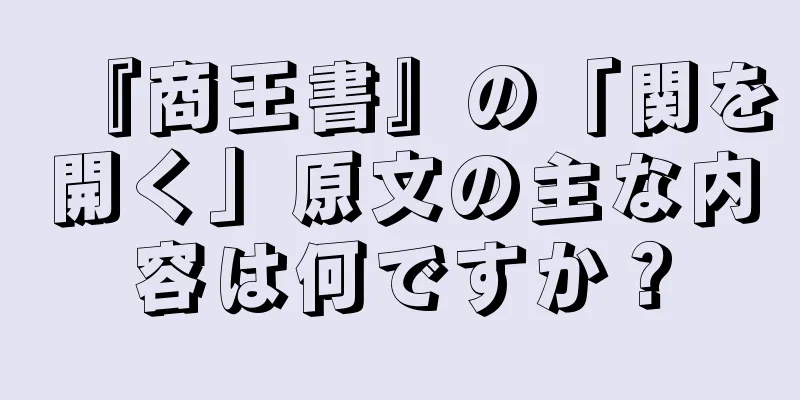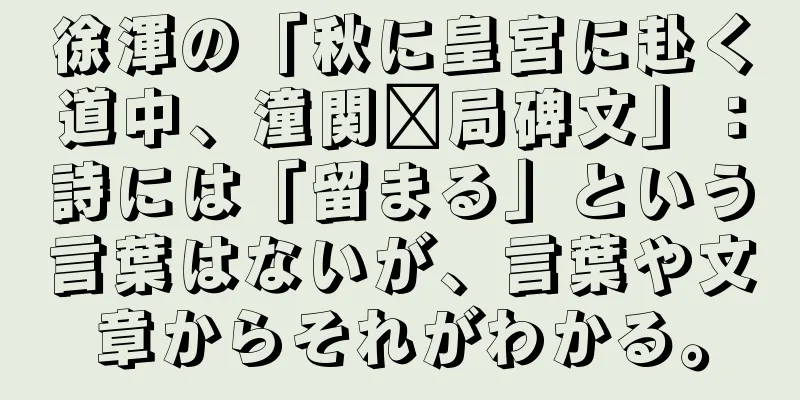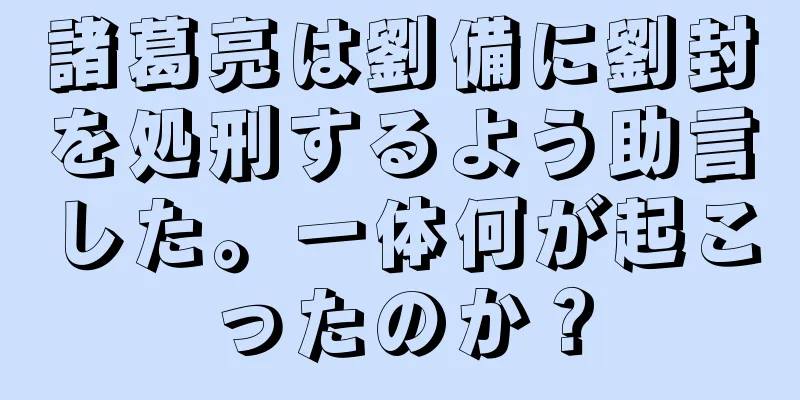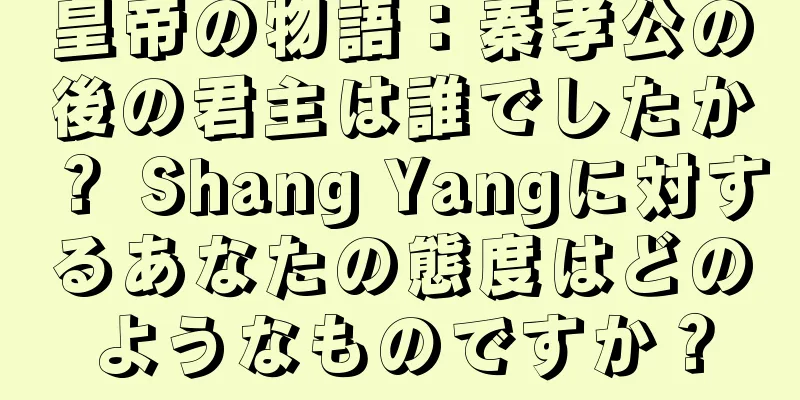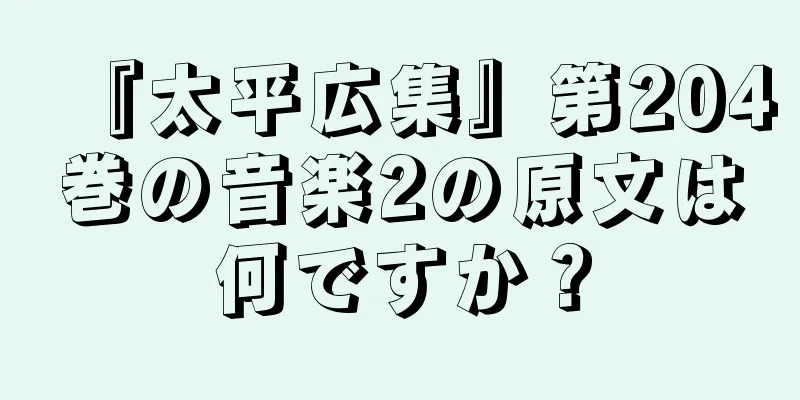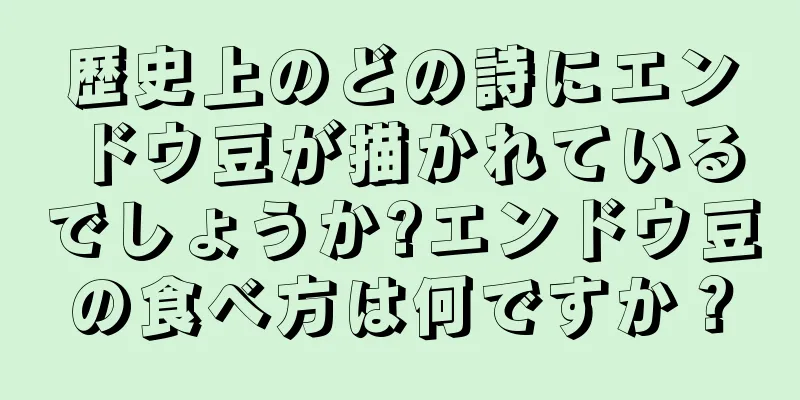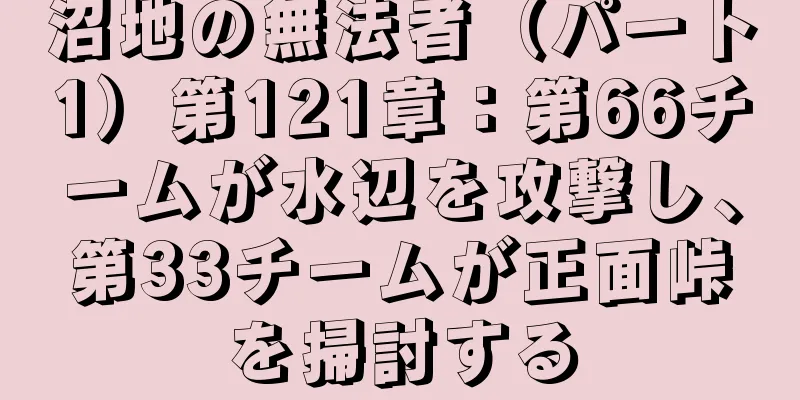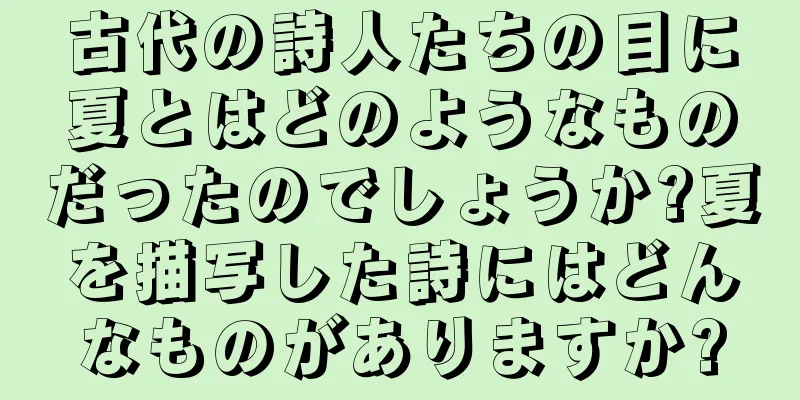三国志の正史では、曹操と孫権という英雄は出会ったことがあるのでしょうか?
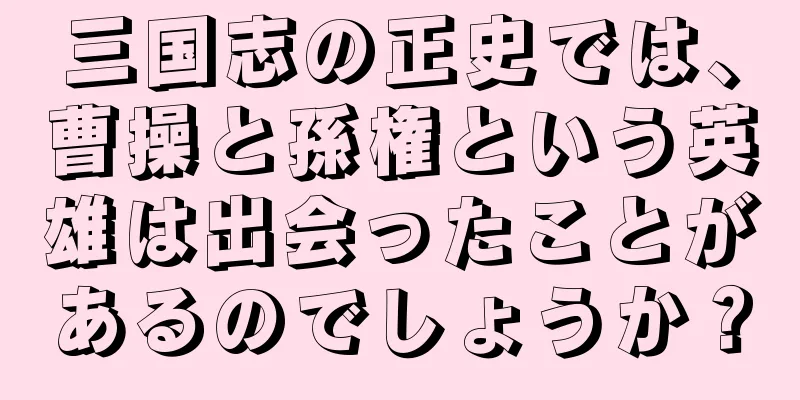
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、後漢末期と三国志の英雄である曹操と孫権が実際に会ったことがあるのかどうかについて、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介します。見てみましょう! 正史では曹操と孫権は会ったことがない 曹操は東漢永寿元年(155年)に生まれ、光和5年(182年)に生まれた孫権より20歳以上年上で、孫権の父である孫堅と同世代であった。 孫権は幼少期、家族とともに九江郡寿春県に住んでいた。中平6年(189年)、孫堅は董卓を攻撃した関東連合に参加した。この時期に孫堅と曹操は会ったはずだが、当時孫権はまだ7歳、弟の孫策はまだ14歳だった。記録によれば、この時期に孫権は孫策に従って蜀県、廬江県に移動しており、孫権も孫策も孫堅の軍にはいなかったため、曹操と遭遇した可能性は低い。 その後、曹操は長い間北方で発展し、孫策と孫権は江東で発展したため、両者が出会うことはほとんどなかった。赤壁の戦いの際、曹操は自ら軍を率いて南下したが、孫権は戦場に出なかった。曹操が敗れて北に帰った後、当然二人は会うことはなかった。 建安18年(213年)正月、曹操は軍を率いて汝勒砦を攻撃し、孫権は水軍を率いて曹操の水軍を包囲した。敗北した後、曹操は持ち場を守り、出撃を拒否した。孫権は自ら船を陸奥口から曹操の陣地に進ませ、敵の状況を調べた。 帰り道、孫権は人々に陽気な音楽を演奏するよう命じた。 曹操は遠くから孫権の船と軍隊が依然として厳重に秩序を保っているのを見て、ため息をつくしかなかった。「もし私に息子がいたら、孫仲武のような子にしたい。劉景勝の息子は豚や犬のようだ!」 本来なら曹操と曹操が最も接近する距離だったはずだが、やはり両者はそれぞれの部隊の指揮官であり、事故を避けるためには弓矢の射程範囲外にいなければならない。そのため、遠くから互いの姿を見ることは可能だが、互いの姿をはっきりと見るのはおそらく現実的ではない。 その後、曹操は建安22年(217年)に再び汝勒を攻撃し、東呉軍を破ったが、孫権が軍を率いて敵と対峙した記録はない。それ以来、曹操は死ぬまで軍を率いて南下することはなかったので、当然二人が再び出会う機会はなかった。 『三国志演義』では曹操と孫権は実際に会った 『三国志演義』における曹操と孫権の対決は、建安18年(213年)正月に汝虚戦場で起こった。正史のこの戦いの記録と比較すると、『三国志演義』の描写は間違いなくよりエキサイティングである。この戦いは三国志演義第61章「趙雲が河を遮って阿斗を占領し、孫権の手紙で老マンを追い払う」に登場します。 『三国志演義』の記録によると、曹操軍が汝虚武に到着すると、曹洪はまず騎兵3万を率いて川辺を巡視させた。前哨部隊は「川沿いに遠くから見ると、無数の旗が立っているが、敵兵がどこに集まっているのか分からない」と報告した。曹操は自ら軍を率いて前線に向かい、汝口に軍を配置した。曹操は百人以上の者を率いて丘の斜面から遠くから軍艦を眺め、真ん中の大きな船の上の青い絹の傘の下に孫権が座っているのを見つけた。「文武両官が両側に立っていた。」曹操は鞭で孫権を指差して言った。「もし私に息子が生まれたら、孫仲武のような子になってほしい。もし劉景勝の子なら、豚と犬になるだろう。」 その後、曹操は呉軍との戦いで不利な状況に陥ったため、このとき両者は一度しか会戦しなかった。その後、曹操は50マイル後退して陣を張りましたが、夜、とても不吉な夢を見ました。翌日の正午、曹操は自ら50人以上の騎兵を率いて陣地を出て、夢で見た夕日山にやって来た。突然、馬と兵の集団が見え、「金色の兜と金色の鎧をつけた男が先頭に立っていた。曹操が見ると、それは孫権だった。」 孫権は曹操を見ると、丘の上で馬の手綱を引いて鞭を曹操に向け、「宰相、あなたは中原を管轄し、非常に裕福で権力も強いのに、なぜそんなに欲深くて揚子江の南を侵略しに来たのですか?」と言った。 曹操は答えた。「お前は部下であり、王室を敬っていない。皇帝の命令に従ってお前を罰するために来たのだ!」 孫権は笑って言った。「こんなことを言うのは恥ずかしいことではないか。君主たちを操るために皇帝を人質に取っていることを世間は知らないのか。漢王朝を尊敬していないわけではない。国を正すために君主を罰したいだけだ。」 … 『三国志演義』では曹操と孫権が会っただけでなく、会話も交わしていたことがわかります。 前述のように、曹操は正史でも三国志演義でも「もし息子が生まれたら孫仲武のような子であってほしい」と言っているが、正史では曹操と孫権はおそらく会ったことがなかった。曹操がそう言ったのは、孫権が自ら敵を探り、軍勢が整然としていた勇気に感動したからに過ぎない。三国志演義では、曹操は孫権と直接会ってそう感嘆し、再会した際に両者は会話を交わした。 |
<<: 2016 イースターの願い: イースターの願いの完全なコレクション
>>: 曹丕が漢王朝を簒奪し自ら皇帝を宣言したとき、劉備に残された選択肢は2つしかありませんでしたか?
推薦する
『紅楼夢』で、賈宝玉が殴られた後、王夫人は何をしましたか?
第33章では、夏休みの昼休みの後、賈正の書斎で宝玉が殴打された。知らなくても大丈夫です。Intere...
「李公安」第23章:陸大栄は法廷で李公安の妻が思いがけず金持ちになったと宣誓する
『李公安』は『李公安奇談』とも呼ばれ、清代の西洪居士が書いた中編小説で、全34章から構成されています...
『徐霞客遊記』永昌記の本来の内容は何ですか?
漢代の永昌県は、元代には大理金池などの宣府部であった。総督は永昌に事務所を設けた。後に、宣威寺都源帥...
結婚して家を出てから、タンチュンはジア家でどのような生活を送っていたのでしょうか?彼女の結末はどうなったのでしょうか?
中国の伝統文化は歴史が長く、奥が深いです!今日は、Interesting Historyの編集者が、...
太平広記・第86巻・奇人・建州の狂僧の具体的な内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
「千秋随・鶯の鳴き声」は張仙によって書かれたもので、悲しみと喜び、別れと再会の感情を描いています。
張邊は、字を子夜といい、北宋時代の雅流詩人である。彼の詩の内容は、主に学者官僚の詩と酒の生活と男女の...
センザンコウの薬効は何ですか?センザンコウの代わりになる薬は何ですか?
センザンコウの薬効についてまだ知らない読者のために、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介します。ぜひ読...
馬超はかつて許褚と激しい決闘をしましたが、勝者はどちらでしたか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
薛家江第27章:彼は冷たい川で3回苦しみ、霊の前で自分の本当の気持ちを告白した
『薛家の将軍たち』は、主に薛仁貴とその子孫の物語を描いた小説シリーズです。これらは『楊家の将軍』や『...
燕国の楽毅は70の都市を連続して征服し、火の牛が空から降りてきて斉衛を助けた。
燕国の楽毅は70の都市を連続して征服し、火の牛が空から降りてきて斉衛を助けた。これは戦国時代に起こっ...
北宋の宰相、張志白の物語。張志白に関する逸話や物語は何ですか?
張志白(?-1028)、号は永輝。彼は滄州青池(現在の河北省滄州市の南東)の出身でした。北宋の宰相。...
『紅楼夢』で、妙玉はなぜ誕生日に宝玉を女々しいと呼んだのですか?
妙豫は小説『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人である。 Interesting Histo...
李尚銀の「霧雨」:この詩は、作者の物に対する多様な書き方を反映している。
李尚鑫(813年頃 - 858年頃)は、字を易山、号を毓曦生といい、淮州河内(現在の河南省沁陽市)の...
歴史を正しく理解する:自国の歴史を年代順に記憶する方法!
1. 単語数が最も少なく、韻も覚えやすい:夏、商、西周東周王朝は2つの時代に分かれている春秋時代と戦...
『紅楼夢』の賈宝玉、林黛玉、妙玉の名前にはどんな意味がありますか?
『紅楼夢』の登場人物の多くには、皮肉や哀悼といった特別な意味を持つ名前があり、これは『紅楼夢』の芸術...