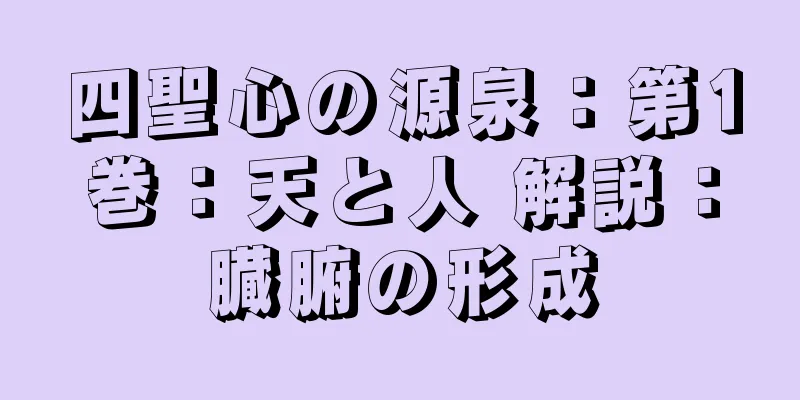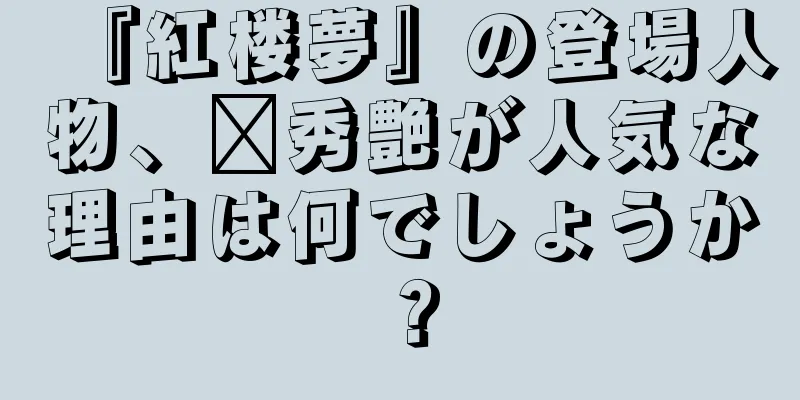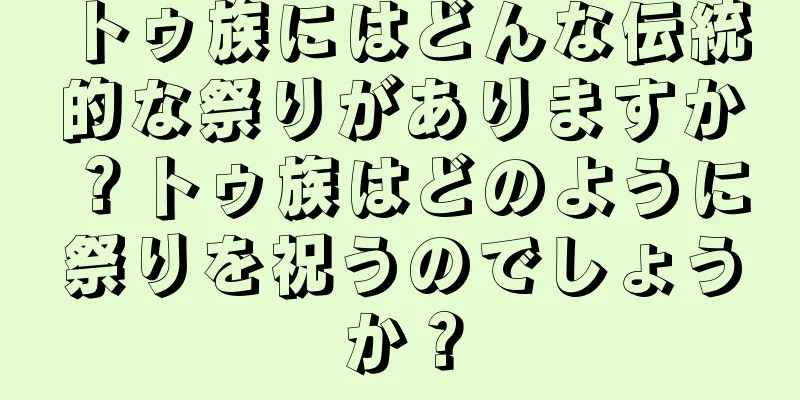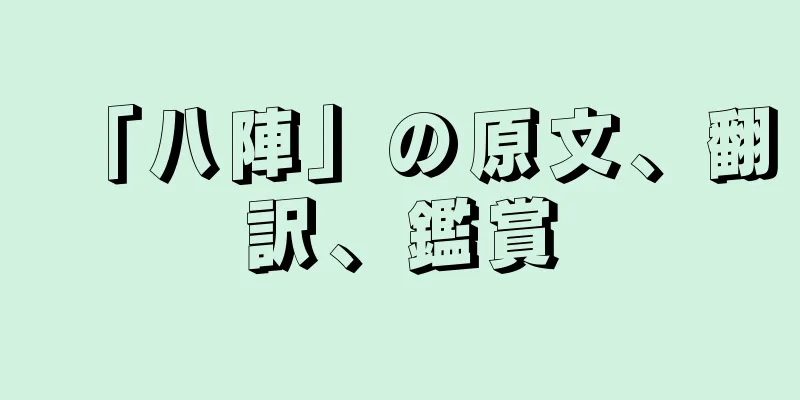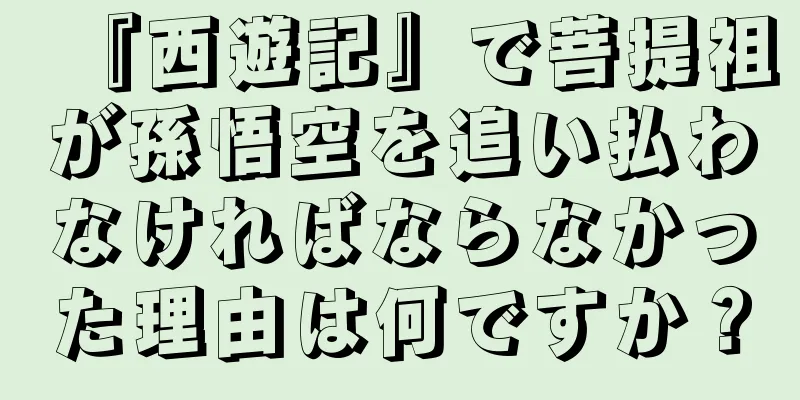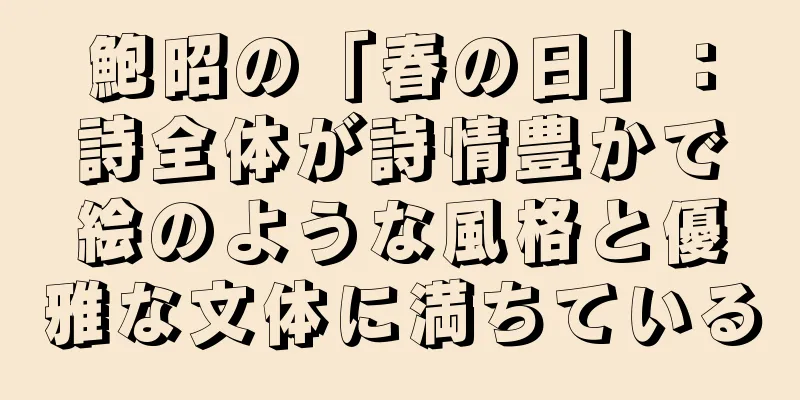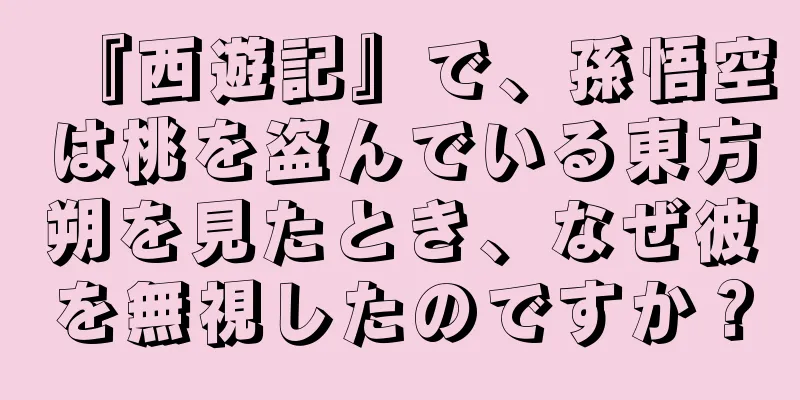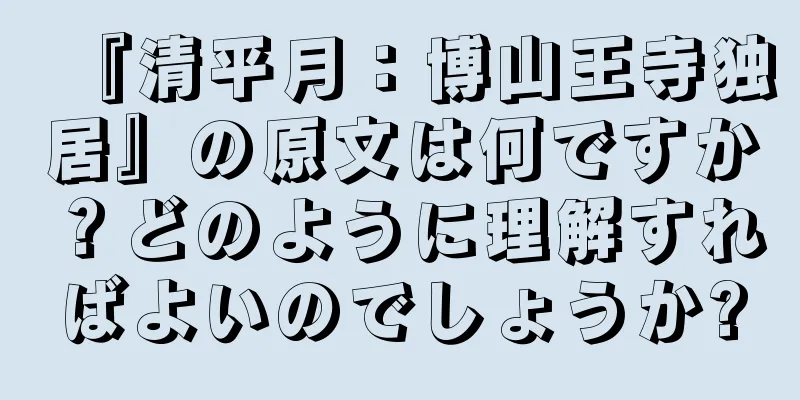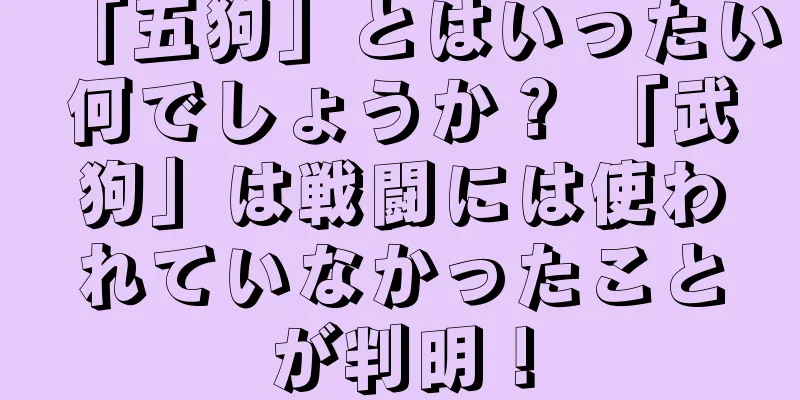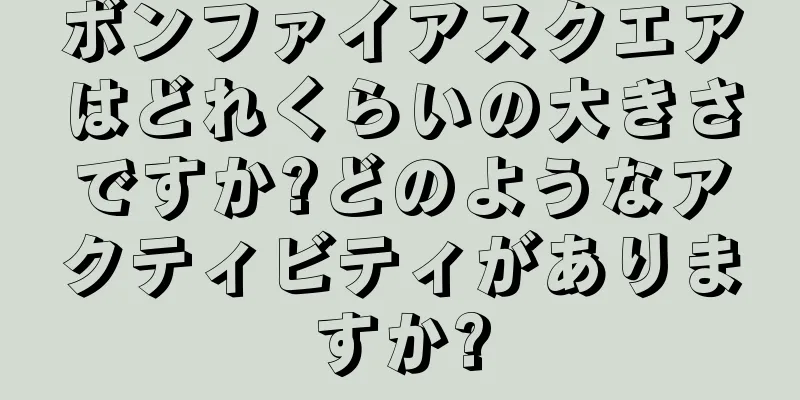東呉の大将軍として、三国志の正史における周瑜のイメージはどのようなものでしょうか?
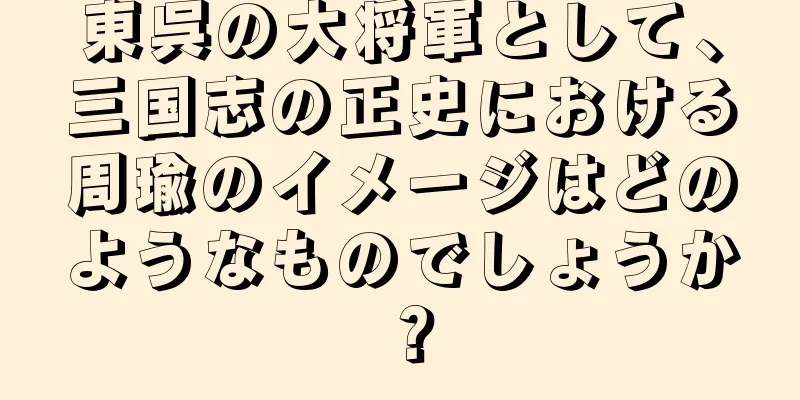
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が歴史上の周瑜について詳しく紹介しますので、見てみましょう! 周瑜は西平4年(175年)に廬江の周家に生まれました。曽祖父の周靖と叔父の周忠はともに太元帥の甥であり、父の周毅は洛陽の知事を務めていました。 『三国志』の「周瑜伝」には、「周瑜は背が高く、力持ちで、容姿も美しかった」と記されている。趣味が似ていたため、幼少の頃から父とともに廬江舒県に移住した孫策と親しかった。裕福な家庭に生まれた周瑜は、自宅の一部を孫策に譲っただけでなく、しばしば経済的援助も行っていた。 興平2年(195年)、周瑜は丹陽の太守であった叔父の周尚を訪ねた。袁術から離脱した孫策は、たまたま軍を率いて溧陽にやって来た。周瑜は、周瑜が丹陽にいることを知り、手紙を書いた。周瑜は軍と食料を率いて周瑜を支援し、孫策に従って横江と当里を征服し、川を渡って左容と薛離を破り、劉瑜を追い払った。その後、孫策は単独で軍を率いて武鈞、会稽などを攻撃し、周瑜は軍を率いて丹陽に戻った。 その後間もなく、袁術は従弟の袁寅を丹陽の知事に任命した。その後、周瑜は周尚とともに寿春に来た。袁術は周瑜を招聘したかったが、周瑜は袁術が賢明な指導者ではないと考え、袁術は居巣県の県長として働き、いつでも江東に戻れるように準備しておくよう要請した。周瑜は在任中に魯粛とも知り合い、後に魯粛とともに武君に戻り孫策に加わった。 孫策は周瑜の到着を非常に喜び、すぐに彼を建衛将軍に任命し、兵士2,000人と軍馬50頭を割り当てました。当時、周一族は廬江一帯で名声を博していたため、孫策は周瑜に牛竹の守備を命じ、後に中谷の長を務めた。 199年、周瑜は孫策によって中央衛将軍に昇進し、江夏の太守を兼任した。孫策に従って荊州を攻撃し、同年12月に万城を占領して大喬と小喬を手に入れ、それぞれ結婚した。その後、荀陽を征伐し、虞章と廬陵を平定した後、周瑜は八丘の守備を命じられた。 建安5年(200年)4月、孫策が暗殺され、孫権が後を継いだ。葬儀に参列するために軍を率いた周瑜は、中央衛将軍に任命され、太書の張昭とともに軍事と政治を統括した。それ以来、周瑜は心から孫権を助け、曹操に人質を送ることを拒否するよう孫権を説得しただけでなく、曹操の採用も拒否した。さらに孫権にもっと人材を採用するよう提案し、魯粛を推薦した。 建安11年(206年)、周瑜は軍を率いて馬・鮑陣営を攻撃し、指導者を斬首し、1万人以上の人々を捕らえた。江夏の太守黄祖は将軍の鄧龍に数千人の兵士を率いて柴桑を攻撃させた。周瑜は軍を率いて反撃し、鄧龍を捕らえた。黄祖の将軍、甘寧が降伏した。周瑜は甘寧が有能な人物だと考え、孫権に推薦した。 2年後、周瑜は前線を担当し、軍を率いて黄祖を攻撃し、夏口を占領して黄祖を殺した。 建安13年(208年)秋、曹操は軍を率いて南下し、荊州の劉聡は降伏し、孫権に手紙を書いて蘇州の降伏を求めた。蘇州の朝廷が論争していたとき、周瑜は孫権のために状況を総合的に分析し、孫権の抵抗の決意を強めた。その後、孫権は周瑜を総司令官に、程普を副司令官に任命し、軍を率いて曹操と戦うよう命じた。 「赤壁の戦い」では、曹操の水陸両軍と対峙し、周瑜はまず呉東水軍を率いて曹操の水軍を打ち破り、曹操に武林北岸に軍を集中させ、その後黄蓋の火攻めの戦略を採用して曹操軍を打ち破った。疫病と軍事的敗北という二重の打撃を受けて、曹操は最終的に南に進軍して東呉を攻撃する計画を断念せざるを得なくなった。 その後、周瑜と程普は軍隊を率いて曹操の将軍曹仁とともに南君のために戦った。この戦いの際、周瑜は自ら馬に乗って戦いを指揮していたが、右の肋骨を矢で撃たれた。しかし、曹仁が軍を率いて攻撃に出たとき、周瑜は負傷しながらも立ち上がり、陣地を視察し、兵士たちに勇敢に戦うよう激励した。一年間の激戦の後、曹仁はついに城を放棄して逃亡した。周瑜は将軍に任命され、南州の知事も兼任した。 赤壁の戦いの後、周瑜は最初劉備を軟禁することを提案したが、孫権は曹操が依然として脅威であり、劉備を制御するのは難しいと考え、曹操と戦うためには劉備と同盟を組むべきだと考え、提案を採用しなかった。 建安15年(210年)、周瑜は「汾魏とともに進軍して蜀を征服し、蜀を占領して張魯を併合する。その後汾魏に国土の防衛を任せ、馬超と同盟を結ぶ。将軍とともに戻って襄陽を占領し、曹操の勢いをくじき、その後北方への作戦を立てよう」という戦略を提案し、孫権はこれを採用した。しかし、この戦略が実行される前に、周瑜は八丘の拠点に戻る途中で重病にかかり、残念ながら36歳で亡くなりました。 『三国志演義』の影響が大きいため、周瑜に対する多くの人の印象は、「禹がいるのに、なぜ梁がいるのか」「周瑜が黄蓋を倒すのは、戦う意志があり、負ける意志がある」「諸葛亮は周瑜を3度怒らせる」などの物語レベルにとどまっており、周瑜は才能はあるものの心が狭いと思っている。実際、歴史上の周瑜は心が狭いのではなく、むしろ心が広い人物でした。 周瑜は廬江周氏の出身で、高貴な家柄の出身であるだけでなく、若くして名声を博し、24歳の時には江東ではすでに名声を博していた。『三国志・呉書・周瑜伝』には、「呉では皆が彼を周朗と呼んだ」と記されている。周瑜は若い頃から高い地位に就いていたが、もし本当に心が狭いのなら、どうして民衆の支持を得て、これほどの成功を収めることができただろうか。 『江表伝』には、「普はかなり年老いており、よく玉をいじめていた。玉は謙虚で寛容で、決して彼と争うことはなかった。後に普は彼を尊敬し、丁重に接した。彼は人々に言った。『周公瑾と親しくなるのは、上等な酒を飲むようなものだ。酔っていることに気づかないだろう』」と記されている。この記録から、孫堅時代の老将軍である程普は、年齢と年功を理由に、若くして高い地位に就いた周瑜に非常に不満を抱いていたことがわかります。彼は何度も周瑜に失礼な言葉を言いましたが、周瑜はそれを真剣に受け止めず、後に程普を説得することに成功しました。これは心の狭い人の行動でしょうか? 歴史上、周瑜は上司、部下、さらには敵からも非常に高く評価されています。たとえば、孫策は周瑜について「あなた方は仲睦まじい夫婦だ」と言いました。孫権は「周瑜は勇猛果敢な人であり、戦略家でもある」と言いました。劉備は周瑜を「雍進は文武両道の人であり、万人の中の英雄であり、また度量が大きい」と呼びました。蒋幹は「彼は優雅で度量が大きく、言葉で軽視することはできません」と言いました。諸葛瑾と武志も「周の方叔、漢の辛、武さえも彼より優れている」と言いました。王朗は周瑜を「江淮の英雄である周瑜は、彼らの将軍になることをいとわない」と呼びました。 周瑜は多才な人物で、政治や軍事の才能に加え、音楽にも非常に長けていました。当時、「歌に間違いがあれば、周朗は振り返る」という諺がありました。当時の江東地方では、周瑜が人柄の良さでほぼ全員を征服していたと言えるでしょう。そんな人がどうして心の狭い人間になれるのでしょうか。 東呉の将軍である周瑜の歴史的イメージは、実は『三国志演義』のそれとは全く異なっています。周瑜は正史の中で高く評価されています。『三国志演義』以降も、周瑜に対する各王朝の評価は概ね肯定的で、「天下の英雄、江左の美男」と賞賛されるほどです。 『三国志演義』では、作者は周瑜のイメージを変えて諸葛亮を高めた。一方では、周瑜に孫策が太史慈を捕らえた功績や孫靖が王思徒を倒した功績など、周瑜の登場シーンを増やした。同時に、周瑜が諸葛亮の才能に嫉妬し、最終的に諸葛亮に激怒して死に至ったと述べ、周瑜が諸葛亮を神格化するための「道具人」になったとしている。 |
<<: シェ族の歴史 シェ族はなぜ自分たちを「シャンハ」と呼ぶのか
推薦する
蘇軾はかつて人々に酒を飲むよう勧める詩を書いたが、それは心の広い楽観的な態度を示した。
古代の文人にとって、酒は欠かせないものだった。食べ物や衣服がなくても生きていけるが、酒がなければ絶対...
『三朝北孟慧編』第31巻の原文には何が記録されているか?
静康コレクション、第6巻。それは、静康元年庚寅の旧暦1月24日に始まり、丸一日で終わりました。 24...
秦の時代の私有土地所有制度はどのようなものだったのでしょうか?その土地は本当に私有地ですか?
秦の時代の土地所有制度はどのようなものだったのでしょうか?土地は本当に私有地だったのでしょうか?次の...
「水の中の青ガマについての三つの詩(その1)」の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
韓愈の『水に青草を三首(一)』の原文は何ですか? どのように翻訳しますか? これは多くの読者が関心を...
古代と現代の驚異 第33巻:唐潔源の奇妙な遊び心
『今昔奇談』は、明代の鮑翁老人によって書かれた、中国語の俗語による短編小説集です。馮夢龍の『三語』と...
那藍星徳の詩「臨江仙・一羽の雁」はどのような感情を表現しているのでしょうか?
以下、Interesting History の編集者が、Nalan Xingde の「臨江仙・古岩...
清朝の皇帝たちは春節をどのように祝ったのでしょうか? 「ペンを置いて」「封を切って」後は作業不要!
今日は、Interesting Historyの編集者が、清朝の皇帝が春節をどのように祝ったかをお伝...
プーラン族はどんなお茶を飲みますか?それはどうやってやるのですか?
もち米茶の作り方は、まず土鍋を火鉢に入れて熱し、適量のもち米を入れて黄色くなるまで煎ります。次に茶葉...
「忠誠心と勇敢さにあふれた五人の若者たちの物語」の第 27 章ではどのような物語が語られていますか?
おべっか使いを斬る能力について、偽物と義兄弟になることを誓う毛宝はどうして剣を持ち去ることができたの...
永嘉の乱は歴史上どのような出来事でしたか?
永嘉の乱は西晋の時代に中原に住む少数民族によって引き起こされた内戦であった。西晋の恵帝の治世中、朝廷...
太平広記・巻第29・神仙・二十七仙の具体的な内容は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
楊康と楊果の関係は?楊康の息子は誰ですか?
楊過は楊康の死後の子である。楊鉄鑫は、別名ムー・イーと呼ばれ、養女ムー・ニエンシを連れて北京に行き、...
宋代の詩における慧充の春江夕景の詩 2 編を鑑賞します。蘇軾は詩の中でどのような感情を表現したのでしょうか。
宋代の蘇軾の『慧充の春江夕景二首』について、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみまし...
『紅楼夢』の賈宝玉は一虹院の女中たちをどのくらい溺愛しているのでしょうか?
『紅楼夢』では、賈宝玉は女性と遊ぶのが一番好きです。では、彼は怡虹院の女中たちをどれくらい甘やかして...
もし劉禅が劉備と同じ野心を持っていたら、蜀漢の将来はどうなるでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...