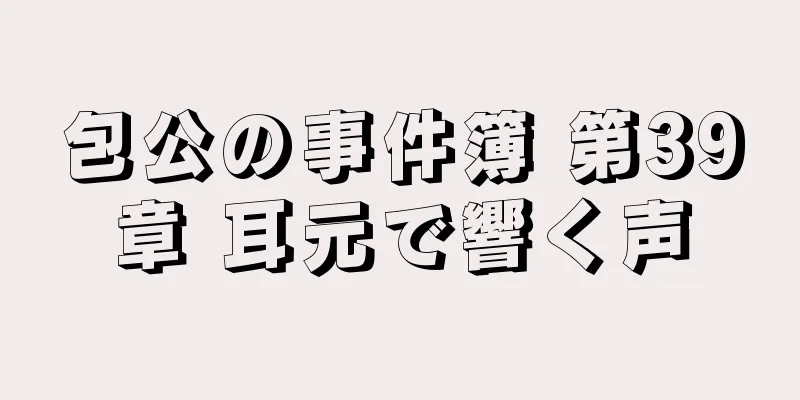「散り梅露」の原文は何ですか?このサンクをどう評価したらいいのでしょうか?

|
【オリジナル】 春のそよ風が武陵馬を誇らしげにさせ、西湖の暖かい3月の日、オーケストラが花市場でウグイスの鳴き声を演奏します。 音楽がわからない人はここに来ないでください。ここは歌ったり、お酒を飲んだり、詩を詠んだりする場所です。 山々は眉をひそめながら通り過ぎ、柳は煙の中に髪を引きずり、西施がぐっすり眠ったことは喜ばしいことである。 【注意事項】 武陵児:裕福な貴族の息子を指します。五陵とは、長安の外にある漢の皇帝の墓5つ、すなわち長陵、安陵、楊陵、茂陵、平陵を指します。これらは富裕層が集まる場所です。これらの墓が建てられると、富裕層はそれぞれの場所に移りました。 オーケストラが水に触れる:湖に浮かぶオーケストラが演奏する音楽の音を指します。オーケストラ、管楽器、弦楽器。 映化市:春にはオリオールの歌声と花の咲く魅力的な場所を指します。 眉をひそめる:雨上がりの遠くに見える春の山々が、西施の眉をひそめた濃い眉のように見えることを表現しています。 【翻訳】 春風がそっと吹き、武陵の若者たちが馬に乗って散歩に出かけます。西湖は暖かい3月で、あちこちに花が咲き、オーケストラの演奏する音楽が湖面に漂います。ソウルメイトでないなら、心ゆくまで歌ったり、飲んだり、詩を朗読したりするためにここに来ないでください。雨上がりの春の山々は、眉をひそめた西施のように魅力的で、飛翔する柳の花穂は、遠くから見ると、霧をたたえたしだれ柳のようで、西施のふわふわした髪のようです。美しい西湖は、熟睡から目覚めたばかりの西施のように繊細です。 【制作背景】 馬志遠は「水仙」の旋律を使って、春、夏、秋、冬の西湖の風景を歌った短い詩を4編書いた。この歌集の創作過程については、現代の詩人である劉世忠の『水仙』の序文に「西湖を西施にたとえれば、薄化粧でも厚化粧でもいつも似合う」という于居翁の詩が紹介されている。作詞家はそのアイデアを盗用し、独自の解釈で演奏した。世間で歌われている「水仙」の4つの歌は、今でも「西施」という2つの言葉で終わり、歌ホールや音楽ハウスで人気があり、人々はいつももっと良くできないかと残念に思っている。西湖の西妃を思うと、秦には誰もいないような気がする。昔、松山の麓に木こりがいました。彼はこれを聞いて、春、夏、秋、冬の四季を歌った詩を作り、「西湖四季漁夫歌」と名付けました。合意内容は、「最初の行は『二』で韻を踏み、その後に『詩』が続き、『西詩』という2つの単語で行末が決まり、これで終わりです。一緒に詩を書こうと誘います。合意どおりにやります」というものでした。ここで言及されている松廬の木こりは、呂樹寨です。このことから、これらの楽曲は陸志の招待により馬志遠と劉世忠によって同時に作曲されたことがわかります。これら3つの作品はすべて『元代歌全集』に収録されているが、その中でも馬の作品は最も新鮮で生き生きしている。 |
<<: 『梅散り・心中事』の著者は誰ですか?この歌の本来の意味は何ですか?
推薦する
邯鄲の戦い:戦国時代における秦に対する最初の大勝利
紀元前257年12月、魏と楚の軍隊が相次いで邯鄲郊外に到着し、秦軍を攻撃した。趙の守備隊は城外の魏軍...
呂布がこんなに強いのなら、呂布以下の強力な将軍たちはどのように順位付けされるべきでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
関公の緑龍三日月刀と張飛の蛇槍は本物の武器ですか?
『三国志演義』には、天佑三兄弟に関する桃園の誓いが記されています。誓いが交わされた直後、中山国から張...
『紅楼夢』で薛宝才が大観園の隅の門を施錠したのはなぜですか?
薛宝才は古典小説『紅楼夢』のヒロインの一人で、金陵十二美女の一人です。次は『おもしろ歴史』編集者が歴...
東晋時代、荘園経済は社会経済の中でどの程度の割合を占めていたのでしょうか?
東晋時代には、社会経済に占める荘園経済の割合は北方よりも大きかった。孫武の時代から、江南の経済は急速...
羅斌王の「沂水にて人を送る」はどのような内面的な感情を反映しているのでしょうか?
羅斌王の「沂水河見送り」はどのような内面の感情を映し出しているのでしょうか。羅斌王は幼い頃から神童と...
古代の蹴鞠は現代のサッカーに相当します。古代の人々は蹴鞠にどれほど夢中だったのでしょうか?
古代の蹴鞠は、実は現代のサッカーに相当します。古代人が蹴鞠に抱く情熱は、現代の世界中のサッカーファン...
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 羅刹海城』の原文の筋書きは何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
「中国のスタジオからの奇妙な物語」からの「羅刹海城」の原文馬冲は、雅号を龍梅といい、商人の息子であっ...
蜀漢の滅亡を招いた犯人は誰ですか?黄昊ですか、それとも劉禅ですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
石公の事件 第24章:蟹は不公平を訴え、くじを飛ばして老魏を捕まえる
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
張岱の散文集『西湖を夢みて』第4巻・西湖南路・法祥寺全文
『西湖夢想』は、明代末期から清代初期の作家、張岱が書いた散文集で、全5巻72章から成り、杭州周辺の重...
韓托州は玉井園で殺害された。勅旨を偽造したのは誰ですか?
春熙六年(1179年)、石密元は成石朗(八位)に任じられ、同八年(1181年)、宣易朗に転じられた。...
范斉の『王の能源楼』:詩全体は16行から成り、4行ごとに1つの意味がある。
范鵬(1272-1330)は、恒夫、徳吉とも呼ばれ、文百氏とも呼ばれた。清江(現在の江西省樟樹)の出...
秦観の「海潮・梅花薄薄」:詩全体が優雅で美しく、穏やかで穏やかだが、意味の流れが絶え間なく続いている。
秦観(1049年 - 1100年9月17日)、字は少邑、別名は太虚、別名は淮海居士、漢口居士とも呼ば...
『劉怡氏伝』が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
劉易在家仏教徒の伝記欧陽秀(宋代)劉夷居士が最初に楚山に追放されたとき、彼は自らを随翁と名乗った。彼...