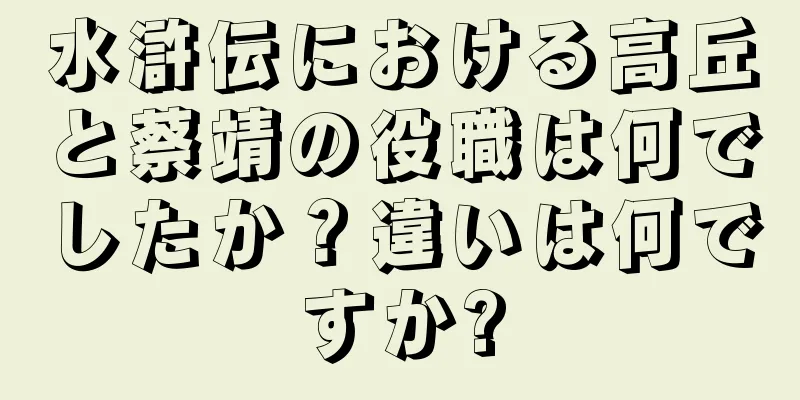唐代の頼基が書いた「玉関を去る」は戦場で死ぬ決意を表現している

|
唐代の頼基が書いた「去魚関」。Interesting History の次の編集者が、関連するコンテンツを皆さんにお届けします。 歴史上、「唐代は汚く、宋代は乱れた」という言葉がありますが、これは両王朝の王室の人間関係が乱れていることを非難するものです。彼らは汚く、世の模範や民衆の見本となるに値しない存在だったと言えます。紳士を自称する人たちの行動について語るのは本当に難しい。自分勝手な欲望のために世論を無視すれば、結局は自分がその結果に苦しむことになる。 唐の高宗皇帝、李治は、朝廷の役人たちの強い反対にもかかわらず、自分の「皇后」である武美娘と結婚し、自分のやり方を貫きました。結局、彼は自らの李王朝を滅ぼす悲劇的な結末を迎えました。武則天が王位を簒奪し、唐王朝の崩壊を叫ぶ声が上がったのも、李治の死後であった。これは、私情のために正義を無視した明らかな悪例である。 頼基は唐の皇帝高宗の「王を廃して武を立てる」計画に反対した朝廷の役人の一人であり、それ以来武則天の嫌悪を買った。その後、彼は邪悪で裏切り者の大臣である徐景宗と李易夫から、頼基、韓元、朱遂良が徒党を組んで反乱を企んでいると虚偽の告発を受けた。頼基は台州太守に、朱遂良は貴州太守に、韓元は鎮州太守に降格され、終身都に戻ることを禁じられた。唐の皇帝高宗はとても愚かで、武帝はとても邪悪でした。 頼基(610-662)は南陽の新野の出身である。彼の先祖は隋に仕え、彼の父は隋の名将頼慧であった。于文之が国王を殺害するためにクーデターを起こしたとき、彼の父と3人の兄は反乱軍に降伏することを拒否し、殺害された。ライ・ジと弟のライ・ヘンは幼かったため、幸運にも災害を逃れることができた。頼基は学問に励み、唐の高祖の時代に科挙に合格し、唐の高宗の時代には宰相を務めた。もし頼基が武則天に反対することを主張していなかったら、彼の官職経歴は比較的順調だったと言えるだろう。おそらくそれは、呉志とその仲間たちと相容れなかったからだろうが、もっと重要なのは、頼基の正統な思想が優勢だったからである。彼の道徳観と教育観は、権力の暴政に屈することはなかった。 659年、唐の皇帝高宗は叔父の長孫無忌に首を吊るよう強制した。王后の叔父である劉と韓元も処刑を命じられた。翌年、頼基は汀州の知事に任命され、トルコ軍と対峙するために単身前線に赴いた。当時、新疆の昌吉回族自治州である汀州は、西突厥10氏族の国境であり、毎年戦争が起こり、国境の住民はひどい苦しみを味わっていました。彼が直接処刑されなかった理由は、おそらく李治が皇太子だった頃、彼が李治の司宜郎であり、彼と何らかの「つながり」があったからだろうと思う。 頼基には『新唐史』をはじめ全三十巻の著作があるが、詩集『全唐詩集』にはこの「去毓関」だけが収録されている。この詩はおそらく彼が汀州に転勤した際に書かれたものと思われる。頼吉がそこに移送されれば死刑は免除されるが、終身刑は免除されない。 2年後、頼基は戦闘で亡くなった。 玉関を出発 [唐代] 頼基 私は手綱を引いてロン・ハンを追いかけます。 玉関を越えて悲しみを運ぶ。 今日、流砂の外で、 生き残ることを考えて涙を流しました。 詩の題名にある「玉関」は玉門関を指しているはずだ。漢の武帝は西域への道を開き、西域から玉が輸入されたルートにちなんで名付けられた河西四郡を設置しました。この道は、敦煌で発掘された唐代の経典では「第五の道」とも呼ばれています。その設立により郵便旅程が大幅に短縮され、輸送能力が向上し、軍事作戦の効率がある程度向上しました。 最初の文「手綱を引いて龍漢に従え」は、手綱の導くままに馬を行かせ、運命の定めに従うという意味です。集めて収集する。家畜を制御するために使われるロープ、手綱。龍寒は道教の用語で、天地の五つの災いの一つです。ここでは気まぐれな運命を指します。例えば、「龍漢末期の世をいかに創るか、敢えて問う」(呉雲『不虚辞』第9)や、「東シナ海は龍漢の数々の災難を経験し、北宮にはいつも楡林の軍勢が並んでいる」(銭謙義『祁雲岩に登り宣天太祖宮を参拝』)などは、どちらもこの意味を使用しています。 2 番目の文「悲しみを抱えて玉門関を越える」は、前の文の続きです。彼はためらいと不安の表情を浮かべ、寂しく悲しい気持ちでいっぱいになり、落ち込んで玉門関を出て歩き出しました。 「玉門関は人里離れており、数千マイルにわたって黄砂が広がり、枯れた白い草が生い茂っている。南は泉容に接し、北は胡に接しているため、将軍が来たら予期せぬ事態に備える必要がある」と唐代の詩人岑申は「玉門関将軍歌」の中で詠み、玉門関の軍事的重要拠点を鮮明に浮き彫りにしている。この連続した二つの詩節で、詩人は自分の態度や表情の描写を通して、自分の内なる絶望を鮮明かつ簡潔に表現しています。 最後の2行は「今日私は流砂の外にいて、生き残ることを考えて涙を流しています。」です。今日私は、地面が黄砂で覆われている万里の長城の外に向かっています。私は一人で涙を流してあなたに会い、いつか生き残れることを願うことしかできません。詩人は自分の現在の状況を非常によく理解しており、過去に悪人たちをあまりにも怒らせてしまったことを自覚しているようだ。韓淵のようにすぐに処刑されることはなかったが、戦争で荒廃した前線では生死が依然として危うかった。だからこそ、自分自身の不可解な生と死に対する悲しみ、最後のため息があるのです。 生と死の間には大きな恐怖があります。私たちの脆弱な体と弱い魂は、心の中で不安と心配を抱える運命にあります。その詩人は悪党と裏切り者の大臣を怒らせたため追放され、最終的には戦争の最前線に赴かなければならなくなった。彼は、外国の敵が頻繁に侵入する国境地帯で、いつ戦闘で殺されるかわからないという予感を抱いていた。予想通り、「龍朔二年、突厥が侵攻し、冀の将軍は抵抗した。彼は部下に言った。『私は詐欺の罪で死刑を宣告された。今、私は自らの体で罪を負わなければならない。』そこで彼は兜もかぶらずに敵に突撃し、五十三歳で亡くなった」(『新唐書』第百五十巻伝記三十)。頼基は名誉ある死を遂げたにもかかわらず、受けた教育を怠ることはなく、心の誇りも失うことはなかった。結局、彼は生死を超越し、心の平安を得ました。 |
<<: 唐代の張文寿が書いた「大坡楽」は女性の視点から感情を表現している
>>: 洛因の「蜂」:この詩は社会問題や歴史問題に対する作者の考えを示している
推薦する
「口若流河」という慣用句はどういう意味ですか?その裏にある物語は何ですか?
「口若6河」という慣用句をどう説明すればいいのでしょうか?その裏にはどんな物語があるのでしょうか?次...
大胆で奔放な詩人、辛其基の詩を鑑賞する:「ヤマウズラの空・黄砂の道」
以下、Interesting History の編集者が、辛其記の「ヤマウズラ空・黄砂路上」の原文と...
『紅楼夢』では、李婉は学者の家庭出身なのに、なぜ王夫人をそんなに嫌っていたのでしょうか?
『紅楼夢』の李婉は学者の家庭に生まれ、幼い頃から「三服四徳」の思想を植え付けられ、夫の家に嫁いだ後、...
馮延思の「密集した枝から数百万の梅の花が落ちる」は風景を利用して孤独感を表現している
馮延嗣は、字を正忠、仲潔とも呼ばれ、五代十国時代の宰相で、南唐の宰相を務めたこともある。詩人でもあり...
唐代の于其子が書いた詩『項羽頌』の中で、詩人は項羽をどのように見ていたのでしょうか?
唐代の于其子が書いた「項羽頌」。次の興味深い歴史編集者が、あなたと共有する関連コンテンツを持ってきま...
呉文英の最も幻想的な詩:「夜のジャスミン - 河江から北京に入り、豊門の外に停泊するときの気持ち」
古代の詩人たちは、さまざまな方法で憧れを表現してきました。たとえば、崔昊は「夕暮れの故郷はどこだ? ...
古代の火起こし道具に関する興味深い事実:ライターはマッチよりも早く発明された
一般の人々の目には、ライターはマッチよりも進歩的なものなので、ライターは現代のマッチよりも後に発明さ...
チベットの民俗祭りやチベットのスポーツ・娯楽活動とは何ですか?
チベットのスポーツ、娯楽、民俗習慣他の場所や他の民族と同様に、チベット人の生活も多様です。人々はさま...
中国の伝統文化作品の鑑賞:易経・第44卦・卦の原文は何ですか?
荀は風、乾は空を表します。風は世界中を吹き渡り、あらゆるものに遭遇します。それは出会いや予期せぬ出会...
『紅楼夢』の蟹宴会の後、皆は楽しくリラックスしていましたが、なぜ石向雲はトランス状態に陥っていたのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
四聖心源:第四巻:疲労と損傷の説明:気の蓄積
『四聖心源』は、1753年に清朝の黄元宇によって書かれた医学書で、『医聖心源』としても知られています...
古典文学の傑作『前漢演義』第22章:項羽が張良を救うために夜逃げする
『西漢志演義』と『東漢志演義』は、もともと『江暁閣批判東西漢通志演義』というタイトルで、明代の中山の...
秦王朝はどのようにして成立したのでしょうか?
秦王朝の成立:秦王朝 (紀元前 221 年 - 紀元前 207 年) は中国史上極めて重要な王朝です...
ファン・リーは成功を収めた後、どうやって引退したのでしょうか?郭建は范蠡に対してどのような態度をとっていたのでしょうか?
春秋時代は大きな変化の時代であり、特に後期には諸侯が激しく争った。范離はそのような時代に生まれました...
秀雲閣第86章:九頭の怪物が家を出て八界宮に戻り説教する
『秀雲歌』は清代の魏文忠が書いた神と悪魔を扱った長編民俗小説である。 「秀雲仙閣」とも呼ばれる。この...