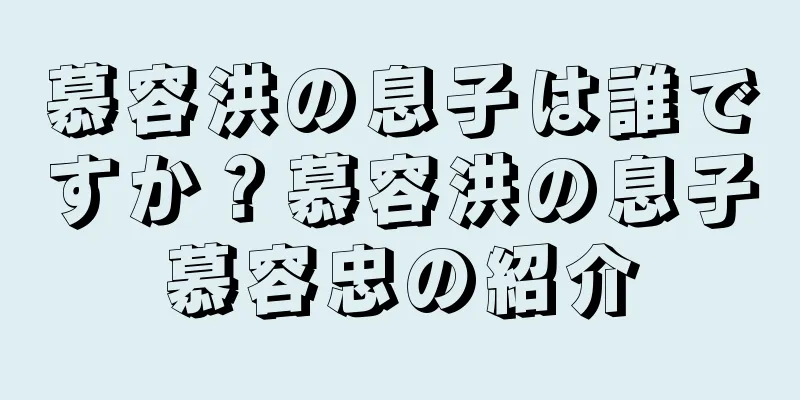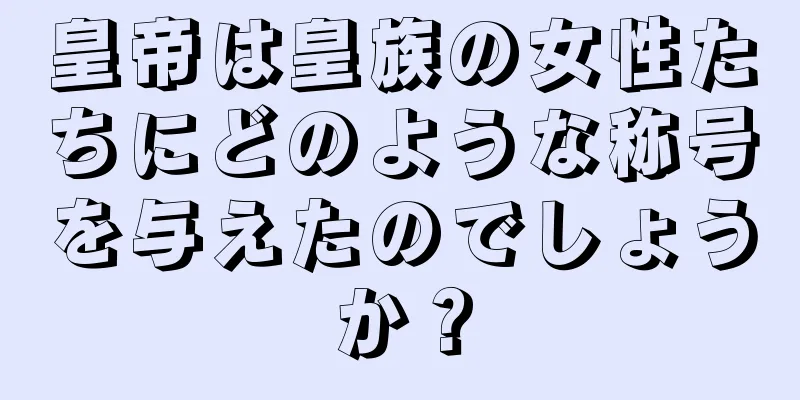蒋魁の「赤い花びら・古城影」:この詩は「興奮が終わり、悲しみがやってくる」というテーマで書かれた。

|
蒋逵(1155-1221)は、字を堯章、号を白石道人、鄱陽(現在の江西省)に生まれた南宋時代の作家、音楽家である。彼はかつて『大月易』を著し、寧宗の時代に朝廷に献上した。彼の著書『白石詩』『白石歌』『続書道集』『江鉄評』などは代々伝えられている。そのうち『白石歌』は自作の歌で、副楽譜も付いている。それでは、次の興味深い歴史編集者が、姜逵の『紅い花弁・古城影』をお届けしますので、見てみましょう! 冰武の日、私は長沙の北家観正殿に客人として訪れました。殿の下には曲がりくねった池があり、池の西側には古い壁、オレンジの木、竹があり、長く曲がりくねった道がありました。南の道を歩いていくと、ピーマンや豆ほどの大きさの梅の木が何十本もあり、中には白い露で赤く染まったものもあり、枝には豊かな影が落ちています。草履を履き、苔むした石の間を歩いていると、私は狂おしいほどの興奮を覚えた。私は急いで馬車を定王台に登らせた。湘江は廬山に流れ込んでいる。湘江の雲は上がったり下がったりして、波は穏やかだった。私の興奮は薄れ、悲しみが訪れ、私は酔ったような旋律を詠唱した。 古城の木陰には、数本の梅の花が咲いているが、その赤い花びらは簪には適していない。池の表面は氷で覆われ、壁は古い雪で覆われ、雲はまだ暗い。緑の蔓や竹が道を悠々と通り過ぎ、砂浜で眠る鳥たちを徐々に驚かせていきます。老人の森と泉、古い王の館があなたを呼んでいます。 なぜ南北に行くのですか?湘の雲と楚の水は私をとても悲しくさせます。鶏が赤い扉に張り付いていて、ツバメが金色の皿の上に群がっていて、時間がどんどん過ぎていくのに、私はただ無駄にため息をつくことしかできません。かつて西塔で開かれた優雅な集まりを思い出し、何千もの金色の糸が今も揺れているしだれ柳を思い浮かべました。家に帰る頃にはもう春が深まっているのではないかと思います。 【感謝】 短い序文に非常に詳しい記述があり、この詩は「興奮が終わり、悲しみがやってくる」という気持ちで書かれたものです。なぜ「喜怒哀楽」があるのか?なぜ「憂い」があるのか?蒋魁は、荒ぶる雲や一羽の鶴のように、自由奔放に生涯を過ごし、死ぬまで官職に就くことはなかった。しかし、文人であり、父が郡守だった官僚の家庭出身で、儒教文化の影響を深く受けていたに違いない。伝統的な「憂い」の感覚が、彼の作品に反映されているのは間違いない。この詩は、山に登ったり観光したりしながらの詩人の悲しみを表現した作品です。前半は早春の旅の楽しさを綴ります。詩の後半は、家を離れて旅をしている気持ちを表現しています。詩全体は広大で精緻で、風景を描写し、感情を混ぜ合わせ、冬の梅の花の寒さと緑を描写しています。文章は素晴らしく、新鮮で、簡潔で力強く、遠い郷愁の表現は深く、優しく穏やかです。 |
<<: ヤン・レンの「木蘭花・春風は庭の西にのみ吹く」:この詩は閨房のための作品である
>>: 姜逵の「天に杏の花、鴛鴦を撫でる緑の絹」は、合肥で恋人を恋しがる旅人のために書かれた。
推薦する
西周の太夫はどのような権力を持っていましたか?泰夫は現在どのような役職に相当しますか?
太夫(たいふ)は、古代中国の官職。西周の時代に始まり、周公丹が太夫(太夫は朝廷の副大臣で皇帝の師匠(...
孔子は多くの弟子の中でどの弟子を最も愛していましたか?
弟子たちの中で、孔子が最も好きだったのは誰ですか?孔子のお気に入りの弟子は顔回でした。孔子が顔回を好...
孫悟空が天界で大混乱を引き起こした後、72人の魔王に何が起こったのでしょうか?彼らが行った場所
菩提祖から戻った後、孫悟空は水蔵洞の魔王を一掃し、澳来国から武器を奪い取り、猿の兵士と将軍を訓練し始...
太平光記・第78巻・錬金術師・王さんの原作の内容は何ですか?どう理解すればいいですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
水滸伝の楊林の結末は何ですか?金宝子楊林の簡単な紹介
水滸伝の楊林の結末は? 金豹楊林の紹介古典小説「水滸伝」の登場人物で、金豹の異名を持つ。楊林はずっと...
曹操の「苦寒行」:この詩は彼の悲しく荒涼とした出来事を直接語り、彼の寛大な気持ちを表現している。
魏の武帝、曹操(155年 - 220年3月15日)は、雅号を孟徳、あだ名を阿満、吉理といい、沛国桥県...
『紅楼夢』で薛潘は黛玉に対してどのような感情を抱いているのでしょうか?
『紅楼夢』では、薛潘は「戴八王」というあだ名を持つダンディボーイの代表です。興味のある読者と『Int...
太上老君の伝説が最初に広まり始めたのはどの王朝ですか?老君の発展の歴史を詳しく解説
太上老君は道教における最高位の道祖であり、世界の創造と救済を担う。彼は「元師天尊」と「霊宝天尊」とと...
白居易の詩「江楼から夕を眺めて客を招く」は杭州郊外の繁栄した風景を描写している。
白居易は、字を楽天といい、別名を向山居士、随音献生とも呼ばれた。写実主義の詩人で、唐代の三大詩人の一...
『紅楼夢』のカニ祭りに参加したのは誰ですか?彼らはカニのどの部分を食べるのが好きですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
『紅楼夢』の薛宝才の牡丹の花札に「無情でも、心は動いている」というフレーズが使われなかったのはなぜですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
忠誠を誓う岳飛の韓世忠の姿
岳飛と韓世忠南宋の愛国的な将軍、岳飛が民衆を率いて金の兵士に抵抗したという伝説が数多くあるが、韓世忠...
麩は昔からとても人気がありました。では、有名な麩と呼べるものは何でしょうか?
中華民族には約5000年の文化があり、その中には優れた詩歌が数多く存在します。特に『中国古詩八大名詩...
カップルにとって最も重要なことは長期的な関係であり、それは衡卦が表現する真理である「繁栄、無過失、利益、堅実」である。
最も重要なのは長寿であり、それは衡卦の「繁栄、無過失、利益、安定」が表す真理です。次の興味深い歴史編...
華雄とは誰ですか?華雄は歴史上どのように亡くなりましたか?
華雄って誰ですか?この質問は非常に簡単です。『三国志演義』や『三国志演義』を読んだことのある人なら、...