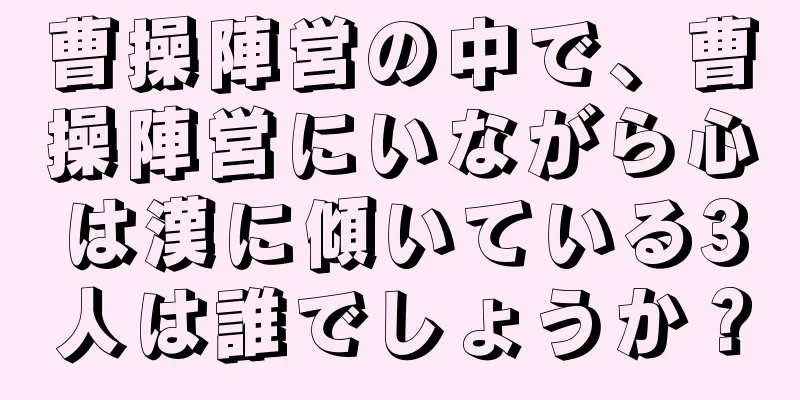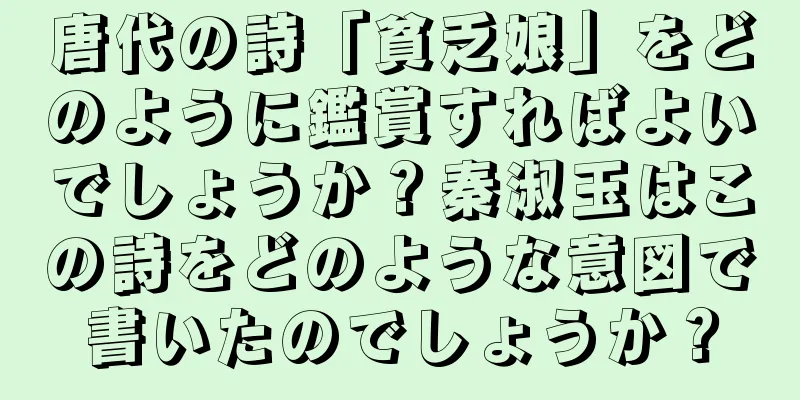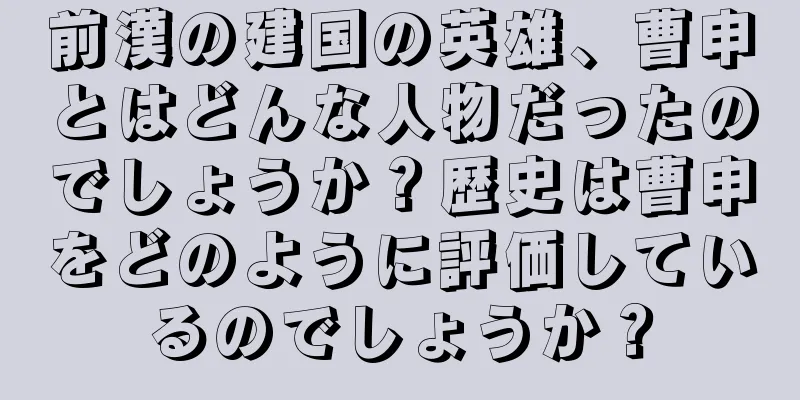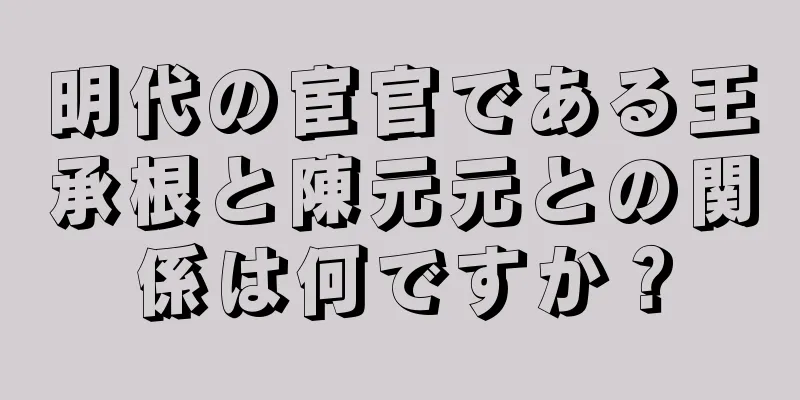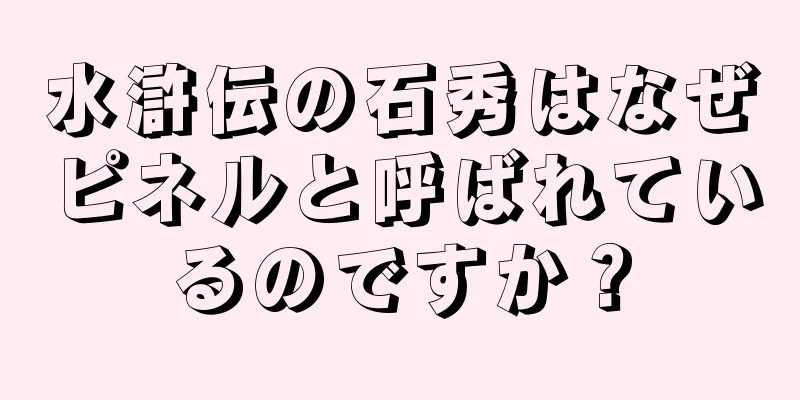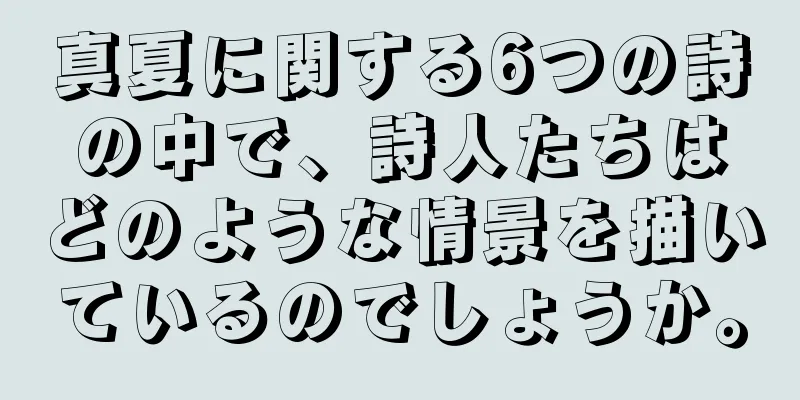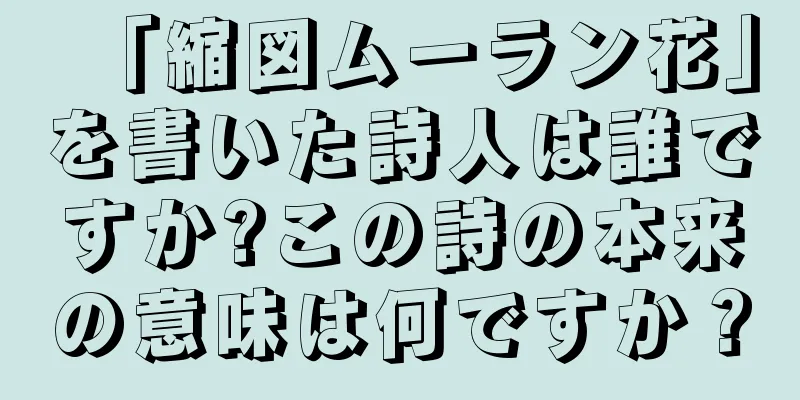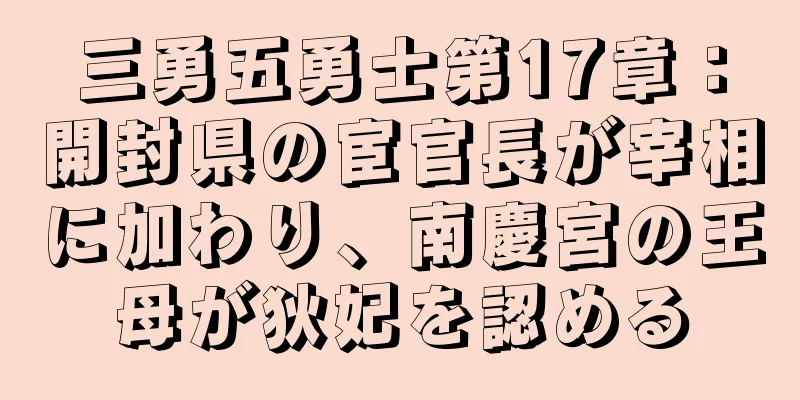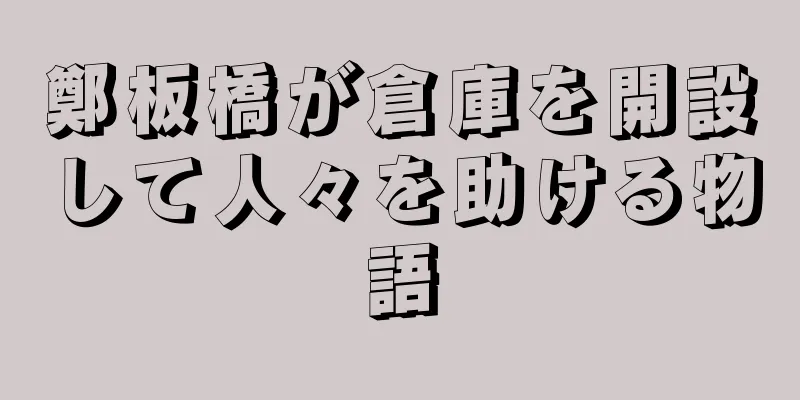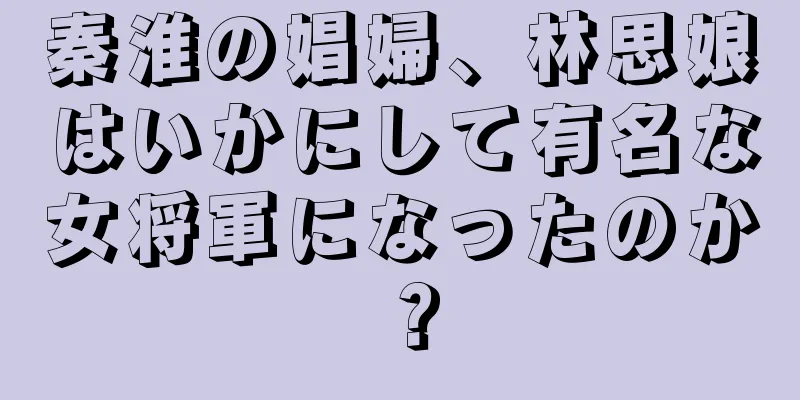『西遊記』の三昧の火は孫悟空をひどく焼くほど強力だったのでしょうか?
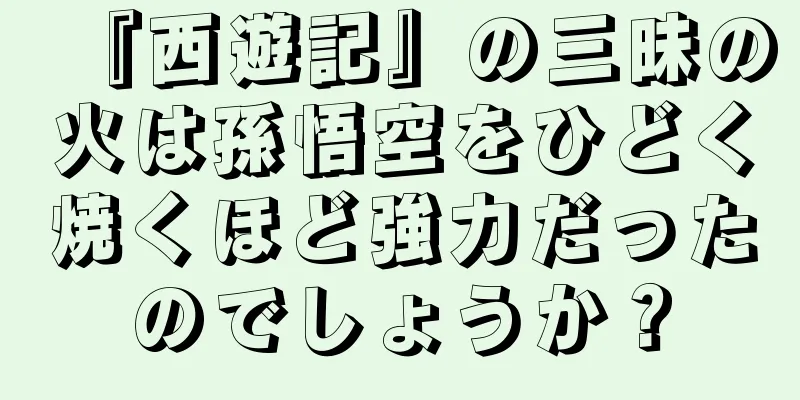
|
レッドボーイは赤ん坊のように見えますが、実は100年の修行を積んだ魔の子です。 Interesting History の編集者は、以下のテキストで上記の質問に対する答えを一つずつ明らかにします。 西遊記第7章を見てみましょう。当時、孫悟空は二郎神に捕らえられていました。玉皇大帝は孫悟空を殺そうと全力を尽くしましたが、ナイフ、雷、火を使っても孫悟空を動かすことはできませんでした。最終的に、太上老君が解決策を提案しました。 玉皇大帝は言った。「あの猿は桃を食べ、皇帝の酒を飲み、不老不死の薬を盗んだ。生のものも煮たものも含め、私の五つの壺の不老不死の薬を全部食べ、三昧の火でそれを一つに鍛えたので、鋼鉄の体となり、急いでも傷つかない。それを道士のところへ持って行き、八卦の炉に入れて、民兵の火で鍛えて私の不老不死の薬を精製すれば、彼は灰になるだろう。」 - 第7章 細部に注意してください。「三昧真火」を持っているのは、太上老君でも八卦炉でもなく、孫悟空自身です。仙桃、皇酒、仙薬を盗んだ後、彼の体内の三昧真火は「訓練」され、最終的に彼の不滅の体につながりました。 ここで、太上老君は孫悟空を八卦炉に投げ込み、「民武火」で訓練することを提案しました。ここでの民武火は「三昧真火」ではなく、「六丁神火」です。 この点については、太上老君自身は明確に述べていないが、後に孫悟空が西方へ仏典を得る旅で唐和尚を護衛していたとき、何度も「自己紹介」をした。例えば、第17章「孫行哲、黒風山で騒ぎを起こす」では、孫悟空は「私は老君の炉に送られて精錬され、六定神火でゆっくりと煮込まれた。日が暮れて炉が開くと、飛び出して鉄の棒を手に空を駆け回る」というような下手な発言をしたことがある。 言い換えれば、六丁神火の威力は三昧真火よりはるかに強いため、太上老君は孫悟空を焼き殺すためにこの方法を選択しました。実際、太上老君の考えも正しく、六丁神火は確かに孫悟空を焼き殺すことができますが、孫悟空が八卦炉に入った後、事故が発生しました。原文を見てみましょう。 炉は銭、坤、根、真、荀、李、坤、徽であった。彼は「荀宮」の下で自分自身を掘り下げようとしていた。荀は風を表し、風があれば火は出ない。しかし、風が煙を巻き起こし、彼の目は赤くなり、彼は眼病にかかったため、「火の目と金の瞳」と呼ばれた。 ——第7章 孫悟空はとても賢く、八卦炉の舜の位置に隠れ、「舜の位置」からの風を利用して火を吹き飛ばし、劉定の神火から逃れました。後のテキストでも、孫悟空が経典を手に入れるために旅をしていたとき、彼は魔力を使って風を起こすたびに、「迅地」に向かって風を吹きつけていた。 最終的な結果は、孫悟空は焼死せず、金色の目で見る能力も発達したというものでした。しかし、孫悟空は「荀彧の位置」からの煙で目が見えなくなり、それ以来煙を恐れるようになりました。これは非常に重要で、以下の文章にある孫悟空の異常な行動の多くはこの点に関連しています。 なぜレッドボーイは孫悟空を傷つけることができたのでしょうか? 上記の分析によると、六定神火の威力は三昧真火の威力よりも大きい。なぜ孫悟空は八卦炉から逃れることができたが、小さな三昧真火によって傷つけられたのだろうか? 実際、孫悟空は紅少年の三昧の火をまったく恐れていませんでした。問題は、紅少年が三昧の火だけでなく濃い煙も吐き出すことでした。 悪魔は二度殴り、呪文を唱えると、口から火が出て、鼻から濃い煙が出て、目が光って炎が現れました。五台の車から炎が噴き出しました。孫悟空はこれを熟知しており、火を避ける術を修練して火の中に飛び込み、怪物を探しました。大聖人は「私が火を避ける術を修練するまで待ってから火の中に飛び込んでください」と言いました。彼は鉄の棒を振り回して怪物を見つけ、それを打ちました。悪魔は旅人が近づいてくるのを見て、彼の顔に煙を吹きかけました。旅人は煙で目がくらみ、思わず涙を流しながら慌てて引き返しました。 ——第41章 孫悟空は三昧の火をまったく恐れませんでした。彼はただ金の棍棒を手に取り、火を避ける戦術を練習し、戦うべき紅坊を見つけるために火の中に突入しました。しかし、濃い煙に遭遇すると、彼の目に涙が溢れ、退却しなければなりませんでした。 孫悟空は煙を恐れています。これは『西遊記』の目に見えない設定であり、読者は自分で発見する必要があります。 最も典型的な例は第70章「魔の宝が煙と砂と火を放ち、悟空は紫金の鈴を盗もうと企む」です。孫悟空が金髪侯から紫金の鈴を盗んだ後、彼は思わず鈴の綿を引っ張って開け、花火と黄砂が噴出しました。孫悟空は非常に怖くなり、すぐにパニックになり、紫金の鈴を落としました。これは、孫悟空が西への旅で本当にまれに見る重大なミスでした。 なぜ孫悟空は龍王に雨を降らせるように頼んだのでしょうか? ところで、孫悟空は紅少年の三昧の火を恐れていなかったのに、なぜ龍王に雨を降らせて火を消せと頼んだのでしょうか。この設定は少し矛盾しているように思えますが、そこには探るべき内部論理があります。なぜなら、「水を使って火を克服する」ことを提案したのは孫悟空ではなく沙悟浄だったからです。原文を見てみましょう。 沙生は言った。「悪魔のやり方はあなたほど良くないし、槍の腕もあなたほど良くない。ただ火力が高いだけで、勝てない。私のアドバイスに従えば、相互生成と相互抑制を使って簡単に倒せるだろう。」 - 第41章 沙悟浄は真実を知らず、孫悟空が三昧の火のせいで負けたと誤解していました。実際、孫悟空が本当に恐れていたのは煙でした。しかし、沙僧がこの提案をすれば、孫悟空ははっきりとこう言うでしょう。「私は三昧の火を恐れているのではなく、煙を恐れているのです!」それは他人に自分の弱点を告げるようなものなので、孫悟空はむしろそれを最大限に活用するでしょう! これは孫悟空の狡猾で機知に富んだ策略です。よく見ると、孫悟空が龍王に雨を降らせるよう頼んだのには 2 つの目的があります。 まず、煙を恐れるという弱点をさらけ出さないでください。 第二に、朱八戒と沙悟浄は彼と正反対です。彼らが恐れているのは煙ではなく、三昧の火です(孫悟空は目の病気を患っていますが、彼らには病気はありません)。孫悟空が龍王に雨を降らせて火を消すように頼めば、朱八戒と沙悟浄が先鋒となって紅少年を食い尽くすのを手伝い、紅少年が疲れ果てるまで待ってとどめを刺すことができます。 西方への旅の途中で、孫悟空はこのような状況に直面するといつも同じことをしました。例えば、彼は泳ぎが得意ではなく、水中で怪物と戦う勇気がなかったので、いつも朱八戒に頼んで水に入って怪物を陸に導いてもらい、故郷に戻ってから行動を起こしました。 しかし、孫悟空が予想していなかったのは、龍王の雨は普通の火しか消せなくて、三昧の火は消せなかったことです。結局、彼は紅坊の花火に押し戻されました。このとき、孫悟空はもう一つのミスを犯しました。火を消すために水に飛び込んだのです! 原文を見てみましょう。 大聖人は炎に包まれて非常に怒っていたので、火を消すために川に身を投げました。しかし、冷たい水が彼を激怒させ、彼は魂を失いそうになった。とても哀れなことです。胸は詰まり、喉は冷たくなり、魂は散らばり、人生は台無しになります。 ——第41章 孫悟空は鋼鉄の体を持っていたので、三昧の火で焼かれても大怪我をすることはありませんでした。しかし、燃えている体で冷たい水に飛び込んだため、交互に襲ってくる寒さと熱さで内臓損傷を起こし、危うく命を落としそうになりました。結局、彼らはこの災難を乗り越えるために観音菩薩に助けを求めなければなりませんでした。 まとめると、孫悟空と紅少年の戦いには多くの欠陥があるように見えますが、実際には内部の論理は厳密であり、単純な神話の物語と比較することはできません。 |
>>: 『紅楼夢』で、なぜ宝玉は宝仔と黛玉を妙玉と一緒にお茶に連れて行ったのですか?
推薦する
崑寧宮とは何ですか?なぜ崑寧宮は不吉な場所とみなされているのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が崑寧宮についての記事をお届けします。ぜひお読...
「春の夜に嬉しい雨」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
春の夜の雨杜甫(唐代)良い雨は季節を知り、春に降ります。風とともに夜に忍び込み、音もなくすべてを潤し...
古典文学の傑作『太平記每日』:礼部第二巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
三国志演義 第30章 官渡での弁楚の敗北、武超孟徳の略奪と穀物の焼き討ち
『三国志演義』は、『三国志演義』とも呼ばれ、正式名称は『三国志演義』で、元代末期から明代初期にかけて...
『紅楼夢』の王禧峰はなぜいつも大観園を丁寧に管理していたのでしょうか?
王希峰は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人です。以下の記事はInteresti...
『紅楼夢』の賈家における宝仔の人気はどのくらいですか?何が変わったのでしょうか?
宝仔は『紅楼夢』のヒロインの一人であり、林黛玉とともに金陵十二美女の第一位に数えられています。これに...
秦王朝の滅亡後、項羽の国はなぜ「東楚」ではなく「西楚」と呼ばれたのでしょうか?
秦末農民反乱は、秦末農民反乱とも呼ばれ、中国本土では秦末に多くの英雄が台頭した事件に付けられた名前で...
司馬遷の簡単な紹介:歴史家司馬遷の歴史における真の姿
人物:司馬遷(紀元前135年 - 紀元前90年)は、字を子昌といい、西漢時代の夏陽(現在の陝西省漢城...
道光帝はなぜ四男の咸豊帝に帝位を譲る遺言を密かに書いたのでしょうか?
易信は道光帝の六番目の息子であり、咸豊帝は道光帝の四番目の息子であった。仙鋒は易鑫より2歳年上だった...
岑申の『崔世玉を楽海より都に送り返す』の原文は何ですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
岑申の『崔世玉を崔世玉を崔世玉に送還して都に帰す』の原文は何ですか? どのように理解しますか? これ...
『紅楼夢』で薛一家が北京に来た理由は何ですか?
宝仔は『紅楼夢』のヒロインの一人です。林黛玉とともに金陵十二美女の第一位に数えられています。今日は、...
清朝における九門司令官とはどのような官職だったのでしょうか?その力は何ですか?
「九門提督」は、中国の清朝時代に北京に駐留していた軍人です。彼の正式な肩書きは「九門提督、五個歩兵哨...
孟浩然の古詩「王九を鸚鵡島江左に送る」の本来の意味を鑑賞
古詩「英武島から江左へ王九を送る」時代: 唐代著者: 孟浩然川沿いの黄鶴楼に登ったとき、遠くに見える...
宋代における人生の四つの芸術とは何ですか?なぜ文学者や学者に求められるのでしょうか?
宋代の人々にとって、お茶を点てること、香を焚くこと、花を生けること、絵画を掛けることなどは、総じて「...
南宋時代の翰林学士について簡単に紹介します。彼らの日々の仕事は何でしょうか?
翰林学士制度は唐代に始まり、唐代後期から五代にかけて進化と発展を続けました。北宋初期までに、翰林学士...