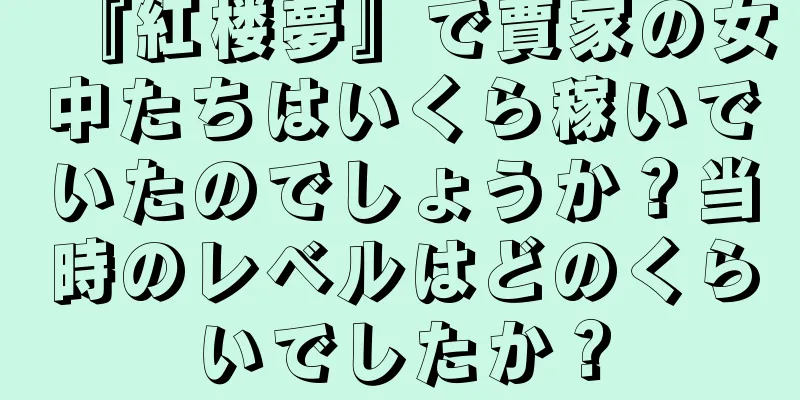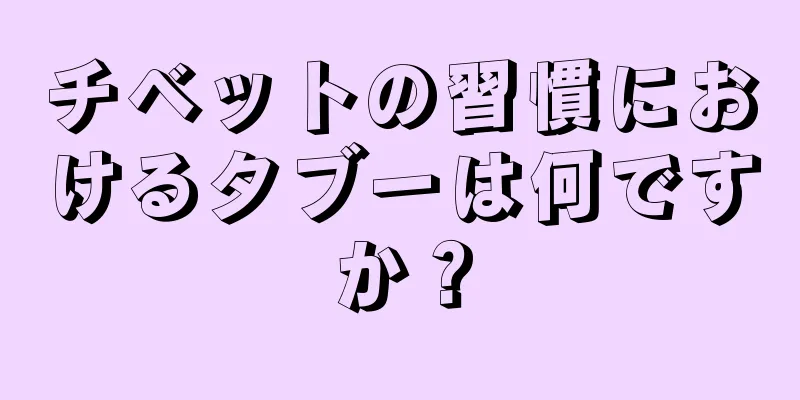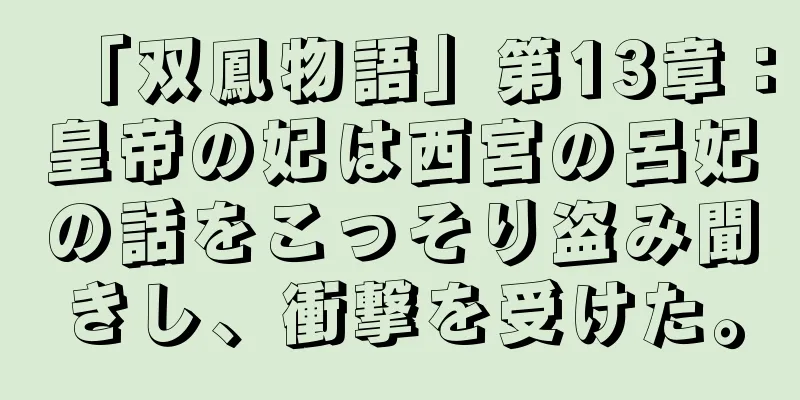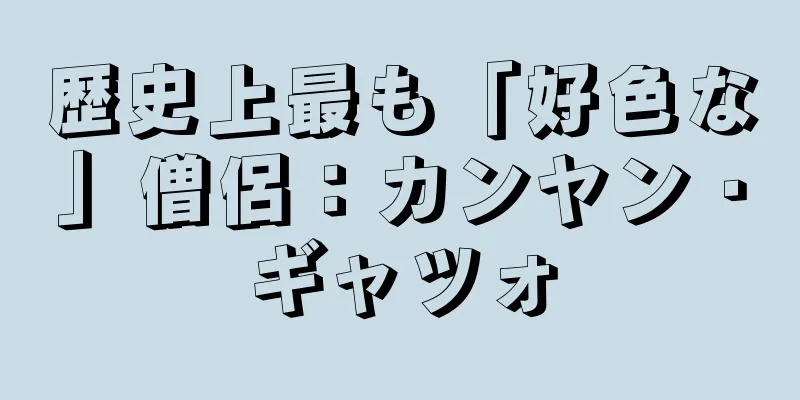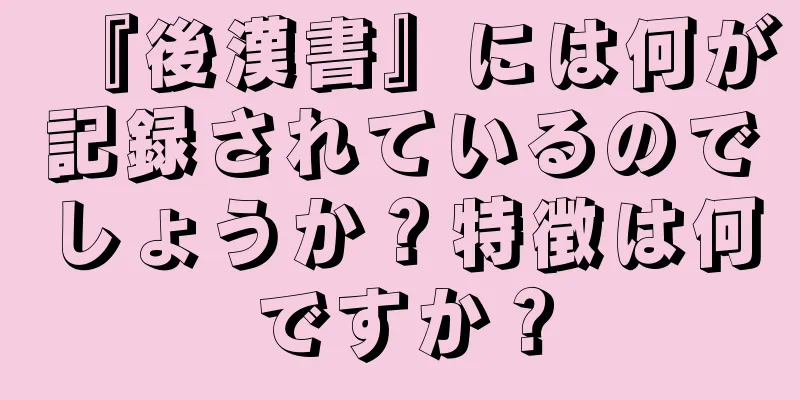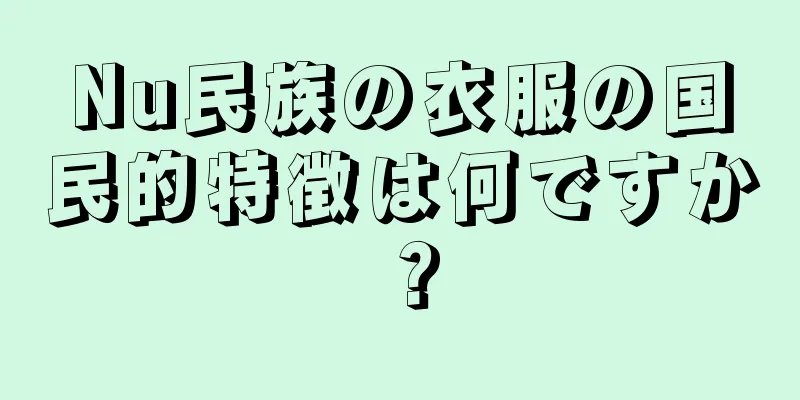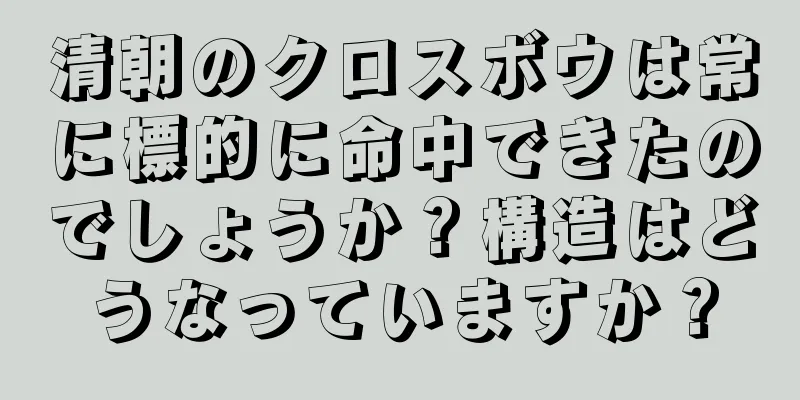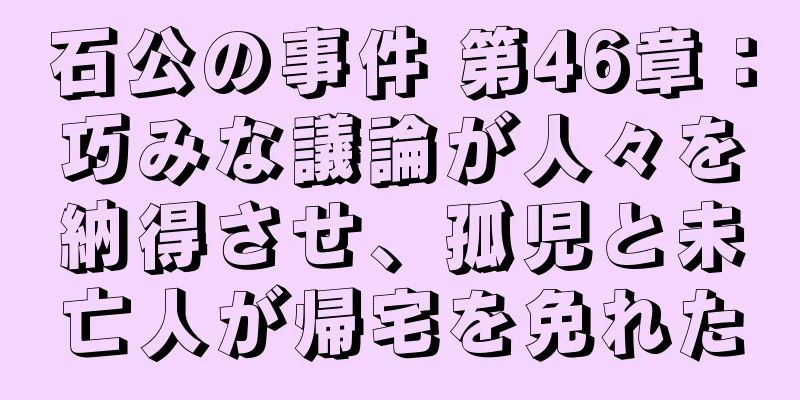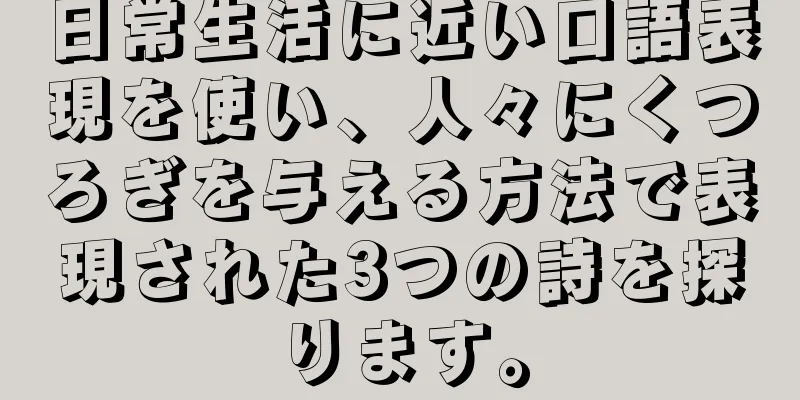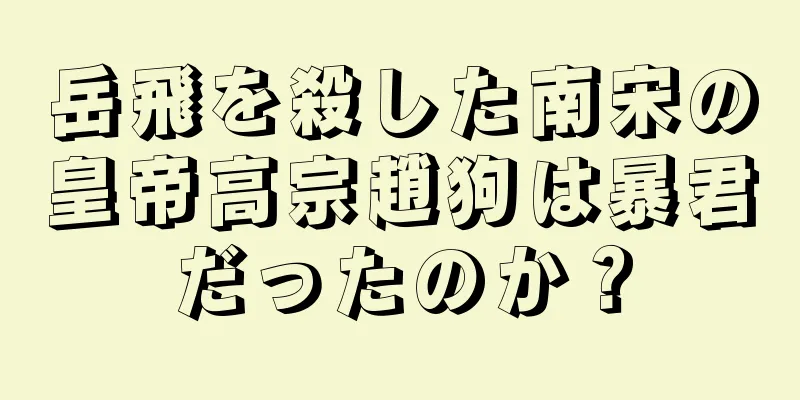古典文学の傑作『太平天国』地理部第17巻全文
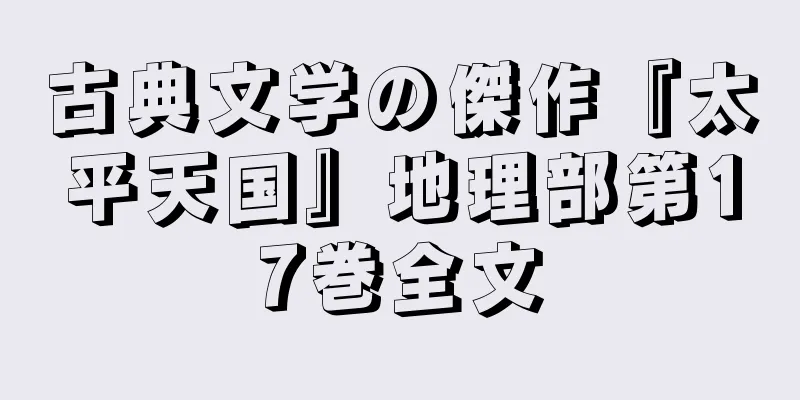
|
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂したもので、太平興国二年(977年)3月に始まり、太平興国八年(983年)10月に完成しました。 『太平毓蘭』は、55部550の分野に分かれ、1,000巻にまとめられた各種書籍のコレクションであるため、もともと『太平宗録』と名付けられていましたが、書籍が完成した後、宋の太宗皇帝が毎日3巻を読み、1年で全巻を読み終えたため、『太平毓蘭』に改名されました。本書は天・地・人・事・物の順に55部に分かれており、古代から現代まであらゆる事象を網羅していると言えます。この本には1000冊以上の古書が引用されており、宋代以前の文献資料も多数保存されている。しかし、そのうち7、8冊は失われており、そのことがこの本の貴重性をさらに高め、中国伝統文化の貴重な遺産となっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が地球部門第17巻の詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! ○ 石田 『西都雑記』には、竇太后が家にいたとき、白いツバメが指ほどの大きさの石を運んで、皇后の織物籠の中に落ちたと記されている。皇后はその石を取り出して二つに割った。石の真ん中には「天地の母」と刻まれていた。皇后はその二つを合わせて、二度と開けることはなかった。皇后になってからは、いつもそれを印章と一緒に置き、天印と呼んだ。 五鹿崇宗は米成子に師事したとも言われています。米成子が若い頃、人々はよく彼に会い、鶏の卵ほどの大きさの刻まれた石を渡しました。米成子はそれを飲み込み、その後、非常に悟りを開いた、世界で有名な学者になりました。その後、程子は病気になり、その石を吐き出して崇宗に渡した。崇宗はそれを再び飲み込み、再び学者になった。 また、漢の武帝が昆明池で魚を飼っていたが、魚はよく飛んで行ってしまった。その後、鯨の形に彫った石を水の中に入れて魚が飛んで行かないようにした。雨が降るたびに魚は鳴き声をあげたという。 顧凱之の『悟りの書』にはこう書かれている。「霊嶺県には石のツバメがいて、風雨が吹くと本物のツバメのように飛ぶことができる。」 「荀陽記」は言う:「石景山の東には丸い石の崖があり、その明るさは人を映し出し、細かいところまで観察できるほどだ。」 『冥界記』にはこう記されている。宮殿の楼閣と湖のそばの岩の間には、鏡のように丸く、人を映すほど明るい石がいくつかある。石鏡と呼ばれる。その後、誰かが通りかかり、片方の目を火で焼きました。その男性はもう目が見えなくなり、盲目になりました。 于仲勇の『湘州記』には、殷陽県蔡子池の南に石臼があり、蔡倫の紙臼であると言われている、とある。 王欣之の『南康記』には、「亀美山の岩は赤く、絵のように明るく、高くそびえ立ち、天を突き抜けて天に近づいている。その名を女媧石という。」とある。激しい嵐の後、空は晴れて空気は静かで、弦楽器の音が聞こえました。 「石易記」は言った。「元角山の東に雲石があり、幅は500マイルで、錦のように見える。それを叩くと、破片が雲のように舞い上がる。」 また、魏の明帝の時代には、泰山の麓に二つの絡み合った石があり、高さは十二丈で、枯れ木のような形をしていたとも言われています。石の模様は鮮やかで、まるで人間の彫刻のようでした。下から上まで、百段以上ありました。魏の明帝の時代には、二つの塔のように、ますます近づいているように見えました。土と石は陰の要素であり、衛は土の徳であり、氣は精神である。 「膠州記」は言う:「海には軽石山がある。その石は軽くて中が空洞なので、足をこするのに使える。また、煮て飲んで喉の渇きを癒すこともできる。」 『東明記』は言う:元定の時代、田支国は九転仙薬を作るために馬石を貢物として捧げた。白髪の方はこの石でこするとすぐに黒くなります。 顧野王の『吉祥図』には「石花とは石の上に生える花を意味する」とある。 劉承之の『江州記』には、興平県蔡子池の南に石窟があり、深さは約200フィートである、石の色は緑色で、硯として使用できると書かれている。 『蜀の記録』には、冀の出身の魏叔同は生まれつき孝行な性格だったと記されている。母親は川の水を飲むたびにそれを飲まなければならず、水を汲むたびに川の中の石が出てくるのです。現在、川には孝子石と呼ばれる石があります。 『十大陸記』には、柳州は西海の真ん中にあり、崑崙石と呼ばれる多くの石があり、その石は鉄に加工したり、刀にしたりすることができると書かれている。光は水晶のように穴を通して輝き、泥を切るように玉を切ることもできる。 「易州記」は言った。龍盤山に長さ40メートル、高さ5メートルの石があり、その真ん中に扉があり、人が閉めることができる扉がある。古い伝説によると、ここは翡翠の少女の部屋だそうです。 史虎の『葉仲記』には、葉城から孟津河の東5マイルに吉北郡の古城県があり、そこに黄世公が埋葬された古城山がある、と書かれている。ある人がこの山に登り、崩れた土の中にはっきりとした模様のある石を見つけました。胡は宮廷知事に任命され、古城知事の職を解かれたが、このことは皇帝に報告されなかった。 「荀陽記」はこう語った。「落星石は公庭湖にあり、周囲は百段以上、高さは五メートルで、石の上には竹林が生えている。」 『武昌記』には、道将軍廟の東に龍石が巻かれていたと記されている。古い伝説によると、この石の周りに龍が巻かれていたという。 『梁州記』は次のように述べている。綿陽城は漢江の上流15マイルにあり、諸葛武侯が守っている。漢江の南に位置し、背を山に向け、水に面している。門の前には石が積み重なって陣形をなしている。 『荊州土経』には、易都に洞窟があり、洞窟の中には1丈離れた2つの大きな石がある、と書かれている。一般的には、一方は陽石、他方は陰石と言われています。洪水や干ばつは災害です。陽石を叩くと雨が降り、陰石を叩くと晴天になります。これが臨君石です。しかし、鞭打たれた者は長く生きられず、人々は彼らを非常に恐れ、罰することを望まない。 『丹陽記録』には、石頭城の西に唐瑞石があり、そこで王盾が周伯仁を殺したと記されている。 また、晋の恵帝永寧二年、湖德県で、小島から二百歩離れた湖で大きな石が見つかり、岸に流れ着いたため、人々は驚き、皆、それが石の来訪だと言ったと伝えられています。ある年、揚州に石氷が持ち込まれました。 裴元の『広州志』には、甘泉県の平原に、一つの岩がそびえ立ち、その頂は雲にまで達し、岩が互いにつながって建物のように見えると記されている。 「安成記」はこう言った。「石室には数斤の白い石があり、雀の頭のような形をしていて、甘くて、しっとりしていて、サクサクしていて、ほとんど食べられそうだった。」 曹叔牙の『奇事記』には、次のように記されている。「毓章に黄白色でざらざらとした石がある。水をかけると熱くなる。鍋をかけて火にかけ、火が通るまで煮る。冷めたら、さらに水をかけてもいい。」雷歓は張華にそれについて尋ねると、張華は「もちろんそれは石です」と答えた。 「韓観義」はこう言った。馬俑は泰山に登って二つの石を見た。一つは漢の武帝の時代の石で、五台の車で山まで運んだが足りなかった。そこで山の中腹に置いて家を建て、五車石と呼ばれた。もう一つには功徳を記念する数字が刻まれ、祭壇に置かれた。 王紹之の『世行記』にはこう書かれている。老口の北に道石があり、霊石とも呼ばれている。晋の永和年間、正装した二体の仙女がこの石の上に止まり、10日後に去っていった。 盛洪志の『荊州記』には、臨河県に斧や刀で研いだ跡のある青い石があり、春夏は明るく清らかだが、秋冬は雑草が生い茂る。雷を研ぐ石と言われている、とある。 また、珠陽の汾水の口には石があるという。深さは不明だが、地上から一尺余りあり、周囲は三尺ほど。色は極めて緑色で、上部は切り口のようで、人の顔が透けて見えるほど透明である。隕石と言われている。郡の西側に池を見下ろす孤立した岩が突き出ており、その根の一部は竹の根のように見えることがあります。 また、范冲の母は雷を怖がっていたため、雷を避けるために石室を造り、石で階段を作ったと言われており、それは現在も残っています。 臨河鳳城県の東5マイルに古い県廟があると言われています。伝説によると、漢の淮南王安が処刑されたとき、彼の息子が逃げてここに来ました。彼は突然石の男に変身し、県門の前に立ったそうです。人々は驚いて彼らを見たが、よく調べてみると、彼らの手足はみんな傷や潰瘍で覆われているのが分かった。 『奇異の記録』には、鏡湖について、民間の伝説によると、玄元帝が湖のほとりで鏡を鋳造したと記されている。現在、玄源鏡砥石は、常に清潔で雑草が生えていません。 『于地之』は言う:会稽の秦王山の秦始皇帝の刻んだ石の前に、幅が数メートルの石がある。これは秦始皇帝が座った石だと言われている。両側に8つの四角い席がある。これは宰相以下の者が座った石だと言われている。そのため、現在は宰相石と呼ばれている。 『玄奘記』はこう言っています。「世界で最も強い場所は東シナ海です。そこは肥沃で、焼けた岩で覆われています。面積は3万里四方です。海水は海を満たすとすぐに枯渇してしまうので、水は溢れることなく東に流れていきます。」 玉門の西南に国があるという。国には山があり、山の上に寺院がある。その国の人々は毎年何千もの石を産出しており、それを雷と呼んでいる。石は春の雷とともに減少し、秋には消えてしまう。 『鄱陽記』には、千倉石は饒州の西方百里にあり、石の形は穀倉のようであると記されている。昔、漁師が夜、石の下にいました。突然、石が開いて、石の中にお金が入っているのが見えました。漁師はそのお金を持って船で去りました。こうして、その漁師は有名になりました。 『県州記録』には、乞子石は馬湖の南岸にあると記されている。東の石の腹からは小石が出て、西の石の腹には小石が入っている。そのため、白族はここで子供を乞うと答えが得られることから、乞子石と呼ばれている。 泗州には金鶏石があり、その石の上では常に金鶏が鳴いているとも言われています。 仙石とも呼ばれています。かつてこの石から仙人が飛び降りたため、仙床とも呼ばれています。 また、謝州農東県の青龍水の下には石豚峰があり、そこには数十体の石豚の母子がいるとも言われている。かつてイ族の人々がここで放牧していたが、豚が石に変わってしまったという。現在、イ族の人々はここで放牧することを敢えてしない。 また、儋州彰化の虎鳴山には人の形をした二つの石があると言われています。海で釣りをしていた二人の兄弟が石に変わったことから、兄弟石と呼ばれています。 貴州省興安県には横たわる石があるという言い伝えもあります。人の形をしていますが、全身が緑と黄色で隠れています。一般的に石神と呼ばれています。雨乞いをすることができます。少し上げると少し雨が降り、大きく上げるとたくさん雨が降ります。 貴州省興安県には横たわる石があるという言い伝えもある。人の形をしているが、全身が緑と黄色で隆起しており、通称「石人」と呼ばれている。雨乞いに使うことができ、軽く隆起すれば小雨が降り、重く隆起すれば大雨が降るという。 馬陵山の断崖には毒蛇がたくさんいて、毒で人を殺してしまうとも言われています。毒を溶かす冷たい石があり、その粉末を傷口に入れると生き延びることができるそうです。 また、涼州の女人山で張魯の娘が石の上で洗濯をしていたところ妊娠したが、魯は彼女を姦通の罪で告発し、釈放したとも言われている。その後、二匹の龍が生まれました。娘が亡くなり、埋葬されようとしたとき、棺の車が突然この山に飛び上がり、そこに埋葬されました。水辺の洗濯石は今も残っており、乙女山と呼ばれています。 また、郴州市の北70マイルに花石山があり、その孤石は非常に高く、仙人が話す場所であると言われています。 『地理志』には、南陵県に女官山がある、とある伝説がある。蜀の官吏の夫を持つ女性がいた。夫はいつも秋に遅れ、彼女は心配して悲しかった。そこで彼女は山に登って外を眺め、人の形をした石に変わった。引かれていた犬も石で作られており、今もその形が残っています。 「ボウズィ」曰く:コウノトリは水鳥で、卵を産むときはよく水に入ります。卵は冷たいので、ミョウバンを取って卵の周りに巻き付けて保温します。 『華陽国之』にはこう記されている。「文山には塩石があり、それを煮ると塩が取れる。」 「易源」は言う:太元の初めに、滕芳は碑文の刻まれた枕で眠っていた。突然、暴風雨が枕を揺らし、周りの人々は恐怖に陥ったが、滕芳はその音をわずかに感じた。 また、永康光王の井戸には洗濯石があり、時々赤いガスが出ていたと伝えられている。その後、2人の胡人がそこに滞在し、突然それを買いたいと思った。クアンは困惑し、お金を量る前に、彼の義理の娘の孫さんが岩の上で戦っている2羽の黄色い鳥を見つけました。孫さんが急いで駆け寄って鳥を捕まえると、鳥は金に変わりました。胡族の人々はこれに気づかず、ますます切迫した要求をしました。お金を手に入れた後、彼らは偶然、中に2羽の鳥しかいない場所を見つけました。 劉景書の『易源』には、晋の武帝の時代に、呉県臨平の堤防が崩れ、石の太鼓が現れたが、打っても音が出なかったと書かれている。彼は張華に尋ねた。張華は「四川の桐の木を魚の形に彫って、たたくと音がするよ」と言った。そこで彼らは言ったとおりにすると、たたく音は数十マイル先まで聞こえた。 『奇事記』には、益州には銅も鉄もないので、人々は青石を砕いて石矢に似た弓矢を作ったと記されている。 『事物論』にはこうあります。「土の精髄は石となり、石は気の核心である。」気によって石が作られるのは、人間の腱と静脈によって爪と歯が作られるようなものです。 「伯武之」曰く:桃林は洪農湖県の秀牛山に位置し、そこには帝台の基礎とされる石がある。 5つの色と模様があり、ウズラの卵のように見えます。 『名山紀行』には、芙蓉島にはそびえ立つ岩があり、その頂上は青と白の色をした生まれたての蓮のように見えると書かれている。 『山海経』には「燕山には童石が多い」とある。翡翠のような形をしていて、緑色の帯があると言われており、燕石と呼ばれています。 また、お金が出てくる山には、洗われた石がたくさんあるとも言われています。お風呂に入れば汚れは取れます。 『水景朱』にはこう記されている。湘林県の公曹は屈と名乗り、廉という息子がいた。廉は県を襲撃し、知事を殺し、自ら王を名乗った。世が乱れた時代に臨沂が建てられ、その後、王位は代々子孫に継承され、三国時代には誰も執着しませんでした。呉はこれに隣接した領土を持っており、これを境界として首陵を侵略した。屈廉以来、この国には書かれた歴史がなく、王朝は失われ、世代数を詳しく把握することは難しく、氏族の血統は絶え、子孫もいない。彼の孫の范雄が跡を継ぎ、人々は喜んで彼を支持した。雄が亡くなった後、彼の息子の易が跡を継いだ。臨南西娟県のイ族の族長で、ヤイ族の奴隷であった范文がいた。文氏が奴隷だった頃、丘の斜面で羊を飼っていたとき、小川で二匹の鯉を見つけました。文氏は鯉を隠して家に持ち帰り、こっそり食べようと考えました。郎が魚を調べていたことを知ったとき、文は恥ずかしくて怖くなり、「石を研ぐために持って帰ってきたんだ、魚を捕まえるために来たんじゃない」と嘘をついた。郎が魚がいる場所に到着すると、2つの石が見えたので、それを信じて立ち去った。その時になって初めて文は驚き始めた。石には鉄が含まれていた。文は山に入り、石の鉄を溶かし、二本の刀を鍛えて、その刃を荘の方に向け、呪文を唱えた。「鯉が刀に姿を変えた。石を砕くことができるのは精霊だ。文はこれを砕いて王になるべきだ。砕くことができないのは精霊がない」。そして、龍源干江が葦のわらを切るように、石荘を砕いた。その結果、人々は徐々に彼に愛着を持つようになりました。石切り機は今も残っており、魚切り包丁も後世に受け継がれています。 漓水河は武陵崇県に源を発し、東は臨里県と凌陽県の旧境を流れていると言われている。漓水河の南岸には、高さ30メートルの人の形をした白い石が2つ立っている。円周は40フィートです。古老の言い伝えによると、崇県の太守と凌陽の太守が国境について議論していたところ、お互いを傷つけてしまい、石になってしまったという。 劉易清の『冥界記』には、楊県の下級官吏である呉甘の主人が、川の南側に住んでいたと書かれている。ある日、主人が川を渡るために船を掘っていたとき、その中に五色の浮石があるのを見つけた。それをベッドの頭から持ち上げると、夜になるとそれは女性に変わった。 また、義都県と建平県の境界には、5、6の峰が交互に並んでいる神秘的な山があり、頂上には、まるで2人が袖を折り、向かい合って寄りかかっているように見える岩があり、両県の監督官が境界をめぐって争っていたとよく言われています。 楊雄の『蜀の実録』には、秦王が蜀王に5人の美女を献上したと書かれている。蜀王は5人の兵士を派遣して5人の女性を歓迎した。彼らは山の空に大蛇が飛んでいるのを見た。5人の兵士がその蛇を追い払うと、山は崩れ、5人の女性は山を登って石になった。 また、武都の男が美しい顔立ちの女性に変身したとも言われている。この女性は山の精霊だったと思われる。蜀の王は彼女と結婚したが、彼女はすぐに亡くなった。王は彼女を、直径一丈、高さ五フィートの石鏡とともに成都の街に埋葬した。 鄧小平は著書の中でこう書いている。「溺れている人を石を投げて助けたり、火を消すのに薪を投げるようなものだ。」 「石碩」は言った。武昌陽新県の北の山に「夫をみる」という石がある。まるで人が立っているように見える。昔、貞淑な女性がいて、夫は遠く祖国のために戦いに出かけた。彼女は幼い息子を連れてこの山に夫を見送った。その女性はそこに立って夫を見つめていたが、その後石に変わってしまった。 『兵書』にはこうある。「軍隊の地盤が岩だらけなら、将軍はそこに長く留まることができる。」 『大史記』にはこう記されている。「水に石を投げたら、それを止めるものは何もない。」 『五行雑記』にはこう書いてある。「夫と姑が喧嘩しているときは、重さ十六ポンドの石を取って戸口に埋めておけば、喧嘩は終わる。」 荀伯子の『臨川記』にはこうある。「石の穀倉は倉庫のような形をしており、千斤の穀物を貯蔵できる。穀倉の口が開いている時は飢饉の年であり、閉じている時は豊作の年である。」 また、石龍山には岩があり、その下には頭と尾の長さが12フィートの龍のような形をした石があると言われています。 『地理記』には、鱗と鎧を持っているので石龍と呼ばれているとある。 石鼓は沂皇河のほとりにあるとも言われています。太鼓のような形をしており、幅は9フィート、長さは14フィート4インチです。 太鼓のように丸くてきれいな形をしていることから太鼓にちなんで名付けられたとも言われています。 また、この砕けた岩は高さ5フィートあり、沂黄河のそばにあるとも言われています。 また、ある女性が水の中で洗濯をしていたところ、龍に引きずり込まれて石に引きずり込まれたという伝説もあります。数日後、雷によって石が割れ、死んだ龍と女性の体が浮かび上がったことから、この石は「砕石」と名付けられました。 浮石とも呼ばれ、汝江の中央に位置し、水位が上昇して高い岸がすべて水没しても、この石は水没しないので、この名前が付けられました。 羅角岩は飛源亭から115マイル離れた飛源河沿いにあり、空にそびえ立ち、数マイル先からでも見通せると言われており、謝霊雲の詩「朝は悲しき元角を出発し、夜は羅角岩に留まる」はこの場所を指している。 『世星記』はこう言った。「営口の東岸に四角い石があり、高さは百フィートで、台のように見えるので、太石と名づけた。」そこから臨水も流れ出ています。壇の横には石室があり、その前の平らな石の上に、すべて銀でできた緑色の鉢で覆われた 10 個の壷が一列に並べられていました。誰かが通りかかる場合、扉を開けて見ることはできますが、持ち去ることは許されません。持ち去ると、死んだように窒息してしまいます。鳳丘の奴隷が2つ盗んだのですが、大蛇に殺されてしまったので、どこから来たのか分からなくなってしまいました。 『永嘉記』には、永嘉の南岸に粘り気のある石があり、堯の時代に神がそれを壊し、邪悪な川に押し込んで川岸に置いたと書かれている。遠くから見ると帆のように見える。現在は天台山につながる張帆渓として一般に知られている。 『県州記録』にはまた、次のように記されている。「東海の新浪神は石を砕いて帆を作った。現在、東海には新浪寺がある。」 |
>>: 『紅楼夢』で薛宝才が夏金貴と対戦したら、勝てるでしょうか?
推薦する
中医学の巨匠、張元帥:なぜ張元帥は金元朝の第5代医学の巨匠になれなかったのか?
張元帥は晋の時代の偉大な漢方医で、芸名は杞谷とも呼ばれた。生没年は不明。彼は幼少の頃から非常に聡明で...
『紅楼夢』では、西仁は金木犀や蘭のように穏やかで従順であると称賛されています。なぜ?
希仁は『紅楼夢』の宝玉の部屋の侍女長の一人です。彼女は徳と雄弁さで知られています。 Interest...
太平広記・巻76・道教・桀祥の原文は何ですか?どう理解すればいいですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
宝ちゃん、秋童の正体は何でしょうか?彼らはどれほど傲慢なのでしょうか?
宝禅と秋童は男たちの甘い言葉を受けて、枝に飛んで鳳凰になったカラスのようでした。興味のある読者と『お...
アチャン民族の習慣 アチャン民族の葬儀と出産の習慣
アチャン族には埋葬という葬儀の習慣があります。重い病気で亡くなった人や難産で亡くなった女性など、少数...
東晋の葛洪著『包朴子』外篇:良則、全文と翻訳と注釈
『包朴子』は晋の葛洪によって書かれた。包埔([bào pǔ])は道教の用語です。その由来は『老子』の...
軍政は反乱を鎮圧するために使われたのに、なぜ混乱を引き起こし、さらには唐王朝の滅亡につながったのでしょうか。
外国軍閥による分立統治とは、通常、唐代の安史の乱後の状況を指し、外国の将軍が自らの軍隊を指揮し、軍事...
李和の「離城」:著者が長安の科挙試験に失敗した後に書かれた
李和(790-816)、雅号は昌吉とも呼ばれる。彼は河南省富昌県長谷郷(現在の河南省益陽県)に生まれ...
夏至に関する詩にはどんなものがありますか?夏にリフレッシュするための夏至に関する10の古代詩
夏至に関する詩を10編紹介します。これで少しでも涼しさがもたらされれば幸いです。夏至[唐代] 全徳宇...
張碩の『夜都音』:詩情は奔放でありながら抑制されており、思想は奥深いが伝わりやすい。
張朔(667-730)は、道済、朔子という芸名でも知られ、樊陽市方城(現在の河北省固安県)の出身であ...
『緑氏春秋』にはイナゴの被害についてどのような記録がありますか?前漢時代に政府はイナゴの被害にどのように対処したのでしょうか?
歴史的に、洪水、干ばつ、イナゴの大発生は、農業生産に最も大きな被害をもたらす三大災害として知られてい...
『紅楼夢』で邱童は幽二潔をどのように扱いましたか?彼女の最終的な結末はどうだったのでしょうか?
秋童は『紅楼夢』の登場人物で、元々は賈舍の侍女でした。次に、Interesting Historyの...
『紅楼夢』での賈玉村の降格は、なぜ以前の解雇よりも重大だったのか?
『紅楼夢』での賈玉村の降格は、なぜ以前の解雇よりも深刻だったのでしょうか?これは多くの読者が気になる...
ユグル族はどんな宗教を信仰していますか?ユグル族の宗教的信仰
ユグル族はチベット仏教のゲルク派(黄宗)に属するチベット仏教を信仰しています。しかし、歴史上、ユグル...
太平広記・巻105・報復・魏勲の具体的な内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...