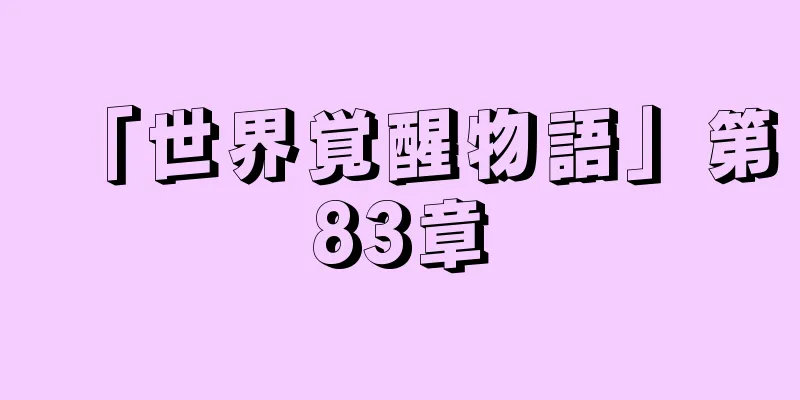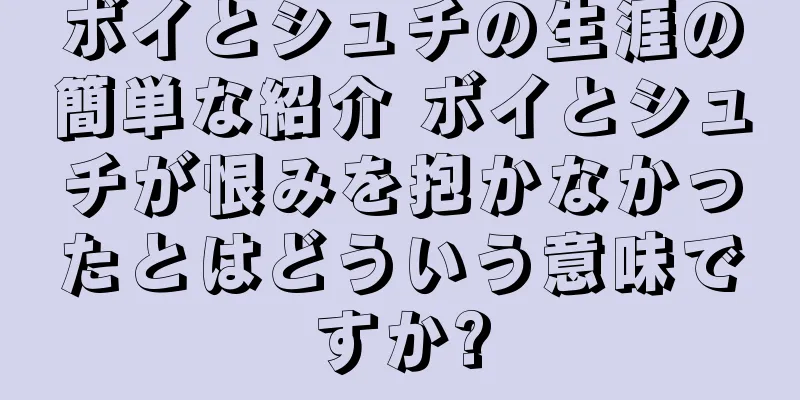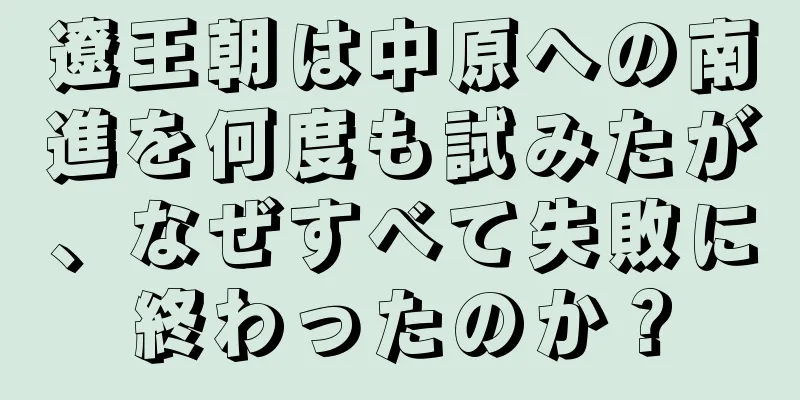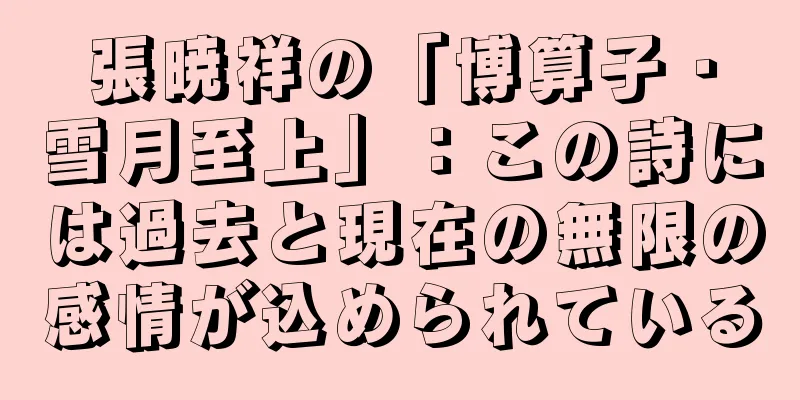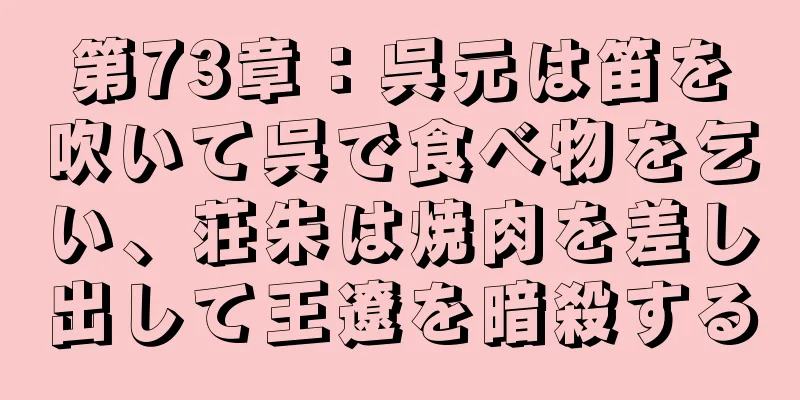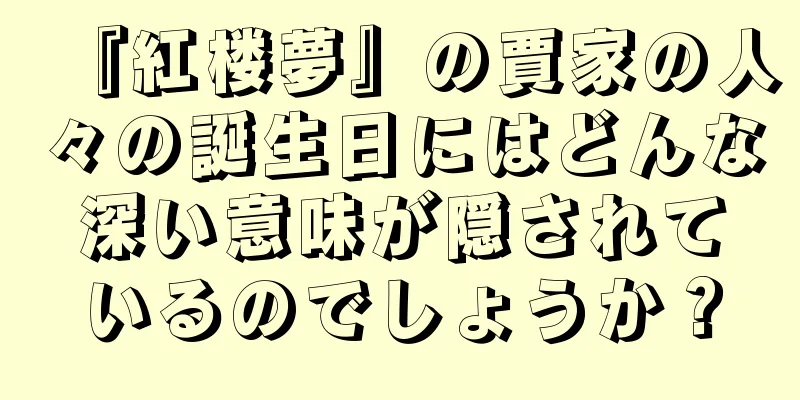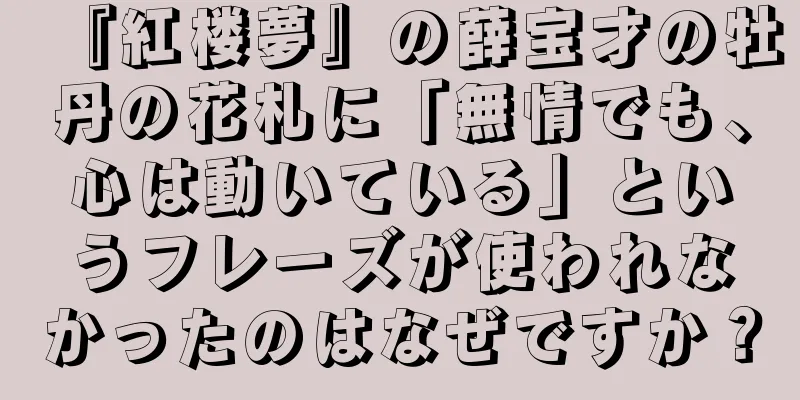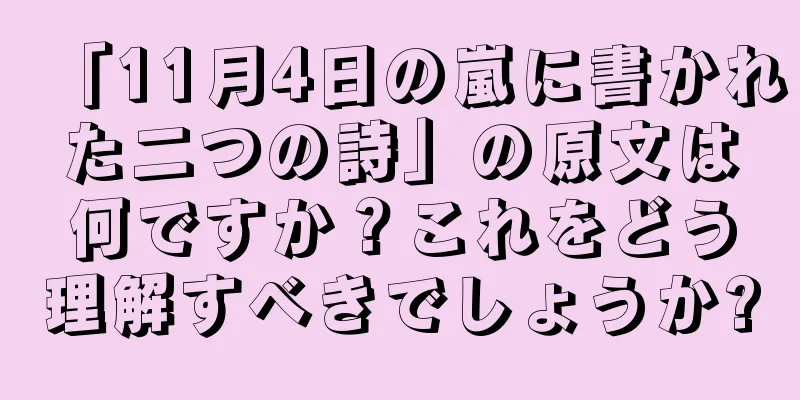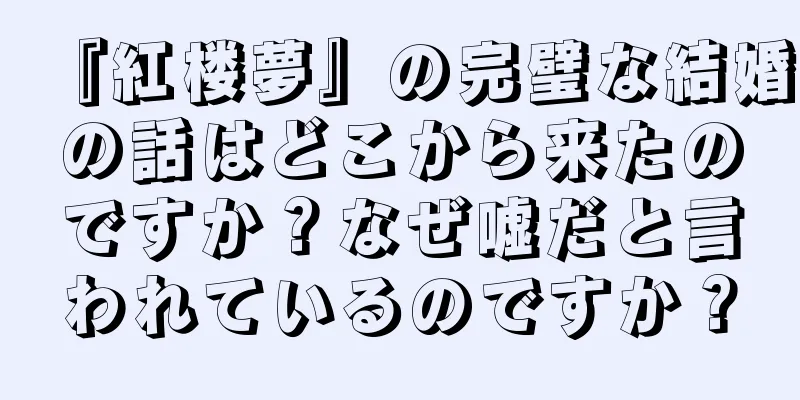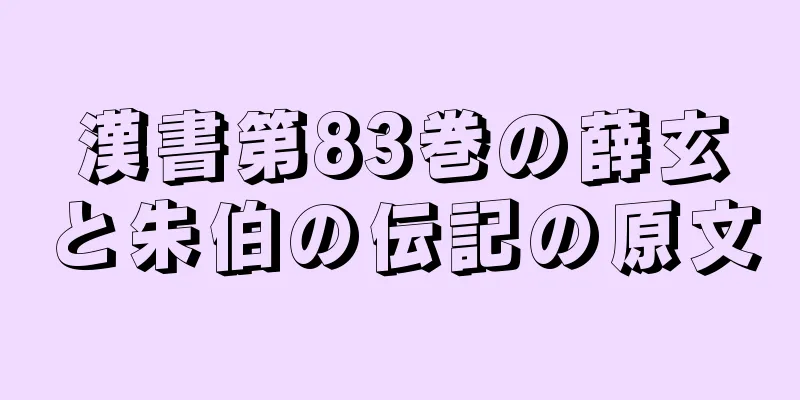古典文学の傑作『太平天国』:人材資源編第9巻全文
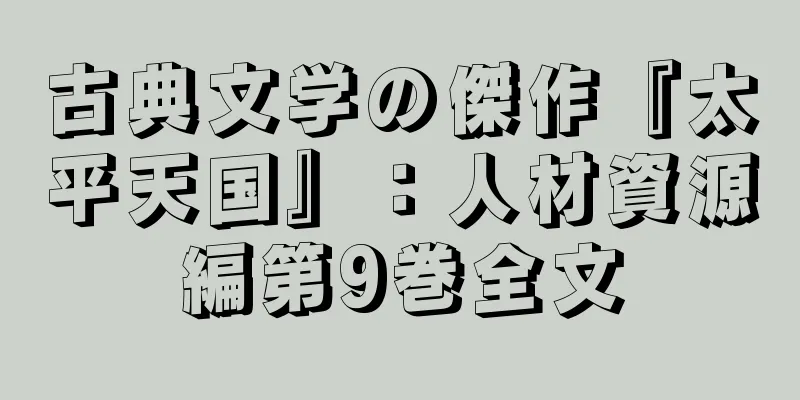
|
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂したもので、太平興国二年(977年)3月に始まり、太平興国八年(983年)10月に完成しました。 『太平毓蘭』は、55部550の分野に分かれ、1,000巻にまとめられた各種書籍のコレクションであるため、もともと『太平宗録』と名付けられていましたが、書籍が完成した後、宋の太宗皇帝が毎日3巻を読み、1年で全巻を読み終えたため、『太平毓蘭』に改名されました。本書は天・地・人・事・物の順に55部に分かれており、古代から現代まであらゆる事象を網羅していると言えます。この本には1000冊以上の古書が引用されており、宋代以前の文献資料も多数保存されている。しかし、そのうち7、8冊は失われており、そのことがこの本の貴重性をさらに高め、中国伝統文化の貴重な遺産となっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が人事省第9巻を詳しく紹介しますので、見てみましょう! ○ リップキス 「舒文」曰く:唇は口の終わりである。 「Shi Ming」によると、「唇は端、口の端を意味します。」キスとは避けることです。踏み込めば粉々に砕け散ります。止めれば避けます。また、綿棒という意味もあります。うがいをするときに唾液を拭うために綿棒を使うことが多いので、この名前が付けられました。 『古典』には、金が郭を攻撃しようとして、虞を通る航路を要求し、虞王は同意したと書かれている。龔志奇は助言した。「『車の両側は互いに依存しており、唇と歯は互いに離れると冷たい』という諺があります。これは于と郭が言いたかったことでしょうか?」 もう一つの物語:呉が魯を攻撃しようとしていたとき、王は子薛に尋ねました。子薛は答えました。「君主たちが助けに来るでしょうが、年を取ることはできません。魯は斉と晋の唇であり、唇と歯は互いに依存しています。あなたもそれを知っています。なぜ救わないのですか?」 『春秋玄明報』にはこうある。「唇は歯の壁であり、神を支え、方向を定める。星のようで、外側に限られているため、唇がなくなると歯が冷たくなる」 『春秋孔雁図』にはこうある。「八つの政策が正しくなければ、人々は口を閉ざすだろう。」 (人は話すときに唇に頼り、その運命は陰によって制御されます。) 『孝経』には、孔子は雄弁に教え、陳記は知恵を伝えたとある。 『史記』には、越の王羌堅はこう言ったとある。「私はいつも自分の力を過小評価し、呉と戦った。会稽に閉じ込められ、唇と舌は昼も夜も乾ききっていた。私はただ呉王と一緒に死にたかった。」 『韓書』は言う:張唐と顔易の間に争いがあった。誰かが顔易の別の考えを張唐に報告し、その件は顔易に引き継がれた。ユン:イーは客と話していて、客は最初の注文にいくつか不都合があったと言った。イーは答えず、軽く言い返した。唐は九人の大臣にこの命令は不都合であると報告したが、公言せず不満を胸に秘め、彼らに死刑を宣告した。それ以来、自分自身の批判を抑圧する方法が生まれました。 また、「薛玄玄」は次のように語った。「沈仙医師は、宣宰相の家族の不適切な行為を中傷した。宣宰相の息子の広済(発音は「秋」)は陽明の客人であり、陽明は西安宮の門の外で沈仙を切り落とし、沈仙の鼻と唇を切り落とした。」光鈞は敦煌に追放され、平民に降格された。 王寅の『晋書』には、「韓俊伝」には「劉勝龍は許昌の出身で、唇は赤く、口数は少なく、野心は大きく、下級の郡役人から雍州の太守にまで昇進した」とある。 『梁書』には、侯景が王位を奪い、太極殿に入り、数万人の従者を擁していたと記されている。唇を吹いて歌い、大声で叫びましょう。 「荘子」はこう言った。孔子は盗賊芝に言った。「将軍の唇は辰砂のようだ。」 『淮南子・朔山』にはこうある。「妊婦がウサギを見ると、赤ちゃんは口唇裂になる。妊婦がヘラジカを見ると、赤ちゃんは四つの目を持つ。」物事は、あるがままのように見えるかもしれませんが、そうではないかもしれません。 賈怡は言った。「沸騰した唇を壁の下に投げ捨てなさい。」 (匈奴の別名。) 「トンスーウェン」はこう言います:唇が歯を覆わないとき、それは噛みつきと呼ばれます。 (ヤと発音します。)龃。 (ラフカット) 『光志』にはこう記されている。「赤い口をした普占の唇は朱で飾られている。」 『楽郷の李嫂の母の碑』にはこう記されている。「老君は唇が厚い。」 趙芝の『自伝』には、次のように書かれている。「芝は身長7フィート4インチ、肌は色白、髪と眉は黒、唇は赤、ひげも髪もあまりなかった。」 敦煌の記録には、王欣(カンと発音、チョウ・リンとも呼ばれる)が亡くなったとき、盗賊が彼の墓を開け、欣が誰かとチュープーをプレイし、盗賊に一杯の酒を差し出しているのを見たと記されている。泥棒たちは恐怖に震えた。酒を飲んだ後、彼は青銅の馬が連れて行かれるのを見ました。その夜、神が城門で告げた。「私は孟増王の使者です。人々は孟増王の墓を掘り返し、酒で唇を黒くしました。明日、黒い唇の者が城に入るでしょう。それはあなたです。」馬はすぐに汗をかいて戻ってきました。泥棒は朝に城門に行きましたが、唇が黒いことに気づかず、役人に縛られました。 (孟増。これは孟の敬称です。) 宋游の「女神への頌歌」:彼女の唇は辰砂のように赤い。 曹植の『洛河の女神』にはこうあります。「赤い唇は外側が明るく、白い歯は内側が明るい。」 「赤い唇を開いてゆっくり話せ」とも言われています。 崔勇の『七つの依存関係』にはこうあります。「紫色の唇と白い歯、雪と翡翠のように白い。」 「Guangya」は「咡はキスと呼ばれます」と言います。 (咡、「バイ」と発音します。) 「淮南子」は言った。「君子は虫歯の治療にキスをしない。」 (虫歯、丘切り傷) ○ 歯 『Shuowen』によると、「龀」は破壊された歯を意味します。男の子の歯は8月に生え始め、8歳で生えてきます。女の子の歯は7月に生え始め、7歳で生えてきます。 (オーディオ) 「Shi Ming」はこう言っています。「歯は始まりです。若者と老人の違いはここから始まるのです。」たくさん食べる人は背が高く、あまり食べない人は若くなります。 「Li」は言います:歯に穴を開けないでください。 (□□は寛容と抑制を表します。) また、濡れた肉は歯で砕ける(砕くとは壊すという意味)とも言われていますが、乾いた肉は歯で砕けないので、使用に適しているのでしょうか? また、高子高が両親の死を悼んでいたとき、三年間血を流して泣き続け、一度も歯を見せなかった(微笑むこともなかった)と伝えられている。君子たちはそれを困難だと思った。 『左伝』はこう言っています。陳羲子は人を遣わして楊勝王を召し出し、皇帝に立てた。同盟が締結されようとした時、景公は「それはあなたの遺言だ」と言って、宝子を讒言した。宝子は「汝子を牛にしてその歯を折ったことを忘れたのか」と言った。(汝子とは屠のことである。景公は縄を口にくわえて牛を作り、屠に引っ張らせると、屠は地面に落ちて歯を折ってしまうのであった。) 『雅歌』の「大師」はこう言っています。「その歯は瓢箪と犀の角のようだ。」 『比公』にもこう書かれている。「多くの祝福を受けたため、髪は黄色く、歯は子供っぽい。」 『公陽評・荘公』にはこう記されている。閔公が殺害されたと聞いて、丘牧は駆けつけ、門のところで閔公を迎え、手に剣を持って叫び声をあげた。宋万弼は秋牧を掴んで頭を殴り、歯がドアに引っかかったままになった。 (サイドハンド、フェイク。□ 袁歌カット。) 『春秋玄明報』には、武王の歯は重なり合っており、それが彼の強さを表している、と書かれている。神芳の像を携えて、天の意志に従って悪を罰せよ。 (宋君の注釈にはこうある。「方」は明堂で統治を担当し、「神」は大陳で伐採と収穫を担当する。どちらも同じ意味なので、より重要な方が主となる。) 『孝経』にはこう書いてある。「先生の歯は重なり合っている。」 (フックスターのように。) 『史記』には、顔回が29歳のとき、髪は真っ白になり、歯は早くに抜け落ちていたと記されている。 范居は魏の高官である許嘉に仕えていたとも言われている。嘉が斉に行くと、范居も従った。斉の襄王は范居の弁舌を聞き、金、牛、酒を与えた。范居が魏の情勢を斉に報告したと范居は思い、贈り物を与えた。彼はこれを魏の宰相に報告したが、宰相は激怒し、部下に命じて朱を殴らせ、朱の肋骨を折り、歯を折らせた。ジュは死んだふりをした。 『漢書』にはこう記されている。張蒼は歯がなく、乳しか飲まなかった。彼は百歳を超えて亡くなった。 謝成の『後漢書』には、舒章湘宋は、号を舒和といい、郡の長官であったと記されている。県知事は下級の県役人によって罪を着せられた。張松は証言するために刑務所に行き、ナイフで自殺しようとした。血が噴き出し、彼の歯はすべて地面に落ちた。知事は助かった。 『晋書』には、文喬は以前歯の病気を患っており、抜歯による脳卒中で亡くなったと記されている。 また、成帝の杜皇后は若い頃は非常に美しかったが、成長すると歯がなかったため、彼女と結婚しようとする者は阻止されたとも言われています。皇帝が結婚の申し込みを受け入れると、彼女の歯は一夜にして全て生え変わりました。 また、謝坤の隣家には美しい女性がいて、坤は彼女を誘惑したが、その女性は坤に杼を投げつけ、坤の歯を二本折ったとも言われている。人々の間では、こんなことを続けていると若いときに歯が折れてしまうという噂があります。 「ヨウユウはクンの文字です。 『山海経』には「黒歯国」とは、歯が黒い国である、とある。 『和図居奇』にはこう記されている。「狄帝は平行歯を持っていた。」 (ソン・ジュン氏曰く:歯が平行で、星型の位置にあるためだそうです。) 『百胡同』によれば、狄帝は八重歯で、その上司は「善」と呼ばれていた。基準を遵守し、陰陽を規制するルールを確立します。 『保朴子』内篇にはこうある。もし誰かが歯を丈夫に保つ方法を尋ねたら、こう答える。「花池で歯を養い、濃い液体で歯をすすげば、歯は動かなくなる。散らばらない精気を取れば、歯は抜けてもまた生えてくる。」 楊泉の『物論』にはこうあります。「歯は年齢を表し、身体の宝である。」隠す目的は五味を調整し、気と気を静めるためです。 『仙人伝』にはこう記されている。「老君の歯はまばらだった。」 『仙人の書』にはこう記されている。「魔法の薬を300年間飲み続けると、歯が石に変わる。」 『王洪物語』にはこう記されている。王洪が琅牙の太守であったとき、張布は彼を殺そうとした。洪は東武城の城門から出ましたが、馬は逃げ出し、戦車は落ちて歯が折れてしまいました。洪氏は非常に怒り、病気を理由に帰宅したため、処罰は免れた。 「子林」は「赤高」(牛玉が切る)と言います。歯が合いません。齼(最初に上げて切る)酢によって歯が傷つくという意味です。噛む、かじる、そして食べる。齨(ジウと発音します)老人の歯は奥歯のようなものです。 『段果沙州記』にはこう記されている。「50歳以上の人は歯が4本とも抜け落ちる。これは冷たい地面が気の流れを阻害するからだ。」 『奇事記』にはこう記されている。「肉屋たちは海外に移住し、草で歯を染めたので、黒い歯と呼ばれるようになった。」 『袁子正書』には、善良の家族は西に埋葬されており、彼らは牛を屠殺し、歯に油を塗っていると書かれている。 『世碩』には、孫子靖が若い頃、密かに何か言おうとしたことがある、とある。王無子は「石を枕にして、小川で口をすすぐ」と言った。王は「石を枕にして小川を飲みながら、石で口をすすぐ」と間違えた。王は「小川は枕にせず、石は水で口をすすぐのではない」と言った。孫子靖は「小川を枕にするのは耳を洗うため、石で口をすすぐのは歯を研ぐためだ」と言った。 王紫友が謝玄に会いに行ったとき、林公はすでにそこにいたとも言われています。王さんは「もし林さんが豊かな髪とこめかみを持っていたら、表情はもっと良くなるでしょうか?」と尋ねた。謝さんは「唇と歯は相互に依存し合っており、失われることはありません」と答えた。 「秦曹」は言った。「聶政の父は漢王のために剣を鍛造したが、期限内に完成しなかったため、漢王は彼を殺した。」石徴はまだ生まれていなかった。成長すると泰山に行き、仙人に会い、琴の演奏を習った。仙人のように見えるように体を塗り、音を変えるために木炭を飲み込んだ。7年後、琴を完成させた。漢に入って妻に会った鄭は櫛を買いに行き、妻に微笑みかけました。妻は泣きながら言いました。「なぜあなたの歯は鄭の歯に似ているのですか?」鄭は山に行き、石を拾って自分の歯を叩き落としました。 「楚辞」曰く:美人は歯が白く、優雅である。 『臨海土水記』には、次のように記されている。「宜州の人々の習慣によれば、女の子が結婚するとき、上の前歯を抜く。」 宋渭の『鄧土子譜』にはこうある。「腰は絹の束のようで、歯は貝を掴んでいるようだ。」 司馬相如は『上林賦』の中でこう言っている。「歯は白く輝いている。」 張謝の「西風」はこう言っています。「澄んだ音は白い歯から出る。」 ○ 歯 『史明』には「牙」は植物を意味し、その形状によって記されているとある。 甘宝の『金記』には、庶民の賈が民淮王を殺害する前に、「南風が激しく白い砂を吹き、千歳の頭蓋骨に歯が生える」という噂があったとある。(南風は庶民の名前。民淮のあだ名は沙門。) 『三国典歴』にはこうある。斉の太公が歯を持って生まれたとき、上瑶典羽にそのことを尋ねた。鄧玄が答えると、太公は怒って彼を殴った。中央書記長の徐志才が祝福にやって来て言った。「これが志牙です。生きている者は賢く長生きします。」最高皇帝は喜んで、彼に褒美を与えた。 ○咽喉頭 「舒文」曰く:喉は喉なり。 「Shi Ming」によると、「Yan」は物を飲み込むことを意味します。緑色で遅いものは「脰」と呼ばれ、何かを投げ込むと受け止められ、落ちていきます。喉とも呼ばれ、空気が流れる重要な場所です。 『古典』には、ディ族は西安で敗北し、ディ族の首領である喬如が捕らえられたと記されている。フーフーは生涯彼の喉を殴り続け、槍で彼を殺した。 『孝経』には「師は喉を助ける」とある。 『史記』には孫子がこう言っている。「戦いから誰かを救いたいなら、戟を使うな。代わりに、戟を使って敵の弱点を攻撃するのだ。敵が閉じ込められ、状況が制限されれば、敵は自分で状況を解決することができるだろう。」 (カンはガンとカンと発音され、喉と同じです。) また、張王が赦免されたと聞いた管高は、「私が死を免れたのは、張王に謀反はしないと告げたからだ。王が逃げた今、私の責任は果たされた。死ぬことに後悔はない。それに、殺人の汚名を着せられた大臣が皇帝の前に出られるだろうか。皇帝が私を殺さなくても、罪悪感は残るだろうか」と言った。そこで管高は頭を上げて死んだ。 (魏昭曰く、「康」は飲み込むという意味です。) 『漢書』にはこう記されている。「ある人が皇帝に手紙を書いて、西府が恨みを抱いており、朝廷の昇進に満足していないと伝えた。彼は星を観察し、皇帝の運勢を観察し、魔女に呪いをかけた。」皇帝は検閲官と最高裁判所長官を派遣して彼を逮捕し、洛陽監獄に収監させた。当局が彼を逮捕し尋問しようとしたとき、彼は空を見上げて叫び、その後、硬直して倒れた。当局が尋問したところ、彼は死んだと答えた。 (石固曰く、「Yan」は喉を意味し、「イー・チエン・ダイ」と発音する。) 『後漢書』には、霍基は宋光の叔父であると書かれている。宋光が陥れられたとき、彼は手紙にこう書いている。「それはトリカブトで飢えを治し、毒で渇きを癒すようなものだ。胃に入る前に、すでに喉を塞いでいる。どうして使えるのか?」 王清の名は公然とも言われている。清福龍は建武初期の都衛公曹であった。清は下級の役人であった。彼は父親と共に大尉に従ってある郡へ向かった。途中で盗賊に遭遇した。龍は身を挺して大尉を守り、災難に遭って亡くなった。清も矢に刺され、声が聞こえた。 また、李固は勅令に対して次のように答えたとも言われている。「陛下には上書があり、天には北斗がある。北斗は天の言葉であり、上書は陛下の言葉である。」 『魏志』によれば、楽陵王茂の弟、王東平が亡くなった。毛沢東は病気を主張し、悲しみを表明することを拒否したため、皇帝は彼の戸籍を抹消するよう命じた。 『蜀の記録』には、彭英が葛良に宛てて書いた次のような手紙が記されている。「昔の人は言った。『左手で世界を掴み、右手で絞め殺すなんて、愚か者はそんなことはしない。ましてや、豆と麦の区別がつくような私には無理だ!』」 『唐書』には、幽州の朱容と鎮州の王廷劫が謀反を起こしたとある。東川の太守王雅は手紙を差し出し、こう言った。「軍勢を率いて戦うときは、まず首を絞めるべきだと聞いている。今、夷、墨、易、定は、この二人の賊の首である。彼らに権力を与え、重兵を駐屯させるのが実に適切だ。そうすれば、彼らは生きているか死んでいるか分からず、スパイも侵入できない。そして、軍勢はまず冀と趙に進軍し、次に景興に進軍する。これで必ず勝てる。」 「保朴子」は言った。喉の渇きは広大な海を指し示すようなものだ。 『女人伝』にはこう記されている。斉の鍾離春は宣王の王妃であった。彼女は非常に醜く、鼻は凹んでおり、喉は節くれだった。 『易布長老伝』には、傅という人物は楊鳳貴、妻は陳季であった。桂は早くに亡くなり、兄弟たちは楊と桂を再び結婚させようとした。季は刀で楊の喉を切り、姚を死に追いやったと記されている。 9つの部族は驚いて彼の例に従いました。 別名:張昭懿、蜀県の石仙の妻。シアンが罪を犯して処刑された後、イーはナイフで自分の喉を切り裂いて死亡した。 「物理学の理論」にはこうあります。「喉は生命にとって重要な開口部です。」 『黄帝内経』には「喉は天の気を司り、咽頭は地の気を司る」とある。 ○ うなずく 「史明」曰く:易は福車とも呼ばれ、骨が強く、口を支えます。これは牙を運ぶために使われた牙車だという説もある。またはチンカーとも呼ばれます。 Chin は含むという意味です。 「韓氏」は言った:そこには美しくて、大きくて{妗酉}な人がいた。 (薛先生曰く、「{妗酉}は重いあごを意味し、闻鹏と発音します。」) 『易経』の「石駁卦」にはこうあります。「あごの中に石駁というものがある。」 『易卦』にはこうも書いてある。「易、堅固であることは吉兆である。」顎を見て言い訳を探している。 『春秋玄明報』にはこう記されている。「侯季其儀は自らの利益を求め、これを農耕と称する。彼は黒い角を持つ象のようで、土を運び、穀物を食べた。」 (宋俊の注釈にはこうある。「顔には二つのイメージがある。顎は下の部分であり、下は地面であり、これは賢明で有益である。」) 『戦国の兵法』には、景国公は議論が上手だったが、その議論には欠陥が多く、部下を不快にさせたと書かれている。孟昌君が抗議すると、景国君は激怒し、屋敷を上室に移し、長男に朝夕の食事の給仕を命じた。衛王が亡くなると、宣王が即位した。太子は景国公を気に入らなかったため、辞任して薛に遣わした。坤弁は斉に到着し、斉の宣王に会った。宣王は「息子よ、景国公はあなたが言うことを聞いている人を愛していると思うか」と尋ねた。宣王は「愛しているなら愛する。誰かの言うことを聞いているなら聞いていない。王が皇太子だったとき、坤弁は景国公に言った。『皇太子は冷酷で人を見下している。もし彼が法に従って父を裏切るなら、皇太子を廃位し、衛冀の息子の応応を皇太子に立てた方が良い。景国公は泣いて言った。『いや、我慢できない。』もしあなたが坤弁の言うことを聞いて、彼の言うとおりにしていたら、今ごろは何も問題はなかっただろうに」。宣王は「私は知らなかった」と言って、景国公を迎えに行った。 『史記』には、黄慧が秦王に宛てて書いた「我が国は廃墟となり、我が国は廃墟となり、我が胃腸は切り裂かれ、我が首は折れ、我が顎は折れている」とある。 蔡澤はハンサムだとも言われています。 (顩、闻鹏切。) 『漢書』にはこう記されている。王莽は眉をひそめた。 范晨の『後漢書』には、班超の雅号は中勝であったと記されている。野心を持ち、些細なことには注意を払わないでください。かつて彼は占い師に会いに行った。占い師はこう言った。「彼は平民で学生だが、一万里離れたところで侯爵になるだろう。」趙が彼の容姿について尋ねると、占い師はこう言った。「彼はツバメの顎と虎の頭を持っている。彼は空を飛び、肉を食べる。彼は一万里離れたところで侯爵になるだろう。」 「蒋彪伝」はこう言った。孫権は顎を押さえて口を大きく開けていた。 『三国志』には、徐志才が13歳だったとき、劉小初が彼を見て言った、「徐朗延寒、班超の姿もある」とある。 『皇帝の系譜』には、玖帝は方毅であると記されている。 『荘子』は言う:芝叔易は斉に隠れた。 孔子は弦楽器を弾いたりハープを弾いたりしながら、黒幕の森をさまよったとも言われています。音楽が半分ほど演奏される前に、漁師が船から降りてきました。ひげと眉毛は白く、髪はほどけ、袖はまくり上げられていました。彼は平原を歩いていき、陸地のすぐ手前で立ち止まりました。彼は左手を膝の上に置き、右手で顎を押さえながら音楽を聴いていました。 『韓子于老』には、白公勝は混乱を心配し、朝廷を止めた。到着すると、棒で刺され、顎を貫かれた。血が地面に流れ落ちたが、白公勝は気づかなかった。鄭の人々はそれを聞いて、「なぜ忘れなかったのか」と言った。(「錣」は馬の鞭である。鞭の先端には馬のような針があり、「錣」と呼ばれる。「竹烈」「陟卫二切」と発音する。) 『和図』にはこう記されている。「黄帝は咸宜を抱く。」 『朔元』には、田丹が狄を攻撃したが、3か月間も倒すことができなかったとある。赤ん坊は歌を歌った。「大きな冠はちりとりのようで、長い剣は顎にある。」 『西京雑録』には、匡衡は字を智桂といい、宋を好み、詩経の解説が上手であったと記されている。当時の人々は彼について「詩経を解説したければ、ここに来なさい。匡衡は詩経を解説して人々を笑わせることができる」と言った。丁は匡衡の愛称である。 王燦の「七つの解釈」には、眉を上げ、顎を尖らせるとあります。 『汝南名人伝』には、周謝は顎が変形し、額が折れており、非常に醜い人物であったと記されている。 譚書は言った。「北斉の李叔には髭がなかった。崔塵は彼を見て言った。「針で顎に何百もの穴を開け、両側の良い髭を選んで植えたらどうだ。」 ○澄江 「世明」曰く:口の下の部分は澄江と呼ばれ、水と汁である。 『経典鍼灸』には澄江は玄江とも呼ばれると記されている。 |
推薦する
『紅楼夢』では、李婉は大観園の最終決定権を持ち、非常に権威がある。
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
宋代の詩『酒泉子』鑑賞:長易観潮、この詩はどのような場面を描いているのでしょうか?
宋代の潘浪の『酒泉子長易観潮図』について、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょ...
西夏黒水城には何がありますか?西夏の黒水城の災害はどうなったのですか?
西夏黒水城には何があるのでしょうか?西夏黒水城の惨事は一体どうなったのでしょうか?ご興味のある方はぜ...
「初冬河想」は孟浩然によって書かれた。詩人は引退を望みながらも、官職を求めていた。
孟浩然(689-740)は、浩然、孟山人としても知られ、襄州襄陽(現在の湖北省襄陽市)の出身です。唐...
学者第5章:王秀才が側室を立てることを提案し、顔静生が病死
『士人』は清代の作家呉敬子が書いた小説で、全56章から成り、様々な人々が「名声、富、名誉」に対してど...
唐代の僧侶、高仙は書道においてどのような功績を残しましたか?
高仙の紹介文には、彼が武城出身で唐代の有名な書家であったことが記されている。彼が生涯にわたって残した...
高石の「大晦日」:詩全体を通して、珍しい言葉や装飾的なフレーズは一つもありません。
高史(704-765)、号は大夫、滄州渤海県(現在の河北省荊県)に生まれた。唐代の大臣、辺境の詩人で...
無名の絵画は文化や芸術の発展にどのような影響を与えるのでしょうか?宋元時代の匿名絵画を分析!
本日は、Interesting History の編集者が、匿名の絵画が文化と芸術の発展にどのような...
中国で現存する最古の新聞は何ですか?誰が設立したのですか?
『金蔵院荘』は、中国の唐代に登場した原始的な報道媒体です。中国で証拠が残っている最も古いメディアであ...
『王江南・仙夢源』の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
望江南・湘門園李嶽(五代)空想は遠く、南は春だ。船上で音楽が流れ、川面は緑に染まり、街全体が舞い散る...
古代詩の鑑賞:「詩経:北山登り」:北山に登り、クコの実を摘む
『詩経』は中国古代詩の始まりであり、最古の詩集である。西周初期から春秋中期(紀元前11世紀から6世紀...
古典文学の傑作「太平天国」:食品飲料第12巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
王燦の『五つの軍歌(その3)』はどのような執筆背景を持っていたのでしょうか?
王燦の『五軍詩(その3)』の執筆背景は何ですか?当時、詩人は曹操に従って南下し、孫権を攻撃しました。...
岑申の『都使に会う』にはどのような感情が表現されているのでしょうか?
岑申の「都使に会う」にはどのような感情が表現されているのでしょうか。この詩は、理想を追い求め、勇敢に...
遼・金・元の衣装:遼の鎧と軍服
遼王朝は契丹族によって建国され、主に中原の先進的な文化、生産技術、社会制度を吸収・採用することで、短...