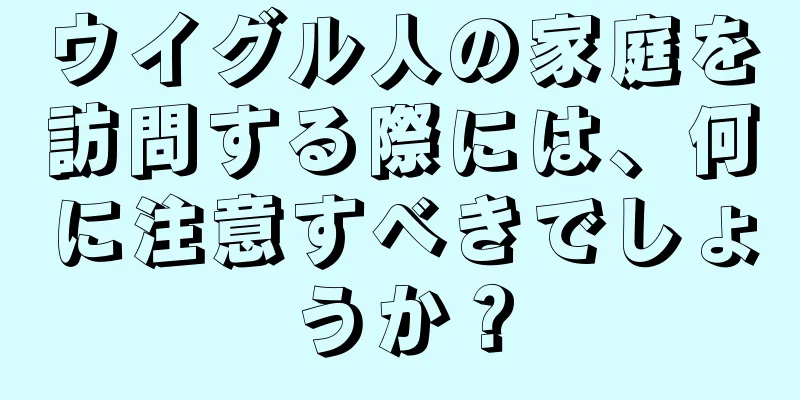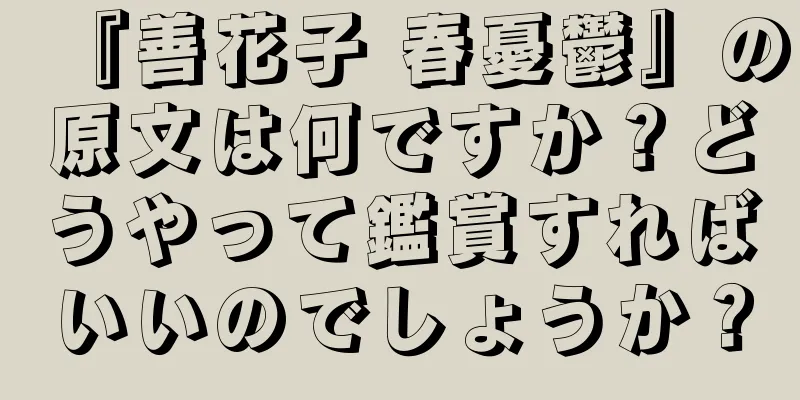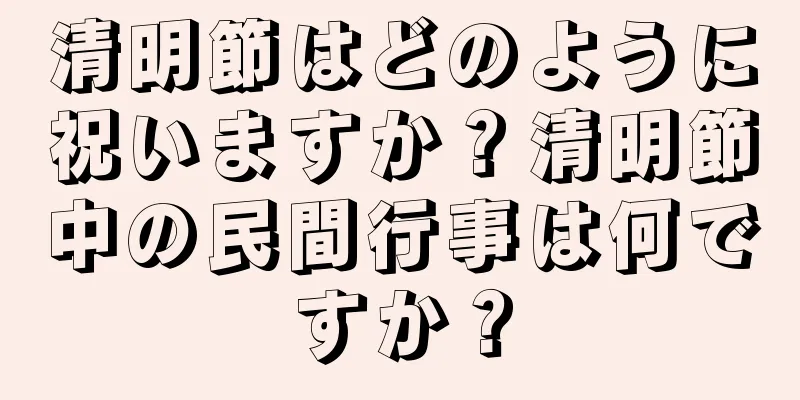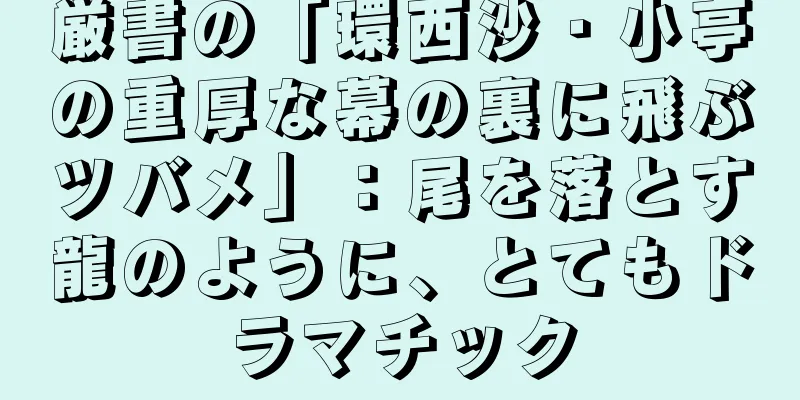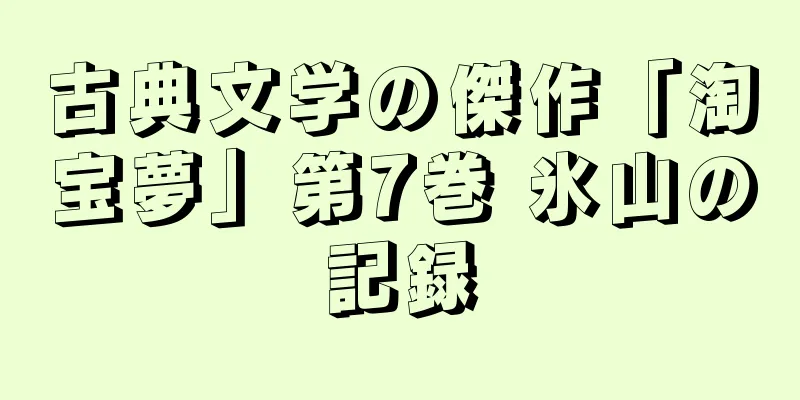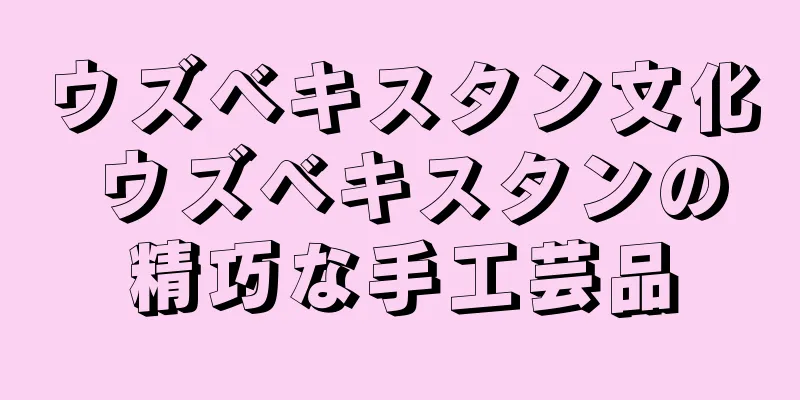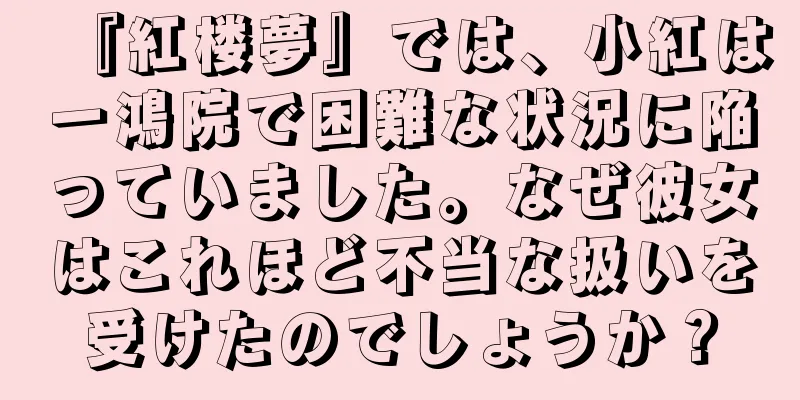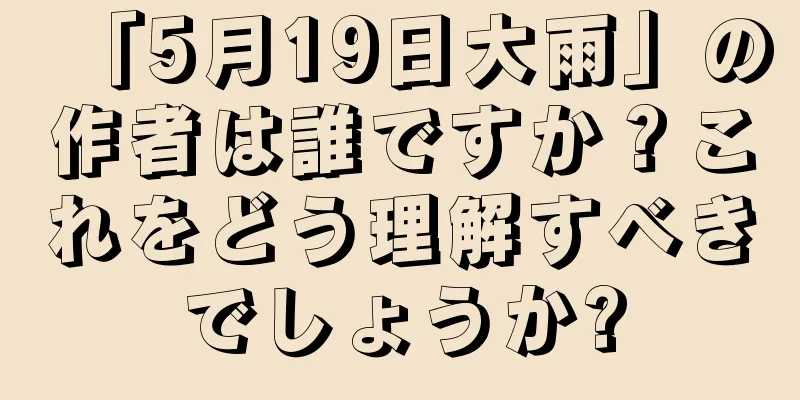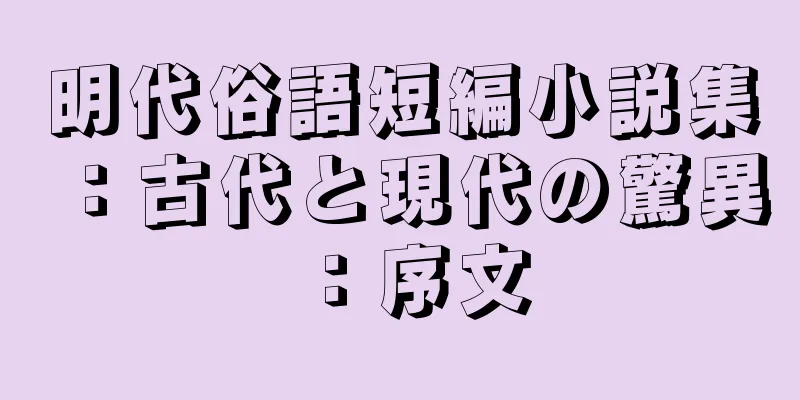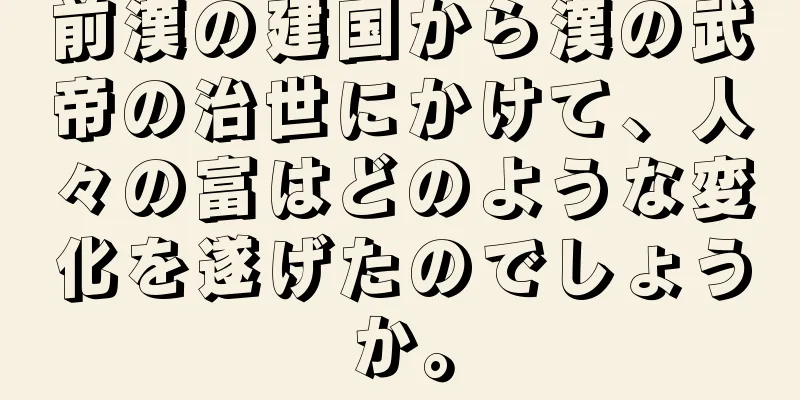中国の歴史における4つの寒冷期を振り返る:数え切れないほどの人々が凍死した
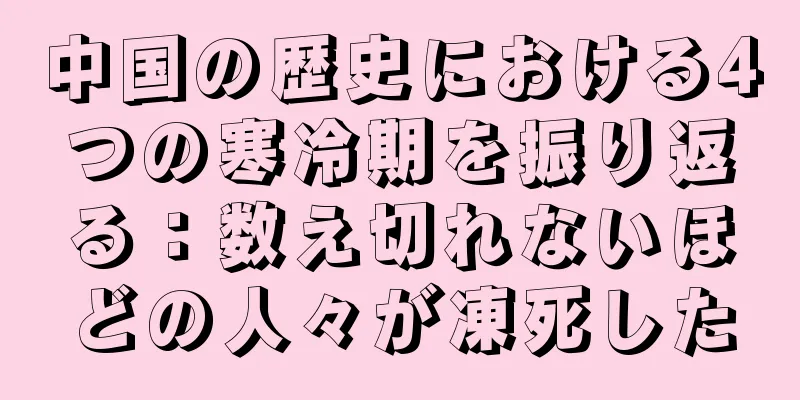
|
1. 漢の武帝の治世中、「大雨と大雪で多くの人が凍死した」 学界では、中国の5000年の気象史において、4回の寒冷期があったと一般的に考えられている。紀元前1100年から紀元前850年までの最初の寒冷期、すなわち西周初期については、関連する歴史的データはほとんど存在しない。 最も古い記録には雪については直接触れられていないが、『竹書紀』に見られる「雹雨」については触れられている。それは西周の孝王7年に起きた出来事である。「冬には大雨と雹が降り、牛や馬が死に、長江と漢江は凍った。」 二度目の寒冷期には、大雪の記録が徐々に増加しました。 二度目の寒冷期は紀元後から600年までで、前漢末期から隋初期に相当します。この時期には、後漢、三国、晋、南北朝がありました。実は、異常気象はこれ以前にも現れており、大洪水が続いていました。劉徹(漢の武帝)の時代には、冬には数年間、極度の大雪が続きました。 漢の武帝は55年間皇帝の座に就き、前漢で最も長く在位した皇帝でした。彼はまた、最も多くの自然災害と人災に見舞われました。この期間、歴史書に記録されているように、3年間にわたって大雪が続きました。 図:雪の日に旅をする古代の人々(宋代の朱睿が描いた「山河遊行図」の一部) 『漢五行書』によると、漢の武帝の元寿元年(紀元前122年)12月、武帝は「一本の角と五つの蹄」を持つ怪物を退治しました。これは吉兆とみなされ、その年は「元寿」と名付けられました。 実は、その年は世の中が全然幸先がよくありませんでした。その年の冬は「大雨と大雪が降り、多くの人が凍死した」。雪はどれくらいの重さだったのでしょうか?多くの人が凍死したという事実から判断すると、この雪は相当な重さだったに違いありません。 7年後、2年連続で雪害が発生しました。元定2年(紀元前115年)3月と元定3年(紀元前114年)3月には、晩春の極寒が起こりました。 元定二年三月、雪は「地面に五尺の積もった」。元定三年の状況は二年目よりもさらにひどく、旧暦三月には中原の河川は凍らなかったが、その年は凍り、旧暦四月には再び大雪が降り、関東地方の十数郡の人々は食糧や衣服が不足し、飢えと寒さに苦しみ、生き延びるために「人食い」の悲劇さえ起きた。 世の中には飢饉が絶えずあったが、劉徹などの西漢の皇帝は国庫の財産の3分の1を費やして墓を建て、副葬品を安置した。東漢初期の建武2年(西暦26年)の雪の日、これらの皇帝の墓のほとんどが赤眉軍に略奪された。当時、反乱軍は衣服も食料もなく、「大雪が降り、谷間は水でいっぱいになり、多くの兵士が凍死した」。このような状況下で、反乱軍は「戻って墓を掘り起こし、宝物を持ち去った」。 2. 唐の昭宗皇帝の治世中、首都では毎日何千人もの人々が凍死した。 二度目の寒冷期には、どの王朝でも異常な降雪日が続きました。三国時代の呉では、平年でも雷雨の後に大雪が降るなど、異常気象が起こりました。 『晋書五行記』によると、当時の呉の皇帝は孫良であった。太平二年二月五日(西暦257年4月5日)、まず雷雨が起こり、夷茂二日には大雪が降り、気温が急激に下がり、「大寒」と呼ばれた。歴史家は「雷が鳴ったので、雪が再び降ることはないはずだ。すべては異常なタイミングによるものだ」と述べた。 グレゴリオ暦の4月5日に降る雪は、人々の間でタブーとされている「6月の雪」と何ら変わりありません。 古代中国では、6月の雪は不吉な兆しとみなされてきた。元代の関漢卿の戯曲『竇鄂不義』では、「6月に雪が降って、3年間雨が降らない」というフレーズで竇鄂の不義を表現している。漢代の民謡『商謝』では、「夏の雨と雪」は世界の終わりの到来とみなされている。もちろん、これはあり得ないことだ。 「六月の雪」は実は異常気象の現れであり、中国の気象史上よくある現象です。例えば、戦国時代には陝西省で「六月の雪」が何度も降りました。 秦の璋王8年(紀元前435年)には「6月に雨と雪が降った」、周の衛烈王4年(紀元前422年)には「4月に晋で大雨と雪が降った」、周の烈王3年(紀元前373年)には「夏の6月に趙で雨と雪が降った」。 実は、このような異常な雪の日はあまり怖いものではありません。怖いのは、唐代末期の異常な大雪です。宮廷の人々でさえ、毎日凍死したほどです。 この大雪は、唐の最後の皇帝である李業(唐昭宗)の治世末期の天福元年(901年)に起こった。この年は大災害の年であった。まず、夏から秋への変わり目に長い雨が降り、冬が明けてから雪が降り始めた。雨と雪は春まで続き、歴史書では「冬から春まで雨と雪が続いた」とされている。 このような極端な気象条件の下で、庶民は苦しみました。「数え切れないほどの人が凍死し、餓死した」これは数え切れないほどの人が凍死したことを意味します。当時の陝西省の首都では、その年の11月に「市内の薪と食料がすべてなくなり」、「毎日数千人が餓死した」。毎日、1000人以上が餓死しました。なんてひどいことでしょう。 その年は飢饉の年で、ひどい雪のため、皇宮でさえ食糧が尽きた。李イエは仕方なく、宮廷の召使たちに、宮殿に小さな製粉所を設け、豆や小麦を挽いて飢えを満たすよう命じた。「後宮から王の16の宮殿まで、毎日3、4人が飢えや凍えで死んだ。」皇室では、毎日3、4人が飢えや凍えで死んだ。民衆の間での災害がいかに深刻であったかは想像に難くない。 唐代には不思議な雪が多かった。例えば、貞元帝の治世21年(805年2月10日)の旧暦1月4日、都に「赤い雪」が降り、都の人々はそれを噂し、不吉な前兆とみなした。 3. 宋代第三寒冷期 中国の気象史において、李業帝の時代は「温暖期」であり、比較的、猛烈な吹雪はそれほど頻繁ではありませんでした。しかし、西暦1000年から1200年にかけての宋王朝の時代には、再び雪害が古代中国人を悩ませました。 図:雪山図(部分、宋代の梁楷筆。東京国立博物館所蔵) この時期は中国で3度目の寒冷期でした。『宋史・五行録』を調べてみましたが、そこには70回以上の暴風雪が記録されており、そのほとんどは連続して発生していました。最も厳しかったのは北宋初期でした。北宋の2代目皇帝、宋の太宗皇帝趙光義は22年間統治しましたが、そのうち5回暴風雪が発生しました。 太平興国7年3月、霜と雪により宣州の桑の収穫が被害を受けました。 永熙二年の冬、南康軍は大雨と大雪が降り、川は凍って水があふれた。 端宮元年閏五月、吹雪が雲州の小麦に被害を与えた。 春化3年9月、大雪により荊昭県の農作物が被害を受けた。 春化4年2月、商州では大雪が降り、多くの人が凍死した。 趙光義の治世中の大雪が最悪だったわけではない。『中国気象災害百科全巻』に載っている2度の大雪の方がはるかに深刻だった。1度は元有2年(1087年)、趙旭(宋哲宗)の治世中に起きた。その冬、首都(現在の河南省開封)のある中原では冬が明けると毎日雪が降り、春まで降り止まなかったため、「寒さが厳しく、多くの人が凍死した」。多くの家族が凍死し、遺体を埋葬する人もいなかった。朝廷は災害救済の布告を出し、「身寄りのない死者は役人が埋葬する」ように命じた。政府は遺体を埋葬するよう手配した。そのため趙旭はその年の元宵節の巡回を取りやめ、地元の人々に慰問するよう通告した。 もう一つの事件は、昭桓帝(宋の欽宗皇帝)の治世中の景康元年(1126年)に起こった。河南省を中心とする中原地方は、再び稀に見る大雪と厳しい寒さに見舞われた。その年の旧暦11月から翌年1月にかけて雪が降り続き、平地には数フィートの厚さの雪が積もり、「多くの人が凍死した」。 都で警備に当たっていた兵士たちの手は凍りつき、武器を握ることさえできなかった。一部の兵士はゾンビのように凍りついていた。雪だけならまだしも、北西の風も強かった。『宋史』には「雪が激しく降り、天候は非常に寒く、地面は鏡のように凍り、歩く者はじっと立っていられない」と記されている。民衆は食べるものも燃やすものもなく、官吏は比較的人道的で、民衆に宮廷の庭園に行って花や木を切って薪にするよう求めていた。 自然災害の後、人災が続いた。靖康2年4月、金軍は東京を突破し、焼き討ち、殺害、略奪を行い、宋徽宗・宋欽宗父子、および王族、側室、貴族、大臣など3000人以上を捕らえ、北金国に連れ帰った。これは「靖康の災い」として知られている。 『中国気象災害大全』では、この二つの雪害を北宋時代の「大寒波災害」として挙げている。この二つが最も深刻なのだろうか?そうは思いません。元有二年の雪災の前年、つまり嘉有元年(1086年)には、旧暦の正月24日に「大雨と大雪」が降り、宮殿の骨組みが壊れました。一週間後、旧暦の二月三日に再び「大雨と大雪」が降り、「泥道は氷で覆われ、城中の人々は寒さと飢えに苦しみ、多くの人が亡くなった」のです。 4. 明清時代の第四寒期 明代中期から中国は第四寒冷期に入り、清代末期の1900年頃まで500年間続いた。ちょうどこの時期に明清代が重なっていたため、国内の学者はこの時期を「明清小氷期」と呼び、国際的には「現代の小氷期」と呼ばれている。 当然ながら、明清時代の雪害はそれ以前のどの時代よりも頻繁だった。『中国気象災害大全』には、1900年以前の「大寒波災害」の抜粋はわずか17件しかなく、そのうち13件は明清時代のものだった。 明代の朱啓玉(皇帝代宗)の治世、景泰4年(1453年)の冬、中国北から南までほとんどの地域で稀に見る大雪と極寒に見舞われた。河北省、山東省、江蘇省、浙江省、広西チワン族自治区などの地域では1か月以上にわたって降雪が続き、深刻な災害が発生した。江蘇省蘇州では太湖の航行が遮断され、港が凍結し、「数万人の人々と家畜が凍死」、浙江省安吉では「百人以上が凍死」、河北省滄州では「数え切れないほどの人々と家畜が凍死」、山東省徳州では「人々と家畜が凍死」した。 広西チワン族自治区柳州市などの南部では、川の魚がすべて凍死したが、南部の川魚が凍死するのは非常に珍しいことだ。これは宋代の天熙二年(西暦1018年)の出来事です。その年の正月、雍州では大雪が降り、「六日六晩続き、川や小川の魚はすべて凍死した」そうです。 これは明朝史上最悪の暴風雪ではなかった。最もひどいのは、ロマンに満ちた皇帝朱后昭(明の武宗皇帝)が統治していた正徳8年(1513年)だったはずだ。最も雪が降り積もったのは華東で、河川が凍り、鳥や動物が凍死し、村人も凍死した。太湖、洞庭湖、鄱陽湖など南部の大きな湖は、実は同時に「超スケートリンク」になった。太湖では「氷が厚すぎて、歩行者は10日以上も氷の上を歩かなければならなかった」。洞庭湖では「氷が厚すぎて、人がその上を走れるほどだった」。 明清時代の小氷期には、清朝が最も深刻な雪害に見舞われた。『中国気象災害大全』によると、明清時代の13の「大寒波災害」のうち、9つは清朝時代に発生した。一部の学者は、17世紀から19世紀までの期間を小氷期の「寒冷期」と呼んでいる。過去500年間で最も寒かった50年間は、この期間、具体的には西暦1650年から1700年の間に発生した。 この最も寒い50年間、1か月連続で大雪が降ることは珍しくなく、むしろよくあることだった。例えば、清朝の順治10年(1653年)には全国的に大雪が降り、「多くの」人々が凍死した。河北省では多くの人が洞窟の中で凍死した。南部では、湖南省永州市などの地域ではその年40日以上雪が降り、「数え切れないほどの人々が凍死した」という。 康熙帝の治世9年(1670年)の冬、華北、華東、華中などの地域で大雪が降り、通常40日から60日連続で降りました。黄河は龍門から龍門まで凍り、淮河は2か月間凍りました。 全国多くの省市の地方史には、凍死した人々の記録がある。湖北省大業などでは「多くの人が飢えと凍死した」、河南省開封では「井戸が凍り、多くの人が路上で凍死した」、江西省南昌などでは「多くの歩行者が凍死した」、安徽省淮寧などでは「多くの人が凍死した」、江蘇省徐邑などでは「多くの人が凍死し、鳥や獣が餌を求めて家の中に入ってきた」、山東省臨沂などでは「多くの人が凍死した」、威海では「歩行者が数え切れないほど亡くなり、家の中で凍死した人もいた」などである。 |
<<: 北宋の放蕩な宰相、李邦厳の簡単な紹介と、北宋の六盗の一人、李邦厳の最後
>>: 北宋時代の有名な裏切り者、李邦厳はどのようにして死んだのでしょうか?
推薦する
デアン族の習慣 デアン族の葬儀習慣の紹介
デアン族には独自の葬儀の習慣があります。火葬を行う僧侶を除いて、ほとんどの人は土葬されます。各村には...
「乙未日本旅行四行詩」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
イーシの日本旅行に関する四行詩① 呉宝初何千もの雲と波が浜辺に立ちはだかり、風は強く、カモメはのんび...
Xibe 建築の特徴は何ですか?
シベ建築清朝の時代から、シベ族は中国東北部と新疆に村や町を築いていた。シベ族の建築文化は主に家屋や寺...
猛毒のツグミとは一体何なのでしょうか?
中国の時代劇には、十香軟筋粉、微笑半布店、七虫七花糊、鶴嘴紅、孟寒薬、失恋粉など、さまざまな小丸薬や...
『紅楼夢』における、悪魔のような賈宝玉のキャラクターと彼の生活環境との関係は何ですか?
今日は、興味深い歴史の編集者が、世界の悪魔である賈宝玉についての記事をお届けします。ぜひお読みくださ...
『易軒定志』第8巻全文:南宋時代の奇談集
『易軒志』は、南宋時代の洪邁が漢文で書いた奇談集である。本のタイトルは『列子唐文』から来ている。『山...
文学と歴史に関する興味深い逸話:皇帝の婿はなぜフー・マーと呼ばれるのか?
「傅馬」とは古代中国における皇帝の婿の称号です。皇帝の婿、主君の婿、国家の婿などとも呼ばれます。では...
魏晋詩の鑑賞:七段詩、曹植は詩の中でどのような芸術形式を使用しましたか?
漢代の曹植の七段詩については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!豆を煮る...
太平広記・巻29・仙人・李衛公の具体的な内容は何ですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
なぜタタール人は高度な教育を受けた民族だと考えられているのでしょうか?
「急流の岸辺には花や緑の草が点在し、とても美しい。アヘマイトの羊は緑の山々を囲む白い雲のようだ…」新...
朱棣は朱雲文を見つけたのか?なぜ胡毅は召還され、礼部左副大臣に昇進したのか?
永楽14年、朱棣は胡毅を呼び戻し、礼部左副大臣に任命した。胡毅は小官から礼部副司令官に昇進した。胡毅...
拓跋涛には何人の息子がいましたか?北魏の太武帝の息子は誰でしたか?
拓跋涛(408-452)は、名を「佛」といい、鮮卑族の出身で、明元帝拓跋涛の長男で、母は明元密皇后で...
荊族は「翁村制度」をどのように実践しているのでしょうか?
「翁村システム」キン族の社会には「翁村制度」(長老制度)があり、「翁村」、「翁館」、「翁吉」、「翁莫...
『紅楼夢』の賈家の女中や召使はどんな服を着ていましたか?
古代中国の長編小説『紅楼夢』は、中国古典文学の四大傑作の一つです。次は、Interesting Hi...
陸倫の詩集「辺境の歌」の一つ:「張普社に答える辺境の歌、第三部」
陸倫(739-799)、号は雲岩、河中普県(現在の山西省普県)の人。祖先は樊陽涛県(現在の河北省涛州...