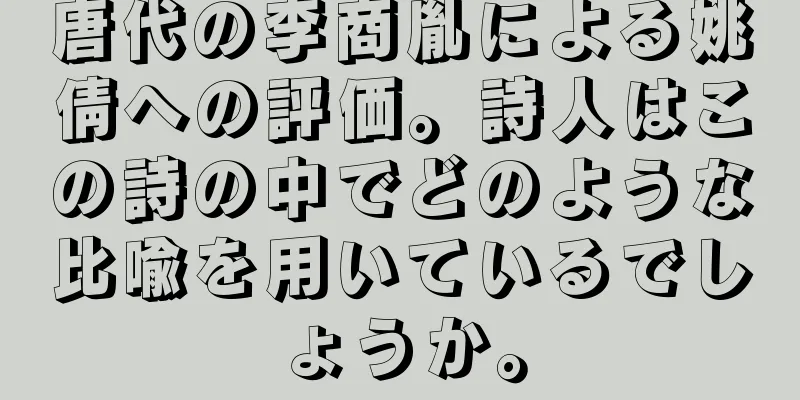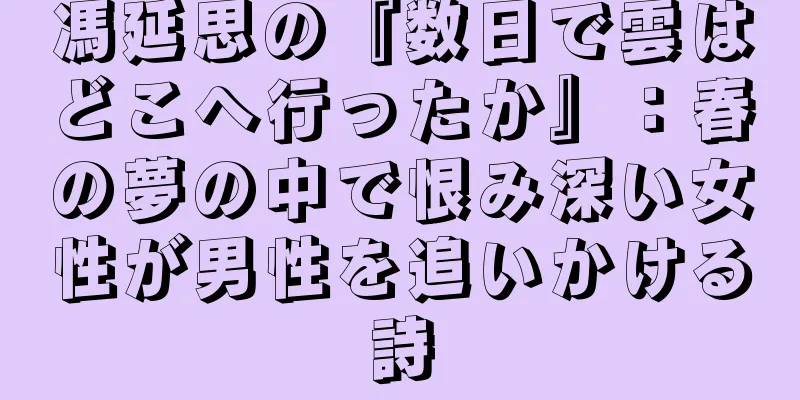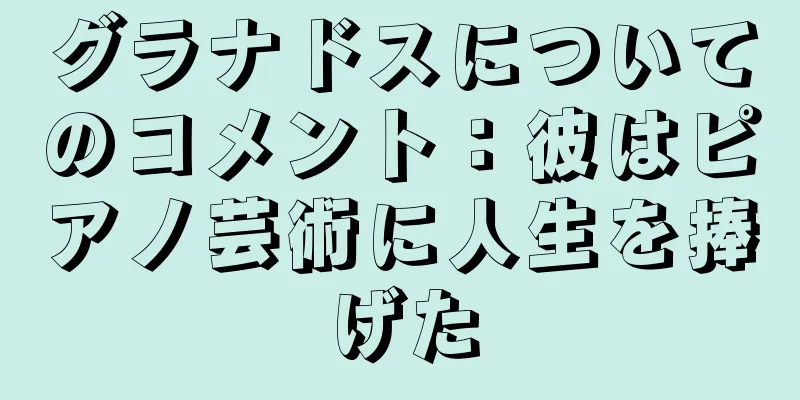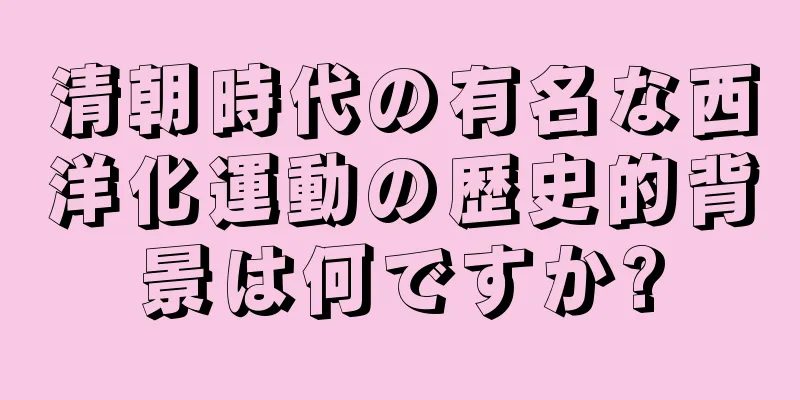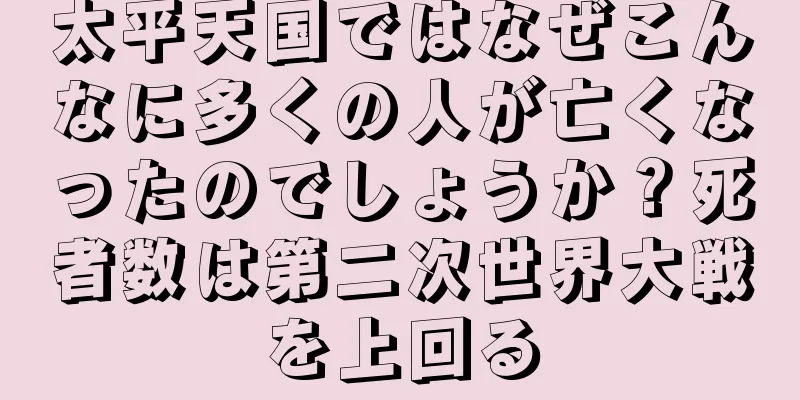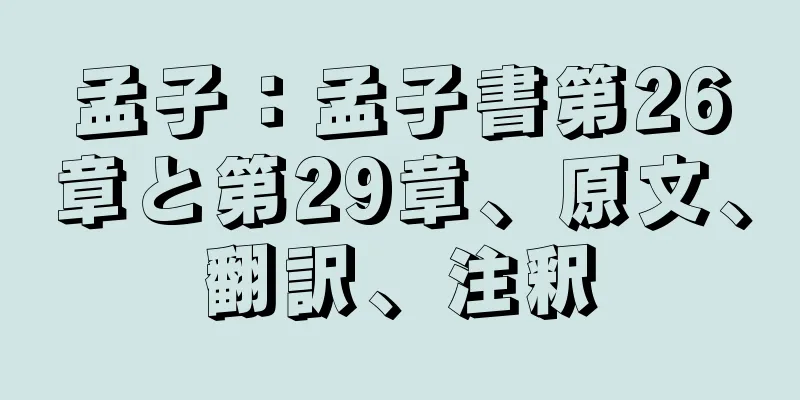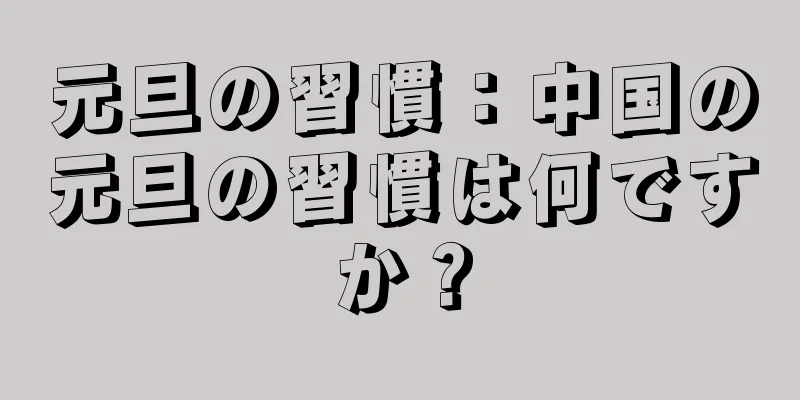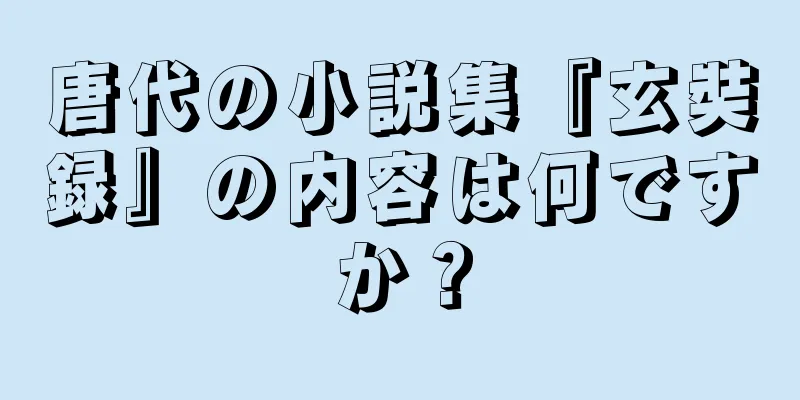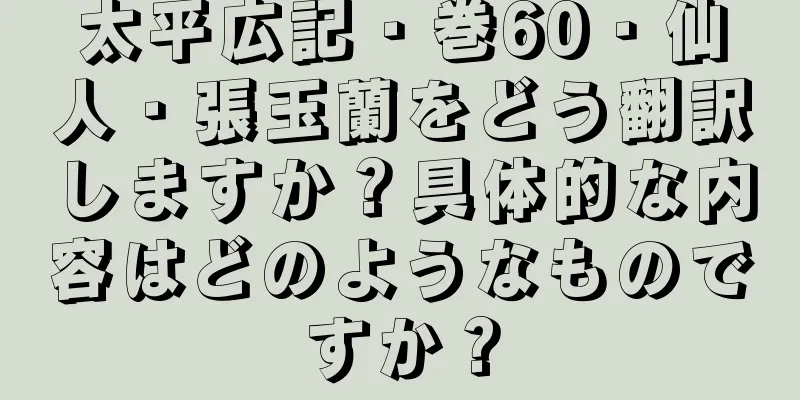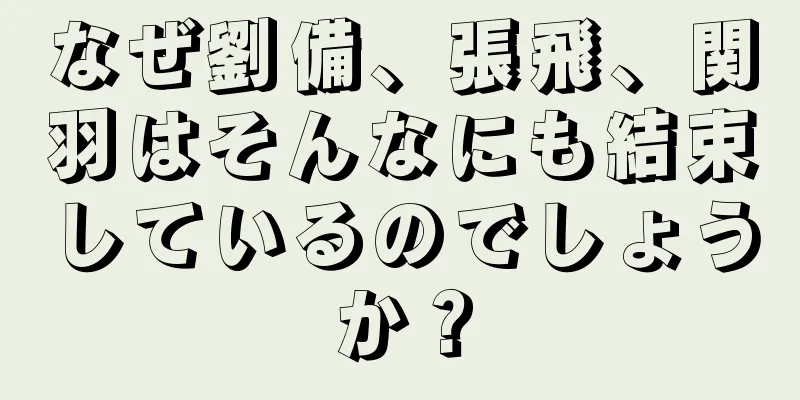日本はどうやって台頭したのか?日本がアジアの大国になった経緯
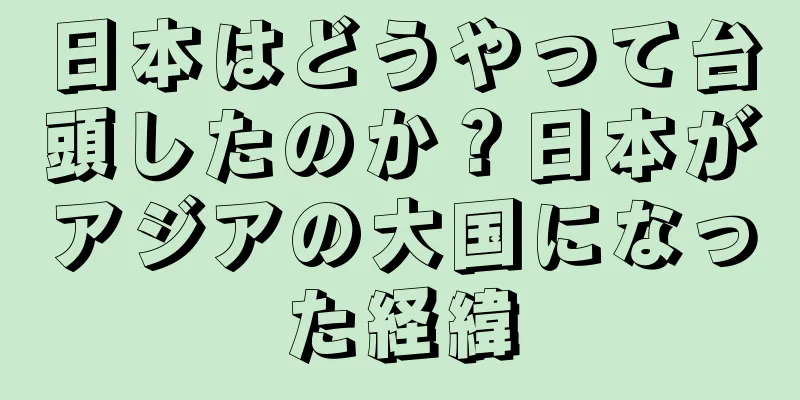
|
私たちがよく読む、日本の発展を紹介する本が 2 冊あります。一つはアメリカの作家ルース・ベネディクトの『菊と刀』、もう一つは戴吉涛の『日本について』です。後者は100ページを超える小冊子で、長くはないが、なかなかの名著である。明治維新後の日本の発展(内政・外交政策立案の根源や日本人の性格形成など)を研究する上で傑作とされ、『菊と刀』を凌ぐ評価を得ている。 『菊と刀』執筆の背景 ルースさんの最大の後悔は、人生で一度も日本に行ったことがないことでした。日本についての彼女の意見や結論はすべて、文書やインタビューに基づいていました。 当時、アジアは依然として慎重に閉鎖的であり、変化に反対しており、特に中国と一連の東アジア諸国は改革に抵抗していた。それに比べて、中世には無知で後進的だったヨーロッパは、封建制度を破壊し、経済発展の障害を取り除いたブルジョア革命を最初に経験した。近代では、ヨーロッパの繁栄とアジアの沈黙が鮮明な対照をなしている。 19 世紀までに、西洋の植民者は多くのアジア諸国に植民地を築きました。アジアは自らの保守主義のために大きな代償を払いました。20 世紀初頭までに、インドは 1 世紀以上にわたってイギリスに完全に支配され、インドネシアはオランダに占領され、フィリピンはアメリカの植民地となり、中国はすべての西洋諸国の競争の対象となりました。多くの植民地化された国々の中で、唯一植民地にならなかったのは日本でした。 近代日本の国力の急激な上昇は世界的に注目され、明治維新を経て半世紀で国家の繁栄と民力の強化という目標を達成しました。日本はまた、外国での植民地化に成功し、軍事的征服を国家建設の基礎として利用した、現代アジアで唯一の軍国主義国家でもある。主流派の観点から見ると、第二次世界大戦の勃発は、世界の反ファシスト諸国が共同で行った侵略に対する正当な戦争であった。しかし別の観点から見ると、日本が引き起こした太平洋戦争は、西洋諸国のアジアにおける植民地侵略を終わらせたのです。戦争初期、日本軍国主義者が掲げた「大東亜共栄圏」の旗印は、東南アジア諸国の民心喚起に一役買った。ジェームズ・モンロー米大統領の有名な言葉「アメリカはアメリカ人のためのアメリカである」と同様に、日本政府も第二次世界大戦の初めに同様の発言をしました。しかし、戦争が進むにつれて、日本軍の残忍で血に飢えた残虐行為は、植民地の人々に対する彼らの態度に反映されるようになりました。これにより、アジアの人々は日本に対する希望を完全に失い、手を携えて日本に抵抗し、最終的に日本に対して勝利を収めました。 しかし、戦争中に日本兵が示した恐ろしい戦闘力、不屈の意志、勤勉な精神は、欧米諸国に衝撃を与えました。その時初めて、人々は、これほど人口の少ないこの遠く離れた小さな島国が、これほどの力を発揮できたことを思い出した。これは確かに、徹底的な研究に値する。 ルースの本はこのような背景の中で書かれました。 「日本について」の確固たる基盤 ディーン・ダイはどうですか?彼女の育ちはルースのそれとは非常に異なっていた。戴氏は、中国が列強による分割の大きな脅威にさらされていた1891年に生まれた。 1894年から1895年にかけての日清戦争後、中国の留学生は日本の急速な台頭を反省し、さらなる学習の目的地として日本を選ぶようになりました。ダイさんは15歳のとき、日本へ留学しました。この時、日露戦争が終わったばかりだった。日本はロシアに勝利し、サハリン島の半分を含む極東の領土の一部を獲得した。また、ロシアに代わって東北部の道路建設権も獲得した。日本国内は歓喜に沸いたが、中国とロシアは大きな打撃を受けた。 ダイ学部長は日本留学中、日本の社会と一般の日本人について徹底的な現地観察を行いました。経済的な問題のため、ダイは学業を修了せずに帰国した。彼の三つの人生観の形成における重要な段階はすべて日本で完成しました。戴さんの日本語はとても上手で、隣に住む日本人は彼が中国人だと分からないと言われています。中国に帰国後、戴氏は孫文に随伴して中国各地を旅し、第二次革命、護法運動、民権日報の創刊など多くの重要な出来事に参加した。孫文は中国と日本を何度も行き来しました。孫文が日本に来るたびに、戴氏はいつも随行していました。また、戴氏は孫文と多くの日本の政治家との会談や交流に通訳として参加しました。こうした外交活動の中で戴氏は桂太郎、犬養毅、田中義一、秋山真之など多くの日本の指導者と深い個人的な友情を築き、近代中国における真の「日本通」であった。このような経験豊かな人物が書いた日本に関する本は、当然ながら権威があり、包括的である。 日本の台頭の背後 日本の近代化は、145年前の1868年の明治維新から始まりました。当時の明治天皇はまだ幼少であり、未成年であったため、日本で実際に改革を推進したのは長州や薩摩の反幕藩士たちであった。彼らの動機は、一方では幕府の腐敗した無能な統治に対する不満、他方では自らの将来に対する不安から来ていた。それはまた、アメリカの黒船に代表される西洋の侵略軍に対する反応であり、抵抗でもあった。明治維新の特徴は、西洋諸国から先進的な設備、システム、科学技術を学び、産業と商業を発展させ、教育を発展させ、世界貿易体制に加わることであった。 日本の学問は徹底していると言えるでしょう。それは日本自身の環境や歴史的伝統と密接に関係しています。日本は極東に位置し、海に囲まれ、大陸からは遠く離れています。北朝鮮に面する対馬海峡までは約100キロ離れています。このような孤立した島は当時の文明の中心地から遠く離れていたため、当然ながら発展は遅れていました。日本は自らの後進性を明確に認識しており、中国やインドの文明が朝鮮半島から日本列島に継続的に伝わるにつれ、後進性に対する意識はより一層強くなっている。 このことは日本人の学問に対する熱意を刺激し、当時、遣唐使が継続的に派遣されていたことからもそれがわかります。このような学問は、日本の発展のすべてに通じていました。また、日本人は学習の過程で、他国の経験を単に模倣したのではなく、学習の成果を日本の国情や習慣と融合させ、独自の文化を創り上げたことが最も評価されるべき点です。日本文化は中国、インド、韓国の影響を受けていますが、全く同じではありません。例えば、言語では漢字を多用しますが、ピンインかなも取り入れています。独特の神道は、中国の儒教とインドの仏教の教えを融合し、さらに日本独自の汎神論を加えて形成されました。学者、農民、商人、職人の四つの階級区分は中国から伝わり、そこから武士階級が発達し、独特の武士道精神が形成されました。 これらはすべて、日本が外国文化を受け入れる過程で現地化してきたことの証左である。こうした歴史的特徴があったからこそ、日本の国家西洋化の過程で、外国文明と国家伝統の間に大規模な衝突や矛盾は起こらず(清水谷で明治維新の三英傑の一人である大久保利通が暗殺されたように、歴史の逆転もある)、改革を阻むような退行的な勢力の影響も明らかにはなかった。日本における明治維新の成功には、根深い理由があるのだ。 一方、中国は昔から広大な国土と豊富な資源で知られており、積極的に外国と交流しなくても自給自足の目標を達成することができます。また、中国は大陸に位置し、それ自体が文明の中心です。近隣諸国からの長期にわたる貢物は中華民族の自信を高めましたが、変化に直面しても変化を嫌がり、後進的な現実を認めようとせず、古いやり方に固執するという種も植え付けられました。中国ではこれまで多くの革命が起こり、抑圧された人々が団結して天命を失った支配階級を打倒し、新しい王朝を樹立した。しかし、新しい王朝が実施した制度は、打倒された王朝、特に2世紀以上も統治した政権の模倣であることが多く、後世の模倣の対象となった。したがって、中国の古代史は、歴代の王朝の歴史に他ならず、歴史の車輪の往復運動であり、まるで古いおじいさんの時計のように、振り子が一方から他方へと揺れ、単調に繰り返されるのと同じである。 日本では改革はあっても革命はなく、改革は上から下へと進められるのが一般的です。一方では、日本は常に比較的後進的で保守的な状況にあり、部族や軍閥が権力と利益のために長い間戦争を繰り広げ、それが極めて破壊的であったためです。土地を所有する大地主たちは荘園を設け、支配する土地を囲み、堀を掘り、見張り台を設け、荘園を監視・管理する特別な人を雇いました。これらの雇われた人々は総じて侍と呼ばれ、日本語では「サムライ」と発音されます。土地を失った農民は小作人となり、地主や武士から長い間抑圧され、搾取された。後進的な経済と制度、そして文明の中心地の外れに位置する日本は、現状を変える必要に迫られていた。 一方、武家政権が確立した後、特に徳川幕府の時代には、日本は制度的な統一を達成しました。比較的狭い領土は比較的集中した人口分布をもたらし、改革政策を全国的に効果的に推進・実施することができ、それぞれが独自のことをする状況はありませんでした。 第三に、長期にわたる階級制度により、日本人は強者に対して従順で謙虚になる習慣を身につけました。農民の抵抗は、地代に対する政府の過度の抑圧を緩和するためだけのものであり、政府を打倒するという考えは一度もありませんでした。これには、日本の土着宗教である神道も貢献しました。神道は日本で生まれました。日本の汎神論、中国の儒教と道教、そしてインドの仏教文明が融合した独特の信仰です。神道は、日本は天照大御神によって創造され、すべての日本人は神の民であることを強調しています。天皇は神の子孫であり、日本を統治する法的権利を持ち、日本の最高の精神的および政治的指導者です。神道は日本に深い影響を与えており、ほぼすべての日本人が神道を信仰しています。明治維新の際、政府は天皇の名の下に改革を行い、ほとんど抵抗に遭わず、日本の改革はより徹底したものとなりました。 中国が歴史の重い重荷に苦しんでいる間、日本は楽々と前進することができた。国全体が上から下まで変化していた。明治時代に日本に来た西洋人が、普通の日本人に「日本の歴史はどこから始まったのですか」と尋ねたことがある。日本人の答えは洞察に富んでいた。「我々の日本の歴史は今日から始まるのです」 |
<<: 清朝の十二皇帝の在位号にはどんな意味が隠されているのでしょうか?
>>: 明代の将軍、李成良を客観的に評価するにはどうすればいいでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』の林黛玉の死の伏線とは何なのか?真実は何なのか?
林黛玉は中国の古典小説『紅楼夢』のヒロインです。よく分からない読者は、Interesting His...
古代史において科挙受験生が飛び越えた「龍門」はどこにあるか詳しく教えてください。
はじめに:学者が科挙で最高点を取ることができれば、鯉が龍門を飛び越えるようなもので、死すべき肉体を離...
「中秋の名月洞庭湖歌」の原文は何ですか?どう理解すればいいですか?
『中秋洞庭湖月詠』の原文はどんな内容ですか? どのように解釈しますか? これは多くの読者が詳しく知り...
「春風」の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
春風白居易(唐代)春のそよ風が最初に庭に梅の花を運び、続いて桜、杏、桃、梨の花が咲きます。奥深い村に...
なぜ北宋は西夏を平定しなかったのか?リトル・シーシアにとって大惨事!
なぜ北宋は西夏を平定しなかったのか?小国だった西夏は大惨事だった!次のInteresting His...
なぜ劉備は関羽に貴族の称号を与えなかったのでしょうか?兄弟間のトリックもある
古代の皇帝は、民衆の心をつかみ、権力を強化し、威厳を示し、寵愛を示すために、昇進、爵位、貴族の称号を...
『紅楼夢』では、賈宝玉には決してかなわない薛潘の強みとは何でしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
『紅楼夢』の希春には尼僧になる以外に選択肢はあったのでしょうか?
『紅楼夢』で最も高貴な女性は誰でしょうか?それはきっと西春でしょう。彼女の高貴さは自然に生まれたもの...
「良いことがやってくる:首を振って赤い塵の世界を去る」を鑑賞、詩人朱敦如は当時臨安に呼び戻された
朱敦如(1081-1159)、号は熙珍、通称は延和、沂水老人、洛川氏としても知られる。洛陽から。陸軍...
宝公の事件 第二章 観世音菩薩の夢
『鮑公案』は『龍土公案』とも呼ばれ、正式名称は『都本鮑龍土百公案全伝』で、『龍土神段公案』とも呼ばれ...
古典文学の傑作「劉公安」第85話:劉勇は事件ファイルを読んで疑念を抱く
『劉公庵』は清代末期の劉雍の原型に基づく民間説話作品で、全106章から成っている。原作者は不明ですが...
周密の有名な詩の一節を鑑賞する: 私は一人で東風に寄りかかっている、私の香り高い思いを誰に送ればよいのか?
周密(1232-1298または1308)は、号を公瑾といい、曹荘、小寨、平州、小寨とも呼ばれた。晩年...
前漢時代の朱夫延と東方朔の比較 朱夫延と東方朔はどんな人物だったのでしょうか?
朱夫炎と東方碩朱夫岩といえば、前漢時代には一定の政治的地位を持っていた人物です。特に政治理論において...
唐代の詩人、魏応武の『仙居集段と重陽』の原文、注釈、翻訳、鑑賞
『仙居集段集重要』は唐代の魏応武によって著されたものです。次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届け...
小鸞の政治献金はいくらですか? 小鸞の政治施策は何ですか?
蕭鸞(452年 - 498年9月1日)は、景斉とも呼ばれ、通称は玄都で、南蘭嶺(現在の江蘇省常州の北...