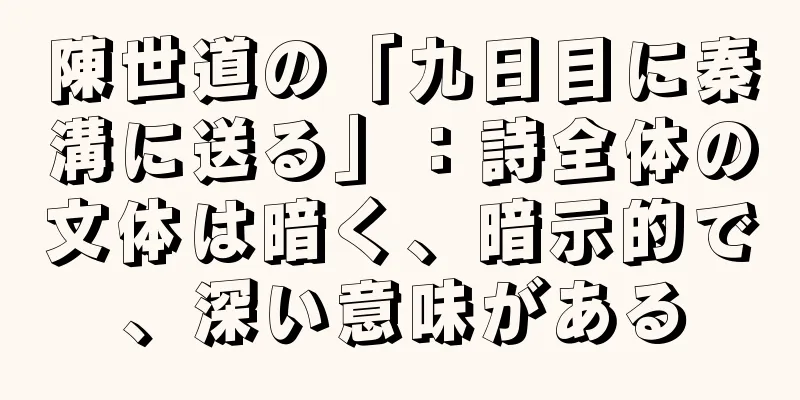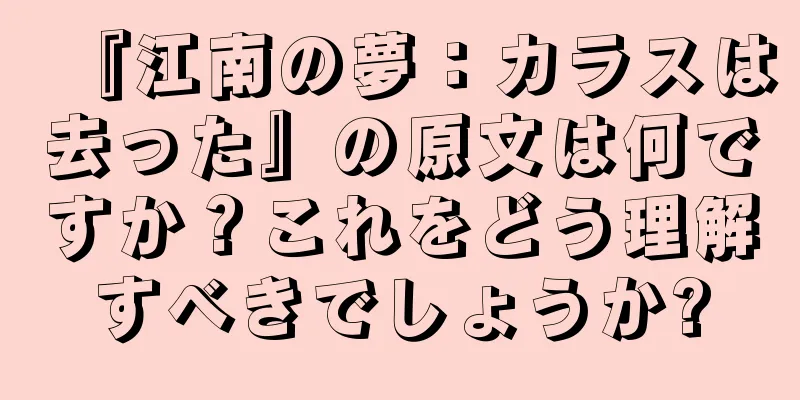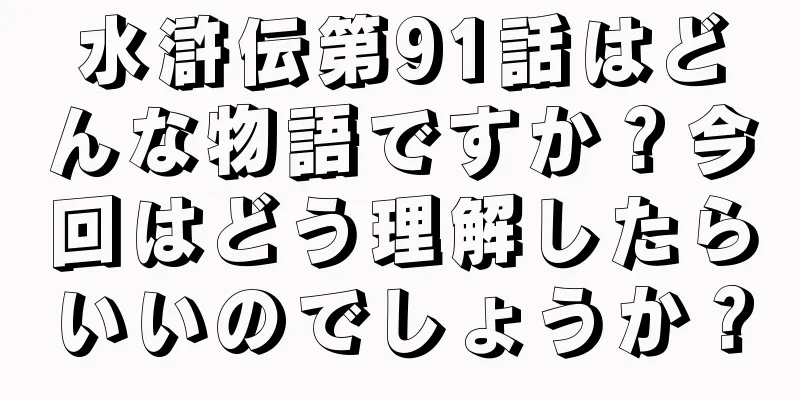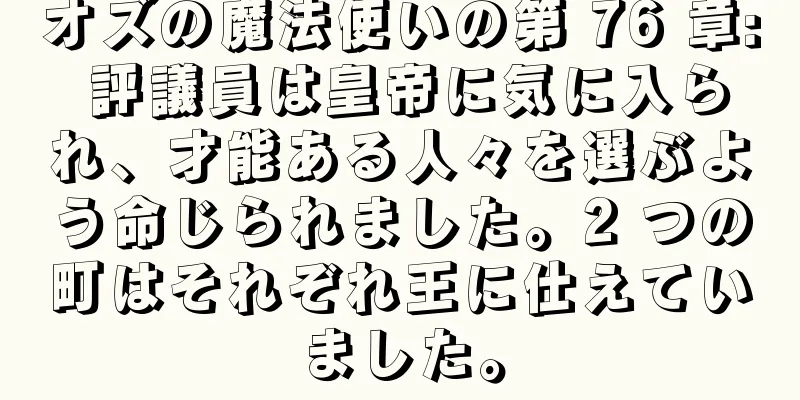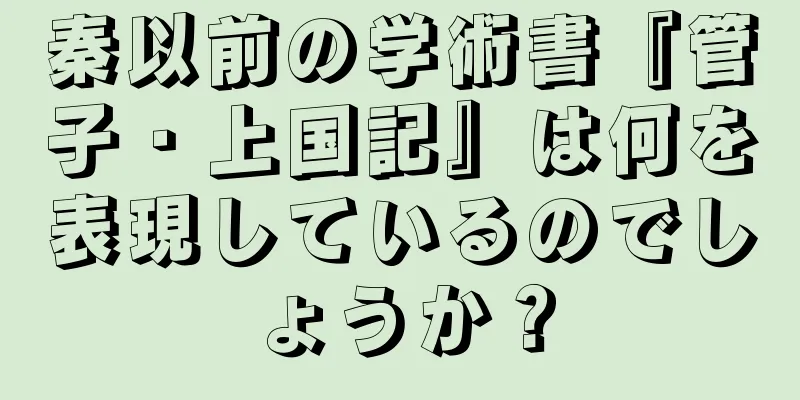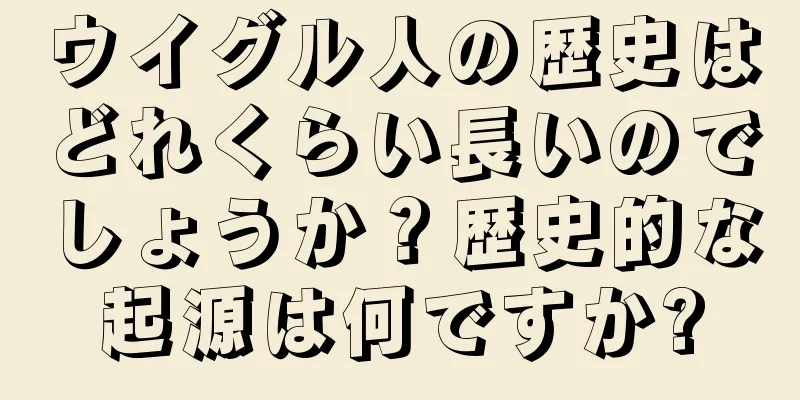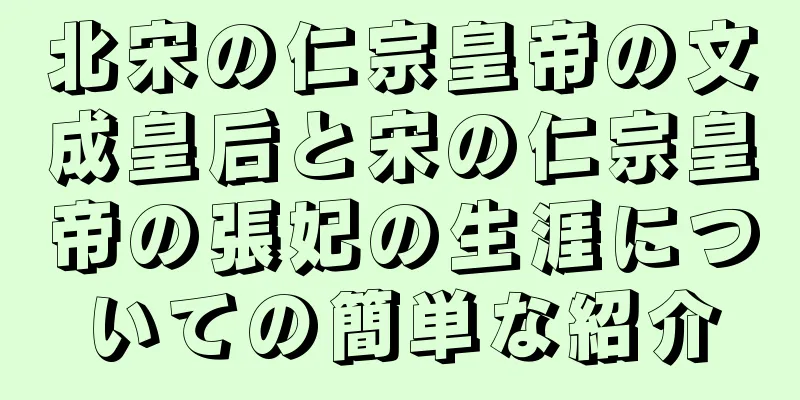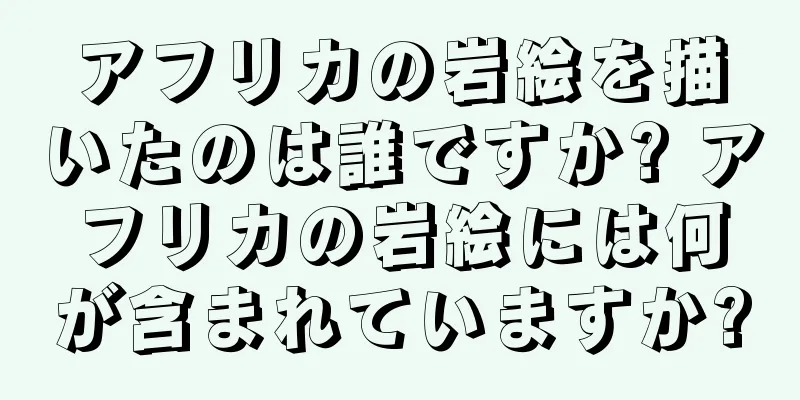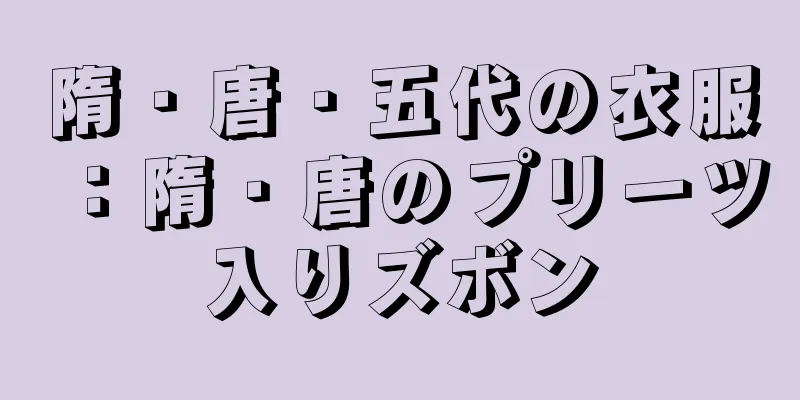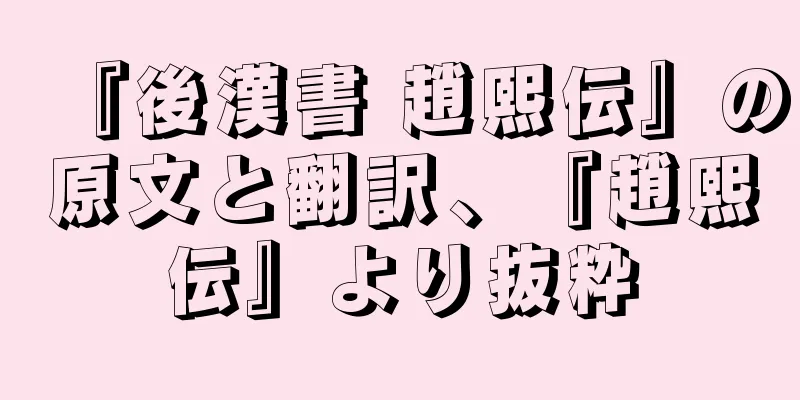「悪魔を語る」とはどういう意味ですか?この文はどこから来たのでしょうか?
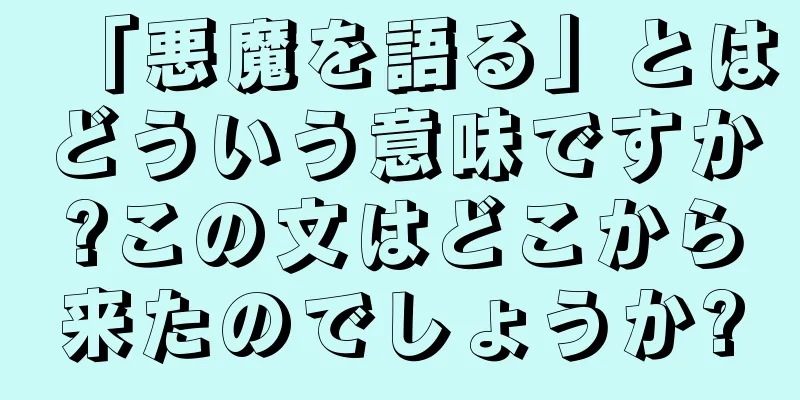
|
「悪魔について語れば、悪魔が現れる」というのはよく知られた格言です。曹操は目と耳が多く、動きが早く、遍在しており、いつでも私たちの前に現れるかもしれないので、警戒しなければならない人物だと書かれています。 「曹操を語れば曹操が現れる」ということわざの起源についてはさまざまな説があります。 ソース 1 曹操が救援に来た 漢の献帝はかつて李傅と郭汜の戦いで危機を逃れた。しかし、李傅と郭汜は力を合わせ、漢の献帝を追い続けた。ある人は曹操を推薦し、青州の黄巾軍を鎮圧するのに大きな貢献をしたので、皇帝を救出できると言った。しかし、使者が送られる前に、同盟軍が到着した。逃げ道がないと見て、夏侯惇は曹操の命令に従い、軍隊を率いて「皇帝護衛」に成功し、後に李・郭連合軍を破った。曹操はより高い官位を与えられた。それで、「曹操を語れば曹操が現れる」ということわざがあります。 曹操が率先して皇帝を守りに来たというのが民間の言い伝えで、三国志演義とは少し異なります。 曹操が董卓を倒した後、董俊の太守を務めたと言われています。当時、山東省で黄巾賊が再び蜂起した。彼は吉北湘宝新と共同で黄巾賊と戦い、30万人以上の降伏兵を集めた。それ以来、曹操の名声は高まり、朝廷によって真東将軍に昇進した。董承と楊鋒は皇帝を洛陽に護衛した後も、李傕と郭汜の侵攻を懸念していたため、漢の献帝に曹操を宮廷に召還して王族を助けてほしいと嘆願した。曹操は命令を受けて山東の全軍を動員し、皇帝を守るために洛陽へ急行した。洛陽城の外に到着するとすぐに、李傕と郭汜は軍隊を率いて洛陽を攻撃した。 「曹操のことを言えば現れる」というこのことわざは、「曹操が皇帝を救いに来る」としても知られています。 ソース2 曹操を捕らえるチャンスを逃した 『三国志演義』第十二章「陶公祖は徐州を三度譲り、曹孟徳は呂布と戦う」では、曹操が濮陽で呂布と戦っていたとき、陳宮の罠に落ちて慌てて逃げた。火の光の中で、呂布が馬に乗って戟を手にして近づいてくるのが見えた。曹操は両手で顔を覆い、馬に鞭を打ち、呂布を負かした。 呂布は後ろから馬に乗って近づき、鉾で曹操の兜を叩きながら尋ねた。「曹操はどこにいる?」曹操は後ろを指差して言った。「前の黄色い馬に乗っているのが曹操だ。」呂布はこれを聞いて曹操を捨て、馬に乗って追いかけた。明代末期から清代初期の学者、毛宗剛はこう述べている。「曹操に会ったら、曹操に尋ね返せ。曹操を放せ。曹操を追ってはいけない。」 諺にもあるように、曹操について語れば曹操が現れる。直接会って会えないのはおかしいでしょう?」 ソース3 曹操の多面性を描く 「曹操を語れば現れる」とは、曹操は目と耳が多く、動きが早く、どこにでも存在するので、いつでも人々の前に現れる可能性があり、人々は曹操に注意しなければならないという意味です。 では、なぜこのような記述が出てくるのでしょうか? これはおそらく曹操の性格と切り離せないものでしょう。曹操は後漢末期の人物だが、明代の『三国志演義』では、手をひっくり返すだけで雲や雨を起こすことができる裏切り者の大臣として描かれている。 「世界に裏切られるよりは、むしろ世界に裏切られたほうがましだ」という有名な言葉は、彼の性格を鮮やかに表している。 東漢末期、朝廷の高官であった喬玄は、曹操がまだ若かった頃、曹操を「乱世の英雄、平時の裏切り者」と呼んだ。歴史上、喬玄の鑑定の専門知識に匹敵する人物はいないようです。 |
<<: 山海関の歴史 山海関はなぜ「世界一の峠」と呼ばれるのか?
>>: 秦の将軍、甘茂の簡単な紹介:甘茂が秦を滅ぼして斉に行ったというのはどういう意味ですか?
推薦する
孟浩然の古詩「白明夫と河を巡る」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「白明福と河を巡る」時代: 唐代著者: 孟浩然古くからの友人が遠くから来てくれたし、郡長も初め...
「生生漫・荀荀密」の原文は何ですか?どう理解すればいいですか?
文才のある李清昭の有名な詩「長悲歌:探見聞」の原文は何ですか? どのように理解しますか? これは多く...
1898 年の改革運動において、改革者たち自身はどのような間違いを犯したのでしょうか?
古代および現代における改革は、既得権益に影響を及ぼすことになる。したがって、旧制度の非合理性を利用し...
三国志演義第84章:魯迅の陣地は700マイルにわたって燃え、孔明は巧みに八陣を組んだ
『三国志演義』は、『三国志演義』とも呼ばれ、正式名称は『三国志演義』で、元代末期から明代初期にかけて...
王維の古詩「龍渓行」の本来の意味を理解する
古代詩「隴西への旅」時代: 唐代著者: 王偉馬は10マイルごとに疾走し、5マイルごとに馬に鞭を打ちま...
戦国時代の斉の人々の軍事的考え方は何だったのでしょうか?それは単に「不当な利益を得ること」なのでしょうか?
今日は、戦国時代の斉人の軍事思想について、おもしろ歴史編集長がお届けします。興味のある方は、編集長を...
もし関羽が華雄に即死させられたら、張飛は戦場に出て華雄と戦うでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『富徳清如于胡冰』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
この詩は翡翠の壺の中の氷のように澄んでいる王維(唐代)玉壺は何の役に立つのでしょうか?普通の氷室の方...
Li Xin には何人の兄弟姉妹がいますか? Li Xin の兄弟姉妹は誰ですか?
西涼最後の君主、李信(?-420年)は、号を世野、通称を同璽といい、隴西省成吉(現在の甘粛省景寧市南...
蘇軾の「大雪」では、雪と梅の花を使って彼の内面の純粋さを表現しています。
蘇軾は東坡居士、蘇東坡とも呼ばれ、北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、書、絵画で大きな業績を残した。...
「竹石図」は清朝の鄭謝によって書かれたもので、竹の粘り強さを描写している。
鄭板橋は、本名を鄭謝、字は科柔、号は連安、板橋、通称板橋先生と呼ばれ、清代の書家、画家、作家で、文学...
『南渓常山道士隠居所探索』の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
南西常山の道教の隠遁者を探す劉長清(唐代)道を歩いていくと、苔の上に足跡が残っていました。静かな小島...
王庭雲の有名な詩の一節を鑑賞する:隅に薄い雪の跡、残った花びらは緑の種子でできている
王廷雲(1151年 - 1202年10月27日)は、晋の作家、書家、画家であった。名は子端、号は黄花...
なぜ賈おばあさんはいつもきれいで美しい女性が好きなのでしょうか?
以下は、Interesting Historyの編集者がお届けします。賈牧が美女を優遇する理由には何...
太平広記第404巻宝5にはどんな登場人物がいますか?
粛宗時代の霊光豆、万仏山亀盆、塵除けスカーフ、浮遊薄毛コート(題字のみ、文字なし)、崇明枕三宝村火玉...