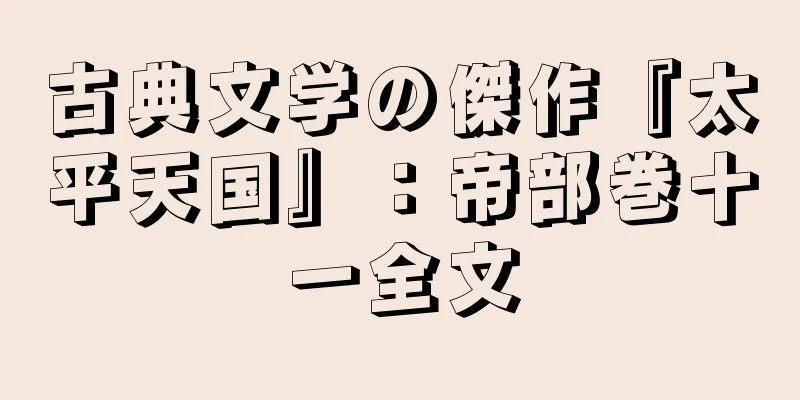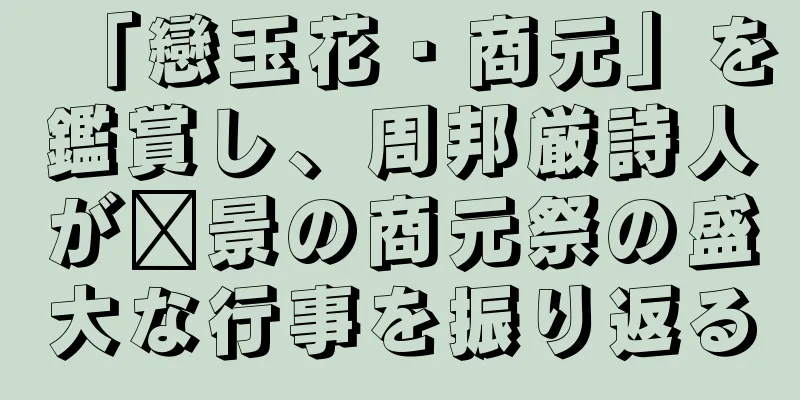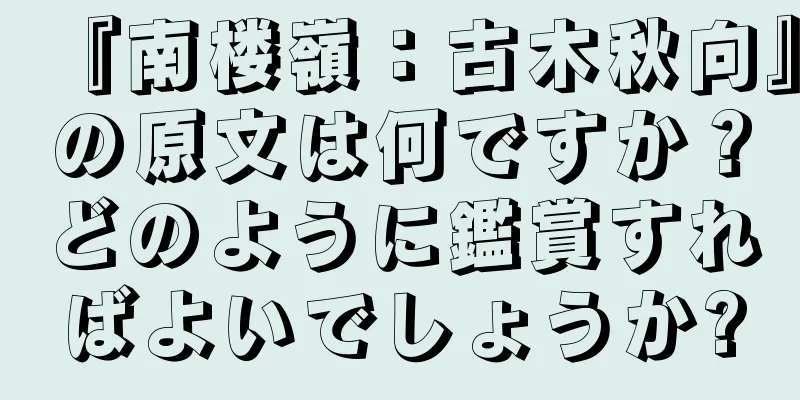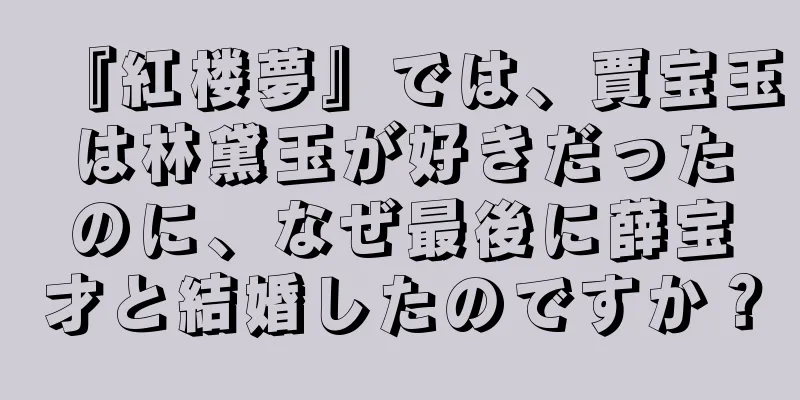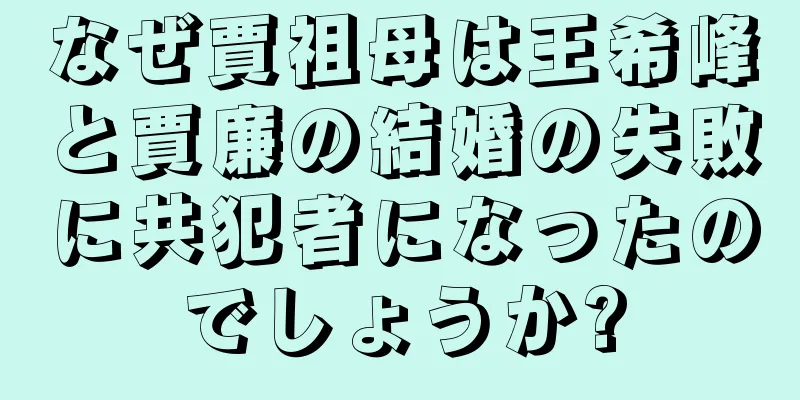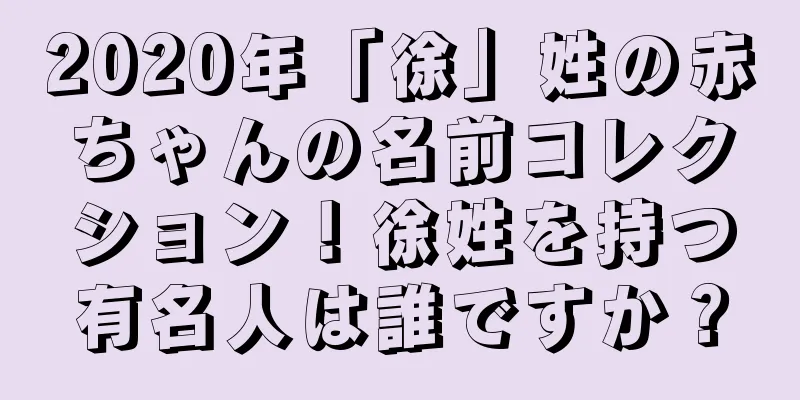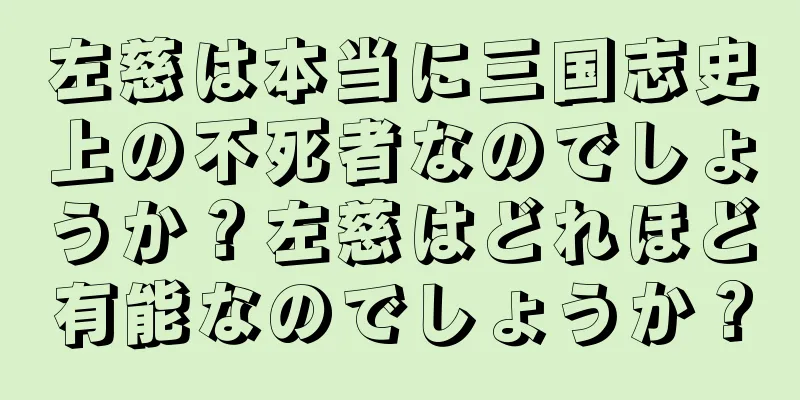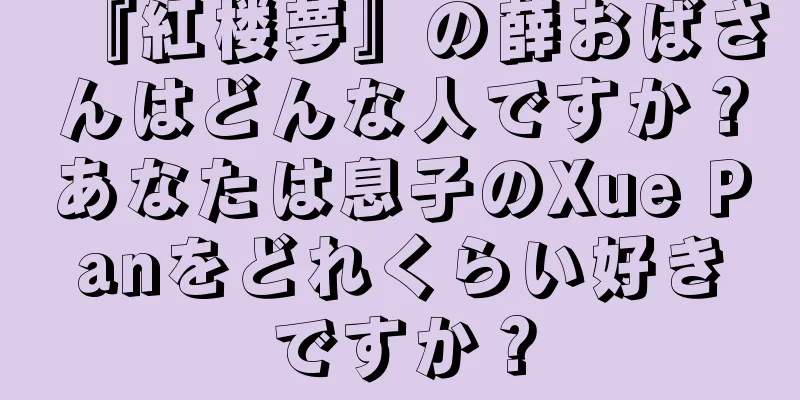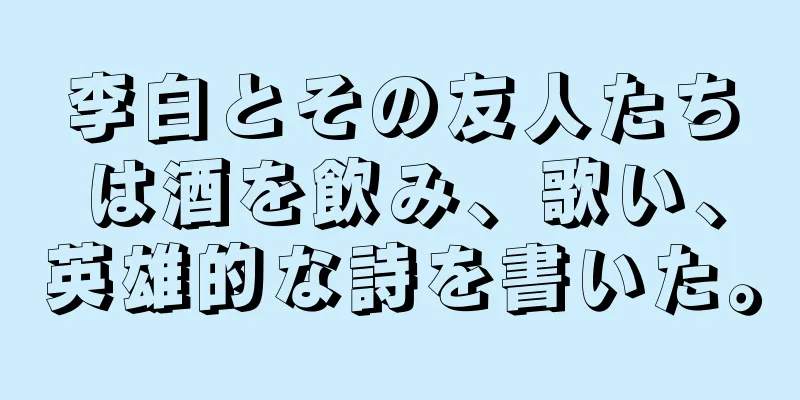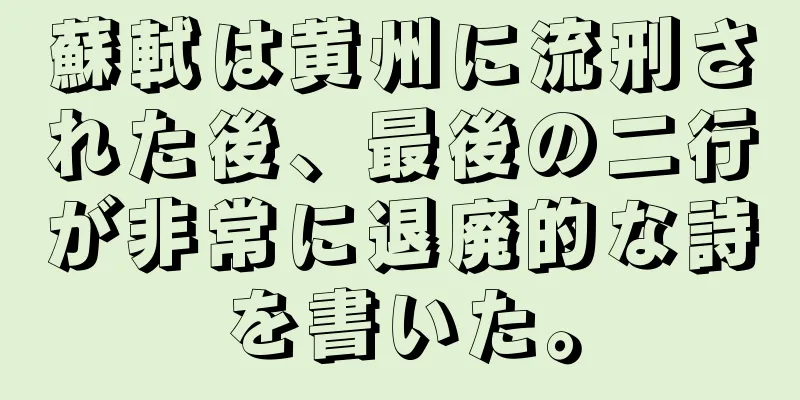箸を発明したのは誰ですか?箸の歴史を探る
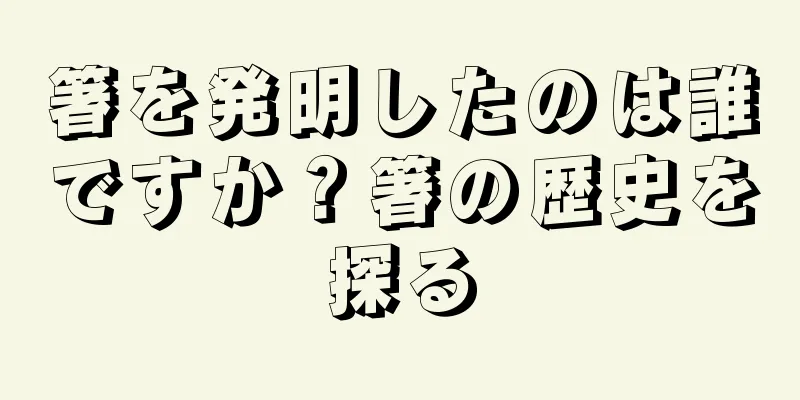
|
箸を発明したのは誰か知っていますか? 知らなくても大丈夫です。Interesting History の編集者が教えてくれます。 箸は中華民族が発明した食事の道具です。私たちの祖先が生肉を食べたり血を飲む野蛮な生活を終えたとき、箸は文明とともに生まれました。箸収集家によれば、現在までに箸の種類は600種類以上あるという。 商代の銅箸、春秋時代の鉄箸、翡翠の犀頭箸などがあります。唐の時代までに、箸は人の誠実さを象徴するために使われました。唐の玄宗皇帝はかつて宰相の宋景に金の箸を与えてこう言った。「私はあなたに金を与えているのではない。あなたの誠実さを示すために箸を与えているのだ。」これは「誠実さを示すために箸を与える」という暗示である。実際、最も一般的な箸は、竹箸、木製箸、そして現代のプラスチック箸です。金属製の箸ほどかさばらず、高価でもありません。作るのも簡単で、地元の材料も簡単に手に入ります。 箸は先秦時代には「梜」、漢代には「箸」、明代には「クッショ」と呼ばれていました。 『礼記』第1部「夷」には「野菜の入ったスープは箸で調理する」とある。応急章には「箸は箸とも呼ばれ、食べ物を拾うのに使われる」とある。『礼記』の鄭玄の注釈には「箸は箸と同じである」とある。 伝説によると、広西チワン族自治区平楽県に起源を持つ「箸竹」と呼ばれる竹があります。「箸のように小さいが、象牙のように硬く、箸を作るのに非常に適している」とされています。中国人は箸に対して一定の要求を持っていることがわかります。 1972年、ニクソン米大統領が中国を訪問した際、周恩来首相は人民大会堂で国賓晩餐会を開き、江安産の竹箸を使用した。ニクソン大統領がナイフとフォークを使う習慣があることを知っていながら、首相が箸を用意したことは実に不可解である。実際、これはまさに我が国の首相の善意なのです。彼は箸の象徴に基づいて客をもてなしたが、これは両国が戦争をせずに平和に暮らせることを暗示していた。カナダ人の記者がすぐにその箸をしまって大切にしていたのも不思議ではない。 では箸を発明したのは誰でしょうか? 考古学的データは、太古の昔に私たちの祖先が木の枝や竹の棒を使って食べ物を拾う方法をすでに知っていたことを証明しています。箸の起源については次のような話があります。 大禹は洪水を治すために、家に入らずに三度通り過ぎ、食事や睡眠の時でさえ、一分たりとも無駄にしようとしませんでした。かつて、大雄は野原で肉を焼いていました。陶器の鍋の中の肉はとても熱くて、すぐに手で食べることができませんでした。時間を無駄にしたくなかったので、二本の枝を切り落とし、肉を取り出して食べました。やがて、大禹は小枝を使って食べ物をつまむ技術を習得しました。部下たちは、彼が手を火傷したり汚したりすることなくそのように食べるのを見て、彼の例に倣いました。これが、箸で食べる習慣の始まりでした。 箸は昔、「箸」と呼ばれていました。古書『漢非子于老』には、「昔、周王が象牙の箸を作ったので、冀子は驚いた」と記されています。周王は商王朝末期の君主です。紀元前11世紀には、象牙で作られた箸が我が国に現れていたことがわかります。つまり、私の国では箸の使用の歴史が3,000年以上も記録されているのです。 さらに、箸に関する民間伝説も数多くあります。ある伝説では、姜子牙が神鳥からインスピレーションを受けて竹の箸を発明したと言われています。 妲己は周王を喜ばせるために、玉のかんざしを箸として使うことを発明したという伝説があります。誰が発明したにせよ、それは中国人であり、箸は四大発明に次ぐ第五の発明に数えられるべきです。 |
<<: なぜ劉備守は皇太子を皇帝として擁立し、唐の昭宗を皇太子として崇めたのでしょうか?
>>: なぜ李淵は死ぬまで新たな王妃を任命しなかったのでしょうか?
推薦する
王毓の『滕王閣序』にある、沈む太陽と一羽の雁が一緒に飛び、秋の水と空が同じ色になっている場面をどう説明すればよいのでしょうか。
「滕王閣序文」次回はInteresting History編集長が関連コンテンツを詳しく紹介します。...
杜甫の有名な詩の一節を鑑賞する:雨の音は寒さを早め、雁の翼は濡れて高く飛ぶのは難しい
杜甫(712年2月12日 - 770年)は、字を子美、号を少陵葉老といい、唐代の有名な写実主義詩人で...
『紅楼夢』の賈夫人と王夫人の関係は何ですか?
『紅楼夢』の賈牧と王福仁の関係は?本当に相性が悪いのか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介します。ご...
曹操の『九漢行』原文、注釈、翻訳、鑑賞、創作背景
曹操の『九漢行』については、興味のある読者はInteresting Historyの編集者をフォロー...
漢の宮殿の屋根の特徴は何ですか?
発展の過程で、古代中国の建物の屋根の組み合わせ形式は常に研究され、いくつかの厳格な規則が形成され、用...
『紅楼夢』で、劉おばあさんはなぜ王希峰の娘に喬潔という名前を付けたのですか?
喬潔は金陵十二美女の中で最年少です。劉おばあさんが二度目に栄果屋敷を訪れたとき、王希峰は彼女に娘に名...
魏晋の古詩の鑑賞:桃花春。この古詩はどのような情景を描いているのでしょうか?
魏晋時代の陶淵明の『桃花春』について、次の興味深い歴史編集者が詳しい紹介をお届けしますので、見てみま...
ハイジの「9月」の原文と評価
神々の死を目撃した草原は野生の花で覆われている遠くの風は距離よりも遠い私のピアノは涙なしですすり泣く...
于滄海のプロフィール 于滄海は小説の登場人物である。
于滄海は、金庸の武侠小説『微笑矜持放浪者』の登場人物である。彼はまた、小柄な于、道士の于としても知ら...
三星堆青銅器の正体は何でしょうか?三星堆文化の未解明の謎とは何でしょうか?
今のところ、三星堆から出土した青銅器については、まだ解明されていない疑問が数多くあります。この二つの...
古代人は清明節をどのように祝ったのでしょうか?古代において、清明節は実は食べ物のお祭りでした。
春が来て清明節になると、人々は外出をしなければなりません。また、清明節は多くの季節の珍味が市場に出回...
帰古子:原典の陰伏七法:精神亀養志法全文と翻訳と注釈
「魏愚子」は「毗と何の計略」としても知られています。これは、ギグジ氏の発言をもとに、後代の弟子たちが...
桃の仁とは何ですか?どのような桃の実が一級品なのでしょうか?
本日は、Interesting History の編集者が、皆様のお役に立てればと、最高級の緑青を帯...
水滸伝で黒旋風の李逵はどのように死んだのですか?黒旋風李逵の紹介
水滸伝で黒旋風の李逵はどのように死んだのか? 黒旋風の李逵の紹介 李逵は中国の古典小説「水滸伝」の重...
古典文学の傑作『淘宝夢』:第5巻:湘湖
『淘安夢』は明代の散文集である。明代の随筆家、張岱によって書かれた。この本は8巻から成り、明朝が滅亡...