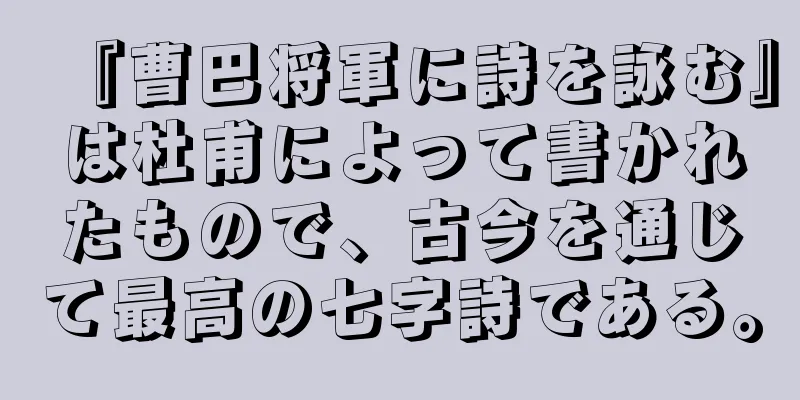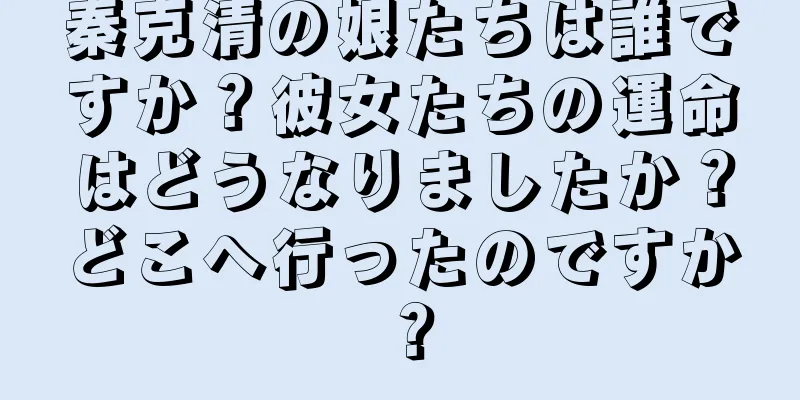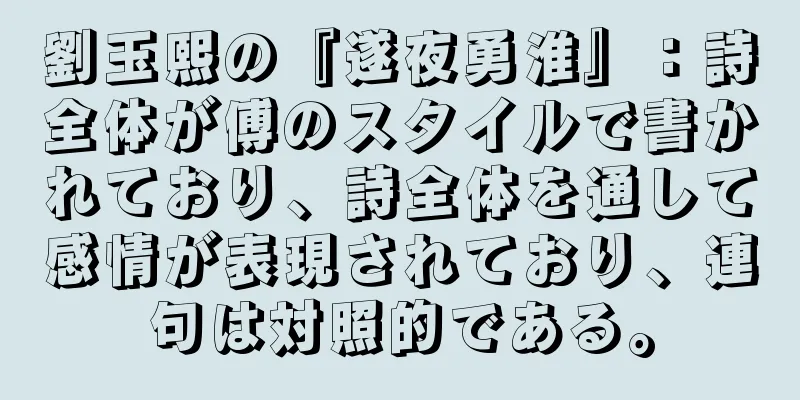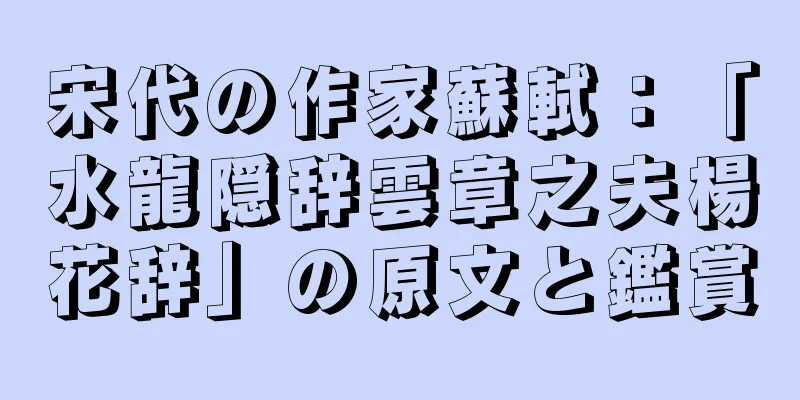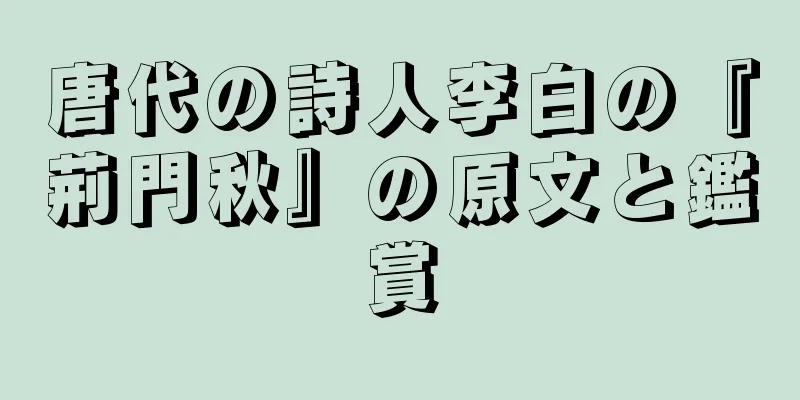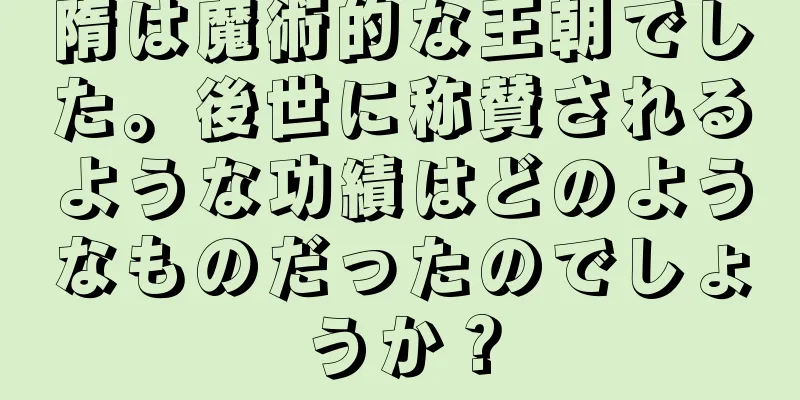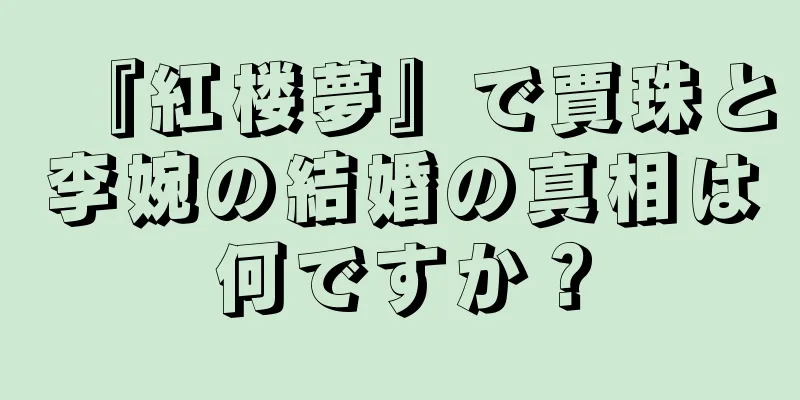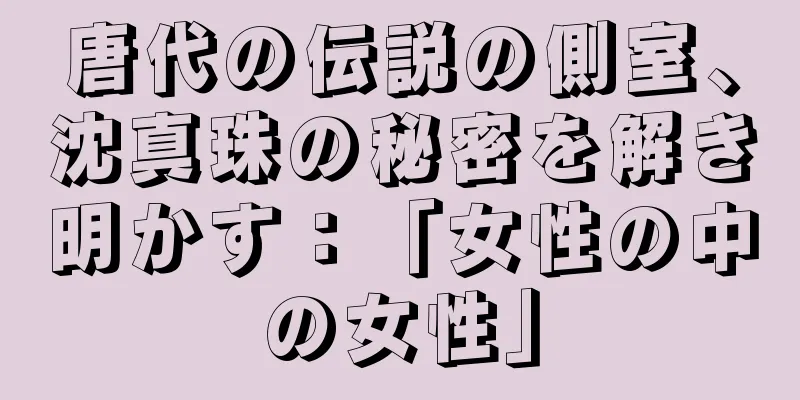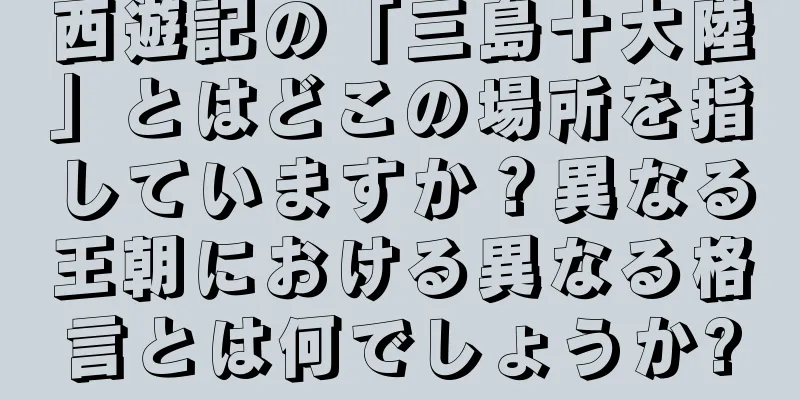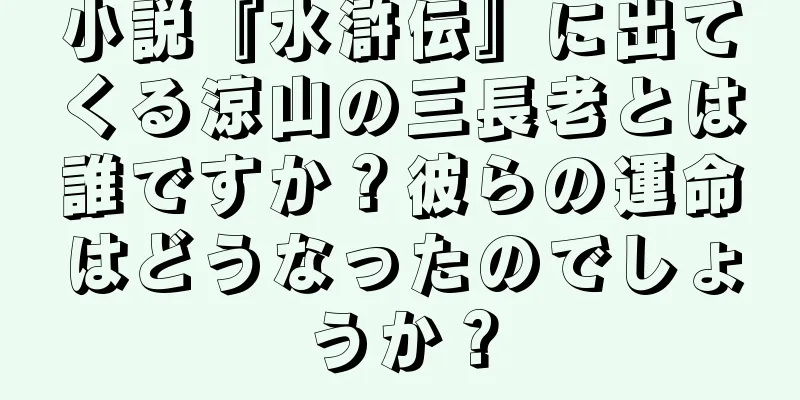一日三食はいつ始まったのでしょうか?昔の人は一日に二食しか食べなかったと言われています。
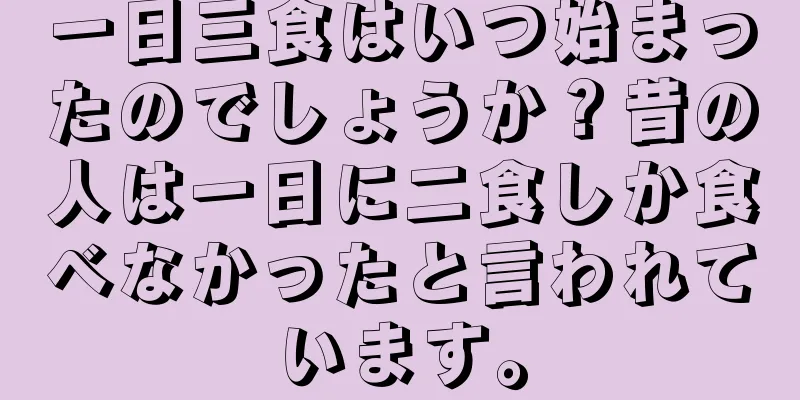
|
一日三食はいつから始まったのでしょうか?昔は一日二食しか食べていなかったと言われています。 一日三食は人々の生活の標準となっています。朝食、昼食、夕食の一日三食を食べるのが最も基本です。残業したり夜更かししたりするときに、夜食を食べる人もいます。食事は実際には、お腹を満たし、物事を行うエネルギーを得るためだけです。しかし、多くの人が知らないのは、1日3食の食生活が実は宋の時代に始まったということです。それ以前は、人々は基本的に1日2食しか食べませんでした。それはなぜでしょうか? 食糧問題について語るには、まず原始社会の始まりから話を始めなければなりません。私たちの最も古い祖先には、1 日に決まった回数の食事を食べるという概念はありませんでした。空腹のときは食べ、空腹でないときは食べなかったので、食事の時間は非常に不規則でした。商王朝の時代までに、人々は基本的に時間通りに食事をする習慣を身につけていましたが、食べる量はまだ個人によって異なっていました。秦以前の時代、一般の人々は1日に2食しか食べませんでしたが、貴族は1回多く食べることもありました。 つまり、誰もが1日2食を基本としつつも、貴族の中には1日3食をとる者もおり、食べる量が地位の象徴となっていたのです。宋代以前は、庶民はまだ一日二食でした。一日四食を食べられるのは王族だけで、王子たちは一日三食でした。例えば、前漢の時代に淮南王が反乱を起こして追放されたとき、彼に下された勅令には「一日三食を二食に減らせ」と明確に書かれていました。食事の回数がその人の地位を表していることがわかります。 一日二食とは、昼間は仕事に出かける前、夜は家に帰ってから食べる食事です。宋代以前は、基本的に夜間外出禁止令があり、一定の時間後には家に帰らなければなりませんでした。外には誰もおらず、娯楽もなかったので、ただ家に帰って寝るだけでした。一部の裕福な人が夜食を余分に食べない限り、基本的に一日二食でした。 しかし、宋代になると状況は完全に変わりました。宋代は弱い王朝だと考える人が多いですが、宋代の経済が非常に発展していたことは否定できません。夜間の外出禁止令も解除され、人々は夜散歩に出かけることができました。夜の生活は以前の王朝よりもはるかに豊かになり、さまざまな居酒屋の場所も制限されなくなったため、人々は食事が1回増え、1日3食になりました。 したがって、1日3食は確かに宋代に始まったのです。結局のところ、昔は経済発展があまり良くありませんでした。同時期に比べれば繁栄した時代だったとしか言えませんが、宋代に比べればそれほど良くはありませんでした。そのため、人々は1日2食しか食べることができませんでした。一方では、この慣習的な規則のためであり、他方では、彼らには本当に余裕がなかったのです。たまには3食食べることもあるかもしれませんが、毎日食べる余裕はなかったので、2食が標準でした。 宋代は違いました。古代で最も幸福な王朝だったと言えるでしょう。テイクアウトの食べ物も登場しました。経済発展期には、人々はそれを買える余裕があったため、1日3食が徐々に定着し、今日まで続いて標準になりました。 |
<<: 金メッキの青銅のライオンは何の素材で作られていますか?金メッキの青銅のライオンを作るにはどれくらいの金が必要ですか?
>>: 秦檜がひざまずいている像の塗装に傷がついたのはなぜですか?なぜこれらの像は100年経っても撤去されないのでしょうか?
推薦する
ヤン・ジダオの友人に対する深い愛情:「臨江仙・淡水での喜びの3年間」
以下、面吉道の『臨江仙・淡水三年歓喜』の原文と評価を『面吉道』編集者が紹介します。興味のある読者と『...
呉謙の「鵲橋仙・昨日停泊した船」:この詩は官僚社会の浮き沈みの孤独な気分を表現している
呉謙(1195-1262)、号は易夫、号は陸寨、宣州寧国(現在の安徽省)の出身で、浙江省徳新市新市鎮...
宋徽宗の徽功皇后と王献公皇后の生涯についての簡単な紹介
献公王皇后(1084-1108)は、北宋の徽宗皇帝の最初の妻でした。彼女は開封の出身で、父は徳州知事...
第19章:鉄玄は孤立した都市を全力で守り、聖勇は郡を回復する
『続英雄譚』は、明代の無名の作者(紀真倫という説もある)によって書かれた長編小説で、明代の万暦年間に...
中国の十二支の犬が持つ象徴的な意味は何ですか?忠誠心は幸運や不運を予言し、悪や災害を防ぐ
今日は、Interesting History の編集者が中国の十二支の犬の象徴的な意味についてご紹...
唐和尚が仏典を手に入れるのに、当初は3年の予定だったのに、なぜ14年もかかったのでしょうか?理由は何でしょう
原作の第8章では、観音菩薩は如来から「仏典を求める人々を探して旅を遂行する」という任務を引き継ぎ、リ...
春秋時代や戦国時代の「春秋」という言葉はどこから来たのでしょうか?
魯国の歴史家は、当時各国で報告された主要な出来事を年、季節、月、日ごとに記録しました。一年は春、夏、...
楊吉の『揚子江千里』は彼の長年の郷愁を表現している。
楊季は、孟仔、号は梅安とも呼ばれ、明代初期の詩人で、「武中四英雄」の一人である。詩風は優雅で繊細、五...
袁真は唐代の有名な作家ですが、人々は彼にどのような称号を与えたのでしょうか?
袁震は唐代の大臣であり、有名な作家でもありました。彼と白居易は親しい友人であり、二人とも新楽局運動を...
『満江紅』の作者は岳飛ですか?論争の的となっている分野は何ですか?
「文江紅」に非常に興味がある方のために、「Interesting History」の編集者が詳しい記...
『紅楼夢』の夏金貴はなぜ敵意に満ちているのか?薛家に不満があったため
『紅楼夢』の夏金貴は薛潘と結婚した後、良い生活を送りたいのではなく、王になりたいと思っていた。では、...
那藍星徳の「環西沙:冷たい画幕に残る雪が光る」:人生の憂鬱を表現するテーマ
納藍興徳(1655年1月19日 - 1685年7月1日)は、葉河納藍氏族の一員で、号は容若、号は冷家...
商鞅の改革:奴隷社会から封建社会への変革を加速
戦国時代、各国は自らの政治権力を強化するため、優秀な人材を登用し、改革運動を展開した。李逵の魏国にお...
古代の王族はどのようにして王女の配偶者となる王子を選んだのでしょうか?
古代の王侯貴族は富と栄誉に恵まれた生活を楽しみ、世間から尊敬されていました。彼らの多くは、残りの人生...
清朝時代の宦官の最高官位は何でしたか?清朝はどのように統治されたのですか?
清朝の宦官の最高官位は何だったかご存知ですか? Interesting History の編集者が解...