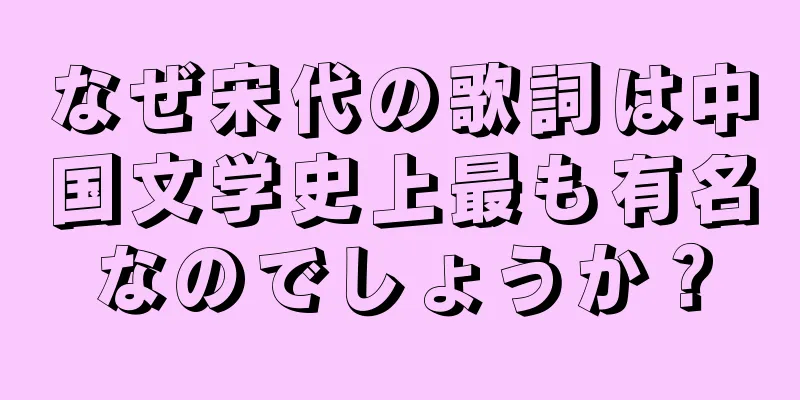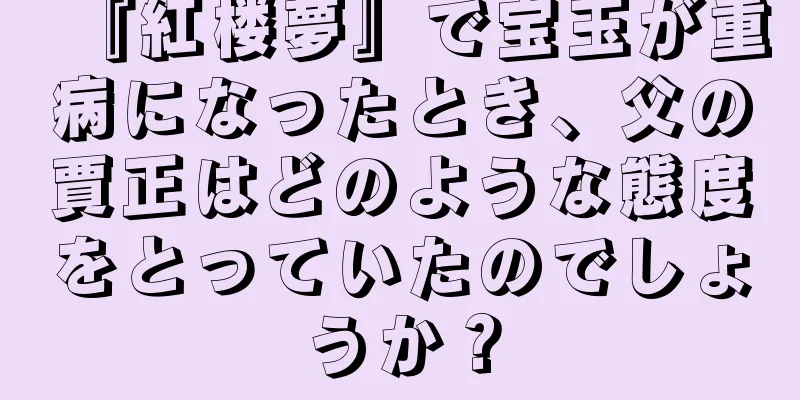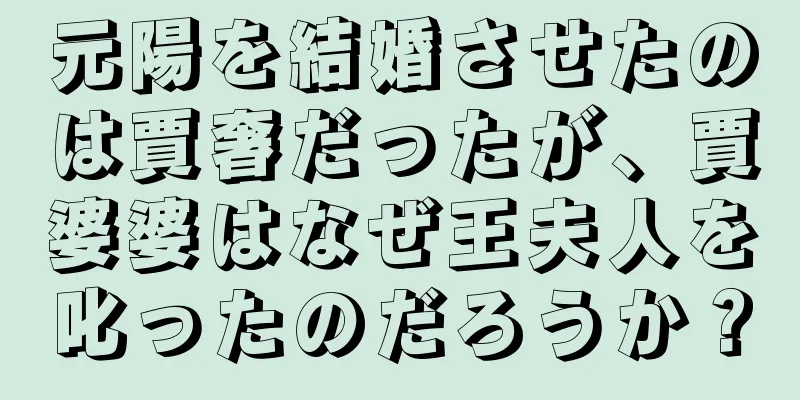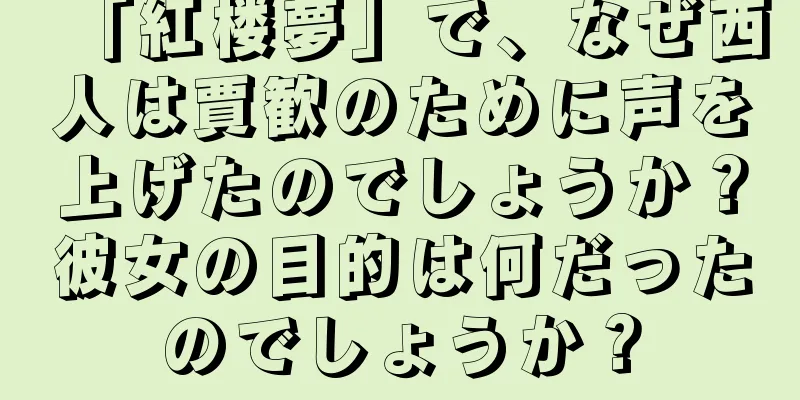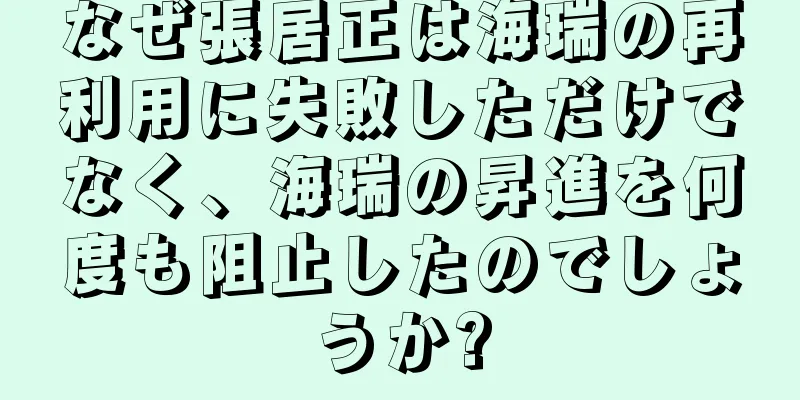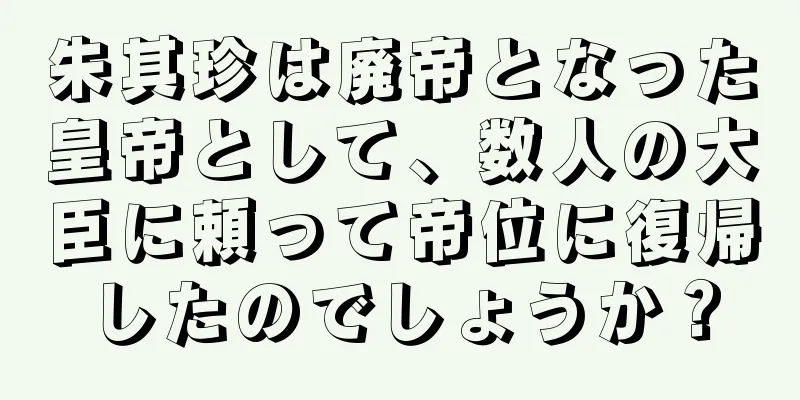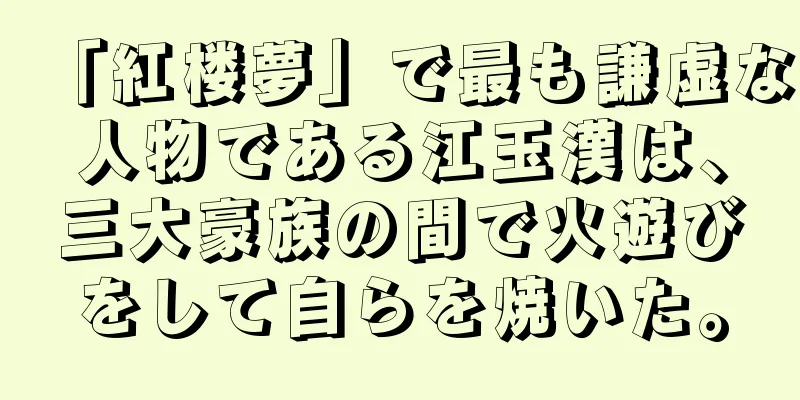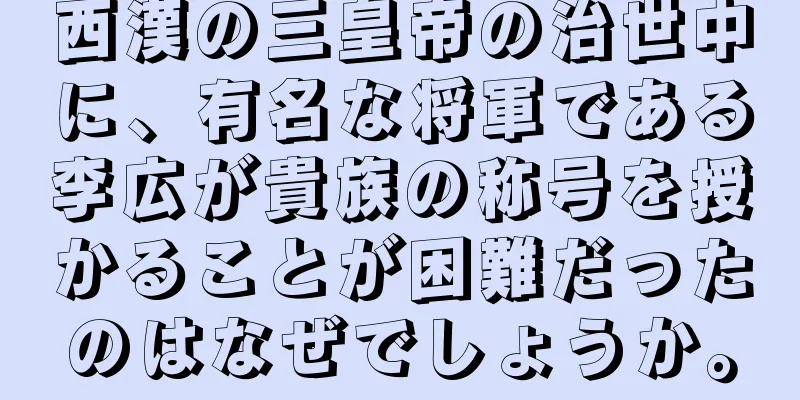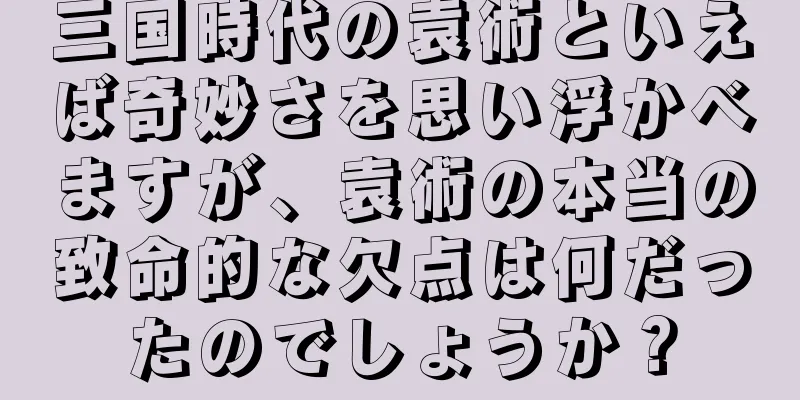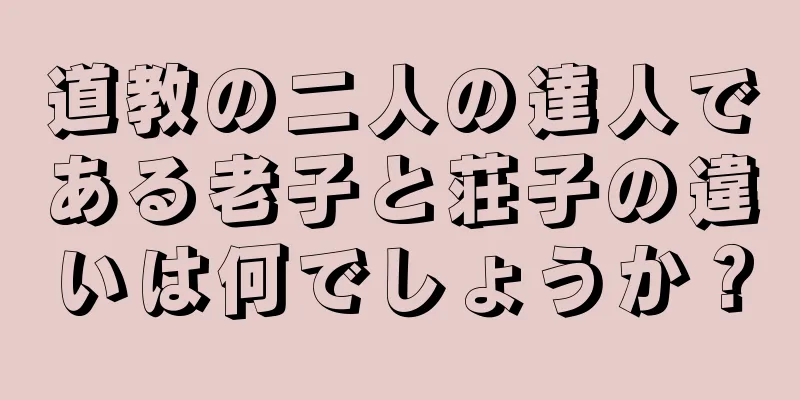唐代の解度使の公式の立場は何ですか?なぜジエドゥシはそんなに恐れられているのか?
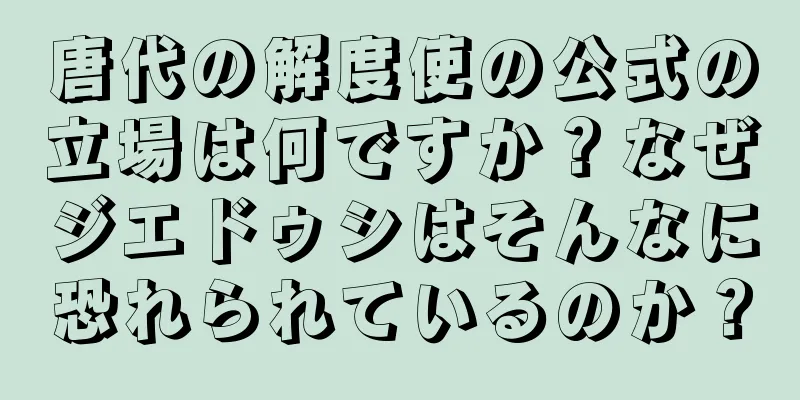
|
唐代の解度使とはどのような官職だったのでしょうか?なぜ解度使はそれほど恐れられたのでしょうか?興味のある読者は編集者をフォローしてご覧ください。 戒徳使は唐代中期から後期にかけて宮廷で恐れられた官職である。この役職に関する最も古い記録は貞観年間に現れ、唐の太宗皇帝李世民によって創設された可能性が高い。 『全唐詩』には「漢山碑」という記事があり、そこには「聖唐大使、右衛将軍慕容宝、斷都使副使、朝医任亜祥らが勅命に従い、大漢真主別嘉の正当な後継者を思野虎漢に任命した」という出来事が記録されている。 この鎮天為が王を任命した出来事は鎮観13年(639年)に起こったもので、その中で「桀都夫士」という官号が明確に言及されている。これを裏付ける記録が『旧唐書』『官記二』にある。「君子で軍を統括するものを元帥といい、文武官を統括するものを総帥といい、使節として派遣されるものを斡旋使といい、大使、副使、判事などがある。」これは、斡旋使大使と斡旋使副使が、貞観中期には同時に存在していたはずであることを示している。 李世民の写真 李世民の治世中の結度氏 李世民が解放軍を創設した当初の意図は、軍事の「統制と派遣」、つまり軍事戦争や防衛の必要が生じたときに設置することであった。結局、唐代は軍事に忙しく、征服すべき目標や守るべき国境の町が多すぎた。李世民は何でも自分でやりたかったが、忙しすぎてできなかった。将軍の権威を強化するために、「命令を受けたその日に旗と杖を与え、彼らを戟度使と呼び、絶対的な軍事力を行使できるようにした」。 このことからも、解度使はもともと参謀官ではなく、特使としての権限を持つ官吏であったことが分かります。両者の間には大きな違いがあります。 公務は法典や官報に制度や階級が定められた常勤官吏であったが、使節は制度に含まれず、官位や階級も与えられなかった。彼らは特定の事柄のために設置された臨時の役職であり、今日の査察班長や特別任務部隊長に似ている。査察が終了し事件が解決すると班長の肩書は外される。 そこで、李世民の時代に、解度使はあなたの仕事を容易にするために皇帝の使節の地位を与えられました。簡単に言えば、出張に行かされて一時的に事務員という肩書きを与えられるということです。結局のところ、李世民の指導力は非常に高く、部下に愚かなことをさせませんでした。街道師は彼の手の中で従順な子羊でしかありませんでした。 さらに、唐代初期の軍事制度は、解度使が状況を操作することを不可能にしており、これは極めて重要な制度的保証であった。 唐代初期の軍事制度は、軍事政策と軍事執行が独立しており、上州兵部が軍事政策の策定を担当し、中央衛府と東宮司が浙充庁を担当し、軍事作戦の執行を担当していた。このような軍事権力体制の下では、誰が解度使に任命されても、上層部から軍事指揮権以外の権力を得ることは困難であった。 では、結党使は軍を率いる際に、草の根から権力を築き上げる機会があったのだろうか。唐代初期の軍制では、下から徒党や派閥を形成して徐々に権力を蓄積していくという手法も実現可能ではなかった。 『長安の一番長い日』に登場する唐の兵士たちの静止画 「政府の兵士は、平時は田畑に駐屯し、当番の兵士は首都の警備のみを行う。四方に災難があれば将軍に退陣を命じ、災難が治まれば兵士を解散させ、将軍は朝廷に戻る。こうすれば民は失業せず、将軍は軍を統率する重責を負うことはない。こうすれば災難を未然に防ぎ、災難の芽を摘むことができる。」唐代初期、賦役制度は均田制によって保証されていた。賦役は一定の土地を割り当てられただけでなく、小作料や労役を支払う必要もなかった。賦役は朝廷の取り決めに満足しており、それに逆らう動機はなかった。 そのため、唐代初期には軍政と兵士は恒久的であり、将軍や軍知事は必要に応じて遠征し、必要に応じて帰国する流動的な存在であった。属国が発展する機会も土壌もなかった。 唐代における結都使の恒久的設置 街道使の恒久的な設置は、唐の睿宗の景雲年間(710-712)に始まった。景雲元年、薛仁貴の子薛娜が幽州の守備司令官と街道使の使節に任命された。景雲二年、鶴巴延嗣は涼州太守と河西太守に任命された。 薛納と鶴巴延寺の後、唐代には各地に街道市を設置するのが常例となった。唐の玄宗皇帝の開元年間には、碩放、河東、樊陽、平洛、河西、竜游、剣南、安渓、北亭、嶺南の十街道市制度が形成された。 解度使の恒久的な確立と同時に起こったのは、唐代の均田制と布氷制の相次ぐ衰退と崩壊であった。 均田制度は布袋制度の経済的基礎であったが、すぐに人口爆発と土地併合という深刻な問題に直面した。唐代の武徳年間(618-626年)の世帯数は200万余りに過ぎなかったが、天宝年間(742-756年)には900万世帯以上に急増した。唐代の荒地開拓により国土面積は増加したが、大規模な土地併合により平等に分配できる土地面積は大幅に減少した。 その結果、均田制の農民の多くが破産し逃亡したが、この事態は唐の高宗永徽年間(650-655)にすでに起こっていた。 「富める併合と貧しき失業」という状況に直面して、唐の皇帝高宗は合併を抑制するために土地取引を禁止する法令を何度も発布したが、高宗の再三の規制により土地取引はますます活発になった。武則天の勝利2年目(西暦699年)までに、均田制度は「国の半分以上の人々が逃げた」ほどに衰退した。 賦兵制において、均田農民は唯一の合法的な兵力供給源であったが、均田制の崩壊と農民の大量逃亡により、基盤を失った賦兵制は必然的に衰退し、崩壊した。 長安の一番長い日に登場する唐代の玄宗皇帝の静止画 唐代も家臣兵制度の維持に努めた。『新唐書・軍記』によると、唐の玄宗皇帝は咸天2年(713年)、家臣兵の脱走を減らすために家臣兵の勤務期間を40年から25年に短縮した。 5年後、彼は官軍の徴兵期間を3年から6年に延長した。一方では、官軍の人数を維持するために、老齢で体力の弱い兵士の兵役期間を延長した。他方では、若い兵士に成長のための時間を与え、将来の選抜対象者の数を増やすことを可能にした。 しかし、これらすべては、布氷制度の最終的な廃止を阻止することはできませんでした。開元11年(723年)、官軍が長安を守れなくなった状況に直面した唐の玄宗皇帝は、宰相の張碩の助言を受けて、長安の警備に当たるために力のある者を募集した。「官軍と庶民12万人を選び、これを永守と呼んだ」。身分のない庶民を募集したこの方法は、官軍制度を徴兵制度に置き換えるものであった。 徴兵制度の実施により、国境の将軍や軍知事はようやく自らの権力を培う機会を得た。唐代以前の魏、晋、南北朝時代においては、国政は貴族階級によって頻繁に操作されていた。唐代中期から後期、五代にかけては軍閥や地方の知事が権力の前面に立つことが多くなったが、その鍵となったのは唐の玄宗皇帝の治世における街道使の権力と地位の変化であった。 唐の玄宗皇帝の治世中の結度使 唐代初期の辺境将軍の任命は非常に独特であった。例えば、貞観7年に外将の斉壁和理が軍を率いて吐谷渾を征服したとき、李世民は李大良と薛万君を同行させた。吐谷渾を破った後、彼はすぐに長安に呼び戻され、北門の警護官を務めた。貞観14年、異国の将軍アシナ・シェールが軍を率いて高昌を攻撃したとき、李世民は侯俊基をその指揮官として派遣した。勝利後、彼は侯俊基を長安に呼び戻して都に仕えさせた。 しかし、将軍が軍の駐屯地を指揮したり国境の駐屯地を守ったりしないという慣習は、李世民の時代以降徐々に廃止されていった。開元年間に十人街道使の制度が確立すると、将軍が街道使を兼務することが当たり前となり、辺境の将軍に軍事作戦の権限を委ねることが慣例となった。 この時点で、解厘使は軍閥になるための二つの条件をすでに満たしていた。第一に、徴兵制度の実施により、兵士を徴兵する権利を獲得したこと。第二に、辺境の拠点で独占的な権力を握ることができたこと。解厘使は軍事、政治、財政の権力を一人の人物にまとめた。しかし、唐の玄宗皇帝には、解度使の勢力拡大を抑制する機会がまだ2度あったが、残念ながらそのどちらもつかむことができなかった。 最初の機会は、解压使の任期を厳しく管理し、解压使の事務所所在地のローテーションを促進することです。この慣習は、解度使の地方権力育成の努力を効果的に抑制することができ、高宗皇帝と武帝の治世中に厳格に施行されたが、唐の玄宗皇帝の治世中に廃止された。 開元から天宝の時代(713-756)には、10人の軍知事のうち23人が5年以上在任し、そのうち2人は10年以上在任したが、その両方を安禄山が一人で務めた。天宝元年(742年)、平廬街道使に任じられ、2年後には幽州街道使(樊陽街道使ともいう)も兼任した。安史の乱が起こるまでの10年間、一度も解任や転任されることはなかった。 これを踏まえると、安史の乱の発生は偶発的なものであったと考える人もいる。安史の乱の在任期間の長さは例外的であると考えられるからである。実際、安禄山がいなかったら、唐代の偉大な聖人は、平和と満足の中でさらに長い年月を生きられたであろう。しかし、すでに結都使が自らの部隊を持ち自立できる状況が形成されており、強者が弱者を掌握し、強幹弱枝という唐代初期の軍勢状況は逆転しており、これは唐の玄宗皇帝が逃した二度目の好機であった。 唐代初期、全国に657の軍司令部があり、そのうち288が関中地区に位置していた。全国60万人の兵士のうち、26万人が首都地区にいた。これは重兵を以て軽兵を制する方式であり、「世界中の兵士が関中の兵士に勝つことはできない」という意味である。この慣習は宋代、明代にも引き継がれました。例えば、宋代初期には20万人を超える近衛兵の半数が首都に駐留し、明代初期には国軍総兵力の約3分の1が首都に駐留していました。 しかし、徴兵権が解度使に移譲されたことで、唐代初期の強者が弱者を支配するという勢力均衡は100年後には完全に崩れ、首都の軍事力が地方より劣る状況となった。天宝時代、十軍知事の総兵力は約49万人であったが、長安の南衙門十二衛に属する騎兵の数は10万人未満であった。 中央帝国軍として従軍したこれらの騎兵は、才能と勇敢さに恵まれた者ではなかった。「志願者は皆、市場の荷運び人、悪党の息子で、軍事訓練を受けたことはなかった」。そのため、国境の兵士と比べると、数で優れているわけではなく、質も心配だった。当時、安禄山は平魯、樊陽、河東の太守を務め、合計18万人以上の精鋭部隊を指揮していた。 国境の町から集まった18万人の精鋭兵士と、役立たずの10万人の近衛兵。唐の玄宗皇帝は、かつては従順だった子羊たちを自ら獰猛な虎に育て上げた。結城氏の圧倒的な権力の優位性が、安史の乱の重要な原因となった。 安史の乱が勃発した後、皇太子李衡は北の霊武に行き、唐の粛宗皇帝として即位した。李密に軍事計画を依頼した。当時、李密は敵の根拠地を排除することに重点を置いており、まず反乱軍の主力を排除し、河北の属国を平定し、次に二つの首都を回復するという戦略を立てました。 『長安の一番長い日』の王子と李毓の静止画 しかし、唐粛宗は権力争いの必要から、治世の初めに自らの地位を固めるために両都の奪還に熱心だったため、状況が有利なうちに動乱の根本原因を根絶する機会を逃し、その結果、河北の3つの鎮は長期にわたる分離統治を維持することになり、これは中唐末期のなかなか取り除けない封建制度の災いとなった。 |
<<: 首相制度はいつ始まったのですか?漢の武帝から宰相の権力が抑圧されたのはなぜですか?
>>: 明代の総督制度はどのようにして生まれたのでしょうか?総督制度を創設した目的は何ですか?
推薦する
ハイ・ルイが再利用されなかった理由は何だったのでしょうか?誰が邪魔しているのですか?
張居正と海睿はともに明代中期の宮廷官僚であった。年齢で言えば、海瑞は張居正より10歳年上だった。官吏...
『後漢演義』第96章の主な内容は何ですか?
遺言によれば、司馬炳泉は印章とリボンを将軍の池氏に引き渡した。しかし、衛公は放縦で贅沢にふけり、病気...
諸葛亮は馬に乗ることができたのに、なぜいつも車椅子で戦争に行ったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
清朝の軍馬はどこから来たのでしょうか?清朝の馬飼育システムを分析!
清朝の軍馬はどこから来たのか?清朝の馬飼育システムを分析!興味深い歴史の編集者が詳細な関連コンテンツ...
「野蛮人の家を訪ねての感想」の著者は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
陸游の『野人の家を通る時の考え』の注釈付き翻訳と解説【オリジナル詩】「野人の家を通り過ぎて思うこと」...
側室である賈元春は、食べ物や衣服などの費用の心配がなかったのに、なぜ楽しむことよりも苦しむことが多かったのでしょうか。
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
『紅楼夢』で宝玉の誕生日の晩餐会で丹春が引いた花くじとは何ですか?
丹春は金陵十二美人の一人です。彼女は賈正とその侍女である趙叔母の娘です。Interesting Hi...
『紅楼夢』で賈夫人の周りにいる10人の侍女は誰ですか?
賈祖母は、石老夫人としても知られ、賈家で最も権力のある人物です。今日は、Interesting Hi...
「一流の学者」という用語の公式な定義を持ち始めたのはどの王朝ですか?
『四庫全書』に収録されている正史を調べてみると、「一流の学者」という用語の最も古い定義も『晋史』にあ...
古代における陸軍次官の地位は何でしたか?パワーはすごいですか?
古代の陸軍省次官とはどのような官職だったのか、どれほど権力があったのかを知りたいですか? 実は、古代...
周王朝にはどのような官職がありましたか?周王朝の政治制度
周王朝にはどのような官職がありましたか? 周王朝の政治制度。ご興味がございましたら、ぜひ見に来てくだ...
『紅楼夢』で、宝玉が殴られた後、希仁は王夫人の前で何と言いましたか?
希仁は『紅楼夢』の登場人物。金陵十二美女の2番目であり、宝玉の部屋の4人の侍女のリーダーである。今日...
隋唐志伝 第64章 秦王宮の門掛け帯、宇文公主の龍のケースの詩の解釈
『隋唐志演義』は清代の長編歴史ロマンス小説で、清代初期の作家朱仁火によって執筆されました。英雄伝説と...
歴史上の肖恆のイメージはどのようなものだったのでしょうか?蕭楚はどのようにして遼の女王になったのでしょうか?
蕭皇太后は、本名を蕭初、愛称を燕燕といい、遼の景宗皇帝野呂仙の皇后であった。 『楊家の将軍』などのド...
翁元龍の「桃花春に酔う-柳」:作者は柳を擬人化し、別れの気持ちを表現している。
翁元龍は、雅号を世科、通称を楚景といい、居章(思明とも呼ばれる)の出身である。生没年は不明だが、宋の...